ブラームス 交響曲第1番(その2)
2014 MAR 17 13:13:29 pm by 東 賢太郎

1985年にアテネへ行って初めてパルテノン神殿に立った。その時に、強い陽射しのなかどういうわけか、これがブラームスの1番だなと思った記憶がある。
「1番は強靭な鉄骨、鋼(はがね)によって組み立てられた音楽である。第1楽章主部アレグロはその鋼鉄の建造物が金属摩擦で高音に加熱される様相を呈した音楽であり、柔らかい音質は一切排除されねばならない。」と当時の日記に書いてあった。
「高温に加熱される様相」。僕が整った演奏ではなく乱れていてもライブを選好するのはそれを求めるからだ。1番を21年かけて仕上げたブラームスの前に立ちはだかったのはベートーベンである。第1楽章には「運命主題」のリズムが鳴り、終楽章は第九を想起させる主題が弦で奏されるが、そういう表面の造りよりも「鋼鉄」のパーツでできているというベートーベンの奇数番の特性を継いだところがより本質的な1番の個性だと僕は思う。
先人の偉業の継承を成し遂げたと判断したのだろう、2番以降に鋼鉄の音楽はもう書かれなかった。1番で名演を残した指揮者が2-4番でもいいとは限らないのはそういうことではないだろうか。フルトヴェングラーは1、4番で神品を残したが2、3番ではいただけない。ミュンシュの2番は熱さで勝負の音楽になってしまう。ベートーベンの偶数奇数のようなものだろうか。
現在はどれが好きかというと、1番はあまり聴かない方になっている。4曲どれも気軽に聴ける曲ではないが、1番は特にブラームスの気合いがみなぎっているので重い。しかし、1番を知らない人に恐れてもらっては困る。それだけ重いということはそれだけパワーが強力ということだ。ツボにはまった時の感動の大きさということで数々の名曲を思い起こしてみても、1番はクラシック音楽の中でも筆頭格に属するものであることは間違いない。こういう曲に足がふらつくほど打ちのめされる体験をしてこそ、クラシックの本当の魅力、すばらしさというものが実感できるのである。
1番が鋼鉄できた音楽であると書いたが、それは交響曲への挑戦状を仕立てようという肩ひじの張った一種の気合いから来ているように思う。モーツァルトが「ハイドンセット」作曲に見せたそれと似るものだ。しかし、ブラームスの音楽は本質的に非常にロマンティックである。古典の装いでそれを隠蔽するのがブラームスのシャイな男ぶりであり、クラリネット五重奏曲の第2楽章など、これはもうロマンを通り越してエロティックな世界に踏み込んでいる。1番がハガネの形式論理に偏ったのとちょうど同じように、正反対のロマンの方角に向けて彼にしては赤裸々なほどに越境しているときこえる。
そういう音楽はブルックナーには一曲たりともない。「赤いはりねずみ」の逸話は必然のことなのだ。ブルックナーは彼特有の旋律、リズム、和声を駆使して総体的に醸し出す、 ヴァルター・ベンヤミンのいうところの「アウラ」を生んだ作曲家だ。美しい旋律を書いて聴衆を酔わせたり、ワーグナー流の和声でエロティックな陶酔に迷い込ませようという意図はない。旋律は一要素にすぎず、彼の交響曲でそれを一緒に口ずさんだところで音楽の聖域に入っていける気はしないという性質のものだ。どこか凡俗の侵入を拒むものがある。だから聴き手の精神から超然としたところのない、人口に膾炙しようというベクトルの働いたブルックナー演奏というものはまったくのまがい物なのだ。
一方、ブラームスの場合はそうではない。「歌える」のだ。それは旋律がそういざなう場合もあれば、和声の流れにのる場合もあるから一概に「歌」とはいえないものだろう。彼の和声は単純ではないが、どんなに知らないところへ連れて行かれてもいつもその先には安心して家に帰れる道が見えてくる。そっちへ向かうのがまるで母に教えられた道であるかのようにいとも自然なのだが、それでいて周囲を見渡すとやはりそこは初めての土地なのだ。僕のように何百回もその道を行った者であっても、そこに立つとまたそう感じる。だからブラームスのファンは多いのであり、僕は397枚も彼のシンフォニーを集めてしまうのだ。
そういう味わいは、おそらくブラームスの音楽だけがもたらすものだ。「歌える」というのは、心地よく母のいうままに従うということであって、オペラをききながらアリアを鼻歌でなぞるのとは全然ちがう。それがどのパートかというとフルートであったりコントラバスだったりホルンだったりするわけだが、僕の場合は鼻歌か口笛でそのパートを通じて全体に「唱和」することになっている。それで音楽に迎え入れられ合体するという経験ができ、アンサンブルの一員であるかのように無上の喜びを得られるという感じなのだ。
1番でお示ししよう。山あり谷あり。ベートーベンの交響曲という霊峰に挑む気概に満ちたこの曲はいばらの道をつき進み、いよいよハイライトである第4楽章のアルペンホルンに到達する。ここが全曲の頂点であり、そして山の頂からブラームスはクララへ「何千回も挨拶」を送るのである。先人は超える対象、クララは向かう対象であり1番はこの部分を分水嶺としている。キスでなく挨拶であるところがいかにも奥手の彼ではないか。それが清澄なフルートにうつり、やがて充足感に満ち満ちたハ長調の弦楽合奏の主題がやってくる。第九に似るといわれるものだ。この主題をぜひ「歌って」みてほしい。
おそらく10人中9人のかたはヴァイオリンのメロディーを歌うのではないか。僕もそうだった。ところがこの地点を何百回も歩いていると、ある時から僕はヴィオラを歌うようになっている。第九のこれに似た喜びの歌の弦楽合奏でも僕はチェロを歌っているが、この部分の両者の近似は単にメロディーが似ているというよりも、対旋律まで歌えてしまう「書法」の近似であると思う。こういう音楽を書くことができたからブラームスはベートーベンに対峙できる交響曲作曲家と認められたのであり、何百回聴いても飽きのこない秘密はこういういう細部にひっそりと隠れているのである。
ブラームスに興味ある方、これから極めてみたいと思われる方は、とにかく何度も聴いて全曲を一緒に歌えるまでなってしまうことを心から推奨したい。ブラームスの曲は実はそれが難しくない。母に導かれる道だ。おそらく誰にとってもそうであり、だから誰でもできるはずなのだ。そしてそれができるようになった時の喜びは、これはもう半端なものではない。1番のみならず4曲とも人を感動させるパワーは折り紙つきの強力な音楽なのである。「感動して打ちのめされる」という経験をあなたは必ず味わうことができるだろうし、クラシック音楽というものの底知れない魅力をきっと知ることになる。僕がそうだったように。
以下、僕のリストで二つ星のCDの補遺である。
スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー / ハレ管弦楽団
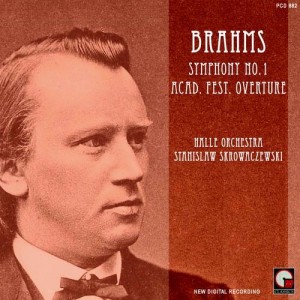 弦のバランスが素晴らしい。鋼鉄と呼ぶには誠にしなやかで、決め所は充分な硬度がある。銀色に光る軟鉄のようだ。フレージング(語り口)が自然でなめらかであり、ppのニュアンスにも富む。第2楽章はオーボエ、ホルンの呼吸が聴かせる。音楽が生きている。ぶっきらぼうな朝比奈とは別な音楽だ。第3楽章の鳴りきった管の音程の見事さ。作曲家の耳だろう。ppには思わず息をひそめる吸引力を感じる。終楽章はやや弦の薄さを感じるのが残念で、これがコンセルトヘボウのようなオケだったらとない物ねだりしたくなる。ホルンの強調など、後年の演奏でより顕著になる理屈っぽさのの萌芽がみられ、それが好悪を分けるだろうが僕はそれでも高く評価している。
弦のバランスが素晴らしい。鋼鉄と呼ぶには誠にしなやかで、決め所は充分な硬度がある。銀色に光る軟鉄のようだ。フレージング(語り口)が自然でなめらかであり、ppのニュアンスにも富む。第2楽章はオーボエ、ホルンの呼吸が聴かせる。音楽が生きている。ぶっきらぼうな朝比奈とは別な音楽だ。第3楽章の鳴りきった管の音程の見事さ。作曲家の耳だろう。ppには思わず息をひそめる吸引力を感じる。終楽章はやや弦の薄さを感じるのが残念で、これがコンセルトヘボウのようなオケだったらとない物ねだりしたくなる。ホルンの強調など、後年の演奏でより顕著になる理屈っぽさのの萌芽がみられ、それが好悪を分けるだろうが僕はそれでも高く評価している。
マルクス・ボッシュ / アーヘン交響楽団
 徹底的に楷書風のライブ演奏である。ロマン的なブラームスを求める聴き手にフレンドリーな指揮ではない。ベートーベンでいえば1,2,8番あたりを古楽器演奏を取り入れた現代オケがやる感じといえば近いだろうか。しかし珍しいだけではない。才気煥発な指揮にオケが敏捷に反応しており、技術的にもきわめて安定している。第1楽章の小気味良い運動性は聴きもので、ブラームスの組み立てた鋼の構造を設計図ごと見せられるよう。フルトヴェングラーの呪縛から最も解き放たれた解釈であり、とにかく胃にもたれない。スコアを忠実に鳴らせばこんなに感動させてくれるという見本のような演奏であり、これはこれで建築構造の理にかなった見事さを実感する。だからパルテノン神殿なのだ。i-tuneで買える。
徹底的に楷書風のライブ演奏である。ロマン的なブラームスを求める聴き手にフレンドリーな指揮ではない。ベートーベンでいえば1,2,8番あたりを古楽器演奏を取り入れた現代オケがやる感じといえば近いだろうか。しかし珍しいだけではない。才気煥発な指揮にオケが敏捷に反応しており、技術的にもきわめて安定している。第1楽章の小気味良い運動性は聴きもので、ブラームスの組み立てた鋼の構造を設計図ごと見せられるよう。フルトヴェングラーの呪縛から最も解き放たれた解釈であり、とにかく胃にもたれない。スコアを忠実に鳴らせばこんなに感動させてくれるという見本のような演奏であり、これはこれで建築構造の理にかなった見事さを実感する。だからパルテノン神殿なのだ。i-tuneで買える。
(補遺2月15日)
アルトゥーロ・トスカニーニ / フィルハーモニア管弦樂団
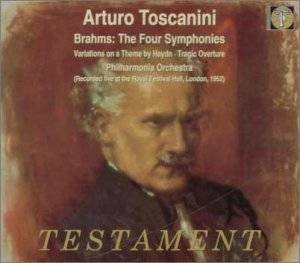 52年9月の伝説的ブラームスチクルスのライブ。冒頭の怒涛のような勢いは圧倒されるばかり。現代も激しい指揮をする人はいるが、こういう苛烈な、激しい緊張を伴った音は出ないだろう。まさに灼熱の鋼の1番だ。音楽演奏とは奏者の人間性の開陳であり、指揮者は音を引き出しているのでありそれを意識しているわけではないだろうが、恐らく、不思議とそういうことになってしまうという性質の行為と思う。すなわち彼はきっとこういう人なのであり、大指揮者トスカニーニを知る意味で代表盤のひとつといっていい。
52年9月の伝説的ブラームスチクルスのライブ。冒頭の怒涛のような勢いは圧倒されるばかり。現代も激しい指揮をする人はいるが、こういう苛烈な、激しい緊張を伴った音は出ないだろう。まさに灼熱の鋼の1番だ。音楽演奏とは奏者の人間性の開陳であり、指揮者は音を引き出しているのでありそれを意識しているわけではないだろうが、恐らく、不思議とそういうことになってしまうという性質の行為と思う。すなわち彼はきっとこういう人なのであり、大指揮者トスカニーニを知る意味で代表盤のひとつといっていい。
(未完)
(こちらへどうぞ)
ブラームス ピアノ協奏曲第1番ニ短調作品15(原題・ブラームスはマザコンか)
Categories:______ブラームス, クラシック音楽






