第一次大戦を考える(その6)-オスマン帝国と第一次大戦
2015 FEB 18 16:16:09 pm by 中村 順一

- ムスタファ・ケマル・アタテュルク
- エンヴェル・パシャ
- サイクス・ピコ協定
① オスマン帝国参戦への経緯
多民族、多宗教の人々を抱え、比較的緩やかな統治体制を敷いてきたオスマン帝国は建国から600年を越えて存続を続けた長寿国家であり、16世紀にはその勢力は世界最強と言っても過言ではなかった。しかし、20世紀を迎え、西欧社会から「ヨーロッパの瀕死の病人」などと揶揄される内憂外患の程度は、極限状態を迎えていた。外患とは英国、フランス、ロシア、ドイツ、イタリアなど、ヨーロッパ列強の軍事、経済あらゆる面における台頭と、オスマン帝国自体の半植民地化への過程である。そして、16世紀、17世紀に2回に亘ってウィーンを包囲し、ヨーロッパ社会の脅威として君臨し続けた強大イスラム帝国は、第1次大戦に参戦し、滅亡への決定的な一歩を踏み出すという皮肉な末路を辿ることになる。
1914年当時にオスマン帝国政権を実質的に掌握していたのは、「統一と進歩委員会(統一派)」の、陸軍大臣エンヴェル・パシャ、宰相メフメット・タラート、海軍大臣アフメト・ジェマルの3人であった。3人は1910年から継続して勃発したトリポリ、2回に亘るバルカン戦争の結果、オスマン帝国の外交的孤立が深刻であることを、重く受け止めざるを得なかった。3人は焦りを伴う愛国心から、真の友人を確保すべく、外交でも積極的に動くべき、という結論に至る。”真に信頼できる同盟国”を確保すべく、欧州列強との交渉が積極的に開始されたのである
外交上、オスマン帝国は19世紀以降、英仏、特に英国と緊密な関係を保ってきた。両国の支援を受け(受けることを望み)、ボスポラス海峡に南下するロシア帝国に対抗せんとする図式こそが、クリミア戦争以来の伝統的な共通認識だったのである。しかし、英仏への同盟の打診は順調には進まなかった。チャーチルには1911年に同盟を拒否されていた。海軍大臣ジェマルは1914年7月にフランス海軍訓練視察に招待され、パリに渡航したが、フランス側からは事実上の同盟拒否を受けてしまった。ここで動いたのがドイツだった。陸相エンヴェルは親独派であり、7月22日に自らドイツ大使ワンゲルハイムに同盟の予備交渉を打診したが、拒否にあった。ドイツ陸軍参謀総長モルトケはオスマン帝国軍が全く大戦争に耐えうる状況にないことを正確に理解していたのである。ところが、ヴィルヘルム2世が7月24日になり、オスマン帝国との同盟締結に支持を打ち出した。おそらくは7月後半になると世界大戦の危機が突如として高まっており、ドイツも動き出したのであろう。皇帝の発言を受けて軍も政府も方針を転換し、予備交渉が開始された。オスマン帝国は既に述べたように、外交上の孤立だけは避けたい、とする希望が強かったため、8月1日から締結交渉が行われ、2日の早朝にはイスタンブールの宰相タラートの自宅にてトルコ・ドイツ軍事同盟が締結された。
ドイツは8月1日に対露宣戦布告に踏み切っており、この同盟は、オスマン帝国がロシア、引いては英仏と戦争を開始する危険が高まったことを意味した。その後統一派、特にタラートとジェマルは参戦回避に尽力したが、9月以降、ベルリンからの参戦圧力は激烈の度を増し、ロシアとは9月末から国境で小競り合いが始まり、オスマン艦隊はロシア領を砲撃すらしてしまった。また破産状態のオスマン軍はドイツの援助なしには、武装動員すら不可能な状態になり、最高幹部の間では参戦やむなしの意識が高まっていった。
結局、11月2日にロシア、5日に英仏が宣戦布告、11日にはオスマン帝国も連合国に対して宣戦布告した(メフメット5世がジハードを布告)。
オスマン帝国のドイツ接近は各国の態度の変遷の中で、偶然の末辿り着いた結果に思える。国の存続すら危ういという認識になってきたトルコ政府首脳にとって、各国が冷淡な姿勢を見せる一方で、以外にも一転して好意的姿勢を見せたドイツに縋り付くのは、やむを得ない、当然の行為とも言えたのである。
②オスマン軍と第1次大戦
親独派のエンヴェルは、一貫してドイツとの同盟をし推進していた。結果的にはトルコ政府の中では彼が参戦を主導した。エンヴェルは、従来からの敵国ロシア帝国を解体してカフカス地方を奪還し、オスマン帝国の自然国境を回復するとして参戦を正当化した。その意図に中にはロシアの支配を受けている中央アジアのトルコ系民族を解放し、中央アジアからバルカンに至るテュルク系諸民族を、オスマン帝国の旗のもとに大統一するというパン=トルコ主義があった。エンヴェルは巧妙にもパン=トルコ主義を突出させることなくパン=イスラム主義に結び付け、大戦にあたってジハードを宣言し、ロシア領内だけでなく、アフガニスタンやインドなどのイスラム教徒には反英闘争を呼びかけた。
オスマン帝国の参戦後、ドイツ軍艦はダーダネルス、ボスポラス海峡を通過して黒海のロシア基地を攻撃した。英国は、ドイツの黒海進出は中東進出に繋がると考え、これを阻止するために、1915年4月、海峡地帯のガリポリに出兵した。この英仏、豪州、ニュージーランド混成軍のガリポリ半島上陸を阻止したのが、ムスタファ・ケマルである。
エンヴェルの掲げたパン=トルコ主義とパン=イスラム主義は矛盾をはらんでいた。パン=イスラム主義なら、全イスラムは団結すべきであるが、パン=トルコ主義ならオスマン帝国領内のアラブ人、アルメニア人、ギリシャ人、クルド人、ユダヤ教徒などの自治独立の要求は当然抑えなければならなくなる。事実、東部戦線での対ロシア戦争の中で、アルメニア人の強制移住と大虐殺が行われた。この「アルメリア人虐殺」は今でも大問題となっており、解決されていない(トルコ政府は公式に認めていない)。英国はオスマン帝国の背後を攪乱するために、この民族対立を利用し、アラビアの反オスマン勢力である、ハーシム家のフセインと結び、その反乱を支援した。この時アラブ軍を指導したのが、「アラビアのロレンス」である。
オスマン帝国はガリポリの勝利以外は各地で敗北を重ね、1918年9月にはブルガリアが降伏したため首都イスタンブールに連合軍が迫った。10月、スルタンのメフメット6世は連合軍と秘密裏に交渉して、自らの戦後の地位の保証を条件に連合軍に降伏。セーヴル条約を締結した。裏切られたエンヴェルは国外に脱出した。中東で戦っていたムスタファ・ケマルはいったんイスタンブールに戻った後、連合国への投降を拒否して反乱軍を組織した。
③スルタン・カリフ制の廃止
オスマン帝国の君主は、14世紀末のバヤジット1世(雷帝、稲妻)の時からイスラム世界の世俗権力(政治的・軍事的権力)であるスルタンを称していた。スルタンはカリフ(預言者の代理人、イスラム国家の指導者、最高権威者の称号)から与えられるとされるのが、イスラム世界、スンニ派の建前である。
カリフの地位はアッバース朝で世襲されていたが、アッバース朝滅亡の後、エジプトのマムルーク朝のもとで保護され、マムルーク朝がカリフ継承権を持ち続けていた。1517年にオスマン帝国のセリム1世がカイロを占領し、マムルーク朝を滅ぼした時に、カリフ継承権を譲り受け、以降、オスマン帝国のスルタンはカリフを称するようになった(スルタン=カリフ制)。
第1次大戦でスルタンの権威が地に落ちると、苦難にあるオスマン帝国のカリフを擁護すべきという運動が特にインドのムスリムの間で起こった(ヒラーファット運動)。インドの反英民族闘争を指導していたガンディーは、彼自身はヒンズー教徒であったが、このカリフ擁護運動と連帯することを主張した。
オスマン帝国は正に存亡の危機だったが、トルコ国内では、自ら議会を解散させたメフメット6世に代わって、国家を代表する資格を持つ、アンカラ政府が結成され、ムスタファ・ケマルが首班となった。この時、西方からアナトリア西部の奪還を狙うギリシャ軍がアンカラに迫っていたが、ムスタファ・ケマルは自ら軍を率いてギリシャ軍をサカリヤ川の戦いで撃退した。その後、トルコ軍は反転攻勢に転じ、1922年9月には、地中海沿岸の大都市イズミールを奪還した(イズミールは今でもトルコ第3の大都市)。この時のムスタファ・ケマルの「全軍に告ぐ、諸君の最初の目標は地中海だ、前進せよ」という言葉はトルコ国民に深い感動を与えたことで有名である。
反転攻勢の成功により、連合国もアンカラ政府の実力を認めたため、ムスタファ・ケマルはセーヴル条約よりも有利な条件のローザンヌ講和条約を連合国との間で締結することに成功した(1923年7月)。
既に1922年にはアンカラ政府はオスマン帝国のスルタンとカリフを分離させて、スルタン=カリフ制を廃止していた。これで、オスマン帝国は正式に終わりを告げており、最後のスルタン、メフメット6世はマルタに亡命していた。
④カリフ制の廃止は残念
スルタン制は廃止されたが、この1922年の時点ではオスマン家は政治的権力は無くしたが、宗教的権威は維持し、カリフとして残っていた。この権威はパン=トルコではなく、パン=イスラムの動きであった。1922年11月にオスマン家のアブデュルメジト2世が皇帝に選出された。この時点で世俗的支配者としてのスルタンは廃止されていたので、アブデュルメジトが継承したのは、カリフの地位のみであった。当時、トルコ国内にも国外にも、7世紀からの伝統のあるカリフの地位を重視し、オスマン家の血統のある人物を象徴的な皇帝として残そうという考え方は存在した。筆者の考えでは敗戦後の日本の象徴としての天皇のように、どうして象徴皇帝=カリフを残せなかったのか、残念である。カリフには長い歴史があり、存続していれば、少なくともスンニ派の世界では権威を絶対だし、忌まわしき「イスラム国」の出現も無かったろう。
しかし、ムスタファ・ケマルは近代化を進めるトルコ共和国で極めて厳密な政教分離を採用したため、1924年にいとも簡単に、カリフ制を廃止した。こうして、イスラム世界で承認された最後のカリフであるアブデュルメジト2世は、オスマン家の一族と共にトルコ国外に追放された。彼は1944年に死んだが、遺体はサウジアラビアのメディナに埋葬されている。ムスタファ・ケマルはイスラム教の持つ後進性を忌み嫌ったといわれているが、あまりにももったいなくなかったか?もしトルコにカリフ制が残っていれば(十分に可能だった)、現代のトルコの国際的地位も全く違うものになっていたろう。
ムスタファ・ケマルは20世紀でもおそらく5本の指に入る英雄だが、彼の出生には謎が多い。ユダヤ教デンメ派(シャブタイ・ツヴィを救世主として信奉し、イスラム教徒のふりをしながらユダヤ教の戒律を守り続けた隠れユダヤ人)の子孫という説がある。トルコでは”絶対に禁句”だが、彼の行動を見ていくと、ありうる話かも知れないと思えてくる。
⑤サイクス・ピコ協定
サイクス・ピコ協定は第1次大戦中の1916年5月に、英国、フランス、ロシアの間で結ばれたオスマン帝国領の分割を約した秘密協定である。既に述べたように、ローザンヌ講和会議で新生トルコ共和国はほぼ現在のトルコの領土を確保できたが、中東地域の分割は、ロシアが離脱した後、英仏の取り分に関して、ほぼこの協定の取り決めが生かされた。(モスル地区は英国領へ)
内容としては以下のとおりである。
・シリア、アナトリア南部、イラクのモスル地区をフランスの勢力範囲とする。・シリア南部と南メソポタミア(現在のイラクの大半)を英国の勢力範囲とする。・黒海東南沿岸、ボスポラス海峡、ダーダネルス海峡地域をロシアの勢力範囲とする。
この協定は周知のように、英国が中東のアラブ国家独立を約束したフサイン・マクマホン協定(1915年)や、英国がパレスチナに於けるユダヤ人居住地を明記したバルフォア宣言(1917年11月)と相矛盾しており、英国の三枚舌外交として批判されている。また、1917年にロシア革命が起こると、同年11月に革命政府によって旧ロシア帝国のサイクス・ピコ協定の秘密外交が明らかにされ、アラブの大反発を強めることとなった。
サイクス・ピコ協定の分割交渉による線引きは後のこの地域の国境線にも影響している。長いこの地域の歴史や民族、部族分布を、言わば無視して人工的に引かれた不自然な国境線が、この地域にもたらした悪影響は大きい。「イスラム国」もサイクス・ピコ協定に怒りを抱いており、彼らが武装闘争を続ける動機の一つになっている。
少し長くなったが、以上で「オスマン帝国と第1次大戦」の投稿、および6回に亘った「第1次大戦を考える」のシリーズを終わりとしたい。筆者としては、興味の尽きない歴史として、今後も様々なトピックを選びつつ、投稿を続けていく所存である。
皆様よろしくお願いします。
Yahoo、Googleからお入りの皆様。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
Categories:未分類





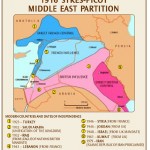
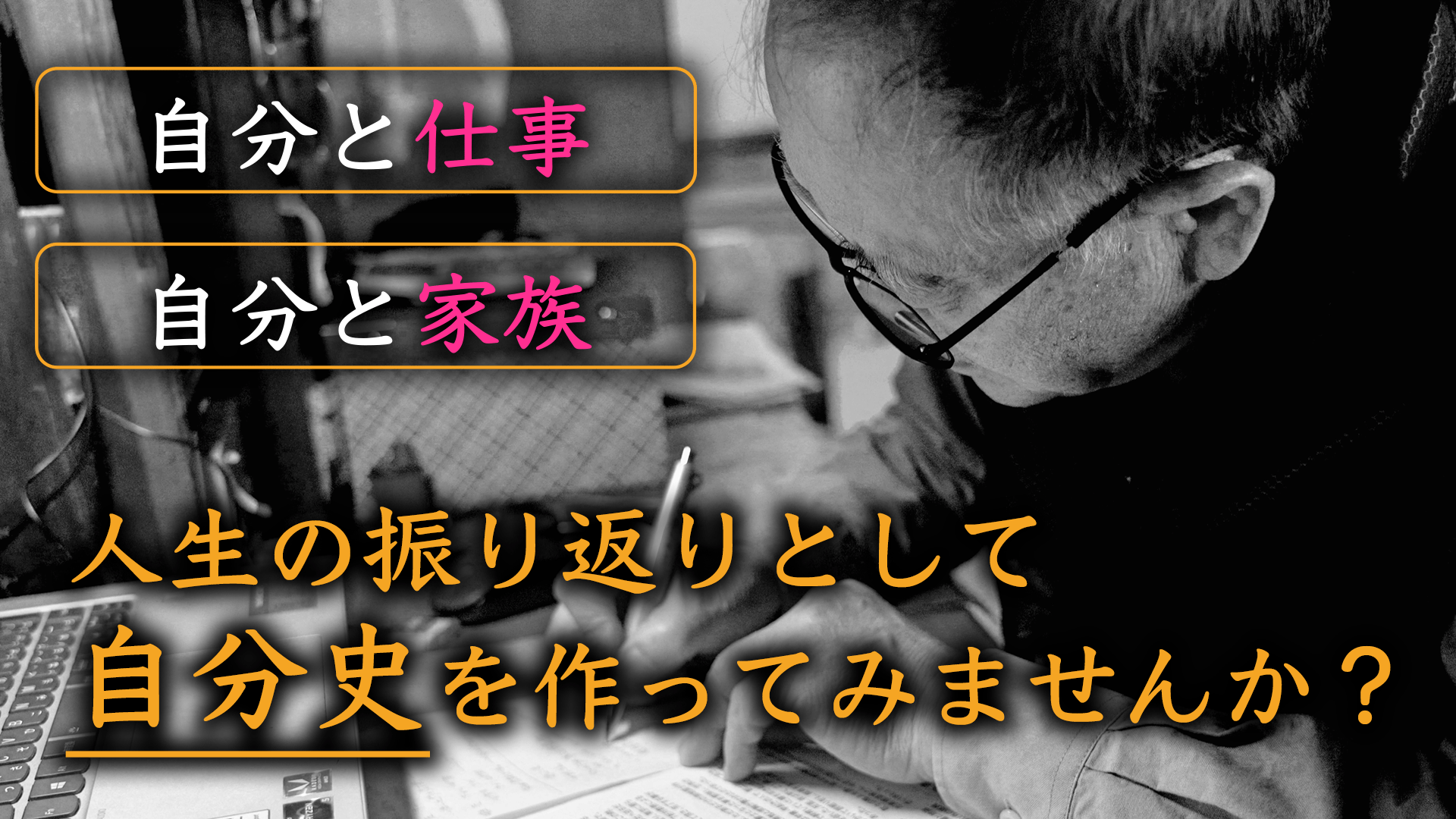


西室 建
2/18/2015 | Permalink
カリフ=皇室制は面白い。目から鱗だが、そういう伝統・制度は内側からも崩れるという教訓になるか。
ところでマルタに行った家系はその後どうしているのかね。
中村 順一
2/19/2015 | Permalink
オスマン皇帝家族は国外に追放になっただけで、ニコライ2世の家族のように殺されてはいない。マルタに亡命したメフメット6世はイタリアのサンレモで死去、遺骸はダマスカスに埋葬された。家族はイタリア、エジプト、フランス等に散らばって住んだ。アブデュルメジト2世はパリで死去、遺骸はメディナ。なおトルコ政府は現在ではオスマン皇帝一族の帰国を認めており、子孫はイスタンブールに住んでいる人もいるようである。