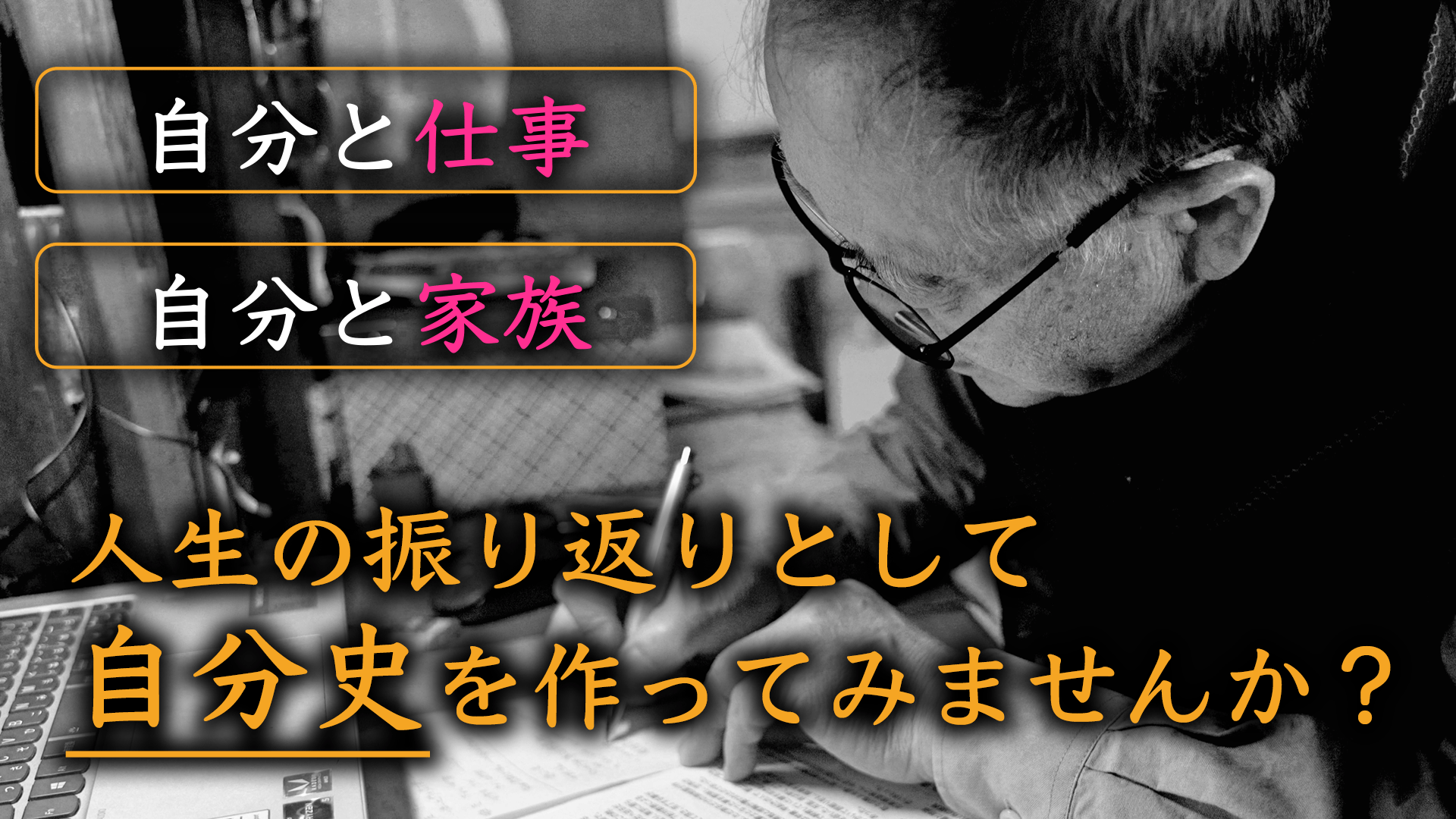耳に聴こえてきた音楽 早期の「がん」になって
2017 OCT 30 12:12:02 pm by 野村 和寿

曲がりなりにも、長いこと出版社で編集者の端くれの生活だったので、この体験をなるだけ忠実に記しておこうと思った。10月初旬、大病院の消化器内科の担当お医者様は、外来の診察で、開口一番、「早期の胃がん」ですと私に告げた。とても無表情だったのが、かえって信憑性を増した感じだった。外来からの帰宅途中、いつもより遠回りして、きっとまだ気持ちの整理がつかず、端からは相当にとぼとぼと歩いていたようにも思える。昼間の住宅街を歩いていると、耳にウォークマンみたいに、聴こえてきたのは、プッチーニの歌劇『マノン・レスコー』の第3幕の冒頭で鳴る「間奏曲(インテルメッゾ)」。たしかカラヤンの演奏のもの。
劇的にヒロイン・マノンの行く末を暗示し、舞台はヨーロッパから米国にまで飛んでしまうという、ロマンチックすぎるオペラ。たしか1986年に、時ならぬ大雪で交通が麻痺した最中のNHKホールで、ウィーンの国立歌劇場が『マノン・レスコー』強行上演をしたときに、聴いたものも同じ曲で、それがあまりにも、たたみかけるような情熱的なシノーポリの指揮だったものだからそれが耳に残っていたのだろう。
(プッチーニ歌劇『マノン・レスコー』フレーニ(マノン) ドヴォルスキ(騎士デ・グリュー) オットー・シェンク演出 シノーポリ指揮ウィーン国立歌劇場管弦楽団 NHKホール 1986年4月3日)下記の音源は、同じ演者のもの。冒頭に3幕が始まる前の情熱的な間奏曲(インテルメッゾ)が収録されている。
続いて聴こえてきたのは、プッチーニの悲劇的なオペラ『トスカ』最終幕、舞台はローマに今も残るサンタンジェロ城の場内で、トスカが歌うアリア。恋人であるカヴァラドッシにもう死んだふりをしなくていいのよ、と歌うところ。歌劇『トスカ』 第3幕「 待つということは、なんて長いことでしょう!」
Maria Callas “Come è lunga l`attesa” Tosca
実は恋人の画家カヴァラドッシはこの時点では、すでに銃殺隊の銃弾に倒れていて、息絶えていたのだったが。それを知らない歌姫トスカが歌う。
少々、一九五〇年代のオペラがまさにグランド・オペラだった、大時代がかった演技のマリア・カラスが耳にウォークマンも何もしていないのに飛び込んできた。それも聴こえてくる音は、いつもよりも『透明感』もあって、ノイズもなしにきわめて鮮明に。街を歩いていても、ずっと聴こえてくるオペラのアリア。
がんの告知前の体調では、少し気分が悪く、少し熱があり、胃が少しもたれ、お腹も少し痛かったのに、告知された後は、むしろ、それら「少し」が一旦停止の感あり。
小林一茶の句「目出度さもちゅう位なりおらが春 」をもじるならば、
「あちこちのいたさも ちゅう位なりおらが春」
気持ち悪さも、なにか普通の状態にもどったのに近く、むしろ、センシティブな分、頭が少しだけ聡明というか、鮮明になったような気分だ。
頭をもたげてくるのは、不思議にも、昔、懸案で解決しなかった、いろいろな問題だった。撮影のときの問題とか、企画がなかなか思い通りにいかなかったとか、その当時は、大問題だと思っていた問題が、次から次へと頭に湧いては消えていく。それらの問題は結局の所、全部うまくいかなかった問題ばかりだったのだが。
ぼくの耳から聴こえてくる「人間ウォークマン」は、ときと場所を選ばずに、いろいろな音楽がきわめてランダムに、聴こえてくるから不思議だった。
逆に言えばなんでこの曲がこんなに大事なときに聴こえてくるのかよくわからない。半信半疑だったともいえるだろう。続いて聴こえてきたのは、なんと「イギリス音楽」。ディーリアスやボーン=ウイリアムス、エルガー、ホルストなどのイギリス音楽。いつもは、イギリス音楽なんて・・・とあたかも小馬鹿にしていたように、ヘンリー・パーセルのあと、ハンデル(イギリス読みのヘンデル)があって、そのあとは、ダイレクトに、ブリテンまで「島国イギリスの音楽」なんてなかろうに・・・と思って、「高(たか)を括(くく)っていたというのに」イギリス音楽は、ホルストの「火星」や「木星」のように、メロディーがストレートに自分の内面に飛び込んでくるかのようなそんな気持ち。
まったく不思議な体験である。ディーリアス「春初めてのかっこうを聞いて」もそう。このまか不思議な曲は、たった一度、ロンドンで聴いたことがあるだけだというのに。動画は「夏の庭園で」という曲。
自然のなかで奏でているように。ヨーロッパ大陸の昔のようなたたずまいが、かえって島国であるイギリスに奇跡的にも残っているのとにているように。ディーリアスの音楽にもこの「不思議なたたずまい」を感じてしまう。上記youtubeは、ジョン・バルビローリのイギリスのハレ管弦楽団の演奏である。
別に特に田舎の景色のいいところをそぞろ歩いているわけでもなく単に街の住宅街をとぼとぼと歩いていただけなのに、これまた不思議だった。
ディーリアスは、なんだかんだと理屈がまったくなくて、ウイスキーをストレートで呑んだときのような、少し、重ったるいけれど、どこかすきっとくる気持ちに似ていた。まったく不思議だった。
ぼくの「人間ウォークマン」は、幻聴なのだろうか? どうして、こんな種類の音楽が予期せずに聴こえてくるのだろうか?それは、どうも自分が予期せずに、病気のなかでも、超有名な胃がんの患者になった、一種のヒロイズムにも似た不思議なマイナー意識を、どこかで、自分で自分を慰めるような、アドレナリンのような気持ちでもあったように思う。
こういうときは、いつもならば、「モーツァルト」とか聴きたくなったのだが、不思議にも「モーツァルト」は聴こえてこず、本当の機械のウォークマンでもって、イヤホンを自分の耳に挿入し、モーツァルトをかけてみても、本来、自分の予測のなかでは、「モーツァルトの音楽」は爽やかなはずなのに、どうも「もったり」としていて、あまり耳には芳しくなく、正直なところ、目が回るようで、あんまり気持ちの良いものではなかった。いつもなら、あんなに好きなモーツァルトなのに。
そして、ぼくのもっとも大好きなベートーヴェンは、手術も無事終わり、いまのところは小康状態を保ち、開口一番がんを宣告したお医者によれば、患部はとりきれたという。もちろん、まだまだ予断は許されない状態をキープしてはいる。手術から1週間が経ち、ようやく、少しはお粥が食べられるようになったころ、ぼくの「人間ウォークマン」にベートーヴェンも登場してきた。
それも、あまたのベートーヴェンのなかでも、聴こえてきたのはそれまで、まったくといってよいほど、「予期」もしていなかった、ベートーヴェンの交響曲のなかでも一番地味といってもよい、「交響曲第二番」だった。不思議なものである。
後に、病院から退院したとき、いつもは滅多に聴かないベートーヴェンの「交響曲第二番」をオーディオでかけて聴いてみた。こういうときは、苦労の末に酸いも甘いもわかったような指揮をするチェコの指揮者ラファエル・クーベリックだろう。そう思えてならなかった。下記の映像は、クーベリック指揮のオランダのロイヤル・コンセルトヘボウ・オーケストラの映像である。
どうでもいい音楽なんて、やはり世の中にはなくて、こちらの気持ちが、予期しないぐらいに心身共に、ある別の状態に向かっているときこそ、本来の意味での
「癒やしの音楽」が普段とはまったく違った形で、しかも予期しない形で流れてくるのだろう。ぼくはこの病気とともに暮らしていくことになったいわば、まだ初心者もいいところだ。しかし音楽には不思議な力のようなものがあるものだ。ぼくの「人間ウォークマン」は、まだ調整がきかずに、突然耳のなかで、鳴り出すという癖を持っている。最近は、プッチーニの『マノン・レスコー』の「インテルメッゾ」も『トスカ』も鳴らなくなり、もっぱらベートーヴェンの「交響曲第二番」のそれも、第一楽章の序奏が終わってオーケストラが動き出すところ」なのである。嘘のような本当の話である。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPはソナー・メンバーズ・クラブをクリックしてください。
プッチーニと「夕焼け小焼け」の関係
2017 JAN 7 8:08:43 am by 野村 和寿

ぼくはオペラを聴くときに、どうしても音楽、メロディーから先に聴いてしまい、ストーリーが後になってしまう傾向があるのですが、メロディーからときどき面白いことに気づかせられることがあります。プッチーニと日本の童謡で誰でもご存じの「夕焼け小焼け」について今回は述べることにします。
ジャコモ・プッチーニ(1858−1924年イタリア)
といえば、『マノン・レスコー』1893年作、『ラ・ボエーム』1896年作、『トスカ』1900年作、『マダム・バタフライ(蝶々夫人)』1904年作と、立て続けにヒット・オペラ作品を作曲していったが、『トゥーランドット』は、1924年11月彼の死によって未完に終わりました。このオペラを契機に、ロッシーニ、ヴェルディ、ドニゼッティ、レオンカヴァッロ、そしてプッチーニと続いたイタリアのグランド・オペラは一気に衰退していくことになるのですが。
『蝶々夫人』の作曲時に、日本から日本の歌謡の楽譜を大量に取り寄せたことはよく知られていて、「お江戸日本橋」のメロディーが、『蝶々夫人』の中に出てきたりします。
そして歌劇『トゥーランドット』を観ていると、どこかで聞き覚えのあるメロディーが聴こえてきます。そうです。これは童謡『夕焼け小焼け』(草川信作曲中村雨紅作詞1923年)の『やーまのおてらのかねがなる』の音楽部分に非常によく似ています。というよりもそっくり同じです。
この音楽は、プッチーニが、きっとまた、東洋を舞台にした、オペラを作曲するにあたって、中国も、日本も、東洋である一緒に考えていて、中国を舞台にしているのに、日本の「夕焼け小焼け」からメロディーを拝借したと考えてもおかしくないのではないかと思われます。
夕焼け小焼け 草川信作曲 中村雨紅作詞 1923年
1 夕やけこやけで 日が暮れて
山のお寺の 鐘がなる
お手々つないで みなかえろ
からすといっしょに かえりましょ
2 子供がかえった あとからは
まあるい大きな お月さま
小鳥が夢を 見るころは
空にはきらきら 金の星

写真は路線バス「夕焼け小焼け」号。歌を作詞した中村雨紅の故郷、東京府南多摩郡恩方村(現在の東京都八王子市)の「夕焼小焼」バス停にて。バスは2006年まで運行されていたボンネットバスが運行されていました。(ウィキペディアより引用)
DATA:プッチーニ(1858-1924年) 歌劇『トゥーランドット』(初演1925年)
1919年作曲にとりかかり、途中1921年から22年作曲が中段されるが、1923年作曲再開1924年11月29日プッチーニの死により未完におわる。アルファーノが補作し1925年4月ミラノ・スカラ座でトスカニーニの指揮により初演。
映像DATA:ジャコモ・プッチーニ 歌劇『トゥーランドット』
トゥーランドット:ガブリエレ・シュナウト
カラフ:ヨハン・ボータ
リュー:クリスティーナ・ガイヤルド=ドマス
ティムール:パータ・ブルチュラーゼ
ウィーン国立歌劇場合唱団テルツ少年合唱団
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
指揮:ワレリー・ゲルギエフ
演出:デイヴィッド・パウントニー
収録:2002年8月、ザルツブルク祝祭大劇場
今回は、よりプッチーニの意図に沿った形で、第3幕の悲劇のヒロイン「リューの死」以降をイタリアの現代音楽の作曲家ルチアーノ・ベリオが補作した版をお聴きください。
ぼくが、数えた中でも第1幕13:45 17:30、20:50、34:08 58:12 1:13:04,1:15:50
第3幕 1:31:18と、なんどもなんども・・・
「やーまのおてらのかねがなる」のメロディーが聴こえました。もしお時間があったら、ぜひ、「夕焼け小焼け」を念頭に入れて、このオペラを聴いてみると面白いと思います。
ベリオ補作版でさえも、これだけの「夕焼け小焼け」が出てくるのです。通常のアルファーノ補作版であれば、さらにエンディングにこれでもかと「夕焼け小焼け」がでてくると思います。
さらに調査を続行していくと、思わぬ事が分かってきました。
中国の古謡に「茉莉花(ジャスミン)」という曲があり、これを聴いていくと
まさに「夕焼け小焼け」の「やーまのおてらの」にそっくりなのです。この曲は清末から伝わっている曲だそうです。つまり年代から推定すると、「夕焼け小焼け」のほうが、中国の古謡から採っているのかもしれなません。あるいは偶然?
いやいやプッチーニは、日本のメロディー「夕焼け小焼け」から採っているのだとすると、こういう状況証拠もあります。
1900年オペラ『蝶々夫人』作曲時に、当時の在イタリア大使夫人 大山久子から、日本の音楽のレクチャーを受けてとあり、大山久子(大山巌大将の親族で長州藩出身 夫は薩摩藩出身)の紹介で、1902年には、海外公演中の日本の女優川上貞奴にもパリ万国博のときに会って、日本の音楽について取材もしています。そのときの印象があって、日本から新曲1922年作の「夕焼け小焼け」の楽譜を取り寄せたのかも知れません。
また、元に戻って、プッチーニの『トゥーランドット』は、ぼくの頭の中では、いまだに「夕焼け小焼け」で鳴っているのです。
「トゥーランドット」というと、ついつい、「ネッスン・ドルマ[誰も寝てはならぬ]が有名でそこばかりが、クローズアップされがちですが、オペラの楽しみはそれだけではありません。すこしでもオペラを知って欲しいと思いまして書いてみました。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPはソナー・メンバーズ・クラブをクリックして下さい。