ブラームス交響曲第3番の聴き比べ(3)
2017 NOV 7 20:20:45 pm by 東 賢太郎

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー / ハレ管弦楽団
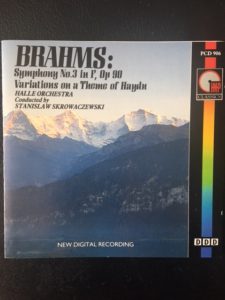 Mr.Sが当時の手兵ハレO.と録音した最初のブラームスSym全集。1987-8年にロンドンでCDとして発売された最初期のブラ全で、入手したてのCDプレーヤーで狂喜して何度も聴いた。思い出の盤なのでどうしても主観が入るが、客観的に聞きなおしてみても、なにより弦楽器セクションの絶妙な音色造りと管楽器の音程の良さがこのレベルのオケにして驚異的レベルで、内声部の管が良く聞こえるバランスが室内楽的完成度にある。一言でまとめるなら雄渾さと深いロマンの味わいが絶妙にブレンドし、3番の醍醐味を十全に描き出した名演。第1楽章、第2主題に向けてテンポを落とす、展開部終盤でホルンを強奏、意外な楽器バランス等個性があるが僕はまったく不自然と感じない。第2楽章、ホルンとクラリネットの主題の歌、弦の細やかなフレージング、第3楽章の一切べたつかない高貴な気品。終楽章、トロンボーンがこれだけ聞こえるのも珍しいが過度なヒロイズムにならず深い満足感に至って終結する(総合点:5)。
Mr.Sが当時の手兵ハレO.と録音した最初のブラームスSym全集。1987-8年にロンドンでCDとして発売された最初期のブラ全で、入手したてのCDプレーヤーで狂喜して何度も聴いた。思い出の盤なのでどうしても主観が入るが、客観的に聞きなおしてみても、なにより弦楽器セクションの絶妙な音色造りと管楽器の音程の良さがこのレベルのオケにして驚異的レベルで、内声部の管が良く聞こえるバランスが室内楽的完成度にある。一言でまとめるなら雄渾さと深いロマンの味わいが絶妙にブレンドし、3番の醍醐味を十全に描き出した名演。第1楽章、第2主題に向けてテンポを落とす、展開部終盤でホルンを強奏、意外な楽器バランス等個性があるが僕はまったく不自然と感じない。第2楽章、ホルンとクラリネットの主題の歌、弦の細やかなフレージング、第3楽章の一切べたつかない高貴な気品。終楽章、トロンボーンがこれだけ聞こえるのも珍しいが過度なヒロイズムにならず深い満足感に至って終結する(総合点:5)。
エヴゲニ・スヴェトラノフ / ソヴィエト文化省交響楽団
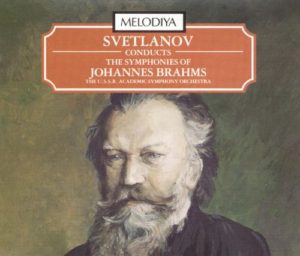 1981年録音。ロンドンで手当たり次第にブラームスSymを買っていた89年に全集で購入。Melodiyaとあるが当時のレーベルはOlympiaであった。オケに国民性によるカラーがあった時代にこういうのが出るとマニアはたまらなかったのだ。懐かしい。意外に?まっとうで拍子抜けだがホールトーンはやや人工的か。終楽章できつめのVnと金管がロシアらしくなるが、オケ(もうないが)はうまい。ソビエト社会主義共和国連邦の遺産だ(総合点:3)。
1981年録音。ロンドンで手当たり次第にブラームスSymを買っていた89年に全集で購入。Melodiyaとあるが当時のレーベルはOlympiaであった。オケに国民性によるカラーがあった時代にこういうのが出るとマニアはたまらなかったのだ。懐かしい。意外に?まっとうで拍子抜けだがホールトーンはやや人工的か。終楽章できつめのVnと金管がロシアらしくなるが、オケ(もうないが)はうまい。ソビエト社会主義共和国連邦の遺産だ(総合点:3)。
ジョージ・セル / クリーブランド管弦楽団
オケが鳴りきってバランスも良く理想的な第1楽章。やや速めの開始が第2主題で減速するに至る難しい提示が実にうまい。第2楽章は透明なアンサンブル、第3楽章は節度ある歌でじっくりブラームスのロマンをきかせる。終楽章、クリーブランドO.の威力全開だが、矛盾するようだがこれだけうまいと耳が贅沢になってどこか予定調和的に思えてしまう。上記ハレ管は手造りの完成度で耳目を捉えたが、文句のつけどころのないこちらはなぜか感銘度が落ちる。セルのブラームスはどれも高水準を満たすが、特に3番は彼に向いていたと思う(総合点:4)。
セルジュ・チェリビダッケ / ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団
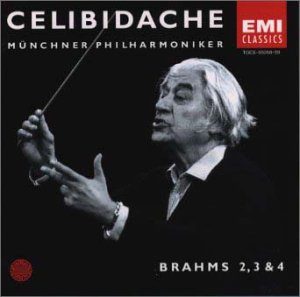 当時「幻の」だったこの指揮者が初来日した77年、大統領でも来たような東京文化会館の熱気は忘れない。聴衆は読響からどんな音が出るか戦々恐々だった。エゴイストに思われるが、後年彼のリハーサルで目撃したのはドビッシーの求める音を微細なまでに純化して鳴らす求道者の姿だった。そこでもそうだったが、第2楽章のテンポ(というより)は陶酔感と時間感覚がタイアップした不思議な世界だ。セルのように基本の拍節感から音符、小節単位でルバートするのでなく、大きな単位での脈動に音量、フレージングの呼吸がシンクロして巨大な揺りかごにいるような心地よさだ。酔えずに冷めていると遅いと感じるのは晩年のブルックナーで顕著だったが、彼の音作り哲学はカーチス音楽院で見た83年からなんら変わっていないと思う(総合点:3.5)
当時「幻の」だったこの指揮者が初来日した77年、大統領でも来たような東京文化会館の熱気は忘れない。聴衆は読響からどんな音が出るか戦々恐々だった。エゴイストに思われるが、後年彼のリハーサルで目撃したのはドビッシーの求める音を微細なまでに純化して鳴らす求道者の姿だった。そこでもそうだったが、第2楽章のテンポ(というより)は陶酔感と時間感覚がタイアップした不思議な世界だ。セルのように基本の拍節感から音符、小節単位でルバートするのでなく、大きな単位での脈動に音量、フレージングの呼吸がシンクロして巨大な揺りかごにいるような心地よさだ。酔えずに冷めていると遅いと感じるのは晩年のブルックナーで顕著だったが、彼の音作り哲学はカーチス音楽院で見た83年からなんら変わっていないと思う(総合点:3.5)
ジョン・エリオット・ガーディナー / オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティック
 確かに対抗配置のVnなどでリヴォルーショナリー(革命的)な音の聞こえる部分がある。オーセンティック楽器での音化はチャレンジングな試みだが演奏様式がこうだったかは僕には確信がもてない。ブラームス時代の奏者がここまで現代的な演奏技術があったかどうか。こう鳴らすには指揮もテクニックがいるだろうが、ブラームスがこんな切れ味良い棒を振ったとはどうしても思えないのだ。楽器音のリアライゼーション目的ならよいが、時代シミュレーションがやりたいならオケはアマチュアを使った方がそれらしくなるのではないか。しかし、いずれにしても、それを我々が知り覚えたからといって、3番のスコアからさらに深い感動が得られるようになるとは特に思わないが(総合点:1)。
確かに対抗配置のVnなどでリヴォルーショナリー(革命的)な音の聞こえる部分がある。オーセンティック楽器での音化はチャレンジングな試みだが演奏様式がこうだったかは僕には確信がもてない。ブラームス時代の奏者がここまで現代的な演奏技術があったかどうか。こう鳴らすには指揮もテクニックがいるだろうが、ブラームスがこんな切れ味良い棒を振ったとはどうしても思えないのだ。楽器音のリアライゼーション目的ならよいが、時代シミュレーションがやりたいならオケはアマチュアを使った方がそれらしくなるのではないか。しかし、いずれにしても、それを我々が知り覚えたからといって、3番のスコアからさらに深い感動が得られるようになるとは特に思わないが(総合点:1)。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
Categories:______ブラームス, ______演奏家について






野村 和寿
11/13/2017 | 11:56 AM Permalink
大学で交響楽団に所属している頃、ブラームスの3番を弾いたことがあります。ぼくはチェロを弾いていたので、第3楽章の冒頭部分であまりにも心地よくて、思わず練習がおわったときに、ビオラ奏者に「なんか悪いね、ごめんね」といったら、ビオラ奏者いわく、vcがメロディーを弾いているときに、それを支えている自分がいつということで、vla奏者も気持ちいいんだそうです。第2楽章で、クラリネットが出てくるところ、vcはそれを支えるだけなのですが、ぼくもこのvla奏者と同じような気持ちになりました。指揮者はエルヴィン・ボルンというカッセルの歌劇場から東京藝大の指揮科の客演教授として来ていた人でした。だから、ぼくにとってはブラ3は特別です。
東 賢太郎
11/13/2017 | 11:38 PM Permalink
野村君ありがとう。弾いている人はそういう気持ちなんだね。そういえばヴィオラの人がドヴォルザークとブラームスが一番とか言ってました。