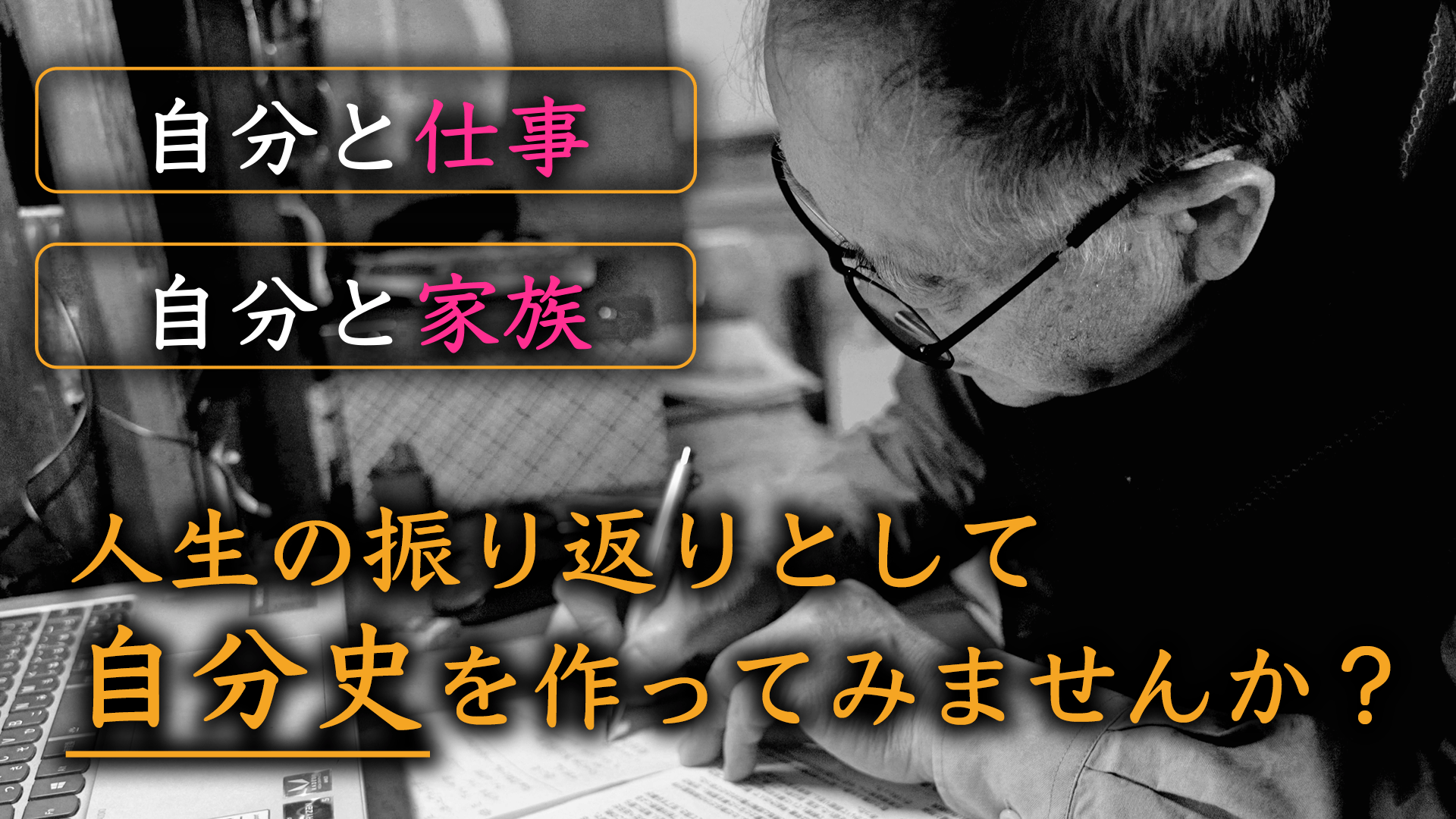R.ゼルキン再説~シューマンのOp. 134と「赤とんぼ」
2019 NOV 19 14:14:26 pm by 大武 和夫

第1回投稿へのコメントに対するご返事に、先週末にアップする原稿にはR.ゼルキンを採り上げる予定であるとお書きしました。少し遅くなってしまいましたが、本稿では再びゼルキンについて書いてみます。
実は書きたいテーマは山ほどありました。すでに終わっている河村尚子さんとオズボーンのベートーヴェンの最後の三つのソナタの素晴らしい演奏、久々に岡田博美さんが弾いてくださった「十八番」であるブラームスのパガニーニ変奏曲の深く心に染み入る全曲演奏(あの超絶技巧曲でそんなことが可能だったとは!)、新国「ドン・パスクワーレ」のおしなべての水準の高さ、ノット/東響のベルクの圧倒的な美しさ、この季節になると無性に聞きたくなるフォーレの後期作品(ことにピアノ・トリオ/ノクチュルヌ13番/ピアノ・クインテット1番/チェロ・ソナタ1番/弦楽クアルテット)、興行成績が悪かったのか早々に通常版の上映を打ち切られてしまい現在では特別編集版だけが数少ない映画館でひっそりとかけられている(ように見える)是枝監督の「真実」、そして何と言っても5度も足を運んでしまった東京都美術館の圧巻の「コートールド展」のセザンヌ「アヌシー湖」、等々。
しかし、あれこれ迷っているうちに時間が経ってしまい、このままだと時期を逸してしまいそうになりましたので、冬に入る前にR.ゼルキンについてもう一度書かせていただくことにしました。(コートールド展のセザンヌとフォーレ、ブルックナーは私にとっては一つのテーマの変奏にすぎませんので、展覧会の会期が終了する前に一つの文章にまとめて書かせていただきます。そして、その前にできれば河村さんとオズボーンについて書き、その中でパガニー変奏曲と組み合わせてベートーヴェンの4番のソナタをも弾かれた岡田さんの演奏についても、触れようと思っています。)
なぜ時期を逸してしまう前にR.ゼルキンなのか。なぜ冬になると時期を逸してしまうのか。判じ物のようだと思われるでしょうが、それはゼルキンが畢生の名演を残しているシューマンOp. 134「序奏と協奏的アレグロ」(「序奏と演奏会用アレグロ」と訳されることもあります。)について、秋の間に書こうと思い立ったからです。(この曲の原題は、ややこしいことにOP. 92と同じ「Konzertstueck」(ウムラウトは本稿では「e」の挿入で代用)なのですが、英語題名も邦題も、2曲で訳し分けています。両曲を区別し、混乱を避けるためでしょうか。)
まだ判じ物ですね。なぜOp. 134の演奏について書くのが秋でなければならないのか。これはピアノ・マニア以外には正答が難しい問かもしれません。
答えは、演奏されることが稀なOP. 134には、あの「赤とんぼ」が何度も何度も、これでもかと言わんばかりに繰り返し登場するからです。それはもうびっくりするぐらいの大盤振る舞いで、まるで「山田耕筰讃歌」の様相を呈している・・・筈はありませんね。山田耕筰のドイツ留学は、もちろんシューマンがエンデニヒの精神病院で悲劇的な死を遂げたはるか後のことなのですから。
初めてこの曲を聴いたのは、R.ゼルキンとオーマンディー/フィラデルフィア管の共演の録音によってでした。記憶が正しければ、大学に入ったころ、つまりもう50年近く前のことになります。ゼルキンを初めて聴いたのはブラームスの2番のコンチェルトのセル/クリーヴランド管の演奏。その演奏に魂消た私(「衰えが隠せず寝ぼけた感じのバックハウス/ベームよりずっと良いじゃないか!」)が二枚目だか三枚目だかに買い求めたのが、忘れもしない、この曲が入ったLPでした。そして現在に至るまで、この曲でこの演奏を凌駕する演奏を知りません。
ややくぐもった色調でひそやかに始まった悲劇が高揚し、それが一旦収まった後、tranquilloの指示(オケはpiu tranquillo)を与えられたピアノがdurで歌うその歌(dolceの指示あり)の、なんと懐かしくも美しいことか! それが正に「赤とんぼ」なのです。「ラド~レミソドラソ、ラド~レミソラファレ」というそのメロディーを、「ユウヤ~ケコヤケ~ノ、アカト~ンボ」と重ねて歌ってみて下さい。そのままピタリと重なるわけではありませんが、主要な音の動きは瓜二つです。それによってもたらされる情動も。
この「赤とんぼ」の主題は、全編を通じて繰り返し現れますが、オケがおずおずと初めてこの旋律全体を奏する箇所と、結尾近くのピアノのカデンツァで32分音符のさざ波の中からくっきりと立ち上がって歌われる箇所では、名状しがたい懐かしさと望郷の感覚に胸が締め付けられる思いがします。そしてそのカデンツァのピアノ書法の見事さと言ったら! 死のわずか3年前の作品ですが、どこにも精神の変調、韜晦など見てとれず、シューマンがピアノに与えた最も美しいページの一つがここにあります。「苦み」が僅かに混じっているように聞こえるのは、彼のその後の人生を知っている後世の人間の先入観かもしれませんが、高揚はしても絶対に華やかにはならない、華美を拒否したような音楽のあり方は、やはり晩年の作品なのだと納得させられます。一種の静かな澄明さがカデンツァを、そして作品全体を支配しており、どんなに高揚しても声高にはならないのです。
そして、そのカデンツァを弾くゼルキンの演奏の立派さも、カデンツァ自体の見事さに少しもひけをとるものではありません。シューマンの精神の襞に分け入り、その情動に寄り添いつつ、例によって人柄の誠実さと朴訥さを隠せない無骨なタッチとやや不器用なフレージングで音を紡いでいくゼルキンの音楽は、少し感じ方の遅いようなシューマンの音楽・・・この表現はホロヴィッツのクライスレリアーナ旧盤のライナーノートで吉田秀和さんが使っておられた言い回しで、これだけで吉田さんの耳の良さと文学的素養・音楽的教養の深さが見て取れますね。借用させていただきます・・・そのものと言ってよく、全く理想的表現だと思わせます。
名前を挙げるのは申し訳ないのですが、例えば比較的最近のペライア/アバード/BPOの共演盤の演奏は、流線形の演奏の典型で、実にサラサラと流れます。演奏時間はゼルキン盤が14分40秒もかけているのに対し、こちらはたったの12分47秒ですから、全体のテンポ設定もだいぶ速いことが分かります。その結果として立ち現れる(因果関係はあるいはその逆か?)少しの淀みもない演奏は、無類に美しいのですが、和声が変化する箇所や、フレージングの切れ目などにはほとんど無頓着で、先へ先へとずんずん進んでしまうように聞こえます。テンポの揺れもほとんど感知できません。散歩の道すがら美しい花が咲いていたり、美しい山が見えてきたら、歩を緩め、あるいは足を止めて、鑑賞したくならないでしょうか。このスマートで現代的な演奏には、そう問いかけたくなります。カデンツァを通して用いられる32分音符の音型は、予想通り見事にノッペリ・スッキリと弾かれていて、ある種のリストの曲の伴奏音型のように響きます。優秀な音楽家ペライアの演奏ですから、これは多分に誇張した批判なのですが、それでも、シューマンらしくないと私は考えてしまいます。こういうところで32分音符がきちんと聞こえてこないと、それはもうシューマンではないのです。(ホロヴィッツはリストの32分音符ですら、決してノッペリ・スッキリとは弾きません。ゼルキンがリストを弾いたとしても、同じだったでしょう。)それはなにも、ガチャガチャうるさく弾けということではありません。そこから赤とんぼの主題が立ち上ってくるのですから、あくまでも背景として静かにひっそりと奏でられるべきであることは当然です。しかし、それがノッペリしていたのでは、音楽が必要とする深みは表現し切れません。ペライアはゼルキンに(も)師事し、カーティスではその助手も務め、あまつさえホロヴィッツの親交を得てロマン派音楽を学び直しもしたというのに、一体どうしたことでしょう。(ペライアは他にも、バッハを沢山弾く前にバロックを学んだと言っていますが、あまりにも流麗な彼のバッハを聴いていると、例えばイネガル一つとっても全くモノになっていないように聞こえます。この俊英にとって残念なことです。)
ロマン派音楽が、地上には存在しない永遠の高みに憧れ、その高みを目指して駆け上ろうとしつつ、それが叶わぬ夢、報いられぬ徒労に終わることを知り、それでも、いやそれが故にこそ、益々憧れが強まり、結果として苦悩し、傷つき、再度立ち上がって再び高みを目指す、そしてまた傷つく、という情動のうちに成り立つものであるとすれば、シューマンの音楽こそ、まさに典型的なロマン派音楽、ロマン派中のロマン派音楽であると言えるでしょう。そして、mollとdurが赤とんぼの旋律をめぐって交錯するこの曲ほど、シューマンがロマン派中のロマン派であることを示す作品が他にあるでしょうか。
そうであるなら、全てのフレーズにそのロマン派の精神が反映されていなくてはなりません。さらさらと流れる歌、ノッペリとした伴奏音型、流線形のスマートさ、そんなものはシュ-マンにあってはならないのです。あってはならないと、私はそう信じます。そして、そのようなシューマンの精神を現実に響く一音一音に籠めた演奏が可能なのは、わが偏愛のゼルキン(とホロヴィッツ)しかいないではありませんか。(これはレトリックであり、現役ピアニストたちの中にも見事なシューマン弾きは数名います。念のため。)
この曲をオーケストラ作品ととらえた場合、これに匹敵するオーケストラ作品がシューマンの作品中に存在するとは思えません。賛同者はおられないかもしれませんが、4曲の交響曲の中で最もシューマネスクと言われる2番より、私はOp. 134の方がさらにシューマネスクであると考える者です。
ピアノ独奏曲には、大幻想曲とクライスレリアーナという記念碑的作品であると同時に最もシューマネスクである金字塔が二つありますが、オケを伴う完成したピアノ作品三つ(Op. 134の他に、協奏曲Op. 54と冒頭で触れたOp. 92があります。)の中では、断然この曲をとります。
そうであるのにOp. 134の驚くばかりの人気の無さはどうでしょう。ピアノ・オタクの私ですら、一度たりとも実演で聴いたことが無いのです。数年前に、敬愛するアンスネスに3曲を一回のコンサートで弾くプロジェクトをやってもらえないかと頼んでみたことがあります。しかし、あまり気乗りしない様子で、それは良いねえというおざなりな返事が返ってきただけでした。河村尚子さんなどはアンスネス以上に最適任者のお一人だと思うのですが、次にお目にかかるときにお願いしてみようかと思っています。
そもそも演奏されることが少ないこの曲に、最高にシューマネスクな名演奏を残してくれたゼルキンに感謝するばかりです。また、日本では遂に評価されることなく終わったオーマンディーの指揮も、過不足ない出来を示しています。フィラデルフィア管というと華麗なオケであるとの先入観が存在しますが、実は木管が(木管も)素晴らしいということがよくわかる録音です。コロムビアの録音も、カッチリとしつつも冷たくなりすぎない立派なものです。(この盤の後で先述のペライア盤を聴くと、あまりにスムーズで角の無い録音に驚かされます。アメリカとヨーロッパの録音の違いと言って片付けるのが憚られるほどの違いです。演奏に見合った録音というべきか、あるいは録音に見合った演奏というべきか。)ゼルキンにとってもこの録音は、A.ブッシュとのシューベルトの大幻想曲、ハンマークラヴィーア、ブラームスの晩年の作品集、先述のセルとのブラームスの2番のコンチェルト等々と並んで、最重要の録音の一つであると言ってよいと思います。
最後に、初めてこの曲を聴いたときに「赤とんぼ」に驚いた私は、山田耕筰が留学中にこの曲(の楽譜ないし演奏)に接したに違いないと考え、少し調べてみました。しかし、残念ながら、どこにもその答えは見つかりませんでした。(答えをご存じの方がいらしたらご教示ください。) さらに、この曲と「赤とんぼ」の旋律の類似性について、誰かが何か書いていないだろうかと考え、その点についても調べてみましたが、当時そういうことを指摘した文献を見つけることはできませんでした。それで私は得意になって、音楽好きの知人たちに、私の「発見」を得々として語ったものでした。しかし、これほど強い類似性に、音楽の素養のある人が気付かないはずはありません。類似性はあまりに自明なので、誰もことさらにそれを説いたりする必要を認めなかったのでしょう。私の独り相撲であり、若気の至りであったということだろうと、今にして思います。汗顔の至りとはこのことです。それから半世紀近く立った現在では、ネットをググれば、すぐに類似性に関する考察を見つけることができます。
これで終えようと考えて読み直してみて、全曲に横溢する「懐かしさ」の感覚と「赤とんぼ」の関係について、きちんと触れていないことに気付きました。つまり、懐かしさの理由が、旧知の赤とんぼに出会えたからなのか、それともそれ以外の事情によるものなのか。初めて聴いたときから「赤とんぼに似ている!」と考えて聴き続けてきたこの曲に対し、その要素を捨象して向き合うことはもはやできません。ですから、前者の要素を否定することは不可能なのですが、しかし、赤とんぼを知らなかったとしても、赤とんぼ類似の旋律自体に、そしてOp. 134の高揚しても決して大言壮語しない曲の作りに、そのしみじみと語りかける美しさに、ある種の懐かしさを覚えないこともまたあり得ないと思うのです。答えにならないこの独白で本稿を閉じることにします。
Categories:未分類