新国~我らのオペラ小屋
2021 APR 16 17:17:14 pm by 大武 和夫

新国立劇場のワルキューレの5回の公演中3回に足を運び、大きな感銘を受けました。
公演は終了していますし、既に様々なメディアでその大成功が喧伝されていますが、私にとってこの公演は20年に及ぶ新国立劇場通いの中でも特筆大書すべき記念碑的な地位を占める公演でしたので、この一文を認め(したため)なければこのブログを始めた意味が無いと考えました。
記念碑的と言うのは、「創立24年を経て新国立劇場は(そのオペラ部門は)ついに『我らの劇場』、『我らのオペラ小屋』になった!」という感激をもたらした公演であったという意味においてです。
今回のワルキューレは、ご存じの通り、当初は前オペラ部門芸術監督飯守泰次郎さんがフリーの立場で振る初めての新国のワーグナー作品として、出演予定であった欧米の素晴らしい歌手達の顔触れと相まって、大きな期待を集めていました。無論私もワクワクして、めくるめく飯守/ワーグナー・ワールドを心待ちにしていました。(ここで脱線しますが、飯守さんが芸術監督在任時の聴衆には、まことに心ないアンチ飯守派が少なくとも数名いました。彼が振ると、出来不出来に拘わらず必ずブーを浴びせるのです。何と不見識なことかと思っていたら、ある公演でその数名が、私の横の1人おいた席からずらっと並んで座っていました・・・無論それがその連中であるということは終演後に初めて分かったのですけれど。彼ら/彼女らは、カーテンコールで指揮者が登壇すると、「そろそろブーをかまそうか?」と声に出して言い、一斉に「ブー」を浴びせ始めました。そして、仲間内でゲラゲラとひどく下卑た調子で笑い転げるのです。その公演は決して水準の低いものではなく、私には立派な演奏に聞こえましたから、ひどく腹が立ちましたが、法律家魂が頭をもたげ、言論の自由は尊重しなければならないと私自身を説得するのです。やむを得ず、しばらくの間その暴挙を耐え忍びました。連中はブーをしばらくの間楽しんだ後、カーテンコールの続く中、笑い交わしながら騒がしく退出していきました。何故飯守さんがそういう連中の餌食になっていたのかは謎ですが、立派な業績を残されたのにお可哀想であったと、今でも同情を禁じ得ません。オペラハウスというのは元来そういう娯楽場で、半可通の独善的な攻撃にも不動心で立ち向かえる指揮者でなければ生き延びられない所だということは、マーラーの例を持ち出すまでもなく頭では分かっているのですけれど。いずれにしても、その飯守さんが肩の荷を下ろしてフリーの立場で振るワルキューレに期待しない訳にはいきませんでした。)
ところが、ご存じの通り、飯守さんは体調不良で急遽降板され、コロナ禍のせいで欧米の歌手達も揃って来日が不可能になりました。その窮状を救ったのが、現オペラ部門芸術監督である大野さんと日本人歌手達、そして後述する新国オペラパレス正規プログラム初登場の指揮者城谷正博さん。
当初やはり「楽」が良いだろうと考えて、最終日3月23日のチケットを買っていた我々夫婦は、指揮者が交代し、しかも最終日は無名の(失礼!)城谷さんという人になると知って激しく落胆(ますます失礼!!)し、慌てて大野さんの初日(3月11日)を追加で押さえました。初日を選択したのは、ジークムントを1幕と2/3幕とで二人のテノール(村上さんと秋谷さん)が歌い分けるという前代未聞の試みに恐れをなし、これは全曲を通して歌えるテノールがいない(日本にいないかどうかは別として、この期間をショートノーティスで押さえられるテノールがいない)という大野さんの判断によるものだろうと想像し、二人の歌手の歌い分けで我慢しなければならないとしたらまだ声が疲れていない初日が無難であろうとの判断によるものでした。この判断は一面で当たっていなくもなかったのですが、他方、誤りであったとも言えます。その詳細は後述します。
そうこうするうちに、賛助会員向け招待券として、20日(大野さんが指揮する4回のうちの最終回)のチケットも新国から送られてきました。これで我々夫婦は、初日、大野さんの最終日、そして城谷さんが振る千秋楽の合計3回を聴きに行くことになりました。
初日の直前に大野さんがユーチューブにアップしたのは、アッバス版なる「管弦楽縮小版」の使用についての解説。そういう版があるとは全く知らなかった私は、この解説から実に有益な情報を得ることができました。巨大な編成を小さくし、木管はそれぞれの2番奏者が持ち替えで対応。弦も12型に縮小するが、管楽器縮小(とワーグナーチューバの割愛!)を補うべくコンバスは5本。おまけに大野さんはリハの過程でいくつかの楽器に音を追加するといった工夫も凝らした由。新国ピットに入ったノットの手兵東響が、大野さんの棒にどう応えるか、歌手の大幅入れ替えで萎えかけていた気持ちが一挙に前向きなものに変わり始めた瞬間です。
そして迎えた初日。私はあまりの感激に、最初の幕間と終演後の二度に亘って友人達にその模様をメールで伝えました。
スケールが大きい代わりにやや茫洋としたところのある飯守さん(悪口ではありません。彼が振るドイツロマン派は、ドイツの深い森の匂いがします。)と比べて、大野さんの棒がどれだけ俊敏・精密で、しかも燃え上がる情熱を描き尽くしていたことか。しかし、私の最大の驚きは、日本人歌手達の大活躍でした。冒頭から、村上ジークムントと小林ジークリンデの素晴らしさに驚倒。2人とも短期間の準備とは思えない仕上がりで、村上さんのヘルデンというにはやや細いものの輝かしいアクートの魅力と、小林さんの思慮に満ちていながら秘めた情熱を感じさせる深い声と演技。この2人が結ばれるのは必然であったと、声と演技の双方で感じさせる公演は滅多にありません。公平を期して書きますが、村上さんはあるフレーズで声がかすれてしまって、ハラハラドキドキさせました。半可通は、恐らくここを先途と騒ぎ立てるでしょう。しかし、私は思ったのです。指輪4作の中で、奸計も裏切りもあくどい策略も登場しない唯一の作品であるワルキューレ。その中で傷つき、倒れそうになりながらも、運命にあらがって健気に真っ直ぐに生き抜こうとするジークムントとジークリンデ。その2人が余裕綽々の美声で良いのかと。追い詰められ、肉体的にも精神的にも極限状況にある人間の魂の叫びが、余裕綽々である筈はないではないかと。これはやや贔屓の引き倒し的議論であることは無論承知しています。しかし、この2人の迫真の歌唱と演技には(そして、後述する秋谷ジークムントにも)、こう言ってみたくなる何かが確かにありました。先走りますが、20日に聞いた際の村上ジークムントの、1幕の幕切れにおける「ヴェルズングの血に栄えあれ」の絶唱には、心の底から感動し、目頭が熱くなりました。間もなくそのヴェルズング族を誕生させた父その人から死に定められる運命とも知らずに、その血を称える喜びの歌の純粋さの、何と無残であることか。しかし、本人のあずかり知らぬそういったその後の展開を離れて、くびきから逃れる妻=妹との再会と命をかけた逃避行の現世を超越した喜び、という観点だけから見ても、実に感動的な絶唱でした。ここで尚「ヘルデンテノールにはほど遠い声量だ」と言うような批判を展開する人と私は、音楽に求めるものが決定的に違うのだとだけ言っておきます。
初日の2幕では、藤村さんの完璧な歌唱コントロールに恐れ入りました。ラデツキーのヴォータンも流石の出来で、この2人の登場によって、一気にヨーロッパの最高水準を思い知らされますが、そこで我ながら驚いたのは、1幕のドラマが全く色あせなかったこと、つまり村上・小林コンビの歌唱・演技が藤村・ラデツキーの歌唱・演技と全く同水準にあるように思われたことでした。そして、満を持して登場した秋谷ジークムントの持続するエネルギーと、チャーミングでここという時の迫力も備えた池田ブリュンヒルデに、またもや刮目することになるのです。
秋谷さんは、2人一役のハンディをものともせず、この演出におけるこの役が長い稽古で体の隅々にまで入っているとでも言うような入魂の歌唱であり演技でした。特に、ブリュンヒルデの死の告知に対して、ジークリンデが一緒に行けないなら自分はヴァルハラに行かないと決然と言い放つあたりの見事さは、これまでに見聴きしたあらゆるジークムントに勝るとも劣らない出来で、感動に震えました。池田さんの素晴らしさは、3幕で全開となるのですが、2幕でも感情表現のみならず、それを可能にする持続的な喉のコントロールが見事。節制+規律+訓練で完璧なフォルムを保ち続ける藤村さんと並んで聴いても、全く聴き劣りしないのですから、驚く他はありません。
少し場面は戻りますが、2幕のヴォータンとフリッカの対話ないし言い争いは、いつも長いなと思うのです。素晴らしい場面だと思いつつ、どこかで長いなと冷めた見方をする自分に気付くということの繰り返しでした。しかし、今回は、むしろ短く感じられたことに驚きました。大野さんの手腕でしょう。総じて、先へ先へと進める力に満ち、せわしなくは絶対にならないのに音楽が一瞬も停滞せず、ワーグナー特有の「うねり」を透明な音で紡ぎ出す離れ業。見事というも愚かなオケの統率ぶりでしたし、どのパートも汚い音をほとんど出さない東響の熱演も絶賛に値します。ワーグナーチューバの割愛も楽器編成の縮小も、意識的に耳を澄ませば勿論分かるのですが、夢中になってワーグナーの世界を指揮者、歌手、オケと一緒に歩む私には、全くと言って良いほど気になりませんでした。
初日の3幕では、小林ジークリンデの、身重であることをブリュンヒルデから告げられた際の歌唱と演技の素晴らしさに息を吞みました。この人、イタリアオペラ界ではスターなのだそうです(知らなくてごめんなさい。)が、ワーグナーについては初心者なのだとか。城谷さんは「わの会」という組織を主催していて、池田さんはその会員として活躍しているようですが、その池田さんが小林さんをワーグナーの世界に引きずり込んだのだそうです。このあたりの事情について興味のある方は、ググってご覧になればいろいろな情報が出てきます。とにかく名ジークリンデ誕生のきっかけを作った城谷さんと池田さんに、我々は感謝しなければなりません。
3幕後半では、勿論ヴォータンとブリュンヒルデ父娘の対話が聴き物です。指輪第2夜、第3夜の流れを予告し、決定づける場面であり、いわば永遠が一瞬に凝縮すると同時に一瞬が永遠に拡散する、そういった場面だと言えます。そう書きながらも不明を恥じつつ告白しますと、私はいつもこの父娘の対話は、2幕のヴォータン・フリッカの場面同様、いやそれ以上に長すぎると思ってきました。どんな名演で見ても聴いても、聴き手としての緊張が完全には持続しないのです。しかし、この日は違いました。もっともっと聴いていたいと感じたということは、文字通り永遠が一瞬に転じ、一瞬が永遠に転じたということでしょう。これは単なるレトリックではありません。そうでなければ、幕が下りる際に、もう終わってしまうのか、これは永遠の世界で私(大武)もそこで生きているのではないのか、と感じたことの説明は付きません。指環とは、永遠と瞬間をめぐる物語だというのが私の仮説です。
さて、二度目、つまり3月20日の公演については、11日に準じます。大野さんの指揮がますます雄弁になり、大きなうねりをより強く感じさせたことは特筆大書したいと思います。他方で、村上ジームムントの1幕の幕切れは、残念ながら声が持たず、やや腰砕けの憾みがありました(そこまで擁護すると、文字通り贔屓の引き倒しになります。)が、全体としては、回を重ねただけのことはある高水準の出来でした。小林ジークリンデの素晴らしさは、本当に絶賛に値します。そして、池田ブリュンヒルデも、これまでに見たことの無い可愛らしいブリュンヒルデ像を描いて、間然とするところがありませんでした。これなら、戦乙女でありながらパパ・ヴォータンの寵愛を一身に受ける存在であるのは当然と思えましたし、幕切れで、ヴォータンに媚びるのではなく自らの主張を堂々と述べることによって我が儘と言えるような措置を執らせることに成功したのも宣なるかな、と聴き手をして納得させるものがありました。
しかし、最大の驚きは、3月23日の楽に待っていました。城谷さんの指揮です。
何しろ一度この公演を聴いただけですから、針小棒大の愚を犯すことになってもいけません。従って、筆を控えたいとは思いますが、大野さんが4回振って劇場を沸かせた後に登場するというのは大変なプレッシャーだったろうと思います。そのプレッシャーに打ち勝って、オケを楽々とドライブし(特に2幕以降)、音のドラマを作り上げた才能には驚嘆します。ワーグナー演奏の新たな名指揮者誕生の瞬間を見届けることが出来た、と胸が熱くなりました。歌手陣も、大野さんのときと全く同じように全身全霊で歌い演じるのです。理屈では指揮者が代わってもベストを付くさなればならないのは当然だと考えても、いざ実際に指揮者が代わり、しかもその指揮者が知名度において劣る人であった場合に、侮るような気持ちを持たずとも、実力の差に気付いたらそれは確実に歌唱に演技に表れます。オペラというのはそういう世界です。特に、日頃城谷さんの薫陶を受けている池田さんや、城谷・池田コンビによってワーグナーの世界に引きずり込まれた小林さんのような人たちであればともかく、藤村・ラデツキー両氏が城谷さんの指揮に安んじて乗りつつ、その持てる力を全開しているように見え/聞えたのは、いかに城谷さんのこの晩の指揮が素晴らしかったかを物語っています。
事情通から教えてもらったところによれば、大野さんはシェフを務めるバルセロナに飛ばなければならないため千秋楽を振ることができず、千秋楽だけ城谷さんに任せたということのようですが、この抜擢は大野さんが城谷さんに寄せる信頼と期待の大きさを示ししたと言えます。渦中の栗を拾って新国を救った大野さんと、千秋楽での抜擢に応えて見事に代役の代役を務め上げ、鮮烈な新国正規オペラ・デビューを飾った城谷さんに、満腔のブラヴォーを捧げます。(飯守さんが大野さんに代わったというニュースが流れたその時点で、既に千秋楽は城谷さんと決まっていましたから、「代役の代役」というのは厳密には不正確なのですが、実際の事の有り様としては正にそういうことだったろうと思います。)
ようやく冒頭の感想にたどり着きました。創立24年を経て新国立劇場は(そのオペラ部門は)ついに『我らの劇場』、『我らのオペラ小屋』になった!
日本人の素晴らしい歌手達を初めて知ったという意味は大きいですが、この感想はそのことだけを言っているのではありません。指揮者の突然の交代、主要キャストの来日断念、コロナによるオケ編成の縮小の必要性、そういった未曾有の危機に対応できる「力」が、日本のオペラ界にはあった、そして結果として事前の予想を遙かに上回る見事な公演を予定通りにこなすことができた、という感慨が、「我らの劇場」、「我らのオペラ小屋」がついに誕生したという思いを抱かせたのです。
城谷さんは今後、新国で必ずまたワーグナーを(そして、彼が他に何を得意とするのか知りませんが、望むらくは他のレパートリーも)振ってくれるでしょうし、小林さんは、ドン・カルロでもエリザベッタ役で登場します。楽しみですね。
本稿を書き渋っている間に、「我らのオペラ小屋」との感を更に強める経験をしました。ついこの間の「夜鳴きうぐいす」と「イオランタ」のダブル・ビル公演です。イオランタを歌った大隅智佳子さんの「夏の夜の夢」のヘレナに続く名演に、ノックアウトされました。世界水準の声と知性と気品溢れる演技。ほれぼれします。これまであまり知らなかったこのオペラが、私にとってはチャイコフスキーのオペラの中で最も素晴らしいもののように思えたのは、ひとえに高関さんの指揮と大隅さんの歌唱のおかげでしょう。東フィルの金管の節度を失わない輝かしさにも良い意味でビックリさせられました。ああ、我らのオペラ小屋!と私は独りごちたのでした。(公演全体としては声楽陣の一部に不満が残りましたが、「イオランタ」の総合的感銘度の高さを減じるものではありませんでした。「夜鳴きうぐいす」の方は、それに比べれば不満点は多々ありました。もっとも、これはクルレンツィスとデセイの超絶的名演(なんという顔合わせでしょう!)のDVDにこちらがスポルされていたからそう感じたのかもしれません。このダブル・ビルの着想自体、何と素晴らしくも大胆であることか。この着想が大野さんのものであったことを、私は確信しています。)
誤解のないように付け加えますが、「我らのオペラ小屋」というのは、偏狭な愛国精神に基づくものなどではなく、日本人歌手と日本人指揮者だけで上演すべきだといったような馬鹿げた論陣を張るものでも勿論ありません。自国民だけを起用するなどというオペラ小屋は、世界のどこにも存在しません。例えば同じ指環でも、ワルキューレはうまく行ったが、ジークフリートや神々の黄昏が、日本人歌手を中心とするキャストで、同じ水準での上演が可能なのか。そういう努力を続けてこられた二期会、藤原歌劇団、琵琶湖オペラ等々の関係者には申し訳ない物言いになってしまいますが、ジークフリート役一つを取って見ても、恐れを知らぬ天衣無縫・天下無双の若者こそ、文字通り余裕綽々の破天荒な歌い振りでなければなりません。そういう歌手が果たして日本にいるかどうか。このこと一つを取って見ても、キャストの国籍が大事だなどと申す積もりの無いことはお分かり頂けるでしょう。
そうではなく、オペラ劇場として、我々地域の愛好家(その中には外国人もおられるでしょう。)に支えられ、愛され、一つの有機体として機能し、今回のような未曾有の危機をも芸術監督の見事なリーダシップの下で一丸となって乗り切ることができる、そういう劇場こそが「我らのオペラ小屋」だと言いたいのです。
来季のプログラムも実に素晴らしいもので、いよいよ大野さんが企画においてもキャストの人選においてもその持てる力とリーダーシップを全面的に発揮し始めたという感を強く持ちます。皆さんも「我らのオペラ小屋」に是非ともお運びください。そしてご一緒に新国を支えようではありませんか。
Categories:未分類



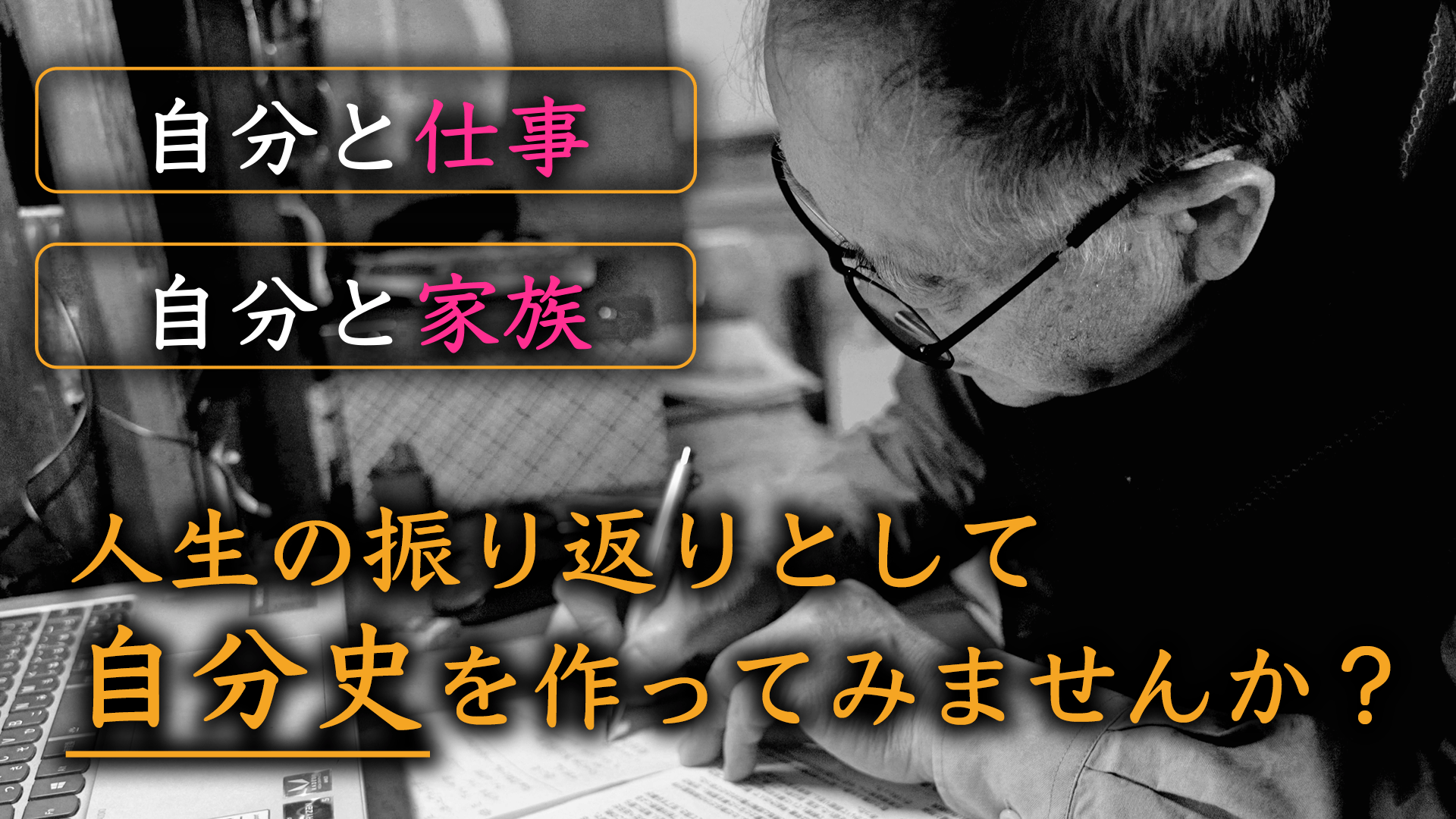


東 賢太郎
4/16/2021 | 10:22 PM Permalink
大武さんのワーグナー愛と感動がストレートに伝わってきて、読みながら感動してしまいました。新国でワルキューレがあるのは知っていて大いに関心がありましたが、なるほど素晴らしいものだったのですね。昨年来劇場に1度も足をはこんでおりませんし今後も難しそうですのでこうしてご感想を拝見するのはとても楽しみです。次もよろしくお願いします。
大武 和夫
4/20/2021 | 12:36 PM Permalink
東さん
実は私のワーグナー愛は複雑で、モーツァルト、ヤナーチェク、そしてRシュトラウスのオペラに対する絶対的かつ無条件の愛とは、だいぶ様相を異にしています。嫌だなあ、ウンザリだという面も多々あり、端的に嫌いなオペラもあります。しかし、指環といくつかの楽劇には、どうにも抗いがたい魅力を感じます。最近は音楽会場、オペラ会場に足を運ぶ回数が増えてコロナ以前をしのぐ勢いになっており、家内には苦言を呈されています。生演奏体験を求める溜りに溜まった欲求が、はけ口を求めて噴出しているのでしょう。河村尚子さんの感動的な三つの演奏会を聴き終えた現在、当方の最大の関心は、来月4回聴きに行く予定のジョナサン・ノットが、果たして来日できるかどうかです。(スイス・ロマンドでクラスターが起きた由で、その後の情報を憂慮しながら待っています。)コロナが収束し、いずれ東さんと新国や音楽ホールでお目にかかる日を楽しみにしています。
Hiroshi Noguchi
4/18/2021 | 10:37 AM Permalink
コロナ禍のおかげで、いろいろなところで日本人の演奏家の実力が再認識されたとは喧伝されていて良かったと思っております。ワグナーのオペラのような総合芸術は特に一人が突出していても良い演奏にはなりませんので、本当に良かったと思います。
一部の若いピアニストは、これまでとは違ったルートでチケットの販売をして、常に売り切れ状態というのも本当に嬉しいことです。最近またビッグネームを来日させる動きがあって、それはそれで良いのですが、コロナで生まれた新しい潮流が育っていくことを祈っています。是非このコロナを生き延びて様々な演奏会の評を上げて戴きたいと思います。
大武 和夫
4/20/2021 | 1:07 PM Permalink
野口様
コメントのご投稿ありがとうございました。いつもお読みくださり、感謝しております。
はい、コロナはむろん厄災ですが、おっしゃるように、他方で若手日本人演奏家に活躍の場を与えてもおりますね。指揮者で言えば、目覚ましいところでは、今をときめく鈴木優人さん(高校の後輩です。)、原田慶太楼さんなど。若手ではありませんが、パパ鈴木(雅明)さんもモダン・オケに不動の地位を確立しましたし、高関さん、下野さん、飯森さんの活躍にも目を見張るものがあります。私が好きなピアノで言えば、何といっても藤田真央さん。八面六臂の大活躍で、むやみに多い演奏機会のチケットがことごとく発売即売り切れというのですから、恐れ入ります。反田恭平さんも全く同様。でも、そういうビッグネームではない若手演奏家も、いろいろに工夫して発信しているのは頼もしいことです。知人の娘さん(パリで学んだ、それはそれは素敵なピアニストです。)など、YouTubeでの活躍ぶりもさることながら、小さい演奏機会を捉えて実に良い演奏を披露しておられます。私事にわたって恐縮ですが、次女が取り組んでいる豪州のちっぽけなオペラ・カンパニーの新作オペラも、親バカにはありがたいことに、ユーチューブでのライブストリーミングが予定されております。配信という媒体は、ベルリンフィルの例を挙げるまでもなく、メジャーな世界ではかなりの期間続けられてきましたが、それがいよいよ無名・新進の演奏家レベルでも手軽に行えることになったということの意味は、実に大きいと思います。
このような若手の発信機会の拡充は、コロナのもたらした二つだけの良いことの一つだと思っています。(もう一つは、人と接触することを何とも思わないアジア的感性が、ソーシャル・ディスタンシング((フィジカル・ディスタンシング)政策(?)によって、根本的に変わりつつあることです。見知らぬ他人との物理的接触を忌み嫌う私は、コロナ収束とともにディスタンシング文化がどこかに行ってしまわないよう願うばかりです。)
別に頂戴したご連絡では、野口さんは若手の演奏機会のプロデュースもなさっているようですね。大きな意義のあるお取組みに心から敬意を表します。
なお、ここで宣言してしまいますが、さきほど東さんのコメントへのご返事にお書きした河村尚子さんの三つの演奏会について、今週中には投稿するつもりでおります。またご笑覧頂ければ幸いです。
、