『職業としての小説家』 読後感
2017 JUL 9 11:11:54 am by 西 牟呂雄

さる先輩に『これ読んでみろよ』と勧められ、躊躇したが一気に読んだ。
躊躇したのは、僕は小説をほとんど読まず、村上春樹は一回も読んだ事がなかったからだ。何だか題名からして難解そうだったし。
ところがこの本は講演原稿のように書いたもので(あとがきを読むまで講演だと思っていた)出だしは苦戦したが面白かった。
いや、一回もというのは正確ではなく、月間文芸春秋に書き下ろした作品を見て以下のマヌケな感想を書いている。
畏れ多いことだ。
この人は相当緻密な人だと思った。とにかく相当な量の小説を、どうやら原書で読んでいる、それも高校生くらいから。
そしてまず『小説を書くのはあまり頭の切れる人には向いてない』と説く。初めはこの言い方に随分と違和感を感じた。よくある反語的な言い回しで『自分が頭はいいが』といった方に持っていきそうだ、と警戒した。だがそれは違って、せっかち、とか軽率な人には向いていない、という話だった。
作中の表現を借りれば『なるべく回りくどい』方法を好んでそのプロセスをむしろ楽しむふうであり、『物事をそう簡単には結論付けない』ことを心がけている。そのやり方が長い作家生活を続けていけるコツのようなものと言っている。なるほど僕はマヌケ・ブログを面白がって書いているが、けったいな思い付きの小説めいた連作は失敗してほとんど読まれない。
それはある意味当然で、現役時代の口癖は『オレに哲学もクソもない。能率とスピードにしか興味がない』と喚き散らして部下達から嫌われていた。小説が書けないわけだ。
学生結婚をして、ジャズ屋を長くやっていたという点。バド・パウエルとかビル・エヴァンス、ハービーハンコックなんかをガンガンかける(レコード時代)お店と聞くと、なかなかヤルなと思わせられる。もっと若い頃はビーチ・ボーイズとビートルズだそうだ。これなんかも取っ掛かりがローリング・ストーンズでその後YAZAWAだった僕とは格が違う。ボブ・ディランの記述もないが、音感的に単純すぎるので聞く気にならなかったのだろう。
衝撃的なのは、初めの方にガラガラの神宮球場でヤクルトー広島の開幕戦を見ていた時の話が出てくる。初回のヤクルトの二塁打を見て、突然小説がかけるかも知れない、という感覚に陥ったとある。以下表現を引用する。
『それは空から何かがひらひらとゆっくり落ちてきて、それを両手でうまく受け止められたような気分でした』
私事で恐縮だが、僕はブログの読者の方は御存知の日本ハム・ファイターズのファンだ。それも昨年の優勝・大谷フィーバーからのミーハーではなく、弱い弱い東京ドーム時代のそのまた前からのファンである。パ・リーグだからヤクルトよりも人気のないチームだった。
学生時代の恩師が球団関係者の義弟だったので、ノベルティーのチケットがゼミで大量に出回り、東京ドーム行きたさにガラガラの内野スタンドに行った。
村上春樹は1978年にその感覚を得たというから、ほぼ同時期に弱小球団の試合を見ていたことになる。
それなのにヤジを飛ばす事に夢中になっていた僕にはひらひら落ちてくるものなどなかった。ドーム球場だったから空から降ってこなかったのだろう。やはり作家になる人は違うのだな。
中学・高校のころの話も書いているが、学校というものが苦手だったとのことで、これは僕もいつの学年でも居心地は実に悪かった。しかし唸らされたのは、表面的には僕と同じような事をして遊んでいたらしいが、勉強を怠けて遊び呆けているという意識がなかった、と言っている。恐らく英語の小説を読んだり音楽を聴いたりすることに相当な濃密な時間を使ったのだろう。僕程度の不良だと”遊び呆けている”自覚がしばしば襲ってきて、これではヤバイくらいのことは思ってしまった。酒の味を覚えるのも早かったのがまずかったのかもしれない。
その後はプロの小説家として、極めてストイックに歩みを進める。驚いたのは長編小説を何回も書き直すらしい。ノリの悪い”章”はまるごと書き換える。或いは英語で書いて(たいしたもんだ)それを日本語に起こすといったことまで試している。
まるで大きな彫刻を掘り進めるように、規則正しく体まで鍛えて、尚且つ書き始めるときはウキウキして『充実感は何ものにも変えがたい』そうだ。
しかも”長編”を書く時には主人公に語りかけられるように筆を進めるとある。ということは小説の終わり方を考えずにスタートしエンドに持っていく(読んでないからわからないけど)自動書記のように(それこそ天啓のようにひらひらと)作品を紡いでいくのだろうか。
これも初めて知ったが、二回芥川賞にノミネートされて受賞しなかった。そしてそれがその後の作家活動に何の関係もないと言い、どうやら本当に関係ない。さらに噂されるように、この調子でノーベル文学賞を取っても文筆活動には全く影響しないと思われる。もっともボブ・ディランと違って授賞式くらいは行くだろうが。
ここまで言われるとなにやら”長編小説”なるものを書いてみたくなるではないか。著者も最後の方で言っている。
『物語というのはつまり人の魂の奥底にあるものです』
多少なりとも僕にも心の奥の喜怒哀楽はあるのだから。
しかし悲しい事に上梓されたこの本によれば僕はその資質を全く持ち合わせていない。だが最後の奥の手はあるような気がする。
それは例えば『長編小説』という題名のアホ・ブログを書けばいいのだ。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:言葉


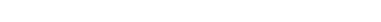
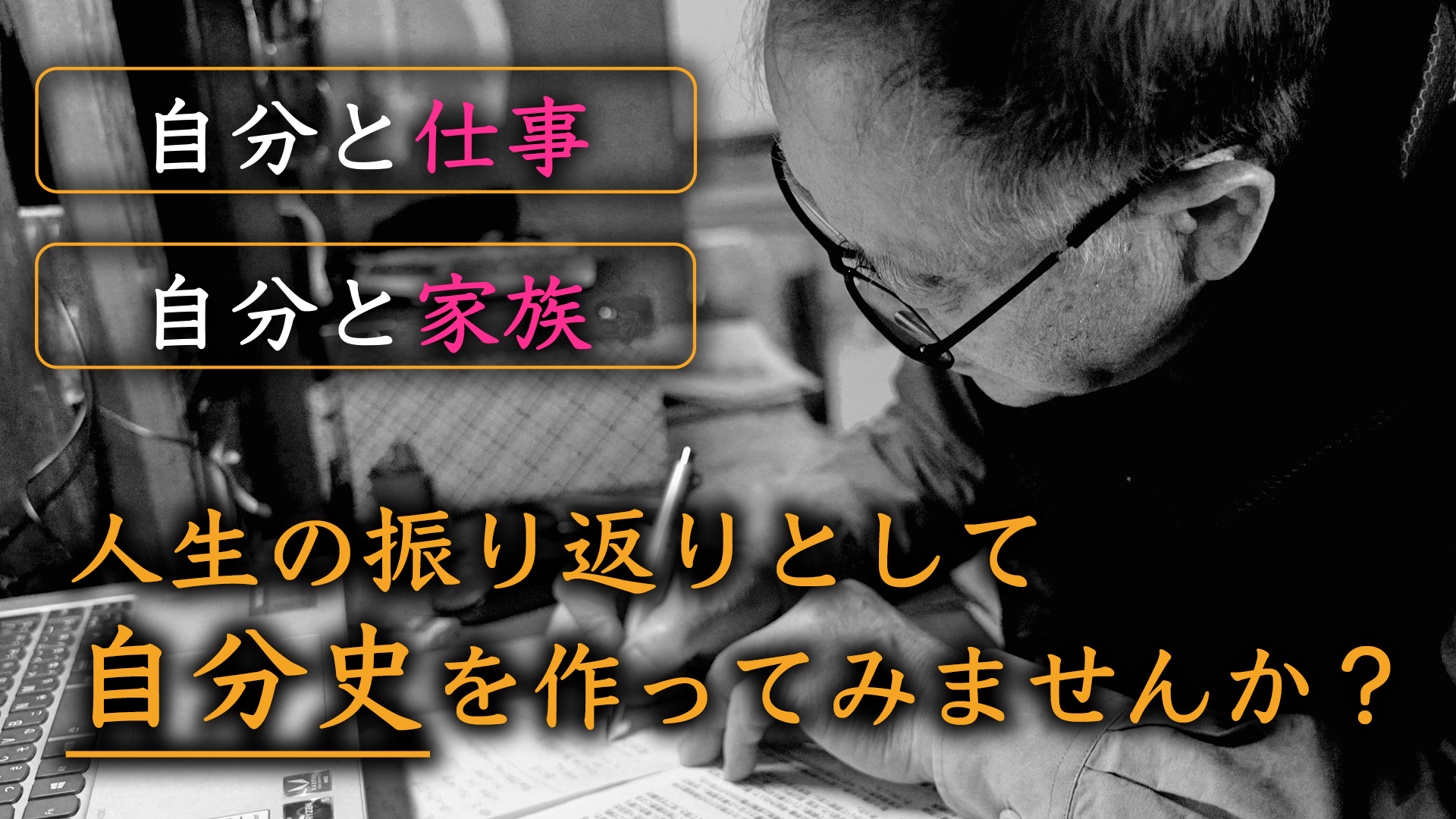


Trackbacks & Pingbacks
[…] 『職業としての小説家』 読後感 […]