グローバル・シテイ・ヘイジョゥ
2020 FEB 20 7:07:39 am by 西 牟呂雄

奈良の都にインド人・ベトナム人・ペルシャ人・中国人がいる。これ、今日の話ではない。
今から千三百年前の話。東大寺大仏殿の開眼供養法会の導師、婆羅門僧正はインド人のボーディセーナ。来日して菩提僊那(ぼだいせんな)を名乗った。
この時代は第十次遣唐使が派遣され、彼らは洛陽で玄宗皇帝に謁見している。ひょっとすればかの安禄山や楊貴妃、私の好きな詩人の王維・李白・杜甫といった人達とニアミスしたかも知れない。洛陽は現在のニューヨークに当たるだろうから、当時の国力から考えて我が国も十分にグローバルに追いつこうとした。
第十次遣唐使は帰朝に当たって先に入唐していた吉備真備の他にかの菩提僊那とペルシャ人李密翳、ヴェトナム人仏哲、中国僧数名を連れて来た。この内ヴェトナム人仏哲は、現在のフエの出身であるが、遠路インドまで辿り付いて菩提僊那に師事し、共にヒマラヤを越えて入唐。その後師に従ってはるばる日本まで来た。
またペルシャ人李密翳はどうやってイランからやってきたのかは分からないが、個人的にはインドにいたペルシャ系の人物ではないかと思っている。クイーンのフレディ・マーキュリーや財閥のタタといったパールシーと呼ばれる連中のことである。パールシーがインドに到着するのは10世紀とされているが、ササーン朝ペルシャの滅亡はもっと早い(ただ、ササーン朝の王子ペーローズがその際に入唐している事実はある)。宗教はゾロアスター教でイスラムではない。
一行は聖武天皇に謁見し、大安寺で暮らしていた。興味深いのは、彼等はいったい何語で日常を過ごしていたのか、である。おそらくは彼等の共通言語である漢語を使ったのだろう。現代では日本人と韓国人がニューヨークで英語でコミニュケートするようなものだ。
ところで、我が国ではお経などは呉音で読まれていたのじゃないかという仮説を立ててみた。一方唐の標準語は漢音。
和尚 (漢音)おしょう (呉音)わじょう
利益 (漢音)りえき (呉音)りやく
食堂 (漢音)しょくどう(呉音)じきどう
阿弥陀経(漢音)あみたけい(呉音)あみだきょう
と言った具合だ。大雑把に言って宮中は漢音で民間は呉音なのだろう。
お経は漢文ではあるが、その読み方が違っていたのだ。そのため一行と共にやって来た袁晋卿なる唐人は通訳だったのではないか。この人は飛び抜けて若く(10代と推定されている)後に朝廷の音博士になった。
ところで最初の仏教伝来は半島を経由したが、その時の読み方はわからない。白村江の戦いでコテンコテンに負けて百済系を中心とした多くの難民が来た後は、こちらのルートはは出てこなくなる。多少の危険はあるものの、航海技術の発達により半島経由の陸路を行くより早かったのだろう。地図を見れば一目瞭然だが、半島の付根は万里の長城の外側で洛陽まではかなりある。従って我が国の読み方は呉音が一般的だったと想像すると、遣唐使による漢音の読み方はモダンというかアカデミックに響いたのではないか。
話は変わるが、大陸から渡ってきた人達の中に女性はいたのだろうか。
唐は王族の李氏が鮮卑系であると言われ、西域に至る大帝国でもあった。従って胡族の流入とともに習慣も多く受け入れている。そのせいかどうか女性の地位が際立って高く、恋愛なども開放的だった。
酒楼においてはソグド人・ペルシャ人の女性が接待したという。
そういった女性が海を越えて渡って来ることはなかっただろうか。正式な遣唐使でなくとも女性を伴って来日したグループはいて、その中にペルシャ系の女性はいたのではないか。八代亜紀さんは九州出身だが、あの容貌はその血を引いているに違いない、と睨んでいる。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:インド


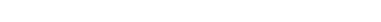
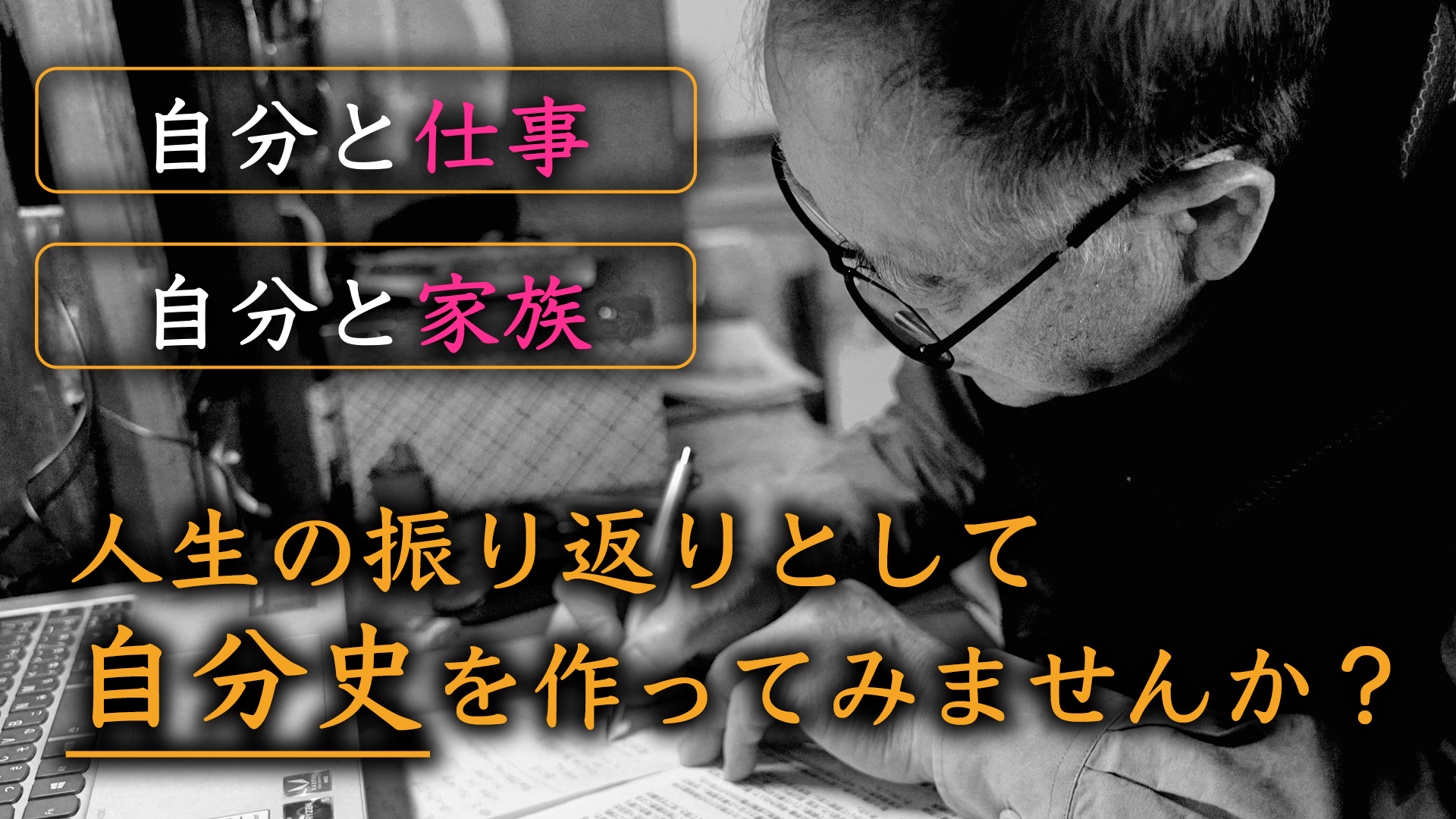


東 賢太郎
2/20/2020 | Permalink
洛陽に行って白馬寺の斉雲塔を見あげたら、なぜか西遊記がぱっと心に浮かんできたのを覚えてる。あれはエキゾティックだ、いわゆる中国っていう感じじゃなくインド人、ペルシャ人がいておかしくないコスモポリタンのムードだ。あれを小野妹子や空海が見たのも不思議な気分だ。その光景のなかに八代亜紀がいたっていいね、おもしろい。
西 牟呂雄
2/23/2022 | Permalink
現在日経に連載されている安部龍太郎の『ふりさけ見れば』を愛読している。題名の通り阿倍仲麻呂が主人公。物語は吉備真備が帰国してきた中臣名代を出迎える所だが、その一行に菩提僊那(ぼだいせんな)、仏哲、李密翳が登場している。また、拙ブログでは『中国僧数名』としたが、それは戒律師の道璿(どうせん)と唐楽演奏家の皇甫東朝(こうほとうちょう)であることが記された。さすがにプロの作家は違う。
皇甫東朝は仏教儀礼の唐楽を伝授したが、大陸では珍しい二文字の姓で半島、ベトナムにも見られる。日本にも半島出身者でこの苗字の人がいるらしい。水滸伝にも梁山泊に108番目に入山する皇甫端(こうほ たん)というのが出て来る。
今後、安部龍太郎氏がどう描くのか楽しみである。
西 牟呂雄
1/11/2024 | Permalink
八代亜紀さんが亡くなってしまった。心から哀悼の意を捧げます。
八代亜紀=ペルシャ系の血筋、という壮大な仮説を楽しんでいたが、本人に聞いてもラチがあかなかったろう。
近頃はジャズも手掛けておられた由、一度ライヴを聞いてみたかったなぁ。