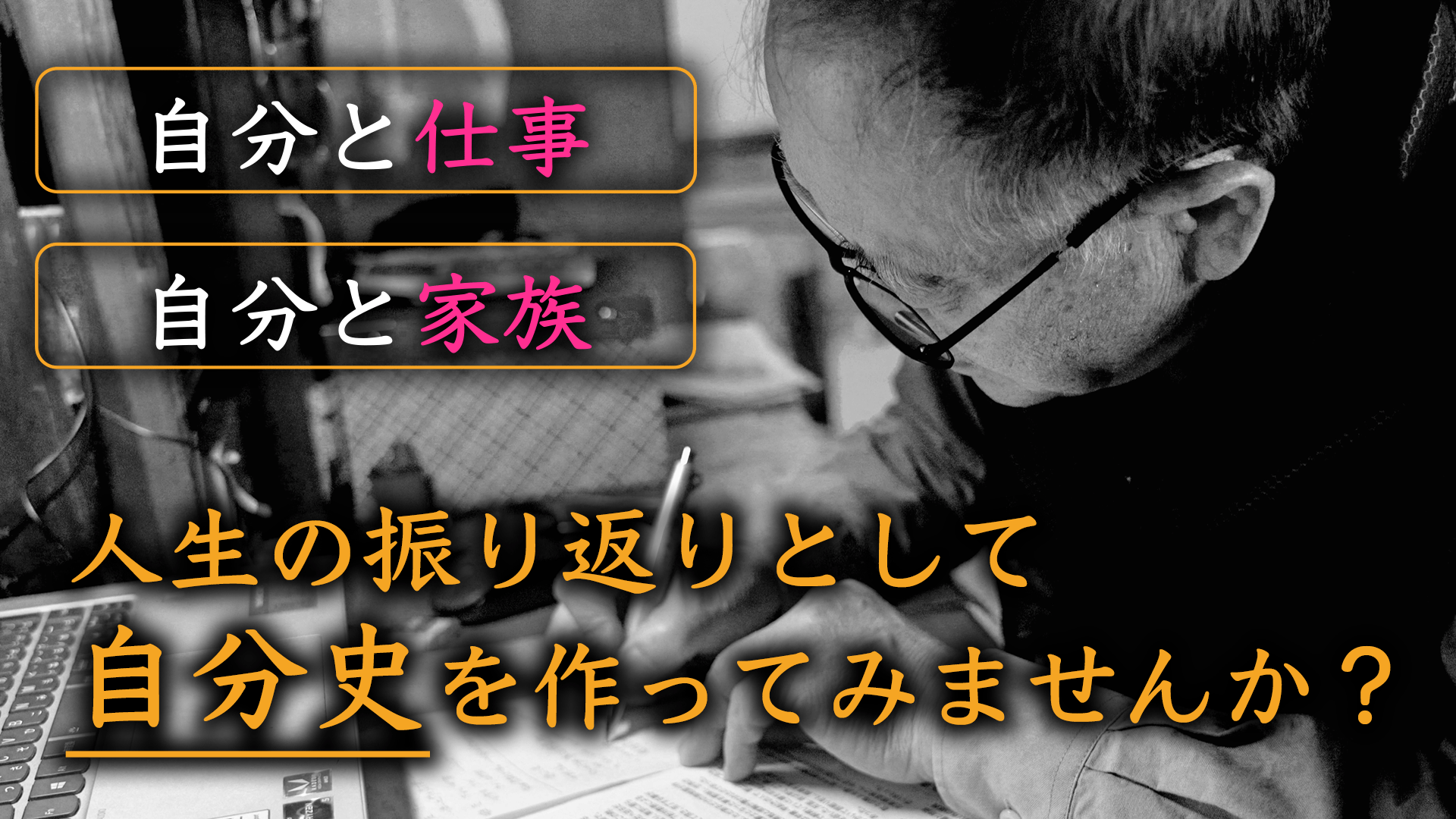耳に聴こえてきた音楽 早期の「がん」になって
2017 OCT 30 12:12:02 pm by 野村 和寿

曲がりなりにも、長いこと出版社で編集者の端くれの生活だったので、この体験をなるだけ忠実に記しておこうと思った。10月初旬、大病院の消化器内科の担当お医者様は、外来の診察で、開口一番、「早期の胃がん」ですと私に告げた。とても無表情だったのが、かえって信憑性を増した感じだった。外来からの帰宅途中、いつもより遠回りして、きっとまだ気持ちの整理がつかず、端からは相当にとぼとぼと歩いていたようにも思える。昼間の住宅街を歩いていると、耳にウォークマンみたいに、聴こえてきたのは、プッチーニの歌劇『マノン・レスコー』の第3幕の冒頭で鳴る「間奏曲(インテルメッゾ)」。たしかカラヤンの演奏のもの。
劇的にヒロイン・マノンの行く末を暗示し、舞台はヨーロッパから米国にまで飛んでしまうという、ロマンチックすぎるオペラ。たしか1986年に、時ならぬ大雪で交通が麻痺した最中のNHKホールで、ウィーンの国立歌劇場が『マノン・レスコー』強行上演をしたときに、聴いたものも同じ曲で、それがあまりにも、たたみかけるような情熱的なシノーポリの指揮だったものだからそれが耳に残っていたのだろう。
(プッチーニ歌劇『マノン・レスコー』フレーニ(マノン) ドヴォルスキ(騎士デ・グリュー) オットー・シェンク演出 シノーポリ指揮ウィーン国立歌劇場管弦楽団 NHKホール 1986年4月3日)下記の音源は、同じ演者のもの。冒頭に3幕が始まる前の情熱的な間奏曲(インテルメッゾ)が収録されている。
続いて聴こえてきたのは、プッチーニの悲劇的なオペラ『トスカ』最終幕、舞台はローマに今も残るサンタンジェロ城の場内で、トスカが歌うアリア。恋人であるカヴァラドッシにもう死んだふりをしなくていいのよ、と歌うところ。歌劇『トスカ』 第3幕「 待つということは、なんて長いことでしょう!」
Maria Callas “Come è lunga l`attesa” Tosca
実は恋人の画家カヴァラドッシはこの時点では、すでに銃殺隊の銃弾に倒れていて、息絶えていたのだったが。それを知らない歌姫トスカが歌う。
少々、一九五〇年代のオペラがまさにグランド・オペラだった、大時代がかった演技のマリア・カラスが耳にウォークマンも何もしていないのに飛び込んできた。それも聴こえてくる音は、いつもよりも『透明感』もあって、ノイズもなしにきわめて鮮明に。街を歩いていても、ずっと聴こえてくるオペラのアリア。
がんの告知前の体調では、少し気分が悪く、少し熱があり、胃が少しもたれ、お腹も少し痛かったのに、告知された後は、むしろ、それら「少し」が一旦停止の感あり。
小林一茶の句「目出度さもちゅう位なりおらが春 」をもじるならば、
「あちこちのいたさも ちゅう位なりおらが春」
気持ち悪さも、なにか普通の状態にもどったのに近く、むしろ、センシティブな分、頭が少しだけ聡明というか、鮮明になったような気分だ。
頭をもたげてくるのは、不思議にも、昔、懸案で解決しなかった、いろいろな問題だった。撮影のときの問題とか、企画がなかなか思い通りにいかなかったとか、その当時は、大問題だと思っていた問題が、次から次へと頭に湧いては消えていく。それらの問題は結局の所、全部うまくいかなかった問題ばかりだったのだが。
ぼくの耳から聴こえてくる「人間ウォークマン」は、ときと場所を選ばずに、いろいろな音楽がきわめてランダムに、聴こえてくるから不思議だった。
逆に言えばなんでこの曲がこんなに大事なときに聴こえてくるのかよくわからない。半信半疑だったともいえるだろう。続いて聴こえてきたのは、なんと「イギリス音楽」。ディーリアスやボーン=ウイリアムス、エルガー、ホルストなどのイギリス音楽。いつもは、イギリス音楽なんて・・・とあたかも小馬鹿にしていたように、ヘンリー・パーセルのあと、ハンデル(イギリス読みのヘンデル)があって、そのあとは、ダイレクトに、ブリテンまで「島国イギリスの音楽」なんてなかろうに・・・と思って、「高(たか)を括(くく)っていたというのに」イギリス音楽は、ホルストの「火星」や「木星」のように、メロディーがストレートに自分の内面に飛び込んでくるかのようなそんな気持ち。
まったく不思議な体験である。ディーリアス「春初めてのかっこうを聞いて」もそう。このまか不思議な曲は、たった一度、ロンドンで聴いたことがあるだけだというのに。動画は「夏の庭園で」という曲。
自然のなかで奏でているように。ヨーロッパ大陸の昔のようなたたずまいが、かえって島国であるイギリスに奇跡的にも残っているのとにているように。ディーリアスの音楽にもこの「不思議なたたずまい」を感じてしまう。上記youtubeは、ジョン・バルビローリのイギリスのハレ管弦楽団の演奏である。
別に特に田舎の景色のいいところをそぞろ歩いているわけでもなく単に街の住宅街をとぼとぼと歩いていただけなのに、これまた不思議だった。
ディーリアスは、なんだかんだと理屈がまったくなくて、ウイスキーをストレートで呑んだときのような、少し、重ったるいけれど、どこかすきっとくる気持ちに似ていた。まったく不思議だった。
ぼくの「人間ウォークマン」は、幻聴なのだろうか? どうして、こんな種類の音楽が予期せずに聴こえてくるのだろうか?それは、どうも自分が予期せずに、病気のなかでも、超有名な胃がんの患者になった、一種のヒロイズムにも似た不思議なマイナー意識を、どこかで、自分で自分を慰めるような、アドレナリンのような気持ちでもあったように思う。
こういうときは、いつもならば、「モーツァルト」とか聴きたくなったのだが、不思議にも「モーツァルト」は聴こえてこず、本当の機械のウォークマンでもって、イヤホンを自分の耳に挿入し、モーツァルトをかけてみても、本来、自分の予測のなかでは、「モーツァルトの音楽」は爽やかなはずなのに、どうも「もったり」としていて、あまり耳には芳しくなく、正直なところ、目が回るようで、あんまり気持ちの良いものではなかった。いつもなら、あんなに好きなモーツァルトなのに。
そして、ぼくのもっとも大好きなベートーヴェンは、手術も無事終わり、いまのところは小康状態を保ち、開口一番がんを宣告したお医者によれば、患部はとりきれたという。もちろん、まだまだ予断は許されない状態をキープしてはいる。手術から1週間が経ち、ようやく、少しはお粥が食べられるようになったころ、ぼくの「人間ウォークマン」にベートーヴェンも登場してきた。
それも、あまたのベートーヴェンのなかでも、聴こえてきたのはそれまで、まったくといってよいほど、「予期」もしていなかった、ベートーヴェンの交響曲のなかでも一番地味といってもよい、「交響曲第二番」だった。不思議なものである。
後に、病院から退院したとき、いつもは滅多に聴かないベートーヴェンの「交響曲第二番」をオーディオでかけて聴いてみた。こういうときは、苦労の末に酸いも甘いもわかったような指揮をするチェコの指揮者ラファエル・クーベリックだろう。そう思えてならなかった。下記の映像は、クーベリック指揮のオランダのロイヤル・コンセルトヘボウ・オーケストラの映像である。
どうでもいい音楽なんて、やはり世の中にはなくて、こちらの気持ちが、予期しないぐらいに心身共に、ある別の状態に向かっているときこそ、本来の意味での
「癒やしの音楽」が普段とはまったく違った形で、しかも予期しない形で流れてくるのだろう。ぼくはこの病気とともに暮らしていくことになったいわば、まだ初心者もいいところだ。しかし音楽には不思議な力のようなものがあるものだ。ぼくの「人間ウォークマン」は、まだ調整がきかずに、突然耳のなかで、鳴り出すという癖を持っている。最近は、プッチーニの『マノン・レスコー』の「インテルメッゾ」も『トスカ』も鳴らなくなり、もっぱらベートーヴェンの「交響曲第二番」のそれも、第一楽章の序奏が終わってオーケストラが動き出すところ」なのである。嘘のような本当の話である。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPはソナー・メンバーズ・クラブをクリックしてください。
ケストナーの『ふたりのロッテ』とメルヘン・オペラ『ヘンゼルとグレーテル』
2017 AUG 16 18:18:31 pm by 野村 和寿

ドイツの詩人で児童文学者のエーリッヒ・ケストナー(1899-1974)の子ども向け小説『ふたりのロッテ』を読了しました。翻訳は高橋健二の翻訳で『ケストナー少年文学全集6』に所収の1962年版(岩波書店)と、池田香代子の翻訳で『岩波少年文庫138)に所収の2006年版(岩波書店)とが出ていて、そのどちらもを読んでみました。ちなみに、少年文庫には、小学4・5年以上と書いてあります。ぼくもその意味では、小学4・5年以上に該当しているので大丈夫かと。
この作品は単なる子どもだましの作品かと思うと大いに違っていて、大人が身につまされる作品です。ネタバレを覚悟で、書いてみます。ビュール湖のほとりのセービュールにある夏の間だけの寄宿学校にやってきた二人の少女、ひとりはルイーゼ・パルフィー ウィーンからやってきた長い巻き毛の少女。南ドイツ・ミュンヘンからやってきたのはきっちり編んだおさげの、ロッテ・ケルナー。ふたりは、髪の毛の形以外、姿形がうり二つだったのです。ふたりのそっくりさんは、同じ部屋、ベッドも隣同士になります。
ルイーゼには父親しかおらず、ロッテには母親しかありません。
ウィーンからやってきた巻き毛のルイーゼのお父さんパルフィー氏は、オペラの楽長、ウィーンで作曲の傍ら、歌劇場で指揮をしているという設定。どうも、R.シュトラウスを思わせる設定なのが面白いです。
歌劇場では、まさにフンパーディンク(1854-1921)のメルヘン・オペラ『ヘンゼルとグレーテル』(1893年初演)が上演されようとしています。本のなかででてくる「ふたりのロッテ」とこのメルヘン・オペラは浅からぬ因縁です。フンパーディンクのほうは、グリム童話を翻案して3幕ものの子どもたちの為の『オペラにしたててあります。グリムが悲劇なのに対して、オペラではハッピーエンドになっています。対象が子どもたちといっても、作曲者フンパーディンク自身、ワーグナーの弟子だったので、その全体を流れるメルヘンといっても、かなりワーグナーの色が濃い作品になっています。
しかも、よくよく考えると、このメルヘン・オペラ『ヘンゼルとグレーテル』は、箒(ほうき)職人の兄ヘンゼとグレーテル(妹)が、両親に捨てられて、森の中に送り出されます。しかも両親は子どもたちを愛しているのです。両親はそうすることを悲しんでいます。森の中で迷ったところからストーリーが始まります。
この点も『ふたりのロッテ』は、しっかりと、関係させています。もちろん、少年時代にこの本を読んだときは、そんなこと知るよしもありませんでした。
メルヘン・オペラの『ヘンゼルとグレーテル』の話を少し。なかで、お菓子の家 実は魔法でおびきよせた子どもたちを食べてしまう悪い魔女の家に、日本では、「お菓子の家」と称しているのですが、「ふたりのロッテ」の中では、「ぽりぽりと取れるコショウ菓子の家」と書いてあります。少し調べてみると、香辛料お菓子レープクーエン(Lebkuchen)わけても、家の形をしたものを、プフェッファークーヘンハウス(Pfeffer kuchenhaus)と称するのだそうです。哱蜜、香辛料、オレンジ・レモンの皮、ナッツを用いて作ったケーキのことだそうです。
そのことを日本では、「お菓子の家」と呼んでいたのを、今回初めて知りました。
映像では、1981年にわざわざ凝ったバイエルン州立歌劇場を中心に活躍した演出家エファーディングの凝った演出のもと、ゲオルグ・ショルティ指揮ウィーンフィルハーモニー管弦楽団が、小さなオペラハウス、会場にいる観客は、子どもたちだけ、そして、ピットには、コンサート・マスター ゲルハルト・ヘッツェル率いるウィーンフィルハーモニーが、ちゃんと正装の燕尾服を着用して演奏にのぞむという映像です。
歌手陣も素晴らしく ヘンゼル=ブリギッテ・ファスベンダー(メゾ・ソプラノ) グレーテル:エディタ・グルベローバ(ソプラノ) ペーター:ヘルマン・プライ(バリトン)お母さん ヘルガ・デルネシュ(ソプラノ)。最初の3人は有名だと思いますが、デルネシュは、1967年のバイロイトでワルキューレを歌ったり、カラヤンの『トリスタンとイゾルデ』でトリスタンを歌っている往年の名歌手です。ワーグナーの弟子だった作曲者フンパーディンクはこのあたりにも、ワーグナーの影響の歌手をおいているところがなかなかにくい演出です。全部で1時間49分。ヨーロッパでは、よく子供連れで聞くことが出来るクリスマスの上演になっています。全曲 下記に動画がありました。
ほかにも、YouTubeでみつかりました。第2幕に「夕べの祈り」というヘンゼルとグレーテルの歌う二重唱がありますが、ここでは、エリーザベト・シュヴァルツコップとエリーザベト・グリュンマーが歌う音楽がありました。カラヤン指揮のフィルハーモニア管弦楽団です。
エリーザベト・シュヴァルツコップ エリーザベト・グリュンマー
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮フィルハーモニア管弦楽団
次に続くのが14人の天使たちによる、「夢のパントマイム」という曲です。この曲をオットー・クレンペラー指揮フィルハーモニア管弦楽団が演奏している音声です。
夢のパントマイム 1960年 オットー・クレンペラー指揮フィルハーモニア管弦楽団
さて本題は「ふたりのロッテ」ケストナー作に戻ります。
二人のロッテのうちのウィーンのルイーゼは、父親ルートウィッヒ・パルフィー氏がオペラの作曲家で「真の芸術家かたぎ」の楽長、奥さん(母)がいないので、食事はインピリアルホテルの食堂で、オムレツ(ウィーン風)、父親は牛の足のいぶし肉(Tafel spitz ターフェル・シュピッツ)をいつも食べています。父の内面生活は独特なもので、複雑、音楽的な着想がわくと、それを書き付け、作曲するためにひとりにならなければならない。ウィーンのフィルハーモニーがバルフィー氏の最初のピアノ協奏曲を初演(のために作曲)したときは、彼は無造作にグランドピアノをとりにやらせ、ケルントナー環状通り(ウィーンのリンク)に借りた仕事部屋に運ばせたとあります、仕事部屋では楽譜を書いているばかりでなく、オペラの女の歌手たちと歌の約の研究に余念がありません。お父さんパルフィー氏のつきあっている女性はイレーネ・ゲルラハ嬢といいます。ワーグナーの『ニーベルンクの指環』のワルハラを想像してしまう名前です。もじりでしょう。
ウィーン国立歌劇場で、『ヘンゼルとグレーテル』をパルフィー楽長が指揮をします。ロッテは、よそいきの服を着て、ウィーン国立歌劇場の2階のロージェという小部屋のようになった上等の席で、天鵞絨針(びろうど)の手すりに体をおしつけて、目を輝かせながらオーケストラを見下ろしています。えんび服を着たおとうさんは、なんとすばらしいスタイルでしょう。楽手たちの中にはずいぶん歳をとった人もいるのに、なんとみんなが指揮に従っています。お父さんが棒で強くおどすと、みんなはできるだけ大きな音で演奏します。低くさせようと思えば、みんなは夕べの風のようにさらさらと鳴らします、みんなはおとうさんをこわがっているにちがいありません。お父さんはさっき満足そうに桟敷席のルイーゼにむかって、目くばせをしました。ウィーン国立歌劇場には顧問官(医者)もいます。医者の顧問官シュトローブル先生です。この先生さすがにウィーンらしく、フロイト(ジークムント 1856-1939年)の影響を受けている精神科医なのです。このあたりも面白いです。この人物もあとあと物語に効いてくる存在です。
一方、もうひとりのロッテ ミュンヘンのロッテは、母だけで父がいません。母はルイーゼロッテ・パルフィー婦人(旧姓ケルナー)は、6年前に夫と離婚、ミュンヘングラフ出版社でグラフ誌の編集長です。編集者なので、帰宅は夜遅くなり、ロッテが、「うちの小さい主婦さん」をしています。ミュンヘンのマックス・エマヌエル通りの小さな住まいに住んでいますが、ロッテは、母のために小さな主婦さんとして、晩のおかずの材料を買いに行きます。オイゲン王子通りのかどの肉やフーバー親方のところで牛肉を半ポンド、かのこまだらのヒレ肉で、腎臓と骨を少しずつ添えてもらいます。スープに入れる野菜とマカロニと塩をかうためワーゲンターラーおかみさんの食料品店に通います。マカロニスープをつくります。マカロニの水のなかに塩をどれくらいいれたらよいのか?ニクズク(ナツメグの和名です・ニクズク(肉荳蔲))をおろしたり、野菜を洗って、ニンジンを削ったりします。20分前に煮立っているお湯にマカロニを投げ込まなければなりません。
もう賢明なる読者のみなさんはおわかりだと思うのですが、夏の寄宿学校から、夏が終わるときに、ミュンヘンへ、ウィーンへ、ふたりのロッテが帰宅するときに、なにしろうり二つの姿形のふたりは、ふたりで、謀って、取り替えっこをしてしまうのです。つまり、ミュンヘンから来たロッテは、「ウィーンのルイーゼ」になりすまし、ウィーンへ。ウィーンから来たルイーゼは、「ミュンヘンのロッテ」になりすまし、ミュンヘンへ戻ります。
姿形はうり二つなのに、性格の違うこのふたりにふりかかる毎日の生活とは? ふたりのロッテは、ふたりだけの情報交換の手紙に、局留め郵便を利用しています番号は「ワスレナグサ ミュンヘン18番」です。そしてふたりのロッテの結末は?お父さんパルフィー氏の音楽家と、お母さん編集者ルイーゼロッテ・パルフィー女史の運命は?
あとは、みなさんお読みになってみてください。全部でわずか205ページほどの佳作です。原題は”DAS DOPPELTE LOTTCHEN” Erich Kästner 1949です。

エーリッッヒ・ケストナー(1899-1974年)ドイツ・ドレスデン生まれ、小説家・詩人 第2次世界大戦時も、ナチス・ファシズムを非難し、自由・民主主義を擁護、戦後初代西ドイツペンクラブ会長。「エーミールと探偵たち」「点子ちゃんとアントン」「飛ぶ教室」などがある。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
ホルン信号とポストホルンは別 追加を発見!
2017 FEB 3 6:06:04 am by 野村 和寿

先日ブログに書いた「ホルン信号とポストホルンとは別?」 で、最近もう1つ、クラシック音楽に使われているポストホルン(郵便ラッパのころ 今のホルンではないです)を模した曲について、このたび、発見いたしましたので、改めてここにアップさせていただきます。ブログは追加がきくので、こういうときにブログは便利ですね。
今でもドイツでは、郵便局のマークは、ポストホルンが使われていますが、シューベルトの歌曲『冬の旅』にも郵便という曲が第13曲目にありました。
詳しくは『冬の旅』は、第1部と第2部に分かれていて全24曲からなる連作歌曲集なのですが、その第2部の冒頭の、第13曲目に「郵便」と題する2分半ほどの歌曲がありました。郵便馬車がひづめを鳴らしながら近づいてきて、郵便が到着したことを示すポストホルンの響きが最初に出てきます。主人公は、もしかして恋人からの文ではないかと一瞬いろめきたつという曲です。
「郵便馬車」シューベルト 『冬の旅』より第13曲
通りの方から郵便馬車のラッパが鳴り響く。どうしてそんなに高鳴るんだ
僕の心よ? あの郵便馬車はおまえに何の手紙も持ってこないぞ。
なのにどうしてそれほど変に急かすんだ
僕の心よ? そうだ、あの郵便馬車はあの街から来たんだ
僕が恋人を愛したあの街から。
僕の心よ? きっとあっちの方を見てあの街がどんな様子なのか尋ねたいんだろ
僕の心よ?
シューベルト作曲D.911『冬の旅』ヴィルヘルム・ミュラーの詩による連作歌曲集 第13曲郵便馬車より
最初の前奏の部分に、いかにも郵便馬車のポストホルンのラッパような節が出てきました。シューベルトも郵便馬車にお世話になっていたんですね。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPはソナー・メンバーズ・クラブをクリックして下さい。
旅する哲学 南イタリア・サレルノへ②世界遺産パレストゥム 吉田秀和氏の訃報
2017 FEB 1 3:03:16 am by 野村 和寿

この世界遺産 正式名称は、「パエストゥムとヴェリアの古代遺跡群を含むチレントとティアノ渓谷国立公園とバドゥーラのカルトジオ修道院」といいます。この柱の太いこと!そして、外壁は、えんえんと海まで続いており、ギリシャの植民都市だったころから、この建築はあると思うと、一気に古代に思いをはせてしまいます。
このギリシャ神殿は、南イタリアの世界遺産「パエストゥム」です。ここの正式名称は、「パエストゥムとヴェリアの古代遺跡群を含むチレントと、ディアノ渓谷国立公園とパドゥーラのカルトジオ修道院」といいます。整備された公園のなかに、こつ然と太い柱の神殿です。周囲の外壁は、なんと、海までずっと続いているのがすごいです。あまり知られていないのですが、ギリシャ時代に南イタリアにまで都市国家がたくさんあって、しかも、これだけ大規模な神殿が建てられていたとは! 南イタリア風の気候で、雲は一転かき曇り、スコールのような雨が。雨にそぼぬれつつ、神殿をながめるのもよしでした!さきほどの神殿にさらに近づいてみますと、この写真の柱が太く、そして、屋根の部分にかかる破風が見えます。ものすごく状態が良くて、なかなか幻想的です。なんか映画のシーンになりそうな。壮大なロマンとでもいいましょうか。
吉田秀和氏の訃報を知りました。吉田氏は、1972年頃、NHK FMで、芸術時評という番組に出演し、日曜の朝10時ごろに、私はよくこの番組に耳を傾けていました。この番組には当時の音楽評論家が集合していました。野村光一、大木正興、遠山一行、中島健蔵などそうそうたるメンバーで、代わる代わる、その月に行われた主な演奏家を、ライブで批評していったのです。その中でも異彩を放っていたのが吉田氏でした。いつも大方の意見とは大いに異なり、厳しく批評していました。カール・ベームのモーツァルトのオペラ「フィガロの結婚」のあまりのテンポの遅さに、吉田氏はとても厳しく反応しており、大方の「とてもいい」という手放しの意見に真っ向から反旗を翻していました。だんだんと大方の意見もそれに引きずられていくかのとき、最後に、吉田氏は「これだけのテンポでも、ウィーンフィルが演奏でき、そして、「フィガロ」をやるんだから、やはりこれはいいんだ」と、大方が吉田氏に傾きかけた後で、また批評を鋭くついたりして、とても過激な存在でした。よく、この演奏は認めないということもいっていました。ユージン・オーマンディのフィラデルフィア管弦楽団のときも、一人、音楽は美しいだけでいいのかと、鋭く迫っていましたが、最後に、でも「音楽はやはり美しいだけということにとても魅力があるんです」とも茶目っ気たっぷりといっていました。ぼくは、当時高校生で、そんなに多くの演奏会に行けなかったので、この番組の時間を楽しみに、まるで演奏会にいったことのように聞いていました。こういう気骨がある批評家に憧れていました。
個人主義のイタリアを旅するには、こちらも半端でない意思をもって、個人主義にならねばならないと思います。イタリア語の表現でも、必ず、自分がなにかしたいということをいわないと、当然のことながら誰もなにもやってくれない。この考え方は大切だと思います。お仕着せではないんです。まずは自分の意思なんです。ボーリオvuolioという言葉を何度も使いました。この原形ボレーレvolere、「欲する」という意味がようやくわかったような気持ちでした。
個人の旅は、なかなか厳しく、常に緊張感を伴い、半端じゃなく気を巡らして、疲れます。しかし、この疲れを乗り切るのは、なにか「巡礼」にも似ているような、そんなきもします。旅先で読む本を吟味に吟味を重ねて持ってきたのですが、あらかたの本はがさばるので、出会った日本人にあげてしまいました。残る本は恥ずかしいのですが沢木耕太郎の「旅する力~深夜特急ノート」でした。まるで、沢木氏が旅で経験したようなことが日々おこっていて、全く予断を許さないのです。
アグリツーリズモのオーナー、プリスコ氏の運転する車は、日本車よりもクッションがかたく、しかも道の曲がりくねり方は相当なもので、極端にいえば、山を越え越え道がついているので、10メートルでカーブ、といったところが右に左に延々と続き、真っ青になり顔面蒼白、ついには、止めてもらって、頭ががんがん、胃液のでるのを必死でおさえます。
行きも帰りも、もう大変で宿に帰るとそれだけで寝込んでしまうほどです。こうした受難のようなことが一方では起き、そのために、常に水分はとっておこうとか、あまり食べると胃によくないので、控えておこうとか、自分で考えて行動しないと行けないのです。 酒も飲んだ後にどうなるかをきちんと予測してから、ちょっと口にするといった感じで、野方図にビールをくらうなどということはしません。こうしたまったく予期せぬことが多々起きる「受難」にも似た状況が「旅」なんです。
遠くの方で稲光、さっきまでスコールのような大雨でした。今は朝の5時すぎなのであたりは静かです。なんの音もしていない。ようやく雨がやんだので、少しずつ小鳥のさえずりがもどってきた感じです。正しいことを正しくしているという自信のようなものが、自分がというところから、みなぎっているような気がします。自分のように迷っていてはたぶん駄目なんだろうなと。もっとはっきりしないといけないんです。 0527朝 アグリトゥーリズモ・プリスコにて
先日の日曜の朝、南イタリアの世界遺産パエストゥムの近く、サレルノを走っていたら対向車線(といっても対向の概念はないです)に、なんとバイクの群れが。それも小型バイクのヴェスパ愛好者だけが、ななんと、200台以上のレースをやっているのでした。
この写真だとあんまりわからないかもしれないのですが。アグリツーリズモ・プリスコ内の食堂です。お客はぼく一人というのが寂しいのですが。これで、1泊日本で代理店経由で、1万円くらいです。直接ここに申し込めばなんと1泊2食付きで、5000円です。ちょっと間にいろいろ入っているので、倍なのですが、ぼくは3泊して約3万円でした。宿に古いフィアットが置かれてありました。ルパン3世にでてくる車と同じ。ユーモラスなのでパチリ。
広大な庭には野草の花が咲き乱れており、遠くからモッツァレラ・チーズのための牛乳を出してくれる水牛の鳴き声がします。あと数時間で残念ながら出発です。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPはソナー・メンバーズ・クラブをクリックして下さい。
旅する哲学 南イタリア・ナポリへその③オペラ
2017 JAN 26 16:16:11 pm by 野村 和寿

われらの存在のなかには 至高の時がある。
その時はくっきりと際立ち 保つのだ。
われらを力づける美徳を・・・・・・ ワーズワース
念願がかなってナポリのサン・カルロ歌劇場でプッチーニのオペラ「ラ・ボエーム」のチケットが入手でき、歌劇場に入ることができました。僕の席は、5階のまさに天井桟敷席でしたが、舞台装置が歌手の表情から、観客の様子までてにとるようにみることができました。なんといってもここは、赤を基調にした座席と、まばゆいばかりの金で縁取られたまことに見事な歌劇場です。案内嬢まで赤のワンピースを着ています。一番驚いたのはオーケストラの手慣れていることと、カンタービレになると、オケが歌手をあおり、歌手がまたオケをあおるというように、まことに理想的な、イタリアの節になります。オケがこれだけ積極的にアンサンブルをやっているのは日本ではなかなかおめにかかれないことです。上の写真は、休憩時間に1階席からロイヤルボックス、そして、上の階をみあげてみました。すごいでしょ。
世の中に行きたいところがどこかと聞かれたら、サンカルロ歌劇場といつも、思っていたくらい、ナポリで行ってみたかった所です。やはり、ナポリはすごかったです。なにしろ、1737年の開場というヨーロッパで(ということは世界で)最初の歌劇場です。何度かの火災にあったからかもしれないのですが、会場には、なんと消防士さんが、消防士のかっこうのまま待機していらっしゃるのにはびっくりしました。お客は、いまだにスノッブな貴族趣味の人たちが多くて、華やかな社交場の感もありました。今日の公演はいわゆる定期公演客向けだからなおさらなんでしょう。いいおじいさんが、歌い手によってどのくらい演目の印象が異なるかを知り合いに議論をふっかけたりして、奥さんもなんかうれしそうに見守るという感じです。
一方、オーケストラや歌い手はそれとは関係なくて、きわめて自由に音楽を語るといった風情で、音楽を動かしているのはまさに自分たちという感じでした。5階席のバルコナータと呼ばれる5階席からみた2階席から上のバルコンです。ひとつひとつは、部屋になっていて、鍵を閉めたりもでき、中でなにがおこなわれているかわからないという仕組み。サンカルロ歌劇場の音楽の次にもり立てるものといえば、まばゆいばかりの光にあるかもしれません。こんなご時世で、LEDが断然効率的なのでしょう。しかし、ここにある光あふれるまばゆい光は、白熱で、ろうそくのひかりの代用をしています。あたたかな光がシャンデリアからも、いろいろな照明からも降って参ります。
休憩時間に1階からみたオーケストラ・ピットです。けっこう深く広く作ってありました。休憩のときは楽団員は三々五々で十分に休憩を取る人や、マーラーの交響曲第1番”巨人”とリムスキー=コルサコフの”シエラザード”をさらっている人などもいました。それにしても、ナポリのオケの金管楽器は、昔のラッパそのものみたいな音がしています。なにか味のあるラッパの音がしています。
きょうの演奏はいつものプッチーニの「ラ・ボエーム」とも少し違っていました。ちょっとマニアックなのですがご紹介。
まず、幕が始まる前に、第2幕で出てくる子どもたちが演壇上に姿をみせ、そのなかの一人が、演出家のメッセージを代読します。第1幕は、主人公ミミとルドルフォの出会い、場所は貧しい屋根裏部屋、2幕は、打って変わってパリ シャンゼリゼでの楽しいクリスマスの時間となるのですが、「人生とはかくも不思議に、いろいろなことがおこります。それはときには衝撃的だったりしますが、必ずいいこともあるのです。ですから1幕と2幕は切れ目なく演奏します。」
第1幕の舞台装置が、ひいていき、2幕のシャンゼリゼがでてきても驚かないでください。こうした「幸せな時間」は、誰にでも訪れるといいのですが、不幸にして幸いなる時間を過ごせない人々もいます。そうした人々のために、まずは祈りましょう。」といって、観客全員が起立し、不幸な人々のために、黙祷を捧げました。不幸な人々とは誰かと特定していないのに、起立、黙祷いかにもカトリックの国の考えそうな話です。そして、1幕が終わると、しずかに、場面は転換していき、シャンゼリゼが現れる。このことに、演出家は美しい幸せ時間をかけているようです。まことに不思議な演出家のメッセージ、そして観客の不思議な「黙祷」でした。
第2幕のシャンゼリゼの通りの舞台を、こっそり5階から撮影したのでどうぞ。『ラ・ボエーム』は、1幕2幕続けて上演され、第3幕の間に幕間休憩です。広大なロビーです。中には記念写真をとる、グループも。とにかくシャンデリアがいくつも光を放つ中で、ほとんどの観客が、女性はカクテル・ドレス、男性はすくなくとも上着にネクタイ着用です。ぼくも蝶ネクタイとミッソーニのジャケットをもっていってよかったなと思いました。こうしてナポリの夜はえんえんとふけていきました。
ちょっとピンぼけなので恐縮なのですが、根性がないので、隠し撮りです。ナポリ サンカルロ歌劇場の案内係は、歌劇場のビロウドの赤で統一した場内で、赤のワンピースを着用しています。日本のクラシック会場のように、いかにもの案内係の制服ではなくて、どちらかといえば、夜会にも着て行けそうな、カクテルドレスにもなるようなそんな服装です。みなさんお若く、とてもきれいに会場に花を添えています。そして、与えられた任務はきちんとこなしています、客の誘導とか、客への気配りとかなかなかよろしいです。文化とは、それぞれの役割をお互いにきちんとこなすということなのかもしれません。
サンカルロ歌劇場の音楽の次にもり立てるものといえば、まばゆいばかりの光にあるかもしれません。こんなご時世で、LEDが断然効率的なのでしょう。しかし、ここにある光あふれるまばゆい光は、当然のように、昔からの白熱球で、ろうそくの光の代用をしています。あたたかな光がシャンデリアからも、いろいろな照明からも降って参ります。
指揮者にいわれてそうするのではなく、オケが自然発生的にするクレッシェンド、そして、曲の変わり目の決然とでる確固としたもの、オケが音楽を作るというプライドの上に、ときにはテンポさえも、自在に操り、それに音量が加わりまさに目指す音楽がありました。若いイタリア人の指揮者君はただただ、交通整理に夢中でしたが、オケはそんなことおかまいなく、自由にプッチーニをやっておりました。
以下友人(シカゴから)のコメントを残してくれました。
素晴らしい!野村さんのコメント、手に取るようにわかります。
プッチーニはソロのみならずアンサンブル・オペラなんだよね。それが手にとるようにわかった。明るい場面と悲劇的な場面で当然ながら音色を極端に変えている。それに忠実にオケが動くと、プッチーニというのは、道具としてのオケの扱い方が上手なんだなと思う。指揮者にいわれてそうするのではなく、オケが自然発生的にするクレッシェンド、そして、曲の変わり目の決然とでる確固としたもの、オケが音楽を作るというプライドの上に、ときにはテンポさえも、自在に操り、それに音量が加わりまさに目指す音楽がありました。和解イタリア人の指揮者君はただただ、交通整理に夢中でしたが、オケはそんなことおかまいなく、自由にプッチーニをやっておりました。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPはソナー・メンバーズ・クラブをクリックして下さい。
ウィーンに恋して 冷たくされて
2017 JAN 15 13:13:40 pm by 野村 和寿

1991年に起きたウィーン取材のことを、26年経た2017年、思い起こして書いてみることにしました。それは、とても大変な取材でした。憧れていた恋人に一気にふられたような、ぼくにとっては、珍しくとても,辛口のブログになります。
面白くないかも知れないです。
1991年はモーツァルトの没後200年記念の年で、いろいろなモーツァルト関係のイベントがおこなわれていました。そこでゴールデン・ウィークを利用して、ウィーン・フィル・メンバーに一週間密着するというぼくが編集者をしていた音楽雑誌の企画で、ウィーンに行ったことがありました。
それまで、ぼくにとって、ウィーンというのは憧れの、理想の音楽都市だと思っていました。当時はまだヨーロッパ直行便はなく、アンカレッジ経由で15時間もかかったヨーロッパでした。ロンドンを経由して、18時間かかってウィーンに到着した。ウィーンの取材は、ウィーンの公立図書館から始まりました。ウィーンの一般の図書館で、モーツァルトはどうやって受け容れられているんだろう。ところが、ぼくの抱いていたウィーン=モーツァルト=音楽の街というステレオタイプなイメージは、もろくも崩れ去った。
1990年代のウィーンは、とくに、日本でのように、モーツァルトについて、お祭り騒ぎではなく、一般の市民達が、特にモーツァルトやクラシックが好きということもありませんでした。もちろん、ウィーンの土産物屋には、モーツァルトの顔を冠したチョコレートやグッズがあるにはありました。また5000シリング札はモーツァルトのデザインでした。しかし、ウィーンはなにも騒いでいませんでした。
モーツァルトの愛好家を自認する図書館長は、ボクの質問に少しも満足な答えを聞くことはできませんでした。モーツァルトに関するコーナーは貧弱で、日本のほうがよっぽど充実していました。古い本が並べられているだけでした。
ウィーンの若い音楽愛好家の家にも取材をしました。「モーツァルトは嫌いです。音楽がこまごまとしていて冗談すぎるから」と、さらっといってのけました。
音楽学生にも取材しました。普通のアパートに住む人にとっては、防音というのが、大きな問題で、音楽家の玉子たちには、ウィーンは決して優しくなかった。というよりもきわめて冷淡な印象がありました。練習する場所にも恵まれていませんでした。
さらに1991年当時にもウィーン楽友協会を取材したおりに、わかったことは、あの黄金のホールをとりしきっている会長は、第2次世界大戦の頃、ウィーンがナチスドイツと併合されていたころからずっと、楽友協会を牛耳ってきた女史。ファシズムと親しかった女性の館長の下、取材にはきわめて非協力的で、保守的で、まったくとりつくしまもありませんでした。
ウィーンのシェーンブルン宮殿で一般の老人夫婦が写真を撮っていたので、記念写真をとってあげましょうか? と聞いたらにべもなく、拒絶された。まるで、自分のテリトリーにむやみに立ち入ることを拒んでいるようでした。
ぼくが、感じた1991年のウィーンは、オーストリア社会党のちの社会民主党のフランツ・ヴラニツキーが、国民党との連立を組み、政権を担っていたが、ウィーン人にしてみると、みるべき政策もなく、デモも頻発していていました。
ウィーンの国立歌劇場にも行きました。ウィーンの駐車事情は極度に悪く、国立歌劇場近くの駐車場は、ことごとく満車で、街のパーキングというパーキングに、車がこれはどうやったら、発車できるんだろうとばかり、無理矢理に駐車がめだった。1時間ほど駐車場を探した挙げ句、入場ができました。
オペラでは、ムソグルスキーの『ホヴァンスティナ』を観ました。当時、音楽監督だった指揮者クラウディオ・アバドによる発掘で、復活上演されていた。1階の平土間席に陣取りましたが、取材目的で、当然のように、大事な取材道具の入ったかばんを、クロークに預けることなく、もって席に着いていました。
隣の過度に太った30代と思われる夫婦は、ボクの席を通って通路に出るときに、わざと、ぼくのかばんを踏みつけて通った。つまり、ボクが、かばんをクロークに預けもしないで、観劇するなんて、田舎者のするものだといわんばかりで、非常に自分自身のことを考えてばかり居て、冷酷な仕打ち、それが現実だった。オペラ観劇後のレストラン事情も決して恵まれては居ませんでした。終演が23時で、まだ近くでオープンしているレストランは非常に寒々としていました。注文した豆のスープは塩辛くてとても美味しいものではありませんでした。
通訳に雇用した日本人女性は、ウィーンにバイオリン留学にきたものの、すでに音楽にはなんらかの理由で、挫折を味わい、今は通訳のような仕事をしていた様子でしたが、これが、ウィーン人よりさらに、保守的で、頑迷で保守的なところは、日本語で通訳しながらも、自分に言い聞かせているようなところがあって、しかもギャランティーはしっかりと高額でした。ウィーン在住の日本人音楽評論家にも会った。彼もまた日本語でもって、ウィーン人のようにコンサーヴァティブそのものだった、これは想像の域を出ないが、こうした留学生のなれの果てのような日本人が、ウィーンには多くいて、それぞれが苦しい生活をしているようだった。あまりよい印象はもっていない。
1989年のベルリンの壁崩壊直後で、社会主義諸国の社会主義の崩壊があったとはいえ、オーストリアは、大きな誇れる産業もなく、地理的には、社会主義国の隣国、黄昏の西ヨーロッパの果てであり、自分たちが保守的に生きていくために、静かに質素に、他人の目に注意を向けながら、日々を暮らして、何もしないようにしようと思うしかないといった、きわめて保守的な空気感でした。
4月の終わりだというのに、吐く息は白く、なにか寒々しい感じがしました。
とてもボクが考えてきた往年のウィーンではないというのが第一印象だった。
ボクの思っているウィーンに対する甘いイメージは大きくひっくり返されてしまった。正直なところ興ざめでした。
ボクは、一番の取材目的である、ウィーン室内合奏団の録音場所であるカジノツェーゲルニッツに向かいました。朽ち果てたような古いホテル。入り口に、何もすることのない男達がたむろしていました。「ここに録音場所があるのか?」と聞くと、「知らない、そういえば、裏の方にあったかも」と、きわめて非協力的だった。裏に回ると、同じく朽ち果てたような昔は豪奢だった面影が、天井からさがったシャンデリアの電灯光が、漏れてきました。
日本のようにモーツァルト・イヤーの本場だとお祭りを想像していた雑誌記者は、そのあまりにも安易な日本的な考えにすっかりと困ってしまいました。
ボクは、ベルナルト・ベルトルッチ監督(代表作「ラスト・エンペラー」)のイタリア映画『暗殺の森』(1970年イタリア・フランス・ドイツ合作)を思い出していました。舞台は、大戦中のイタリアとフランス、撮影は名匠ヴィットリオ・ストラーロの暗い青がかった空気感のもとで、主人公役のジャンルイ・トランティニアンが殺し屋の映画だ。ウィーンとは違うけれど、世紀末的な色合い漂う、冷酷なまでの頽廃感が似ていると、思っていました。
ウィーン室内合奏団の話は次回へ・・・・つづきます。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPはソナー・メンバーズ・クラブをクリックして下さい。
トルコ音楽に魅せられて
2017 JAN 14 5:05:11 am by 野村 和寿

モーツァルト(1756—91年)やベートーヴェン(1770-1827年)の時代、オーストリア(ハプスブルク君主国)ウィーンでは、トルコへの関心が高まっていました。
ベートーヴェンの時代(1792−1827年・彼の人生の後半の35年間にあたります)はオスマントルコが、ウィーン(ハプスブルク君主国の首都)を包囲して100年程度しか経っていません。
オスマントルコとオーストリア(当時のハプスブルク君主国)の戦争は、墺土戦争(Austro-Turkish War, 1716ー1718年)と呼ばれる。18世紀にオーストリア(ハプスブルク君主国)とオスマン帝国が東ヨーロッパ・バルカン半島のセルビアを主戦場として衝突した戦争でした。
異民族への関心は、今の日本語でいえば、民衆のレベルでは、エスニックなものへの関心ということであり、あるいはエキゾチシズム、夢の王国としての異国への憧憬の表現でもあります。モーツァルトやベートーヴェンに、当時のウィーンで日常的であったはずの「ヤニチャール音楽」をあえて「トルコ風」というところに、フォルクローレとエスニシティ(エキゾチシズム)に対するウィーン古典派の音楽との差異を鋭敏に感じ取ったことを発見するのです。
ベートーヴェンの第九交響曲の第4楽章で、テナー・ソロがトルコマーチ(アラ・マルチャ)にのって、歌うのは、その歌詞がまさに異教的で、ギリシャ神話を連想させるからにほかなりません。
そこで、まずは、本家本元のオスマントルコの軍楽隊の音楽を御紹介します。これは、トルコ・イスタンブールにある軍事博物館で午後2時から毎日演奏されています。曲名は「オスマントルコ 軍楽隊 オスマンの響き 古い陸軍行進曲 ジェッディン・デデン 祖先も祖父も」です。
この曲が有名になったのは、NHKで放送された向田邦子の『阿修羅のごとく』(1979−80年 演出和田勉 出演加藤治子、八千草薫、いしだあゆみ 佐分利信)というテレビドラマで最初に流れた音楽になってからです。耳をつんざくチャルメラの一種ズルナ、太鼓ダウル、ラッパ=ボル、シンバル=ズィル、そして、日本の山伏が修行の際に用いる音の鳴る杖=チェブギャーン、この強烈な音楽は、さぞや敵国を圧倒したことでしょう。圧倒したついでに、ベートーヴェンやモーツァルトの心もわしづかみにしたはずです。
ベートーヴェンが、トルコの音楽に触発されて作曲したとされるトルコ行進曲は、もともと、劇音楽 アテネの廃墟の第5曲に登場します。
ピアノで演奏される版は、後にピアノ用に編曲されたものです。
まずは、 ベートーヴェン「トルコ行進曲」オーケストラ版
劇音楽 「アテネの廃墟」より第5曲
演奏はユージン・オーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団の演奏です。
同 ピアノ版 アントン・ルービンシュタイン
(チャイコフスキーと同じ頃のロシアのピアニスト)編曲
エフゲニ・キーシン(ピアノ)BBCプロムスより
次はモーツァルトです。ベートーヴェンがまじめに、トルコ音楽を踏襲したのにくらべると、モーツァルトのは、機知に溢れてとてもかわいくて、いたずらっ子なところがあります。
モーツァルト 「ピアノソナタ第11番」から「トルコ行進曲」 ラン・ランのピアノ独奏です。
https://youtu.be/uWYmUZTYE78
さらにモーツァルトは、明らかに、歌劇「後宮からの誘拐」‘または「後宮への逃走」1782年作曲)というトルコを思わせる某国でのお話をオペラにしました。冒頭に演奏される序曲も、最初からトルコの香りがいっぱいに漂ってきます。恋人コンスタンツェを某国(トルコ)から救い出すという話です。
モーツァルト 歌劇『後宮からの誘拐』序曲K.384
ファビオ・ルイージ指揮ウィーン交響楽団 2006年日本ツアーのときの演奏です。
さらにモーツァルトには、トルコ風と題されたバイオリン協奏曲第5番があります。
第3楽章(ユーチューブの演奏では全部で29:05のうちの、20:13から)は、フランスの舞曲風に始まるのですが、22:17から、これがまったく肌合いの違うトルコ音楽になります。とくに24:10からは顕著で、まさに、トルコの軍楽隊のようなあらあらしい変奏があって、優雅から粗暴へと、モーツァルトはここでも遊んでいます。
モーツァルト バイオリン協奏曲第5番 ヒラリー・ハーン(バイオリン)
パーヴォ・ヤルヴィ指揮ドイツ・カンマーフィルハーモニー 2012年12月4-5日ドイツ・ブレーメン録音
最後は再びベートーヴェンです。ベートーヴェンは、あまり宗教的な人でなかったので、むしろ、ギリシャやトルコなどに興味をもっていたようです。第九のフィナーレで、テノールのソロが歌うところは、まさにトルコ行進曲の歓喜への行進です。楽譜にも、「アラ・マルチア(行進曲風)と記されています。
ベートーヴェン『第九交響曲』第4楽章から「アラ・マルチア」
ヨーゼフ・クリップス指揮ロンドン交響楽団 全体は1:05:38ですが、該当部分は、51:09からにあります。
ソリストは、ジェニファー・ヴィヴィアン(ソプラノ)シャーリー・ヴァーレット(メゾ・ソプラノ)ルドルフ・ペトラーク(テノール)ドナルド・ベル(バリトン)BBC合唱団レスリー・ウッドゲート(合唱指揮)
録音時期:1960年1月録音場所:ロンドン、ウォルサムストウ・アセンブリー・ホール 録音当時最新鋭を誇ったアメリカのエヴェレスト・レーベル35㎜磁気フィルムに記録・収録されています。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPはソナー・メンバーズ・クラブをクリックして下さい。
「ホルン信号」と「ポストホルン」とは別?
2017 JAN 12 3:03:43 am by 野村 和寿

ボクは敬愛してやまない作曲家である、ハイドンと、モーツァルトに、この何十年ものあいだ、とんだ勘違いをしていました。とても些細なというかトリビアな話題なのですが、ハイドンの交響曲やモーツァルトのセレナーデのことです。 ハイドンの交響曲第31番は、副タイトルに、「ホルン信号(英語では、Horn signal)」というのが付いており、モーツァルトのセレナーデに「ポストホルン」というのがあるのです。ぼくは、白状してしまいますが、これをまったく逆に、あるいは混同して理解していました。 大学のオーケストラのホルンの名手 T先輩に指摘されて、もう何十年ぶりかで理解を改めることが出来ました。
フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732-1809年)は、少なくとも104曲以上の交響曲を作曲したことから「交響曲の父」と呼ばれますが、なかでも交響曲第31番は、副タイトルが、「ホルン信号」と呼ばれています。 なぜ、ホルン信号と呼ばれるのか? なぜ、ハイドンはこんな名前の交響曲を作曲したのか? 当時、伺候していたハプスブルク家(後にオーストリア=ハンガリー帝国)のアイゼンシュタットにあるエステルハージ宮(水晶の館と呼ばれます)で、1756年から1790年まで、1796年から1809年までと、なんと都合47年間も、お抱えの作曲家だったハイドンが、日々の宮廷生活からヒントを得て、交響曲に生かしていったといってもおかしくはありません。
ホルン信号を発するのは、「コルノ・ダ・カッチャ(直訳すると狩猟用の角笛)」と呼ばれる楽器でした。 この楽器は、通常、貴族たちの狩のときに、狩りをする人々の相互の連絡用として、鳴らされ、重宝されてきました。なにしろ、狩猟ですから、鉄砲を使うわけで。誤って別の貴族を撃ってはならないわけです。しかも、多くの狩猟犬をかかえているので、合図が聴こえるように、コルノ・ダ・カッチャは用いられました。 しかし、まだまだ音楽用に使える程度ではなかったので、これをもとにして、音楽用に改造されて完成したのが、ナチュラルホルンです。
ナチュラルホルンは、さらに進化して、現在の、フレンチホルンへと発展を遂げます。ナチュラルホルンは、今のフレンチホルンと外見は似ているものの、ピストンやロータリーがなく、音は基本的に倍音といって、音の系列が同じ音だけを出すのが基本的です。
ただ、技が6種類あって、音の吹き出し口を右手で、押さえ方を微妙に調整することで、なにもピストンなしでも、ドレミファの音階が出せるのでした。もちろん、演奏は難しいのですが、名手の手にかかれば、できないことでもない。 そして、ナチュラルホルンは、ごく弱いピアニシモから、強いフォルテシモに至るまで表現力が豊かなのです。それで、現代に甦った古楽器を使った演奏団体では、往々にして、昔のナチュラルホルンの柔らかな音色を生かして演奏するということまで行われています。
クリストファー・ホグウッド(1941-2014年)指揮エンシェント室内管弦楽団の演奏です。 https://youtu.be/H30PPIqVsSU
一方、モーツァルト(1756-1791年)のセレナーデ第9番「ポストホルン」に使われている、ポストホルンという楽器は、名前は似ているのですが、こちらはいわゆる喇叭(ラッパ族)の仲間です。郵便馬車に分乗して旅を続け、生涯のうちで、その3分の1を旅に費やしたといわれるモーツァルトが、いつもお世話になっている郵便馬車の警笛がわりのポストホルンに着目したとしても不思議はありません。モーツァルトは、貴族たちの前で宴会の世界で入場と退場の音楽を前と後につけたセレナードを作曲しました。この1779年モーツァルト22歳のときの、セレナーデ第9番K.320もそのうちの1曲で、特に第6楽章には、ポストホルンによるソロがあります。このユーチューブ映像ですと、曲のはじめからですと41:36から43:10の間になります。ポストホルンが、トランペット奏者によって、煌びやかに、高らかに鳴らされています。 宴会の音楽でも手を抜かないどころか、どこまでも典雅でしかも、清涼感あふれるところが、モーツァルトのモーツァルトゆえんたるところです。
ニコラウス・アーノンクール(1953-2016年)指揮ドレスデン国立歌劇場管弦楽団の演奏です。 https://youtu.be/tIVqr2xqzAk
なお、ベートーヴェン(1770-1827年)も交響曲第8番第3楽章で、ポストホルンを思わせる音楽を作曲しています。 1812年夏、ベートーヴェンも、「不滅の恋人」といわれるブレンターノ嬢(が有力とされる)と会ったとされる、チェコの温泉地カールズバードを訪れていますが、そんなときに郵便馬車を利用しているのです。モーツァルトと違ってこちらも、郵便馬車の和やかな馬車の揺れのような感じを音楽で表現しています。第3楽章は全体で、5:57ありますが、このうち、2:49から4:22までのところが、郵便馬車からベートーヴェンがヒントを得て作曲したといわれている部分になります。ただし、ベートーヴェンの場合は、それを、ポストホルンでなくて、ホルン(ナチュラルホルンや、現在のフレンチホルン)で演奏しています。このあたりが、混同を招くところの原因のような気もします。
オット-・クレンペラー(1885-1973年)指揮ニューフィルハーモニア管弦楽団の演奏です。
まとめです。ホルンという名前でも、ホルンの系統のナチュラルホルン(ハイドン交響曲31番) 現在のフレンチホルンがある。またトランペットの系統のポストホルン(モーツァルトセレナーデ第9番第6楽章)もあり、こちらは、通常ホルン奏者でなく、トランペット奏者が演奏することが多い。さらに、ポストホルンを模したベートーヴェン交響曲第8番第3楽章は、ナチュラルホルン、あるいは現在ではフレンチホルンで演奏される。
*本稿と直接関係ないのですが、ハイドンの交響曲第31番は、まだまだ、交響曲が定型になる前の作品であり、ホルン信号以外にも、オーケストラのほか、ソロ・バイオリン、ソロ・チェロ(ブログ上の楽譜の写真右)、そしてなんとソロ・コントラバスまでが登場してとてもユニークな音色が楽しめます。
*郵便馬車のことを、音楽書でみると、必ずといってよいほど「当時の未舗装の道路を郵便馬車でいくのは、現在の道路とは比べものにならないくらい大変だったろう」という文をみかけます。ところが、ウィーンで実際に当時の馬車をみかけ、乗車したときは、ウィーンの中心部が石畳であったこともありますが、実にクッションがきいていて、快適でした。18世紀に入るとドイツでは、市民階級をも巻き込んだ国際的な観光ブームがおこっていたそうで、1790年から1810年にかけて旅行手引き書がヨーロッパで300点も出版されています。たとえば、時代は若干さかのぼりますが、アドルフ・クニッゲ(Adolph Knigge 1752-96年)というドイツの作家による「ブラウンシュヴァイクへの旅」などという18世紀の旅行ブームの火付け役になった本も出版されています。音楽書だけでなく人間科学の分野の本も参考にすると、驚くほど違った光景が見られる一例です。(参考:東洋大学人間科学研究所紀要2008年8号)
ソナー・メンバーズ・クラブのHPはソナー・メンバーズ・クラブをクリックして下さい。
チェロという楽器をご存じでしょうか
2017 JAN 11 6:06:02 am by 野村 和寿

チェロという楽器をご存知でしょうか。
2010年と2016年の2回、ベートーヴェンの第九交響曲を、母校早稲田大学のOBのオーケストラで演奏する機会がありました。ちなみに、演奏団体は、早稲田でオーケストラを共にした50歳以上のメンバーのオーケストラです。
平均年齢はなんと67歳くらいで、ボクなど一番若いひよっこの部類に入っていました。
ベートーヴェンの第九交響曲は、この世の混沌を表すような、弓の先で聴こえるか聴こえないかわからないくらいに、極小さく第1楽章が始まります。常に冷静に音の出るコンマ何秒か前に指揮者からくる指示と、楽譜に書かれた旋律の速度やニュアンスの指示を読み取り、右手で弓に伝え、左手の音程で瞬時に音に変えていくという作業を続けます。
第4楽章! 冒頭は、低音を担当するチェロのまさに「世紀の見せ場」です。満場の聴衆が固唾をのむ中、歌舞伎役者が見得を切るように、対話が始まります。「ここまでの音楽では『歓喜』は来ない」と、今までの旋律をことごとく否定するのがチェロの役です。満場の聴衆がチェロの動きを注視しているのが分かります。到達する「歓喜の歌」の最初は、小さく弾く必要があり、過度に気持ちの高ぶりを抑え、音が上滑りにならぬよう必死で押さえながら、楽器が一番いい音で鳴るように制御します。チェロで弾かれる朗々と歌う旋律が、満場の観客の注視の中で静かに流れます。合唱が入ってきました。オーケストラの伴奏で、合唱が絶叫します。オケと合唱の約400名が1つになり、「歓喜の歌」を高らかに歌い全力で疾走します。第9を弾くときは人生で何度かしか味わえない満ち足りた時間が過ぎていき、不思議な高揚感で至福なときです。チェロとともに生きる実感を持てるのです。
今回の演奏で、気がついたことは、第1楽章で登場する、付点音符がついた音の形(ター ンタタタタン)が、第4楽章の最後の最後で、同じようなところにつながっていること。つまり、あの第九の緊迫感は、最初から最後まで一貫していたことにきがつかされました。やはり、ベートーヴェンは演奏のたびに、新たな発見があるものです。
早稲田大学2016フロイデメモリアル演奏会の演奏風景です。ほんの少しですがお裾分けです。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPはソナー・メンバーズ・クラブをクリックして下さい。
赤とんぼとシューマン
2017 JAN 8 5:05:06 am by 野村 和寿

前回のボクのブログで、「夕焼け小焼け」を御紹介しましたが、もうひとつの
「夕焼け・・・」ではじまる童謡「ゆうやーけこやけーの あかとんぼ」。そうです。今回は「赤とんぼ」を中心として、シューマンとの関係を語りたいと思います。ボクは長い間、「夕焼け小焼け」と「赤とんぼ」とを混同して疑いませんでした。申し訳ないです。
「赤とんぼ」は、1921(大正10)年に雑誌「眞珠島」に掲載された三木露風の詞を元に、山田耕筰が1927年に作曲した童謡です。
赤とんぼ(作詞:三木露風、作曲:山田耕筰 1927年)
1, 夕焼け小焼けの 赤とんぼ 負われて見たのは いつのひか
2, 山の畑の 桑の実を 小籠(おかご)に摘んだは、まぼろしか。
3, 十五で姐(ねえ)やは嫁にいき お里のたよりも 絶えはてた
4, 夕焼け小焼けの 赤とんぼ とまっているよ 竿の先
赤とんぼ 由紀さおり 安田祥子(うた)
シューマンの「ピアノとオーケストラのための序奏とアレグロ・アパショナート ト長調 作品54」を聴いてみますと、少なくとも、ボクの聴いた限りでも、
全体の演奏時間13:48のなかでも、2:53、3:06,3:15、4:48、5:47、5:56,7:35,10:31、10:43に山田耕筰の「赤とんぼ」中の「ゆうやーけこやけーの」のメロディーと、瓜二つの部分が登場してきます。
まずは、お時間があれば、この映像で聴いてみてくださいませ。
シューマン ピアノと管弦楽のための序奏と協奏的アレグロ op134
アンジェラ・ヒューイット(ピアノ独奏)、アンドリュー・マンツェ指揮BBC交響楽団 2011年プロムス 8月14日Prom48 Brahms&Schumann ロイヤル・アルバートホールでの演奏です。
よりその部分だけの抜き出した映像もありました。
1981年(昭和56)年4月12日付けの夕刊フジ紙に、作家の吉行淳之介氏(1924大正13年−1994平成6年)が発表した見出し「赤とんぼ・・・シューマンから飛び出した!!ピアノと管弦楽作品聞いていた そっくり旋律18回も」とまるで、スクープ記事のような大見出しの記事を掲載しました。
この夕刊フジの記事の元ネタはの文藝春秋の昭和56年(1981年)9月号に吉行淳之介の寄稿したエッセイからきています。
ボクがシューマンの「ピアノとオーケストラのための序奏とアレグロ・アパショナート」のなかで、数えて「赤とんぼ」のメロディーだと思ったのは9回でしたが、上記記事では18回とありました。
この記事以前にも1963(昭和36)年に石原慎太郎氏がドイツの友人から聞いた話として、ある雑誌で「ドイツの古い民謡だ」と発表し、当時存命中だった山田耕筰の猛抗議をうけています。
▇ボクの推理
山田耕筰(1886明治19年〜1965昭和40年)は、1910(明治45)年から1914(大正3)年にかけて、ドイツ・ベルリン(当時のプロイセン王国)の王立アカデミーに留学して、作曲家マックス・ブルッフ(1838−1920年 チェロの名曲「コール・ニドライ」の作曲者で有名)に師事しています。留学中に日本初の交響曲「勝ちどきの平和」を作曲したりしています。
彼が帰朝後「赤とんぼ」をスケッチして作曲したのは1927(昭和2)年です。
いっぽう、ロベルト・シューマン(1810〜1856年)が、本曲を作曲したのは1849年のことです。
山田耕筰が、ベルリン留学中にシューマンの「ピアノとオーケストラのための序奏とアレグロ・アパショナート ト長調 作品54」を演奏会で聴いたことは、十分にありえるのです。
ボクは、シューマンはドイツの古い民謡からメロディーを採った→山田耕筰はそのシューマンからメロディーを採って「赤とんぼ」を作曲したのではないかと思います。ただ、クラシックの世界では、別の作曲家のメロディーを、ほかの作曲家が、本歌取りするという例はほかにもたくさんあり、それが、悪いといっているのではなくて、クラシック音楽というのは長い間、メロディーをそうやって伝えてきたともボクは、考えています。
*ちなみに、以前「赤とんぼの謎」というCDがキングレコードから2004年に発売されたことがありました。今でも購入可能です。世界40カ国以上で歌われている「赤とんぼ」の謎について集めたテノール・ヘフリガー、バイオリン・カンポーリ、フルート・ランパルまで24種類の音源を集めたCDでした。
*ちなみに本題から外れますが、シューマンの映像中、ピアニスト・アンジェラ・ヒューイットが弾いているピアノは、ベーゼンドルファー、スタインウェイ、ヤマハといった大メーカーのピアノではなくて、イタリアのFazioliファツィオリというブランドのピアノです。1981年に出来たばかりの新進ですが、最近人気になってきました。音が柔らかで優しい音が特長です。
ピアノ工房はイタリア・ベニスから北へ60キロメートルのサチーレにあります。ご興味ある向きには下記をご覧くださいませ。
社史の映像はこちらから
社史はこちらから
工場ツアー映像はこちらから
*シューマンは音楽評論家もしていたので『音楽と音楽家』(岩波文庫青502 Ⅰ)という興味深い評論集が出ています。ちなみにこの評論集は、音楽評論家の吉田秀和氏(1913大正2年〜2012平成24年)が翻訳し、吉田氏の最初の著作で1941(昭和16)年2月に創元社から出版されました。なんと戦争の始まる年です。今も絶版にはならず刊行中です。非常に面白いです。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPはソナー・メンバーズ・クラブをクリックして下さい。