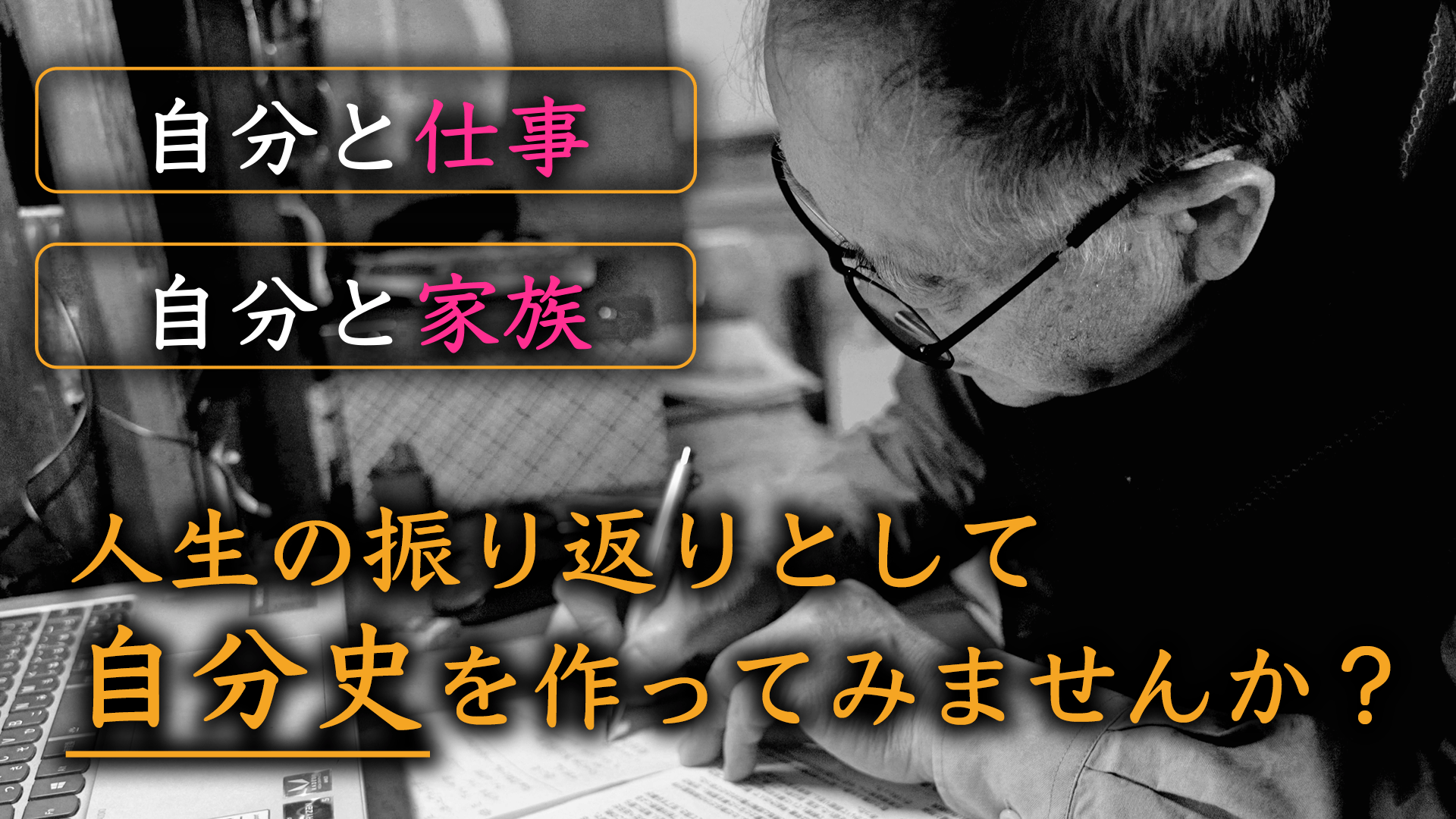河村尚子の快進撃は続く
2022 SEP 22 17:17:25 pm by 大武 和夫

今回の来日でも河村さんは大活躍。首都圏だけでも、8月24日のベーゼンドルファー東京ショールームでのミニコンサート(シューベルト)に始まり、朝日カルチャーセンターでの音楽学者堀朋平氏との対談によるシューベルトを巡るレクチャー、ヴァルチュハ/読響とのブラームスのピアノ協奏曲1番の2回の演奏、読響メンバーとの弦楽五重奏版(!)のシューマンのピアノ協奏曲の2度に亘る演奏、アフラック・クラシック・チャリティーコンサートにおける海老原光/東響とのシューマンのピアン協奏曲の後、紀尾井ホールでのリサイタル(シューベルト)、そしてコバケン/日フィルとのブラームスのピアノ協奏曲1番と大車輪でした。その間に山形でもリサイタル(シューベルト)を開いておられます。これらは、多岐に亘るイベントのように見えて、実はシューマンとブラームスに集中しておられ、びしっと一本筋が通っています。そして、9月19日の兵庫でのリサイタル(シューベルト)を終えて、ドイツに戻られました。台風が近づいている状況でのご帰国ですから気を揉みましたが、20日には無事にドイツに戻られた由で、ホッとしました。
シューベルトを巡るレクチャーは2回目ですが、実に興味深いお話に加えて、その場でD. 960の第2楽章を弾かれるというおまけ付き。何と贅沢であったことか。
そのシューベルトの演奏は、ベーゼンのショールームと紀尾井ホールとで2度聴いたD. 960も、紀尾井だけで聴いたD. 959も、驚きに満ちた演奏でした。
一言で言えば、どんな哀しみ、苦しみの中にあっても希望を失わず、常に命が躍動する音楽を書き続けた音楽家としてのシューベルトを描き切った演奏、というのが私の聴後感でした。
カルチャーセンターで河村さんは大略、シューベルト晩年の作品には、梅毒という業病に苦しむ中で罹患前の楽しい時間を回顧する喜ばしげな楽想と、直面する激しい痛み、苦しみ、そして哀しみに彩られた痛ましい楽想のめまぐるしい交代が特徴的だが、自分(河村さん)はシューベルトの本質はオプティミストだと感じる、というようなことを語っておられました。よく「絶望」という表現がシューベルト晩年の作品について用いられますが、絶望とは全ての希望が絶たれた救いの無い状態を指します。つまり、希望など持ちようも無い状態の表現です。そのような大方の視点に抗って、シューベルトの本質はオプティミストであると喝破した河村説(大げさかもしれませんが)に、私は驚くとともに深く共感しました。
例えばD. 944のハ長調大交響曲フィナーレ。一体本当の絶望から、あのように無限の喜びがこんこんと湧き出てくるものでしょうか。いや、絶望の淵にあってこそ救いを求めたくなるのだし、魂の喜びへの渇望が湧き出すのだ、という反論もあるでしょう。しかし、それは言葉の遊びだと私には思えます。そういう小賢しい理屈をこねくり回すぐらいであれば、河村さんに倣って、どんな時でもシューベルトは本質的にオプティミストであった、と言うことを選びたいと思います。
D. 960のフィナーレに込められた希望は、河村さんの演奏によって露わです。重苦しい情趣が支配的なソナタの中にあって終曲は少し軽すぎるのではないかと、以前の私はやや不満に思っていました。しかし、ホロヴィッツの再録を聴いたあたりから、いや、これこそシューベルトがこの曲を絶望の淵に沈めたくなかったことの証ではないかと思い始めていました。その私の漠然とした思いに形を与えてくれたのが、今回の河村さんの発言であり、実際の演奏でした。具体的には、付点音符と三連符の組み合わせ(言うまでもなく大ハ長調交響曲にも特徴的です)が、希望の象徴だというのが今回私が強く感じたことです。希望が、血肉をまとった魂を躍動させる、というような言い方をしてみたくなります。肉体を伴う魂が希望に鼓舞されて踊っている・・・。ここでも、河村さんならではの躍動するリズムが見事です。ちなみに河村さんは、カルチャーセンターで堀先生のご質問に対して、踊ることが好きですと答えておられました。さもありなんと膝を打ったのは私だけではないでしょう。(優れた音楽家と運動神経というテーマでも、いずれ書きたいと思っています。ピンポンの名手であったハイフェッツ、航空機パイロットでカーカーレーサーでもあったミケランジェリ等々。)
世間で決定的、歴史的名盤との評価が高いリヒテルのD. 960の商業録音(他にも彼の同曲のライブ音源は山ほどあります)に欠けているのは、この要素だと今になって思います。無論素晴らしい演奏ですし、「絶望」の深い淵からの叫び、うめきとして至高の表現だと思います。しかし、リヒテルの演奏で聴くと、そうであるが故に、いかにも終楽章の収まりが悪いと思えるのです。喜びに満ちた楽想と思える箇所も、絶望に塗りつぶされた全曲の中にあってはそのように表現することが許されない、とでも言うかのような弾きぶりです。一般に私はリヒテルに対して極めてアンビヴァレントなのですが、ここでも、ソ連という抑圧社会の中で生き抜いた天才芸術家の悲劇、ということを思わざるを得ません。つまりリヒテルの表現は、あの特殊な歴史社会的条件の下であの決断(亡命しないという決断)を行った天才芸術家に固有の表現であると。(あらゆる状況は歴史的産物であり、あらゆる表現は何かしらの決断の結果であるという茫漠とした一般論とは、全く次元の違う話です。)
シューマンについても書きたいことが沢山ありますが、今日はどうしても書きたいブラームスについて書きます。(後日続編としてシューマンについても書くことになりそうです。そのくらいシューマンにも大きな感動を与えられました。)
ブラームスの協奏曲1番。我が偏愛の曲です。2番も素敵ですが、どちらを選ぶかと言われたら、私は躊躇なく1番を採ります。私にとってこの曲の「肝」は、終楽章の最初のカデンツァの後まもなく始まる、上行・下行を繰り返す右手の雄大なスケールとそこに楔のように打ち込まれる左手のコントラスト、そして次第に高揚する音楽が遂にたどり着く二つ目のカデンツァ、この二箇所に尽きます。
二つ目のカデンツァはゲネレル・パウゼになだれ込むのですが、そのゲネラル・パウゼの直前には、ブラームスによってアッチェレランドの指定が与えられています。以前に東さんにそうお話したら、ブラームスにアッチェレランドは珍しいという指摘を受けました。ピアノ以外のレパートリーに関しては彼の博識の足許にも及ばない私は、そうですかとしか返事できなかったのですが、ブラームスのオーケストラ曲には確かに珍しいような気もします。これは、この曲が若書きで、「遅れてきた疾風怒濤」とも言うべき激情に彩られているからだろうと考えます。(聴き巧者である敬愛する友人S氏は「1楽章冒頭からして『クララ!』と叫んでいるみたいじゃないですか!」との卓見を披露してくれました。)いずれにしても、そのアッチェレランドが如何に難しいことか。ここではピアニストの全力量が試されます。
両手が単純な音形を繰り返すごく短い時間の中でアッチェレランドすることがどれほど難しいかは、実例を聴くとよく分かります。ここで討ち死にする例は枚挙に暇がありません。成功例としてホロヴィッツ(ワルターとの伝説的実演の方)、R.ゼルキン、シュナーベルと言った名前を私が挙げるだろうと予想された方は正解ですが、他には、カッチェン、アンスネス、ルプー、フレイレ、そして大好きなカペルを挙げたいと思います。アッチェレランドが始まる直前でテンポを揺らして(緩めて)おいてアッチェレランドに移行するというのはよく見られる解釈で、河村さんもそう弾いています。しかしその移行の自然さには息を吞みます。リズムの弾力性も他に類を見ません。(全曲を通して、音色とフレージングだけでなく、リズムについても固い表現と柔軟な表現、そしてその間に存在する無限のグラデーションを使い分けるのが河村流で、これはもう後天的な訓練ではどうにもならない生来の音楽的才能、本能によるものとしか言いようがありません。)その結果得られるアッチェレランドの圧倒的なことと言ったら! そしてそのアッチェレランドがゲネラル・パウゼに結実する音楽的必然性をこれほど明快に示す演奏も珍しい。
筆がホロヴィッツに及ぶと脱線してしまうのが悪癖であることは、皆さんもう覚悟しておられると思いますので、前段落での言及を受けて少しだけ脱線しますと、ホロヴィッツのワルターとの共演(1936年)はこのあたりの呼吸が実に見事で、河村さんと双璧と言いたくなります。もっともトスカニーニと組んだ実演(1935年)では、あまりにもトスカニーニが直線的に煽るものですから、テンポを揺らす余裕が奪われてしまい、アッチェレランドが驚異的であるのに殆ど印象に残らないという残念な結果に終わっています。今回の演奏のグランド・デザインを作ったのがコバケンさんなのか河村さんなのかは存じませんが、トスカニーニより遙かに遅い基本テンポにより、アッチェレランドとそこに至る高揚を一層強く印象付け、大きなカタルシスを聴衆に与えることに成功したと言えそうです。
ご存じの通り、曲はピアノ抜きのオケのトゥッティで終わりますが、そこでピアノがガツンと鳴らないところが如何にもブラームスらしくて素敵です。演奏によってはそのことを物足りなく感じさせるのですが、流石は河村さんとコバケンさん、そのような愚は犯さず、幸福な全き充足感のうちに曲は終結します。
河村さんの音楽の特質の一つとして、細部に工夫を懲らしつつも「木を見て森を見ない」ことが皆無であるという見通しの良さ、楽曲構造の把握の見事さが挙げられます。そのことに照らしますと、楽曲のごく一部に拘る上記のような印象批評こそ、実は河村さんの芸術の対極に位置するものと言えるかもしれません。本稿をお読みになったら(以前にブログを見ているとおっしゃっていました。)河村さんはきっと、大武さん、そういう聴き方はいけませんよ、とおっしゃるでしょう。でも、以前にも書いたように、これは万人に向けた「批評」ではなく、タイムカプセルとしての私的心覚えなのですから、それでも良いと私は割り切っています。河村さんの思いとかけ離れた聴き方をしてしまっている可能性が大であることを、読者の皆さんと他ならぬ河村さんにお詫びしておきます。
数段落上に、終楽章の二箇所が肝だと書きました。あまりに長くなりますので、そのうちのもう一つの箇所(右手の雄大なスケールの箇所)については、今回は触れないことにします。これまた心を沸き立たせ、終結に向けた高揚感をいやが上にも高めるする素晴らしい弾き振りだった、とだけ書いておきましょう。
よくリストのソナタはピアニストのあらゆる能力・資質を丸裸にする危険なレパートリーだと言いますが、それと同じくらい、いや場合によるとそれ以上に演奏者の全力量を白日の下に晒してしまうのが以上の二箇所だというのが私の持論です。その両者で聴き手の心を鷲掴みにし、音楽が要求する呼吸と拍動を聴き手に身体で感じさせ、夢中な状態の聴き手をコーダまでぐんぐんと引っ張って行く河村さんの力量には、脱帽の他ありません。
このブラームスを含む日フィルのコンサートの全体については、テレビマンユニオンの「Member’s TVU Channel」というサイトで配信が行われています。宣伝料をもらっているわけではありませんが、当日足を運ばれなかった方には(運ばれた方にも)是非とも視聴されるようお勧めします。有料(1000円)の価値は十分にあります。但し、スマホでは当日の感動のほんの一部しか味わえません。iPhoneですとAirPaly、Androidスマホの場合はそれに対応する機能/アプリ(そういう機能/アプリがある筈です)を利用して、テレビ等の大画面に映像を投影し、音はできればテレビ以外のスピーカで聴くという環境を整えることによって、当日の体験にかなり近い感動を味わうことが可能であることを申し添えます。
指揮のコバケンさんが、舞台の奥で河村さんのアンコール(ブラームスのOp 118-2のインテルメッツォ。配信で再度聴いても落涙してしまいます。)に聴き入り、曲の終結に向けて頭を垂れる姿がはっきりと映し出されています。最後に河村さんと一緒に再度ステージに登場したコバケンさんは、感動さめやらぬ聴衆の拍手を制してから、大略次のように話されました:「私たち [ ご自分とオケという意味でしょう ] は茫然と聴き入っておりました。彼女は、世界でただ一人という凄い存在になってくれると思います。皆さん、河村尚子をよろしくお願いします!」
心から出たコバケンさんの感動的なスピーチを聴きながら、私は心の中でこう独りごちていました:「ありがとうコバケンさん。でも、河村さんは既に世界で唯一の凄い存在になっていますよね!」と。
忘れられない出会い~音楽編(第1回)完結編
2022 AUG 26 18:18:05 pm by 大武 和夫

(承前)
コラールを聴き、キース・ジャレットに魂を奪われて乗り込んだのが、シアトルのオペラハウス。76年1月のことです。N君、N君弟と私が並ぶ3つの席は、はっきりとは覚えていませんが、天井桟敷というほどではないかもののピアノからは遠く隔たった上階の席でした。
最初に鳴り響くピアノの音に驚倒。なんという豊かさ! 響きも音楽の造形も豊穣の極。ffでも全く割れることのないまろやかな音は、RCAとコロンビアの録音でなじんでいたものとは大違いでした。無論広大なダイナミック・レンジは健在で、ppの繊細さも録音とは桁違いなのですが、とにかく圧倒的に豊かな音楽に最初はびっくり仰天し、それはすぐに感動に変わっていきました。そして、ピアニストは実演を聴かないと分からないと痛感したことでした。
件(くだん)のシューマンの3番が、なんと豊かに、そしてその場で生起する有機的な音楽として、美しく鳴り響いたことでしょう。この曲が出版社によってオーケストラ抜きの協奏曲と名付けられたのはこういうことなんだ!・・・そう思いました。その豊かな音楽に浸りながら、自分は今生まれてこのかた味わったことの無い感動に酔いしれている、とも思いました。
それまでにも私は、数々の名ピアニストを聴いています、リヒテル、ギレリス、シフラ、ペルルミュテール、アニー・フィッシャー、R. ゼルキン、ミケランジェーリ、アラウ、バレンボイム、アシュケナージ、アルゲリッチ、ゲルバー、ポリーニ等々。録音だけで知っているラフマニノフ、レヴィーン、ホフマン、ギーゼキング、バックハウス、コルトー、ケンプ、エトヴィン・フィッシャー、ルービンシュタイン等々を加えると大変な数になります。それらの実演・録音(ホロヴィッツ自身の録音も加えて)を聴くうちに、ピアノという楽器はこういう音がするものだという「物差し」が自分の中にできていました。ところが生で聴いたホロヴィッツの音の、そして音楽の豊かさは、その「物差し」には到底収まりきらない、文字通り桁外れのものでした。アンコールの1曲として弾かれたラフマニノフの2番のソナタの終楽章といったら、月並みな言い方ですが、まるでフル・オーケストラが舞台に載っているように聞こえました。
あまりの感動にフラフラしつつ、私はN君とN君弟にほとんど何も言わず(言えず)に、ひとりで楽屋に向かって駈けだしていました。楽屋入り口で誰何されとことは覚えていますが、何と言って切り抜けたかは忘れてしまいました。ともあれ、その時点ではまだ英語を自由に話せなかった私は、今から振り返ると奇跡的なことに、入り口の検問を突破して、グリーン・ルームに足を踏み入れていました。
そこに座ってくつろぎつつwell-wishersと歓談しているホロヴィッツその人を見たときには、頭がクラクラして倒れそうになりました。必死の思いで話した言葉は覚えていませんが、横にいた当時のマネージャー、ハロルド・ショーとワンダ・トスカニーニ・ホロヴィッツが、この若者はわざわざ友人と2人ではるばる東京から、あなたを聴きにやってきたのだと説明してくれたようです。するとホロヴィッツはすくっと立ち上がって、良く来てくれた、ありがとう、と握手を求めるのです。夢心地で握手を交わしたら、ホロヴィッツは、君はピアノに向いた良い手をしている、掌の肉が厚く柔らかいね、とお世辞を言うのです。ドギマギしていると、今度はワンダ夫人が東京のホールはいくつかあるようだが良いホールはどこか、と尋ねるではありませんか。音で言えば文化会館大ホールでしょうと即答すると、ホロヴィッツ自身は、聞いたことがあるぞ、良いホールらしいね、NHKホールの音響はどうかな?などと聴くのです。関係者には申し訳ありませんが、NHKホールの音響については否定的なことを話したと記憶しています。
誰しもこの会話の当事者であったなら、間もなくホロヴィッツは公演のために来日する積もりだな、と思うでしょう。実際にはあの破滅的な初来日にはまだ7年もかかるのですが。(そして初来日時には、今度は私が米国留学中でした。)
後に続くwell-wishersの時間を奪ってはいけないと、夢から覚めかけて考えた私は、最後にもう一度ホロヴィッツと握手して楽屋を出ました。
しかし、初めて訪れた街の初めてのオペラハウスですから、運転して連れてきてくれたN君弟の車がどこに停めてあるかなど、さっぱり分かりません。このまま野宿することになるかもしれないと暢気に考え始めたときに、N君とN君弟が、こっちを見つけてくれました。
無鉄砲というか、無思慮というか、向こう見ずというか、今から振り返ると信じられない思いです。私を長いこと探してくれていたに違いない2人は、さぞかし呆れたことでしょう。感謝の他ありません。
でも、楽屋を訪ねたお陰でハロルド・ショーとの文通が始まり(携帯やメールが誕生する遙か以前のことです。)、その後2回に亘ってホロヴィッツの米国での演奏会に招待されることになりました。(もっとも、当然のことながら旅費・宿泊費まで出してくれる訳ではありませんから、招待を受ける方も大変です!)
また、そのときは楽屋にいたことに気付きもしなかったホロヴィッツのtravel companionであったマダム・ホーウィッチという老女にはその後何度もお会いし、ホロヴィッツに関する興味深い逸話を教えてもらったり、つい先日惜しくも逝去された野島稔さん(当時NYに住んでおられました。)を紹介してもらったりしたのですから、出会いとは実に不思議なものだと思わざるを得ません。
後日譚をひとつ。
ハロルド・ショーは、RCA復帰後の録音のテスト・プレスLPを何枚か送ってくれました。シアトルでの演奏会の次の演奏会はパサデナで、そこでホロヴィッツはスクリアビンの5番を弾いています。実は、シアトルでの演奏会当日だったか前日だったかの現地の新聞に、日本からツアーを組んでホロヴィッツを聴きに来た人達(著名音楽評論家某氏に率いられていたという記憶です。)をホロヴィッツがホテルの客室に招いたという記事が写真入りで出ていました。表敬訪問自体は記事の前日か前々日だったと思われます。そんなツアーが組まれていたとは全く知らず、日本から聴きに来たのは我々2人だけだろうと思っていた私は、些か拍子抜けしましたが、本当に悔しかったのは、彼らは(全員ではないかもしれませんが)パサデナに移動して次の演奏会も聴く、そこではスクリアビンの5番がメインだと新聞に出ていたことです。
この辺まで来ると、ごひいきのスターに熱狂し、そのスターと常に行動を共にして他のファンを出し抜こうとする「追っかけ」ヅカ・ファンみたいだと我ながら苦笑してしまいますが、その時点ではリヒテル盤(DG)でしか聴いたことが無く、凄い曲だと思っていたスクリアビンの5番をホロヴィッツがどう弾くのか、あの豊かで繊細極まりない音でスクリアビンの狂気がどう表現されるのか、興味津々でした。ですから、パサデナまで行く日本人一行が、ことさら羨ましく思えたのです。(ちなみにN君と私は演奏会の翌日だったか翌々日にシアトルを発って、グレイハウンドでサン・フランシスコまで、26時間だか28時間だかのバス旅行を敢行しました。Those were the days. そして我々は若かった。)
司法修習生になり、任地であった京都で1年半弱に亘ることになる下宿生活を始めていた私のもとに、記念すべきRCA復帰第一弾のテスト・プレスがハロルドから送られてきました。NOT FOR SALEとレーベルに明記してあった盤を見て狂喜したことを鮮明に覚えています。
当時は狭い下宿で貧しい生活を送っており、東京から持参したのはオープンリール・テープレコーダーとFMチューナー、それにヘッドフォンだけでしたから、そのテスト・プレスを聴くためには、裁判所の近くにあったクラシック喫茶に持ち込むしかありません。そして、客の少ない時間帯に、マスターと一緒にスクリアビンの凄演に聞き惚れました。物凄い起伏とドラマ、千変万化の音色と感情の燃焼。リヒテル盤は技術的には恐らく上で、実演なのにほぼ完璧なのですが、最初から凄まじい爆発と沈潜の繰り返しで、曲の構造が分かりませんし、ややモノクロームで飽きそうになります。それに、聴いていて自分が曲のどこにいるのか分かりません。それに対してホロヴィッツの計算は実に緻密で、何段階にも亘るテンポと強弱の変化、それにペダリングを含めた音色の微妙な設定により、曲がどこに向かっているのかがよく分かり、クライマックスが間もなく訪れそうだということまで聴き手に切迫感とともに理解させます。それでいてクライマックスが予定調和的に響くことは全くなく、地球が爆発しそうな凄みは、リヒテルに勝るとも劣りません。シューマンの3番は実演を聴いていますから、その感動には勿論及びませんが、それでも、豊かで充実した実演の音が、コロンビア時代より的確に捉えられているように思えました。(その後遙かに良い装置で聴けるようになってからは、コロンビアの音の良さを改めて認識するようになり、現在では、どちらの音を好むとも言いがたくなっています。)とは言っても、他のお客さんとマスターに遠慮しながら持参LPを掛けてもらうのですから、遠慮が先に立ち、何度も聴くというわけにはいきません。もどかしくてなりませんでした。しかし、それが今となっては懐かしいのです。聴こうと思えば文字通りいつでも聴ける現在の聴環境より、不自由だった当時の方が真剣に鑑賞できていたのではないかと言う気もします。
時が経ってCD時代になり、LPの名盤が次々にCD化されます。そして、シューマンの3番とスクリアビンの5番をカップリングしたこのRCAの名盤も、比較的早い時期にCD化されました。発売されるやすぐに買い求めたことは、ご想像の通り。しかし、一聴して仰天しました。シューマンの1楽章冒頭がなんだか変なのです。そう、編集ミスで、始まってすぐの箇所に数拍分の脱落があったのです。レコード屋に指摘しても埒があかないので、編集担当の名プロデューサー、ジョン・プファイファーに手紙だったかファックスだったかを送りました。彼は誠実な人で、無名の日本人ファンの指摘に耳を傾けてくれました。そしてしばらくして寄こした返事には、ご指摘の通りの脱落がある、申し訳ない、しかし貴方は良い耳を持っている、とありました。楽譜を読める人が譜を見ながら聴けば一発で分かる編集ミスですし、そもそも拍節感のある人なら、たとえ曲をよく知らなくても、聴いてすぐにおかしいと分かる筈です。ですから、お世辞もたいがいになさい、自分のミスを小さいミスだと言いたいがための修辞ですね、と書きたかったのですが、過ちを認めて謝ってくれた誠実さに免じて、それは控えました。そして、編集し直して脱落を修復した盤ができあがると、親切なプファイファーはそれをプレゼントしてくれました。これにはちょっと驚きました。編集ミスのある初期盤を取っておけば歴史的価値があったかもしれませんが、LPを米国プレス、英国プレス、ドイツ・プレス、オランダ・プレス、。フランス・プレス等々の各国盤で揃えていましたから、正しく編集されたCDが届くや、ミスのあるCD盤は捨ててしまいました。当時の私は、まだLPの方を大事にしていたのですね。ちょっと惜しかったかなと思わないではありません。(LP時代のホロヴィッツの新譜は可能な限り各国盤を揃えていたのですが、今振り返るとなんとも勿体ないことに、スペースの関係でほぼ全て捨ててしまいました。これは、無慮数千枚の他のLPについても同様です。)
そういうわけで、ホロヴィッツが弾くシューマンの3番とスクリアビンの5番は、私にとって特別中の特別、またまた古い表現で恐縮ですが「別格官幣社」なのです。シューマンの3番を聴くと、グリーン・ルームでのホロヴィッツとの会話がまざまざと思い出されますし、スクリアビンを聴くと、今は亡きハロルド・ショーとの文通や京都のクラシック喫茶の光景がくっきりと蘇ります。そして蛇足を付けくわえるなら、京都に思い
を馳せると、決まってある日の河原町のジャズ喫茶での体験を思い出します。修習生生活を終えて帰京するその日に、何回となく通ったジャズ喫茶に別れを告げに行きました。私の好みを知っているマスターがかけてくれたの、出たばかりのキースの新譜「My Song」。タイトル曲におけるヤン・ガルバレクの繊細で透明感溢れるソプラノ・サックスに魅了され、ピアノが戻るあたりのアンサンブルの見事さと静かな盛り上がりに、息を飲みました。でも、コラールの真価を私が理解するには、まだ長い歳月を要します。
(この稿、完)
忘れられない出会い~音楽編(第1回)
2022 AUG 18 17:17:18 pm by 大武 和夫

忘れられない曲、演奏会、演奏家、作曲家、録音等との出会いと、その出会いを可能にしてくれたきっかけについて、備忘録として書きます。「きっかけ」は、人であったり、書物であったり、演奏会であったり、様々です。
第1回は三題噺です。ホロヴィッツ、ジャン=フィリップ・コラール、そしてキース・ジャレット。不思議な組み合わせとお考えかもしれません。これらの演奏家との出会いのきっかけを作ってくれた恩人は、永年の友人N野君とその弟さんです。
舞台は46年前のシアトル。当時シアトルに留学していたN君弟がN君を通じて私に、ホロヴィッツが翌年正月にシアトルに来て弾くという知らせをもたらしてくれたのは、1975年のことでした。数十年ぶりの西海岸での演奏会という触れ込みでした。その頃までには私のホロヴィッツ狂ぶりは友人の間で知れ渡っていました。軍資金も無いのに、同居の叔母に借金をすることを前提に(!)「行きたい」と即答した私でした。短答試験に落ちて大学を留年し、ようやく司法試験に受かった直後のことです。
貧しい家に育ったので海外旅行などしたこともありません。他方、N君は裕福な名家の御曹司で、既に海外旅行の経験者でした。でも心優しいN君は、こちらの懐事情に合わせて格安フライトに付き合ってくれました。中華航空便でハワイまで。数時間のトランジットを経てコンチネンタルに乗り換えて、シアトルまで。シアトルの空港に近づき高度を下げると、美しいシアトルの町並みが目に飛び込んできました。初めての西海岸、いや初めてのアメリカ本土。感動で胸が高鳴りました。ハワイでは待機時間中にワイキキビースを踏んでこようということになり、冬の厚いセータ姿でビーチを訪れました。何をするでもなく、汗をかきながら(!)ビーチを男2人で散歩するという、それだけのことでしたが、何故だかそのことはいつまでも忘れません。「コンチネンタル」の発音が「コンニネンナル」と聞こえたことも。
三題噺の最初の登場者ホロヴィッツ(の実演)との出会いは、以上の通りです(演奏会当日のホロヴィッツその人との「出会い」については後ほど詳述します)が、ではコラールが何故三題噺に登場するのか。
ホロヴィッツが弾く予定のプログラムがN君経由でもたらされたのは、確か日本を発つ2日前のことだったと記憶しています。そして、その中に聴いた事の無い曲を発見した私は、出発前日に渋谷のヤマハに飛んで行きました。(当時道玄坂中腹にあったヤマハ渋谷店には、大学の帰りによく寄っていました。)幸いなことすぐに見つかったLPが、コラールのデビュー録音であるシューマン集。その中に、ホロヴィッツで間もなく聴くことになる3番のソナタが収録されていたのです。東芝EMI盤のジャケットには、遠山一行さんのコラール讃とも言うべき解説が載っていましたっけ。美しい文章でした。
帰宅するやすぐさま針を通しましたが、当時の私のヤクザな耳には、さほどの名曲とは聞こえませんでした。よく知っている2番や、せめて1番だったら良かったのに、とホロヴィッツの選曲に文句を付けたくなる始末。でも、出発前に通して3回ほど聞けたお陰で、それなりに曲になじむことができ、シアトル・オペラハウスでのホロヴィッツのリサイタルに臨む予習としては、まずまずであったと思います。春秋社版のスコアを持っていたので、ちょっと弾いてみましたが、下手くそなアマチュアの手には余るパッセージが頻出し、さじを投げました。繰り返しが多いことにも閉口。繰り返しの多さはシューマンのトレードマークではありますが、知っている曲における繰り返しと初めて聴く曲の繰り返しとでは、全く印象が異なります。(知っている曲だと繰り返しが楽しみになったりしますが、知らない曲の繰り返しにはうんざりさせられる確率が高いというのが卑見です。私のような凡庸な聴き手にだけ当てはまることなのかもしれませんけれど。)この心理的効果に気付くのは、ずいぶん先のことです。
この時点では、コラールが晩年のホロヴィッツと親交を重ね、大きな影響を受け、深く尊敬するに至ることなど知る由もありません。コラールを通して初めて知った3番のソナタにあまり感動しなかったということは、曲の真価のみならずコラールの真価をも、全く捉えることができなかったということでしょう。情けない話です。このデビュー録音を聴き直して感心するようになったのは、遙か後年のことです。ホロヴィッツはどうやらコラールを通じてフォーレを深く知り、愛するに至ったふしがありますが、ひょっとするとシューマンの3番についても、コラール盤に刺激されて久方ぶりに取り上げようという気になったという可能性がありそうです。推測に過ぎませんが。
コラールは本当に素晴らしい芸術家で、近年ポツポツと発売される新譜は、皆宝です。コラールについては、フォーレの難しさ(コラールでさえ譜読みで間違えている箇所がある!)と併せて、稿を改めましょう。
さて、どこに行っても大都市なら必ずレコード店に立ち寄る癖のある私は、N君と街の案内役兼運転手を買って出てくれたN君弟にお願いして、シアトル随一のレコード屋に連れて行ってもらいました。ホロヴィッツのリサイタルの前日のことだったと記憶しています。
店内に足を踏み入れた瞬間に耳を捉えたのは、聴いた事も無い音楽。寄せては返す波のようなうねりの、ロマンティック極まりない音楽。しかし、どうやらクラシックではないようです。耳をそばだてるまでもなくブルーノートの多用に気付きます。そして、ブルース調、ブギウギ調とめぐるしく変わる曲想の虜になっていました。どこか永遠を思わせる透明な・・・しかし少しだけ魅力的なひずみを抱えたような・・・美しい響きにも心を奪われました。グルーヴィーでありながら、ポリフォニックな展開もあり、フレーズや和音が反復されそろそろ嫌になりそうな頃合いで見事に転調と曲想の転換を決める鋭敏なセンスには、舌を巻きました。物凄い音楽的教養の迸り。
恐らくジャズ・ピアニストだろうとは思いながらも、それまでに知っていた数少ないジャズ・ピアニスト達・・・ビル・エヴァンス、バッド・パウエル、デューク・エリントン、レニー・トリスターノ、チック・コリア等々・・・とは全く重なりません。この音楽の弾き手は、確実に私にとって未知のピアニストだと思いました。気付いたときにはレジに直行し、今かかっているその盤をくれ、と言っていました。それが、あの名盤「ケルン・コンサート」との、そして天才キ-スとの出会いでした。
泊めてもらっていたN君弟のアパートに戻った3人は、私が持参して皆で聴こうと提案していたコラール盤に耳を傾けました。しかし、コラールを聴きながらも私は、早くケルン・コンサートの続きを聴きたいものだと思っていました。時間的制約がある上に、何と言っても転がり込んだ居候の身で我が儘は言えません。結局キースは2枚組LPの1枚目の表を聴き通せただけでした。残りを聴くのは帰国後になります。
90年代後半の体調不良を乗り越えて演奏会活動を再開したキースが、数年前に起こした脳卒中の後遺症である麻痺状態のため、もうピアノが弾けないという報に接したのは2年前のことです。何と悲しいことでしょう。キースについても書きたいことは山ほどありますので、これも稿を改めましょう。今はただ、彼が与えてくれた美しい音楽とその感動に、心からのお礼を言うだけです。ありがとうキース!
実はそのレコード屋では、他にも1枚買って買っていました。それが、当時既に日本でも話題を呼んでいた二レジハージの録音でした。見つけた時に、しめた!と思い、ケルンコンサートと共に買ったのです。しかし、この盤との出会い、ニレジハージとの出会いは、キースとの出会いとは違い、決して幸せなものではありませんでした。買ったLPは針を通すチャンスとて無く、帰国して初めて聴きました。いや聴こうとしました。聴こうとしたものの、聴けなかったです。質の悪いアメリカ・プレスのLPには時折あったことですが、盤が反り返っていて、しかも、何故か傷だらけ。ビニールで包装してあったので、購入前に開封して盤を確認できなかったのは痛恨でした。アメリカでは検盤という文化が無いと知るのは後年のことです。
シアトルで買ったものですから、日本のレード屋で交換などできません。泣く泣くヤマハで輸入盤を買い直したましたが、その演奏には全く心を動かされませんでした。なんだか凄そうな演奏ですけれど、私には瀕死の大蛇がのたうち回っているようにしか聞こえませんでした。音が汚いことも類を見ません。その後出た何枚かの録音も同様で、落胆のほかありませんでした。
無名で終わるべき演奏家にハイライトを当てて売り出そうという商魂は、その人に失礼であるだけでなく、一般公衆を馬鹿にしています。いまでも彼を持ち上げる人がいますが、私には全く理解できません。
という訳で、ひょっとすると二レジハージとの出会いをも含めて「四題噺」になったかもしれなかったのですが、結果は「三題噺」どまりだったという訳です。しかし、時を同じくして出会ったという一点で、二レジハージもある意味で忘れがたい演奏家であると言えるかもしれせん。
長くなりましたので、続き=ホロヴィッツのシアトル・オペラハウスの演奏をめぐって=は、To Be Continuedということにさせて頂きます。
コンサートの拍手
2022 JUL 26 17:17:29 pm by 大武 和夫

あまり嬉しくない風景がすっかりコンサートホールに定着してしまいました。それは、オーケストラ・メンバーの最初の1人が舞台に現れると直ぐに拍手が始まり、延々と続き、やがてコンサート・マスターが登場すると拍手は高まり、彼/彼女のお辞儀でようやく鳴り止む、という風景です。
静寂の中で団員が出そろい、チューニングが終わって再び静まりかえったホールにやがて指揮者(と場合によってソリスト)が登場し万雷の拍手を浴びる、というのが私が理想とする風景です。そこではコンマスへの拍手もありません。
まずコンマスへの拍手から書いてしまいましょう。リーダー(コンマスの英語圏での呼び名)に拍手するのは恐らく英米の習慣で、欧州大陸では、その伝統はほとんど無いか、あるとしても歴史が浅いと思います。著名オケのコンマスと言えば欧州では大変な地位なのですから、拍手ぐらいしても良いように思えますが、コンサートの主役はやはり指揮者(とソリスト)だという考えなのだろうと推察します。その指揮者・ソリストの登場前に大きな拍手が与えられてしまうと、もうクライマックスが来てしまったように思え、指揮者・ソリストをわくわくしながら待つ楽しみが半減してしまいます。
日本でもコロナ以前のN響では、マロさんは拍手を受けていなかったように記憶していますが、現在では普通にお辞儀をして拍手を受けているように見えます。(あまりN響は聴きに行きませんので、記憶違いかもしれません。)
私にとって更に居心地が悪いのは、最初にステージに登場する団員から延々と拍手が続くことです。これが始まったのは、コロナで一切のコンサートが行われなかった数ヶ月の後、勇気を持ってコンサートを開催してくれたいくつかのオケのコンサートで、聴衆が溢れる感謝と喜びをオケに対する励ましとともに拍手の形で表現したときだろうと思います。2020年夏にそのようなコンサートのいくつかに足を運んだ私自身、同じように行動していました。それは感動的な瞬間でした。聴衆が文字通り一体となる、そういう一体感を味わえる瞬間は、実は滅多にあるものではありません。
しかし、それは非常時の感情表現であり、Life “with” Covid 19が常態となった今でも続けるべきこととは思えません。私には、今やすっかり惰性となっているように思えます。ブルーインパルスの編隊飛行に感動するのは、特別な機会に特別な思いを込めて飛んでくれるからです、あれを毎日やって欲しいと思う人はいないでしょう。拍手も、私に言わせれば同じで、現在のだらだら続く拍手は、むしろ指揮者・ソリストの登場をアンチ・クライマックス化してしまっているように思えてなりません。
もう一つ居心地がよくないのは、音楽会開始時ではなく、幕間がある音楽会における後半の演奏開始時です。前半開始時と同様のプロトコールで出迎える聴衆、それがもう習慣となっているオーケストラがあるかと思えば、後半は指揮・ソリストにしか拍手を送らない聴衆/オーケストラ/演奏会もあります。この不統一が、私には居心地が良くありません。
独奏会であれば奏者が登場するたびに拍手が起きます。皆それを当然と思って疑いません。オーケストラの演奏会における指揮者に対しても同様です。ところが、コンマスを含むオーケストラ団員に対し登場の都度拍手をするかどうかは、決まっていないように見えます。こういうことを無理に統一する必要はないと思いますし、各自の自由に任せれば良いという気もしますが、それでもなんだか割り切れない思いを持つのは、恐らく聴衆自身が新しい流儀にまだ馴染んでおらず、戸惑いを持っていて、とりあえず周囲の動きに同調しておこうという気配が見てとれ、それを私は非常に日本的で嫌だと感じるからです。
団員が登壇しても拍手を始めず、コンマスが登場しても拍手しない私は、今やホールの異端児です。最近では、なんだかそのこと自体に居心地の悪さを感じてしまいます。だからと言って宗旨替えをする積もりも無いのですけれど。
コロナ以前に戻らないものかと、音楽会に足を運ぶたびに思う今日この頃です。
素人音楽批評
2022 JUL 8 17:17:52 pm by 大武 和夫

またしても前回の投稿から随分月日が経ってしまいました。私としても想定外でした。
昨年、ある尊敬するアーティストとお話ししていて、当ブログに話が及び、ブログでは極力アーティストの悪口は書かないようにしています、と申しました。これに対し、そのアーティストは大略(=パラフレーズしています)、当然です、素人に根拠のない悪口を書かれるぐらいプロにとって迷惑なことはありません、そんなに批判するなら貴方演奏してみなさいよ、と言いたくなります、とおっしゃるのです。これは時折みかける演奏家側の反論ですが、そういって簡単に片づけられない重みがありました。当該アーティストの音楽の素晴らしさ、音楽に取り組む態度の真摯さ、そして音楽に関する限りご自分にも他人にも厳しく妥協を許さないその姿勢を熟知し、尊敬していたからです。
その会話に触発されて種々検索してみた私は、音楽の分野に限らず、匿名でなされるネガティブな批評に対する反感・憎悪の表明がいかに多いかを知りました。音楽関係者の投稿もありました。私の興味を引いたのはもちろん音楽関係者の投稿です。こっちは生活がかかっているんだ、匿名の批評なんてサイテーだぞ、ろくに音楽の分からない素人は黙っていろ、言いたいことがあるなら自分の日記に書け、公開するな!といった見解の表明です。
しかし、匿名と氏名公表の違いが問題である筈はありません。ネガティブな批評の内容や書きぶりが批評対象者から見て耐えがたいものであるが故の反論・批判なのですから、匿名かどうかは重要ではないでしょう。匿名批評はアマチュアの手になるものが多いという経験則に照らせば、匿名批評批判は、どうやら匿名性自体の批判ではなく、素人による批評に対する批判がその本質であるように見えます。つまり、匿名ネガティブ批評批判も、氏名を明らかにしたうえでのネガティブ批評の批判も、結局のところ、アマチュア批評批判に他ならないのではないか、ということです。
そのような匿名批評批判と尊敬する音楽家の批判に通底するのが、素人による批評に対する批判だとすると、これはなかなか根深い問題だぞと思われて、書きかけていた本ブログ投稿用原稿の筆がパタリと止まりました。
そして私は、いったい私のような素人にプロの音楽家の音楽作りをあれこれ言う資格などあるのだろうかと懊悩することになりました。もとより私の駄文は印象批評に過ぎず、誰の役にも立たない類のものです。それが、時としてプロの音楽家を傷付けることがあるのだとしたら、私にはそういう権利は無いな、と思ったのです。
しかし、時が経つにつれて、それは自分の投稿についての意識過剰のなせる業だと思うようになりました。世間の大多数の人々にとって私の印象批評のつぶやきなど、そもそも何の意味もありません。問題となるのは、批評の対象となった音楽家がたまたま私の文章を目にして不快な思いをしないかどうか、という点に限られるでしょう。(誰の目にも触れない媒体・・・例えば日記・・・に何を書こうが、それは基本的には言論の自由の行使として許されます。)しかし、明らかなアマチュアである私のネガティブ批評など、批評対象者であるプロの音楽家にとっては、著名評論家のネガティブな言辞に比べれば、おそらく取るに足りないものでしょう。もちろんこれは、公開に際して一定のエチケットを守り、過度に攻撃的な言辞を控え、素人である限界をわきまえた書きぶりに徹した場合の話です。実は、この最後の点こそ大切だというのが、私の結論の一部です。
それに、敢えて申せば、少なくとも日本には音楽専門教育を受けていないアマチュアの評論家は沢山います。文学部教授が文学から越境して音楽を論じる例、美術家が音楽とのコラボを通じて音楽の世界に足を踏み入れて音楽を論じるようになった例、更には一番多い例としては、マスコミ(新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等々)で芸術関係担当部署に配属されたことから音楽批評に手を染めて評論家になった人達・・・。そういう人達に比べて、自分は一体何が劣っているのだ?という気持ちも、次第に湧いてきました。
ただただ本サイトの趣旨に則って、こういう人間がいてこういうことを感じ、表現していたという証を、未来へのタイムカプセルの内容として記録に残す、それだけを目指します。その過程で傷付かれる方がもしいらしたら、是非お知らせください。名誉にかけて誠実な対応をお約束します。
一つお約束します。知名度の高くない現役の方、特に若い方については、極力ネガティブなことは書かないようにします。これは、逆に、高名な方や物故者に対しては遠慮せずにネガティブなことも書かせて頂く、ということを意味します。また、自分に嘘は付きたくありませんから、若い方、知名度の低い方についてネガティブな感想を持った場合は、「君子危うきに近寄らず」で何も書かないことにします。
知名度が低い方、若い方について一言付言します。そういう方でも、プロの演奏家である以上ネガティブな評言に対する耐性は備えておくべきだし、ましてそれが私のような素人の手になるものであれば無視すれば良い、という考えもあり得ます。しかし、芸術家の感性は一般人には推し量りがたいものがあります。ネガティブな評言が対象者のアーティストとしてのその後の音楽人生に思わぬ負の影響を与えてしまう、という可能性は否定できません。他方で、名のある方であれば私ごときの印象批評に(もしそれが目に留まったとしても)いちいち反応されることなど無いでしょうし、プロとしての誇りや名声が私の文章によって傷付けられることなど無いでしょう。他のもっと遙かに有力な媒体に賛辞が溢れかえっているでしょうから(←そうでなければ高名になどなれません)。これが、高名な音楽家と知名度の低い音楽家を区別する理由です。合理性のある区別だと思っていただけるかどうか自信はありませんが、私自身はこの区別はなかなかのものではないかと気に入っています。ですから、もし将来、このブログで私がネガティブなことを書いたとしたら、その対象とされた音楽家の方は、地位を確立し名声を得ていることの証左だと思ってください。
寄り道が好きなのは私の悪癖ですが、ここで、ある演奏家にだけ罵詈雑言に近いネガティブ批評を浴びせ続けた批評家と、その対象とされた演奏家の組み合わせを、二組思い出しました。一つは、ニューヨーク・ヘラルド・トリビューンに寄稿した作曲家ヴァージル・トムソンとホロヴィッツ。もう一つはボストン・グローブに寄稿した評論家リチャード・ダイアーと小澤征爾。
トムソンについてはいろいろな本に引用されている批評を少し見ただけですが、要はホロヴィッツを歪曲の天才といい、自然なフレーズは一つも奏でられない、とこきおろすのが常だったようです。曲により、聴きようによって、ホロヴィッツの演奏がそのように聞こえることがあることは否定しません。この私ですら辟易する解釈も確かにあります。しかし、トムソンが批評家として公正でなかったのは、この評言をホロヴィッツのすべての演奏に当てはまるアプリオリな定義のようなものとして使用することで満足して、実際に鳴り響いている音を謙虚に耳を傾ける誠実さを欠いていたと思われる点です。トムソンが批評家として活躍していた40年代から50年代におけるホロヴィッツの実演に接した経験はもちろん私にはありませんが、その時期の録音を聴くだけでも、トムソンの頑ななネガティブ批評が全く当てはまらない例がいくつもあることは明らかです。つまり彼は、実際に鳴り響く音に誠実に向き合っていなかったということです。一種の知的怠惰、知的欺瞞ですね。日本にもかつて(今でも?)そういうステレオタイプのことしか言わない批評家は沢山いました。「さすがに本場の演奏」、「この指揮者らしくエネルギッシュな指揮ぶり」、「巨匠〇〇〇の薫陶を受けただけのことはある」等々、「本当にちゃんと聴いたの?」と思わせる例は枚挙に暇がありません。
ダイアーと小澤さんについても全く同じことが言えます。昔のことですが、ある時期にボストン響の定期会員だった私は、ダイアーによる批評の数々に辟易させられました。格別小澤さんのファンではない私も、小澤さんの演奏に感動したことは何度もあります。(当時が彼のピークだったかもしれません。小澤ファンの皆さん、ごめんなさい。)しかしダイアーは、どんな演奏であろうが悪口一辺倒。もはや個人攻撃レベルだとうんざりさせられたものです。日本にも、特定の演奏家が出てくると紋切型の攻撃を行う批評家が、かつては珍しくなかった(今でもいる?)ように思います。演奏家は、評論家が感性と知性を尽くして誠実に演奏に向き合い、ステレオタイプの言説に頼らず、その都度自分の言葉で批評を紡ぎ出してくれることを願っているに違いありません。そして、そのような知的誠実さに裏打ちされた批評であれば、仮にそれがネガティブであったとしても、演奏家には一つの反省材料として受け止めてもらえる可能性があると思います。
寄り道したのは、理由が無いわけではありません。プロの音楽家であろうがアマであろうが、職業評論家であろうが素人評論家であろうが、音楽について人に何かを伝えようとするときには、最低限、耳を開き、すべての先入観を棄て、虚心坦懐に音楽と接する、そしてそうして得られた感想や考えを、誠実さと謙虚さを以って表現しなければならないということを言いたかったのです。さらに、暴力的・攻撃的な言説を慎むことはもちろん、社会的規範の則(ノリ)を超えないよう努めることも重要でしょう。そのようなルールを自分に課したうえで、心覚えとしてこのブログという未来へのタイムカプセルに残すべく、自分にしか書けない駄文を自分の言葉で綴り続けよう、というのが私の結論です。
前置きが長くなりましたが、これからは以上に基づき、気持ちも新たに、頻繁に投稿しようと考えています。
さて、今回は、この一年余りの間に起きたことで、是非書きたかったことを、ごく簡単に箇条書きにします。次回以降展開する積もりはありません。
1. やはりオリンピックでの大迫選手は素晴らしかった。引退宣言が信じられませんでしたが、つい最近引退を撤回し、またレースに出始めたことは、嬉しい限りです。
2. 田中希美選手、三浦龍司選手、廣中りりか選手、橋岡優輝選手も、それぞれオリンピックでは見せましたね。先ごろの日本選手権でも皆大変良い成績で、今季の活躍が楽しみです。中でも私は三浦選手に心底惚れ込んでいます。あの伸びやかなストライドと圧倒的なラストスパートは、これまでの日本人選手には見られないものです。走りを見ていると心が伸びやかに解放される、そんな走りです。今後は是非10,000メートル経由でマラソンにまで挑戦して欲しいものです。また、故障中で日本選手権を辞退した不破聖衣来選手にも大いに期待しています。まだ若いのですから、まずはじっくり休んで故障を直してください。
3. やっぱり志ん朝は凄い! 久しぶりにDVDでいくつかの演目を鑑賞し、大笑いしつつ、あらためてその特別の才能に感銘を受けました。古い言葉で言えば、別格官幣社。なんというか、出てくるだけで寄席の空気ががらりと変わって、誰しもが期待に胸をときめかせて舞台に見入る、登場人物と一緒になって泣き笑う、そういう芸です。その空気がDVDでもよく分かります。今そんな落語家がいるでしょうか? その志ん朝を生で何度も聴けたのは、幸運だったという他ありません。大圓朝と志ん朝のどちらか一人が生き返っていま聴けるとしたら、どちらを選ぶか、なんて埒もないことを時折考えます。私なら断然志ん朝です。圓朝の偉大さ、その並外れた業績はよく知っていますが、何せ実演に触れたことがありません。私は談志が苦手で、談志命(いのち)という知人達(複数います。)と常に議論になるのですが、私にとって2人の差がどこから来るかは説明する必要すら感じないほどです。談志が理屈っぽいことを言うのも好きではありませんし、第一あのしわがれ声がいけません。何よりも品格を感じさせない。「業(ごう)」というような三文文士でも恥ずかしくて使えないような言葉で落語の本質を表現するのも、気恥ずかしくて嫌です。ああ上手いな、と思うこともあるのですけれどね。先日亡くなった小三治も無論良い噺家ではありましたが、志ん朝とは格が違います。自分の両親を除き、私がその死に最も大きな衝撃を受けたのは、ホロヴィッツ、リヒテル、志ん朝、クライバー、ヴァントの5人でした。5人とも逝去を知ったときには、宇宙が崩壊したような衝撃を受けたものです。圓朝忌(現名称は圓朝まつり)があるのなら、志ん朝忌があっても良いじゃないか、そう思えてなりません。尤も、落語協会での序列、比較的若年での他界、人間国宝にもならなかった、等々の諸事情がこれを許さないことはよく分かります。仕方ないので、私は10月1日になると、志ん朝を聴いては「一人志ん朝忌」としゃれこんでいます。
4. Rippleをご存じですか? このブログで以前にご紹介したピアニスト長尾洋史さんがお仲間と繰り広げる、小アンサンブルを中心とした音楽の饗宴です。午前中から夕方までの音楽三昧。昨年初めてお邪魔して、唖然としました。内容は一言ではとても言い表せません。長尾さんのなんでも弾けてしまう凄さと、抜群のアンサンブル能力、そして企画・運営能力の素晴らしさに圧倒されます。実は、今年のRipple(「Ripple14」 )がすぐそこに迫ってきています。日時は7月23日11時から。場所は代々木上原のムジカーザ。(詳細はどうぞググってお探しください。)御用とお急ぎでない向きは、是非お運びください。後悔されないことを保証します。
5. 昨年の草津国際音楽アカデミー&フェスティバルにおける岡田博美さんのアパッショナータの演奏は、本当に凄まじかった。冒頭のユニゾンから終結の破局まで、すべてが灼熱のアパッショナータ。端正な演奏が特徴とよく言われる岡田さんから、こんなに完全燃焼の超絶的大演奏を聴けたのは、久しぶりのように思います。以前のブログにも書きましたが、2年半前に初期のベートーヴェンを弾いて、あたかも後期のように「澄み切った」印象を与えて驚かせてくれた岡田さんが、今度は全く別の意味で私を驚かせました。草津といういささか地味なフェスティバルでの演奏である上に、聴衆の数も大したことはありませんでしたから、世間の注目度は低かったと思います。でも、この大演奏を聴けた聴衆は本当に幸せでした。これまでに聴いた数多の実演、録音を凌駕する至高の演奏だったと言って憚りません、リヒテルのいくつかの演奏にひけをとらない燃焼度の高さでありながら、ミスははるかに少なく(あったのかしら?)、あらゆる意味で超絶的な演奏でした。コーダではこちらの呼吸が止まりました。改めてピアニスト岡田博美に脱帽の一幕でした。
6. 能楽等の我が国伝統芸能について。一般社団法人日本芸術文化戦略機構という組織(英語名称の略称は「JACSO」)の顧問弁護士を務めるようになったことから、能楽、舞楽、雅楽、浄瑠璃等に親しむようになりました。JACSOは人間国宝をお二人、それに元文化庁長官お一人を加えたお三方を顧問にお願いしており、理事長は宝生流シテ方の重要無形文化財。これまで私にとって縁の無かった我が国伝統芸能・芸術を学ぶのに、願ってもない最高の環境を提供してくれています。そして、まだまだ初学者ですが、これらの芸能・芸術は相当面白い。演目によっては物凄く面白い。私にとっての重要性という点で、これらの諸芸能・芸術が西欧クラシック音楽にとって代わることはおそらくお今後も無いだろうと思いますが、それでも、つい2,3年前まで私にとってほぼ「ゼロ」であったジャンルが、みるみるうちにその存在意義を主張するようになり、私の意識の中で一定の、それもかなり大きな地位を占めるに至っているというのは、個人的には驚くべきことです。いや、素晴らしいことだと申しましょう。蒙を啓かれる心地良さと言ったらよいでしょうか。そして、その対象が啓蒙されるに値する価値を有するものだとの理解が徐々に進む、その嬉しさたるや。そうそう、望外の喜びは、つい最近熱海はMAO美術館の能楽堂で催されたアルゲリッチと能楽の共演。久々に彼女で聴くソロ(バッハのパルティータの2番)と、シテ方人間国宝による舞(創作)の共演。その舞の振り付け等を担当したのが我がJACSOの理事長で、彼が当日は解説も担当したことから、幸運にも鑑賞の機会を与えられました。アルゲリッチは実に神経の行き届いた共演ぶりで、改めて彼女を見直しました。ポリフォニーの彫の深さを求めなければ、ダンサブルという点を含めて、最高の演奏だったと思います。いや、舞との共演はダンサブルでなければなりませんから、彼女は敢えて峻厳なポリフォニー表現を控えたのかもしれません。彼女を聴いて時に不満に思う「上滑り」は微塵も見られず、年齢を考えると驚異的としか言えない鍵盤コントロール能力に賛嘆しつつ、豊かに流れる音楽と洗練の極みと言うべき舞のコンビネーションに身をゆだねる、至福の一時でした。驚いたことに、能楽堂を一杯にした聴衆は、終演後スタンディング・オーヴェイションを見せました。恐らく能楽ファンよりアルゲリッチ・ファンが多く詰めかけていたからだろうとは思いますが、それにしても能楽堂でスタンディング・オーヴェイションとは魂消ました。昔昔来日したジャン・コクトーが某能楽堂に連れて行かれて能楽を鑑賞し、あれ以上に退屈なものを知らないとこきおろしたという伝説(事実のようです。)があります。このエピソードに惑わされて能楽を敬遠してきたのは実に勿体なかったと、今にして思います。西洋音楽ファンの皆さんも、能楽堂を訪ねてごらんになってはいかがでしょうか。優れた能楽師の発声、優れた楽器演奏者(囃子方)の発する玄妙な音、そして所作の気韻の高さ。それらから学ぶものは少なくない筈です。(個人的には、JACSO理事長などは素晴らしいバリトン歌手になれただろうと思っているのですが、それはいかにも西洋音楽至上主義の発想だと反省する今日この頃です。)
まだまだあるのですが、このくらいにします。次回からは、気持ちも新たに、リアルタイムの話題をできるだけ頻繁に投稿していきたいと考えています。よろしくお付き合いください。
河村尚子讃
2021 JUL 21 17:17:15 pm by 大武 和夫

今春来日時の河村尚子さんは凄かった。
首都圏で行われた3つの公演に行き、英語で言うなら文字通りswept overされました。圧倒的の一言です。
昨年の来日時の公演についても投稿したかったのですが、あまりに時間が経ち過ぎました。(本稿もすっかり時間が経ってしまっていますが、数ヶ月の遅れであれば、情報の鮮度はすっかり落ちていますが何とかお許し頂けるのではないかと考えました。特に、末尾に述べますが、今年中の再来日はもう無いようですので、本稿をアップする意味は無くはないように思います。)
生命の躍動そのものを感じさせる豊かで大きな音楽は、いつも私に「元始、女性は太陽であった」(平塚らいてう)という有名な言葉を思い出させます。
河村さんの音楽は神経の行き届いた素晴らしい精妙さ・繊細さを持ちながら、なによりも豊かさとスケールの大きさを感じさせます。豊かでスケールが大きいというと、何となく茫洋として掴みどころの無い演奏を想起させるかもしれませんが、全くそうではありません。彼女の演奏は明晰な頭脳・・・大変頭の良い方であることはお話ししているとすぐに分かります・・・による徹底的な曲の分析の結果であり、全体であれ細部であれ、常にくっきりとした輪郭・フォルムを保っています。この音、このフレーズ、この和音がここに置かれているのはこういう背景と論理の結果であり、従って、こう弾かれなければならない、という強靱な意志の力を感じさせます。ですから、茫洋のまさしく正反対。そうであるのに、音楽は頭でっかちに干からびるどころか、不思議なほど人間存在の根源に迫る豊かさと大きさで鳴り響くのです。天才の天才たる所以です。そして、そのような豊かで大きな音楽を作る演奏家は、日本人に限らず現在どれほどいるでしょう。
彩の国埼玉芸術劇場で行われたリサイタルは、中でも白眉で、私にとって生涯でベストの音楽会の一つでした。モーツァルト(Kv. 397)の変幻自在な表現はどうでしょう。極めて独創的な曲の理想的な表現。シューベルトのG-durソナタ(D. 894)はもう、豊かに拡がる「幻想」そのもの。聴き手はその世界に浸り、河村さんとともに歩みを進めます。ドビュッシー(映像第1集全曲)がまた素晴らしい。常に生き生きと語りかけながら音楽が前へ前へと進む、その弾力溢れる生命力はどうでしょう。そして、ショパンがこんなにもシンフォニックに響いたことはありませんでした。幻想即興曲ですら後期作品のように響くことの驚異。(この曲は没後作曲者の遺志に反して出版されたため大きな作品番号を与えられていますが、4曲の即興曲の中では最も早く書かれた作品です。)我が偏愛の舟歌も、実演でこれほど感動させられたことはありません。この曲はリズムの取り方一つをとっても実に難しく、曲に統一感を与えることが至難です。しかし、河村さんは、小ぎれいにまとめるのではなく、破天荒な内容を封じ込めたこの曲のあらゆる要素を見事に描き出しつつ、そこに有機体としての統一感を与えるという奇跡を実現させていました。技術的な完成度の高さは言うまでもありませんが、私のようなすれっからしのピアノ・フリークにも技術に耳をそばだてるなどという卑しい聴き方を許さないような、何と言ったら良いか、凜としたものが彼女の演奏にはあるのです。
シューベルトの途中から涙が溢れてしまい、それが目からだけでなく鼻からも鼻水となって流れ出るので、マスクの中はもうグショグショ。口の中に入ってくる涙と鼻水と格闘しながらの鑑賞でした。
アンコールがまた凄い。まずはシューマンの幻想小曲集から「Warum」。深いところで、異なる次元に属する複数の声が歌い交わすポリフォニーに、心を揺さぶられました。次はお得意のシューマンの「献呈」。いつも彼女の献呈は見事なのですが、今回はとりわけ輝かしい喜びにあふれていて、ハッとさせられました。河村さん自身帰国時にドイツでのPCR検査の結果(勿論陰性)を認めて貰えず(日独の検査方法の違いによると言われたそうです。)、ホテルでの長期隔離生活を余儀なくされるという辛い経験をされましたから、その心情が反映されていたのかもしれません。このリスト編曲は、近年多くのピアニストが手がけていますし、上手な人も少なくありませんが、精妙でありながら豊かで喜びに満ちたスケール大きな表現は、全く河村さんの独壇場です。唯一無二と言いましょう。そしてアンコールの最後が、何とベートーヴェンの「告別」の終楽章。「告別ー不在ー再会」の、その「再会」。選曲自体に既に、久しぶりに聴衆を前にして演奏する喜び、聴衆との再会に心を震わせる河村さんの心情が吐露されていると見るのは、ごく自然でしょう。そして、その演奏も、そう確信させるだけの圧倒的な素晴らしさでした。同じ表現を何度も使用するのは気がひけますが、豊かで喜びに溢れた究極の「再会」でした。感動に涙しながら私は、心の中で「河村さん、お帰りなさい。ありがとう。そして、ルートヴィヒ君も素晴らしい曲をありがとう。」と感謝の言葉をつぶやいていました。
何度も「豊かなスケールの大きさ」という表現を用いてきましたが、日本人演奏家で、そのような表現が当てはまる演奏をする人は、男女を問わず楽器を問わず、一体どれだけ他にいるでしょう。そう思うにつけ私は、彼女の天賦の才は勿論のことながら、ドイツで音楽教育を受け、ロシア人名ピアニスト(クライネフ)に師事したという彼女の経歴の意味するところの大きさを思うのです。リヒテルがドイツ人として生まれながらロシアで音楽教育を受け、晩年はほとんど国外(日本にも家を持っていました。)で過ごしたこと(知人にピアノ・フリークで日本語研究者であるドイツ人がいますが、来日時に話したリヒテルのドイツ語は完璧で、全く何の訛りも無かったそうです。その知人は、柴田南雄さんがドイツ人でないリヒテルにはアウフタクトの感覚が欠けていると書いたのを読んで、そんなことありえないと笑っていましたっけ。)や、教育はロシアで受けたものの若い頃にロシア(ソビエト)を脱出してパリやベルリンで西欧文化にどっぷりと浸かり、その後にアメリカに移住し、更にはイタリア人巨匠指揮者の女婿となったホロヴィッツなどの例も、複数の文化的背景を持つことの特別の意味を物語って余りあると思います。
河村さんは今秋も来日が予定されていましたが、クララハスキル・コンクールの審査員を務められることとの関係で、うまく日程調整が付かなくなり(コロナの隔離期間のせいです。)、その結果、つい最近になって来日は取りやめになったようです。(少なくとも東京芸術劇場での芸劇ブランチコンサートは中止になりました。)残念ですが、コロナが明ければまた以前のように定期的に帰国して演奏してくださるでしょう。そのことを慰めとしつつ、次のご帰国を鶴首して待ちたいと思います。
新国~我らのオペラ小屋
2021 APR 16 17:17:14 pm by 大武 和夫

新国立劇場のワルキューレの5回の公演中3回に足を運び、大きな感銘を受けました。
公演は終了していますし、既に様々なメディアでその大成功が喧伝されていますが、私にとってこの公演は20年に及ぶ新国立劇場通いの中でも特筆大書すべき記念碑的な地位を占める公演でしたので、この一文を認め(したため)なければこのブログを始めた意味が無いと考えました。
記念碑的と言うのは、「創立24年を経て新国立劇場は(そのオペラ部門は)ついに『我らの劇場』、『我らのオペラ小屋』になった!」という感激をもたらした公演であったという意味においてです。
今回のワルキューレは、ご存じの通り、当初は前オペラ部門芸術監督飯守泰次郎さんがフリーの立場で振る初めての新国のワーグナー作品として、出演予定であった欧米の素晴らしい歌手達の顔触れと相まって、大きな期待を集めていました。無論私もワクワクして、めくるめく飯守/ワーグナー・ワールドを心待ちにしていました。(ここで脱線しますが、飯守さんが芸術監督在任時の聴衆には、まことに心ないアンチ飯守派が少なくとも数名いました。彼が振ると、出来不出来に拘わらず必ずブーを浴びせるのです。何と不見識なことかと思っていたら、ある公演でその数名が、私の横の1人おいた席からずらっと並んで座っていました・・・無論それがその連中であるということは終演後に初めて分かったのですけれど。彼ら/彼女らは、カーテンコールで指揮者が登壇すると、「そろそろブーをかまそうか?」と声に出して言い、一斉に「ブー」を浴びせ始めました。そして、仲間内でゲラゲラとひどく下卑た調子で笑い転げるのです。その公演は決して水準の低いものではなく、私には立派な演奏に聞こえましたから、ひどく腹が立ちましたが、法律家魂が頭をもたげ、言論の自由は尊重しなければならないと私自身を説得するのです。やむを得ず、しばらくの間その暴挙を耐え忍びました。連中はブーをしばらくの間楽しんだ後、カーテンコールの続く中、笑い交わしながら騒がしく退出していきました。何故飯守さんがそういう連中の餌食になっていたのかは謎ですが、立派な業績を残されたのにお可哀想であったと、今でも同情を禁じ得ません。オペラハウスというのは元来そういう娯楽場で、半可通の独善的な攻撃にも不動心で立ち向かえる指揮者でなければ生き延びられない所だということは、マーラーの例を持ち出すまでもなく頭では分かっているのですけれど。いずれにしても、その飯守さんが肩の荷を下ろしてフリーの立場で振るワルキューレに期待しない訳にはいきませんでした。)
ところが、ご存じの通り、飯守さんは体調不良で急遽降板され、コロナ禍のせいで欧米の歌手達も揃って来日が不可能になりました。その窮状を救ったのが、現オペラ部門芸術監督である大野さんと日本人歌手達、そして後述する新国オペラパレス正規プログラム初登場の指揮者城谷正博さん。
当初やはり「楽」が良いだろうと考えて、最終日3月23日のチケットを買っていた我々夫婦は、指揮者が交代し、しかも最終日は無名の(失礼!)城谷さんという人になると知って激しく落胆(ますます失礼!!)し、慌てて大野さんの初日(3月11日)を追加で押さえました。初日を選択したのは、ジークムントを1幕と2/3幕とで二人のテノール(村上さんと秋谷さん)が歌い分けるという前代未聞の試みに恐れをなし、これは全曲を通して歌えるテノールがいない(日本にいないかどうかは別として、この期間をショートノーティスで押さえられるテノールがいない)という大野さんの判断によるものだろうと想像し、二人の歌手の歌い分けで我慢しなければならないとしたらまだ声が疲れていない初日が無難であろうとの判断によるものでした。この判断は一面で当たっていなくもなかったのですが、他方、誤りであったとも言えます。その詳細は後述します。
そうこうするうちに、賛助会員向け招待券として、20日(大野さんが指揮する4回のうちの最終回)のチケットも新国から送られてきました。これで我々夫婦は、初日、大野さんの最終日、そして城谷さんが振る千秋楽の合計3回を聴きに行くことになりました。
初日の直前に大野さんがユーチューブにアップしたのは、アッバス版なる「管弦楽縮小版」の使用についての解説。そういう版があるとは全く知らなかった私は、この解説から実に有益な情報を得ることができました。巨大な編成を小さくし、木管はそれぞれの2番奏者が持ち替えで対応。弦も12型に縮小するが、管楽器縮小(とワーグナーチューバの割愛!)を補うべくコンバスは5本。おまけに大野さんはリハの過程でいくつかの楽器に音を追加するといった工夫も凝らした由。新国ピットに入ったノットの手兵東響が、大野さんの棒にどう応えるか、歌手の大幅入れ替えで萎えかけていた気持ちが一挙に前向きなものに変わり始めた瞬間です。
そして迎えた初日。私はあまりの感激に、最初の幕間と終演後の二度に亘って友人達にその模様をメールで伝えました。
スケールが大きい代わりにやや茫洋としたところのある飯守さん(悪口ではありません。彼が振るドイツロマン派は、ドイツの深い森の匂いがします。)と比べて、大野さんの棒がどれだけ俊敏・精密で、しかも燃え上がる情熱を描き尽くしていたことか。しかし、私の最大の驚きは、日本人歌手達の大活躍でした。冒頭から、村上ジークムントと小林ジークリンデの素晴らしさに驚倒。2人とも短期間の準備とは思えない仕上がりで、村上さんのヘルデンというにはやや細いものの輝かしいアクートの魅力と、小林さんの思慮に満ちていながら秘めた情熱を感じさせる深い声と演技。この2人が結ばれるのは必然であったと、声と演技の双方で感じさせる公演は滅多にありません。公平を期して書きますが、村上さんはあるフレーズで声がかすれてしまって、ハラハラドキドキさせました。半可通は、恐らくここを先途と騒ぎ立てるでしょう。しかし、私は思ったのです。指輪4作の中で、奸計も裏切りもあくどい策略も登場しない唯一の作品であるワルキューレ。その中で傷つき、倒れそうになりながらも、運命にあらがって健気に真っ直ぐに生き抜こうとするジークムントとジークリンデ。その2人が余裕綽々の美声で良いのかと。追い詰められ、肉体的にも精神的にも極限状況にある人間の魂の叫びが、余裕綽々である筈はないではないかと。これはやや贔屓の引き倒し的議論であることは無論承知しています。しかし、この2人の迫真の歌唱と演技には(そして、後述する秋谷ジークムントにも)、こう言ってみたくなる何かが確かにありました。先走りますが、20日に聞いた際の村上ジークムントの、1幕の幕切れにおける「ヴェルズングの血に栄えあれ」の絶唱には、心の底から感動し、目頭が熱くなりました。間もなくそのヴェルズング族を誕生させた父その人から死に定められる運命とも知らずに、その血を称える喜びの歌の純粋さの、何と無残であることか。しかし、本人のあずかり知らぬそういったその後の展開を離れて、くびきから逃れる妻=妹との再会と命をかけた逃避行の現世を超越した喜び、という観点だけから見ても、実に感動的な絶唱でした。ここで尚「ヘルデンテノールにはほど遠い声量だ」と言うような批判を展開する人と私は、音楽に求めるものが決定的に違うのだとだけ言っておきます。
初日の2幕では、藤村さんの完璧な歌唱コントロールに恐れ入りました。ラデツキーのヴォータンも流石の出来で、この2人の登場によって、一気にヨーロッパの最高水準を思い知らされますが、そこで我ながら驚いたのは、1幕のドラマが全く色あせなかったこと、つまり村上・小林コンビの歌唱・演技が藤村・ラデツキーの歌唱・演技と全く同水準にあるように思われたことでした。そして、満を持して登場した秋谷ジークムントの持続するエネルギーと、チャーミングでここという時の迫力も備えた池田ブリュンヒルデに、またもや刮目することになるのです。
秋谷さんは、2人一役のハンディをものともせず、この演出におけるこの役が長い稽古で体の隅々にまで入っているとでも言うような入魂の歌唱であり演技でした。特に、ブリュンヒルデの死の告知に対して、ジークリンデが一緒に行けないなら自分はヴァルハラに行かないと決然と言い放つあたりの見事さは、これまでに見聴きしたあらゆるジークムントに勝るとも劣らない出来で、感動に震えました。池田さんの素晴らしさは、3幕で全開となるのですが、2幕でも感情表現のみならず、それを可能にする持続的な喉のコントロールが見事。節制+規律+訓練で完璧なフォルムを保ち続ける藤村さんと並んで聴いても、全く聴き劣りしないのですから、驚く他はありません。
少し場面は戻りますが、2幕のヴォータンとフリッカの対話ないし言い争いは、いつも長いなと思うのです。素晴らしい場面だと思いつつ、どこかで長いなと冷めた見方をする自分に気付くということの繰り返しでした。しかし、今回は、むしろ短く感じられたことに驚きました。大野さんの手腕でしょう。総じて、先へ先へと進める力に満ち、せわしなくは絶対にならないのに音楽が一瞬も停滞せず、ワーグナー特有の「うねり」を透明な音で紡ぎ出す離れ業。見事というも愚かなオケの統率ぶりでしたし、どのパートも汚い音をほとんど出さない東響の熱演も絶賛に値します。ワーグナーチューバの割愛も楽器編成の縮小も、意識的に耳を澄ませば勿論分かるのですが、夢中になってワーグナーの世界を指揮者、歌手、オケと一緒に歩む私には、全くと言って良いほど気になりませんでした。
初日の3幕では、小林ジークリンデの、身重であることをブリュンヒルデから告げられた際の歌唱と演技の素晴らしさに息を吞みました。この人、イタリアオペラ界ではスターなのだそうです(知らなくてごめんなさい。)が、ワーグナーについては初心者なのだとか。城谷さんは「わの会」という組織を主催していて、池田さんはその会員として活躍しているようですが、その池田さんが小林さんをワーグナーの世界に引きずり込んだのだそうです。このあたりの事情について興味のある方は、ググってご覧になればいろいろな情報が出てきます。とにかく名ジークリンデ誕生のきっかけを作った城谷さんと池田さんに、我々は感謝しなければなりません。
3幕後半では、勿論ヴォータンとブリュンヒルデ父娘の対話が聴き物です。指輪第2夜、第3夜の流れを予告し、決定づける場面であり、いわば永遠が一瞬に凝縮すると同時に一瞬が永遠に拡散する、そういった場面だと言えます。そう書きながらも不明を恥じつつ告白しますと、私はいつもこの父娘の対話は、2幕のヴォータン・フリッカの場面同様、いやそれ以上に長すぎると思ってきました。どんな名演で見ても聴いても、聴き手としての緊張が完全には持続しないのです。しかし、この日は違いました。もっともっと聴いていたいと感じたということは、文字通り永遠が一瞬に転じ、一瞬が永遠に転じたということでしょう。これは単なるレトリックではありません。そうでなければ、幕が下りる際に、もう終わってしまうのか、これは永遠の世界で私(大武)もそこで生きているのではないのか、と感じたことの説明は付きません。指環とは、永遠と瞬間をめぐる物語だというのが私の仮説です。
さて、二度目、つまり3月20日の公演については、11日に準じます。大野さんの指揮がますます雄弁になり、大きなうねりをより強く感じさせたことは特筆大書したいと思います。他方で、村上ジームムントの1幕の幕切れは、残念ながら声が持たず、やや腰砕けの憾みがありました(そこまで擁護すると、文字通り贔屓の引き倒しになります。)が、全体としては、回を重ねただけのことはある高水準の出来でした。小林ジークリンデの素晴らしさは、本当に絶賛に値します。そして、池田ブリュンヒルデも、これまでに見たことの無い可愛らしいブリュンヒルデ像を描いて、間然とするところがありませんでした。これなら、戦乙女でありながらパパ・ヴォータンの寵愛を一身に受ける存在であるのは当然と思えましたし、幕切れで、ヴォータンに媚びるのではなく自らの主張を堂々と述べることによって我が儘と言えるような措置を執らせることに成功したのも宣なるかな、と聴き手をして納得させるものがありました。
しかし、最大の驚きは、3月23日の楽に待っていました。城谷さんの指揮です。
何しろ一度この公演を聴いただけですから、針小棒大の愚を犯すことになってもいけません。従って、筆を控えたいとは思いますが、大野さんが4回振って劇場を沸かせた後に登場するというのは大変なプレッシャーだったろうと思います。そのプレッシャーに打ち勝って、オケを楽々とドライブし(特に2幕以降)、音のドラマを作り上げた才能には驚嘆します。ワーグナー演奏の新たな名指揮者誕生の瞬間を見届けることが出来た、と胸が熱くなりました。歌手陣も、大野さんのときと全く同じように全身全霊で歌い演じるのです。理屈では指揮者が代わってもベストを付くさなればならないのは当然だと考えても、いざ実際に指揮者が代わり、しかもその指揮者が知名度において劣る人であった場合に、侮るような気持ちを持たずとも、実力の差に気付いたらそれは確実に歌唱に演技に表れます。オペラというのはそういう世界です。特に、日頃城谷さんの薫陶を受けている池田さんや、城谷・池田コンビによってワーグナーの世界に引きずり込まれた小林さんのような人たちであればともかく、藤村・ラデツキー両氏が城谷さんの指揮に安んじて乗りつつ、その持てる力を全開しているように見え/聞えたのは、いかに城谷さんのこの晩の指揮が素晴らしかったかを物語っています。
事情通から教えてもらったところによれば、大野さんはシェフを務めるバルセロナに飛ばなければならないため千秋楽を振ることができず、千秋楽だけ城谷さんに任せたということのようですが、この抜擢は大野さんが城谷さんに寄せる信頼と期待の大きさを示ししたと言えます。渦中の栗を拾って新国を救った大野さんと、千秋楽での抜擢に応えて見事に代役の代役を務め上げ、鮮烈な新国正規オペラ・デビューを飾った城谷さんに、満腔のブラヴォーを捧げます。(飯守さんが大野さんに代わったというニュースが流れたその時点で、既に千秋楽は城谷さんと決まっていましたから、「代役の代役」というのは厳密には不正確なのですが、実際の事の有り様としては正にそういうことだったろうと思います。)
ようやく冒頭の感想にたどり着きました。創立24年を経て新国立劇場は(そのオペラ部門は)ついに『我らの劇場』、『我らのオペラ小屋』になった!
日本人の素晴らしい歌手達を初めて知ったという意味は大きいですが、この感想はそのことだけを言っているのではありません。指揮者の突然の交代、主要キャストの来日断念、コロナによるオケ編成の縮小の必要性、そういった未曾有の危機に対応できる「力」が、日本のオペラ界にはあった、そして結果として事前の予想を遙かに上回る見事な公演を予定通りにこなすことができた、という感慨が、「我らの劇場」、「我らのオペラ小屋」がついに誕生したという思いを抱かせたのです。
城谷さんは今後、新国で必ずまたワーグナーを(そして、彼が他に何を得意とするのか知りませんが、望むらくは他のレパートリーも)振ってくれるでしょうし、小林さんは、ドン・カルロでもエリザベッタ役で登場します。楽しみですね。
本稿を書き渋っている間に、「我らのオペラ小屋」との感を更に強める経験をしました。ついこの間の「夜鳴きうぐいす」と「イオランタ」のダブル・ビル公演です。イオランタを歌った大隅智佳子さんの「夏の夜の夢」のヘレナに続く名演に、ノックアウトされました。世界水準の声と知性と気品溢れる演技。ほれぼれします。これまであまり知らなかったこのオペラが、私にとってはチャイコフスキーのオペラの中で最も素晴らしいもののように思えたのは、ひとえに高関さんの指揮と大隅さんの歌唱のおかげでしょう。東フィルの金管の節度を失わない輝かしさにも良い意味でビックリさせられました。ああ、我らのオペラ小屋!と私は独りごちたのでした。(公演全体としては声楽陣の一部に不満が残りましたが、「イオランタ」の総合的感銘度の高さを減じるものではありませんでした。「夜鳴きうぐいす」の方は、それに比べれば不満点は多々ありました。もっとも、これはクルレンツィスとデセイの超絶的名演(なんという顔合わせでしょう!)のDVDにこちらがスポルされていたからそう感じたのかもしれません。このダブル・ビルの着想自体、何と素晴らしくも大胆であることか。この着想が大野さんのものであったことを、私は確信しています。)
誤解のないように付け加えますが、「我らのオペラ小屋」というのは、偏狭な愛国精神に基づくものなどではなく、日本人歌手と日本人指揮者だけで上演すべきだといったような馬鹿げた論陣を張るものでも勿論ありません。自国民だけを起用するなどというオペラ小屋は、世界のどこにも存在しません。例えば同じ指環でも、ワルキューレはうまく行ったが、ジークフリートや神々の黄昏が、日本人歌手を中心とするキャストで、同じ水準での上演が可能なのか。そういう努力を続けてこられた二期会、藤原歌劇団、琵琶湖オペラ等々の関係者には申し訳ない物言いになってしまいますが、ジークフリート役一つを取って見ても、恐れを知らぬ天衣無縫・天下無双の若者こそ、文字通り余裕綽々の破天荒な歌い振りでなければなりません。そういう歌手が果たして日本にいるかどうか。このこと一つを取って見ても、キャストの国籍が大事だなどと申す積もりの無いことはお分かり頂けるでしょう。
そうではなく、オペラ劇場として、我々地域の愛好家(その中には外国人もおられるでしょう。)に支えられ、愛され、一つの有機体として機能し、今回のような未曾有の危機をも芸術監督の見事なリーダシップの下で一丸となって乗り切ることができる、そういう劇場こそが「我らのオペラ小屋」だと言いたいのです。
来季のプログラムも実に素晴らしいもので、いよいよ大野さんが企画においてもキャストの人選においてもその持てる力とリーダーシップを全面的に発揮し始めたという感を強く持ちます。皆さんも「我らのオペラ小屋」に是非ともお運びください。そしてご一緒に新国を支えようではありませんか。
知られざる名手たちによるピアノ・デュオの至福
2021 FEB 8 5:05:56 am by 大武 和夫

前回からまた相当の時間が経過してしまいました。すぐにも投稿を再開するつもりでしたが、頚肩腕症候群という症状を呈してしまい、首・肩・上腕部の痛みに苦しむ生活が続きました。生来のストレートネックによる頸椎ヘルニアが根本原因のようですが、巣籠り生活の中でスマホを注視する時間が増えた皆さんも、どうぞお気を付けください。
さて、ようやく症状が治まり始め、PCに向かえるようになったら、その間に書きたいテーマはどんどん増えてしまっています。前回頭出しをしたテーマは追って順次カバーするとして、今日は2月6日に聴いた長尾洋史・藤原亜美ピアノ・デュオのマチネー「連弾の楽しみ」について書きましょう。
長尾洋史さんというピアニストをご存じの方は、残念ながらそう多くはないと思います。しかし、オーケストラをよく聴く首都圏在住者で彼の演奏に接したことのない人は、ほとんどいない筈。そう、長尾さんは「オケ中ピアノ」の名手なのです。在京オケであると外国オケ来日公演であるとを問わず、たとえばペトルーシュカのピアノ・パートを頼まれるのは、たいていの場合長尾さんです。
私はペトルーシュカだけでも、オケ中ピアノを弾く長尾さんを何度も聴いています。いつ聴いても、その鮮やかさと正確さと言ったら、ブーレーズ/NYOの同曲名録音でピアノを担当する名手チャールズ・ローゼンの顔色を無からしめるものです。一事が万事。他のレパートリーでも水際立ったオケ中ピアノを聞かせる長尾さんは、譜読みが正確で速いことでも定評があり、滅多に演奏されないピアノ・パートを含む近・現代曲の演奏では、多くの場合オケを問わず長尾さんが登場します。
その長尾さんは、室内楽の名手でもある(←オケ中ピアノを通じてオケ・メンバーの信頼を勝ち得ていることの証左でしょう。)と同時に、実は隠れた(失礼!)ソロの名手でもあります。昨年は2枚のソロCDを発表していますが、特にゴルトベルク変奏曲には参りました。少しも奇抜なことはしていません。目立たないところで装飾音に工夫はしていますが、現代の演奏家で装飾音を楽譜通りにしか弾かない人はいないでしょう。テンポも総じて常識的。他の要素を犠牲にしても声部の違いを弾き分け、対位法をことさらに際立たせようとする偏執狂的な態度も皆無。様式に反する極端な強弱も、大仰なアッチェレランドや意図的なラレンタンドも、注意深く避けられています。要はすべてが中庸なのです。普通そういう演奏は、乾燥して豊かさに欠けるつまらないものとなりがちで、実際そういう演奏はとても多いと思います。しかし、長尾盤では、微動だにしないテンポと正確無比なリズムの中から、たゆたうような詩情が溢れて止まらないのです。これは一体どういう逆説でしょう。黄金の中庸というべきか。ゴルトベルクの私的ベスト・スリーに入るのはもちろん、ひょっとするとベスト・ワンかも、と思えます。
実は私はあるご縁で長尾さんと親交があり、このCDも発売前にお送り頂いて、あまりの感激に二度、三度と深夜すぎまで繰り返して聴いてしまいました。こんなことは滅多にありません。その感動を長尾さんに伝えるメールの中で「中庸」という表現を用いたところ、長尾さんから、大略、まさに「中庸」こそ自分がバッハで目指していることであり、来月号(記憶が正確なら昨年の2月号でしたか)の「ぶらあぼ」誌掲載インタビューでも同じ言葉を使っています、という嬉しいご返事を頂きました。
そして、長尾さんは、藤原亜美さんという、こちらも長尾さんに負けず劣らず私が大好きなピアニストと、時折4手を披露してくれます。この二人のデュオを初めて聴いたのは、忘れもしない文化会館小ホールでのメシアン「アーメンの幻影」で、でした。もう20年近くも前のことです。(文化会館小ホールと言えば、それまでの私のとっての最大のメシアン体験であったジャン=ロドルフ・カールスの「眼差し」全曲演奏の会場でもありました。四半世紀を隔てた不思議な符合という他ありません。)
精緻・精密の極致であり、あらゆる点で模範的な演奏でしたが、本当に驚くほど多種多様な感情を聴き手の内に呼び覚ますのです。この演奏が本稿の目的ではありませんから、これ以上述べませんが、我々にとって、さらには後世の音楽ファンにとっても幸いなことに、長尾・藤原デュオは、同じころこの曲を録音してくれています。これこそ、他のあらゆる名盤を凌駕する決定的名盤です。決定的名盤などという言葉は、それを用いることによって他の演奏の美点を心理的に覆い隠してしてしまう危険な副作用がありますから、滅多に使うものではありません。しかし、この録音については、私は躊躇なく決定的名盤と呼びます。録音も極上。メシアンに聞かせて上げたかった!
藤原さんは、長尾さんと並んでソロの隠れた名手でもあり、以前はかなりの数のソロ録音を発表しておられました。モシュコフスキーの全集などは、もっともっと注目されてしかるべき素晴らしさでした。(それに、舞台映えする美しい方です!)
その長尾さんと藤原さんは、3年前に巣鴨の小さなスタジオでドビュッシーの4手(2台と連弾)を披露され、このデュオは本当に世界最高水準だな、と私を改めて感激させています。そして、オール・ドビュッシーのCD2枚組が、来る4月にリリースされることになりました。ここでようやく昨日のデュオ演奏会に話を戻しますと、長尾さんによれば、その発売を記念して何かまたやりたいということで、6日の演奏会を企画したのだそうです。
コンタルスキー兄弟亡きあと、世界最高のデュオはこの二人だと確認させてくれた演奏会でした。ラベック姉妹、タールとグロートホイゼン等、4手のアンサンブルは多々ありますが、長尾・藤原の素晴らしさは頭一つ抜けています。
場所は、東京は目黒区洗足駅前のプリモ芸術工房という小さな会場で、聴衆は20名限定。プロは渋さの極みで、前半がシューベルトのD. 823(「ディヴェルティメント」と「アンダンティーノと変奏曲」の2曲からなる「フランスのモティーフによるディヴェルティメント」)とD. 951(「ロンド」)で、後半はドビュッシーのバレエ音楽「おもちゃ箱」(連弾への編曲は多和田智大氏;語り付き)。本当に渋い、玄人好みとしか言いようのないプログラムです。大衆的アピールはゼロ。
連弾の難しさは、経験したことのない人には分かりません。2台ピアノとは決定的に違います。2台のレパートリーはみな、程度の差こそあれ協奏曲的に、というか2台が競い合うような形で書かれています。連弾は一つの目標に向かって心と技をピタリと寄り添わせる必要がある点で、まず奏者2人の関係性が全く異なります。2台ピアノには超絶技巧を要する曲がいくつかありますが、連弾にはほとんど無いのも、このことと深く関係していると思います。
並んで座りますから、相手の身体の動きが直接感じられますし、腕が交差することもあります。異性同士の場合、身体的距離の近さがある種の感情にもたらすこともあるでしょう・・・私には幸か不幸かそういう経験はありません(笑)・・・し、異性同士でなくともある種の親密感が生まれるのは必然です。その反面、他の奏者に接する側の肩や腕の動きに微妙な制約を感じることも、ママあります。鍵盤を所狭しと指が駆け巡る超絶技巧が連弾に適していないことは、連弾曲に超絶技巧曲が見当たらないことの一つの原因でもあります。
フレージングやテンポ感を統一する必要があるのは、2台の場合ももちろん同じですが、連弾では、そのあたりに意見の相違が少しでもあると、2台の場合よりはるかに深刻な結果を招きます。
どちらか一方が踏むことになるペダルがまた厄介です。普通は和声を支える低音部担当者が踏みますが、高音部担当者のソロのような箇所では、高音部担当者にペダルが任されることもあります。ペダリングというのは、ピアノ演奏にとって極めて重要な要素ですから、自らペダルを踏まずに、しかしペダルが要求される曲を弾くというのは、ペダルを踏まない方の奏者に一定のストレスを与え得ます。自分ならこう踏むのになあ、とペダル担当者のペダリングに不満を持ったりしたら、精神的一体感が阻害され、アンサンブルは崩れるでしょう。何より集中を削ぎます。2台なら、各奏者がある程度の枠の中で自由にペダリングを行っても、演奏の統一感が損なわれる度合いはずっと小さいはずです。
おそらく最も重要なことは、ピアノ書法が全く異なるということです。2台の場合は、それぞれの奏者がピアノの全音域を演奏可能であるのに対し、連弾では、腕が交差する場合があるとは言え身体まで入れ替えることはありません(実際に入れ替わって弾く「曲弾き」はここでは考察の対象外)から、奏者ごとに担当する音域がおのずと決まってきます。すると何が起きるか。2台に比べると、連弾は中音域の音が厚いことになりがちです(必ずしも密集和音を意味する訳ではありません。)。したがって、声部間のバランスが常にうまく保たれていることが、2台の場合よりはるかに重要になります。
以上のことから、連弾は2台に比べて、親密さを表現するのにより適した媒体と言えますが、他方で、それにも関わらず音響現象としては、ガチャガチャとうるさいことになりがちだと言えます。プロのデュオでも、うるさいなあと思わせることは珍しくありません。常時デュオを組んでいる二人であれば、そんなことは起きないだろうとお考えですか? いえいえ、それは本当に耳が良く、センスが良く、お互いを理解し信頼しあっている二人が、曲への音楽的アプローチを共通にしたうえで綿密なリハーサルを繰り返すことによって初めて可能なことなのです。常時二人で弾いているデュオの場合、連弾というフォーマットを所与のものととらえてしまっていて、緊張感をもって演奏に臨んでいないなあ、と思わせる例も珍しくありません。
そのあたりの匙加減が、長尾・藤原デュオは本当に絶妙なのです。
第1曲で、高音部担当の藤原さんが長尾さんの盤石の低音部に載せて単純な上行スケールを奏でるところで、不覚にも目頭が熱くなりました。一体なぜこんな単純なスケールに感動するの?と思う間もなく、音楽は進みます。同じ曲の終り近く(ヘンレ版のシューベルト4手全集第2巻ですと最後の2ぺージ少々)で、長尾さんのスケールと藤原さんのスケールが親密に繰り返し歌い交わすところの美しさと言ったら!
二人とも弾き崩しの全くない正攻法で、自己顕示のための音量変化や恣意的テンポ変化を嫌う潔癖な楷書的解釈でありながら、その演奏からなぜあれほど無限のニュアンスが紡ぎだされ、心が揺さぶられるのか。魔法のようです。いや、考えてみると、これはシューベルトの音楽そのものにも言えることですね。シューベルトの笑顔と哀しみが同時に透けてみえるような曲の数々であり、演奏でした。これ以上何を望むことがあるでしょう。
後半のドビュッシーは、一転してセンスの塊。リズムの何と生き生きしていることか。そして和声が常に最善のバランスで鳴り響くことにも驚倒。長尾さんが音大の副科ピアノで指導を担当されたという多和田智大さんという方の手になる連弾用編曲が見事なら、ソプラノ歌手國光ともこさんによる語りも、鮮やかに情景を切り取って、曲の面白さを際立たせていました。
アンコールには、ドビュッシーの小組曲から「小舟にて」と、シューベルトが晩年に対位法を学んで作ったという「フーガ」(D. 952)が演奏され、素晴らしい午後のひとときが閉じられました。
こんな素晴らしい演奏会が、東京の住宅街の片隅でひっそりと行われているのです。連弾はピアノ・フリークにとっては興味の対象外かもしれませんが、もっともっと多くの人に聴いて欲しいと強く思いました。主催者はライブストリーミングの配信を行っていましたが、どれほどの聴衆の聴くところとなったのでしょうか。会場に来られなかった多くの人がPCやスマホで鑑賞したことを祈るとともに、巨大都市東京で、一見ささやかでありながら実は極めて重要なこのような音楽イベントを、一般の音楽ファンに知らせ、届けることの難しさに思いを馳せたことでした。プリモ芸術工房さん、ありがとうございました。
なお、これは蛇足ですが、プリモ芸術工房に設置してある1936年製NYスタインウェイの素晴らしさにも大きな感銘を受けました。無論演奏が素晴らしいから楽器の素晴らしさが引き立つのですが、今でいうとSに相当するように見える最小の小型グランドから、何と豊かで香り高い音が立ち昇ってきたことでしょう。この頃までのNYスタインウェイの色合いの濃さと、タッチに敏感に応じる俊敏さは、私にとってピアノの理想形です。つい拙宅の前世紀末のハンブルク製Bと比較してしまうのですが、帰宅後、頚肩腕症候群発症以来初めて少し鳴らしてみたハンブルクのBが、モノクロでダルな音に聞こえてなりませんでした。(もちろん腕前の劣悪なことに大きな原因があるのですが、それだけではないということです。)「このNYスタインウェイは欲しい!」と強烈な物欲に駆られるというおまけつきのコンサートでした。
再開の弁
2020 NOV 27 16:16:44 pm by 大武 和夫

最後の投稿から思いがけず長い期間が経過してしまいました。コロナ禍による環境の変化に呆然としていたということもありますが、何よりも生の音楽に接する機会を奪われたことが私には大きかったように思います。やはり私にとって生の音楽体験はかけがえのないものなのだと思い知らされます。こうして久しぶりに筆を執るようになったのも、音楽会・オペラが次第に増えてくるに連れ、言いたいことが少しずつ出てくるようになったからです。
とはいえ、この数ヶ月の間に書きたいと思ったことは何度もあり、友人にはそろそろブログを再開すると公言したりもしていたのですから、これだけ長い期間の沈黙の説明にはなりません。根本的には、私の怠惰な性格によるものだったと、反省を込めて思います。書かないでいるとそれが常態になってしまい、書くのが億劫になるのですね。困ったものです。今日は、その悪循環を断ち切るべく、思い切って筆を執りました。
休んでいる間に書きたいと思ったテーマは、実は沢山あります。頭の中でほぼ原稿が出来ていたものもあります。
概ね時系列順に並べると、「一山選手は凄い!」、「車は左、人は右?」、「荷物は座席の下へ~演奏会マナーあれこれ」、「ジャン=フィリップ・コラール再発見とフォーレの譜読みの難しさ」、「ノットの映像出演!」、「真央君でもこんなことがあるの?」、「原始女性は太陽であった(河村尚子讃)」、「やっぱり談志は苦手」、「夏の夜の夢考(ブリテン作品の新国上演に寄せて)」、「アルマゲドンの夢に落涙」。こんなところでしょうか。書き落としたものもあるかもしれませんが、思い出したらリストに加えることにします。
これらのテーマを次々に書いて掲載していきたいと思っています。
今日のところは頭出しだけですが、病人の社会復帰と同じで、いきなりの重労働は厳禁です(笑)から、慣らし運転からぼちぼち取り組んで行こうと思います。
改めて気長にお付き合い頂ければ幸いです。
東京マラソンに瀬古を思う
2020 MAR 3 0:00:22 am by 大武 和夫

ご無沙汰してしまいました。今日は昨日(3月1日)の東京マラソンについて、どうして書きたいと思いました。
感動しました。井上の果敢な飛び出しにも感動しましたが、何といっても大迫の勝負強さに、最近二回のマラソンの失敗からの完璧な復活に、そして一度後退したのにズルズルと順位を下げるのではなく立ち直って日本新記録まで手にした気持ちの強さに、打たれました。あのゴールシーンでじんと来なかった人はいないでしょう。
今回は前半のペースが凄かったため、ネガティヴ・スプリットは無理だと期待もしていませんでしたが、それでも30キロから35キロは圧巻のスプリット・タイム。優勝者レゲセを10秒も上回っていたというのですから、やはり大迫は只者ではありません。
自身中高と陸上部に属していて(ただし「オールラウンド出ると負けプレーヤー」と自嘲する落ちこぼれ部員でした)半世紀以上にわたる陸上競技ウォッチャーであり、特に長距離・マラソンを熱心に追いかけてきた者として、今回のレースの感動は半端ではありませんでした。
しかし、この投稿の目的は大迫をほめたたえることではありません。大迫の快挙を称えながらも、この記録とレース振りではオリンピックのメダルは難しいという趣旨の冷静な意見をレース後に述べた瀬古俊彦氏がいかに偉大であったかを振り返りたくて、筆を執ったのです。
そう、大迫の激走は、かつてわが国には瀬古俊彦という不世出の大選手がいたことを強く思い出させてくれました。二人とも早稲田出身で強い、というような話ではありません。そうではなくて、本当に世界の圧倒的ナンバーワンであった瀬古に、少しは近づけるかもしれない、「世界で戦うことを、それだけを意識した」日本人マラソン選手が、40年ぶりについに我が国に現れたということを言いたいのです。
瀬古の自己ベストは2時間8分27秒で、大迫の昨日の記録より3分近くも遅いのですが、それは、40年の時の流れ、トレーニング方法の進歩、靴等の用具の改良、選手をサポートする体制の違い、スポーツ医学の進歩等々を考えると、問題になりません。それどころか、瀬古の記録は、今なら少なくとも2時間3分台に匹敵することは間違いないと思います。瀬古と同等の才能と勝負強さを持った選手が現在理想的な環境で育っていたとしたら、その程度の記録は優に出せていただろうということです。それくらい瀬古という選手はけた外れに凄かった。
出るマラソンはことごとく優勝し、最後まで競り合ってもスプリント勝負で相手を置き去りにすることは間違いない、そんな選手は後にも先にも日本にいたためしがありません。
1980年だったかに東京の旧国立競技場で行われた陸上競技大会(企業名が付いた冠大会でしたが名称も年もよく覚えていません・・・)で、あのラッセ・ヴィレンと1万メートルで対決した瀬古は、最後の1周の圧倒的なラストスパートで、相手を置き去りにして優勝しました。それはもうほれぼれするぐらい見事な、美しいスパートでした。マラソン・ウォッチャーと言っても沿道で見るのは嫌いで、専らテレビ観戦派ですので、瀬古を実施に見たのはそのときだけでした。そして、そのトラック・レースで瀬古を見ることができたことは本当に幸運でした。世界一の選手の全盛期。そのあまりにも鮮やかな勝ちっぷりは、脳裏に焼き付いて離れません。
モスクワ・オリンピックへの日本の不参加は本当に衝撃でした。瀬古が出ていたら、ぶっちぎりで金メダルだったと今でも確信しています。(モスクワの優勝者チェルピンスキーとは80年の年末に福岡で対決し、瀬古が勝っています。)それだけに、ロサンゼルス大会への期待は大きかったのです。
アメリカ留学中もアメリカのマラソン雑誌を定期購入していましたし、瀬古が出る日本のマラソンの結果は、自宅に国際電話をして尋ねました。ネット世代には想像もつかないでしょう。Those were the days. サラザールは雑誌インタビューで、一番マークする選手として瀬古の名を上げ、「彼の1万メートルの記録は27分35秒なんだよ。なんてすごいんだろう。彼のことはうんとリスペクトしているよ。」と語っていました。実際には瀬古の1万のベストは27分42秒ですが、そんな細かいことはどうでもよろしい。27分42秒も、当時としては大きなリスペクトに値する優れた記録でした。そして、そう瀬古をほめたたえるサラザールの記事を読んで、同じ日本人としてとても誇らしい思いがしたものでした。(サラザールはその後オレゴン・プロジェクトの指導者として晩節を汚しましたが、現役時代は世界最高のランナーの一人として尊敬を集めていました。)
1984年夏のロサンゼルス・オリンピックは、アメリカから移り住んだロンドンで見ました。マラソン当日はロンドン到着直後で、まだシティの法律事務所での研修生としての勤務は始まっていませんでした。そして、その日の午後は、1歳の長女を抱いて、家内とハイドパーク探索に出かけました。
ところが、どうしたことか、途中でめまいがして熱っぽくなったのです。このまま散歩は続けられないなと思い、サーペンタイン・レイク湖畔のカフェテリアで軽い夕食をとり、タクシーで帰宅しました。フラフラしながら帰宅して熱を測ると、38度の熱です。その時点では、瀬古も事前に血を吐き、下痢をして最悪のコンディションだったことなど知る由もありません。しかし、なんだか胸騒ぎを覚えました。体温を計ってすぐにベッドに直行して休み、マラソンが始まる直前に起きだして、小さなフラットのチッポケな安物テレビの前に陣取りました。
25キロあたりからの悪夢のような光景に呆然としつつ、ひょっとして瀬古も私のような体調の悪さに苦しんでいるのではないかという考えが頭をよぎりました。圧勝以外はありえないと信じていましたので、敗戦のショックは言葉では言い表せないほどでした。深夜長時間のテレビ観戦も手伝って私の熱は更に上がり、少し大げさに言うなら、もう何がどうなってもいいという厭世的な気分になりました。それぐらい瀬古に寄せる期待は大きく、敗戦の落胆も大きかったのです。
瀬古は、帰国後しばらくは殻を破ろうとしてお嫁さん募集中と言ってみたり、それまで見せなかった笑顔を振りまいたりしていましたが、そういう瀬古にはもうあまり興味を持てませんでした。その後のシカゴとボストンの圧勝で、さすがは瀬古、やはり本当の世界一は瀬古だとの確信は戻りましたが、後から振り返ってみると、この二つのレースは偉大な選手の偉大なキャリアの最後の輝きだったのですね。
昨日のレース後の瀬古の上記コメントを、失礼だとか、優しさが足りないなどと受け止めた人もいるだろうと想像します。しかし、世界広し、マラソンの名選手多しと言えども、瀬古以外にそういう直言ができる人はいないのです。瀬古以外にそのようなことを言う資格のある人も、いないのです。
瀬古よ、良く言った。そして、瀬古がそういうことを言う気になったのも、大迫の才能と努力、そして精神力の強さに感じ入ったからに相違ありません。
願わくば大迫が、往時の瀬古の存在に少しでも近づいてくれますように。夏のオリンピックが中止になりませんように。そして大迫が、瀬古の二つのオリンピックの記録(ロサンザルスは14位、ソウルは9位)をしのぐ成績を残してくれますように。頑張れ、大迫!