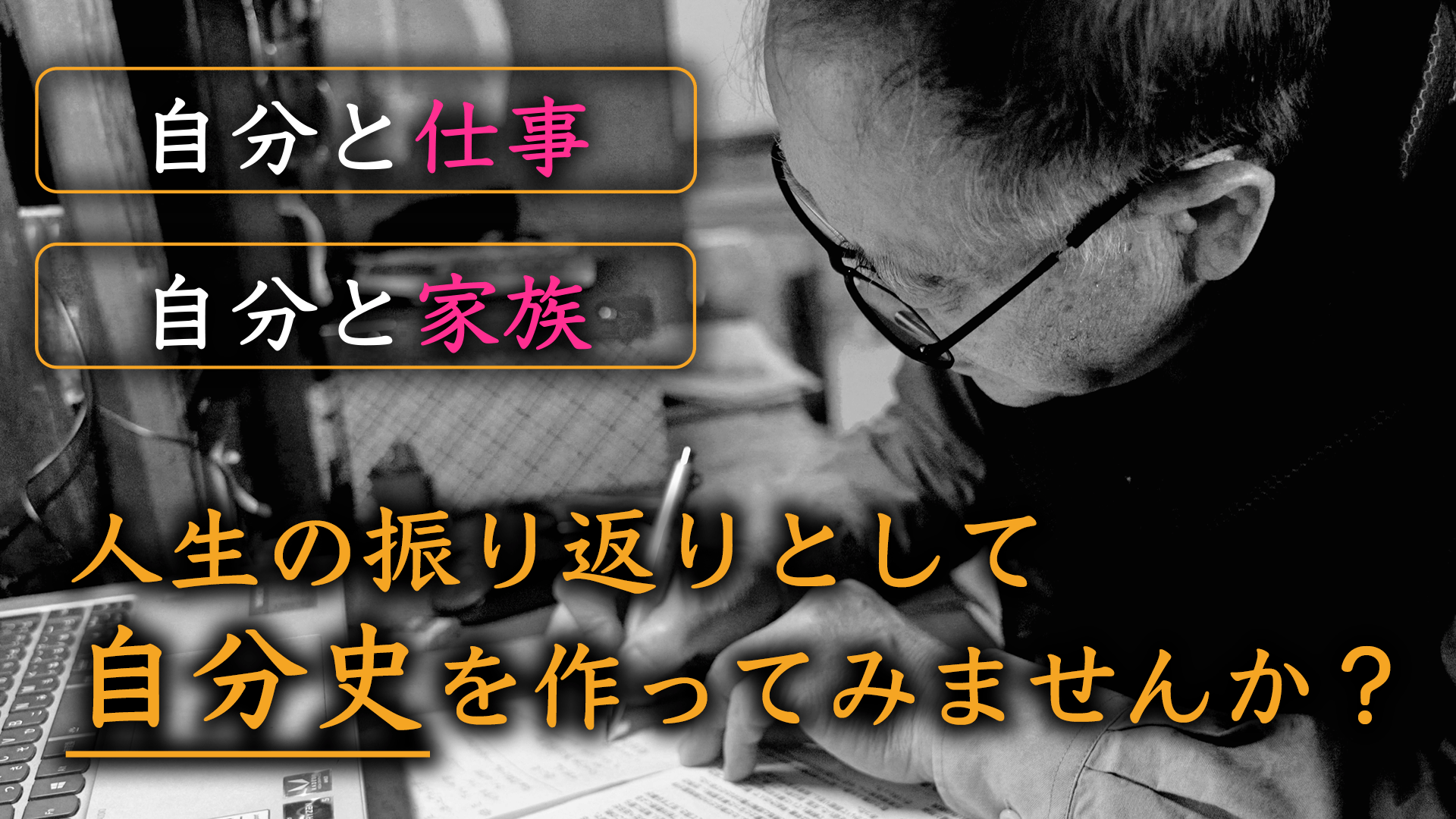新国~我らのオペラ小屋
2021 APR 16 17:17:14 pm by 大武 和夫

新国立劇場のワルキューレの5回の公演中3回に足を運び、大きな感銘を受けました。
公演は終了していますし、既に様々なメディアでその大成功が喧伝されていますが、私にとってこの公演は20年に及ぶ新国立劇場通いの中でも特筆大書すべき記念碑的な地位を占める公演でしたので、この一文を認め(したため)なければこのブログを始めた意味が無いと考えました。
記念碑的と言うのは、「創立24年を経て新国立劇場は(そのオペラ部門は)ついに『我らの劇場』、『我らのオペラ小屋』になった!」という感激をもたらした公演であったという意味においてです。
今回のワルキューレは、ご存じの通り、当初は前オペラ部門芸術監督飯守泰次郎さんがフリーの立場で振る初めての新国のワーグナー作品として、出演予定であった欧米の素晴らしい歌手達の顔触れと相まって、大きな期待を集めていました。無論私もワクワクして、めくるめく飯守/ワーグナー・ワールドを心待ちにしていました。(ここで脱線しますが、飯守さんが芸術監督在任時の聴衆には、まことに心ないアンチ飯守派が少なくとも数名いました。彼が振ると、出来不出来に拘わらず必ずブーを浴びせるのです。何と不見識なことかと思っていたら、ある公演でその数名が、私の横の1人おいた席からずらっと並んで座っていました・・・無論それがその連中であるということは終演後に初めて分かったのですけれど。彼ら/彼女らは、カーテンコールで指揮者が登壇すると、「そろそろブーをかまそうか?」と声に出して言い、一斉に「ブー」を浴びせ始めました。そして、仲間内でゲラゲラとひどく下卑た調子で笑い転げるのです。その公演は決して水準の低いものではなく、私には立派な演奏に聞こえましたから、ひどく腹が立ちましたが、法律家魂が頭をもたげ、言論の自由は尊重しなければならないと私自身を説得するのです。やむを得ず、しばらくの間その暴挙を耐え忍びました。連中はブーをしばらくの間楽しんだ後、カーテンコールの続く中、笑い交わしながら騒がしく退出していきました。何故飯守さんがそういう連中の餌食になっていたのかは謎ですが、立派な業績を残されたのにお可哀想であったと、今でも同情を禁じ得ません。オペラハウスというのは元来そういう娯楽場で、半可通の独善的な攻撃にも不動心で立ち向かえる指揮者でなければ生き延びられない所だということは、マーラーの例を持ち出すまでもなく頭では分かっているのですけれど。いずれにしても、その飯守さんが肩の荷を下ろしてフリーの立場で振るワルキューレに期待しない訳にはいきませんでした。)
ところが、ご存じの通り、飯守さんは体調不良で急遽降板され、コロナ禍のせいで欧米の歌手達も揃って来日が不可能になりました。その窮状を救ったのが、現オペラ部門芸術監督である大野さんと日本人歌手達、そして後述する新国オペラパレス正規プログラム初登場の指揮者城谷正博さん。
当初やはり「楽」が良いだろうと考えて、最終日3月23日のチケットを買っていた我々夫婦は、指揮者が交代し、しかも最終日は無名の(失礼!)城谷さんという人になると知って激しく落胆(ますます失礼!!)し、慌てて大野さんの初日(3月11日)を追加で押さえました。初日を選択したのは、ジークムントを1幕と2/3幕とで二人のテノール(村上さんと秋谷さん)が歌い分けるという前代未聞の試みに恐れをなし、これは全曲を通して歌えるテノールがいない(日本にいないかどうかは別として、この期間をショートノーティスで押さえられるテノールがいない)という大野さんの判断によるものだろうと想像し、二人の歌手の歌い分けで我慢しなければならないとしたらまだ声が疲れていない初日が無難であろうとの判断によるものでした。この判断は一面で当たっていなくもなかったのですが、他方、誤りであったとも言えます。その詳細は後述します。
そうこうするうちに、賛助会員向け招待券として、20日(大野さんが指揮する4回のうちの最終回)のチケットも新国から送られてきました。これで我々夫婦は、初日、大野さんの最終日、そして城谷さんが振る千秋楽の合計3回を聴きに行くことになりました。
初日の直前に大野さんがユーチューブにアップしたのは、アッバス版なる「管弦楽縮小版」の使用についての解説。そういう版があるとは全く知らなかった私は、この解説から実に有益な情報を得ることができました。巨大な編成を小さくし、木管はそれぞれの2番奏者が持ち替えで対応。弦も12型に縮小するが、管楽器縮小(とワーグナーチューバの割愛!)を補うべくコンバスは5本。おまけに大野さんはリハの過程でいくつかの楽器に音を追加するといった工夫も凝らした由。新国ピットに入ったノットの手兵東響が、大野さんの棒にどう応えるか、歌手の大幅入れ替えで萎えかけていた気持ちが一挙に前向きなものに変わり始めた瞬間です。
そして迎えた初日。私はあまりの感激に、最初の幕間と終演後の二度に亘って友人達にその模様をメールで伝えました。
スケールが大きい代わりにやや茫洋としたところのある飯守さん(悪口ではありません。彼が振るドイツロマン派は、ドイツの深い森の匂いがします。)と比べて、大野さんの棒がどれだけ俊敏・精密で、しかも燃え上がる情熱を描き尽くしていたことか。しかし、私の最大の驚きは、日本人歌手達の大活躍でした。冒頭から、村上ジークムントと小林ジークリンデの素晴らしさに驚倒。2人とも短期間の準備とは思えない仕上がりで、村上さんのヘルデンというにはやや細いものの輝かしいアクートの魅力と、小林さんの思慮に満ちていながら秘めた情熱を感じさせる深い声と演技。この2人が結ばれるのは必然であったと、声と演技の双方で感じさせる公演は滅多にありません。公平を期して書きますが、村上さんはあるフレーズで声がかすれてしまって、ハラハラドキドキさせました。半可通は、恐らくここを先途と騒ぎ立てるでしょう。しかし、私は思ったのです。指輪4作の中で、奸計も裏切りもあくどい策略も登場しない唯一の作品であるワルキューレ。その中で傷つき、倒れそうになりながらも、運命にあらがって健気に真っ直ぐに生き抜こうとするジークムントとジークリンデ。その2人が余裕綽々の美声で良いのかと。追い詰められ、肉体的にも精神的にも極限状況にある人間の魂の叫びが、余裕綽々である筈はないではないかと。これはやや贔屓の引き倒し的議論であることは無論承知しています。しかし、この2人の迫真の歌唱と演技には(そして、後述する秋谷ジークムントにも)、こう言ってみたくなる何かが確かにありました。先走りますが、20日に聞いた際の村上ジークムントの、1幕の幕切れにおける「ヴェルズングの血に栄えあれ」の絶唱には、心の底から感動し、目頭が熱くなりました。間もなくそのヴェルズング族を誕生させた父その人から死に定められる運命とも知らずに、その血を称える喜びの歌の純粋さの、何と無残であることか。しかし、本人のあずかり知らぬそういったその後の展開を離れて、くびきから逃れる妻=妹との再会と命をかけた逃避行の現世を超越した喜び、という観点だけから見ても、実に感動的な絶唱でした。ここで尚「ヘルデンテノールにはほど遠い声量だ」と言うような批判を展開する人と私は、音楽に求めるものが決定的に違うのだとだけ言っておきます。
初日の2幕では、藤村さんの完璧な歌唱コントロールに恐れ入りました。ラデツキーのヴォータンも流石の出来で、この2人の登場によって、一気にヨーロッパの最高水準を思い知らされますが、そこで我ながら驚いたのは、1幕のドラマが全く色あせなかったこと、つまり村上・小林コンビの歌唱・演技が藤村・ラデツキーの歌唱・演技と全く同水準にあるように思われたことでした。そして、満を持して登場した秋谷ジークムントの持続するエネルギーと、チャーミングでここという時の迫力も備えた池田ブリュンヒルデに、またもや刮目することになるのです。
秋谷さんは、2人一役のハンディをものともせず、この演出におけるこの役が長い稽古で体の隅々にまで入っているとでも言うような入魂の歌唱であり演技でした。特に、ブリュンヒルデの死の告知に対して、ジークリンデが一緒に行けないなら自分はヴァルハラに行かないと決然と言い放つあたりの見事さは、これまでに見聴きしたあらゆるジークムントに勝るとも劣らない出来で、感動に震えました。池田さんの素晴らしさは、3幕で全開となるのですが、2幕でも感情表現のみならず、それを可能にする持続的な喉のコントロールが見事。節制+規律+訓練で完璧なフォルムを保ち続ける藤村さんと並んで聴いても、全く聴き劣りしないのですから、驚く他はありません。
少し場面は戻りますが、2幕のヴォータンとフリッカの対話ないし言い争いは、いつも長いなと思うのです。素晴らしい場面だと思いつつ、どこかで長いなと冷めた見方をする自分に気付くということの繰り返しでした。しかし、今回は、むしろ短く感じられたことに驚きました。大野さんの手腕でしょう。総じて、先へ先へと進める力に満ち、せわしなくは絶対にならないのに音楽が一瞬も停滞せず、ワーグナー特有の「うねり」を透明な音で紡ぎ出す離れ業。見事というも愚かなオケの統率ぶりでしたし、どのパートも汚い音をほとんど出さない東響の熱演も絶賛に値します。ワーグナーチューバの割愛も楽器編成の縮小も、意識的に耳を澄ませば勿論分かるのですが、夢中になってワーグナーの世界を指揮者、歌手、オケと一緒に歩む私には、全くと言って良いほど気になりませんでした。
初日の3幕では、小林ジークリンデの、身重であることをブリュンヒルデから告げられた際の歌唱と演技の素晴らしさに息を吞みました。この人、イタリアオペラ界ではスターなのだそうです(知らなくてごめんなさい。)が、ワーグナーについては初心者なのだとか。城谷さんは「わの会」という組織を主催していて、池田さんはその会員として活躍しているようですが、その池田さんが小林さんをワーグナーの世界に引きずり込んだのだそうです。このあたりの事情について興味のある方は、ググってご覧になればいろいろな情報が出てきます。とにかく名ジークリンデ誕生のきっかけを作った城谷さんと池田さんに、我々は感謝しなければなりません。
3幕後半では、勿論ヴォータンとブリュンヒルデ父娘の対話が聴き物です。指輪第2夜、第3夜の流れを予告し、決定づける場面であり、いわば永遠が一瞬に凝縮すると同時に一瞬が永遠に拡散する、そういった場面だと言えます。そう書きながらも不明を恥じつつ告白しますと、私はいつもこの父娘の対話は、2幕のヴォータン・フリッカの場面同様、いやそれ以上に長すぎると思ってきました。どんな名演で見ても聴いても、聴き手としての緊張が完全には持続しないのです。しかし、この日は違いました。もっともっと聴いていたいと感じたということは、文字通り永遠が一瞬に転じ、一瞬が永遠に転じたということでしょう。これは単なるレトリックではありません。そうでなければ、幕が下りる際に、もう終わってしまうのか、これは永遠の世界で私(大武)もそこで生きているのではないのか、と感じたことの説明は付きません。指環とは、永遠と瞬間をめぐる物語だというのが私の仮説です。
さて、二度目、つまり3月20日の公演については、11日に準じます。大野さんの指揮がますます雄弁になり、大きなうねりをより強く感じさせたことは特筆大書したいと思います。他方で、村上ジームムントの1幕の幕切れは、残念ながら声が持たず、やや腰砕けの憾みがありました(そこまで擁護すると、文字通り贔屓の引き倒しになります。)が、全体としては、回を重ねただけのことはある高水準の出来でした。小林ジークリンデの素晴らしさは、本当に絶賛に値します。そして、池田ブリュンヒルデも、これまでに見たことの無い可愛らしいブリュンヒルデ像を描いて、間然とするところがありませんでした。これなら、戦乙女でありながらパパ・ヴォータンの寵愛を一身に受ける存在であるのは当然と思えましたし、幕切れで、ヴォータンに媚びるのではなく自らの主張を堂々と述べることによって我が儘と言えるような措置を執らせることに成功したのも宣なるかな、と聴き手をして納得させるものがありました。
しかし、最大の驚きは、3月23日の楽に待っていました。城谷さんの指揮です。
何しろ一度この公演を聴いただけですから、針小棒大の愚を犯すことになってもいけません。従って、筆を控えたいとは思いますが、大野さんが4回振って劇場を沸かせた後に登場するというのは大変なプレッシャーだったろうと思います。そのプレッシャーに打ち勝って、オケを楽々とドライブし(特に2幕以降)、音のドラマを作り上げた才能には驚嘆します。ワーグナー演奏の新たな名指揮者誕生の瞬間を見届けることが出来た、と胸が熱くなりました。歌手陣も、大野さんのときと全く同じように全身全霊で歌い演じるのです。理屈では指揮者が代わってもベストを付くさなればならないのは当然だと考えても、いざ実際に指揮者が代わり、しかもその指揮者が知名度において劣る人であった場合に、侮るような気持ちを持たずとも、実力の差に気付いたらそれは確実に歌唱に演技に表れます。オペラというのはそういう世界です。特に、日頃城谷さんの薫陶を受けている池田さんや、城谷・池田コンビによってワーグナーの世界に引きずり込まれた小林さんのような人たちであればともかく、藤村・ラデツキー両氏が城谷さんの指揮に安んじて乗りつつ、その持てる力を全開しているように見え/聞えたのは、いかに城谷さんのこの晩の指揮が素晴らしかったかを物語っています。
事情通から教えてもらったところによれば、大野さんはシェフを務めるバルセロナに飛ばなければならないため千秋楽を振ることができず、千秋楽だけ城谷さんに任せたということのようですが、この抜擢は大野さんが城谷さんに寄せる信頼と期待の大きさを示ししたと言えます。渦中の栗を拾って新国を救った大野さんと、千秋楽での抜擢に応えて見事に代役の代役を務め上げ、鮮烈な新国正規オペラ・デビューを飾った城谷さんに、満腔のブラヴォーを捧げます。(飯守さんが大野さんに代わったというニュースが流れたその時点で、既に千秋楽は城谷さんと決まっていましたから、「代役の代役」というのは厳密には不正確なのですが、実際の事の有り様としては正にそういうことだったろうと思います。)
ようやく冒頭の感想にたどり着きました。創立24年を経て新国立劇場は(そのオペラ部門は)ついに『我らの劇場』、『我らのオペラ小屋』になった!
日本人の素晴らしい歌手達を初めて知ったという意味は大きいですが、この感想はそのことだけを言っているのではありません。指揮者の突然の交代、主要キャストの来日断念、コロナによるオケ編成の縮小の必要性、そういった未曾有の危機に対応できる「力」が、日本のオペラ界にはあった、そして結果として事前の予想を遙かに上回る見事な公演を予定通りにこなすことができた、という感慨が、「我らの劇場」、「我らのオペラ小屋」がついに誕生したという思いを抱かせたのです。
城谷さんは今後、新国で必ずまたワーグナーを(そして、彼が他に何を得意とするのか知りませんが、望むらくは他のレパートリーも)振ってくれるでしょうし、小林さんは、ドン・カルロでもエリザベッタ役で登場します。楽しみですね。
本稿を書き渋っている間に、「我らのオペラ小屋」との感を更に強める経験をしました。ついこの間の「夜鳴きうぐいす」と「イオランタ」のダブル・ビル公演です。イオランタを歌った大隅智佳子さんの「夏の夜の夢」のヘレナに続く名演に、ノックアウトされました。世界水準の声と知性と気品溢れる演技。ほれぼれします。これまであまり知らなかったこのオペラが、私にとってはチャイコフスキーのオペラの中で最も素晴らしいもののように思えたのは、ひとえに高関さんの指揮と大隅さんの歌唱のおかげでしょう。東フィルの金管の節度を失わない輝かしさにも良い意味でビックリさせられました。ああ、我らのオペラ小屋!と私は独りごちたのでした。(公演全体としては声楽陣の一部に不満が残りましたが、「イオランタ」の総合的感銘度の高さを減じるものではありませんでした。「夜鳴きうぐいす」の方は、それに比べれば不満点は多々ありました。もっとも、これはクルレンツィスとデセイの超絶的名演(なんという顔合わせでしょう!)のDVDにこちらがスポルされていたからそう感じたのかもしれません。このダブル・ビルの着想自体、何と素晴らしくも大胆であることか。この着想が大野さんのものであったことを、私は確信しています。)
誤解のないように付け加えますが、「我らのオペラ小屋」というのは、偏狭な愛国精神に基づくものなどではなく、日本人歌手と日本人指揮者だけで上演すべきだといったような馬鹿げた論陣を張るものでも勿論ありません。自国民だけを起用するなどというオペラ小屋は、世界のどこにも存在しません。例えば同じ指環でも、ワルキューレはうまく行ったが、ジークフリートや神々の黄昏が、日本人歌手を中心とするキャストで、同じ水準での上演が可能なのか。そういう努力を続けてこられた二期会、藤原歌劇団、琵琶湖オペラ等々の関係者には申し訳ない物言いになってしまいますが、ジークフリート役一つを取って見ても、恐れを知らぬ天衣無縫・天下無双の若者こそ、文字通り余裕綽々の破天荒な歌い振りでなければなりません。そういう歌手が果たして日本にいるかどうか。このこと一つを取って見ても、キャストの国籍が大事だなどと申す積もりの無いことはお分かり頂けるでしょう。
そうではなく、オペラ劇場として、我々地域の愛好家(その中には外国人もおられるでしょう。)に支えられ、愛され、一つの有機体として機能し、今回のような未曾有の危機をも芸術監督の見事なリーダシップの下で一丸となって乗り切ることができる、そういう劇場こそが「我らのオペラ小屋」だと言いたいのです。
来季のプログラムも実に素晴らしいもので、いよいよ大野さんが企画においてもキャストの人選においてもその持てる力とリーダーシップを全面的に発揮し始めたという感を強く持ちます。皆さんも「我らのオペラ小屋」に是非ともお運びください。そしてご一緒に新国を支えようではありませんか。
知られざる名手たちによるピアノ・デュオの至福
2021 FEB 8 5:05:56 am by 大武 和夫

前回からまた相当の時間が経過してしまいました。すぐにも投稿を再開するつもりでしたが、頚肩腕症候群という症状を呈してしまい、首・肩・上腕部の痛みに苦しむ生活が続きました。生来のストレートネックによる頸椎ヘルニアが根本原因のようですが、巣籠り生活の中でスマホを注視する時間が増えた皆さんも、どうぞお気を付けください。
さて、ようやく症状が治まり始め、PCに向かえるようになったら、その間に書きたいテーマはどんどん増えてしまっています。前回頭出しをしたテーマは追って順次カバーするとして、今日は2月6日に聴いた長尾洋史・藤原亜美ピアノ・デュオのマチネー「連弾の楽しみ」について書きましょう。
長尾洋史さんというピアニストをご存じの方は、残念ながらそう多くはないと思います。しかし、オーケストラをよく聴く首都圏在住者で彼の演奏に接したことのない人は、ほとんどいない筈。そう、長尾さんは「オケ中ピアノ」の名手なのです。在京オケであると外国オケ来日公演であるとを問わず、たとえばペトルーシュカのピアノ・パートを頼まれるのは、たいていの場合長尾さんです。
私はペトルーシュカだけでも、オケ中ピアノを弾く長尾さんを何度も聴いています。いつ聴いても、その鮮やかさと正確さと言ったら、ブーレーズ/NYOの同曲名録音でピアノを担当する名手チャールズ・ローゼンの顔色を無からしめるものです。一事が万事。他のレパートリーでも水際立ったオケ中ピアノを聞かせる長尾さんは、譜読みが正確で速いことでも定評があり、滅多に演奏されないピアノ・パートを含む近・現代曲の演奏では、多くの場合オケを問わず長尾さんが登場します。
その長尾さんは、室内楽の名手でもある(←オケ中ピアノを通じてオケ・メンバーの信頼を勝ち得ていることの証左でしょう。)と同時に、実は隠れた(失礼!)ソロの名手でもあります。昨年は2枚のソロCDを発表していますが、特にゴルトベルク変奏曲には参りました。少しも奇抜なことはしていません。目立たないところで装飾音に工夫はしていますが、現代の演奏家で装飾音を楽譜通りにしか弾かない人はいないでしょう。テンポも総じて常識的。他の要素を犠牲にしても声部の違いを弾き分け、対位法をことさらに際立たせようとする偏執狂的な態度も皆無。様式に反する極端な強弱も、大仰なアッチェレランドや意図的なラレンタンドも、注意深く避けられています。要はすべてが中庸なのです。普通そういう演奏は、乾燥して豊かさに欠けるつまらないものとなりがちで、実際そういう演奏はとても多いと思います。しかし、長尾盤では、微動だにしないテンポと正確無比なリズムの中から、たゆたうような詩情が溢れて止まらないのです。これは一体どういう逆説でしょう。黄金の中庸というべきか。ゴルトベルクの私的ベスト・スリーに入るのはもちろん、ひょっとするとベスト・ワンかも、と思えます。
実は私はあるご縁で長尾さんと親交があり、このCDも発売前にお送り頂いて、あまりの感激に二度、三度と深夜すぎまで繰り返して聴いてしまいました。こんなことは滅多にありません。その感動を長尾さんに伝えるメールの中で「中庸」という表現を用いたところ、長尾さんから、大略、まさに「中庸」こそ自分がバッハで目指していることであり、来月号(記憶が正確なら昨年の2月号でしたか)の「ぶらあぼ」誌掲載インタビューでも同じ言葉を使っています、という嬉しいご返事を頂きました。
そして、長尾さんは、藤原亜美さんという、こちらも長尾さんに負けず劣らず私が大好きなピアニストと、時折4手を披露してくれます。この二人のデュオを初めて聴いたのは、忘れもしない文化会館小ホールでのメシアン「アーメンの幻影」で、でした。もう20年近くも前のことです。(文化会館小ホールと言えば、それまでの私のとっての最大のメシアン体験であったジャン=ロドルフ・カールスの「眼差し」全曲演奏の会場でもありました。四半世紀を隔てた不思議な符合という他ありません。)
精緻・精密の極致であり、あらゆる点で模範的な演奏でしたが、本当に驚くほど多種多様な感情を聴き手の内に呼び覚ますのです。この演奏が本稿の目的ではありませんから、これ以上述べませんが、我々にとって、さらには後世の音楽ファンにとっても幸いなことに、長尾・藤原デュオは、同じころこの曲を録音してくれています。これこそ、他のあらゆる名盤を凌駕する決定的名盤です。決定的名盤などという言葉は、それを用いることによって他の演奏の美点を心理的に覆い隠してしてしまう危険な副作用がありますから、滅多に使うものではありません。しかし、この録音については、私は躊躇なく決定的名盤と呼びます。録音も極上。メシアンに聞かせて上げたかった!
藤原さんは、長尾さんと並んでソロの隠れた名手でもあり、以前はかなりの数のソロ録音を発表しておられました。モシュコフスキーの全集などは、もっともっと注目されてしかるべき素晴らしさでした。(それに、舞台映えする美しい方です!)
その長尾さんと藤原さんは、3年前に巣鴨の小さなスタジオでドビュッシーの4手(2台と連弾)を披露され、このデュオは本当に世界最高水準だな、と私を改めて感激させています。そして、オール・ドビュッシーのCD2枚組が、来る4月にリリースされることになりました。ここでようやく昨日のデュオ演奏会に話を戻しますと、長尾さんによれば、その発売を記念して何かまたやりたいということで、6日の演奏会を企画したのだそうです。
コンタルスキー兄弟亡きあと、世界最高のデュオはこの二人だと確認させてくれた演奏会でした。ラベック姉妹、タールとグロートホイゼン等、4手のアンサンブルは多々ありますが、長尾・藤原の素晴らしさは頭一つ抜けています。
場所は、東京は目黒区洗足駅前のプリモ芸術工房という小さな会場で、聴衆は20名限定。プロは渋さの極みで、前半がシューベルトのD. 823(「ディヴェルティメント」と「アンダンティーノと変奏曲」の2曲からなる「フランスのモティーフによるディヴェルティメント」)とD. 951(「ロンド」)で、後半はドビュッシーのバレエ音楽「おもちゃ箱」(連弾への編曲は多和田智大氏;語り付き)。本当に渋い、玄人好みとしか言いようのないプログラムです。大衆的アピールはゼロ。
連弾の難しさは、経験したことのない人には分かりません。2台ピアノとは決定的に違います。2台のレパートリーはみな、程度の差こそあれ協奏曲的に、というか2台が競い合うような形で書かれています。連弾は一つの目標に向かって心と技をピタリと寄り添わせる必要がある点で、まず奏者2人の関係性が全く異なります。2台ピアノには超絶技巧を要する曲がいくつかありますが、連弾にはほとんど無いのも、このことと深く関係していると思います。
並んで座りますから、相手の身体の動きが直接感じられますし、腕が交差することもあります。異性同士の場合、身体的距離の近さがある種の感情にもたらすこともあるでしょう・・・私には幸か不幸かそういう経験はありません(笑)・・・し、異性同士でなくともある種の親密感が生まれるのは必然です。その反面、他の奏者に接する側の肩や腕の動きに微妙な制約を感じることも、ママあります。鍵盤を所狭しと指が駆け巡る超絶技巧が連弾に適していないことは、連弾曲に超絶技巧曲が見当たらないことの一つの原因でもあります。
フレージングやテンポ感を統一する必要があるのは、2台の場合ももちろん同じですが、連弾では、そのあたりに意見の相違が少しでもあると、2台の場合よりはるかに深刻な結果を招きます。
どちらか一方が踏むことになるペダルがまた厄介です。普通は和声を支える低音部担当者が踏みますが、高音部担当者のソロのような箇所では、高音部担当者にペダルが任されることもあります。ペダリングというのは、ピアノ演奏にとって極めて重要な要素ですから、自らペダルを踏まずに、しかしペダルが要求される曲を弾くというのは、ペダルを踏まない方の奏者に一定のストレスを与え得ます。自分ならこう踏むのになあ、とペダル担当者のペダリングに不満を持ったりしたら、精神的一体感が阻害され、アンサンブルは崩れるでしょう。何より集中を削ぎます。2台なら、各奏者がある程度の枠の中で自由にペダリングを行っても、演奏の統一感が損なわれる度合いはずっと小さいはずです。
おそらく最も重要なことは、ピアノ書法が全く異なるということです。2台の場合は、それぞれの奏者がピアノの全音域を演奏可能であるのに対し、連弾では、腕が交差する場合があるとは言え身体まで入れ替えることはありません(実際に入れ替わって弾く「曲弾き」はここでは考察の対象外)から、奏者ごとに担当する音域がおのずと決まってきます。すると何が起きるか。2台に比べると、連弾は中音域の音が厚いことになりがちです(必ずしも密集和音を意味する訳ではありません。)。したがって、声部間のバランスが常にうまく保たれていることが、2台の場合よりはるかに重要になります。
以上のことから、連弾は2台に比べて、親密さを表現するのにより適した媒体と言えますが、他方で、それにも関わらず音響現象としては、ガチャガチャとうるさいことになりがちだと言えます。プロのデュオでも、うるさいなあと思わせることは珍しくありません。常時デュオを組んでいる二人であれば、そんなことは起きないだろうとお考えですか? いえいえ、それは本当に耳が良く、センスが良く、お互いを理解し信頼しあっている二人が、曲への音楽的アプローチを共通にしたうえで綿密なリハーサルを繰り返すことによって初めて可能なことなのです。常時二人で弾いているデュオの場合、連弾というフォーマットを所与のものととらえてしまっていて、緊張感をもって演奏に臨んでいないなあ、と思わせる例も珍しくありません。
そのあたりの匙加減が、長尾・藤原デュオは本当に絶妙なのです。
第1曲で、高音部担当の藤原さんが長尾さんの盤石の低音部に載せて単純な上行スケールを奏でるところで、不覚にも目頭が熱くなりました。一体なぜこんな単純なスケールに感動するの?と思う間もなく、音楽は進みます。同じ曲の終り近く(ヘンレ版のシューベルト4手全集第2巻ですと最後の2ぺージ少々)で、長尾さんのスケールと藤原さんのスケールが親密に繰り返し歌い交わすところの美しさと言ったら!
二人とも弾き崩しの全くない正攻法で、自己顕示のための音量変化や恣意的テンポ変化を嫌う潔癖な楷書的解釈でありながら、その演奏からなぜあれほど無限のニュアンスが紡ぎだされ、心が揺さぶられるのか。魔法のようです。いや、考えてみると、これはシューベルトの音楽そのものにも言えることですね。シューベルトの笑顔と哀しみが同時に透けてみえるような曲の数々であり、演奏でした。これ以上何を望むことがあるでしょう。
後半のドビュッシーは、一転してセンスの塊。リズムの何と生き生きしていることか。そして和声が常に最善のバランスで鳴り響くことにも驚倒。長尾さんが音大の副科ピアノで指導を担当されたという多和田智大さんという方の手になる連弾用編曲が見事なら、ソプラノ歌手國光ともこさんによる語りも、鮮やかに情景を切り取って、曲の面白さを際立たせていました。
アンコールには、ドビュッシーの小組曲から「小舟にて」と、シューベルトが晩年に対位法を学んで作ったという「フーガ」(D. 952)が演奏され、素晴らしい午後のひとときが閉じられました。
こんな素晴らしい演奏会が、東京の住宅街の片隅でひっそりと行われているのです。連弾はピアノ・フリークにとっては興味の対象外かもしれませんが、もっともっと多くの人に聴いて欲しいと強く思いました。主催者はライブストリーミングの配信を行っていましたが、どれほどの聴衆の聴くところとなったのでしょうか。会場に来られなかった多くの人がPCやスマホで鑑賞したことを祈るとともに、巨大都市東京で、一見ささやかでありながら実は極めて重要なこのような音楽イベントを、一般の音楽ファンに知らせ、届けることの難しさに思いを馳せたことでした。プリモ芸術工房さん、ありがとうございました。
なお、これは蛇足ですが、プリモ芸術工房に設置してある1936年製NYスタインウェイの素晴らしさにも大きな感銘を受けました。無論演奏が素晴らしいから楽器の素晴らしさが引き立つのですが、今でいうとSに相当するように見える最小の小型グランドから、何と豊かで香り高い音が立ち昇ってきたことでしょう。この頃までのNYスタインウェイの色合いの濃さと、タッチに敏感に応じる俊敏さは、私にとってピアノの理想形です。つい拙宅の前世紀末のハンブルク製Bと比較してしまうのですが、帰宅後、頚肩腕症候群発症以来初めて少し鳴らしてみたハンブルクのBが、モノクロでダルな音に聞こえてなりませんでした。(もちろん腕前の劣悪なことに大きな原因があるのですが、それだけではないということです。)「このNYスタインウェイは欲しい!」と強烈な物欲に駆られるというおまけつきのコンサートでした。
再開の弁
2020 NOV 27 16:16:44 pm by 大武 和夫

最後の投稿から思いがけず長い期間が経過してしまいました。コロナ禍による環境の変化に呆然としていたということもありますが、何よりも生の音楽に接する機会を奪われたことが私には大きかったように思います。やはり私にとって生の音楽体験はかけがえのないものなのだと思い知らされます。こうして久しぶりに筆を執るようになったのも、音楽会・オペラが次第に増えてくるに連れ、言いたいことが少しずつ出てくるようになったからです。
とはいえ、この数ヶ月の間に書きたいと思ったことは何度もあり、友人にはそろそろブログを再開すると公言したりもしていたのですから、これだけ長い期間の沈黙の説明にはなりません。根本的には、私の怠惰な性格によるものだったと、反省を込めて思います。書かないでいるとそれが常態になってしまい、書くのが億劫になるのですね。困ったものです。今日は、その悪循環を断ち切るべく、思い切って筆を執りました。
休んでいる間に書きたいと思ったテーマは、実は沢山あります。頭の中でほぼ原稿が出来ていたものもあります。
概ね時系列順に並べると、「一山選手は凄い!」、「車は左、人は右?」、「荷物は座席の下へ~演奏会マナーあれこれ」、「ジャン=フィリップ・コラール再発見とフォーレの譜読みの難しさ」、「ノットの映像出演!」、「真央君でもこんなことがあるの?」、「原始女性は太陽であった(河村尚子讃)」、「やっぱり談志は苦手」、「夏の夜の夢考(ブリテン作品の新国上演に寄せて)」、「アルマゲドンの夢に落涙」。こんなところでしょうか。書き落としたものもあるかもしれませんが、思い出したらリストに加えることにします。
これらのテーマを次々に書いて掲載していきたいと思っています。
今日のところは頭出しだけですが、病人の社会復帰と同じで、いきなりの重労働は厳禁です(笑)から、慣らし運転からぼちぼち取り組んで行こうと思います。
改めて気長にお付き合い頂ければ幸いです。
東京マラソンに瀬古を思う
2020 MAR 3 0:00:22 am by 大武 和夫

ご無沙汰してしまいました。今日は昨日(3月1日)の東京マラソンについて、どうして書きたいと思いました。
感動しました。井上の果敢な飛び出しにも感動しましたが、何といっても大迫の勝負強さに、最近二回のマラソンの失敗からの完璧な復活に、そして一度後退したのにズルズルと順位を下げるのではなく立ち直って日本新記録まで手にした気持ちの強さに、打たれました。あのゴールシーンでじんと来なかった人はいないでしょう。
今回は前半のペースが凄かったため、ネガティヴ・スプリットは無理だと期待もしていませんでしたが、それでも30キロから35キロは圧巻のスプリット・タイム。優勝者レゲセを10秒も上回っていたというのですから、やはり大迫は只者ではありません。
自身中高と陸上部に属していて(ただし「オールラウンド出ると負けプレーヤー」と自嘲する落ちこぼれ部員でした)半世紀以上にわたる陸上競技ウォッチャーであり、特に長距離・マラソンを熱心に追いかけてきた者として、今回のレースの感動は半端ではありませんでした。
しかし、この投稿の目的は大迫をほめたたえることではありません。大迫の快挙を称えながらも、この記録とレース振りではオリンピックのメダルは難しいという趣旨の冷静な意見をレース後に述べた瀬古俊彦氏がいかに偉大であったかを振り返りたくて、筆を執ったのです。
そう、大迫の激走は、かつてわが国には瀬古俊彦という不世出の大選手がいたことを強く思い出させてくれました。二人とも早稲田出身で強い、というような話ではありません。そうではなくて、本当に世界の圧倒的ナンバーワンであった瀬古に、少しは近づけるかもしれない、「世界で戦うことを、それだけを意識した」日本人マラソン選手が、40年ぶりについに我が国に現れたということを言いたいのです。
瀬古の自己ベストは2時間8分27秒で、大迫の昨日の記録より3分近くも遅いのですが、それは、40年の時の流れ、トレーニング方法の進歩、靴等の用具の改良、選手をサポートする体制の違い、スポーツ医学の進歩等々を考えると、問題になりません。それどころか、瀬古の記録は、今なら少なくとも2時間3分台に匹敵することは間違いないと思います。瀬古と同等の才能と勝負強さを持った選手が現在理想的な環境で育っていたとしたら、その程度の記録は優に出せていただろうということです。それくらい瀬古という選手はけた外れに凄かった。
出るマラソンはことごとく優勝し、最後まで競り合ってもスプリント勝負で相手を置き去りにすることは間違いない、そんな選手は後にも先にも日本にいたためしがありません。
1980年だったかに東京の旧国立競技場で行われた陸上競技大会(企業名が付いた冠大会でしたが名称も年もよく覚えていません・・・)で、あのラッセ・ヴィレンと1万メートルで対決した瀬古は、最後の1周の圧倒的なラストスパートで、相手を置き去りにして優勝しました。それはもうほれぼれするぐらい見事な、美しいスパートでした。マラソン・ウォッチャーと言っても沿道で見るのは嫌いで、専らテレビ観戦派ですので、瀬古を実施に見たのはそのときだけでした。そして、そのトラック・レースで瀬古を見ることができたことは本当に幸運でした。世界一の選手の全盛期。そのあまりにも鮮やかな勝ちっぷりは、脳裏に焼き付いて離れません。
モスクワ・オリンピックへの日本の不参加は本当に衝撃でした。瀬古が出ていたら、ぶっちぎりで金メダルだったと今でも確信しています。(モスクワの優勝者チェルピンスキーとは80年の年末に福岡で対決し、瀬古が勝っています。)それだけに、ロサンゼルス大会への期待は大きかったのです。
アメリカ留学中もアメリカのマラソン雑誌を定期購入していましたし、瀬古が出る日本のマラソンの結果は、自宅に国際電話をして尋ねました。ネット世代には想像もつかないでしょう。Those were the days. サラザールは雑誌インタビューで、一番マークする選手として瀬古の名を上げ、「彼の1万メートルの記録は27分35秒なんだよ。なんてすごいんだろう。彼のことはうんとリスペクトしているよ。」と語っていました。実際には瀬古の1万のベストは27分42秒ですが、そんな細かいことはどうでもよろしい。27分42秒も、当時としては大きなリスペクトに値する優れた記録でした。そして、そう瀬古をほめたたえるサラザールの記事を読んで、同じ日本人としてとても誇らしい思いがしたものでした。(サラザールはその後オレゴン・プロジェクトの指導者として晩節を汚しましたが、現役時代は世界最高のランナーの一人として尊敬を集めていました。)
1984年夏のロサンゼルス・オリンピックは、アメリカから移り住んだロンドンで見ました。マラソン当日はロンドン到着直後で、まだシティの法律事務所での研修生としての勤務は始まっていませんでした。そして、その日の午後は、1歳の長女を抱いて、家内とハイドパーク探索に出かけました。
ところが、どうしたことか、途中でめまいがして熱っぽくなったのです。このまま散歩は続けられないなと思い、サーペンタイン・レイク湖畔のカフェテリアで軽い夕食をとり、タクシーで帰宅しました。フラフラしながら帰宅して熱を測ると、38度の熱です。その時点では、瀬古も事前に血を吐き、下痢をして最悪のコンディションだったことなど知る由もありません。しかし、なんだか胸騒ぎを覚えました。体温を計ってすぐにベッドに直行して休み、マラソンが始まる直前に起きだして、小さなフラットのチッポケな安物テレビの前に陣取りました。
25キロあたりからの悪夢のような光景に呆然としつつ、ひょっとして瀬古も私のような体調の悪さに苦しんでいるのではないかという考えが頭をよぎりました。圧勝以外はありえないと信じていましたので、敗戦のショックは言葉では言い表せないほどでした。深夜長時間のテレビ観戦も手伝って私の熱は更に上がり、少し大げさに言うなら、もう何がどうなってもいいという厭世的な気分になりました。それぐらい瀬古に寄せる期待は大きく、敗戦の落胆も大きかったのです。
瀬古は、帰国後しばらくは殻を破ろうとしてお嫁さん募集中と言ってみたり、それまで見せなかった笑顔を振りまいたりしていましたが、そういう瀬古にはもうあまり興味を持てませんでした。その後のシカゴとボストンの圧勝で、さすがは瀬古、やはり本当の世界一は瀬古だとの確信は戻りましたが、後から振り返ってみると、この二つのレースは偉大な選手の偉大なキャリアの最後の輝きだったのですね。
昨日のレース後の瀬古の上記コメントを、失礼だとか、優しさが足りないなどと受け止めた人もいるだろうと想像します。しかし、世界広し、マラソンの名選手多しと言えども、瀬古以外にそういう直言ができる人はいないのです。瀬古以外にそのようなことを言う資格のある人も、いないのです。
瀬古よ、良く言った。そして、瀬古がそういうことを言う気になったのも、大迫の才能と努力、そして精神力の強さに感じ入ったからに相違ありません。
願わくば大迫が、往時の瀬古の存在に少しでも近づいてくれますように。夏のオリンピックが中止になりませんように。そして大迫が、瀬古の二つのオリンピックの記録(ロサンザルスは14位、ソウルは9位)をしのぐ成績を残してくれますように。頑張れ、大迫!
美術と音楽・雑感
2020 JAN 14 18:18:24 pm by 大武 和夫

明けましておめでとうございます。本年が皆様にとって良い年でありますように。
さて、コートールド美術館展(東京都美術館)について投稿する予定だと書いてから、ずいぶん時間が経過してしまいました。その間に当の展覧会は終了してしまったのですが、そもそも展覧会についてというよりも、展覧会に触発されて私のセザンヌ愛について書いてみようと思っていましたので、今からでも遅すぎることは無いのです(←弁解)。しかし、年末に書き始めてみたところ、自分がセザンヌについて、更に言えば近代フランス美術史について、いかに無知であるかを思い知らされ、結局当面は断念せざるを得ないという結論に達しました。現在はセザンヌに関する本をいくつか読んで勉強しています。いつになるか分かりませんが、いずれセザンヌへの思いをきちんと語らせていただきます。
その概要を少し予告しますと、こういうことになります。
私はマネの平面性が嫌いです。マネに限りません。ジャポニスムの洗礼を受け始めて以降、西欧の画家が平面性を強調・追求する例は枚挙にいとまがありません。しかし、日本美術を知っている私には、乱暴な一般化をお許し頂けるなら、西欧画家の平面性はおしなべて過度に人工的かつ装飾的で著しく洗練を欠き、かつ本当の「魂」を感じることができない場合が多い。セザンヌはその対極にあり、いつもどうやってこの世界の、この宇宙の構造を二次元の絵画に表現し尽くすかを考えていたのだと思います。どんなに平面的に見えるタッチで造形しても、その造形センスの根本には、宇宙の成り立ちをキャンバスに写し取るという強い意志が感じ取れます。
その意味で、セザンヌからキュビスムへは、ほんの一跳びであるように思われます。しかしその一跳びは、アームストロング船長の月面第一歩ではありませんが、単なる一跳びではなく巨大な跳躍であったように私には思えます。というのは、セザンヌにとっては、キュビスムのようにこの世界を捉え「直す」ことは、彼が信じるこの世界・宇宙の成り立ちを裏切ることになったのではないかと想像するからです。(キュビスム誕生はセザンヌの没後ですから、時代的先後関係を無視した論述に抵抗を感じる向きもおありだと思います。私が言いたいのは、仮にセザンヌ自身が長生きしてピカソやブラックの業績を目にしたとしても、彼らに共感は持ったかもしれません(両者ともセザンヌを近代美術の父と崇めています。)が、自らその方向に進もうとは思わなかったに違いない、ということです。)
セザンヌのこの宇宙の構造への確たる信頼は、ほとんど信仰と言っても良く、ブルックナーが「三和音」に自分の全存在を賭けるほどの全幅の信頼を置いていたことと軌を一にするように私には思えます。ブルックナーの方がセザンヌより10数年早く生まれ、10年早く亡くなっていますが、大雑把に言えば同時代人と言えなくもありません。その時代の時代精神、でしょうか。更に言えば、フォーレも。実際には、フォーレの生年はセザンヌより更に6年遅く、没年は18年も後ですから、セザンヌを挟んでブルックナーとは一世代近く離れていることになります。しかし、晩年のフォーレの作品が、どれほど複雑を極める転調や分析し切れないような和音を重ねても、最後には三和音に対する全き信頼で高らかに曲を閉じる、そのあり方には、やや我田引水ですが、ブルックナーとセザンヌと共通する、自らの信念に賭ける一種の信仰者としての崇高さが光り輝いています。
ついでに書いてしまいますと、セザンヌの青は、いつも私にブルックナーの5番の終楽章のコーダを思い出させます。というより、終結部コラールの588小節以下で吹き鳴らされるホルンの旋律・・・峨々たるアルプスの山容をバックに悠然と空を舞う大鷲さながらの雄大さ・・・を聴くとき、私の脳裏には必ずセザンヌの青が浮かびます。そして、ほとんど必ず涙腺が緩みます。逆にセザンヌの傑作を見ていると、私の頭の中では必ずと言って良いほど、同じ5番のコーダか、フォーレのピアノ・トリオが鳴り響き、これまた忘我の境地に入ってしまいます。(正確に申すなら、ブルックナーは7番や8番のこともありますし、フォーレは弦楽クワルテットやチェロ・ソナタ、さらにはピアノ・クインテットであることもあります。)今回のコートールド展で、私が永年愛してきた「アヌシー湖」に数年ぶりで対面したときも、全く同じでした。何度も足を運びましたが、あるときはブルックナーが、そしてまた別のときにはフォーレが、私の耳元で鳴り響いて止みませんでした。視覚と聴覚というのも興味深いテーマですが、そこまで一般化せずとも、このようなセザンヌ=ブルックナー=フォーレという私の感覚が何故生じたかについては、是非とも分析し、いずれはなにがしかの文章にして投稿してみたいと思っています。
さて、そのコートールド美術館展はもう終わってしまいましたが、美術外のことにも触れますと、1930年代初頭に、コートールド氏は、彼が定期的に開催していたコンサートに、なんとシュナーベルやホロヴィッツ、クレンペラーなどを招聘しているのですね。そういう記録も展示してあり、これには驚きました。その場に居合わせたかった! 美術の目利きは音楽の目利きでもあったということでしょう。人生の達人、と言ってみたくなります。
いずれにしても、大改装のためにコートールドが閉館中であることから、この展覧会は実現しました。ですから、次の大改装までは、同じ質と数量のコートールド収蔵品が日本にやってくることは無いでしょう。また、しばらくはロンドンでも見られないのですから、昨年日本に暮らしていた我々は、実に運が良かったと言わなければなりません。
そのコートールド展と同じくらい素晴らしい展覧会が、実は現在まだ開催中です。三菱一号館美術館の「印象派からその先へ」(1月20日まで)。これには舌を巻きました。というのは、ここで展示されている吉野石膏コレクションなるコレクションを全く知らず、どうせ二流品ばかり揃えたコレクションだろうと高を括っていた(吉野石膏と美術館の関係者に深くお詫びします)ところ、驚くほど質の高い見事な作品群だったからです。
高を括ったもう一つの原因は、ポスターに私が苦手なルノワールの絵があしらわれていたことです。そこで、話が脱線しますが、ルノワールについて一言。
私は昔からルノワールが苦手だったのですが、その程度が亢進して「嫌い」というレベルにまで達してしまったについては、ピアノの巨匠リヒテルを恨まざるを得ません。リヒテルに関する書籍は山ほどありますが、その多くに、彼がいかにルノワールを嫌っていたかが記述されています。と言っても、賢いリヒテルは、直接的にルノワールを非難するのではありません。彼は、ドビュッシーのプレリュード1巻は、2巻と違い、決して全曲を弾きません。何曲かを除外するのですが、除外曲に必ず含まれるのが「亜麻色の髪の乙女」でした。その理由として彼は、この曲は「まるでルノワールの桃色のブヨブヨした女性の裸体のように気持ち悪い」から弾かない、と言うのです。リヒテルにとってドビュッシーは著名作曲家の中でも別格の存在の1人なのですが、そのドビュッシー作品の中でもこの曲だけはこのように酷評され、必ずルノワールが引き合いに出されます。全くルノワールもいい迷惑です。そして、画家でもあるリヒテルの言葉に、若き私は感化されてしまったのですね。無論、生来ルノワールが苦手という生地があればこそ、リヒテルの言葉が一定の共感を持って受け止められたのですけれど。
「亜麻色の髪の乙女」がプログラムされている演奏会で、この曲だけを聴かないという訳にはいきません(そもそもこの曲自体特に嫌いな訳ではありません)が、展覧会でルノワール作品を避けて通ることは容易です。「ルノワール展」なら、行かなければよろしい。そういうわけで、これまでルノワールはほとんどちゃんと鑑賞せずに来ました。
それで、三菱一号館美術館の展覧会については、そのルノワールがポスターとチケットにあしらわれている展覧会など碌なものではない、という先入観が当初私を支配していたのです。
実際には、その前にコートールド展で出会ったいくつかのルノワール作品には、やや心が動いていました。こんなことなら食わず嫌いを止めて、もっと以前からちゃんと鑑賞していれば良かったとも思いました。(何度も訪ねたコートールドでも、その他の国内外の多数の美術館でも、ルノワールだけは素通りしていました。)それでも、感覚的にルノワールは(そしてフラゴナールやワットーやローランサンは)私に縁遠く、心に訴えるものがやはり少ないのです。恐らく私は、満ち足りて豊穣な芸術が苦手なのでしょう。(晩年の素晴らしい室内楽録音を除きルービンシュタインを好きになれないのも、このことと通底するように思います。)
そういう偏見をまだ持ったまま三菱一号館美術館に足を運んだ私は、ルノワールの本当の良さに、初めて目覚めかける体験をしました。そういう作品が展示されていた、ということでもあります。もっとも、この展覧会で更に強く私の胸を打ったのは、初めて見るセザンヌ(初期作品)と、何点かの初めて実物を見るモネ、それにピサロとシスレーの各数点でした。ピサロとシスレーがこれほど偉大だったとは。特にピサロの画面構成には脱帽。また、ユトリロの良さにも開眼しかけました。更に、これも私が近年ようやくその真価を理解するようになったシャガールも、驚くほど質の高い作品が多数来ていました。作品名を忘れてしまいましたが、窓の外に広がる遠景の山々を写実的に描写した作品の、その遠景には心底痺れました。何という技量!
個々の作品に触れて論じる力量は私にはありませんが、総体としてこの展覧会は、コートールド美術館展、そして夏に開催された西洋美術館の「松方コレクション展」と並ぶ、昨年東京で開催された最良の美術展の一つであったと思います。あと6日で終わりますから、未見の方は是非ともお運びください。目を開かれること間違い無し。
吉野石膏という会社には満腔の敬意を表します。今世紀に入ってから始めたコレクションだというのですが、一体どういう目利きがアドヴァイザー/キュレーターとして関わってこられたのでしょう。そんな短期間でこれほどの質のコレクションが出来上がるなど、現代のおとぎ話としか言いようがありません。そういえば同社は、「ぶらぶら美術・博物館」のスポンサーの1社でしたね。いつも同番組の同社のCMを見ては、一体どういう会社なのだろうと思っていました。吉野石膏さん、ごめんなさい。しかし、このコレクションの志の高さを見るに、恐らく大変立派な理念を持った会社なのだろうと推測します。展覧会を企画された三菱一号館美術館とコレクションを創られた吉野石膏の関係者各位に、心から感謝したいと思います。
最後に、少し脱線しますが、リヒテルがホロヴィッツの最後の録音だったか、あるいはグラモフォンの録音のどれかだったかについて、大略「ホロヴィッツは指に過ぎない。しかし、一体何という指だろう!」と賛嘆した(あきれた?)言葉を思い出しました。何故この文脈で思い出したかというと、勿論セザンヌがモネを評した「モネは眼に過ぎない。しかし、一体、なんという眼だろう!」と語った有名なエピソードを、まず思い出したからです。リヒテルのホロヴィッツ評が、このセザンヌのモネ評を下敷きにしていたかどうかは分かりません。しかし、美術にも造詣の深いリヒテルのことですから、パロディー狙いではなかったとしても、そのエピソードが念頭にあったことは想像に難くありません。実に面白いですね。私個人は、あらゆる譜面から、人によっては人工的で小賢しく煩わしいと思うほど徹底的に音楽の立体的構造(ロマン派的ポリフォニー構造と和声的構造)を抉り出し、刻み出しては止まないホロヴィッツのあり方は、セザンヌかモネのいずれかと引き比べるなら、むしろセザンヌのあり方にこそ近いように思われるのですけれど・・・。このあたりには大いに異論があるでしょうし、そもそも私はモネも大好きですから、仮にホロヴィッツがモネに近いという発想があったとしても、それに異を唱える必要は無いのかもしれません。(まさかホロヴィッツをルノワールに例える人はいないでしょう(笑)が、もしいたら大いに異を唱えないところです。)
以上、素人の感覚的論述に過ぎませんが、音楽と美術というテーマは、非常に興味深いものがあります。(そう考える私が、両分野の表現者であったクレーの作品を愛するのは、自然なことなのかもしれません。)今後は、この両分野の相互作用に関する考察を深めて、美術についても折に触れて発信していきたいと思っています。どうぞ今年もよろしくお付き合いください。
秋のベートーヴェン・ピアノ演奏を振り返る
2019 DEC 22 18:18:09 pm by 大武 和夫

だいぶ時間が経ってしまいましたが、予告したベートーヴェン演奏について、思い出しながら書いてみます。
まずは岡田博美さんのリサイタル(11月9日、東京文化会館小ホール)から。
この演奏会は「軽妙洒脱の技」と題され、前半にベートーヴェンの4番のソナタとブラームスのパガニーニ変奏曲を置き、後半がドビュッシーの子供の領分とサン=サーンスが二曲という興味深いプログラムでした。苦手なサン=サーンスはさておくとして(名演だったと思いますが、何しろ曲に当方の感性に訴えるものが少ないので・・・)、何故「軽妙洒脱」と題されたのか、その意図がなんとなく分かる気がしました。もちろん、サラサラと表面をなぞるようにして名技を誇示するという意味では全くなく、いわば汗みずくの力演でない形で曲の本質をえぐり出すとしたらどういう演奏になるか、を岡田さんは見せようとしたのでしょう。
岡田さんは、これまでだって一度も汗みずくで力ずくの演奏などしたことが無いではないかと反論される向きもあるかもしれません。それは認めます。しかし、今回の演奏の「抜けきって」いたことは、岡田さんとしてもこれまで類を見ないものだったと思います。
なんと言っても圧巻だったのはブラームスでした。若い頃からのオハコで、何度も聴いていますが、技巧のために書かれたようなこの超絶的難曲で、これほど技巧を感じさせずに音楽的充実だけを味わわせてもらったのは初めてのことでした。美しく、深い。まるで後期の小品のようなズシリとした手応え。それでいて超絶的パッセージのこなし方は惚れ惚れするぐらいに鮮やかで、若き日の岡田さんと少しも変わらないのです。
実は私は、ブラームスの数あるピアノ曲の中で、この曲は比較的苦手でした。ミケランジェリやヴェデルニコフの超絶的名演はありますが、それらを通しても曲に本当に感動したことは無かったと思います。タウジヒの示唆を受けたブラームスが、名技性を追求するとこうなるということを示そうとして書いた若書きなのだから、音楽的深みが乏しくても当然だ、というのがこれまでの私の考えでした。これが偏見であることを示し、蒙を啓いてくれたという意味で、私にとって画期的な音楽体験でした。この岡田さんの歴史的名演をCD化しなかったらバチが当たりますよ、とカメラータに申し上げておきます。もっとも、カメラータの皆さんは、拙稿など見ておられないでしょうが・・・。
さて、岡田さんのベートーヴェンです。長いこと岡田さんの追っかけをやり、ロンドンにまで何度も聴きに行っていますが、4番のソナタを聴かせてもらったのは初めてでした。この演奏には驚かされました。奇をてらった解釈だったということではありません。およそ珍奇な解釈とは最も縁遠いのが岡田さんです。そうではなく、初期の作品であるのに、これもブラームス同様(演奏順で言えばブラームスはベート-ヴェンの次ですが)「抜けきって」後期作品のように聞こえるのです。晴れやかな若さにも欠けることは無いのですが、それより何より高雅な気品が全曲を覆っているのです。私好みのsfのガツンとくる荒々しさなど、薬にしたくもありません。全曲を聴き終えて通常感じる爽やかな一陣の風が吹き抜けていったような後味に加えて、なんとも言えない寂寥感や苦みが感じられたことに、心底驚きました。個人的には、疾風怒濤の時代精神がもっと前面に出ても良いように思えましたが、余人の及ばぬ境地であることは間違いありません。若い若いと思っていた岡田さんももうベテランの域です。現在の岡田さんの澄み切った心境の一端が伺えるユニークな名演だったと思います。
次にオズボーン。11月1日、トッパンホールの演奏会です。こちらは岡田さんとは正反対の、ガツンと来るベートーヴェンでした。それも最後の三曲でガツンですから、私の驚きは言葉では言い尽くせません。
オズボーンはベートーヴェンを確か2枚リリースしており、それらは彼らしいスタイリッシュで余計な思い入れを排したクールな味わいの名演でした。しかし、同じベートーヴェンのハンマークラヴィーアの数年前の実演の録画放送(NHKBS)では、前回来日時にメシアンの「幼子イエズスに注ぐ20のまなざし」の実演で見せたと同じ圧倒的な集中度の高さと燃え上がるようなボルテージの高さが顕著に見て取れました。それで私は、彼のCD演奏は、スタジオ録音の限界を示しているのだろうと感じていました。(実はオズボーンを知ったのはたかだかこの数年のことで、ハンマークラヴィーアを弾いた来日公演のときは、行けなかったのではなく、よく知らなかったので行かなかったのです。悔やんでも悔やみきれません。)
それでも、流石にハンマークラヴィーアとは違い最後の三つのソナタなのだから、もっとお行儀の良い演奏になるだろうと想像していました。しかし、その想像は完全に間違っていました。彼のベートーヴェンは徹頭徹尾「闘うベートーヴェン」なのです。最期まで闘うことを止めない存在。それこそがベートーヴェンだと言っているような演奏。
興が乗ると鍵盤をガンガン叩く、音が濁っても気にしない(気にはしているのでしょうが拘泥せずズンズン先へ先へと進む)、フレージングが多少不明瞭になっても、細かいことよりも全体のデッサンを大切にする、そういう演奏です。低回趣味と無縁といえば、このくらい無縁な演奏も無いでしょう。
一例を挙げましょう。Op. 111。この曲は、闘争的な1楽章と浄化に向かう2楽章という割り切った捉え方をされることが多いと思います。勿論それには一理あります。しかし、少し乱暴に整理してしまうと、オズボーンの演奏では、2楽章の中でも闘争と浄化が強烈に、激烈ともいえるような形で対比されるのです。彼は本当に興奮すると腰を浮かせ気味にして鍵盤を強打する癖がありますが、この晩を通じて彼が最も高く腰を浮かせ最も強く鍵盤を叩いたのは、驚くなかれ、Op. 111の最後の長大なトリルが始まる直前でした。DのトリルがGのトリルに移行し、そのトリルをはさんでアリエッタ主題が歌われていくわけですが、そのDのトリルの直前の小節です。スコアをよく見ると、そこに至る過程では、(sf→pを何回も挟みながらですが)長大なcrescが指示されています。そして、一カ所もffの指示は無いものの、Dのトリルの直前の小節では、16分の9拍子の3つ目、6つ目、そして9つ目の16分音符に、明確にsfの指示があるのですね。彼は、これを忠実に音化したかったのでしょう。その努力の結果、音は濁り、フレージングも不明確になり、浄化に向かう過程でこんなに汚い音で良いのかという疑念を私のようなナイーヴな聴き手に抱かせることになったのですが、彼には本望だったのだろうと想像します。そして、確かに他の誰の演奏とも違う闘うベートーヴェンが、最後のソナタの最後の2頁にすら現出していたことは間違いありません。
そのような解釈が典型的にうかがわれた箇所をもう一つ上げるとすると、以前の拙稿で畏友の表現を借りて「ブギウギ」と表した2楽章第三変奏でしょうか。これは凄かった。ちっともブギウギ風には聞こえず(そもそもブギウギではないのですからブギウギのように聞こえるか聞こえないかを論じること自体おかしいのですが、ブギウギ風だというのはリズムの面白さを印象づける演奏だという意味だとご理解下さい。)、なんだか怪獣が咆吼しているようなのです。早いテンポでアクセントを強打する結果、音は濁り、何をやっているのか分からなくなる寸前だったと言い換えましょう。でも、sempre fとsfの嵐を忠実に再現しようとした結果なのだろうと、ここでも私はそれなりに納得しました。(彼の技術の限界が垣間見えたような気もしましたが。)少し甘すぎるでしょうか。
しみじみと深い歌に欠けていた訳では無く、ppの沈潜や心からの「歌」の充実には心打たれましたが、全体から受けた印象は「ベートーヴェンは最期まで闘うことを止めなかった」というメッセージでした。これが今のオズボーンが表現したかったことなのだろうと思います。ある意味で、やや老成し過ぎたような感のあるイゴール・レヴィットの全集盤(レヴィットも天才中の天才として私は大好きであり、この全集は私にとって今年の「組み物of the Year」ですから、これは少し厳しすぎる言い方かもしれません。)とは、本当に全く対照的ですし、岡田さんの現在の演奏とも、違う意味で好対照。今後才能あふれるオズボーンのベートーヴェン解釈がどう変わっていくのか、楽しみに追いかけたいと思います。
そして、最後に河村さんです。彼女のベートーヴェンは、青葉台フィリアホール(10月26日)と紀尾井ホール(11月13日)で最後の三つのソナタを二度聴いたほか、コバケンさん/日フィルとの共演で皇帝も聴きました(11月9日、サントリーホール)。
最後の三つのソナタはどれも非常な名演で、感銘を受けました。全体の造形が見事であるのに細部が彫琢し尽くされていて、弾き手の意思が隅々まで及んでいる。何の意図もなく置かれた音など一つも無いのです。以前の河村さんのベートーヴェンには、ものすごく素晴らしいけれども、やや「面白すぎる」ところが散見されました。面白すぎるというのは批判を意図した表現ではないのですが、誤解を避けるために「以前は、どうしてもこうでなければならないという内的必然が、必ずしも常にすべての音に感じられるわけではなかった」と言い換えましょうか。今回の演奏は、まさに、あらゆる音に「こうでなければならない」という彼女の強固な意志(とベートーヴェンの強固な意志)が感じられたということです。これを論証するには私の筆力はあまりに乏しいので、一つだけ例をあげるに留めます。
またか、と思われるかもしれませんが、Op. 111の2楽章の第三変奏。例のブギウギです。この変奏での、細部まで考え抜かれていながらリズムが自然に躍動し、音が飛び跳ねる見事さには、本当に惚れ惚れさせられました。以前にも触れましたが、例えばリヒテルのフィリップス盤では、驚くほどリズムが正確なのですが、何も伝わってこない。砂を噛むようで全く面白くないのです。彼ほどの巨匠にもこういうことがあるのですね。(リヒテルはムラのあることで有名でしたが、それにしてもこれは無いだろうと思います。)河村さんのリズムは、もっとはるかに人間的で弾力に富んでいます。そして、度を越さないsfがリズムの魅力を際立たせます。バックハウスの大雑把なリズムとは対極ですし、オズボーンのように崩れたりもしません。そのリズムの素晴らしさが、そこから紡ぎだされるそれに続く浄化の過程にとって、どれほど重要な役割を果たしていることか!
総じて今回素晴らしいと思ったのは、細部の彫琢が全曲の感動をいささかも損なわないばかりか、「このような細部の積み重ねあってこその全体なのだ」と思わせてくれたことです。
皇帝も大名演で、特に2楽章の木管との対話など、河村さんから芳香が立ち上るかのように美しかった。コバケンさんの合わせ物のうまさにも改めて感服しましたが、2楽章はむしろ河村さんが指揮者であるかのように見え、聞こえました。しかし、何しろ河村さんですから、女性的な演奏だったというようなことは金輪際ありません。ある畏友は、かつて彼女の演奏を「男前」と評したことがあります。これは言い得て妙。決めるべきところで思い切りよくビシッと決める彼女の演奏の特質の一端を、実に巧みに言い表した名言だと思います。(誤解の無いよう申し添えますが、「男勝り」という表現が女性差別の色彩を帯びるのに対し、「男前」はジェンダー・フリー(?)です。)スキッと造形され、雄大さや力強さにも富む、理想的な「男前」の名演であったとだけ申しておきましょう。
以上のうち、オズボーンの演奏と河村さんの紀尾井ホールでの演奏には、NHKのカメラが入っていました。いずれも、おそらくBSの「クラシック倶楽部」で、その一部が遠からず放送されるだろうと想像します。楽しみに待ちたいと思います。
振り返ってみれば、今年は少なくともピアノに関する限り、東京・春・音楽祭におけるレヴィットのディアベッリ変奏曲の演奏や、本稿で触れた3人のピアニストの四つの公演等、心に残るベートーヴェン演奏に恵まれた年でした。生誕250年に当たる2020年にも大いに期待したいと思います。(東京・春・音楽祭で河村さんがクレメンス・ハーゲンとベートーヴェンのVc/Pfデュオ作品全曲を二晩かけて演奏するのが、まずは大注目ですね。)
蝶ネクタイの勧め
2019 NOV 28 20:20:54 pm by 大武 和夫

この先2回の投稿の内容を予告しましたが、なかなか時間がとれませんので、全く別のお話をひとつ。
サイト掲載の私の写真は蝶ネクタイ姿ですから、ご覧の皆さんは「何を気取っているのだ!」と思われるかもしれません。しかし、これは私の普通の姿です。
以前は結び下げのネクタイを普通に締めていました。それが20年前に、一夜にして変りました。そして今では結び下げネクタイは葬式に行くときにしか絞めません。ごくたまに絞めるだけですから、締め方を忘れていて往生します。(このことからお分かりのように、元来手先が器用ではありません。ピアノ演奏の腕もお察しの通りです。)だからと言って蝶ネクタイならサッサッサと短時間で容易に絞められるかというと、そういうわけでもないのです。それなのに常用するのは何故か、自分でも時々不思議に思います。
初めて絞めた蝶ネクタイは、留学先のハーバード・ロースクールの事務方の偉い人が後年来日した際に、お土産にくれたものでした。(これは大学の紋章をあしらったものですが、その後その紋章は、比較的最近全米の大学を吹き荒れた「奴隷制の名残はすべて一掃しよう!」という急進的学生運動のあおりで、廃止されました。同紋章は創立当時の高額寄付者の家紋を取ったものですが、その寄付者は自宅で奴隷を使用していたのだそうです。愛着のある紋章でしたから残念ですが、このサイトの禁止事項である政治にかかわる問題ですから、それ以上の意見は述べません。廃止された紋章を残すその蝶ネクタイは、今では時代の証人として貴重な存在となっています。)もらったは良いものの締め方が分からず、某輸入洋服店に行って締め方を教わり、ついでに、その店で売っていた蝶ネクタイも購入しました。締め方を教えてもらうだけでは申し訳ないと考えた私の気の弱さのなせる技です。(弁護士として活動するときには気の弱さは影を潜め、私のもう一つの個性である図々しさが前面に出るのですけれど・・・。)しかし、大げさを承知で申すなら、そこで買ったもう一つの蝶ネクタイが私の人生を変えました。
それまでにも蝶ネクタイは持っていました。夜の準正装(ディナージャケット=タキシード)に合わせるための黒の蝶ネクタイでしたが、それは形が出来ていて首に巻くだけ、という簡易型でした。従って、その使用を通じて実際に絞める技術を習得していたというわけではありません。
上記の店で買った蝶ネクタイは、おそらくはハーバードのCoop(生協)で取り扱っていたのであろう廉価な土産品と違い、品質がよくて遙かに絞めやすく、しかも柄、色調もとても良いものでした。その後今日に至るまで買い求めた優に百本を超える蝶ネクタイの中でも、お気に入りの一つとなって今日に至っています。
後述する「長所」にも書きますが、絞めると気持ちが引き締まる快感に味をしめた私は、毎日蝶ネクタイ姿で出勤するようになりました。当初は人目が気になります。20年前は日常的に蝶ネクタイを着用する人はまず見かけませんでした。ロースクール卒業後に研修生として受け入れてくれたNYの法律事務所にもロンドンの法律事務所にも、蝶ネクタイ着用者はいることはいましたが、勿論彼らは圧倒的少数派でした。まして当時の日本においておや、ということです。
しかし、これは私自身の自意識過剰のなせる技であるということもまた事実であったと思います。だんだんと人目が気にならなくなり、こちらが自然に振る舞えるようになると、東京のような大都会では蝶ネクタイに目を留める人も少なくなります。こちらが人目を気にすると注目されているような気がして恥ずかしいのですが、こちらが大胆に振る舞って人目など気にしない態度を取ると、他人は放っておいてくれるものです。
当初は、例えば週末に音楽会に行くときなどに蝶ネクタイ着用を躊躇したこともあるのですが、そういう仕事を離れたいわば「ハレの場」にこそ着用していくべきであると考え直し、現在ではおよそ上着を着る時にはほとんど必ず蝶ネクタイを組み合わせるという具合に進化(?)しています。(今でも秋冬には例外的にクラヴァットを首に巻くことがあります。しかし、暖房が強く入った場所では秋冬でも夏と同様に汗をかきますので、首に直接巻くクラヴァットの出番はどんどん減っています。)
さて、そういうわけで、現在は蝶ネクタイ100%の生活を送っています。その私から見た蝶ネクタイ着用の長所と欠点を列記してみましょう:
<長所>
* 結び下げより安い。意外に思われるかもしれませんが、使う生地の量が少ないからでしょう。Hermes等の高級ブランド品でも、蝶ネクタイの方が結び下げより安い価格設定になっています。
* 風が吹いても大丈夫。
* ラーメンの丼の中にネクタイが入ってしまうことが無い。
* タイピンというあまり粋でない小物(これは私の偏見)を使う必要がない。
* きちんと絞めると気持ちが引き締まり、仕事であれ、音楽会であれ、レセプションであれ、次なるイベントに向けて心の準備が出きる。
* 何より絞めるのが楽しい。上述したように器用でない私は、今でも物によっては苦労することがありますが、きれいに絞め上がったときの気持ちは実にすがすがしい。
* 太さや長さに流行がある結び下げと違い、まず流行というものが無い。従って、いつ求めた物でも、流行遅れなどを気にすることなく着用可能。
* 飛行機で着用しているとフライトアテンダントの扱いが顕著に違い、良い待遇を受けられる。これは複数の知人(米国人と日本人)の経験談で、私自身は試したことがありません。機内でくつろぎたいとき、特に長距離フライトで寝たいときには、邪魔になるとしか思えませんが・・・。
* すぐに覚えてもらえる。これまで見知らぬ方から音楽会のフォワイエや駅のホームで(!)突然声をかけられたことがあります。「いつも蝶ネクタイをしていらして、しょっちゅうお見かけするので・・・。」以前よく法廷に行っていたときには、書記官に「蝶ネクタイの先生」などと呼ばれることもありました。
* なんだか偉そうに見える(?)のか、例えば職場のビルの受付嬢が、大勢の中で私にだけにこやかに挨拶をしてくれる。
<欠点>
* 悪目立ちして、周りから浮いて見える。東京では、目立って見えるというのは自意識過剰の思い込みであり、ずいぶん前にその思い込みを克服しました。しかし、地方都市では、例えば大都市名古屋ですら、なんとなく好奇のまなざしを感じることが珍しくない。
* すぐに見つかるので悪いことはできない。(これが何故欠点なのか!というご意見もあるでしょう。)
* ホテルでバイキングの朝食の列に並んでいると、突然前にいたおばさまから「ちょっとお~、スクランブル・エッグ切れちゃってるじゃないのお。もお~!」とお叱りを受けたり、隣の列にいたおじさまから「済みませんが、小さいスプーンを取ろうとして落としてしまったのですが・・・」と話しかけられたりする。いずれのパターンも実際に複数回経験あり。スタッフの振りをして答えるというのも手ですが、面倒なので「そうですねえ・・・」とだえ答えて言葉を濁すというのが私の定番対応。そのうちに本物のスタッフがやってきて、発言者は目を白黒させることになります。こっちの蝶ネクタイは黒ではないのですけれどね。
* 吉本興業所属かと誤解される。
* ものすごく気取り屋だと誤解される。
* 超保守派と思われる。(そういう面もあることを自覚していますから敢えて「誤解」とは言いませんが、そうでない面も多分にある私は、見かけで他人を判断しないで欲しいと切に望みます。)
* どこでも手に入るわけではない。これはなかなか重要。特に日本では常時置いてある店は結構限られています。欧米だとてそう多くはありません。(しかしそれだけに、良品を探し求めて素敵な店・品に出会えたときの嬉しさは、実に大きい。)
* 暑いときや疲れたときに簡単に緩めることができない。結び下げならスッと緩めてまた戻すということが容易で、これは羨ましいと思うことがあります。もっとも、その対応作として、首回りが大きめのシャツを注文ないし購入するよう工夫しています。
* 様々な締め方を楽しむことができない。これは欠点には違いありませんが、同じ一つの絞め方でも、個々の蝶ネクタイに合わせて締め方を微妙に調節する楽しみはあります。
良いところと悪いところは、ざっとこんなところでしょうか。私にとっては、戦場(職場、裁判所、交渉現場等)に赴き、あるいは人前に出るに際し気持ちを引き締めるという効用が、他の全ての長所を上回り、全ての欠点を覆い隠しします。
最後に、これは長所のところに書くべきだったかもしれませんが、蝶ネクタイを愛用する法律家協会(略称「蝶法協」;英語名は「Bow Tie Lawyers Association」)という親睦団体があり、その創立メンバーの1人であることは、私の誇りとするところです。個人情報にかかわりますからメンバーのお名前は挙げませんが、著名法曹10名(正確には著名法曹9名と非著名な私の合計10名)が君子の交わりを楽しむという会です。共通点は法律家である他はただ一つ、蝶ネクタイを愛用するということです。会則には華美を排するとあり、Concert Goerの私は心配しましたが、演奏会・オペラに通うこと自体は華美とは言えないという甚だ文化水準の高い判断が会員の暗黙の合意であるようで、実に有り難いことだと感謝しています。
会員資格要件が蝶ネクタイの「愛用」であって「常用」でないところがミソです。会長のI教授や有力会員のH教授、F弁護士、そして私以外の会員は、常用まではされていないようにお見受けします。しかし、皆さん「普及活動」と称して、様々な場に蝶ネクタイ姿でお出かけになっては証拠写真を撮ってもらって会員間で交換し、あるいはSNSで披露するという、微笑ましくも麗しい努力を重ねておられます。ちなみに私は食いしん坊であることから、蝶法協のCDO(Chief Dining Officer)を拝命しています。必ずどこかのレストランで開催する総会に10名の男性が蝶ネクタイ着用で集うのは壮観です。珍しい光景にレストランのスタッフから驚かれることもあります。
蝶法協の名は海外にも轟きつつある(?)ようであり、先般は米国在住の米国人法律家から入会申し込みがあって驚かされました。もっとも、現在の人数が心地よく日本人入会希望者もお断りしているとして、謝絶しました。米国支部を作っていただくよう誘導すべきだったかもしれません。
皆さんも蝶ネクタイをお絞めになってはいかがでしょう。思いがけない心理的効果があるでしょうし、人生が変わる(?)かもしれません!
R.ゼルキン再説~シューマンのOp. 134と「赤とんぼ」
2019 NOV 19 14:14:26 pm by 大武 和夫

第1回投稿へのコメントに対するご返事に、先週末にアップする原稿にはR.ゼルキンを採り上げる予定であるとお書きしました。少し遅くなってしまいましたが、本稿では再びゼルキンについて書いてみます。
実は書きたいテーマは山ほどありました。すでに終わっている河村尚子さんとオズボーンのベートーヴェンの最後の三つのソナタの素晴らしい演奏、久々に岡田博美さんが弾いてくださった「十八番」であるブラームスのパガニーニ変奏曲の深く心に染み入る全曲演奏(あの超絶技巧曲でそんなことが可能だったとは!)、新国「ドン・パスクワーレ」のおしなべての水準の高さ、ノット/東響のベルクの圧倒的な美しさ、この季節になると無性に聞きたくなるフォーレの後期作品(ことにピアノ・トリオ/ノクチュルヌ13番/ピアノ・クインテット1番/チェロ・ソナタ1番/弦楽クアルテット)、興行成績が悪かったのか早々に通常版の上映を打ち切られてしまい現在では特別編集版だけが数少ない映画館でひっそりとかけられている(ように見える)是枝監督の「真実」、そして何と言っても5度も足を運んでしまった東京都美術館の圧巻の「コートールド展」のセザンヌ「アヌシー湖」、等々。
しかし、あれこれ迷っているうちに時間が経ってしまい、このままだと時期を逸してしまいそうになりましたので、冬に入る前にR.ゼルキンについてもう一度書かせていただくことにしました。(コートールド展のセザンヌとフォーレ、ブルックナーは私にとっては一つのテーマの変奏にすぎませんので、展覧会の会期が終了する前に一つの文章にまとめて書かせていただきます。そして、その前にできれば河村さんとオズボーンについて書き、その中でパガニー変奏曲と組み合わせてベートーヴェンの4番のソナタをも弾かれた岡田さんの演奏についても、触れようと思っています。)
なぜ時期を逸してしまう前にR.ゼルキンなのか。なぜ冬になると時期を逸してしまうのか。判じ物のようだと思われるでしょうが、それはゼルキンが畢生の名演を残しているシューマンOp. 134「序奏と協奏的アレグロ」(「序奏と演奏会用アレグロ」と訳されることもあります。)について、秋の間に書こうと思い立ったからです。(この曲の原題は、ややこしいことにOP. 92と同じ「Konzertstueck」(ウムラウトは本稿では「e」の挿入で代用)なのですが、英語題名も邦題も、2曲で訳し分けています。両曲を区別し、混乱を避けるためでしょうか。)
まだ判じ物ですね。なぜOp. 134の演奏について書くのが秋でなければならないのか。これはピアノ・マニア以外には正答が難しい問かもしれません。
答えは、演奏されることが稀なOP. 134には、あの「赤とんぼ」が何度も何度も、これでもかと言わんばかりに繰り返し登場するからです。それはもうびっくりするぐらいの大盤振る舞いで、まるで「山田耕筰讃歌」の様相を呈している・・・筈はありませんね。山田耕筰のドイツ留学は、もちろんシューマンがエンデニヒの精神病院で悲劇的な死を遂げたはるか後のことなのですから。
初めてこの曲を聴いたのは、R.ゼルキンとオーマンディー/フィラデルフィア管の共演の録音によってでした。記憶が正しければ、大学に入ったころ、つまりもう50年近く前のことになります。ゼルキンを初めて聴いたのはブラームスの2番のコンチェルトのセル/クリーヴランド管の演奏。その演奏に魂消た私(「衰えが隠せず寝ぼけた感じのバックハウス/ベームよりずっと良いじゃないか!」)が二枚目だか三枚目だかに買い求めたのが、忘れもしない、この曲が入ったLPでした。そして現在に至るまで、この曲でこの演奏を凌駕する演奏を知りません。
ややくぐもった色調でひそやかに始まった悲劇が高揚し、それが一旦収まった後、tranquilloの指示(オケはpiu tranquillo)を与えられたピアノがdurで歌うその歌(dolceの指示あり)の、なんと懐かしくも美しいことか! それが正に「赤とんぼ」なのです。「ラド~レミソドラソ、ラド~レミソラファレ」というそのメロディーを、「ユウヤ~ケコヤケ~ノ、アカト~ンボ」と重ねて歌ってみて下さい。そのままピタリと重なるわけではありませんが、主要な音の動きは瓜二つです。それによってもたらされる情動も。
この「赤とんぼ」の主題は、全編を通じて繰り返し現れますが、オケがおずおずと初めてこの旋律全体を奏する箇所と、結尾近くのピアノのカデンツァで32分音符のさざ波の中からくっきりと立ち上がって歌われる箇所では、名状しがたい懐かしさと望郷の感覚に胸が締め付けられる思いがします。そしてそのカデンツァのピアノ書法の見事さと言ったら! 死のわずか3年前の作品ですが、どこにも精神の変調、韜晦など見てとれず、シューマンがピアノに与えた最も美しいページの一つがここにあります。「苦み」が僅かに混じっているように聞こえるのは、彼のその後の人生を知っている後世の人間の先入観かもしれませんが、高揚はしても絶対に華やかにはならない、華美を拒否したような音楽のあり方は、やはり晩年の作品なのだと納得させられます。一種の静かな澄明さがカデンツァを、そして作品全体を支配しており、どんなに高揚しても声高にはならないのです。
そして、そのカデンツァを弾くゼルキンの演奏の立派さも、カデンツァ自体の見事さに少しもひけをとるものではありません。シューマンの精神の襞に分け入り、その情動に寄り添いつつ、例によって人柄の誠実さと朴訥さを隠せない無骨なタッチとやや不器用なフレージングで音を紡いでいくゼルキンの音楽は、少し感じ方の遅いようなシューマンの音楽・・・この表現はホロヴィッツのクライスレリアーナ旧盤のライナーノートで吉田秀和さんが使っておられた言い回しで、これだけで吉田さんの耳の良さと文学的素養・音楽的教養の深さが見て取れますね。借用させていただきます・・・そのものと言ってよく、全く理想的表現だと思わせます。
名前を挙げるのは申し訳ないのですが、例えば比較的最近のペライア/アバード/BPOの共演盤の演奏は、流線形の演奏の典型で、実にサラサラと流れます。演奏時間はゼルキン盤が14分40秒もかけているのに対し、こちらはたったの12分47秒ですから、全体のテンポ設定もだいぶ速いことが分かります。その結果として立ち現れる(因果関係はあるいはその逆か?)少しの淀みもない演奏は、無類に美しいのですが、和声が変化する箇所や、フレージングの切れ目などにはほとんど無頓着で、先へ先へとずんずん進んでしまうように聞こえます。テンポの揺れもほとんど感知できません。散歩の道すがら美しい花が咲いていたり、美しい山が見えてきたら、歩を緩め、あるいは足を止めて、鑑賞したくならないでしょうか。このスマートで現代的な演奏には、そう問いかけたくなります。カデンツァを通して用いられる32分音符の音型は、予想通り見事にノッペリ・スッキリと弾かれていて、ある種のリストの曲の伴奏音型のように響きます。優秀な音楽家ペライアの演奏ですから、これは多分に誇張した批判なのですが、それでも、シューマンらしくないと私は考えてしまいます。こういうところで32分音符がきちんと聞こえてこないと、それはもうシューマンではないのです。(ホロヴィッツはリストの32分音符ですら、決してノッペリ・スッキリとは弾きません。ゼルキンがリストを弾いたとしても、同じだったでしょう。)それはなにも、ガチャガチャうるさく弾けということではありません。そこから赤とんぼの主題が立ち上ってくるのですから、あくまでも背景として静かにひっそりと奏でられるべきであることは当然です。しかし、それがノッペリしていたのでは、音楽が必要とする深みは表現し切れません。ペライアはゼルキンに(も)師事し、カーティスではその助手も務め、あまつさえホロヴィッツの親交を得てロマン派音楽を学び直しもしたというのに、一体どうしたことでしょう。(ペライアは他にも、バッハを沢山弾く前にバロックを学んだと言っていますが、あまりにも流麗な彼のバッハを聴いていると、例えばイネガル一つとっても全くモノになっていないように聞こえます。この俊英にとって残念なことです。)
ロマン派音楽が、地上には存在しない永遠の高みに憧れ、その高みを目指して駆け上ろうとしつつ、それが叶わぬ夢、報いられぬ徒労に終わることを知り、それでも、いやそれが故にこそ、益々憧れが強まり、結果として苦悩し、傷つき、再度立ち上がって再び高みを目指す、そしてまた傷つく、という情動のうちに成り立つものであるとすれば、シューマンの音楽こそ、まさに典型的なロマン派音楽、ロマン派中のロマン派音楽であると言えるでしょう。そして、mollとdurが赤とんぼの旋律をめぐって交錯するこの曲ほど、シューマンがロマン派中のロマン派であることを示す作品が他にあるでしょうか。
そうであるなら、全てのフレーズにそのロマン派の精神が反映されていなくてはなりません。さらさらと流れる歌、ノッペリとした伴奏音型、流線形のスマートさ、そんなものはシュ-マンにあってはならないのです。あってはならないと、私はそう信じます。そして、そのようなシューマンの精神を現実に響く一音一音に籠めた演奏が可能なのは、わが偏愛のゼルキン(とホロヴィッツ)しかいないではありませんか。(これはレトリックであり、現役ピアニストたちの中にも見事なシューマン弾きは数名います。念のため。)
この曲をオーケストラ作品ととらえた場合、これに匹敵するオーケストラ作品がシューマンの作品中に存在するとは思えません。賛同者はおられないかもしれませんが、4曲の交響曲の中で最もシューマネスクと言われる2番より、私はOp. 134の方がさらにシューマネスクであると考える者です。
ピアノ独奏曲には、大幻想曲とクライスレリアーナという記念碑的作品であると同時に最もシューマネスクである金字塔が二つありますが、オケを伴う完成したピアノ作品三つ(Op. 134の他に、協奏曲Op. 54と冒頭で触れたOp. 92があります。)の中では、断然この曲をとります。
そうであるのにOp. 134の驚くばかりの人気の無さはどうでしょう。ピアノ・オタクの私ですら、一度たりとも実演で聴いたことが無いのです。数年前に、敬愛するアンスネスに3曲を一回のコンサートで弾くプロジェクトをやってもらえないかと頼んでみたことがあります。しかし、あまり気乗りしない様子で、それは良いねえというおざなりな返事が返ってきただけでした。河村尚子さんなどはアンスネス以上に最適任者のお一人だと思うのですが、次にお目にかかるときにお願いしてみようかと思っています。
そもそも演奏されることが少ないこの曲に、最高にシューマネスクな名演奏を残してくれたゼルキンに感謝するばかりです。また、日本では遂に評価されることなく終わったオーマンディーの指揮も、過不足ない出来を示しています。フィラデルフィア管というと華麗なオケであるとの先入観が存在しますが、実は木管が(木管も)素晴らしいということがよくわかる録音です。コロムビアの録音も、カッチリとしつつも冷たくなりすぎない立派なものです。(この盤の後で先述のペライア盤を聴くと、あまりにスムーズで角の無い録音に驚かされます。アメリカとヨーロッパの録音の違いと言って片付けるのが憚られるほどの違いです。演奏に見合った録音というべきか、あるいは録音に見合った演奏というべきか。)ゼルキンにとってもこの録音は、A.ブッシュとのシューベルトの大幻想曲、ハンマークラヴィーア、ブラームスの晩年の作品集、先述のセルとのブラームスの2番のコンチェルト等々と並んで、最重要の録音の一つであると言ってよいと思います。
最後に、初めてこの曲を聴いたときに「赤とんぼ」に驚いた私は、山田耕筰が留学中にこの曲(の楽譜ないし演奏)に接したに違いないと考え、少し調べてみました。しかし、残念ながら、どこにもその答えは見つかりませんでした。(答えをご存じの方がいらしたらご教示ください。) さらに、この曲と「赤とんぼ」の旋律の類似性について、誰かが何か書いていないだろうかと考え、その点についても調べてみましたが、当時そういうことを指摘した文献を見つけることはできませんでした。それで私は得意になって、音楽好きの知人たちに、私の「発見」を得々として語ったものでした。しかし、これほど強い類似性に、音楽の素養のある人が気付かないはずはありません。類似性はあまりに自明なので、誰もことさらにそれを説いたりする必要を認めなかったのでしょう。私の独り相撲であり、若気の至りであったということだろうと、今にして思います。汗顔の至りとはこのことです。それから半世紀近く立った現在では、ネットをググれば、すぐに類似性に関する考察を見つけることができます。
これで終えようと考えて読み直してみて、全曲に横溢する「懐かしさ」の感覚と「赤とんぼ」の関係について、きちんと触れていないことに気付きました。つまり、懐かしさの理由が、旧知の赤とんぼに出会えたからなのか、それともそれ以外の事情によるものなのか。初めて聴いたときから「赤とんぼに似ている!」と考えて聴き続けてきたこの曲に対し、その要素を捨象して向き合うことはもはやできません。ですから、前者の要素を否定することは不可能なのですが、しかし、赤とんぼを知らなかったとしても、赤とんぼ類似の旋律自体に、そしてOp. 134の高揚しても決して大言壮語しない曲の作りに、そのしみじみと語りかける美しさに、ある種の懐かしさを覚えないこともまたあり得ないと思うのです。答えにならないこの独白で本稿を閉じることにします。
ピアノ演奏と映像 その(2)(完)
2019 NOV 8 2:02:58 am by 大武 和夫

前回は河村尚子さんを共通項とする二つのピアノ映像のうち、R.ゼルキンのベートーヴェンを取り上げました。今日は二つ目の「蜜蜂と遠雷」について書いてみましょう。
その前にお詫びと補遺を。お詫びは前回投稿に誤記・編集ミスがあったこと。一番ひどい誤りは、投稿一覧に表題が出ない形で投稿してしまったことです。これは親切な会員が直してくださいました。他のミスについても訂正方法を教えてくださいましたが、間違いがあっても皆さんには判読可能だったと思いますし、間違いを残しておくのもご愛敬で初回投稿の記念になると考え、そのままにすることにしました。ご海容ください。補遺の方は、音源だけの名演奏を挙げた際に、ついうっかりヴェデルニコフ盤とA.フィッシャー盤に言及し損ねたこと。こちらの方が罪は大きでしょう。どちらも本当に見事な演奏で、二人の掛けがえの無いアーティストの残した宝物です。特にヴェデルニコフは、驚くばかりの模範的名演奏です。
さて、「蜜蜂と遠雷」です。結論から言えば、是非ご覧になることをお勧めします。何しろ演奏が素晴らしい。俳優も総じて好演で、中でも私が贔屓にしている松岡茉優さんが見事な演技を見せます。
もともと原作を私はあまり評価していませんでした。本に詳しい元出版社編集部員の友人から勧められ、あまり気乗りしないまま電子書籍で読みました。なかなか良いとは思いましたが、「ピアノの森」には及ばないと思いました。コンクールに参加する若者群像というテーマは「ピアノの森」にも共通しますし、古くはあのくらもちふさこさんの傑作漫画「いつもポケットにショパン」のテーマでもありました。(「いつもポケットにショパン」を私は別マ連載時にリアルタイムで読みました。キーシンが国際的に活躍する前なのに、主人公2人のうちの男の子の名前が「きしん(季晋)ちゃん」だったり、当時は桐朋在学中で後年私の「追っかけ」の対象となる岡田博美さんの名前が登場人物間の会話で言及されるなど、くらもちマジック炸裂の大傑作。ピアノ好きにとっては必読書です。私など、以前ご存命中の吉田秀和さんに送って差し上げようかと思ったくらいです。ちなみに、もう一人の主人公である麻子の名前は、わが長女と同じです。と言うより、その素敵な主人公の名前を長女命名の際に参考にさせてもらったという方が正確であり、この作品はその意味でも私にとって忘れられない名品なのです。)
そういう訳で私は原作を読んでいる間中「二番煎じ」という思いが頭から離れませんでした。恩田さんが二つの先行作品を参考にされたかどうかは知りません。もし偶然だったのだとしたら、それは恩田さんにとって不幸なことでした。なぜなら、私のようにピアノ関連書物を渉猟してやまない人間には、どうしても二番煎じと映ってしまうからです。
しかし、それで原作の評価を是正(上方修正)するとしても、映画は、私には原作を上回る出来と思えました。何よりもそれは音楽の力であり、映像の力です。4人のピアニストが主要登場人物4名の音源を担当していますが、皆素敵な演奏です。とりわけ、私が「追っかけ」状態にある河村尚子さんと藤田真央さん、この二人の演奏が素晴らしい。二人とも自発性と音楽する喜びにあふれる演奏で知られる天才ですが、藤倉大さんのオリジナル曲「春と修羅」の演奏がどちらも何とも鮮やかです。河村さんのプロコフィエフの3番のコンチェルトを聴くのは、大友/群響との共演以来のことですが、まさに圧倒的なエネルギーの奔流です。
心配した映像と音のシンクロ具合も、うまく手を隠したり、手と身体が同時に移るところではカメラを引き気味にするなど、あまりボロが出ないよう工夫しています。細かく見ればおかしいところもあるのですが、それでも総じて栄伝亜夜役の松岡茉優さんの演奏ぶりはなかなか自然で、大健闘と言えます。プロコフィエフの3番のコンチェルトを亜夜が弾いている場面を上からとらえた映像では、鍵盤を走る腕と手が鮮明に映し出されますが、その音とのシンクロ具合は、息を飲むほどです。一瞬河村さんの手と腕かと思いました。後日お目にかかった河村さんは違うと教えてくださいましたが、実は松岡茉優さんの手・腕でもないのだそうです。これ以上は企業秘密かもしれず、暴露がためらわれますので、皆さんのご想像にお任せします。とにかくこの場面には驚かされました。
それにしても松岡さんは良い女優に成長したものです。是枝さんの「万引き家族」での体当たり演技で一皮むけたと思いましたが、「蜜蜂と遠雷」のこの役は彼女のために作られたのではないかと思わせるほどの自然な演技です。それでいて濃密な感情を画面いっぱいに漲らすことができるのですから、大したものです。過日放送されたNHK「ららら♪クラシック」に河村さんと一緒に登場した松岡さんは、河村さんの演奏の感想を語っていましたが、その内容が実に的確であることには、失礼ながら驚かされました。ピアノは小さいころに習っていただけだと言っていましたので、きっと生来音楽を感じる感性に秀でているのでしょう。
音楽とは直接関係ありませんが、斎藤由貴さんの英語が見事なことは特筆大書ものです。脚本があってしゃべっているのですから、あれがそのまま彼女の英語力を示すものだとは思いませんが、それにしても見事です。純日本産・純日本育ちの人であれだけちゃんとした発音をマスターしている人はほとんどいません。同時通訳でも、発音だけみれば彼女に劣る人はいくらもいます。ただし、それが映画にリアリティを与えるのに役立っているかはまた別問題で、もう少したどたどしい方が、あの審査員役によりふさわしかったかもしれない、という贅沢な感想を持ちました。(「シン・ゴジラ」で米国大統領特使を演じた石原さとみさんにこそ、斎藤さんの発音が欲しかった!)
映画については誉め言葉だけだと思われるといけないので、付け加えますと、不満も結構あります。
まず、少女時代の亜夜が今は亡き母親と連弾に興じる場面。まだヒット中ですからネタバレを避けて曲名は書きませんが、ソロの某超名曲を即興で(?)アレンジして、親子が連弾するという美しい回想シーンです。しかし、そのアレンジが、あまりセンスが良いとは思えません。担当作曲家には申し訳なく思いますが。(その点、NHKで放送したアニメ版「ピアノの森」の冒頭に流れるショパンのエチュードOp. 10-1のアレンジは見事でした。途中からオケがかぶさってくるそのオケが、ピアノ・ソロによく合っていて、美しく心地好いのです。シリーズの何回目かまで見進んだ時には、少し大げさに言えば、そのオケ伴付きのバージョンがそもそも原曲だったのではないか、と錯覚してしまうほど耳に馴染んでいました。)
連弾といえば、映画の一つのクライマックスである亜夜と塵の連弾シーンにも不満が残ります。あまりに丁寧に作りこまれていて、即興らしさが皆無。二人の息がピタリ合って、コーダに至るまで意見の不一致がどこにも無く、何のほころびも生じないなんて、ジャズのどんなジャム・セッションでもあり得ません。これも映画全体からリアリティを奪う結果となりました。
次にあげるべきは、やはり指揮者の演技でしょう。鹿賀丈史さんの力演で、心理描写は悪くないのですが、その指揮姿がいかにもサマになっていません。こんな棒にオケが付いてくるはずは無いと思ってしまうのです。本物の指揮者が稽古を付けてあげるといったことができなかったのでしょうか。予算の都合?
他にも不満点はたくさんあるのですが、開始直後に引っ掛かった場面は、私にとって実に重大でした。その後ずっとそのひっかかりを引きずってしまい、本当の意味で映画に没入できなかったのですから。それは、聴衆と思われる音大生風の女の子2人が、会場フォワイエの階段を下りながら、「カーネギーでコンツェルトまでやってるんだって!」とコンテスタントの噂をする場面です。噂の対象は、おそらくはジュリアードの学生、マサルでしょう。引っ掛かりというのは、「カーネギー」という言い方をするだろうか?ということと、「コンツェルト」っていったい何だ?ということでした。
「サントリーホール」を「サントリー」と略称することはちっとも珍しくありませんが、日本の音楽ファン、それも学生が、「カーネギ-ホール」を「カーネギー」と呼ぶことは、皆無とは言いませんが珍しいでしょう。また、協奏曲を「コンチェルト」と呼ぶのはごく普通のことですが、あえてドイツ語を使って「コンツェルト」という日本人はいません。少なくとも私はそういう日本人にお目にかかったことがありません。原作にそうあるのか脚本家の発想なのかは分かりません(原作を再読して調べてみようと思いつつ果たせずにいます。)が、おそらく「音楽を志す学生は通(ツウ)ぶってそういう言い方をするのだろう。」という誤った推測に基づくのだろうと思います。「神は細部に宿る」と言いますが、こういう細かいところで、原作者または脚本家(および映画監督)のお里(音楽的教養の程度)が知れるのです。なお、「コンツェルト」という言い方は、映画の中でもう一度出てきました。その場面と発言者は覚えていませんが、同じ引っ掛かりをさらに強く持ちました。ひょっとすると私の聞き間違いで、実際には二度とも「コンチェルト」と言っているのかもしれませんが、違う俳優が異なる場面でそれぞれ発音しているのですから、聞き間違いの確率は低いと思います。それに、筋金入りの音楽ファンであると同時に、職業柄、言葉の選択と発音にはうるさい(和英とも)私は、滅多なことで聞き間違えません。特にそれが音楽に関連する事柄であってみれば、です。(日常生活でボーッとしているときには、よく家族の言葉を聞き違えて怒られますが、それはそれ、これはこれです(笑)。)
以上を要するに、クラシックおたくにとってはリアリティの欠如と言わざるを得ない場面、興覚めする場面がたくさんあるのですが、それでも映画館に足を運ばれることをお勧めします。(もっとも、私が見た日比谷シャンテでは、ff時にスピーカーの僅かなびり付きが気になりました。映画館にコンサートホールの生の音を期待しないことです。)冒頭に書いたように、音源を担当した四人のピアニストの演奏のすばらしさと、松岡茉優さんの演技の素晴らしさが、この映画を一聴(「一視」という言葉は無いのか・・・)の価値あるものとしています。
ピアノ演奏と映像 その(1)
2019 NOV 5 22:22:46 pm by 大武 和夫

はじめまして。当クラブの編集ご担当が既に私の紹介文を載せてくださっていますが、重複にわたらない範囲で自己紹介させて頂きます。弁護士業42年、ピアノ演奏歴(下手の横好き)60年弱、音楽愛好歴(クラシックとジャズ)と落語愛好歴はどちらも50数年で、所属事務所のパートナーを退いた今は、予定を入れるのも音楽優先になりつつあります。
私にとっての「神」は、ベート-ヴェン、ブルックナー、セザンヌ、フォーレ、ホロヴィッツ、キース・ジャレット、古今亭志ん朝ですが、うち幾人かについてはいずれ項を改めてじっくり書きたいと思っています。
音楽好きが嵩じて、音楽関連で言いたいことが出てくると音楽好きの友人数名にメールを送ってはうるさがられる、ということを繰り返してきました。そこで、どこかに自分の意見を投稿したいと次第に思うようになりました。自己承認欲求というよりも、まとまった形で書いた物を残しておける場所があり、時折訪ねてくれる(かもしれない?)友人知人の笑覧を請うという形が、その都度メールを押しつけがましく送るよりスマートではないかと思い始めたからです。
そんな折に、発起人である東さんの書かれたものをこのSMCサイトで見つけ、興味を惹かれました。と言うより、ここまでクラシック音楽に造形が深く、しかもその体験を言語化できる愛好家がおられるこということに、同じ愛好家の一人として驚き、感動しました。そして、こういう方が主催されるサイトの片隅に私の駄文がひっそりと置かれるとしたら、それは素敵ではないか、と思ったのです。幸いお仲間に入ることができましたので、こうして初投稿に及びました。
もっとも、音楽家以外の「神」も上に挙げたことからお分かりのように、決して音楽一筋ではありません。絵画や落語、映画などについても折に触れて投稿させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
前置きはそのくらいにして、本題に入ります。最近二つのピアノ演奏映像を見て、いろいろ思うところがありましたので、そのことについて書いてみましょう。
一つはルドルフ・ゼルキン(以下単に「ゼルキン」。ちなみに、これも優れたピアニストである息子は、我が国では独語読みの「ペーター・ゼルキン」でも英語読みの「ピーター・サーキン」でもなく、「ピーター・ゼルキン」という不可思議な読み方をされていますが、やはり英語読みすべきでしょう。)の晩年のウィーンでのリサイタルの実況録画を収めたDVD。もう一つは、話題の映画「蜜蜂と遠雷」です。
この二つには、ピアノという以外に共通項が無いと思われるかもしれません。しかし、」私にとっては大きな共通点が存在します。それは、河村尚子さんです。(このブログでは、不統一を承知で、日本人名には基本的に「さん」を付けますが、外国人については著名人の場合は敬称を略します。)
河村さんがどれほど優れたピアニストであり、私がどれくらい彼女に惚れ込んでいるかは、日を改めて書きたいと思いますが、現在日本各地でベート-ヴェンの最後の三つのソナタを弾いておられます。また、河村さんときびすを接するようなタイミングで、これも私が敬愛するスティーヴン・オズボーンが来日して、同じ3曲を披露しました。前記の父ゼルキンのDVDは、正にベートーヴェンのOp. 109~Op. 111の演奏を収めたものでした。そして、「蜜蜂と遠雷」では、主要登場人物の一人である栄伝亜夜の演奏を、河村さんが担当しておられます。それもたっぷりと。そういうわけで、この二つの映像作品を並べて論じるには、私なりの必然性があるのです。
と言っても、河村さんのOp. 109~Op. 111の演奏はここでは論じません。河村さんのお名前を出したのは、本稿の関係では、あくまでも二つの映像作品をつなぐものとして、でした。
さて、まずはR.ゼルキンです。ホロヴィッツを「神」とし、その人間性の醜悪な一面も含めて全面的にホロヴィッツに「帰依」する私が、ゼルキンをも同等に愛し、むしろホロヴィッツ以上に深く尊敬していると言うと、驚く人がいます。そうでしょうね、一方はショーマンシップの権化のように言われ、他方は厳格なドイツ楽派でショーピースはまず弾かない石部金吉だったのですから。
しかし、この二人が肝胆相照らす仲であったことは疑いありません。ゼルキンは、道化の仮面の裏にあるホロヴィッツの深い音楽性と底知れない音楽的教養(これについても後日書く積もりですが、私は「音楽的教養」という言葉を「教養」とは区別して用います。)に畏敬の念を抱き(ある夜若き日のホロヴィッツの家を訪問しようとしたゼルキンが、窓から漏れてくるハンマークラヴィアのフーガの練習の見事さに慄然としたというエピソードは、よく知られています。)、ホロヴィッツはホロヴィッツで、独墺から見れば一種の辺境に生まれ育った自分と対比したときに、独墺の音楽的伝統のただ中に生まれながらも自由に音楽をはばたかせることができる同い年のゼルキンに対し、一種の憧憬を持ったのではないでしょうか。そしてまた、ゼルキンの音楽への徹底的で完全な没入に、自分と似た資質を読み取り、大きく共感するところがあったことは想像に難くありません。ゼルキンという人は、あの偉大なシュナーベル(私は彼も大好きで敬愛しています。)に対しても、練習をさぼるノンシャランな態度を容赦なく糾弾するという一面を持ち合わせていましたが、その彼がホロヴィッツを非難したことは、記録に残る限り一度も無いのです。逆もまたしかりです。
ああ、だめですね、ゼルキンについては、書きたいことが余りにたくさんあって、つい筆が横道に分け入ってしまいます。書いているのはウィーンでのベートーヴェン演奏のDVDについてでした。
一言で言いましょう。これほど言葉の真の意味で高貴で豊かなベートーヴェンが他にあるだろうかと。天空の高みから次第に地上に舞い降りてくるようなOp. 109の終曲コーダの、大きく弧を描くフレージングの見事さ。あらゆるフーガの中でも私が最も愛するOp. 110のフーガの、全く力みの無い充実と無理の無いテンポ(なにしろ演奏時には84歳でした)による終曲の神々しいばかりの圧倒的高揚と高らかな人間賛歌。そして、破天荒な音のドラマが静まった後、虚空に音が吸い込まれて次第に消えていくような寂寥感あふれるOp. 111のコーダ。
年齢が年齢ですから技術的には危なっかしいところは沢山ありますが、むしろ驚かされるのは彼の指の強靱さと、太くてごつい親指を中心とした回転運動の機敏さと手首/指の柔軟さです。トリルも無理のないスピードではありますが、充実しきった美しさの極み。何よりも、ごまかしが一つも無い音楽的誠実さと集中度の高さに打たれます。
実は今回音源だけを聴いた演奏には、他にも素晴らしい演奏が沢山あり(シュナーベル、バックハウス、ソロモン、ナット、ゼルキン自身のコロムビア録音、グルダ、グード、レヴィット等々)、いずれも感動的でしたが、総合的感銘度はゼルキンのDVDがダントツでした。視覚効果によるところが小さくないということかもしれません。ゼルキンの演奏中の表情を捉えるカメラワークは見事で、普通なら手を見せず表情だけ見せるアップはうるさくて嫌なのですが、この盤に限って、それが見事と思わせるのは何故なのか。ゼルキンという偉大なピアニストの圧倒的な「人間力」のなせる技でしょうか。何しろ私は、彼が音楽の本質をえぐり出すべく苦闘する表情を見るだけで感動してしまうのですから。病膏肓の誹りを甘んじて受けますが、あらゆる音に命を通わせるとはどういうことなのか、その見本がここにあります。
とかく我が国では、ゼルキンというと、所詮は伴奏ピアニストだとか、合わせ物は上手いけどね・・・と言われがちです。ブッシュ=ゼルキン、あるいはブッシュSQとの共演でしか知られていなかった時代が長かったが故の誤解であることは、彼の実演や最良の録音を知る者には明らかです。(最良の録音と書いたのは、彼はあまりに自分に厳しく、そのためにツギハギして作った音盤には、音楽の自然な流れが寸断された印象を与える物や、ゼルキン特有の白熱する高揚が捉えられていない物が少なくないからです。)ソリストとしてのゼルキンは、特に晩年は、北米は勿論ヨーロッパでも高く評価され、尊敬を集めていました。
面白いのは、このDVDでも、そしてこれより大分前のコロムビア録音でも、これほどの巨匠としては随分たどたどしく聞こえるフレーズが散見されることです。例えば、111の2楽章の第3変奏(それまでの16分の6拍子が32分の12拍子に変わり、L’istesso tempoと記載されています;ある畏友はこの変奏を「ブギウギ」と称しましたが、なるほどブギウギのリズムパターンです。)など、エッと思うくらいたどたどしく響くのです。まあ、リズム的に難しい箇所であり、楽譜通りのリズムで完璧に弾いている演奏(例えばリヒテルのフィリップス盤)が良いかというと、そうも言いきれないところがあります。しかし、この変奏におけるゼルキンのたどたどしさは、そういう一般論には収まりきらないものがあるように思えるのです。
実演でブラームスのヘンデル変奏曲や、レーガーのバッハの主題による変奏曲の圧倒的な演奏を聴き、また、手すさびに(?)入れたショパンの前奏曲全曲録音を機き、彼の鍵盤支配能力の高さに驚倒した経験のある私には、これらのフレーズをゼルキンがスムーズに弾けない訳はないと思うのです。そこで思うに、彼はわざとたどたどしく弾いたのではないでしょうか。つまり、彼が考えるベートーヴェンとは、流麗さには目もくれない音楽であり、シャイなゼルキンは、自分が流麗に弾けてしまうことを恥じて、敢えてギクシャクと弾いているのではないか、その結果がたどたどしく聞こえるのではないか、ということです。(実は1983年にはボストンでゼルキンが弾く最後の三つのソナタの実演を聴くという幸運に恵まれています。ですから、その実演でこの箇所の弾きぶりを確認できたはずなのですが、Op. 109の冒頭数小節で涙があふれ出てしまい、その後のことは、当時も今も全く覚えていないのです。思いがけない自分の心の動きに動転してしまって冷静に聴けなかったことを、ただ恥じるばかりです。)
そういえば、ブラームスの2番のコンチェルトの終楽章69節以下の左手の音型のゼルキンの、これまたややどたばたした弾きぶりについて、かつて吉田秀和さんが、「滑稽」、「野暮」、「村夫子」といったような用語を並べながらも、「こういう点ででも、ゼルキンには尊敬と親密の情を覚えずにはいられない。」と書いていたことを思い出しました。それに続く部分でも、吉田さんは、「ほかの箇所」でのゼルキンの演奏の欠点(セルとの共演盤について吉田さんが感じた不満点)を並べ立てて、「いくら私がゼルキン好きとはいえ、こういう箇所まで同情的に『人間味あふれる演奏』とか何とかいうわけにはいかない。」と締めくくっているのですが、その書きぶりにもゼルキンに対する深い愛情が見て取れて、微笑ましく読んだものでした。(この吉田さんの文章は、白水社の全集をはじめとして様々な版に収められていると思いますが、今私が正確な引用のために便宜棚から取り出して見ているのは、音楽之友社から出た「吉田秀和作曲家論集5 ブラームス」(293~294ページ)です。)
ブラームスで吉田さんが愛情をもって批判した箇所が、みな意図的な表現であったという積りはありません。それでも、それらの箇所を聴くたびに、「ブラームスがそんなに流麗であって良いのだろうか?」というゼルキンの呟きが聞こえてくるような気がしてなりません。
脱線しましたが、私が見るところ、そういう一徹さ、流麗さを犠牲にしてたどたどしく響いても、それがベート-ヴェンであれブラームスであれ、自身がその作曲家の本質だと信じるものを抉りださずにはおかないという頑固さこそが、ゼルキンのゼルキンたる所以ではないかと思えるのです。
贔屓の引き倒しと言われればそうかもしれませんが、ゼルキンのベートーヴェン演奏には、ほとんどそう確信させるintensityがあります。そして、そのように不器用でたどたどしくさえ聞こえるところのあるベート-ヴェンが、どれほど魅力的であることか!(もっとも、上述したように、彼の録音には、編集のし過ぎで自然な流れが失われたものが散見されます。そういう録音における流れの欠如と、ここで論じているたどたどしさとは、全く別のことです。両者を区別するのは易しくないかもしれませんが。)
こうしてゼルキンのベートーヴェンの気高さに思いを馳せているうちに、その対極が思い出されてしまいました。昨年の新国立劇場の「フィデリオ」です。鳴り物入りで上演されたカタリーナ・ワーグナーによる新演出は、牢獄に象徴される圧政から解放されたと思った民衆は、実はみな新たな形態の圧政に絡め取られており、しかもそのことに気付いてすらいないという、無残で吐き気を催させる結末でした。彼女の政治的意図は明らかですが、そのことによって、登場する善男善女を嘲笑するだけではなく、ベートーヴェンの音楽を卑しめ、貶めることにどうして思い至らないのでしょう。作曲家の書いた一つ一つの音符や記号、さらにはその文脈、背景、演奏史等々にも細心の注意を払ってスコアを実際に鳴り響く音とする演奏家に対する愚弄でもあることが、どうして分からないのでしょう。演劇や映画の世界で一流になれなかった人材が、舞台芸術の演出家として好き放題が許される場をヨーロッパのオペラ劇場に見いだしてから、かなりの時が経過しています。しかし、私には全く信じられないことに、その猛威はいまだに衰えていません。(保守的なメットですら読み替え演出楽派(?)に征服されつつあります。)そして、提灯持ちの批評家、マスコミは、「読み替え演出」に疑義を呈する者に対し、保守反動のレッテルを貼ります。音楽が全く分からない「読み替え演出派」の演出家自身も、疑義を呈する者を辛辣に批判するのが常です。私は読み替え演出一般が嫌いですが、我慢できるものもあります(大野和士さんが今年新国等で振った「トゥーランドット」の終わり方がその一例です。)が、あの「フィデリオ」を許し、あまつさえ評価するような方とは、お付き合いしたくありません。飯守泰次郎さんがあの演出に共感して振られたのか、我慢して最後まで振られたのかは寡聞にして存じませんが、私だったら、音楽に込められた明確なメッセージを読み取ることを拒否し、自身の不潔な思いつきを試して作曲家を辱める演出家の知的不誠実と傲慢さに対する怒りと嫌悪で、とても最後まで振り通せなかったでしょう。歌手であったらリハーサルで降板していたでしょう。ゼルキンにあの「フィデリオ」を見せたら、彼は一体何と言ったことでしょう・・・。
嫌なことをも思い出してしまいましたが、その不愉快な記憶も薄らぎ、霞むほど、ゼルキンのDVDを久しぶりに視聴して感動しました。私と同様にあの「フィデリオ」に嫌悪感を持たれた音楽愛好家の皆さんには、毒消しの特効薬としてゼルキンのDVDを強くお勧めします。
思いがけず長くなってしまいましたので、「蜜蜂と遠雷」については、次回投稿に譲ります。