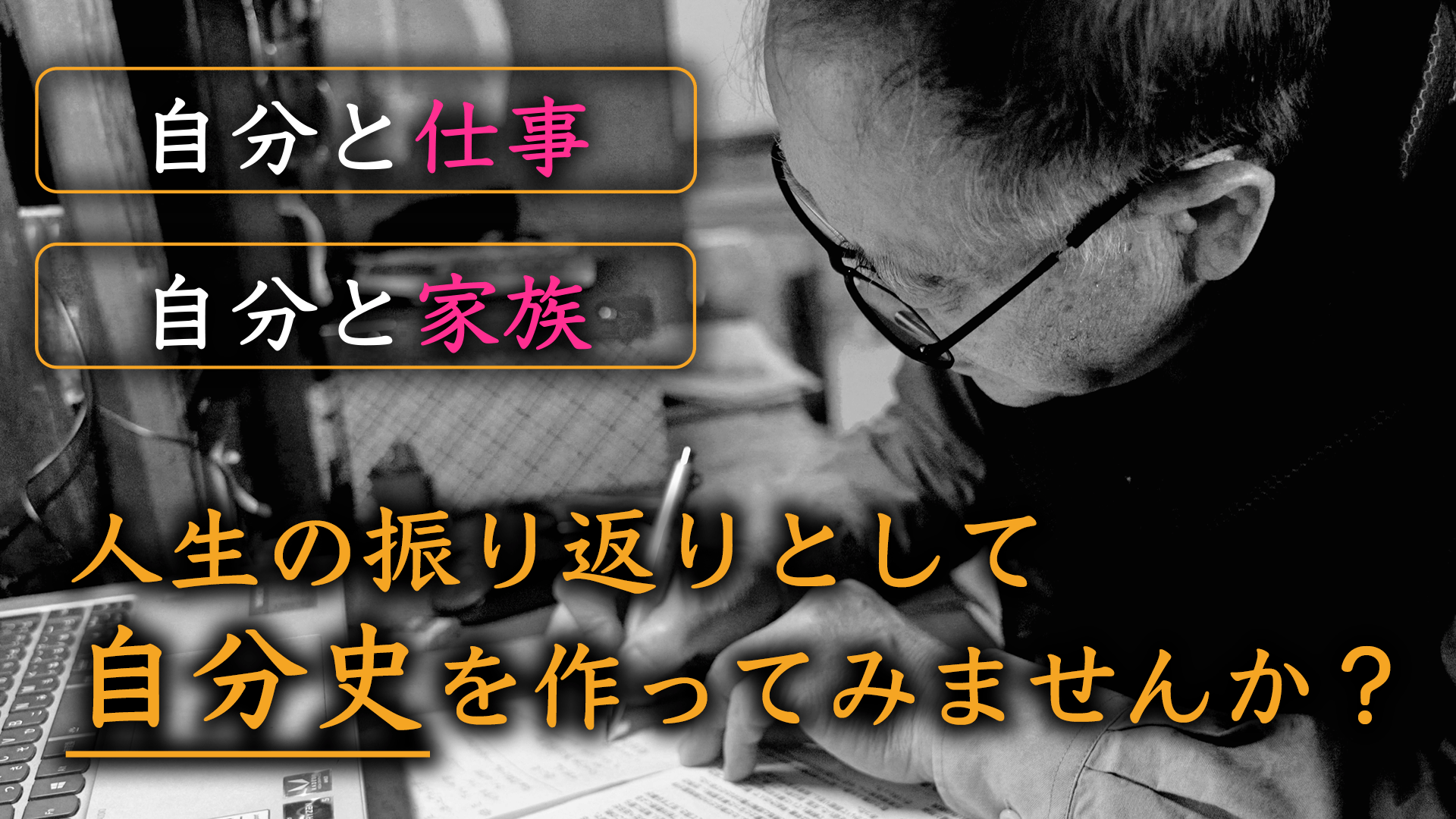秋のベートーヴェン・ピアノ演奏を振り返る
2019 DEC 22 18:18:09 pm by 大武 和夫

だいぶ時間が経ってしまいましたが、予告したベートーヴェン演奏について、思い出しながら書いてみます。
まずは岡田博美さんのリサイタル(11月9日、東京文化会館小ホール)から。
この演奏会は「軽妙洒脱の技」と題され、前半にベートーヴェンの4番のソナタとブラームスのパガニーニ変奏曲を置き、後半がドビュッシーの子供の領分とサン=サーンスが二曲という興味深いプログラムでした。苦手なサン=サーンスはさておくとして(名演だったと思いますが、何しろ曲に当方の感性に訴えるものが少ないので・・・)、何故「軽妙洒脱」と題されたのか、その意図がなんとなく分かる気がしました。もちろん、サラサラと表面をなぞるようにして名技を誇示するという意味では全くなく、いわば汗みずくの力演でない形で曲の本質をえぐり出すとしたらどういう演奏になるか、を岡田さんは見せようとしたのでしょう。
岡田さんは、これまでだって一度も汗みずくで力ずくの演奏などしたことが無いではないかと反論される向きもあるかもしれません。それは認めます。しかし、今回の演奏の「抜けきって」いたことは、岡田さんとしてもこれまで類を見ないものだったと思います。
なんと言っても圧巻だったのはブラームスでした。若い頃からのオハコで、何度も聴いていますが、技巧のために書かれたようなこの超絶的難曲で、これほど技巧を感じさせずに音楽的充実だけを味わわせてもらったのは初めてのことでした。美しく、深い。まるで後期の小品のようなズシリとした手応え。それでいて超絶的パッセージのこなし方は惚れ惚れするぐらいに鮮やかで、若き日の岡田さんと少しも変わらないのです。
実は私は、ブラームスの数あるピアノ曲の中で、この曲は比較的苦手でした。ミケランジェリやヴェデルニコフの超絶的名演はありますが、それらを通しても曲に本当に感動したことは無かったと思います。タウジヒの示唆を受けたブラームスが、名技性を追求するとこうなるということを示そうとして書いた若書きなのだから、音楽的深みが乏しくても当然だ、というのがこれまでの私の考えでした。これが偏見であることを示し、蒙を啓いてくれたという意味で、私にとって画期的な音楽体験でした。この岡田さんの歴史的名演をCD化しなかったらバチが当たりますよ、とカメラータに申し上げておきます。もっとも、カメラータの皆さんは、拙稿など見ておられないでしょうが・・・。
さて、岡田さんのベートーヴェンです。長いこと岡田さんの追っかけをやり、ロンドンにまで何度も聴きに行っていますが、4番のソナタを聴かせてもらったのは初めてでした。この演奏には驚かされました。奇をてらった解釈だったということではありません。およそ珍奇な解釈とは最も縁遠いのが岡田さんです。そうではなく、初期の作品であるのに、これもブラームス同様(演奏順で言えばブラームスはベート-ヴェンの次ですが)「抜けきって」後期作品のように聞こえるのです。晴れやかな若さにも欠けることは無いのですが、それより何より高雅な気品が全曲を覆っているのです。私好みのsfのガツンとくる荒々しさなど、薬にしたくもありません。全曲を聴き終えて通常感じる爽やかな一陣の風が吹き抜けていったような後味に加えて、なんとも言えない寂寥感や苦みが感じられたことに、心底驚きました。個人的には、疾風怒濤の時代精神がもっと前面に出ても良いように思えましたが、余人の及ばぬ境地であることは間違いありません。若い若いと思っていた岡田さんももうベテランの域です。現在の岡田さんの澄み切った心境の一端が伺えるユニークな名演だったと思います。
次にオズボーン。11月1日、トッパンホールの演奏会です。こちらは岡田さんとは正反対の、ガツンと来るベートーヴェンでした。それも最後の三曲でガツンですから、私の驚きは言葉では言い尽くせません。
オズボーンはベートーヴェンを確か2枚リリースしており、それらは彼らしいスタイリッシュで余計な思い入れを排したクールな味わいの名演でした。しかし、同じベートーヴェンのハンマークラヴィーアの数年前の実演の録画放送(NHKBS)では、前回来日時にメシアンの「幼子イエズスに注ぐ20のまなざし」の実演で見せたと同じ圧倒的な集中度の高さと燃え上がるようなボルテージの高さが顕著に見て取れました。それで私は、彼のCD演奏は、スタジオ録音の限界を示しているのだろうと感じていました。(実はオズボーンを知ったのはたかだかこの数年のことで、ハンマークラヴィーアを弾いた来日公演のときは、行けなかったのではなく、よく知らなかったので行かなかったのです。悔やんでも悔やみきれません。)
それでも、流石にハンマークラヴィーアとは違い最後の三つのソナタなのだから、もっとお行儀の良い演奏になるだろうと想像していました。しかし、その想像は完全に間違っていました。彼のベートーヴェンは徹頭徹尾「闘うベートーヴェン」なのです。最期まで闘うことを止めない存在。それこそがベートーヴェンだと言っているような演奏。
興が乗ると鍵盤をガンガン叩く、音が濁っても気にしない(気にはしているのでしょうが拘泥せずズンズン先へ先へと進む)、フレージングが多少不明瞭になっても、細かいことよりも全体のデッサンを大切にする、そういう演奏です。低回趣味と無縁といえば、このくらい無縁な演奏も無いでしょう。
一例を挙げましょう。Op. 111。この曲は、闘争的な1楽章と浄化に向かう2楽章という割り切った捉え方をされることが多いと思います。勿論それには一理あります。しかし、少し乱暴に整理してしまうと、オズボーンの演奏では、2楽章の中でも闘争と浄化が強烈に、激烈ともいえるような形で対比されるのです。彼は本当に興奮すると腰を浮かせ気味にして鍵盤を強打する癖がありますが、この晩を通じて彼が最も高く腰を浮かせ最も強く鍵盤を叩いたのは、驚くなかれ、Op. 111の最後の長大なトリルが始まる直前でした。DのトリルがGのトリルに移行し、そのトリルをはさんでアリエッタ主題が歌われていくわけですが、そのDのトリルの直前の小節です。スコアをよく見ると、そこに至る過程では、(sf→pを何回も挟みながらですが)長大なcrescが指示されています。そして、一カ所もffの指示は無いものの、Dのトリルの直前の小節では、16分の9拍子の3つ目、6つ目、そして9つ目の16分音符に、明確にsfの指示があるのですね。彼は、これを忠実に音化したかったのでしょう。その努力の結果、音は濁り、フレージングも不明確になり、浄化に向かう過程でこんなに汚い音で良いのかという疑念を私のようなナイーヴな聴き手に抱かせることになったのですが、彼には本望だったのだろうと想像します。そして、確かに他の誰の演奏とも違う闘うベートーヴェンが、最後のソナタの最後の2頁にすら現出していたことは間違いありません。
そのような解釈が典型的にうかがわれた箇所をもう一つ上げるとすると、以前の拙稿で畏友の表現を借りて「ブギウギ」と表した2楽章第三変奏でしょうか。これは凄かった。ちっともブギウギ風には聞こえず(そもそもブギウギではないのですからブギウギのように聞こえるか聞こえないかを論じること自体おかしいのですが、ブギウギ風だというのはリズムの面白さを印象づける演奏だという意味だとご理解下さい。)、なんだか怪獣が咆吼しているようなのです。早いテンポでアクセントを強打する結果、音は濁り、何をやっているのか分からなくなる寸前だったと言い換えましょう。でも、sempre fとsfの嵐を忠実に再現しようとした結果なのだろうと、ここでも私はそれなりに納得しました。(彼の技術の限界が垣間見えたような気もしましたが。)少し甘すぎるでしょうか。
しみじみと深い歌に欠けていた訳では無く、ppの沈潜や心からの「歌」の充実には心打たれましたが、全体から受けた印象は「ベートーヴェンは最期まで闘うことを止めなかった」というメッセージでした。これが今のオズボーンが表現したかったことなのだろうと思います。ある意味で、やや老成し過ぎたような感のあるイゴール・レヴィットの全集盤(レヴィットも天才中の天才として私は大好きであり、この全集は私にとって今年の「組み物of the Year」ですから、これは少し厳しすぎる言い方かもしれません。)とは、本当に全く対照的ですし、岡田さんの現在の演奏とも、違う意味で好対照。今後才能あふれるオズボーンのベートーヴェン解釈がどう変わっていくのか、楽しみに追いかけたいと思います。
そして、最後に河村さんです。彼女のベートーヴェンは、青葉台フィリアホール(10月26日)と紀尾井ホール(11月13日)で最後の三つのソナタを二度聴いたほか、コバケンさん/日フィルとの共演で皇帝も聴きました(11月9日、サントリーホール)。
最後の三つのソナタはどれも非常な名演で、感銘を受けました。全体の造形が見事であるのに細部が彫琢し尽くされていて、弾き手の意思が隅々まで及んでいる。何の意図もなく置かれた音など一つも無いのです。以前の河村さんのベートーヴェンには、ものすごく素晴らしいけれども、やや「面白すぎる」ところが散見されました。面白すぎるというのは批判を意図した表現ではないのですが、誤解を避けるために「以前は、どうしてもこうでなければならないという内的必然が、必ずしも常にすべての音に感じられるわけではなかった」と言い換えましょうか。今回の演奏は、まさに、あらゆる音に「こうでなければならない」という彼女の強固な意志(とベートーヴェンの強固な意志)が感じられたということです。これを論証するには私の筆力はあまりに乏しいので、一つだけ例をあげるに留めます。
またか、と思われるかもしれませんが、Op. 111の2楽章の第三変奏。例のブギウギです。この変奏での、細部まで考え抜かれていながらリズムが自然に躍動し、音が飛び跳ねる見事さには、本当に惚れ惚れさせられました。以前にも触れましたが、例えばリヒテルのフィリップス盤では、驚くほどリズムが正確なのですが、何も伝わってこない。砂を噛むようで全く面白くないのです。彼ほどの巨匠にもこういうことがあるのですね。(リヒテルはムラのあることで有名でしたが、それにしてもこれは無いだろうと思います。)河村さんのリズムは、もっとはるかに人間的で弾力に富んでいます。そして、度を越さないsfがリズムの魅力を際立たせます。バックハウスの大雑把なリズムとは対極ですし、オズボーンのように崩れたりもしません。そのリズムの素晴らしさが、そこから紡ぎだされるそれに続く浄化の過程にとって、どれほど重要な役割を果たしていることか!
総じて今回素晴らしいと思ったのは、細部の彫琢が全曲の感動をいささかも損なわないばかりか、「このような細部の積み重ねあってこその全体なのだ」と思わせてくれたことです。
皇帝も大名演で、特に2楽章の木管との対話など、河村さんから芳香が立ち上るかのように美しかった。コバケンさんの合わせ物のうまさにも改めて感服しましたが、2楽章はむしろ河村さんが指揮者であるかのように見え、聞こえました。しかし、何しろ河村さんですから、女性的な演奏だったというようなことは金輪際ありません。ある畏友は、かつて彼女の演奏を「男前」と評したことがあります。これは言い得て妙。決めるべきところで思い切りよくビシッと決める彼女の演奏の特質の一端を、実に巧みに言い表した名言だと思います。(誤解の無いよう申し添えますが、「男勝り」という表現が女性差別の色彩を帯びるのに対し、「男前」はジェンダー・フリー(?)です。)スキッと造形され、雄大さや力強さにも富む、理想的な「男前」の名演であったとだけ申しておきましょう。
以上のうち、オズボーンの演奏と河村さんの紀尾井ホールでの演奏には、NHKのカメラが入っていました。いずれも、おそらくBSの「クラシック倶楽部」で、その一部が遠からず放送されるだろうと想像します。楽しみに待ちたいと思います。
振り返ってみれば、今年は少なくともピアノに関する限り、東京・春・音楽祭におけるレヴィットのディアベッリ変奏曲の演奏や、本稿で触れた3人のピアニストの四つの公演等、心に残るベートーヴェン演奏に恵まれた年でした。生誕250年に当たる2020年にも大いに期待したいと思います。(東京・春・音楽祭で河村さんがクレメンス・ハーゲンとベートーヴェンのVc/Pfデュオ作品全曲を二晩かけて演奏するのが、まずは大注目ですね。)
Categories:未分類