忘れられない出会い~音楽編(第1回)
2022 AUG 18 17:17:18 pm by 大武 和夫
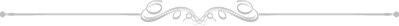
忘れられない曲、演奏会、演奏家、作曲家、録音等との出会いと、その出会いを可能にしてくれたきっかけについて、備忘録として書きます。「きっかけ」は、人であったり、書物であったり、演奏会であったり、様々です。
第1回は三題噺です。ホロヴィッツ、ジャン=フィリップ・コラール、そしてキース・ジャレット。不思議な組み合わせとお考えかもしれません。これらの演奏家との出会いのきっかけを作ってくれた恩人は、永年の友人N野君とその弟さんです。
舞台は46年前のシアトル。当時シアトルに留学していたN君弟がN君を通じて私に、ホロヴィッツが翌年正月にシアトルに来て弾くという知らせをもたらしてくれたのは、1975年のことでした。数十年ぶりの西海岸での演奏会という触れ込みでした。その頃までには私のホロヴィッツ狂ぶりは友人の間で知れ渡っていました。軍資金も無いのに、同居の叔母に借金をすることを前提に(!)「行きたい」と即答した私でした。短答試験に落ちて大学を留年し、ようやく司法試験に受かった直後のことです。
貧しい家に育ったので海外旅行などしたこともありません。他方、N君は裕福な名家の御曹司で、既に海外旅行の経験者でした。でも心優しいN君は、こちらの懐事情に合わせて格安フライトに付き合ってくれました。中華航空便でハワイまで。数時間のトランジットを経てコンチネンタルに乗り換えて、シアトルまで。シアトルの空港に近づき高度を下げると、美しいシアトルの町並みが目に飛び込んできました。初めての西海岸、いや初めてのアメリカ本土。感動で胸が高鳴りました。ハワイでは待機時間中にワイキキビースを踏んでこようということになり、冬の厚いセータ姿でビーチを訪れました。何をするでもなく、汗をかきながら(!)ビーチを男2人で散歩するという、それだけのことでしたが、何故だかそのことはいつまでも忘れません。「コンチネンタル」の発音が「コンニネンナル」と聞こえたことも。
三題噺の最初の登場者ホロヴィッツ(の実演)との出会いは、以上の通りです(演奏会当日のホロヴィッツその人との「出会い」については後ほど詳述します)が、ではコラールが何故三題噺に登場するのか。
ホロヴィッツが弾く予定のプログラムがN君経由でもたらされたのは、確か日本を発つ2日前のことだったと記憶しています。そして、その中に聴いた事の無い曲を発見した私は、出発前日に渋谷のヤマハに飛んで行きました。(当時道玄坂中腹にあったヤマハ渋谷店には、大学の帰りによく寄っていました。)幸いなことすぐに見つかったLPが、コラールのデビュー録音であるシューマン集。その中に、ホロヴィッツで間もなく聴くことになる3番のソナタが収録されていたのです。東芝EMI盤のジャケットには、遠山一行さんのコラール讃とも言うべき解説が載っていましたっけ。美しい文章でした。
帰宅するやすぐさま針を通しましたが、当時の私のヤクザな耳には、さほどの名曲とは聞こえませんでした。よく知っている2番や、せめて1番だったら良かったのに、とホロヴィッツの選曲に文句を付けたくなる始末。でも、出発前に通して3回ほど聞けたお陰で、それなりに曲になじむことができ、シアトル・オペラハウスでのホロヴィッツのリサイタルに臨む予習としては、まずまずであったと思います。春秋社版のスコアを持っていたので、ちょっと弾いてみましたが、下手くそなアマチュアの手には余るパッセージが頻出し、さじを投げました。繰り返しが多いことにも閉口。繰り返しの多さはシューマンのトレードマークではありますが、知っている曲における繰り返しと初めて聴く曲の繰り返しとでは、全く印象が異なります。(知っている曲だと繰り返しが楽しみになったりしますが、知らない曲の繰り返しにはうんざりさせられる確率が高いというのが卑見です。私のような凡庸な聴き手にだけ当てはまることなのかもしれませんけれど。)この心理的効果に気付くのは、ずいぶん先のことです。
この時点では、コラールが晩年のホロヴィッツと親交を重ね、大きな影響を受け、深く尊敬するに至ることなど知る由もありません。コラールを通して初めて知った3番のソナタにあまり感動しなかったということは、曲の真価のみならずコラールの真価をも、全く捉えることができなかったということでしょう。情けない話です。このデビュー録音を聴き直して感心するようになったのは、遙か後年のことです。ホロヴィッツはどうやらコラールを通じてフォーレを深く知り、愛するに至ったふしがありますが、ひょっとするとシューマンの3番についても、コラール盤に刺激されて久方ぶりに取り上げようという気になったという可能性がありそうです。推測に過ぎませんが。
コラールは本当に素晴らしい芸術家で、近年ポツポツと発売される新譜は、皆宝です。コラールについては、フォーレの難しさ(コラールでさえ譜読みで間違えている箇所がある!)と併せて、稿を改めましょう。
さて、どこに行っても大都市なら必ずレコード店に立ち寄る癖のある私は、N君と街の案内役兼運転手を買って出てくれたN君弟にお願いして、シアトル随一のレコード屋に連れて行ってもらいました。ホロヴィッツのリサイタルの前日のことだったと記憶しています。
店内に足を踏み入れた瞬間に耳を捉えたのは、聴いた事も無い音楽。寄せては返す波のようなうねりの、ロマンティック極まりない音楽。しかし、どうやらクラシックではないようです。耳をそばだてるまでもなくブルーノートの多用に気付きます。そして、ブルース調、ブギウギ調とめぐるしく変わる曲想の虜になっていました。どこか永遠を思わせる透明な・・・しかし少しだけ魅力的なひずみを抱えたような・・・美しい響きにも心を奪われました。グルーヴィーでありながら、ポリフォニックな展開もあり、フレーズや和音が反復されそろそろ嫌になりそうな頃合いで見事に転調と曲想の転換を決める鋭敏なセンスには、舌を巻きました。物凄い音楽的教養の迸り。
恐らくジャズ・ピアニストだろうとは思いながらも、それまでに知っていた数少ないジャズ・ピアニスト達・・・ビル・エヴァンス、バッド・パウエル、デューク・エリントン、レニー・トリスターノ、チック・コリア等々・・・とは全く重なりません。この音楽の弾き手は、確実に私にとって未知のピアニストだと思いました。気付いたときにはレジに直行し、今かかっているその盤をくれ、と言っていました。それが、あの名盤「ケルン・コンサート」との、そして天才キ-スとの出会いでした。
泊めてもらっていたN君弟のアパートに戻った3人は、私が持参して皆で聴こうと提案していたコラール盤に耳を傾けました。しかし、コラールを聴きながらも私は、早くケルン・コンサートの続きを聴きたいものだと思っていました。時間的制約がある上に、何と言っても転がり込んだ居候の身で我が儘は言えません。結局キースは2枚組LPの1枚目の表を聴き通せただけでした。残りを聴くのは帰国後になります。
90年代後半の体調不良を乗り越えて演奏会活動を再開したキースが、数年前に起こした脳卒中の後遺症である麻痺状態のため、もうピアノが弾けないという報に接したのは2年前のことです。何と悲しいことでしょう。キースについても書きたいことは山ほどありますので、これも稿を改めましょう。今はただ、彼が与えてくれた美しい音楽とその感動に、心からのお礼を言うだけです。ありがとうキース!
実はそのレコード屋では、他にも1枚買って買っていました。それが、当時既に日本でも話題を呼んでいた二レジハージの録音でした。見つけた時に、しめた!と思い、ケルンコンサートと共に買ったのです。しかし、この盤との出会い、ニレジハージとの出会いは、キースとの出会いとは違い、決して幸せなものではありませんでした。買ったLPは針を通すチャンスとて無く、帰国して初めて聴きました。いや聴こうとしました。聴こうとしたものの、聴けなかったです。質の悪いアメリカ・プレスのLPには時折あったことですが、盤が反り返っていて、しかも、何故か傷だらけ。ビニールで包装してあったので、購入前に開封して盤を確認できなかったのは痛恨でした。アメリカでは検盤という文化が無いと知るのは後年のことです。
シアトルで買ったものですから、日本のレード屋で交換などできません。泣く泣くヤマハで輸入盤を買い直したましたが、その演奏には全く心を動かされませんでした。なんだか凄そうな演奏ですけれど、私には瀕死の大蛇がのたうち回っているようにしか聞こえませんでした。音が汚いことも類を見ません。その後出た何枚かの録音も同様で、落胆のほかありませんでした。
無名で終わるべき演奏家にハイライトを当てて売り出そうという商魂は、その人に失礼であるだけでなく、一般公衆を馬鹿にしています。いまでも彼を持ち上げる人がいますが、私には全く理解できません。
という訳で、ひょっとすると二レジハージとの出会いをも含めて「四題噺」になったかもしれなかったのですが、結果は「三題噺」どまりだったという訳です。しかし、時を同じくして出会ったという一点で、二レジハージもある意味で忘れがたい演奏家であると言えるかもしれせん。
長くなりましたので、続き=ホロヴィッツのシアトル・オペラハウスの演奏をめぐって=は、To Be Continuedということにさせて頂きます。
Categories:音楽


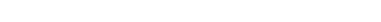
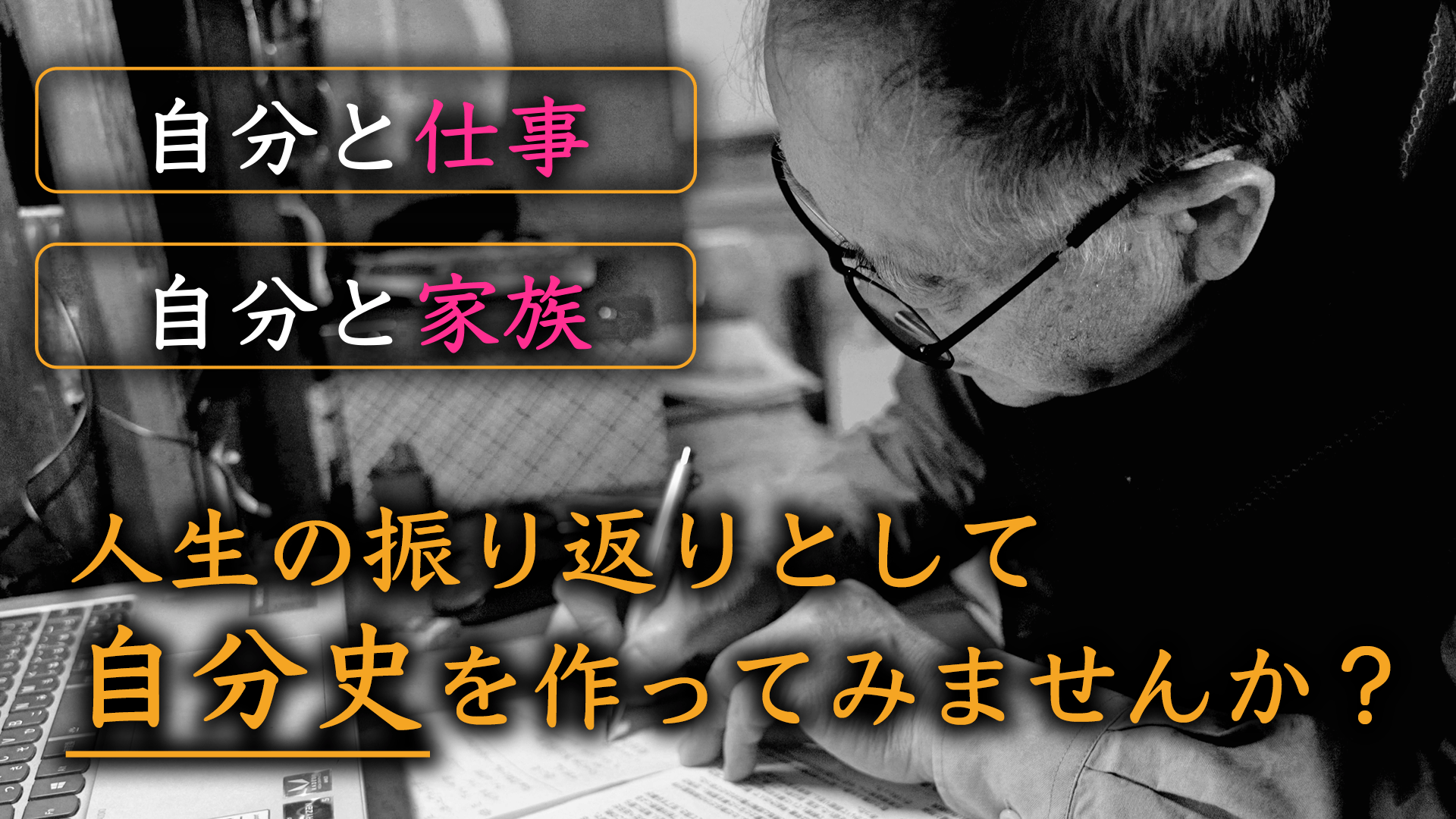


ST
8/20/2022 | 6:17 PM Permalink
音楽にまつわる個人的なエピソードほどお聞きして楽しいものはありません。今は、音楽との出逢いは偶然性より検索の時代で、わたしにとっては面白みに欠けるのです。
わたしはホロヴィッツもまだまだよく聴けていないのですが、あるCDブックレットのなかに、彼のご自宅にピカソの大道芸人の絵があるのを見つけました。調べると《腕を組んですわるサルタンバンク》という絵のようです(ご存じかも知れませんが)。
「ここでピカソは、芸人への憐憫の情を抱いて描いているようには見えません。むしろ芸人は、新しい時代を先導する英雄のごとき凜々しさを身にまとっています。そこには、伝統的な美を、自らが試行錯誤して洗練させた結果としての新しい手法で乗り越えようとする画家の意図が重ね合わされているようです」と説明がありました。
大武 和夫
8/22/2022 | 9:51 AM Permalink
コメントありがとうございました。残念ながら後年ホロヴィッツはそのピカソを売り払ってしまいました。一時は、ハイフェッツに絵画の蒐集方法について指南するほど、絵画蒐集に打ち込んでいたようです。リヒテルは自らの絵画作品をLPジャケットに用いたりしていましたが、ホロヴィッツが絵を描いていたという話は聞いたことがありませんから、恐らく鑑賞専門だったと思われます。
ご指摘のピカソの作品に描かれた大道芸人は、ホロヴィッツその人のように見えませんか? その作品の前に、芸人と同じように腕を組んで立つホロヴィッツの写真を初めて見た私は、あっと声を上げそうになりました。ホロヴィッツは微笑んでおり、芸人の憂愁の表情とは違うのですが、常に呆けたおどけ者を演じる癖のあるホロヴィッツの心の中は分かりません。私には、自分との同質性を芸人の中に見てとったホロヴィッツの含羞、と見えます。絵の前の長椅子にゆったりと座った写真も有名ですが、こちらは、気取ったポーズが目立つばかりで、そのような対応関係を見て取る楽しみはありません。少なくとも私にとっては。
話は飛びますが、矢代秋雄さんの名作ピアノ・ソナタは、大原美術館の委嘱作品であり、矢代は展示されているフランス絵画をイメージしながら作曲したようです。矢代夫人とご一緒に岡田博美さんの演奏する矢代ソナタをルドンの名作の前で聴けたのは、忘れがたい体験でした。
美術と音楽の関係は、私にとって永遠のテーマの一つです。
(以下、9月9日補遺)つい最近矢代さんんと河村尚子さんとご一緒する機会がありました。たまたま大原美術館での岡田さんの演奏に話が及んだので、「ルドン」と申すや否や矢代さんに、「大武さん、モローですよ。ギュスターヴ・モロー。ルドンじゃありません。」と訂正されてしまいました。大原美術館には素敵なルドンもあるのですが、矢代秋雄氏が作曲時に念頭においておられたのは、モローの作品だったのですね。以前にもそ伺っていたに相違ありませんが、なぜだか私の脳内ではそれがルドンに変換されてしまっていました。脳内誤変換の結果、皆さんをミスリードしたことをお詫びします。特に、ルドンということで反応してくださったSTさんには、申し訳なく思います。しかし、そのSTさんの御投稿のお陰で、粟津則雄さんをまた読もうかという気になりました。お詫びとお礼を両方申しあげておきます。
ST
8/23/2022 | 11:14 AM Permalink
はい、わたしにもなんとなくそう見えました。ホロヴィッツが聴衆を楽しませたい驚かせたいというのと、演奏することの芸術性の両方を求めているというふうに見えました。素敵なかたです。
ルドンといえば粟津則雄さん。わたしは粟津さんの美しい批評が大好きです。作品を鑑賞する以上に好きかも知れません。