第一次大戦を考える その2-大衆が欲した戦争ー
2015 JAN 22 17:17:57 pm by 中村 順一

- 塹壕から機関銃を操作するドイツ兵
- 1914年のクリスマス休戦時の前線のドイツ兵とフランス兵
- 第1次大戦時の各国のプロパガンダ
ヨーロッパの君主制が、100年前のウィーン会議の頃のようなしっかりした君主制であったら、各国の指導者が望まなかった戦争など起こるはずがなかったろう。だが、1914年当時になると、オーストリアのハプスブルク家もロシアのロマノフ家もドイツのホーエンツオレルン家も、実質的にはかつての強大な権力は失われており、それぞれの国の官僚と大衆に迎合しなければ、生きながらえない存在になっていた。
そしてこの当時どこの国でも大衆は熱狂的に戦争を支持していた。この点も第2次大戦前とは大きく異なっている。各国の君主や外交官らが戦争を避ける努力を続けていた1914年6月から実際に戦争が始まった8月にかけて、各国の大衆はどの国でも同じように戦争を求め続けたのである。老若男女、宗派、政治的傾向の相違を超えて、民衆の間に「愛国熱狂と好戦熱狂」が湧き上がり、戦争に協力し、軍隊に志願するぞ、と考えざるを得ない方向に人々を誘導した。
6月28日の暗殺事件の数時間後には、早くもサラエボで、セルビアを撃て、というデモが組織された。人々はオーストリアの愛国的な歌を歌いながら、セルビア人の店を略奪した。オーストリアの新聞は一斉に、反セルビアの論説を掲載し、2日以内に、この反セルビアデモはオーストリア・ハンガリー二重帝国の全域に広がった。一方セルビアの民衆は大公暗殺のニュースを喜び合い、新聞は犯人の写真を掲げて、”英雄”と呼び、オーストリアのボスニア支配を攻撃する材料にした。そしてこの熱狂は、不可思議なことに、オーストリアとセルビアのみに限定されず、瞬く間に全ヨーロッパに広がっていった。
8月初めの開戦時の体験は多くの人々の記憶にしっかりと刻まれている。ドイツ皇帝の動員命令を士官が読み上げたベルリンの街頭、ミュンヘンのオデオン広場、ぺテルスブルクの冬の宮殿前に群がる膨大な数の人々、行進する兵士たちを熱狂的に送り出すパリの女性たち、を捉えた当時の写真も,映像も大量に残されている。
それはドーバー海峡を隔てた英国でも例外ではなかった。外相のグレイ(自由党)は、8月3日に議会でドイツの中立国であるベルギーへの侵攻を許せない罪として、ドイツに宣戦すべき、と演説したが、それは当時の民衆の戦争熱に押されてしまったものだった。野党労働党の党首マクドナルドはこれに反対し、ベルギーの中立を守るだけのために、英国が参戦する理由にはならないと反論した。これは実に正論である。当時の英国は戦争を開始するほど反ドイツとは言いにくく、陸軍大臣のホルデインは根っからのドイツびいきであったし、1914年5月の帝国防衛委員会でも、対独関係に関し、楽観的な見通しを示したばかりであった。
ところが、すでに議会は沸点に達しており、マクドナルドの慧眼に賛同したものはほとんど皆無、即座に労働党は参戦支持を表明し、マクドナルドは辞任した。開戦の報道に人々は熱狂し、トラファルガー広場からダウニング街までを埋め尽くした。参戦後、陸軍省では何十万という義勇兵が殺到してくるのに、彼らに与えなければならない予備の小銃は英国中の倉庫をかき集めても3万挺しかなく、他の人々にはやむを得ず、棍棒を渡したと記録している。戦争を避けようとして必死に奔走した外相グレイら政治家の実らなかった努力と、新聞に扇動された大衆の戦争熱との隔たりをどう解釈すべきなのだろうか。
オーストリアのユダヤ系作家、ツヴァイクはこう書いている。
「ほとんど半世紀の平和のあとで、1914年における民衆の大多数はいったい戦争について何を知っていたのだろうか。彼らは戦争を知らず、ほとんど戦争のことを考えたこともなかった。戦争は一つの伝説であり、まさしくそれが遠くにあることが、戦争を英雄的でロマンティックなものとしたのであった。彼らは戦争を、学校の教科書や画廊の絵から眺めていた。金ぴかの軍服を着た騎兵のまばゆいばかりの突撃。いつも壮烈に心臓の真ん中を射抜く弾丸、出征兵士が参加する軍楽隊の音楽が高らかに鳴り響く勝利の行進であった。”クリスマスまでにはまた家に帰ってきますよ”、と1914年8月に新兵たちは笑いながら、母親に叫んだ。村や町で誰が現実の戦争のことをまだ覚えていたであろうか。せいぜい2~3人の老人が、今回の同盟国であるプロイセンと1866年に戦ったことがあった(普墺戦争)。しかしそれは何と速やかな、血なまぐさくない、遠い戦争であったことか。たった3週間の出征、そしてそれは間もなくたいした犠牲者も出さずに終わっていた。ロマンティックなものへの足早な遠足であり、荒々しい男らしい冒険、このように1914年の時点で戦争は、人々から思い描かれていた。」(ツヴァイク「昨日の世界」)
アメリカのジョセフ・ナイは、第一次大戦の開戦原因に関して、「ナショナリズムは、国境を越えて労働者階級を束ねると称していた社会主義よりも、銀行家を結束させていた資本主義よりも、そして君主間の親戚関係よりも、結局、強力だったのである」と述べている。また英国のポール.M.ケネディは、「第一次大戦に至る数十年間、各国は左翼運動(社会主義運動、労働運動、女性解放運動など)ばかりを研究し、右翼運動(ナショナリズム、帝国主義、人種主義)に関する研究は極めて貧弱だった。」と嘆いている。この時右翼運動の勢いが結局破局に繋がったのだが、当時は、右翼は左翼ほどの危険性をもって見られず、各国の歴史家もその研究を怠ってしまっていて、大戦に繋がる”戦争熱”を認知できなかった、と言わざるを得ない。
大衆心理は検証が難しい対象と言えよう。民衆の側にあった、開戦原因に繋がる要因は実証的には確定できない。名著「第一次世界大戦の起源」の著者、英国のジェームス・ジョルは、これを1914年の”雰囲気”と書いている。
大衆心理(戦争熱)と政治の相互作用がついに戦争、破局に至ったという経緯は、我々としては、まさに現代の東アジアの状況に当てはめて考える必要がある。経済的な関係が緊密なら友好的な国際関係が築かれ、戦争にはならない、との考え方は、第一次大戦の経験からは成り立たない。変わりやすい民衆心理のチェックは、常に怠れない。時によってそれは危険になる。新聞に煽られた、日露戦争直後の民衆の暴動、太平洋戦争直前の大衆の熱狂、日本にも同じ歴史があるではないか。日本も1945年から70年間戦争を経験していない。第一次大戦前の欧州と、その意味では似た環境にある。
Yahoo、Googleからお入りの皆様。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
Categories:未分類






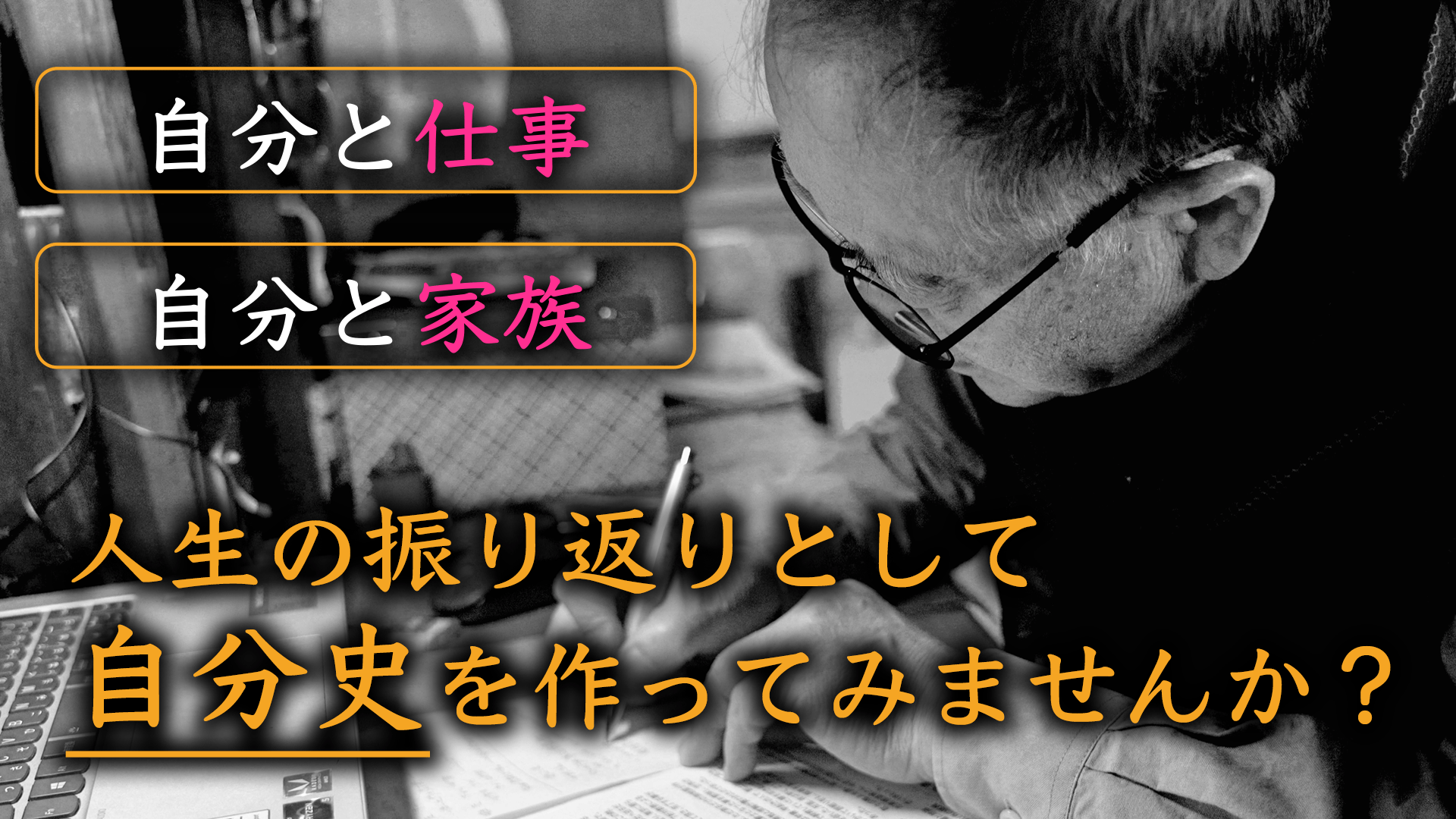


西室 建
1/22/2015 | Permalink
熱気は反省を生むことなく、ヨーロッパはほぼ同じ組み合わせで20年ちょっとで又始めるわけだな。
今度こそ戦争は・・・、とEUもできたが怪しくなってきている。
マズいぞ、マズい。
日本が巻きこまれてはいかんな。毅然とせねば。