第一次大戦を考える(その5)-最悪の戦後処理
2015 FEB 11 18:18:44 pm by 中村 順一

- ジョルジュ・クレマンソー首相
- デビッド・ロイド・ジョージ首相
- ウッドロウ・ウイルソン大統領
経済学者のケインズの名著に「講和の経済的帰結(The Economic Consequences of the Peace)」がある。これはパリ平和会議に英国代表として出席していたケインズが、そのあまりにも同盟国に過酷な賠償に抗議して、途中退席し、帰国した後に書いたもので、ヴェルサイユ条約批判の古典になっている。ケインズはこの過酷な賠償で中欧を破壊することは、決して英国とフランスの為にならない、と強く警告した。
この「講和の経済的帰結」でケインズは条約後の状態を「カルタゴ式平和」と表現している。
第3次ポエニ戦役でローマ軍はカルタゴを包囲したが、カルタゴ市民20万人は必死に抵抗し、ローマ軍目がけて、女性、子供に至るまで投石を試みた。ローマ軍は全ての人々を虐殺し、最終的にカルタゴの象徴、ピュルサの人口が5万人まで激減した時にカルタゴはついに降伏した。その後の戦後処理では、ほとんどの人々が奴隷として売られた。ローマの戦略は、「カルタゴは絶対に二度と復活させない」、という断固としたものだった。ケインズは第1次大戦の戦後処理をこのカルタゴに例えたのである。
パリ講和会議はフランス代表ジョルジュ・クレマンソー、英国代表ロイド・ジョージ、アメリカ代表ウッドロー・ウィルソンの3巨頭が仕切った会議であるが、ケインズは「講和の経済的帰結」でこのクレマンソーを”妖怪”の如く描写し厳しく批判した。(この原文は極めて激しい描写である。) クレマンソーの方針は、「ドイツを脅威ある存在としては、2度と復活させない、1870年以降、ドイツが得たものは全て放棄させる」、という断固たるものだった。ウィルソンは理想主義的な「14箇条の平和原則」を1918年1月に発表し、公正な講和を目指す、とアピールしていたが、クレマンソーに反対されると、ほとんど抵抗できなかった。当時ランシングをはじめとするアメリカ代表団内部でも条約が「14原則」とかけ離れている、と批判する声は高かったのであるが、ウィルソンは逆に意地になって、自分の立場が弱いのを認めようとしなかった。ロイド・ジョージがこの2人を調停すべき立場にあり、事実そのように行動した形跡もあるのだが、彼も、当時の反ドイツの強硬な英国の世論を納得させなければならず、1918年12月の総選挙で、大戦でかかった戦費はドイツに賠償金として払わせる、と公約した手前、ウィルソンにすべて同調するわけにもいかなかった。その意味では、この戦争は既に述べたように大衆が欲して開始され、大衆の好むように終結したとも言えるのである。
ドイツに課せられた賠償金は1320億マルクという天文学的数字になり、ドイツは全植民地を奪われ、アルザス・ロレーヌにあったドイツ人の私有財産を含む、在外資産の諸権利と諸名義のすべてを連合国に譲渡させられた。ケインズはこの私有財産の処理は「国際法の概念がこの講和条約によって、壊滅的な打撃を受ける」と批判している。
この3巨頭を100年前のウィーン会議におけるメッテルニヒ、カスルリー、タレーラン、アレクサンドル1世らに比べるとあまりの違いに驚かざるを得ない。ウィーン会議は”会議は踊る”と揶揄され、肝心の戦後処理の討議がさっぱり進まない、と言われたが、実は各国の利害が錯綜して処理が難しいのを見越しつつ、ゆっくりダンスを楽しみながら機が熟するのを待つ、という落ち着きと18世紀の貴族的精神が生きていた。敗戦国フランスの代表タレーランが、「最も重要」と言って、フランスきっての美人と料理人を連れて行ったのも、その貴族的精神に基づいていて、そういう雰囲気だったからこそ、ウィーン会議は成功し、その後長い間ヨーロッパは平和を謳歌できたのである。
それに比べると、パリ会議を仕切った3人の組み合わせは最悪だったと言わざるを得ず、ウィルソンは、14箇条を基礎にして”公正な講和”を結ぶためにパリにやってきたことを冒頭で宣言し、アメリカの戦争への多大な貢献を認めて連合国が休戦条約を承認したのであるから、もっと強く出ても良かった。しかし、ウィルソンはクレマンソーに振り回され、その結果、近代史上最悪の戦後をドイツに強制することになった。ウィルソンはこの時、病魔に侵されており、1919年10月には脳梗塞で倒れ、4年後に死んでいる。ウィルソンの戦後処理に対する、不可思議なほどの、弱い対応はどうしてなのだろうか。筆者には謎であり、残念でもある。
ドイツでは、講和条約に対する反発が根強かった。ドイツは、敵兵を全くドイツ国内に侵入させておらず、ドイツ一般市民には敗北感が薄かった。さらにヒンデンブルクが議会証言で、革命派による”背後の一突き”によって、ドイツが休戦に追い込まれたと主張したことで、”不当な休戦”によってもたらされた”過酷な講和条約”に対する怒りはドイツ国民の間に広く浸透した。
この不満の高まりが、やがて世界恐慌を経て、ヒトラーへと繋がっていくことになる。
このシリーズは、あと一稿で終了する予定である。最終稿は、「オスマン帝国と第1次大戦」 につき書いてみることとしたい。
Yahoo、Googleからお入りの皆様。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
Categories:未分類



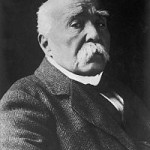
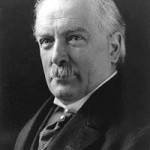

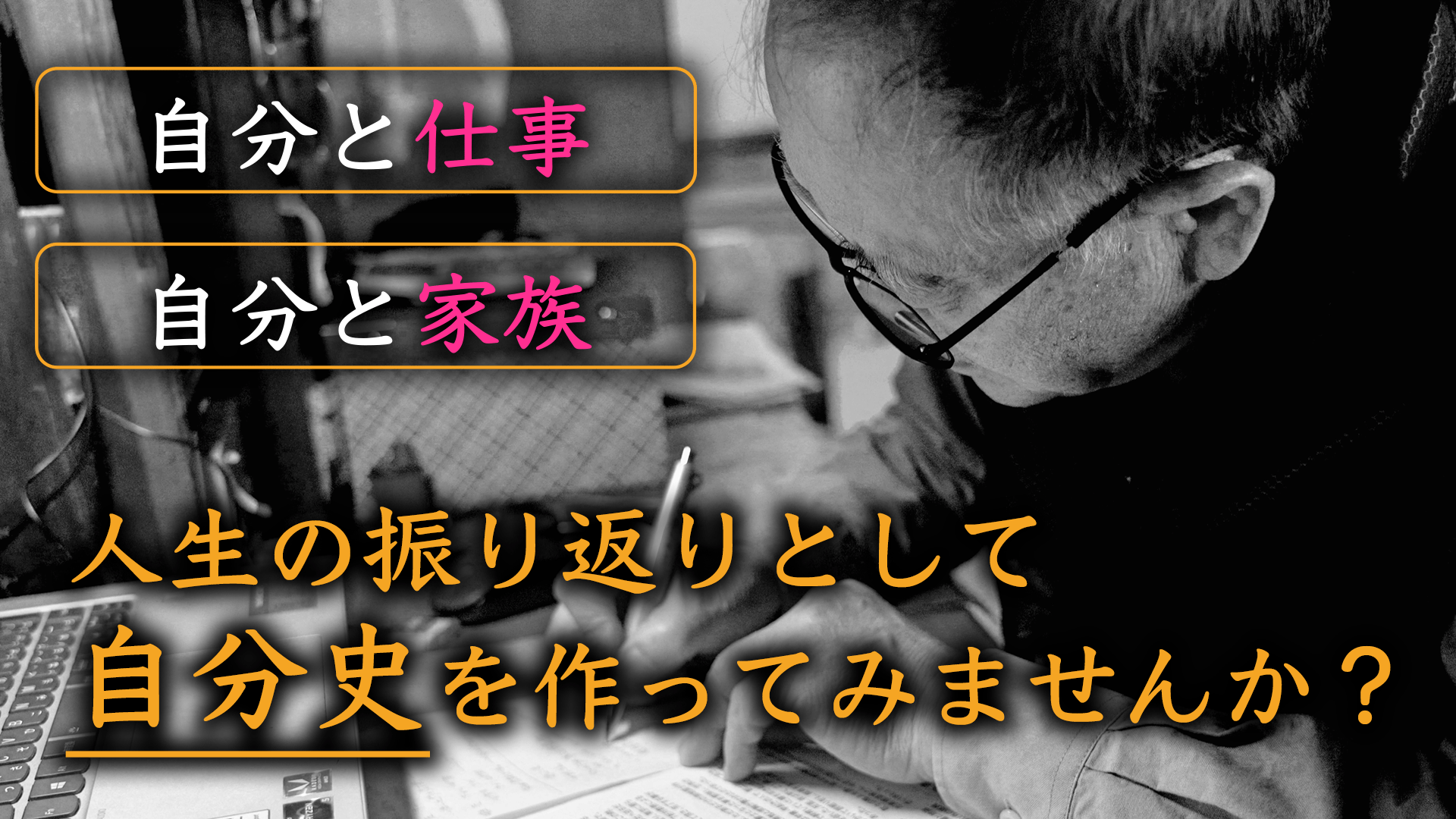


西室 建
2/12/2015 | Permalink
ウィルソンの「14箇条の平和原則」も表面はそれなりなのだが、本音はアメリカっぽい「オレにも分け前をよこせ。」が透けて見えてクレマンソーのドイツ憎しの主張に無視される結果となった。フランスってのはどうも。
結果的にできた国際連盟 League of Nations も調停機能は全くなかった。だが今の国連 United Nations がどうかと言えば難しい。なけりゃ困ることも多いのだが『国連中心主義』とまではなかなか行けない。小沢一郎がどういうつもりで言っていたのやら。
平和にはカネがかかるのはしょうがないが。
東 賢太郎
2/12/2015 | Permalink
クレマンソーは「ドイツの方角を睨んだまま、立った姿勢で埋葬してもらいたい」と遺言し、その通りに葬られたらしい。彼個人の普仏戦争の怒りだろうが、もっといえば当時のフランスはドイツを文化的に完全に馬鹿にしていたんだ。ハプスブルグのウィーンすらコンプレックスがあってマリア・テレジアはイタリアに赴任させた息子たちへの手紙をフランス語で書いた。タレーランの美女と料理人作戦にはそういう背景があった。ましてもっとド田舎のプロシアなどフリードリヒ2世は自分の宮殿にサンスーシーとフランス語で名前をつけている恥ずかしいコンプレックスぶりである。そんな奴らにアルザス・ロレーヌを取られた屈辱の仕返しという余分な面もあってケインズらは眉をひそめたんじゃないか。
中村 順一
2/12/2015 | Permalink
両兄のおっしゃる通りであります。しかし、この戦後処理が、もう少しクレマンソーの怒りではなく、大人の対応を見せていたら、第2次大戦はおそらく無かった、と思うと本当に残念。歴史の偶然性、連関性は怖い。ヒトラーだって、ウィーンで試験に合格していれば良かったですねえ。