小津安二郎の『小早川家の秋』は大人の映画です。
2017 JAN 1 5:05:55 am by 野村 和寿
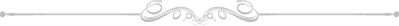
念頭にあたり、新春を飾るにふさわしい、ボクが好きな映画の中でもとびきりの作品を紹介しようと思います。1961(昭和36)年の東宝(宝塚)作品、『小早川家の秋』です。監督は小津安二郎です。タイトルは、これで、「こはやがわけのあき」と読ませます。古くからの伏見の蔵元、小早川家の人々を舞台にした小津安二郎監督の映画は、当主である小早川万兵衛が、焼けぼっくいに火がついた京都・祇園通いがメイン・ストーリーになっています。
小早川家の秋 予告編はこちらからどうぞ
人情を俳優になるだけ、小気味よいほどさばさばと一見なにも情のこもっていないように喋らせる小津流の演出は、最初、観る側に、疑問符をもって迎えられるかも知れません。しかし、よくよく味わうとこの淡泊なせりふの言い回しは、観客を、ストーリーへの没入を喚起させ、「より詳しく登場人物をみていかないとだめだぞ」と思わせてしまいます。
つまり、惚れた、腫れたということを、盛大に人物が語りすぎるとかえって、観客はストーリーに没入することができなくなると考えていると、ボクには思うのです。
音楽は、タイトル曲からして、バッハの「2声のためのインベンション」のさわりの部分や、ヨハン・シュトラウス2世の、喜歌劇『こうもり』序曲、はては、ストラヴィンスキーの舞踊音楽「春の祭典」、ケテルビーの『ペルシャの市場にて』などを、軽妙洒脱に翻案したフランスのプーランク風の、皮肉交じりのウィットに富む映画音楽になっていて、その軽妙さは、ストーリーを何気に補足しながら面白くしています。音楽は、黛敏郎が担当しています。よくよく練られたストーリーに呼応するよくよく練られた映画音楽です。
ストーリーは、19年前、祇園の芸者だった佐々木つね(浪花千栄子)には、21歳になる娘(団令子)がいて、彼女は神戸の外国商社のタイピスト。女性として生きていく術を親子で引き継ぐかのように、パトロンに、いかにおねだりするかと言うことに長けている母と娘。小早川家当主・万兵衛は、競輪の帰り道に、ばったりと佐々木つねと駅で出会います。その万兵衛は、佐々木つなの娘が、自分の子だと思っていますが、どうも、そう思っているのは万兵衛ひとりで、本当のところは、どうだかわかりません。
一方、小早川家では、伏見の造り酒屋の当主・万兵衛は、娘婿(小林桂樹)に家業をまかせて、半ば隠居状態。最近、当主の京都通い(伏見からみると、京都というのは別の地なのです)に気づき始めます。しっかりとした長女(新珠三千代)、そして、阪大の学者だった長男は既に他界、長男の嫁(原節子)の後妻の口の話、次女(司葉子)の見合いと自由恋愛の相手(宝田明)、当主の妹(杉村春子)と、きわめてしっかりした女性たちに対して、男性陣は、しごく駄目男ばかりです。
当主の義弟(大阪 亡くなった嫁の実家の弟・加藤大介)は、大阪の文化のわからぬ御仁ですが、小早川家にいまだに口をはさみたくなる。後妻(原節子)の見合い相手で下世話な鉄工所の社長(森繁久弥)を紹介したりします。小早川家をめぐる、当主・万兵衛も実は、養子なのです。駄目男たちと、賢い女たち實にさまざまな境遇の人々が、万兵衛を中心にさまざまな出来事を繰り広げる、それが小早川家の初秋に近い夏に起きる出来事なのです。
万兵衛を演じるのは2代目中村鴈治郎(今の中村玉緒の父)です。歌舞伎役者らしい、軽妙な足の運び、粋を知るものでなければ出せないような、元芸者とのやりとり、みていて、思わず嬉しくなるキャラクターを演じます。孫とのかくれんぼうごっこを利用して、家を抜け出して、いそいそ京都に通ったりします。あわてていたので、駅前のたばこ屋で千円借りて、電車賃を都合したりする、家ではなにもしないのに、昔の妾宅では、裾をまくり上げて、嬉しそうに廊下の雑巾がけを頑張る。そんな、おばかさん。昔はこうした旦那が京都にはあちこちに存在して、飲み屋をちょっと1杯で、また次の飲み屋へ、といった粋な遊び方を心得る人々が存在していました。
この映画がさらに興味深いところは、小津安二郎がメガホンをとった数少ない松竹大船撮影所以外の作品だということです。この映画は東宝映画配給ですが、実は、東宝の元会社でもある宝塚映画の作品です。小津監督は、ドイツのアグファー社製のカラーフィルムを使って、京都の古さを、渋い赤の色調は印象的に描き出しています。
公開された1961年当時は、映画全盛の頃で、五社協定といって東宝・松竹それぞれ俳優たちも専属でした。登場する、長女役の新珠三千代も、その夫役の小林桂樹も義弟の加藤大介に加えて、森繁久弥や若大将映画のヒロインだった団令子も登場します。情念を過剰に描く傾向にあった東宝映画の俳優たちが、いつもとは大いに異なる小津の演出方法で、感情を過度に吐露せずに、演じる姿は、かえって、いつもと違う雰囲気をよく出しています。
小津映画の常連の笠智衆もほんの少しだめ押しのように、いい場面で登場してきます。そして淡々としたいつもの小津調で語る締めの役を演じています。
日本では本作は、当時から現在まで小津映画の失敗作といわれてきましたが、フランスでは絶賛されて今でも上映されています。フランスのタイトルは”Dernier Caprice”。日本語に訳すと『最後のきまぐれ』)になります。いいタイトルです。ぼくは、小津映画のなかでも、突出していい映画だと思っています。今回、これを書くにあたり、1日じゅう本作品を何度も見返しましたが、見返すほどに発見があり、改めて面白いと思った次第です。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPはソナー・メンバーズ・クラブをクリックして下さい。
Categories:未分類


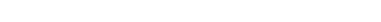


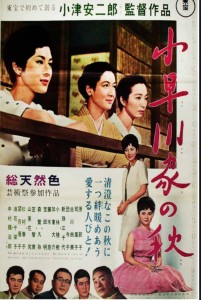

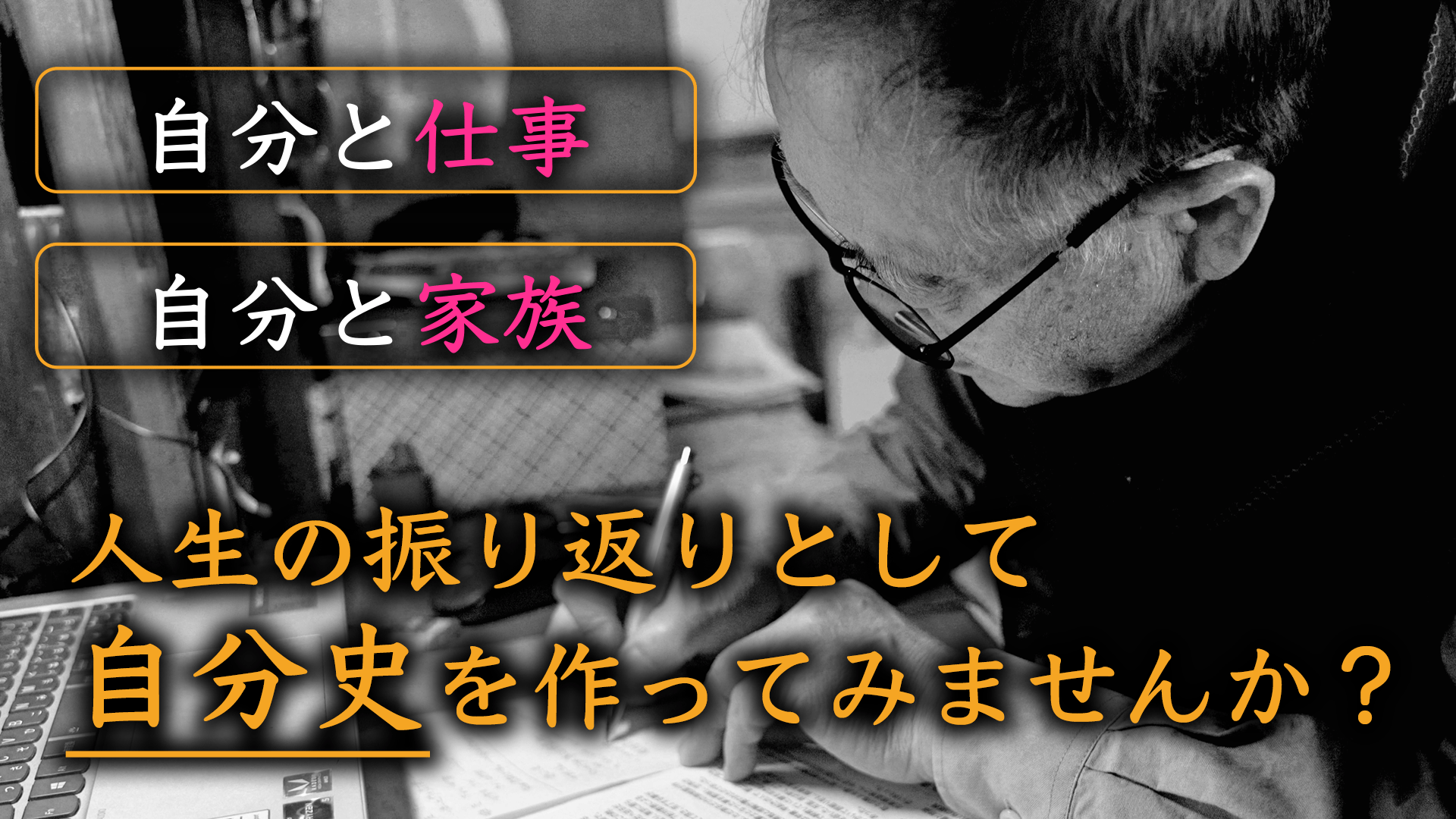


中島 龍之
1/6/2017 | 9:58 AM Permalink
「晩春」が、父娘のストーリーなら、「小早川家の秋」は、家族のストーリー、出演者が大物ばかりなので、主役がわからない映画でした。平凡な日常の会話の中に、淡々とストーリーが流れて行く。しかし、それでも魅せられるのは美人女優のスター性でしょうか。今のように、会いに行けるアイドルが増えて身近になった時代、存在するだけで絵になる俳優さんの時代ですね。映画はそうあってほしいものです。淡々とした会話の中に内なる感情がこもっています。セリフのない時間の画面がいいですね。そこに家族それぞれの感情を想像してしまいます。音楽は、野村さんの解説がないと分かりませんでしたが、音楽も面白いですね。笠智衆が短いながらも出て、火葬場の煙突を見て語るシーンがまた味があっていいですね。笠智衆と煙突の煙で、人生を語らせ、この映画を数十秒でまとめさせた所が、小津映画なのでしょうか。
野村 和寿
1/6/2017 | 10:11 AM Permalink
中島さん 本作が、今の映画と決定的に違うのは、主役とかストーリーとかに拘泥することなく、観る自分が、配役の誰かに仮託して映画を構成するところでしょうか。まさに中島さんのご指摘の通りだと思います。
通常、この映画は、小津映画の中では継子扱いされています。外様の東宝で撮ったからでしょう。しかし、加藤大介の演技を気に入って、次回の秋刀魚の味でも、東宝から加藤大介を借りてきて起用したりして、あの有名な岸田今日子がママのバーでの軍艦マーチのシーンにつながってもいます。また 中島さんご指摘の通り、笠智衆に小津のいいたいことを集約させていわせた、と一般的には語られております。また、プロデューサーの藤本真澄によると、最後の川の送りのシーンが、カットによって、川の流れが逆になっていると試写で指摘したそうです。いずれにしましても、小津の映画を観てくださり、まことにありがとうございました。