『飛行艇クリッパーの客』Ken Forettの乗客になる
2017 AUG 5 6:06:09 am by 野村 和寿

飛行艇を舞台にした海外小説『飛行艇クリッパーの客』(新潮文庫・上下巻1993年)を読了しました。前回『インペリアル航空第109便』(リチャード・ドイル著)の飛行艇は、英国のショート社製ショート・サザーランドと呼ばれる飛行艇でしたたが、今回の飛行艇は、アメリカ・ボーイング社が1938年に完成させたB-314飛行艇です。
B-314クリッパー機は全長109フィート(33.2メートル)、翼幅長さ152フィート(45.6メートル)通常、船だと大西洋横断に、4-5日かかってましたが、クリッパーだと、正味25-30時間で、イギリスとNYを結ぶことが出来ました。
1939年現在のポンドとドルの交換率は1対4.2 1ドルは3.5円でしたので、NYロンドン⇒NY運賃 片道90ポンド 2017年現在の円レートで概算すると、片道375万円です。ちなみに英国航空のファーストクラス現在のロンドン・NY片道運賃は、122万円ですので、当時の片道運賃は現在の運賃の約3.07倍ということになります。この価格がわずか19人の乗客になると思うと高いのか高くないのかさて・・・?
「空飛ぶ宮殿」と呼ばれ、いわく、美しくこわれやすいシャボン玉。世界一ロマンチックな飛行機、史上最大の大西洋横断旅客機といわれていた。19人の乗客をのせて、イギリスのサウンサンプトン河口域を離水のためにエンジンをパワー全開にして、風上に機首を向け、一路最初の着水地、アイルランドのフォインズ目指して、離水しました。B-314クリッパーは、4基の巨大星形1500馬力のエンジンを4基もち、航続距離は、ゆうに、アイルランドから一気にカナダ・ニューファンドランドまで3000㎞を飛行することができます。B-314クリッパーは1938年に完成し、全部で12機が製造されました。その中の1機が物語に登場する「クリッパー」とは、もともと快速の帆船の意味です。
前回取り上げた飛行艇の「インペリアル航空第109便」(リチャード・ドイル著)の物語が、飛行艇の乗員の話だったのに対して、今回とりあげるケン・フォレットの作品「クリッパーの乗客」は、飛行艇に乗り合わせた乗客を中心とする物語。「袖振り合うも多生の縁」ということで、ぼくもこのクリッパー機の乗客になったつもりで読み進んでみることにしました。

飛行艇クリッパーの乗客は平成5年(1993)年新潮文庫から刊行されましたが、現在絶版。古書ではアマゾンで1円から入手可能です。ちなみに1円でも怪しいものではありません。ほかに郵送料が257円(関東への送料)かかるため古書店はペイするのです。
ロンドンから特別仕立ての車両に乗車し、列車内では、フルコースのランチ(シュリンプ・カクテル、フィレミニヨン・ステーキ、アスパラガス・オランデーズソース、マッシュポテト添え、ピーチメルバ、プチフール、コーヒーこれだけみても英国的という感じで感心はしませんね)をいただき、飛行艇の出発地である、サウサンプトンの港へと向かう。ときは1939年の9月 ヒトラーによるポーランド侵攻で幕が落とされた第2次世界大戦の幕が落とされたその3日後ということになってい。ちなみに、9月1日は日曜日、最初のロンドンに出た独空軍空襲に対しての空襲警報は、英国国教会の礼拝の最中、11時28分に出されたとあります。このようなエピソードがわかって面白いです。
その3日後の9月4日、戦争の難をのがれアメリカを目指す幾多の人々のなかで、このNY行きのB-314クリッパー機も登場します。著者のケン・フォレットは、入念な準備による細かい描写で知られた作家です。代表作『大聖堂(ドゥオーモ)』で、ぼくは、ヨーロッパ各地にある大聖堂がなぜ、同じ形をしているかを知ることが出来ました。つまり大聖堂ばかりを建築して回っている職人集団が存在し、彼らがあちこちの大聖堂を建築したので、形が同じだったのです。
話をクリッパーの乗客に戻しましょう。
ここに登場する乗客にも、ぼくが今まで知らなかった1939年当時の事情がわかってとても興味深いものがありました。アルジャーノン・オクスンフォード卿一家が登場します。父親であるオクスンフォード卿は、なんとイギリスのファシスト党の党首をしていた人物に描かれています。英国ファシスト党の考えというのは、戦後タブーでなかなか真意がわかりませんでしたが、今回、それを知ることが出来ました。
英国ファシスト党の考え方は、「資本主義、社会主義、がともに破綻し、民主主義は結局一般大衆にはなんの利益ももたらさない。善意独裁者が、産業を統制する強権国家主義をめざし、大衆に訴える。世界はこのままいくと混血児とユダヤ人のものになってしまう」と信じる。なぜ、ファシスト党なのか? これには、第一次世界大戦後のイギリス経済、特に農産物価格の世界的暴落をもろに受け、オクスンフォード家は破産寸前になった。そこで、アメリカ人銀行家の跡取り娘を嫁に迎えている。
イギリス貴族の経済的衰退とファシズムとが結びついたという例は、ほかでもみたことがあります。日系の作家カズオ・イシグロが書き、映画『日の名残』(1993年・英国)となって名優アンソニー・ホプキンスが、その執事役として演じていました。また、史実でも、英国にもあった黒シャツ党は、ロンドンにも存在しデモ行進をしていたとありました。ファシズムはイタリア・ドイツだけではなく、英国にも、独伊以外でもっとも浸透をみせていたのでした。父の影響を受けた長女エリザベスは、21歳。熱烈な王制主義者でナチ崇拝者。「このままだと世界は混血児とユダヤ人のものになってしまう」と思い込んでいます。しかし父への反発は強く、旅行中に「ドイツ・ナチズムを崇拝する外国人」になりたくて、リスボン行きの船でドイツへと向かいます。
一方で、ユダヤ人に救いの手を差し出す人物も登場します。フランス人の銀行家ガボン男爵。シオニズムのようなユダヤ民族主義運動に莫大な富を投じ、イギリスの不興をかている。ガボン男爵の考えは「我々ユダヤ人自身の国家を作らねばならない。アラブ人を排除することにつながる。軍国主義と人種差別が合体したものがファシズムだ」とし、ドイツの世界的に高名な原子物理学者カール・ハートマンをアメリカへの亡命に手を貸そうとしています。
終始、モーツァルトの歌劇『魔笛』でいえば、パパゲーノとパパゲーナのように道化で登場するのが二人の若者。ハリー・バンデンポスト・アルビー 実名はハリー・マークス 22-3歳とオクスンフォード卿の次女マーガレット19歳。
マーガレットは、侯爵家によくあったように家庭教師に勉強を教わり、学校には通ったことがない。その恋人で、オックスフォードの最終学年だったイアン・ロチデールをスペイン市民戦争義勇兵として国際旅団に参加し戦死。社会主義者で、ジャズが好き、キュビズムの絵が好き、自由詩が好き、英国軍の傷病者運搬車の運転手になりたい。
一方のハリー・マークスは、父親が第一次大戦で戦死し、ビルの清掃婦の母親の手ひとつで、貧しいバターシーのアパート、共同流し場とトイレで育ったが、高級宝石店のショウウインドウをのぞき、宝石をみる目を磨いているうちに、近代的なブリリアント・カットと19世紀の旧式マインカットのダイヤモンドのカットの違いを覚え、午後のテニスの合間にお茶を飲みに戻ってくるという生活や、遅くに起き陶器のカップでコーヒーを飲み、華美な服装をし、高いレストランでの食事に憧れていた。アスコット競馬場で、器量のよくない金持ちの令嬢に次から次へと声をかけ、夜会に呼ばれ、ドーセット伯爵邸では、ジョージ王朝風の銀のボンボン入れや、同漆塗りのかぎ煙草入れ、ミセス・ハリージャスパーズ邸では、ティファニーのルビーの留め金付きパールのブレスレットを、マルボリ伯爵夫人邸では、銀のチェーンつきアールデコのダイヤモンドペンダントを失敬、2年間の盗みの総決算として247ポンドを盗みます。この若い二人は一服の清涼剤として登場します。
ちなみに、本ブログを書くにあたり調べていくうちに面白いことに気がつきました。当時、実際に、飛行艇の途中経由地である。アイルランドのフォインズ(首都ダブリンから4-5㎞)に、現在、フォインズ博物館飛行艇&海軍博物館のホームページを見つけてしまいました。こういうことはやっていて、なにかとてもうれしいことでした。下記からURLでいきつくことができるので、是非のぞいてみてください。

アイルランド・フォインズに、「フォインズ博物館飛行艇&海軍博物館」のホームページをみつけました。実際のB-314飛行艇のレプリカが展示されています。手作りのかわいい博物館です。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」







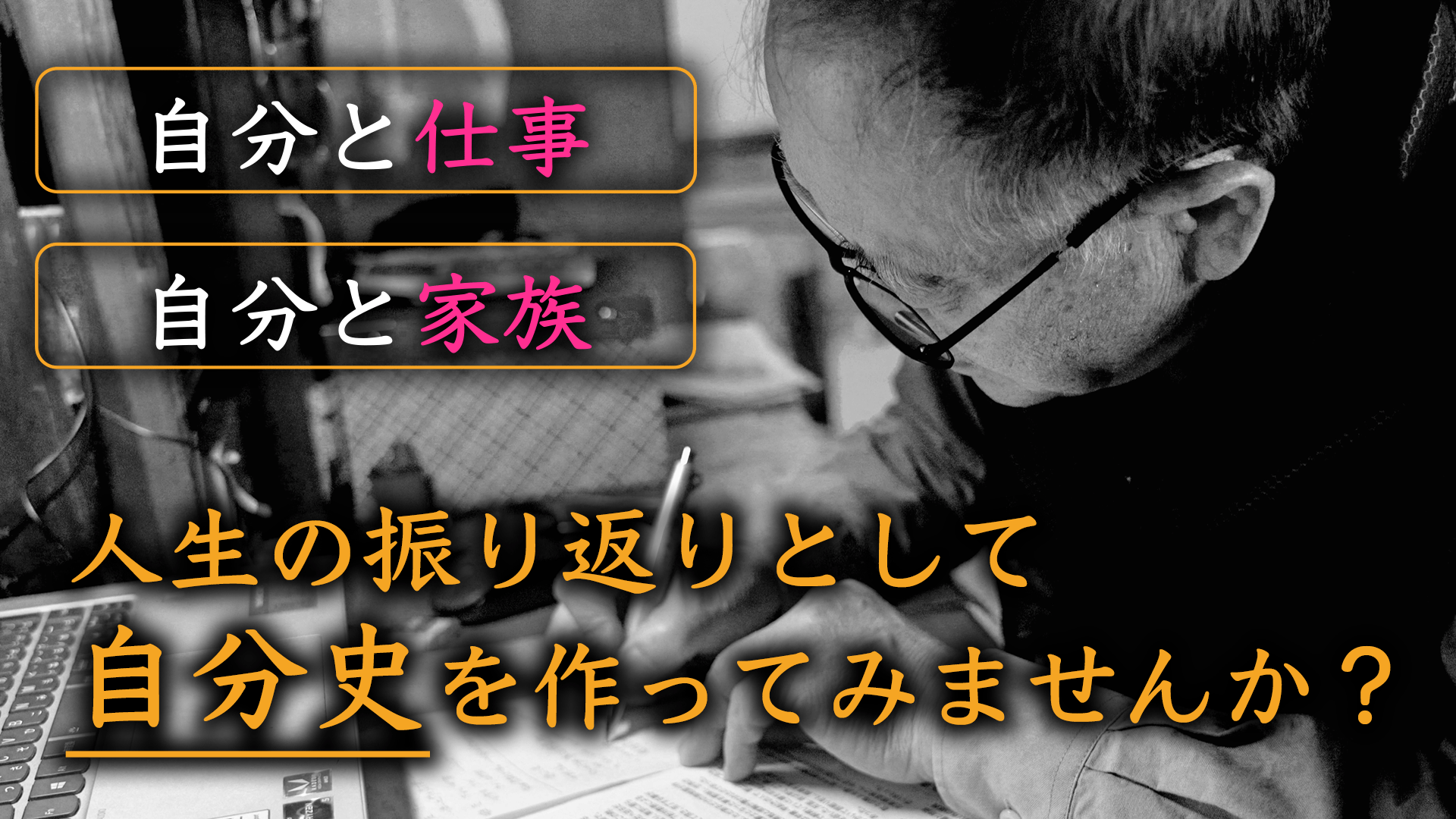


東 賢太郎
8/6/2017 | 12:53 PM Permalink
貴君の詳細な記事を読んでいてひきこまれました。32年も前、ロンドンに住んでいた頃ですが、英国の地中海クルーズ船で1週間過ごしました。500人の乗客で東洋人は僕ら夫婦だけでした。当時の貧しい僕らからすると周囲は大金持ちですが、毎日同じテーブルで食事する4,5夫婦と仲良くなってしまうのです。それを飛行機でやる世界があったのかということですね。読むとハネムーンスイートと全員用の簡易ベッドもあったようで、ロンドンの列車内のメニューからサービス・クオリティを推察するに、それで当時の事情を勘案して片道375万円はまったくリーゾナブルでしょう(但し、9月にアスパラガス・オランデーズソースは間違いなく缶詰だね、これは減点)。
HPも全部拝読しました。アイルランドは大好きな国なんです(判官びいきに訴える)。いきなり「フォインズは2世紀ほど前からの、我が国としては若い街だが」なんて書きぶりが泣かせ(笑わせ)ます(オンリーと書かない西洋人には稀なる気配りが最高!米国人様は大事な客だ。日本人も中国客へのホスピタリティの出し方を見習ったらいい)。
「アイリッシュ・コーヒーの起源」も傑作です。「オリジナルの作り方」は淵まで1cm未満にコーヒーを注ぎクリームをスプーンの背から流し込めとある。飛行機が帰着して疲れて寒い客にウィスキー入りはわかるけど、その場の思いつきでホイップクリームを加えたのは天才的で、これがなかったらこの飲み物はなかったと思わせますね。最後に「かき回してはいけない」とあるんでそこにプライドすら感じます。すごくアイルランド人らしい。久々に感動。
大聖堂の大工さんですが日本なら宮大工に当たる石工の超絶テクノロジー集団でしょう。フォレットの著作は読んでませんがフリーメイソンのことではないでしょうか。余人をもって替え難いので国境をまたいで雇われざるを得ず、全部の王侯と聖職者の秘密を知ってしまっている連中です。だから男だけで口の堅さが売りです。それが思想家、知識人を巻き込む隠れ蓑となってやがて啓蒙思想となります。
こんなにミクロの視点にまで引きずり込んでいただいてこの記事に感謝です。飛行艇はもうないけどもこういう旅をもう一度してみたいなと思うようになりました。僕は忙しすぎますね、よくわかった。クルーズでテーブルが一緒だった英国紳士たちはたぶん今の僕ぐらいの年齢だったろうなあなどと、いろいろ考えることがあります。
野村 和寿
8/6/2017 | 1:22 PM Permalink
東君 コメント感謝。読んで頂いてうれしいです。この作家はとにかくディテールを読み込んでいくと面白いです。たとえば、オクスンフォード家の通常の食事時間は、朝9時、昼14時、夜20時半であるのに対し、労働者階級のハリーの食事は朝7時、昼12時、夜17時になっていて食事時間が違うとか、
カナダ・ニューブランズウィック州シェディアック(セントローレンス湾)でのクリッパー機の夕食も小説に登場します。シェディアックの獲れたてのロブスターで作ったロブスター・カクテル、キドニー・スープ、メインは、舌平目のカーディナルソースまたは牛フィレステーキ ポテトと芽キャベツ添え 白ワインです。クリーム添えのアップルタルト、またはチョコレート添えのアイスクリーム。となっていて、ここでも、微に入り細に入り、作者の考える英国風のフルコースですね。面白いです。
東 賢太郎
8/6/2017 | 1:38 PM Permalink
なるほど、それは今のロンドンでリッツで出てきて何の違和感もない、むしろ当たり前すぎるメニューです。戦前から英国風はそのままということですね。キドニー・スープはまだいいけどキドニー・パイはだめでした。失礼して残してしまった人生数少ないディッシュのひとつです。舌平目とフィレは定番というか、英国はそれとラムしかないからね、でもそれだけに調理法には気合がはいってます。いや懐かしい。