知られざる名手たちによるピアノ・デュオの至福
2021 FEB 8 5:05:56 am by 大武 和夫

前回からまた相当の時間が経過してしまいました。すぐにも投稿を再開するつもりでしたが、頚肩腕症候群という症状を呈してしまい、首・肩・上腕部の痛みに苦しむ生活が続きました。生来のストレートネックによる頸椎ヘルニアが根本原因のようですが、巣籠り生活の中でスマホを注視する時間が増えた皆さんも、どうぞお気を付けください。
さて、ようやく症状が治まり始め、PCに向かえるようになったら、その間に書きたいテーマはどんどん増えてしまっています。前回頭出しをしたテーマは追って順次カバーするとして、今日は2月6日に聴いた長尾洋史・藤原亜美ピアノ・デュオのマチネー「連弾の楽しみ」について書きましょう。
長尾洋史さんというピアニストをご存じの方は、残念ながらそう多くはないと思います。しかし、オーケストラをよく聴く首都圏在住者で彼の演奏に接したことのない人は、ほとんどいない筈。そう、長尾さんは「オケ中ピアノ」の名手なのです。在京オケであると外国オケ来日公演であるとを問わず、たとえばペトルーシュカのピアノ・パートを頼まれるのは、たいていの場合長尾さんです。
私はペトルーシュカだけでも、オケ中ピアノを弾く長尾さんを何度も聴いています。いつ聴いても、その鮮やかさと正確さと言ったら、ブーレーズ/NYOの同曲名録音でピアノを担当する名手チャールズ・ローゼンの顔色を無からしめるものです。一事が万事。他のレパートリーでも水際立ったオケ中ピアノを聞かせる長尾さんは、譜読みが正確で速いことでも定評があり、滅多に演奏されないピアノ・パートを含む近・現代曲の演奏では、多くの場合オケを問わず長尾さんが登場します。
その長尾さんは、室内楽の名手でもある(←オケ中ピアノを通じてオケ・メンバーの信頼を勝ち得ていることの証左でしょう。)と同時に、実は隠れた(失礼!)ソロの名手でもあります。昨年は2枚のソロCDを発表していますが、特にゴルトベルク変奏曲には参りました。少しも奇抜なことはしていません。目立たないところで装飾音に工夫はしていますが、現代の演奏家で装飾音を楽譜通りにしか弾かない人はいないでしょう。テンポも総じて常識的。他の要素を犠牲にしても声部の違いを弾き分け、対位法をことさらに際立たせようとする偏執狂的な態度も皆無。様式に反する極端な強弱も、大仰なアッチェレランドや意図的なラレンタンドも、注意深く避けられています。要はすべてが中庸なのです。普通そういう演奏は、乾燥して豊かさに欠けるつまらないものとなりがちで、実際そういう演奏はとても多いと思います。しかし、長尾盤では、微動だにしないテンポと正確無比なリズムの中から、たゆたうような詩情が溢れて止まらないのです。これは一体どういう逆説でしょう。黄金の中庸というべきか。ゴルトベルクの私的ベスト・スリーに入るのはもちろん、ひょっとするとベスト・ワンかも、と思えます。
実は私はあるご縁で長尾さんと親交があり、このCDも発売前にお送り頂いて、あまりの感激に二度、三度と深夜すぎまで繰り返して聴いてしまいました。こんなことは滅多にありません。その感動を長尾さんに伝えるメールの中で「中庸」という表現を用いたところ、長尾さんから、大略、まさに「中庸」こそ自分がバッハで目指していることであり、来月号(記憶が正確なら昨年の2月号でしたか)の「ぶらあぼ」誌掲載インタビューでも同じ言葉を使っています、という嬉しいご返事を頂きました。
そして、長尾さんは、藤原亜美さんという、こちらも長尾さんに負けず劣らず私が大好きなピアニストと、時折4手を披露してくれます。この二人のデュオを初めて聴いたのは、忘れもしない文化会館小ホールでのメシアン「アーメンの幻影」で、でした。もう20年近くも前のことです。(文化会館小ホールと言えば、それまでの私のとっての最大のメシアン体験であったジャン=ロドルフ・カールスの「眼差し」全曲演奏の会場でもありました。四半世紀を隔てた不思議な符合という他ありません。)
精緻・精密の極致であり、あらゆる点で模範的な演奏でしたが、本当に驚くほど多種多様な感情を聴き手の内に呼び覚ますのです。この演奏が本稿の目的ではありませんから、これ以上述べませんが、我々にとって、さらには後世の音楽ファンにとっても幸いなことに、長尾・藤原デュオは、同じころこの曲を録音してくれています。これこそ、他のあらゆる名盤を凌駕する決定的名盤です。決定的名盤などという言葉は、それを用いることによって他の演奏の美点を心理的に覆い隠してしてしまう危険な副作用がありますから、滅多に使うものではありません。しかし、この録音については、私は躊躇なく決定的名盤と呼びます。録音も極上。メシアンに聞かせて上げたかった!
藤原さんは、長尾さんと並んでソロの隠れた名手でもあり、以前はかなりの数のソロ録音を発表しておられました。モシュコフスキーの全集などは、もっともっと注目されてしかるべき素晴らしさでした。(それに、舞台映えする美しい方です!)
その長尾さんと藤原さんは、3年前に巣鴨の小さなスタジオでドビュッシーの4手(2台と連弾)を披露され、このデュオは本当に世界最高水準だな、と私を改めて感激させています。そして、オール・ドビュッシーのCD2枚組が、来る4月にリリースされることになりました。ここでようやく昨日のデュオ演奏会に話を戻しますと、長尾さんによれば、その発売を記念して何かまたやりたいということで、6日の演奏会を企画したのだそうです。
コンタルスキー兄弟亡きあと、世界最高のデュオはこの二人だと確認させてくれた演奏会でした。ラベック姉妹、タールとグロートホイゼン等、4手のアンサンブルは多々ありますが、長尾・藤原の素晴らしさは頭一つ抜けています。
場所は、東京は目黒区洗足駅前のプリモ芸術工房という小さな会場で、聴衆は20名限定。プロは渋さの極みで、前半がシューベルトのD. 823(「ディヴェルティメント」と「アンダンティーノと変奏曲」の2曲からなる「フランスのモティーフによるディヴェルティメント」)とD. 951(「ロンド」)で、後半はドビュッシーのバレエ音楽「おもちゃ箱」(連弾への編曲は多和田智大氏;語り付き)。本当に渋い、玄人好みとしか言いようのないプログラムです。大衆的アピールはゼロ。
連弾の難しさは、経験したことのない人には分かりません。2台ピアノとは決定的に違います。2台のレパートリーはみな、程度の差こそあれ協奏曲的に、というか2台が競い合うような形で書かれています。連弾は一つの目標に向かって心と技をピタリと寄り添わせる必要がある点で、まず奏者2人の関係性が全く異なります。2台ピアノには超絶技巧を要する曲がいくつかありますが、連弾にはほとんど無いのも、このことと深く関係していると思います。
並んで座りますから、相手の身体の動きが直接感じられますし、腕が交差することもあります。異性同士の場合、身体的距離の近さがある種の感情にもたらすこともあるでしょう・・・私には幸か不幸かそういう経験はありません(笑)・・・し、異性同士でなくともある種の親密感が生まれるのは必然です。その反面、他の奏者に接する側の肩や腕の動きに微妙な制約を感じることも、ママあります。鍵盤を所狭しと指が駆け巡る超絶技巧が連弾に適していないことは、連弾曲に超絶技巧曲が見当たらないことの一つの原因でもあります。
フレージングやテンポ感を統一する必要があるのは、2台の場合ももちろん同じですが、連弾では、そのあたりに意見の相違が少しでもあると、2台の場合よりはるかに深刻な結果を招きます。
どちらか一方が踏むことになるペダルがまた厄介です。普通は和声を支える低音部担当者が踏みますが、高音部担当者のソロのような箇所では、高音部担当者にペダルが任されることもあります。ペダリングというのは、ピアノ演奏にとって極めて重要な要素ですから、自らペダルを踏まずに、しかしペダルが要求される曲を弾くというのは、ペダルを踏まない方の奏者に一定のストレスを与え得ます。自分ならこう踏むのになあ、とペダル担当者のペダリングに不満を持ったりしたら、精神的一体感が阻害され、アンサンブルは崩れるでしょう。何より集中を削ぎます。2台なら、各奏者がある程度の枠の中で自由にペダリングを行っても、演奏の統一感が損なわれる度合いはずっと小さいはずです。
おそらく最も重要なことは、ピアノ書法が全く異なるということです。2台の場合は、それぞれの奏者がピアノの全音域を演奏可能であるのに対し、連弾では、腕が交差する場合があるとは言え身体まで入れ替えることはありません(実際に入れ替わって弾く「曲弾き」はここでは考察の対象外)から、奏者ごとに担当する音域がおのずと決まってきます。すると何が起きるか。2台に比べると、連弾は中音域の音が厚いことになりがちです(必ずしも密集和音を意味する訳ではありません。)。したがって、声部間のバランスが常にうまく保たれていることが、2台の場合よりはるかに重要になります。
以上のことから、連弾は2台に比べて、親密さを表現するのにより適した媒体と言えますが、他方で、それにも関わらず音響現象としては、ガチャガチャとうるさいことになりがちだと言えます。プロのデュオでも、うるさいなあと思わせることは珍しくありません。常時デュオを組んでいる二人であれば、そんなことは起きないだろうとお考えですか? いえいえ、それは本当に耳が良く、センスが良く、お互いを理解し信頼しあっている二人が、曲への音楽的アプローチを共通にしたうえで綿密なリハーサルを繰り返すことによって初めて可能なことなのです。常時二人で弾いているデュオの場合、連弾というフォーマットを所与のものととらえてしまっていて、緊張感をもって演奏に臨んでいないなあ、と思わせる例も珍しくありません。
そのあたりの匙加減が、長尾・藤原デュオは本当に絶妙なのです。
第1曲で、高音部担当の藤原さんが長尾さんの盤石の低音部に載せて単純な上行スケールを奏でるところで、不覚にも目頭が熱くなりました。一体なぜこんな単純なスケールに感動するの?と思う間もなく、音楽は進みます。同じ曲の終り近く(ヘンレ版のシューベルト4手全集第2巻ですと最後の2ぺージ少々)で、長尾さんのスケールと藤原さんのスケールが親密に繰り返し歌い交わすところの美しさと言ったら!
二人とも弾き崩しの全くない正攻法で、自己顕示のための音量変化や恣意的テンポ変化を嫌う潔癖な楷書的解釈でありながら、その演奏からなぜあれほど無限のニュアンスが紡ぎだされ、心が揺さぶられるのか。魔法のようです。いや、考えてみると、これはシューベルトの音楽そのものにも言えることですね。シューベルトの笑顔と哀しみが同時に透けてみえるような曲の数々であり、演奏でした。これ以上何を望むことがあるでしょう。
後半のドビュッシーは、一転してセンスの塊。リズムの何と生き生きしていることか。そして和声が常に最善のバランスで鳴り響くことにも驚倒。長尾さんが音大の副科ピアノで指導を担当されたという多和田智大さんという方の手になる連弾用編曲が見事なら、ソプラノ歌手國光ともこさんによる語りも、鮮やかに情景を切り取って、曲の面白さを際立たせていました。
アンコールには、ドビュッシーの小組曲から「小舟にて」と、シューベルトが晩年に対位法を学んで作ったという「フーガ」(D. 952)が演奏され、素晴らしい午後のひとときが閉じられました。
こんな素晴らしい演奏会が、東京の住宅街の片隅でひっそりと行われているのです。連弾はピアノ・フリークにとっては興味の対象外かもしれませんが、もっともっと多くの人に聴いて欲しいと強く思いました。主催者はライブストリーミングの配信を行っていましたが、どれほどの聴衆の聴くところとなったのでしょうか。会場に来られなかった多くの人がPCやスマホで鑑賞したことを祈るとともに、巨大都市東京で、一見ささやかでありながら実は極めて重要なこのような音楽イベントを、一般の音楽ファンに知らせ、届けることの難しさに思いを馳せたことでした。プリモ芸術工房さん、ありがとうございました。
なお、これは蛇足ですが、プリモ芸術工房に設置してある1936年製NYスタインウェイの素晴らしさにも大きな感銘を受けました。無論演奏が素晴らしいから楽器の素晴らしさが引き立つのですが、今でいうとSに相当するように見える最小の小型グランドから、何と豊かで香り高い音が立ち昇ってきたことでしょう。この頃までのNYスタインウェイの色合いの濃さと、タッチに敏感に応じる俊敏さは、私にとってピアノの理想形です。つい拙宅の前世紀末のハンブルク製Bと比較してしまうのですが、帰宅後、頚肩腕症候群発症以来初めて少し鳴らしてみたハンブルクのBが、モノクロでダルな音に聞こえてなりませんでした。(もちろん腕前の劣悪なことに大きな原因があるのですが、それだけではないということです。)「このNYスタインウェイは欲しい!」と強烈な物欲に駆られるというおまけつきのコンサートでした。
Categories:未分類



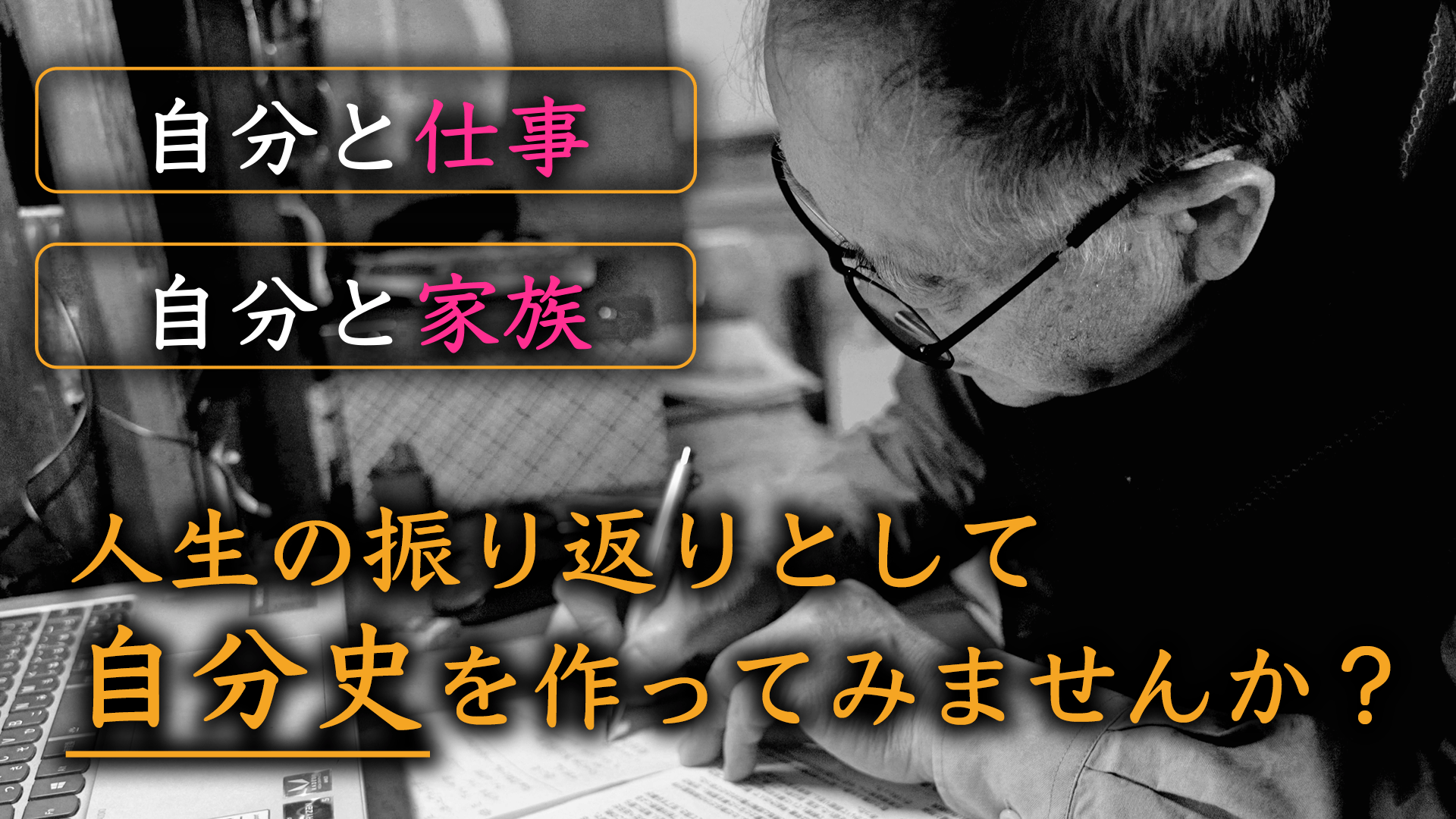


東 賢太郎
2/15/2021 | 3:20 PM Permalink
大武さん、連弾の楽しみを学ばせていただき有難うございます。長尾・藤原デュオは寡聞にして知らず、もっと知られても良いというおっしゃる意味がわかる気がいたします。
マ・メール・ロワのレドロネットを聴きましたがとても繊細で緻密ですね、ガラス細工のような曲ですし日本的な感性の美が活きていると感じました。これだけ上質の連弾で聴かせてもらうとこのフォーマットが合っている曲は知らないだけでたくさんあるのかなとも感じました。ドビッシーの海はいろんな人がやっていますが、ソナタとして聴くのも大好きです。
私見ではレドロネットは中間部で和音がF#からFm/a#にがらりと変わる箇所がポイントですが、長尾・藤原デュオのような弾き方もあるし、アルゲリッチのように色彩もテンポも変転させて聴き手を別世界に連れこもうという人もいます。譜面にはありませんが実にセクシーでありラテン的感性のようでもあり、彼女はいつも高音部担当ですが必ず直前で相手に目配せして誰とやってもそうなってます。変転ぶりはグルジア人のブニアティシヴィリだと全開で、日本人の海老 彰子だと心なしか控えめです。面白いものですね、こういうものは単なる好き好きですが、解釈に奏者の人間性が出るのは鑑賞の楽しみです。長尾・藤原デュオまだよくわかりませんがフランス物を得意とされているようでもありドビッシーは聞きものになりそうですね。
大武 和夫
4/20/2021 | 12:24 PM Permalink
東さん
コメントありがとうございます。
日本的とのご指摘には、なるほどと思う面があります。もっとも、実演を聴きますと、それだけでは済まないドラマの表出も素晴らしいのです。実演とその記録の差という永遠の論点がここにも表れているのかもしれません。録音録画だけではとらえきれないものがあるからこそ、我々は生に足を運ぶのですから。
アルヘリチはもう何十年も生を聴いていませんが、おっしゃることは実によく分かります。ブニアティシヴィリは苦手中の苦手ですが、いずれ書かせていただきます。もっとも、悪口は書いていて気持ちよくありませんから、やはり控えるべきかもしれません。
少し前に発売された長尾・藤原デュオの2枚組CDは、録音の限界ということを踏まえた上で、東さんのような聴き巧者にこそ是非お聴き頂きたいと思います。
東 賢太郎
4/21/2021 | 11:29 AM Permalink
聴いてみます。大武さんのおっしゃる、
実演とその記録の差という永遠の論点がここにも表れているのかもしれません。
は同感です。ライブを聴いてその人がわかったり、楽曲の真価を知ったりということがよくありました。出会いはレコードでも実演で印象が上書きされてクラシックがどんどん楽しくなったという感じでしょうか。はやく復帰できる環境になって欲しいものです。