コンサートの拍手
2022 JUL 26 17:17:29 pm by 大武 和夫
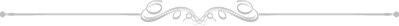
あまり嬉しくない風景がすっかりコンサートホールに定着してしまいました。それは、オーケストラ・メンバーの最初の1人が舞台に現れると直ぐに拍手が始まり、延々と続き、やがてコンサート・マスターが登場すると拍手は高まり、彼/彼女のお辞儀でようやく鳴り止む、という風景です。
静寂の中で団員が出そろい、チューニングが終わって再び静まりかえったホールにやがて指揮者(と場合によってソリスト)が登場し万雷の拍手を浴びる、というのが私が理想とする風景です。そこではコンマスへの拍手もありません。
まずコンマスへの拍手から書いてしまいましょう。リーダー(コンマスの英語圏での呼び名)に拍手するのは恐らく英米の習慣で、欧州大陸では、その伝統はほとんど無いか、あるとしても歴史が浅いと思います。著名オケのコンマスと言えば欧州では大変な地位なのですから、拍手ぐらいしても良いように思えますが、コンサートの主役はやはり指揮者(とソリスト)だという考えなのだろうと推察します。その指揮者・ソリストの登場前に大きな拍手が与えられてしまうと、もうクライマックスが来てしまったように思え、指揮者・ソリストをわくわくしながら待つ楽しみが半減してしまいます。
日本でもコロナ以前のN響では、マロさんは拍手を受けていなかったように記憶していますが、現在では普通にお辞儀をして拍手を受けているように見えます。(あまりN響は聴きに行きませんので、記憶違いかもしれません。)
私にとって更に居心地が悪いのは、最初にステージに登場する団員から延々と拍手が続くことです。これが始まったのは、コロナで一切のコンサートが行われなかった数ヶ月の後、勇気を持ってコンサートを開催してくれたいくつかのオケのコンサートで、聴衆が溢れる感謝と喜びをオケに対する励ましとともに拍手の形で表現したときだろうと思います。2020年夏にそのようなコンサートのいくつかに足を運んだ私自身、同じように行動していました。それは感動的な瞬間でした。聴衆が文字通り一体となる、そういう一体感を味わえる瞬間は、実は滅多にあるものではありません。
しかし、それは非常時の感情表現であり、Life “with” Covid 19が常態となった今でも続けるべきこととは思えません。私には、今やすっかり惰性となっているように思えます。ブルーインパルスの編隊飛行に感動するのは、特別な機会に特別な思いを込めて飛んでくれるからです、あれを毎日やって欲しいと思う人はいないでしょう。拍手も、私に言わせれば同じで、現在のだらだら続く拍手は、むしろ指揮者・ソリストの登場をアンチ・クライマックス化してしまっているように思えてなりません。
もう一つ居心地がよくないのは、音楽会開始時ではなく、幕間がある音楽会における後半の演奏開始時です。前半開始時と同様のプロトコールで出迎える聴衆、それがもう習慣となっているオーケストラがあるかと思えば、後半は指揮・ソリストにしか拍手を送らない聴衆/オーケストラ/演奏会もあります。この不統一が、私には居心地が良くありません。
独奏会であれば奏者が登場するたびに拍手が起きます。皆それを当然と思って疑いません。オーケストラの演奏会における指揮者に対しても同様です。ところが、コンマスを含むオーケストラ団員に対し登場の都度拍手をするかどうかは、決まっていないように見えます。こういうことを無理に統一する必要はないと思いますし、各自の自由に任せれば良いという気もしますが、それでもなんだか割り切れない思いを持つのは、恐らく聴衆自身が新しい流儀にまだ馴染んでおらず、戸惑いを持っていて、とりあえず周囲の動きに同調しておこうという気配が見てとれ、それを私は非常に日本的で嫌だと感じるからです。
団員が登壇しても拍手を始めず、コンマスが登場しても拍手しない私は、今やホールの異端児です。最近では、なんだかそのこと自体に居心地の悪さを感じてしまいます。だからと言って宗旨替えをする積もりも無いのですけれど。
コロナ以前に戻らないものかと、音楽会に足を運ぶたびに思う今日この頃です。
Categories:音楽


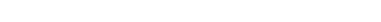
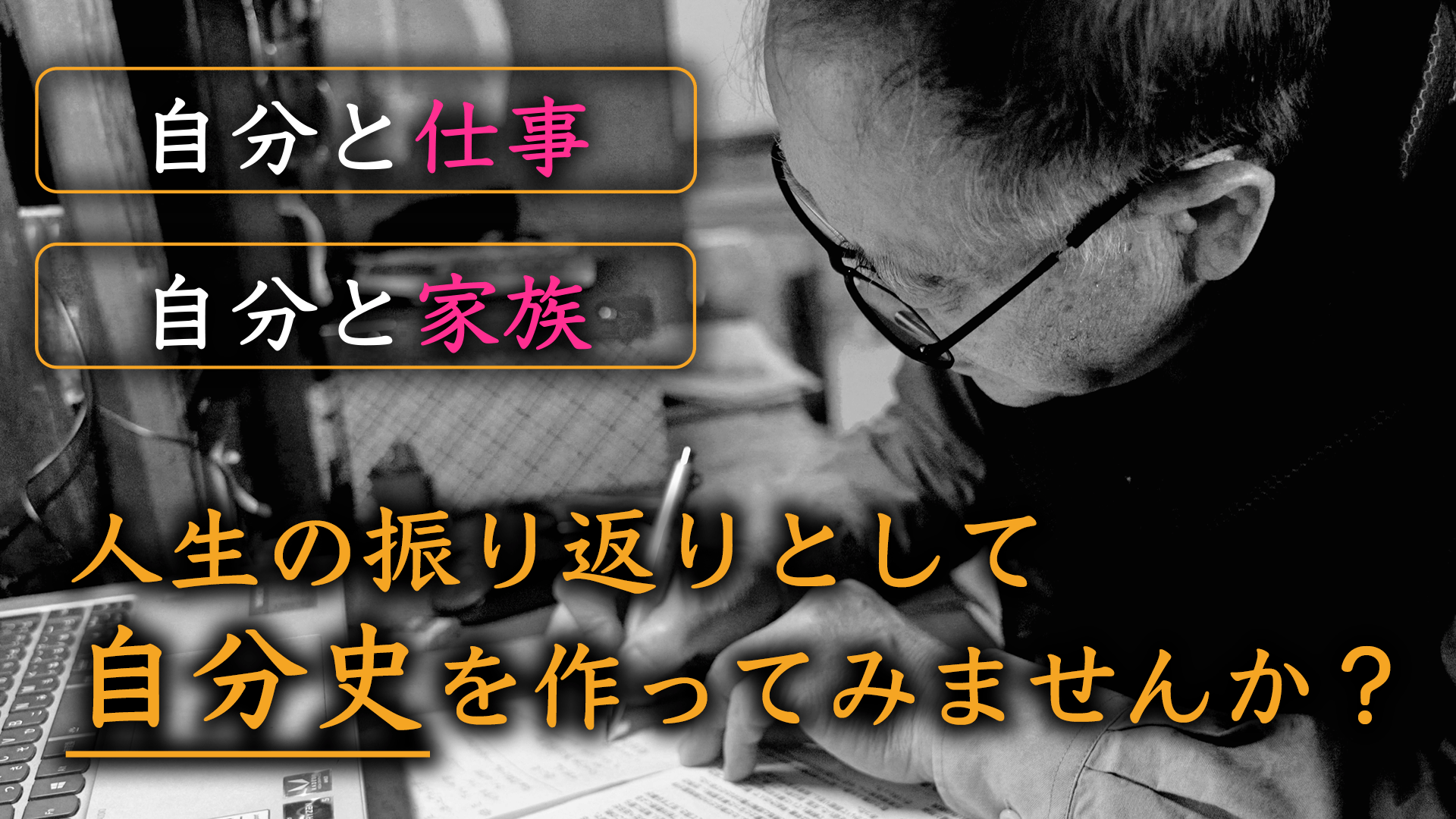


東 賢太郎
7/27/2022 | 1:38 AM Permalink
大武さん、大変興味深いご指摘と思います。最近日本で演奏会に行ってないので忘れてましたが、確かに最初の団員の入場から拍手がおきてました。とても変ですね。ラハティ響の楽員は日本人のコーテシーだと解釈したのでしょう、皆さん笑顔で客席に深く一礼してましたね。それはそれでなごやかでよい雰囲気でしたが、チェリビダッケやアイザック・スターンが舞台に現れるまでの(聴衆まで身動きしてはいけないぐらいの)ピリピリした時間、あれはもう演奏の一部だったような気がいたします。2年間フィラデルフィア管の定期会員でしたが、コンマスのノーマン・キャロルが出てくるとパラパラと1,2秒の拍手があって彼がにこりともせず頷く程度の軽い礼をしていた気はします。この世界、アメリカも田舎ですから。そこでまた静まってオーマンディやムーティが現れるまで(場合によってけっこう長い時間)緊張の糸が張った無音です。
Hiroshi Noguchi
8/3/2022 | 12:42 AM Permalink
シュナーベルの演奏会についてショーンバーグは、聴衆は聖別されて帰路につくという内容のことを言っていたように思います。元来音楽は神に捧げられていたのでしょう。近現代の聴衆を対象とするようになっても「絶対性のある藝術」としての音楽会、東大兄の仰っている緊張感と言ったものもその一端だと思いますが、が厳然と存在してきたのは同感です。
一方コロナの間、様々な形で配信が行われ、僕は無料で配信されたベルリンフィルの室内楽は随分楽しみました。そういう配信では普段ソロでの演奏会の少ない楽器ばかりのものもありました。日本のオーケストラも色々な工夫をした配信がありました。そうすると、音を出していた各奏者に対して、丁度テレビタレントに対するような親近感をもった、新しい聴衆も増えてきているのではないでしょうか。吉田秀和がご存命であったら、まあ現状では危なくてでて来るわけにはいかないでしょうが、何と仰ったか伺ってみたいところです。多分音楽会の聴衆が増える様な言い回しをなさるのでしょうが。
そういう多様な聴衆を相手にするのに相応しい新しい試みがありました。
アレキサンダー・ガジェヴの演奏会では、アナウンスが先ず聞こえて、客席が暗くなり、2分間の瞑想を求められ、舞台が明るくなると既にガジェヴはピアノに向かっていて演奏が始まるという演出をしています。ショパンコンクールで2位となった謂わば「凱旋」演奏会だけで無く、去年夏の演奏会でもそうでしたので、観客をリセットしてある一様な状態に運んでいく、新しい、しかもある程度成功した試みだと思います。
ちなみに「しめ」はシューマンの幻想曲、この矛盾に満ちた曲を見事な設計で統一感を与えていました。
コロナは終わっておらず、放置された医療体制、手抜かれたワクチン摂取励行のツケが明らかになってきました。しかもBA.7.5が主流になってワクチンの効果が薄れる”恐れ“は益々高くなります。Sタンパクの一度に五つの変異は初めてでしょう。政府には秋にBA.5用のワクチンをという声もあるようですが、その頃までBA.5が頑張っていてくれれば良いのですが。とはいえ成田笹沼のブラームスに出掛けて、都響の2軍を相手にほどよい見切りで見事なブラームスを演奏じさせた指揮者の秋山和慶に感嘆した不良老人の戯言です。
大武 和夫
8/17/2022 | 4:50 PM Permalink
東さんと野口さんのコメントにご返事します。(東さんへのご返事は大分遅くなってしまいました。)お二方とも、ありがとうございました。
まず、東さんのご経験、興味深く拝読しました。ええ、緊張が支配する空間に音楽が鳴り響き、演奏終了後の拍手でその緊張が溶ける、という昔ながらのスタイルが私には望ましく思えます。オケ入場時からの拍手はその構造を揺るがすように思えたが故の拙文でした。
野口さんが言われる新しい聴衆のあり方という論点も、とても興味深いですね。吉田翁が何と言われたかというご考察も、共感を持って拝読しました。ガジェブは聴いていませんが、そのの試みは、守旧派である私のような聴き手にも十分受け入れられるというか、よく理解できるものです。形態は異なりますが、晩年のリヒテルがホールを真っ暗にして、譜面立ての譜面にだけ光が当たるような局所照明で弾いたことを思い出しました。守旧派ではありますが、要は演奏家と聴衆の集中に貢献するようなあり方であれば、旧来のしきたり通りでなくても構わないと思う、ということでしょうか。うまくまとまりませんが。
東 賢太郎
8/17/2022 | 6:59 PM Permalink
Noguchiさん、一応緊張と上品に書きましたが、ローマ歌劇場のジョコンダで遭遇したテノールへのブーイングの嵐は壮絶でこっちまで恐怖を感じました。フランクフルトのアルテ・オーパーでは前座のスエーデン人による初演曲にサッカー場なみの満場のブーが浴びせかけられ、なんか気の毒だなあこれまだありなのかと(シャンゼリゼ劇場で春の祭典がきっとこうだったという意味です)。舞台と客席はそういう関係で、お行儀よく鑑賞して拍手して帰るだけという文化は欧州にはないです(最近は知りません)。英国はやや紳士的で米国は日本に近いです、やっぱり借りもの文化なんですね。日本で唯一 “危険”を感じたのは1977年10月18日、東京文化会館のチェリビダッケ本邦初登場のときです(読響)。オケがチューニングして会場が暗くなって、満場が息を殺して静まり返って今か今かと極限の緊張に包まれましたが、なかなか出てこないんです。正確にはわかりませんが1分や2分じゃなかったです何分かは待ったと思いますが聴衆の間に無言の動揺が伝わり始めてハラハラしたのを覚えてます。休憩のロビーでは武満徹さん、吉田秀和さんをお見かけしました。