ファッツィオリの調律
2017 MAY 15 23:23:42 pm by 吉田 康子

公演に先立ち4/22に全員が本番会場でリハーサルを行いました。
おそらくファッツィオリに初対面だった指揮者の田崎瑞博先生は、指揮をしながら耳をすませ、途中で舞台を離れて客席に行ってみてから響きを確認していました。「今までのピアノとは全く違う響きがする。オーケストラの音と綺麗に溶け合う。これでショパンを弾いたらどんなだろう?!またロシアもののコンチェルトの場合は?」と興奮気味に話していました。
今回はファッツィオリの調律を頼みませんでした。費用でなく時間の問題でした。マチネ公演だと午前中がリハーサルで午後2時開演となるために最短でも2時間を要する調律を入れる時間がありません。公共ホールの常で、9時開館という規定を繰り上げるという融通を効かせてくれるところは稀にしかありません。今回の豊洲も典型的なお役所的運営でしたから例外など望めませんでした。しかもGWの最終日とあって、前日にも全く空き無しの状況。「度々調律は行っているから」みたいなホールスタッフの言葉にも半信半疑でしたが、今回はせめて私自身が楽器に慣れるつもりで、本番直前の5/1にホールを借りて個人練習を行いました。
https://sonarmc.com/wordpress/site43/2017/05/02/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%83%e3%83%84%e3%82%a3%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%92%e5%bc%be%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82%e6%ba%80%e5%93%a1%e5%be%a1%e7%a4%bc/
弾いているうちに楽器の様子も実感としてつかめるようになってきました。キーの深さ、遊び、戻り具合、ペダルの効きなど。初対面の人でも時間をかけて話していれば少しずつ親しくなれる、そんな感じに似ているのかもしれません。
ただ一つ、気になることが出てきました。ひとつだけ他の音のように響かない音がありました。

隣のキーは柔らかく適度な残響もあるのに、その音だけコツンとした堅い音しか出ません。無理に鳴らそうとすれば、他との音量もタッチのバランスも崩れてしまいます。しかも、その音は中心から2オクターヴ高い「ド」の音だったんです!今回弾く25番はハ長調です。事もあろうにハ長調の主音のドが不調でした。すぐさまホールスタッフを呼んで直近の調律はいつだったかを確かめました。3日前の4/28だったとのこと、そして私の本番の5/7までに調律の予定は無いとのことでした。その場に居たスタッフは事の重大さを理解していない様子、そして後で立ち寄った東さんもファッツィオリの響きに酔うばかりで、ひとつだけ違う音の事など気に留めていない感じでした。
やっぱり調律を何としても入れるべきだったと後悔してもあとの祭りです。練習の時間が終わってホールを後にしての帰りの電車でさんざん考えた末に、どうしても気持ちが収まらなくて電車を降りた駅からファッツオリの会社、ピアノフォルティに電話をしました。車中でホールの使用状況を検索したら、その日の午後と夜間、翌日の午前がメンテナンスとなっていました。可能なら調律師と一緒に豊洲へ引き返すつもりで、帰宅後でなく駅からの電話でした。「社長のワイルさんを」と言いましたが、海外出張で不在とのこと。電話に出た方が調律師だと言うので、事の次第を詳細に伝えました。もちろん調律を頼んでいないのだから、無理を承知の上だとも言い添えました。「私はアマチュアのピアノ弾きだからプロのようなわけにはいかないけれど、5/7本番には満席に近い多くのお客様が来て下さることになっている。そういう場でピアノ自体に問題があるのはファッツオリのメンツにかかわることではないか?」と。

相手の方は穏やかに話を聞いてくれて「実は明日1時間半しか時間を貰えていないが、メンテナンスで豊洲行く予定をしている。問題の音を完璧に直せる時間が無いかもしれないが、気に留めておく」と約束してくれました。「ただ、それ以降にも使用の予定が入っているようなので、5/7まで良い状態を保てるかどうかは保証の限りではない」とも。「それでも結構です、少しでも良い状態になれば十分有難いです。」と私も返事しました。電話を切り際に、相手の方が「調律師の越智です。」と名乗ってくれました。それを聞いて全員の力が抜けて救われた気持ちになりました。先の記事で紹介した通り、FAZIOLIを興したFAZIOLI氏からも「100万人に一人の耳を持つ天才」と認められショパンコンクールにも派遣されていた調律師の越智 晃氏、当の本人でした。これで私の出来る事は全てやり切って条件は整った、あとは本番まで練習を重ねて臨むばかりだと納得と安堵の思いでした。


そんな事があった6日後の5/7の本番。リハーサルでファッツオリの前に座って一番先にドの音を確かめました。予想通り完璧ではないけれど前回よりかなり良い状態になっていました。越智さんのおかげです。やっぱりちゃんと仕事をしてくれました。
指揮者の田崎先生は、前回同様に指揮台からだけでなく客席や通路を歩いて色々な位置からの響きを聴いていました。「このピアノは通常よりオクターヴの高い音を強調しない調律になっている、このピアノの特性をよく理解している人が調律したようだ。Aの音を442.5でなくて442.3にあわせて」とコンマスに伝えているのを傍で耳にして、その耳の鋭さに改めて感嘆しました。そこで5/1の事の次第と調律師の越智さんについて田崎先生に伝えました。「公共のホールだから、何も知らない人が鍵盤を思い切り引っぱたいてしまって、アクションに狂いが出たのかもしれない」とのこと。「とにかく直して貰えてよかった」と。


今思えば、思い切って電話したこと、しかも翌日に調律に行く前日であったこと、越智さんに直接話せたこと、など絶妙なタイミングと運に恵まれました。自分が一歩踏み出したからこその結果を得られたのだと思います。もちろん本番での演奏もファッツオリの美しい音色と田崎先生の指揮のもと、しっかりとしたオケの皆さんに支えて頂いてのモーツァルト、幸せな時間でした。
Categories:ライヴ・イマジン


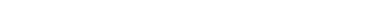
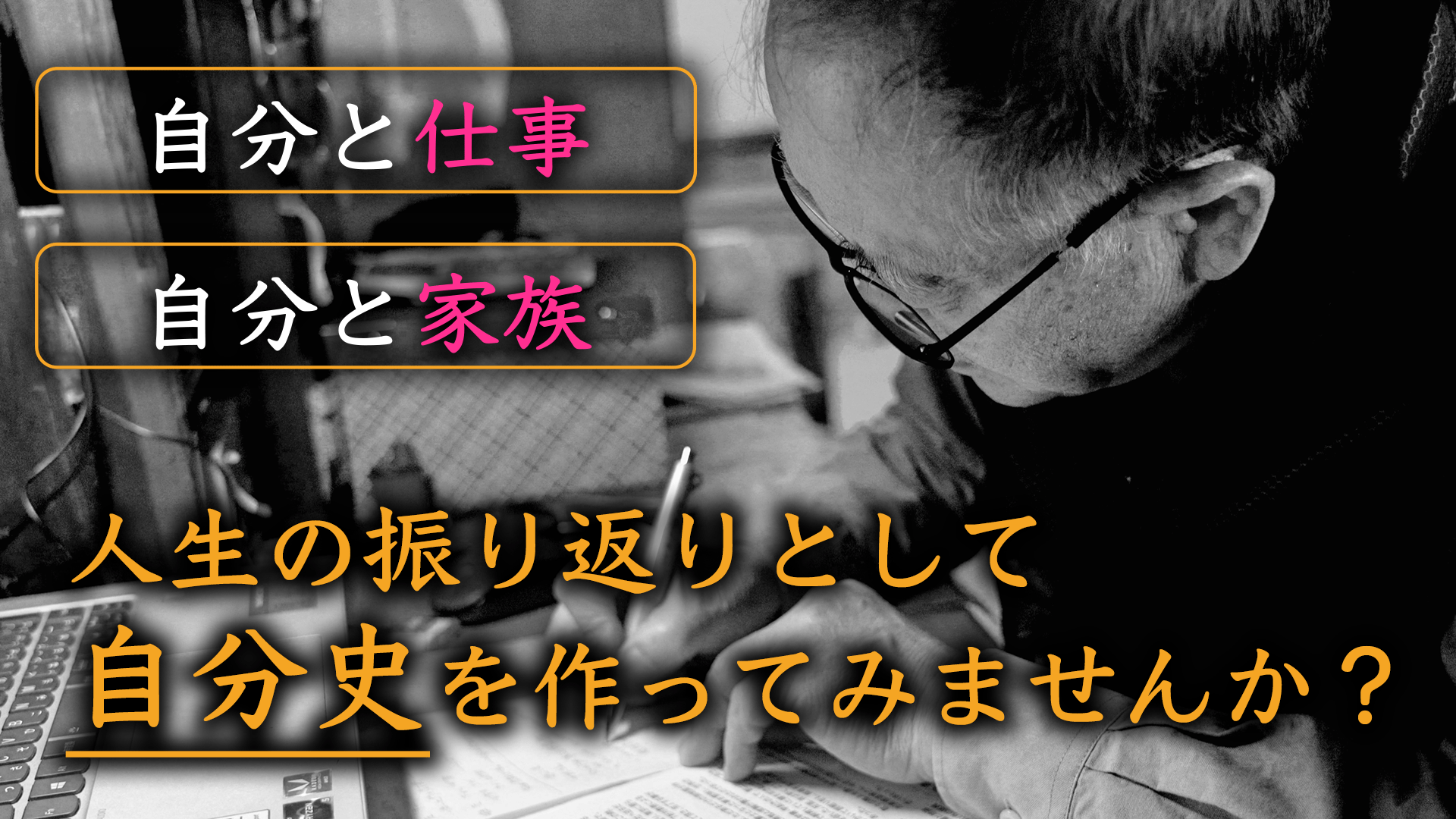


西村 淳
5/16/2017 | 5:32 AM Permalink
これはこれ、当日はバタバタしていて何が起きているか把握できていなかったのですが、なるほどなるほど。出来ることはすべてやる。これが大切ですね。調律あってからこそピアノが生きる、メンテナンスの大切さはどんな楽器も同じですが、もっと理解が必要なことがよくわかりました。田崎先生のアプローチにも驚嘆します。こういう話は「すごいな」って思う反面、私自身の限界も感じてしまいます。
吉田 康子
5/16/2017 | 9:37 AM Permalink
楽器は価値の解る人が使って、メンテナンス出来る人がいてこそ特性が発揮できるものだと思います。単なる「高額商品を買った」という体面や満足感だけでは制作者に申し訳ないくらいです。バブルの名残なのか、何でこんなところに?という場所に、誰も使わない立派なホールやピアノ、パイプオルガンがあったりすると哀しくなります。使う側にもカルチャーが要求されますね。
田崎先生の耳の良さは、評判には聞いていたものの今回改めて実感しました。その場でちょっと聞いただけでファツィオリの特性を即座に理解し、調律師の意図まで感じ取れる人がどれだけいるのか?と。また調弦について田崎先生から442.5と442.3という0.2セントの差に言及されて、すぐに対応出来るコンマスも凄いと思いました。
東 賢太郎
5/16/2017 | 12:29 PM Permalink
音楽家が楽器を大切にするのはわかりますが凄い話ですね。それを耳だけで聞き分ける田崎先生の能力も驚きです。5月1日はその「ド」のキーを僕は2回だけ、モーツァルトとシェラザードで使ってるはずですがまったく気がついてません。響きに酔う以前に間違えないだけで精一杯でしたが(笑)。それにしても越智さんをぎりぎりのタイミングで引き当てて直していただいた吉田さんの交渉力(営業力)、お見事ですね。強運もお持ち合わせのようで僕はそっちに感服です。
吉田 康子
5/17/2017 | 2:21 AM Permalink
さすが25番はハ長調なだけあって「ド」が頻発します。しかもキメの音だったりするので、これが不発だと「どうしてくれるんだ?!」と腹立たしい気持ちになりました。普段なら穏便に事を済ませようと考えるのですが、やはり譲れない事については、自分の意見を主張すべきだと強気モードになります。ファッツオリのピアノフォルティには以前行ったことがあり、社長のワイルさんにも会ったことがあるので、怖いものなしでした。まぁ頑張った甲斐あっての納得の結果が得られて良かったです。
東 賢太郎
5/17/2017 | 8:08 AM Permalink
わかります。右手前方で聴いてましたが粒立ちも和音のバランスも良かったですよ、交渉の甲斐ありましたね。第二楽章の木管との合奏は現代のピアノだといつもどうかなと思う箇所ですが、ブレンドが美しく、フォルテピアノとも違う調和でした。そういう所でファツィオリは新境地を開いたかもしれませんね。25番は第一楽章は典型的なモーツァルトのハ長調で明快、外交的、祝典的でハ短調になっても一時の翳りなのですが、第二楽章以降は違ってデモーニッシュなものが現れてきます。音楽に断層があります。終楽章はイドメネオの軽い主題なのにもうこの時点ではそれで済まず即興的に展開しながらドン・ジョバンニにまで足を踏み入れてます。断層の両側をうまく表現できた良質の素晴らしいモーツァルトでした。
拝聴して、このピアノでさらに聴きたくなったのはシューベルトの後期ソナタです。ちなみにベートーベンはチッコリーニであんまり気に入らなかったのです。あと、一つだけ気になったのはシェラザードで真ん中より2つ下のミのffがほんの僅かですがもの足りない感じが残りました。これでラフマニノフのコンチェルトみたいなのをやったらどうなんでしょう?そこはやはりスタインウェイなのでしょうか。
吉田 康子
5/21/2017 | 1:58 AM Permalink
今回この曲を弾く機会を得て、沢山の事を勉強させて頂きました。今後の糧にしていきたいと思っています。
また録画して頂いた映像を拝見して、正面からと右側からでは聞こえ方がかなり違うことについて驚きでした。ということは、お客様も席の場所によって違う印象だったかもと思いました。これは会場の特性なのか、楽器の持ち味なのか、色々な要素が絡んでくるのでしょう。ピアノの場合は弾き手に楽器選択の幅があるのが、楽しみでもあると思います。
西村 淳
5/21/2017 | 5:33 AM Permalink
動画は私も見せていただきました。さすがに大変クリアーなものでしたが、「音」は明らかに違います。使用マイクが違ったのかもしれません。ただ同じものを使用しても、ちょっとした角度を変えるだけで変わるのも事実だし、ではこの違いをどう生かすか?演奏上ではどうしようもないものですからね。ファッツイオリ、この強烈な個性を持ったピアノはやはり現代っ子、意外にシェーンベルクとか、バルトークとかとの相性がいいのかもしれません。