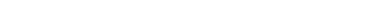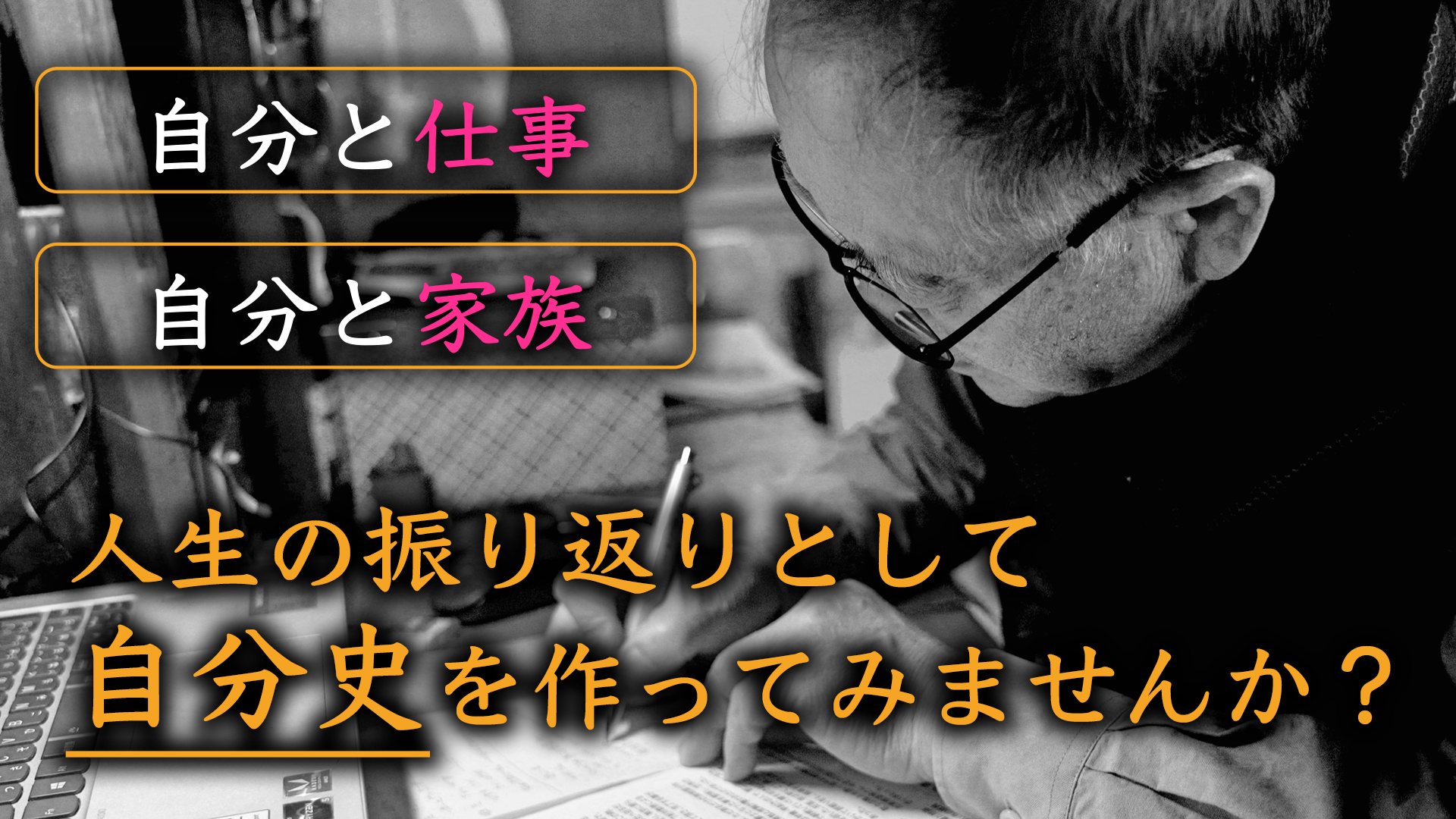「鱒」の五重奏曲(D667)気づき
2024 APR 2 21:21:21 pm by 西村 淳

シューベルト以上に自然の描写をうまくやった作曲家は他にいない。急流、せせらぎ、淀み。水しぶき、川面のきらめき、森に降り注ぐ明るい光などすべてが音楽となって対象のイメージはクリアに導かれる。歌曲を通して言葉を音符にすることには長けていた。でも器楽曲を作るには「形式」に則らなきゃできないし、有名になるには交響曲も書かなきゃならない。さてどうすればよいか。永遠の「さすらい人」は1823年にその答えを見つけたようだ。
【鱒のピアノ五重奏曲】
この曲は有名な割に生で聴く機会が少ないのは通常のピアノ五重奏曲の編成、弦楽四重奏+ピアノではなく、弦楽三重奏+コントラバス+ピアノという編成が大きい。こうすることで弦楽四重奏という完成されたフォーマットより透明度の高い響きが得られる。なにしろ弦楽器は3本、三和音しか出せないわけだから。これに両手ユニゾンでの出番が多いピアノが加わり、ピアノ・デュオのプリモの役割を負わせている。このユニットはシューベルトお得意のピアノ連弾の延長線上にあると言ってもいい。コントラバスをセコンドのベースラインとすることで安定し、形がピタッと決まる。第4楽章の有名なヴァリエーションでは各楽器それぞれに出番を与えるという奏者にとっても嬉しい構成にしてくれている。
【曲の気づき】
前述のように、ピアノの扱いが独特であることと、内容にいくつもの斬新な試みが行われている。その一つ目は3つの楽章の後半が調性を代えて、前半を再現していることにある。シューベルトは、この方式により、これ以降の大規模な作品を、他の方法よりも労力をかけずに書くことができるようになったとされている。1818年から1823年まで未完成の弦楽四重奏曲D703以外に室内楽作品はパタッと途切れており、逆に「鱒」の五重奏曲(1823年作として)から吹っ切れたように、弦楽四重奏曲「ロザムンデ」D804、「死と乙女」D810、八重奏曲 D803、そして特別な弦楽五重奏曲 D956に至る名曲が誕生している。それまではこんなものじゃ恥ずかしくて世に出せない、と作曲途中で中断したり、投げ出してしまったものが数多くあったのにシューベルト様式の確立はベートーヴェンの束縛から逃れることができた。
二つ目は第一楽章の再現部が主調のイ長調ではなく、ニ長調になっていることが挙げられる。このアプローチは以前の作品としてはモーツァルトのピアノ・ソナタハ長調K545に存在し、ベートーヴェンの作品では例外として、弦楽四重奏曲第15番イ短調Op.132にあるのみ。こうすることで主題はベートーヴェンが完成したガッチリした巌のような構成から柔和な微笑みに姿を変える。しかもシューベルトは聴き手に意識させぬ目まぐるしい転調により目的を達成する。
第二楽章は第1テーマが♭一つのヘ長調で始まって24小節目から第2テーマが♯3つのとても遠い嬰へ短調に転調する。この間でシューベルトは転調に5小節を使っていてその真ん中の小節はナポリの六と呼ばれる1小節を嵌め込む。基本、西洋音楽は4小節をひと固まりとするため、この小節が無くても成立するがより柔らかい響きを滑り込ませることで自然に第2テーマが導かれる。
最終楽章の冒頭のドミナントのEのオクターヴはピアノ・ソナタハ長調「グラン・デュオ」D812や第21番変ロ長調 D960の終楽章を予感させるもので、毅然と鳴らすべきだろう。その後のロンドの主題との対比と、目まぐるしい転調は自然に行われやはりそれを意識させない。この楽章は展開部を持たないソナタ形式として捉えることもできるようだが、Hのオクターヴが再現部に屹立する。巧みな和声の組合で反復性は感じ取れず、最後に主調、イ長調に帰納する。
シューベルトが終生、頭を垂れていた大ベートーヴェンが”Es muss sein!”(かくあるべし)と弦楽四重奏曲第16番Op.135 に書き込んだ。逆にシューベルトからは”Muss es sein?”(そうでなければならないのか?)と素晴らしい切り返しが聞こえるようだ。英雄の時代は終わりを告げ、表題に「幻想」とか「さすらい」など、まだ見ぬものへの憧れを込めここにロマン派芸術が花開いた。
Categories:未分類