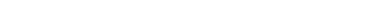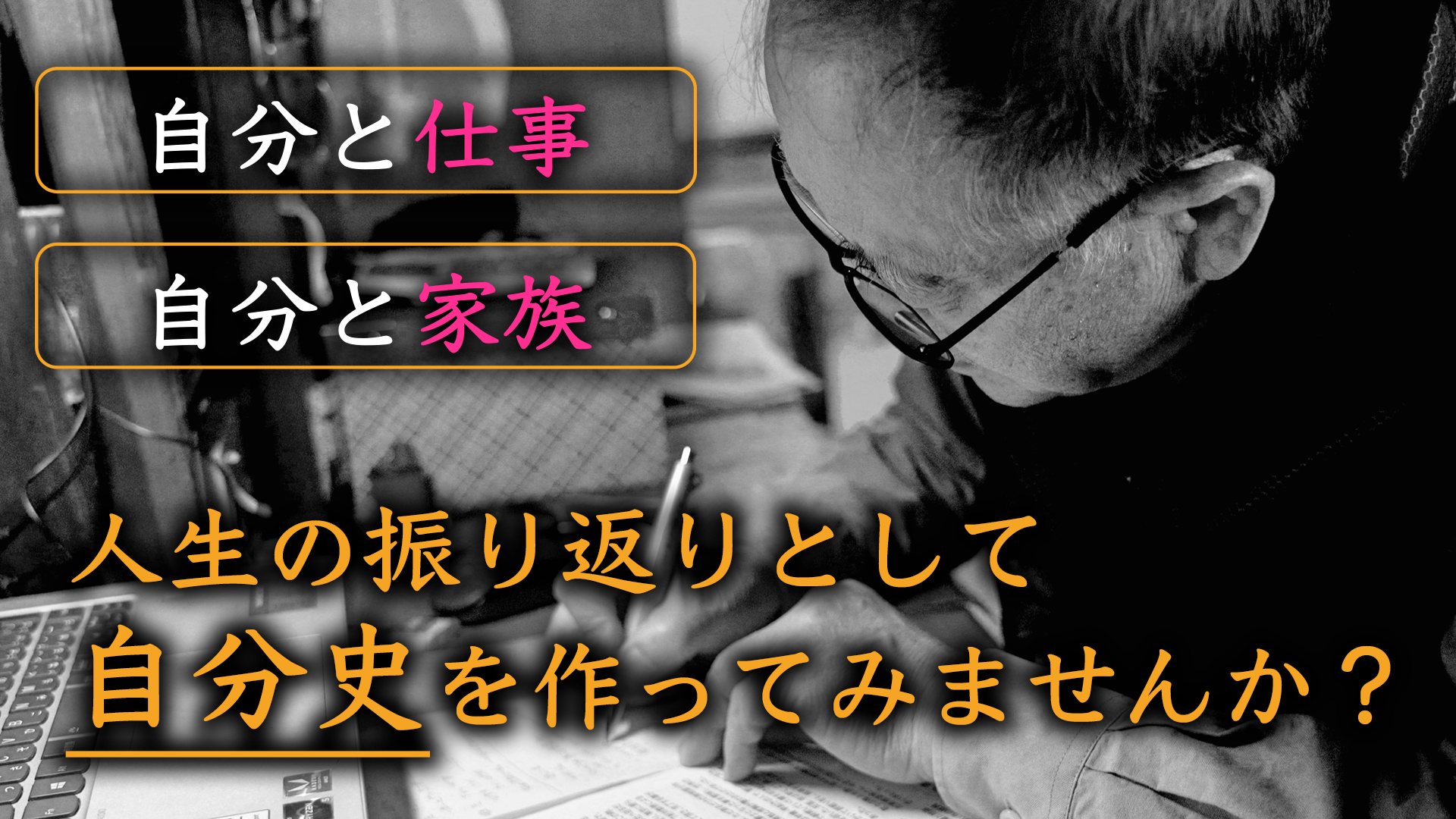アンコールやるの?
2021 OCT 5 20:20:19 pm by 西村 淳

ようやく街に楽器を携えて歩いている人たちが戻ってきた。このまま忌まわしコロナが収束に向かってくれるなら一気に音楽も息を吹き返すだろう。まだまだ音楽は死んでなんかいない。
このところライヴ・イマジンではアンコールをやらない、というかやれないでいる。この会を始めた時から常にアンコールまで含めたプログラミングを工夫していたし、実際、アンコールでは出演者全員が舞台に再度立てるように、ということを試みていた。要は○○ちゃんが出ているから・・というスタイルの上にあったわけだが、やれない理由は出演者よりもプログラムの一貫性に重きを置くようになってきたことが大きい。
アンコールを含めたプログラミングの成功例として「ライヴ・イマジン46」を挙げる。このプログラムは曲の持つ意味と出演者のPRの両面を生かしたものである。この時のアンコールはソプラノの髙山美帆さんに再登場を願い、リヒャルト・シュトラウスの「明日!:Morgen!」を前半のピアノ伴奏とは別にヴァイオリンの前奏が泣かせるピアノ五重奏編曲の別ヴァージョンで企画。時節柄コロナの終息を願い、明日につなぐという願いを込めて。この美しい歌曲は大変良い評価をいただいた。
【ライヴ・イマジン46 プログラム】
:2020年12月27日 豊洲シビックセンターホール
リヒャルト・ワーグナー(1813~1883)
■ 楽劇「トリスタンとイゾルデ」より前奏曲と愛の死(弦楽四重奏版:コーエン・シェンク編曲)
リヒャルト・シュトラウス(1864~1949)
■ 歌曲
・ セレナーデ Op.17-2 Stänchen
・ 献呈 Op.10-1 Zueignung
・ 夜に Op.10-3 Die Nacht
・ 若い魔女の歌 Op.39-2 Junghexenlied
・ 明日! Op.27-4 Morgen!
セザール・フランク(1822~1890)
■ ピアノ五重奏曲 ヘ短調
では、本来アンコールはどうあるべきなのか?アマチュア、プロの違いはお客様からお金を頂いているかどうか。人の心は弱い。お金が絡んでしまうと、「NO」は演奏者の側からはなかなか言えなくなる。“アンコールは是非「ラ・カンパネラを!」”そう、この決定権は奏者というよりはプロデューサーにある。
ウィーン・フィルが来日すると、必ずヨハン・シュトラウスの「美しく青きドナウ」をアンコールにやっていた。皆が待ち望んでいるものだし、それがベートーヴェンのあとであってもウィーン・フィルの名刺代わり。無論、指揮者が望んでいたとは思えないが。一方、奏者も大物になると口を挟めなくなることもあるようで、キーシンは興が乗ると10曲以上1時間を超えるアンコールをするし、ルドルフ・ゼルキンはバッハの「ゴルトベルク変奏曲」を全部弾いたとか。一方、偏屈な人もいて、アファナシエフやリヒテルは上手く演奏できなかったからそれをもう一度なんてこともあるようだ。もしかするともっと下手になるかもしれない。だったら3回目をやるのか?阿呆な奴だと思う。
いつもお世話になっている田崎瑞博先生の古典四重奏団はアンコールはやらない。どうして?と尋ねると全身全霊を込めた演奏の後は、その響き、「想い」を持って帰ってほしいからと。これは目が覚めた発言だった。アンコールが一貫性のプログラミングの延長線上に置かれたものであればさらに「想い」は強く届けられるかもしれないが、「想い」を打ち消してしまっては何にもならず、企画者の腕の見せ所である。
日日是楽日
2021 AUG 11 17:17:24 pm by 西村 淳

2021年3月31日をもってサラリーマン人生が終わった。最後の五年間は鉄鋼関連の会社だった。しばらくリモートワークだったのですんなりと新しい環境になじむことができたが、同じように家にいると言っても仕事をしているのとしていないのは天と地ほども違う。
小さい頃から協調性のない奴(と言われていた)だったがそれを第一に求められる社会で30年余り。そんな中にいてもやはり同調性なんか全くなかったし、すべて自分で判断して結論を導いてきた、というかそうしかならなかった。とにかく会社という小さな世界の中での歓びは仕事の達成感であり、それが世の中のためになるという自負があってのこと。これがあったからこそじっと我慢も出来た。その一方で手柄は横取りされるわ、出る杭はめり込むほど打たれるわ・・止めておこう、愚痴ったところできりがない。
最近は如実に足腰の衰えは感じられ、時々思考が止まっていることがわかる。外見上はごまかせても歳相応というべきものは絶対にある。つまらぬ努力はせずに自然を受け止めよう。爺は突然やってくるらしいからそれまでにやるべきことをやっておこう。
チェロの練習も日頃やれなかった基礎練習を再開。指ならべ、スケールと音程確認。今になってその大切さを思い知る。
そういえばライヴ・イマジン47のヴァインベルクのピアノ五重奏曲の練習だって平日昼間にみんな集まってできるようになったのは、私の足の鎖が解かれてからだ。1日24時間のうち12時間働いて、7時間睡眠。残り5時間で飯を食い、風呂に入り、資料原稿を探りながらなんとか練習時間をひねり出す。これほどの時間制約の中でよくライヴ・イマジンを継続できたと思う。
一方、家にいることが多くなって半径500m圏内でしか生活していない。当然他人との接点もなくなるし近視眼的にモノの値段に敏感になったりする。お、水が2Lで75円。買いだな~んちゃって。行動半径が狭くなった分、本を読み、歴史を語り、はたと膝を打つ。知らなかったことばかり・・そう、今からだって遅くはない。
「知らなくてはならないことを、知らないで過ごしてしまうような勇気のない人間に、わたしはなりたくありません」いかんいかん、気が短くなってテレビに向かって文句を言うガミガミ爺さんにならないように自戒すべし。
さて、秋も立ったことだし昔から気になっていた漱石の「自転車日記」でも読もう。
静けさの中から (14) 脳細胞
2021 MAY 19 20:20:09 pm by 西村 淳

☘(スーザン):頭の中で音楽を想像している時と、実際に音楽家が音を出しているのを聴いている時。どちらの場合もまったく同じ脳細胞が働いているのだという。
おもしろい。必ずしもピアノの前に座っていなくても、有効な練習ができる、ということにつながるではないか。躍起になって楽器を弾くばかりでなく、頭の中で想像をすることで学ぶという方法は、現代の音楽教育にもっと取り入れられるべきではないかと思う。最近、音楽学生や、音楽家たちは、RSI(反復運動過多損傷)と呼ばれる身体の痛みに悩まされている人が多い。頭で考えている時にも実際の音を聴くのと同じ作用があるのなら、黙って楽譜を見ているだけで、たくさんの勉強ができるはずだ。
私の知り合いにも、黙って楽譜を見つめることで、大いなる喜びを得る人たちが実際にいる。彼らは楽譜やスコアをじっと見ているだけで、音を想像することが出来、まるで音楽会で生の音楽を聴いているかのように感じるらしい。ケンブリッジ大学時代の先生、フィリップ・ラドクリフ教授もそのひとりだった。彼は生演奏の音楽会を聴きに行かない。業を煮やした学生が、やっとの思いで教授を引っ張り出しても彼が感じるのは頭の中でなっていた音楽との比較と再確認だけだった。
実際の音楽を聴いている時と頭の中で音を相応している時。どちらも確かに同じ脳細胞が働いているのかもしれないが生演奏は脳細胞以外に、体全体を刺激する。そして体全体がそれに応える。決定的な違いがある。
?(私):ギーゼキングの伝説的な話を思い浮かべたが、天才と比べることは無意味。私の場合は、室内楽のスコアがあっても入るタイミング、ほかの人がやっていることの確認、和音の確認などの作業であって、スコアがそのまま頭の中で音楽として鳴る、というような才能は埋もれたままだ。確かに慣れると響きとして頭の中では鳴っているようだが、全曲を適切なテンポで読み‥聴き続ける・・ことはできないし、ましては初見であればお手上げだ。ヴィオラ記号は変換する訓練が必要だけど、他のことも訓練で行けるなら勉強法の一つとしては認めなければならない。ピアニストやヴァイオリニストは過度な練習で「局所的ジストニア」を発症する人も多い。レオン・フライシャーやゲイリー・グラフマンもその活動を中断された。その悲劇的な状況が少しでも救われるなら。
スコアをカバンに入れて持ち歩き、出張の新幹線の中で見ていた時、名古屋から隣に座った紳士が音楽関係の人だったことがあり、もしやその黄色い本はオイレンブルクのスコアではありませんか?と来たことがあった。ブラームスのピアノ四重奏曲だったが、話の内容はあまりよくは覚えていない。でも音楽談義で東京までがあっという間だったことを想い出す。
ヴァインベルク覚書
2021 MAY 12 21:21:39 pm by 西村 淳

ヴァインベルクという作曲家については未だに日本では馴染みの薄いものだ。この20年ほどの間にすでに欧米ではヴァインベルク・ルネサンスが花開き、17曲ある弦楽四重奏曲のツィクルスがダネル四重奏団によって世界中の主要都市(台北でも!)で行われているしオペラ「パサジェルカ」は舞台上にアウシュヴィッツ収容所が出現することで話題になっている。(NHK・BSで放映されたようだが残念ながら見逃している)
国内では交響曲 第12番 作品114「ショスタコーヴィチの思い出に」を下野竜也指揮・NHK交響楽団が2019年に取り上げたものくらいしか見当たらない。世界の潮流をスルーしているのは我がニッポンくらいか。
そんなヴァインベルク・ルネッサンスを味わいたいとピアノ五重奏曲を6月5日(土)に豊洲文化センターで採り上げる。アマチュアの新交響楽団が芥川也寸志の指揮でショスタコーヴィチの第4交響曲を世界初演から25年(!)後、1986年に国内初演を行ったように、ピアノ五重奏曲ももしかするとアマチュアによる日本初演の栄誉が与えられるかもしれない。
ヴァインベルクについてはまだ書いたものが少なくD.Fanningの「Miecztslaw Weinberg: In Search of Freedom」が唯一のものである。唯、Amazonで70,000円以上もするのでちょっと躊躇してしまう。この他には断片的にショスタコーヴィチの関連図書やCDのライナーノーツ、ダネル四重奏団が来日した時のインタヴュー記事があるくらい。1980版のGROVEの音楽事典にも記載はない。
そうは言ってもコンサートのプログラムには何かを載せなければならないので、拾い読みしたものを整理しておくのも悪くないだろう。
ヴァインベルクが無名だった理由は、第二次大戦前、多くのユダヤ人音楽家が西に逃れたのに反しヴァインベルクは東へ向かったことで、ソヴィエトが解体する前の鉄のカーテンと冷戦による情報伝播の遮断が最大要因と見る。当時、東へ逃避したユダヤ人がどれくらいいたのかは不明ながら、少なくとも彼等にとってロシア支配地域は多くの同朋が住む場所だった。結果として身に危険が及ぶほどのことがあったにせよ、ソ連国内では多くの賞賛を得てしばしば演奏される作曲家の一人としてかなりの成功をおさめることができた。周囲にはコーガン、ロストロポーヴィチ、ギレリス、コンドラシン、ボロディン四重奏団などの超一流の音楽家がいたし、彼らが積極的にその作品を演奏し録音したことは西側に逃避した連中より音楽的にはよほど恵まれた環境だった。レコードは昔、神保町にあった新世界レコード社の棚で見かけたような気もする。そして何よりこの人にはショスタコーヴィチとの厚い友情がある。2台ピアノでよく遊び(ショスタコーヴィチの交響曲第10番は二人で演奏した録音もある)お互いに多くの音楽的な剽窃を楽しんでいるのである。
ミチェスワフの父シュムドはモルドバの首都キシナウでのポグロムにより父・祖父を失い彼が生まれる10年前にワルシャワにやって来てイーディッシュ劇場でのヴァイオリニスト、指揮者として生計を立てていた。当時300万人を超える欧州最大のユダヤ人口を抱えていたポーランドはワイマール文化の爛熟期においてその牽引をしていたに違いなく、クルト・ヴァイルのキャバレー・ソングなどはアメリカに持ち込まれボードビルやミュージカルとなって大衆化していった。
父の音楽活動はミチェスワフに最初の実践的な経験をだけでなく伝統的なユダヤ音楽を植え付けた。当時カロル・シマノフスキが指導していたワルシャワ音楽院での8年間は音楽理論のみならず、Tutcqynskiの下で示した際立ったピアノの腕はレオポルド・ゴドフスキ、イグナーツ・フリードマン、さらにイグナーツ・パデレフスキに続く輝かしい伝統に加わり、ヴィルティオーゾの道も拓けていた。
ところが第二次世界大戦の勃発は約束された未来を覆し、ヒトラーの機甲師団がポーランドを蹂躙する直前、ヴァインベルクは1939年にワルシャワを徒歩で発ち東に500km離れた白ロシア共和国のミンスクに逃避、さらに1941年6月、「独ソ不可侵条約」を破棄したドイツ軍がソ連になだれ込むと、モスクワ経由の列車で3200km離れたウズベキスタンのタシュケントに逃げ込んだ。タシュケントでは幸いオペラ劇場で職を見つけたが、シベリヤ抑留者が建設に参加させられたナヴォイ劇場はまだこの時には完成していない。その後、ショスタコーヴィチの援助により1943年からモスクワに在住し、1996年に亡くなる迄、この地に留まった。ショスタコーヴィチはヴァインベルクの才能を最大限の賛辞を惜しまず自分と同レベルの作曲家と認めていた。彼がモスクワに到着した時にはすでにショスタコーヴィチは作曲家としての名声を確立し第8交響曲にとりかかっており、1943年のピアノ五重奏曲はスターリン賞を受賞していた。
ヴァインベルク:『ショスタコーヴィチは新しい音楽を紹介し、12歳の年齢差とその名声に係わらず先生と生徒というよりは寧ろ平等に接してくれました。彼はモスクワの同じブロックにあるアパートに住んでいて、定期的に顔を合わせ互いの作品を2台ピアノのためにアレンジして演奏しました。』この言葉を裏付けるように、ショスタコーヴィチの交響曲第10番の二台ピアノ版の録音と、「アレクサンダー・ブロックの詩による7つのロマンス」Op.127を病気療養中の作曲者に乞われ初演、1967年10月23日モスクワ音楽院大ホールでのヴィシネフスカヤ(ソプラノ)、オイストラフ、ロストロポーヴィチとの共演も録音が遺されている。またショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲第10番は茶目っ気たっぷりにその数を競い、ヴァインベルクの数字を追い越した記念として彼に献呈されていてショスタコーヴィチの微笑ましい一面を伝える。
1948年のジダーノフ批判により作品のいくつかがショスタコーヴィチやプロコフィエフの同様、演奏禁止リストに載ったとき、作曲家同盟に属さず、フリーランスの作曲家として活動していた彼の経済状態は悪化する。イデオロギー、文化、科学の責任を持つジダーノフはコスモポリタニズムと形式主義の特徴を有し特にユダヤ人の芸術家や思想家によって作られ、西側の音楽的発展と関連した作品の消去を目的としたキャンペーンを開始した。それらに代わって、ジダーノフが望んだ作品は容易に大衆に溶け込み、ソヴィエトの栄光を輝かせる作品だったが、ヴァインベルクはその命令に従わなかったし、自身の音楽について以下のように発言している。
『私の作品は戦争に関連しています。ただこれは私が意図したものではなく、私や家族の悲劇的な運命によるものなのです。私たちの生きた時代に人類に降りかかった恐怖、戦争について書くということがモラルの責任を果たすことと考えています。』
同年、ショスタコーヴィチの交響曲第8番が批判された時、彼を擁護した義父・ミホエルスがKGBに暗殺された。1953年の初頭にはスターリンの反ユダヤ主義による医師団陰謀による破壊活動が流布され、ヴァインベルクは2月7日にとうとう逮捕されてしまう。ショスタコーヴィチは内務大臣ベリヤへ働きかけ、妻は自身の逮捕を予測し彼に子供の養育を託すメモを準備したがここで幸運が舞い込む。3月5日のスターリンの突然の死。捕らえられていた人々は解放され、逮捕前の名誉が回復された。
巨大な作品群はあらゆるジャンルに亘っている。歌劇「パサジェルカ」は何とアウシュヴィッツ強制収容所がその舞台だし、「レクエイム」には日本の原爆歌人・深川宗俊の作品が使われている。何と、私たち日本人ですら忘れかけていたものを、遠く離れた地で想いを寄せてくれた人がいることに素直に感動する。全体像を知るためには多くの作品と接しなければならないが、ピアノ五重奏曲の他にはベートーヴェンと同じように生涯にわたり書かれた弦楽四重奏曲から手始めに聴き始めている。
音楽の特徴として抒情性が挙げられる。時々気味が悪いほどショスタコーヴィチの作曲技法に近いことが指摘されるが表現方法は驚くほど新鮮。稀に内容が人の受容を越えた感覚を持つこともある一方、ポーランド、モルドバなどの民謡を積極的に採り上げている。この辺りの個人的見解はまだまだ書けるレベルにはないので別の機会に譲ろうと思う。
クローン病との長い闘いの後、ロシア正教に改宗し1996年に亡くなった。
アンサンブル・フランのコンサート
2021 FEB 8 21:21:18 pm by 西村 淳

演奏行為は自己表現の一つの手段だとするなら、オーケストラの団員として弾くのははどうしても窮屈である。なぜなら指揮者という絶対的な権力者への忠誠を求められるから。私はあまりオーケストラの活動が得意ではない。その理由は自分でやることは自分で決めたい、この一点に集約される。すべての責任は自分で負う、というやり方。アブナイのは独りよがりになりがちでよく言っても孤高の人、悪く言えば奇人変人となる。究極はバッハの無伴奏チェロ組曲だけを弾いて一生を終えることなのかもしれないが、まさに奇人変人。自分で決めたくても私はそこまではなれない軟弱な人なのでなんとか浮世に居場所を確保できているようだ。
前置きが長くなったが、第一生命ホール(晴海トリトンスクエア)で行われた「アンサンブル・フラン」の演奏会を聴いた。

この団体はアマチュア合奏団の中ではトップクラスの実力を持ち、特にこのコンサートではライヴ・イマジンに参加しているメンバーが3人も弾いているし、高名な指揮者が振っている。プログラムは以下の通り。
指揮・高関健
曲目
・ ブリテン:フランク・ブリッジの主題による変奏曲 Op.10
・ ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第12番 変ホ長調 Op.127(弦楽合奏版)
・ アンコール:ベートーヴェン 弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 Op.130 ~ 第五楽章 カヴァティーナ
メイン・ディッシュは勿論Op.127。ライヴ・イマジン45で演奏した記憶はまだ生々しく、弦楽合奏でやるとどんな演奏になるのかワクワク感もあった。プログラムによればヘンレ版のパート譜にピアニストのマレイ・ペライアがコントラバス譜を付加したとのこと。なぜペライアがこの曲に拘ったかは不明ながら弦楽合奏とするにはこのバスパートの補強は必須で実際その効果はコントラバスは2名であってもとても力強いものがあった。逆にこれ無しに弦楽合奏は無理じゃないかとも感じた。
一方、指揮者がいることで、冒頭に書いた通り弦楽四重奏としての自主性、自在性が希薄になる面は否めない。バーンスタインがウィーン・フィルを指揮した第14番の録音があるがここでも同じような印象、つまり違う音楽になっている。得るものもあり、失うものもある。この形態を良しとするのは指揮者がいることで見通しの良くなる「大フーガ」くらいかもしれない。
ポルカのリズム
2021 FEB 1 15:15:53 pm by 西村 淳

ショスタコーヴィチの「弦楽四重奏のための2つの小品」の2曲目は「ポルカ」。原曲はバレエ「黄金時代」にあるポルカを1931年10月31日から翌日にかけて1晩で完成された作品とある。ワクワクするようなそして幾分かの諧謔を伴った大好きな曲だ。次のライヴ・イマジン47のプログラムに載せているが参考にボロディン四重奏団の録音を聴いてみた。極めるとはこのことなり、何と素晴らしい演奏だろう。完全に脱帽だが、ひとつ気になったことがあった。2拍子でB♭(G線)-F(C線)と四分音符でチェロが動くところがある。何のことはないが、弦の太さのせいかFのほうが強く聞こえる。意識がそこになければ自然にこうなるだろう。この四重奏団でチェロを弾いているベルリンスキー、ちょっと苦い思い出もあり、「おい爺さん、ちゃんとやれよ」、とその時は思ったし、拍節感のないやつだなあ、1拍目をちゃんと強く弾こうぜとも。
ところがちょっと引っかかる所もあってポルカのリズムを調べてみようと思い立ち、ヨハン・シュトラウスの「アンネン・ポルカ」や「トリッチ・トラッチ・ポルカ」を聴いてみた。あらら、ここでは当たり前のように通常の1拍目ではなく2拍目に重きを置いて弾いているではないか。ああ、浅はかだったのは爺さんじゃなくて、こっちのほうだったようだ。深く恥じ入った次第。
ついでに私の年代ならだれでも知っている左卜全の「老人と子供のポルカ」。「♪ズビズバー、ズビズバー、やめてけれ、やめてけれ、ゲバゲバー」(太字;強め)とやってるやってる。逆にこうじゃないとポルカは踊れないんだろう。
教訓:ポルカの基本リズムパターンはタタ・タンだ!
だったらPolkadots and Moonbeamsって素敵なスタンダードナンバーはどうだろう?アハハ、これは水玉模様のことでポルカとは何の関係もないけれど、英語を学び始めたころはポルカだけが耳についていただけの話。
そんなわけで少なくともここに関しては正しいポルカをお披露目できそうだ。無知とは怖いもので疑問を持たなかったら知らぬうちに大恥をかいてしまう。くわばらくわばら。そう、漢字の読み方だって同じだ。「東海林さだお」は「とうかいりん」じゃなくて「しょうじ」でした。爺さん疑ってごめんなさい、私も天国に行ったら謝らせてね。
因みにこの爺さん、ヴァレンティン・ベルリンスキーは1943年、モスクワ音楽院のドゥビンスキ―を中心にした生徒たちで結成した四重奏団のチェロ奏者・ロストロポーヴィッチをわずか数週間で追い出しボロディン四重奏団に半世紀以上に亘り居座った伝説のツワモノだ。
メトロノームが壊れた
2021 JAN 21 7:07:58 am by 西村 淳

メトロノームは練習に欠かせない機器である。ゆっくりしたテンポで始め、要求されるテンポまで徐々にアップしたり、三連符の感覚(これがけっこう難しい・・)を是正したり有用な使い途はそれぞれだ。
長年使用していたSEIKO製のメトロノームを不注意で落とし壊れてしまった。最近では「トリスタンとイゾルデ」の「愛の死」の練習に一役買っていたのに。
これでも動かないわけではないけれど、ボリュームにガリが出てきたりしていたので、そろそろ替え時か。これは譜面台にうまく付けられるので同じ後継機を検索。

メトロノームは1816年にオーストリアのヨハン・ネポムク・メルツェルが発明した。時代は資本主義=産業革命の真っただ中。時間管理は音楽にも持ち込まれてしまった。
メトロノーム速度を最初に譜面に書き込んだのはベートーヴェンだった。「彼の記入した速度は現実の演奏と乖離している、彼のメトロノームは狂っていたからだ」などと言う人もいるようだ。博物館の写真を見ると背の高いピラミッドのような形をしていて今売られているものとよく似ている。振り子の原理は同じだし印象としてはそれほど精度が悪いようにも思えない。
1817年12月、メトロノーム発明の翌年にベートーヴェンは「ライプツィッヒ音楽新聞」にそれまで出版されていた8つの交響曲のメトロノーム速度を発表している。ちょうど後期の作品を作り始めるころにあたるが、少なくとも私の知る限りにおいてはこれ以降の作品にメトロノーム記号は付加されていない。だが難聴が進み「会話帳」を使い始めたのもこのこの頃だし、頭で考えたテンポは実際よりも早いとされているようなので「現実の演奏との乖離」についてはそのように理解している。ただこのメトロノームの速度を尊重したとされているルネ・レイボヴィッツの交響曲の録音は演奏が可能であることを証明しているし、違和感は感じない。
時がたち、バルトークやストラヴィンスキーの音楽の時間軸はぶれてはいけない物になっていく。クルレンツィスがストラヴィンスキーのリハーサルをやっている動画では何とメトロノームを盛大に鳴らしながらやっているではないか!?これには驚いた。
さらにそんなメトロノームを「楽器」として扱ったのがジョルジ・リゲティの「ポエム・サンフォニック」(100台のメトロノームのための)。ゼンマイ式のメトロノームならいざ知らず電子式のものを使ったら永久に止まることがなく、無間地獄に落ちてしまいそうだ。少なくともこれは私の音楽ではないし、リゲティは弦楽四重奏曲第1番あたりであればチャレンジしたいとさえ思っていたがこれってユーモアなのか?もし何かを意図して本気だったらシェーンベルクの実験なんかままごとだ。
(翌日)善は急げ、有用有急、新しいのを買った!!楽しくするためにクロじゃなくスカイブルーを選択。環境が変わるとあれもこれもやってみたくなるのが凡人。ちょっと上手くなった気分で。
聖夜
2020 DEC 16 21:21:44 pm by 西村 淳

ルートヴィッヒ・ファン・ベートーヴェンの250回目の誕生日。
もし個人的にお祝いするなら「エロイカ」以外には考えられず、最近入手したアダム・フィッシャー/デンマーク・室内管弦楽団の演奏を聴く。そうそうここはいい、でもここはちょっと賛同したくないなあ、などとまるで批評家になったような聴き方をしているのに気づく。もっとも演奏は設計図に基づいて家を建てているようなものだ。いい職人がいればいい物が出来上がるし、腕が悪いとどこかギシギシしたり隙間があったり。でも住めるならそれでいいじゃないか、十分、と最近は思うようになった。
今年は念願の一つ、「弦楽四重奏曲第12番」を演奏することができた。いろいろありすぎて逆にいい思い出を作れたし、考えてやっているうちに間違いなくウデも数ステップアップしたのを実感できた。正しい姿勢で弾けるようになった。スポーツ選手と一緒でルービンシュタインの背筋の伸びた姿を思い浮かべるまでもなく一流の奏者の演奏している姿は美しい。おかげで肩の痛み、腰の痛みからすら解放されたし、痛めていた左指も80%以上快復した。弓の持ち方、中指の使い方をちょっと変えただけで劇的に音が変わった。
そうそう、エロイカ。いい感じで第4楽章の途中を数人の弦楽器奏者が室内楽的にやっている。これは16型のオケじゃちょっとむりだろうな・・お、ボナパルトがアルプス越えをしている姿も見えるぞ。シンフォニア・エロイカ。私にとっての最高の交響曲だ。
誕生日おめでとう、ルートヴィッヒ君!心からお祝いを。ちょっと鬱陶しいこともある奴だけどわが心、最大の友よ!
「歓びの歌」が始まるぞ
2020 DEC 2 13:13:02 pm by 西村 淳

クラシックのコンサートもようやく9月19日から全席使用可能と政府のお墨付きがでてから「消えた」ライヴが活気を取り戻しつつあるようだ。何しろウィーン・フィルまでやってくるわけで年が明けると堰を切ったように外タレの来日公演が始まる。11月には武蔵野市民文化会館でアンドレイ・ガヴリーロフの復活リサイタルもあった。(こんな所でやること自体、彼の今の立ち位置なのかもしれないけれど、日本在住とか)
コロンビア・アーティスツ・マネージメントが破産しようと、ポストコロナがどうなろうと、とにかくこのスタイルを死守し取り戻すのに必死である。
でも今年はさすがに第九はやらないだろう、と思いきや、「ぶらあぼ」の12月号を見て驚いた。やるんです!それも関東圏で42回(東京34回、神奈川7回、埼玉1回)も!因みに関西では6回、北海道2回、中部、四国、九州なし。
第九交響曲を年末に、という年中行事はいつのころからあるのか知らないし、これが日本だけのことなのかも知らない。まして聴きに行ったこともなかった。
それにしても第九の歌詞と現実の乖離。どうやって内容と違和感のないように実現するのか、見もの聴きもの。第九の合唱は「抱き合え、幾百万の人々よ!このキスを全世界に!」と叫ぶ(歌う)。コロナの時代にこのスローガンは真逆なはずだし、三蜜そのものの合唱団の間には衝立を用意し、マスクやフェイスシールドをして歌うのだろうか?6日には大阪城ホールで「サントリー1万人の第九」と銘打って実行するようだ。国技館での5000人の第九だって唖然としていたのにその倍。嬉しい?
会社って何だろう?
2020 SEP 7 16:16:28 pm by 西村 淳

仕事をして、給料をもらうところ。
遅刻をしないこと、くい打ちされぬよう目立たないようにすること、ゴマをする相手を間違えないこと、何より「お言葉ですが」とは決して言わないこと。これが出来れば立派な会社人だ。
今の社会のシステムでは会社はなくてはならないもので、「いい会社」=「安定した大きな会社」となっている。そこに入るためには「いい学校」を出ることが必要で多くの親は子の安寧を願ってこの道を辿ってほしいと思っている。子供は何の疑問も持たずに試験で人よりもいい点数を取ることを目標にする。結果めでたく有名な「いい会社」に入れ、そこが一部上場だったりすると最高だ。
子供の頃から面白くもない暗記に(なんと数学だって暗記することで点数がとれるのだ!)大きな疑問を感じていたし、中学、高校と進むにつれて益々その疑問符の数は増していった。こうなると学業は低空飛行をし、「まともに評価されない」=「いい会社に入れない」のかもしれないという漠然とした不安を抱えながら墜落寸前。幸い丸の内の一角に本社を構える企業の一つに入社できたものの、文系の頭構造だったのに親の定めた既定路線の理系に進んだツケは大きく、自分には別の世界があり違った仕事があるはずだと考えているようなことがあったし、結果冴えない会社人として飯を食い続けた。そんな生業でもゴールまで残り僅かのところまで来ている。
何気なく手に取った沢木耕太郎の「鼠たちの祭り」(新潮文庫)にちょっと刺激的なことが書いてあった。会社は給料をもらうばかりじゃない、新たな視点がとても新鮮だった。
伝説の相場師、坂崎喜内人の話:
『人ばかりでなく企業だって変わらない、小さい会社はバタバタつぶれているのに、大証券会社が傾くと国が手助けする。資本主義においては、企業利潤の正当性はひとつに危険負担の対価という発想で説明される。あらゆる企業はリスクを減らそうとするが、しかしどうしても残るリスクがある。だからこそ、起業家精神というものが称揚され、利潤が認められる。
リスク背負わざるもの、儲けるべからず。だが、巨大だと言うだけの理由でそのわずかの危険も取り除かれるとしたら、資本主義における起業家精神の死を意味する。
リスクのない社会は確かに安定した社会である。しかし同時に息苦しい社会でもある。「我々青年を囲繞する空気は、今やもう少しも流動しなくなった」(「時代閉塞の現状」)と書いたのは60年以上前の石川啄木である。もっとも「時代閉塞」でなかった時代が果たしていつあったのか、というシニカルな反問も成り立つのだが、少なくともリスクのない安定した社会では、「囲繞する空気」が流動しないことだけは確実だ。空気はよどみ、深いニヒリズムが、ガスのようにひろがる。』
「リスクを背負うから利潤が認められる」、なるほどそういうものだったんだ。経済学ではこんなことを勉強しているのかしら。この文章が発表されて50年経った日本は息苦しさが加速、おまけに最近はマスクまでしてしまっている。