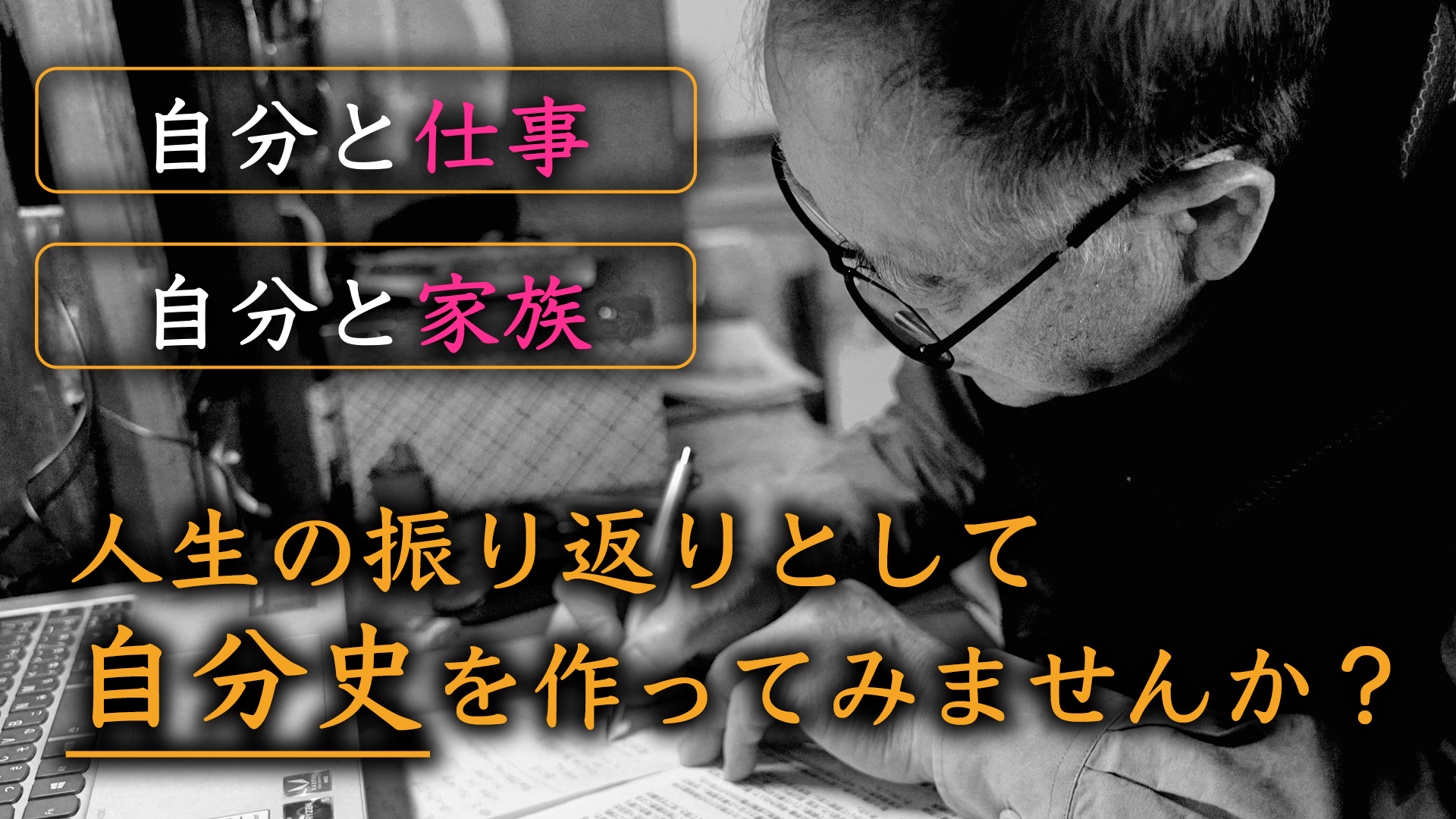真冬の花火
2026 JAN 22 0:00:20 am by 西 牟呂雄

喜寿庵の芝生に薄っすらと白い雪、冷え込む外気、流れる川。
キーンと張りつめた暗闇の中で、震えながら花火を灯した。
夏の日の喧騒の中に置いて行かれた花火を見つけたからだ。
この寒いのにどうかと思ったが、止めることができなかった。
丁寧に地面にろうそくを立て火を点ける。風が強く炎はユラユラゆれてしばしば消えた。また点ける。
そして花火を翳すのだが、山火事が起きるほど空気は乾燥しているのにすぐには弾けてくれない。
アッ、点いた!
漆黒の闇に溶けていく白煙。見つめていれば眩い色彩。
一本目の炎で次を、また次を、また次を。
車が通る。この寒いのに何をやってるんだ、とばかりにスピードを落とす。
歩く人は火事が心配なのか迷惑そう。不思議そうに見るのは僕の出で立のせいか、スキー・ウェアだからね。
花火は無くなった。目にはあの火花が残っていて、その目で空を見上げても残像が明るすぎて星など見えない。
しばらくして星がチカチカ見えるようになる頃は、あの色合いは既に朧気である。
ことばとしての『はなび』という音は更に歪んでいて、ついさっきワタシが見たものとは部妙に違う。
そしてそれを『花火』という文字にしてしまえば、もはやその面影さえ失っている。
そういう『ことば』とか『文字』では表せないサムシングは、冬の闇の中には満ち満ちている。
普段は気付きもしないのだが、季節に不似合いな花火の光と煙を浴びると姿を現してくる。
この世は欺瞞・悪意・劣情に溢れかえり、昼間は大地を覆いつくしている。
人はそれぞれ大いに語り、見聞きし、しばしわかったようなつもりになっている。
しかし、冬の夕刻を過ぎたあたりからそれら邪悪の気は姿を消し、人と大地はようやく落ち着きを取り戻す。
自分はと言えば、この冷気の中で風にあたればしばしば震えている。
するとわたしの頭の中が肉体から飛び出してしまい、それもお臍のあたりからスルリと抜け出してしまい、体で言えば目の高さあたりで浮いたまま360度を見渡して、次に天空を見上げてうっとりとしている。
その内に私(ワタシという意識)がどんどん広がった。そして空の星を映すほどの大きな鏡になって、次の瞬間には私が空から自分のいた所を映している意識に陥り、とうとう地球全体を包む鏡の球体になってしまった。
ひときわ黄金色に輝いてるメタリックな人影、あれがわたしの抜け殻に違いない。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:春夏秋冬不思議譚 四季編