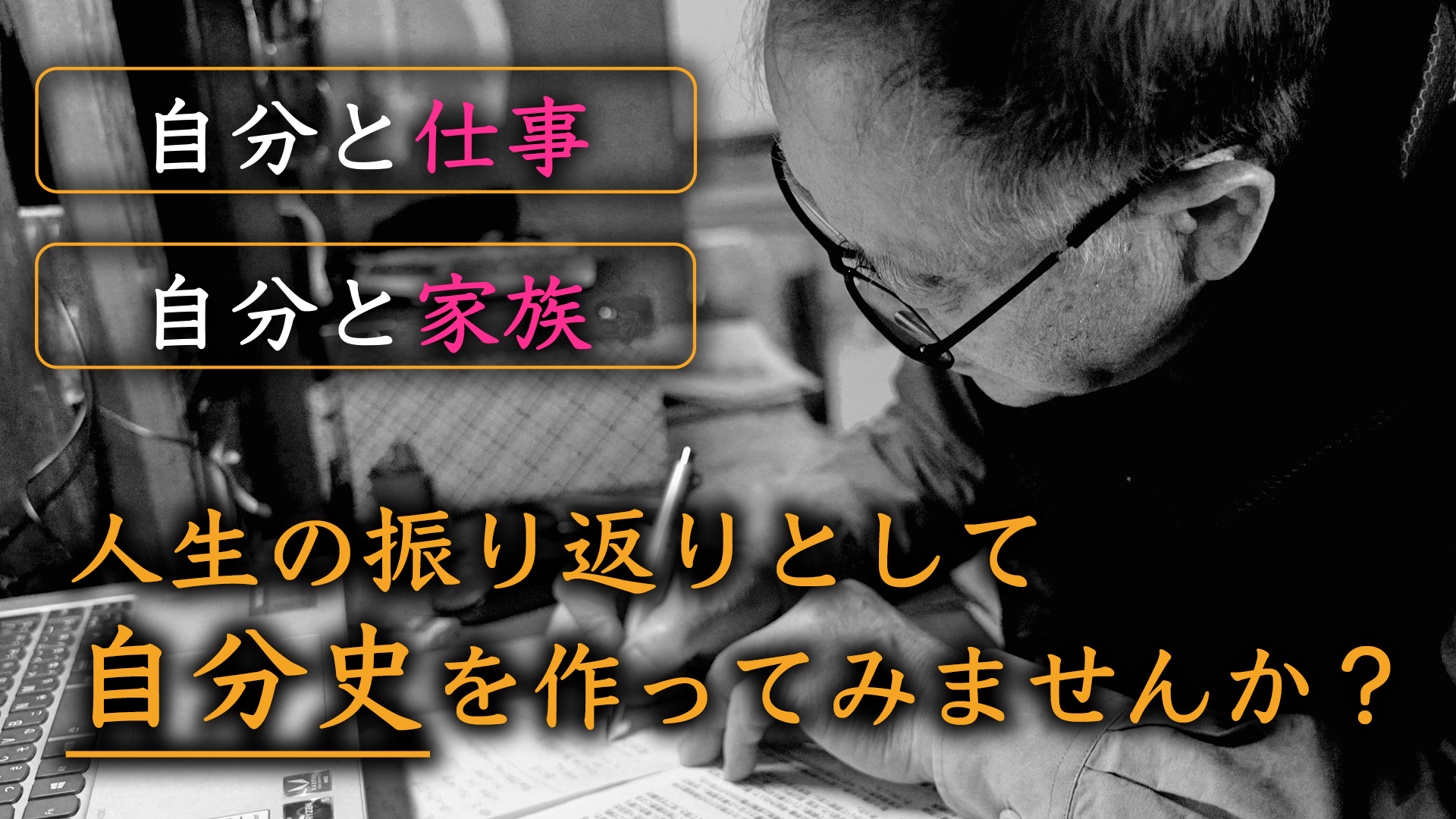鮮烈 馬庭念流 Ⅲ
2018 AUG 14 20:20:15 pm by 西 牟呂雄

Y県のY湖畔の合宿所にやってきた。年度が変わっていないので先輩はいないし新入生はまだだから新三年生と新二年生だけの春合宿である。
新主将のクロカワは最初から殺気立っていた。バラベに負けたんだから無理も無いが、朝練のランニングや素振りからして常軌を逸したノルマを言い出して師範に止められた。
そして掛り稽古ではクロカワとシバタとタカヤマが3人がかりでバラベに襲い掛かった。ところが例の田吾作スタイルのバラベは打ち込みを受けまくり全てしのいだ。そしてたまに打ち返すのは首筋とか内股といったあたり、そして鍔迫り合いに執着する。通常の剣道の試合では反則になりかねない悪い太刀筋なのは相変わらずだ。
僕も近くでやっていたからズッと見た訳ではないが、稽古が終わって面を外した時はむしろクロカワ達の方が息が上がっている。
練習が終わって飯を食べたりする時や自由時間になると、クロカワ達は固まっていて僕はなぜか全く空気を読めないバラベと一緒にいることになってしまう。すっかり反主流派扱いされて実に居心地がよろしくない。
ところが翌日になるとこの前の決闘でバラベにコテンパンにやられたレギュラーのイシイとノムラがこちらの方に加わってきた。新二年生の中にもこちらの陣営にスリ寄ってくる者が出てきてなんだか部が真っ二つに割れたようになってしまった。主将クロカワは表情が強張ってきて、ますます(特に)僕に対して刺々しくなってくる。
三日目になると体力をすり減らして腕も足も感覚が鈍ってきて全員ヨロヨロ状態、食欲も落ちて皆の機嫌は悪~くなっていった。そして・・・・。
四日目の晩の自由時間にクロカワがバラベと僕を呼び出した。師範の個室に来い、と申し入れてきたのだ。一体何が起こるのか、僕達の陣営は後からゾロゾロとついてくると、主流派の方も固まってやってきて師範の部屋の前で鉢合わせした。
『よし、行こう』
とクロカワが促すので三人で中に入った。中にはハナフサ師範(大学法学部教授)がいた。
『オッ、来たな。まあ座れ』
僕たちは神妙に正座した。
『クロカワ。部内の雰囲気はよくないな』
『ザスッ。バラベの反則まがいの太刀筋が問題になって部が割れています』
『エッ、反則なの。どこが』
『フム。バラベ、君は確かフランスでお父さんと型の稽古ばかりしていたそうだな』
『ザスッ』
『実戦剣術の馬庭念流だ。君が首筋を撃ったり内股を祓うのは動脈を狙っていることになる。真剣だったら出血多量で即死するわけだ』
当のバラベも含めて一同ギョッとした。
『バラベ。気づかずに流派を継承しているのはしょうがないとして、馬庭念流正統は他流試合は厳禁しているのを知らないだろう』
『ザスッ知りませんでした』
『君は確かに強い。だが他の部員が見たことも無い型に驚いていることもある。そしてここはE高校剣道部で馬庭念流の道場じゃない。バラベは型を直すところから始めなければここにはいられないよ』
『・・・・ザ・・ス』
合宿残りの二日間、師範はバラベに付きっ切りの別メニューで足捌きから教え直した。なぜかバラベは嬉々として稽古に励んでいて、チョット前の高校部活動としてはどうかと思われる派閥対立のようなものはなくなった。まるで漫画のような終わりかたで合宿は平和に打ち上げられたのだった。
異変は新学期初日に発覚した。三年進級時のクラス替えでわかったのだがバラベは落ちていて再度二年生をやることになっているではないか。
クロカワが僕のところに来た。
『オイ、バラベは落ちたらしいな』
『うん。ま~オレの見る限り相当な数の赤点みたいだったけどまさか落ちるとは思わなかった』
『それがさ、こんなもの持ってきたんだ。直接会えなかったけど机の上に置いてあった』
見れば退部届ではないか。
『何だよこれ。せっかく型も直されて部の方もいい雰囲気になりかけたところなのに』
『オレもそう思ってた矢先だ。びっくりしたよ』
『とにかく会いに行こうぜ』
『うん。落ちると元のクラスだからな』
この前までいたクラスに行くとちょうど奴が教室を出るところで鉢合わせたがアッと同時に声を上げた。奴はフェンシングの面を持って歩いていた。
『おい、どうしたんだ』
奴はやや恥ずかしそうに言った。
『いや面目ない。リドブル・・・って落ちちゃった。試験の問題だって半分はわかんないからね』
『それは、まぁ、がんばれよ、って退部するのか』
『だって下級生だったのと一緒にされるのやだもん』
『もったいないだろう。合宿がんばったじゃないか。それでその面は何のまねだ』
『あっこれ。フェンシングのマスクだよ』
『そんなもん持ってまさかフェンシングをやるのか』
『うん。隣の席のイシカワ君に誘われてさ。フェンシング部は今四人しかいなくて二年生はイシカワ君だけなんだって』
『だってお前フランスにいたときもブシドゥしかやってないだろ。できんのかよ』
『それがイシカワ君は僕たちの決闘を見てたらしいよ。それでね、僕の足の捌きと後ろへの跳び方がフェンシングに向いてるそうだよ。掛け声もルールもフランス語なんだよ』
『あのガニ股の構えがか』
『だけどあんなにやりたがってた「みんなでブシドゥ」はどうなったんだ』
『それが「フェンシングにもキシドウがある」って言うんだよ。似たようなもんなんだって。でも「キシドウ」ってどう書くのか知ってる?』
『・・・・』
『・・・・まっがんばれよ。それより少し漢字勉強しろ。また落ちたら退学になるぞ』
クロカワはあんなに嫌っていたのにやけに寂しそうだった。
だが学年も部活も違ってしまってすっかりバラベとも話さなくなった。しかし風の便りに、秋のインターハイの県大会で決勝まで行ったらしい。やはり奴はその手の達人だったのだろうか。
そして僕たちはそのままE学園の大学に進学するのだが、どうやら奴はまた落第して姿を消してしまい音信も途絶えてしまった。日本にはいないかもしれない。
僕とクロカワは大学部でも体育会剣道部に入り、道場ではこっそりと時々あの変な構えで『イ~~~ヤ~~~!』とやっている。そしてクロカワはいつも懐かしそうに言うのだ。
『風みたいな奴だったね』
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
鮮烈 馬庭念流 Ⅱ
2018 AUG 12 16:16:05 pm by 西 牟呂雄

「ついにサンクになったよ!」
年が明けてすぐだ。昼休みに食堂でうどんを食べていたところにバラベがやってきて突然言った。3人の同じクラスの仲間を連れていた。
「何の話だ。サンク?」
「フランス語の五だよ。ブシドゥドウコウカイに入ってくれるメンバーが集った」
「ナニッ、マジか」
一緒にいるのは何でそんな話に乗って来るのかと疑わしいのばかりだ。抜群の秀才だが偏屈で有名なミギタ、オタクで運動神経ゼロのヤマダ、不良というか落ちこぼれというかケンカばかりしているという噂のシマダ。何だってこんなややこしい奴らを・・・、それに4人じゃないか。
「教務課にドウコウカイの申請ももうしてきた。防具は授業で使うやつを使用する許可もくれた」
「待てよ、一人足りないだろう」
「お前を入れて5人いるじゃないか」
「バカ、オレは剣道部の現役だぞ」
「おいイデイ、幸い剣道場が使用できるのが月に一度、第三週の土曜の5時からだけらしいんだぜ。ヒマだろ」
シマダがニヤニヤしながら言い放つ。こんな不良チンピラがどうした心境の変化だ。なんだかんだいって練習に付き合わされることになった。
そして一回目の練習日なるものが来てしまった。土曜だから午前中で授業が終わる。ミギタは図書室で勉強しヤマダとシマダはお茶を飲みに校外に出て僕はスマホで時間を潰して、剣道場で先に着替えた。するとそこにラグビーのヘッドギアのようなものを幾つも抱えたバラベとオッサンがやって来た。奴は体操着でオッサンはゴルフ・ウェアのようなカジュアルでやけに目付きが鋭い。同時に他の三人も体操着で現れた。
「やあ。これ僕のパパ」
「ボンジュール。皆さんようこそ。ブシドゥをやりたいと息子から聞いたんで初めの型だけは教えに来たよ」
それからバラベ親子が向き合う様に残りの僕達も向き合って型の稽古が始まった。使うのはなんと木刀だ。例によって剣道とは程遠いヘッピリ腰ガニ股の田吾作スタイルで剣先を右側に。ところがそこからオッサンの方が歌舞伎の発声のような甲高い『イ~ヤァ~(だんだん上がる)』という気合で振り下ろす。えらくゆっくりだが、それをバラベがガッと受け止めて『イイイイイイェェェェイッ』と押し返してもみ合い、離れる。これだけ。仕方なく僕たちもやったところ、驚いた。結構疲れる。
2回目の稽古にはバラベの奴はすっかり師範気取りになってハリキった。『もっと強くなる為』と称して受けをやる方におぶさってギシギシ言うほど体重を預けてくる。こいつはキツかった。不思議な事に他の奴等も余程ヒマなのか休まずに来ていた。しかしこのラグビーのヘッドギアのような面は確かに視界が開けて使い勝手がいいし、竹刀剣道のように打ち合いでなく木刀での型稽古だから、間違って当たったとしても怪我にならないように工夫されている。
と、そこに何故か剣道部の僕の同期が二人ドタドタと入ってきた。何事だ。クロカワとシバタだが、何だか殺気立ってるが。すると来年は主将と言われている二年最強のクロカワがいきなり怒鳴り出した。
「イデイ!お前何やってんだ」
「武士道同好会に付き合ってんだが」
「冗談じゃないぞ。お前だって来年はレギュラーかもしれないのにそんな遊びに付き合ってる場合か」
「練習休んでないからいいだろ、別に」
「こいつだな。お前のクラスのフランス帰りは」
「はい。バラベですが」
「イデイ。こいつがやってるのが何だか分かってんのか。高崎で昔流行った馬庭念流(まにわねんりゅう)とかいう百姓剣法だって師範が言ってたぞ。裏切るつもりか」
「ちょっと待て。裏切るってオレが嘘でもついたのか」
「E高剣道部の伝統と誇りをどこに捨てて来た」
「別に捨てちゃいねえ。そっちこそいきなり何だ」
僕がムッとして啖呵を切ると、ここでケンカ屋のシマダが身を乗り出して来た。
「それでどう落とし前を付けろってんだ。ん?」
しまった。取り返しがつかなくなるぞ。クロカワは剣道も強いが気も強い。
「落とし前?ここは剣道部が仕切ってんだ。そっちでなんとかしろ」
「じゃあブシドゥらしく決闘しようよ」
バッバラベ!ばか!なにをトンチンカンなことを。
「けっとう だとー」
「僕達は5人だから5対5で決着をつけよう」
「オイ、やめろ」
「面白い。やってやろうじゃないか。いつだ」
・・・・シマダが言っちゃった。
結局次の週に5×5で試合をすることに・・・・。意外だったのはバラベ本人が『マニワネンリュウって何のことだい』と真顔で聞いたことだ。
いいかげん星取戦にするか勝ち抜き戦にするか(なにしろこっちはシロート)しまいには『木刀を使わせろ』だの審判をだれにするかと散々モメ、5対5の先鋒・次鋒・ 中堅・副将・大将で勝ち抜き形式となった。星取り形式では全く歯が立たないことが明らかだからだ。
つい決闘の日が来た。もう下期もあと一週間という二月の終わりだった。
当日は内密に立ち会うということで同好会の練習日だったが、何故か僕達の決闘騒ぎを聞きつけた同じ道場を使う他の部の連中には噂が漏れたらしく、10人くらいの野次馬まで集ってしまった。
こちらは絶対に勝てない下手のミギタとヤマダを副将・大将にして僕とバラベでイチかバチかの勝負をかけるしかない。ところがシマダがどうしても初めに出ると言い張って先鋒になり次峰がバラベ、中堅が僕の作戦を立てた。僕で食い止められなければ終わる。バラベが厳かに言うではないか。
「いいかい。僕らがやってるブシドゥは絶対にこっちからは仕掛けないのが基本だ。そして向こうが動いたらガチーッと受けて遮二無二押し返す。これを繰り返していれば負けない、いいね」
「ザスッ」
なぜかみんなその気になって返事が揃って笑えた。
無論剣道部の方も声出しをやっていた。
そして試合が始まると、何と驚いたことにクロカワが先鋒ではないか。こちらの作戦を見抜いたのか、一人で5人抜くつもりなのは明らかだ。せめて僕が先鋒に回るべきだった。
始まった。するとシマダは初っ端に例の歌舞伎調の『イ~ヤ~~!』と発した。クロカワは別に驚きもせず間合いを計っている。あいつは剣先をクイックイッとやる癖があってタイミングを計って小手を狙う。
ところが我らのナントカ流の構えは手首の位置が低く、小手が打ちにくいようでなかなか攻撃できない。ふーむ、実戦的なんだな。クロカワは堪らず上段に変えた。そして動かないシマダの竹刀を一度叩いたと思うと『メーン!』と飛び込んだ。
シマダは素早く反応してガシッと受けると『イ~ヤ~~!』と突進した。クロカワは慌てたようで竹刀を戻さずそのまま押され、体当たりを受け止めた格好で揉み合った。道場の隅まで押しやられたのだが踏み止まった刹那、シマダの抜群の運動神経が反応して『エ~イっ』の気合とともに抜き胴が入ったのだ。
『胴一本』
審判役でわざわざ立ち会ってくれた三年生、オカダさんの旗が上がった。剣道部側の動揺が手に取るように伝わってきた。クロカワは呆気にとられたようで、面を外すとボーッとしている。
次峰シバタ。やはりビックリしたようで突っ込んでこないでしきりに剣先を絡ませては後ずさりを繰り返す。シマダはミョーに堂々としてきて、田吾作の構えがもっと低くなった。シバタは実にやりにくそうに右へ右へと廻りだす。とっ突如シマダが例の掛け声と共に突進、シバタを場外に押し出した。完全にビビッている。もう一度押し合いになるとカンが働いたかまるでチャンバラみたいに打ちまくって『イ~ヤ~~!』と面を取ってしまった!剣道部はザワつき出した。
中堅タカヤマ。シマダは調子に乗って最初から気合を発しながらマヌケにもジリジリと攻めに出て、あんなに寄ったら危ないぞ、と思った途端、あっさり面を取られた。
さて、師匠格のつもりのバラベが前へ進む。シマダよりも低いまるで地を這うような感じで動かない。そこでタカヤマがさっきの要領で打ち込んで来た瞬間に、バッと後ろに飛んで見せた。練習でもやっていない動きで驚いた。そして間をおかずにトンッと飛燕の動きで簡単に小手を撃った。無論『イ~ヤ~~!』の抑揚とともにだ。つっ強い。
残りの剣道部イシイとノムラのときは低い構えから背筋を伸ばしての上段と練習のときには見せたことのない変幻自在の動きで、時に脛や肘まで打って翻弄しなにもさせずに面を決めた。
僕の出番はなくなって剣道部に勝ったのだ。
えらいことになった。このことはまさか負けまいと審判を引き受けてくれた3年のオカダさんからキャプテンのシイノさんの耳に入ったようで大問題となった。練習日に集合がかかり緊急ミーティングが開かれた。
1年から3年までの25人が全員集合しハナフサ師範までがドッカリと腰を据えて目をつぶって腕組みををしていた。えらいことになってしまった。シイノさんが激しく言った。
「クロカワ。伝統あるE高校の節度を汚すような他流試合まがいのことを勝手にやってしかも負けたとはどういうことだ。おまけにオレや師範に断りも無くオカダが審判までやっているとは何事か」
まずいな、本当に怒ってる。これは・・。
「イデイ!どんな気分だ。所属する剣道部の名誉を踏みにじる勝ちを得た気分は!言ってみろ」
突然こっちに振られた。これはボソボソ言い訳しないほうがいいかな・・。
「シイノ。そう怒るな」
ハナフサ師範が低い声で言った。
「E高校剣道部が対抗試合ならともかく、他流試合まがいをしでかしたことは言語道断。しかもオカダ、相手二人に五人とも抜かれるとは剣道部始まって以来の恥辱だ。どの程度の負けか」
オカダさんは自分が悪いわけでもないのにすっかりしょげ返ってボソボソ言った。
「相手は守りを固めて動かないのです。そこでこちらが仕掛けるとガッと受けられそのまま押され負けしました」
「諸君。剣道とは何か。武士の魂を鍛える真剣勝負だろう。私の見たところあのバラベという生徒は上州馬庭念流の正真正銘の達人だ。ここは負けて学ぶしかあるまい。クロカワ。膝を屈してでも入部してもらえ」
「ザッス!ト・コ・ト・ン学びます」
大変だ。クロカワの目がヤバい。このト・コ・ト・ンは部員の間では相撲部屋でいう『かわいがってやれ』或いは某大学アメフト部の『潰せ』の意味なのだ。このままでは僕も相当にやられるに違いない。
それにしてもあのバラベが達人だったとは違和感がある。ただのアホにしか見えないのだが。そして剣道部への入部を認める旨を伝えるのは僕の役目になった。
翌日さっそくブシドゥ同好会を招集した。
「大変なことになった。ハナフサ師範が僕達の入部を認めた」
「セ・ボン!みんな、剣道部員になれるぞ」
喜んでいるのはバラベだけ。当り前だ。他の3人はもともと部活動なんかやる気はないのに物珍しさでつきあっていただけだ。
後期が終わり先輩たちはもう卒業する。といっても大半が大学部に内部進学する。ただし大学でも剣道をやるのは2~3人が常だ。
僕達は三年に進級するが、問題はその前に春合宿があるのだ。
つづく
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
鮮烈 馬庭念流 Ⅰ
2018 AUG 10 20:20:19 pm by 西 牟呂雄

2学期が始まった。それはそれは熱かった夏休みをノンベンダラリと何もせずに過ごし(剣道部の合宿には行ったが)やれやれと登校してきたクラスの連中は同じバカ面をしていた。
担任の山田先生が一人の生徒を連れて教室に来た。
「おはよう。みんな夏休みはよく遊びよく学んだだろうな。今学期から一人転校生をわが組でお迎えすることになった。紹介する、バラベ・ユズル君だ」
「バラベです。皆さんより一つ年上なんですが、宜しく御願いします」
「バラベ君は暫く外国にいたんで日本の高校のことは良くわかってないから、みんなで分からん事は教えてやってくれ。それで席なんだが、いい機会だから全体の席替えをする。先生もあんまりアイデアがないから一学期の時と同じに要望があれば聞く。後はくじ引きだ」
山田先生の方針はクラス全体の座席表を回して好きな所に自分の名前を書き込む。競合する場合は二人ならばじゃんけんで、3人以上はアミダくじで決める、という民主的なのか公平なのかよく分からない方法だった。
一見簡単なようだが、誰それと隣になりたいとかアイツの隣はいやだという奴が出てくるとモメて、更にじゃんけんで負けたりアミダが外れた奴がどこを選ぶか、が始まると結構な手間だった。大体良くできる真面目な連中が黒板が見やすいとか言って前の方に固まり、バカ共は後ろに溜まる。E高校は名前の通りE大の付属男子校で、試験偏差値はそれなりなのだがエスカレーター式に余程の落ちこぼれでもなければE大に行ける。理系の看板学部を目指す連中がやたらと勉強するのは浪人することができないからだが、だらけきった奴等は遊び放題に遊んでいた。
「じゃあ表を回すから各自記入してあしたの朝決めよう。今日のところはバラベ君には一番後ろの廊下側で授業を受けてもらう。一時間目まで解散」
この隣に机が入っていたのはその為か。ってオレの隣じゃないか。変な奴だったらいやだな。まっあしたまでならいいか。
そのバラベというのが隣に座って1時間目は物理だ。やけに色の白い奴だ。
やはり異分子が混じるとクラスは緊張するのか。こいつはできるのかバカなのか、面白いやつかつまらないのか、明るいのか暗いのか、皆の関心は寄せられているようだ。
ところが気が付いたがこのバラベという奴はノートを持ってない。変なメモ紙にゴソゴソ黒板を写したり教科書に直接書き込んでいるみたいだ。
二時間目の世界史もそうだった。
三時間目の英語でもそう。そしてボソボソと英語を喋っている。
たまりかねて休み時間に聞いた。
「バラベ君、ノート書かないのかい」
「うん、ありがとう。持ってないし字が上手く書けないんだよ」
奴は恥ずかしそうにメモ紙を隠したが、何だか印刷されたものの裏を使っているようで詳しく聞くのをはばかられた。真っ直ぐに目が合うと細面の顔立ちをしている。
昼休みになったので僕はお弁当を広げた。半数は校内の大食堂で食べ、半分くらいがクラスに残る。奴はというとリュックの中からガサガサと取り出したのは何と牛乳パックとクロアサンだ。五分くらいで食べ終わってスマホをいじりだした。
「おいおい、学校でスマホは禁止だぞ。持ち物検査で見つかったら一週間取り上げられるんだよ」
「エッ、そうなんですか。知らなかった」
「どこに住んでんの」
「〇◎です」
「へぇ、反対側だね。帰国子女って言ってたけどどこから来たの」
「ブフゴニュフォンセです」
「それって何州なの」
「エッ??」
「ニューヨークの方?それか西海岸?」
「ああ、エッジュニじゃないよ」
「えたじゅに?」
「フランス語で合衆国の事。フランスにいたんです。だから英語はできないんだ」
「フランス!パリにでもいたの?」
「ノン。すごい田舎です。日本語ではブルゴーニュってワインの産地ですよ」
「へー、そこでなにやってたの」
「父さんがワイン造りをずっとやってました。でも独立できなくて日本に帰って来たんです。僕はもっと早く帰りたかったけど」
そういうことか。フランス語は3年生で必修になるがそれまでは役に立たない。
午後の授業が終わって放課後になった。未だによそよそしいクラスの雰囲気の中、バラベは帰り支度をして僕に話しかけてきた。
「一緒に帰ろうよ」
「そいつはダメだ。きょうは剣道部の練習」
「イデイ君剣道部なの。僕も入りたい」
「うーん、どうかなー。ウチは大学の先輩たちが巾をきかせてるから結構キツいよ。やったことあんの?」
「父さんとずっと稽古してたんだ、あっちにいたときに。道具も持ってるんだ」
「ふぅーん。フランスで剣道をねえ。珍しがられたろうなあ」
「まあね。でも近所の奴等が2~3人面白がって一緒にやってた。『ブシドー』って言って」
「わかった。じゃあ練習見に来いよ。主将達にも会わせてやるから」
体育館の横の部室に行くと皆が着替えていた。中学部と大学も一緒だから全体では軽く百人を超える所帯なので、高等部は一応月水金の練習だが今日は20人くらいだった。
うまい具合にシイノ主将とハナフサ師範(大学教授)がいたので引っ張っていった。
「ザッス(部内の伝統的とされる挨拶)。入部希望者を連れて来ました。同じクラスのバラベっす」
「あっあのー、バラベと申します」
「本気か。二年の二学期だぞ。合宿も経験しないでついてこれるのか」
「ザッス。転校生っす」
「ブシドーはやっていました」
「はぁッ、ブシドウってなんだ」
「すっすいません。帰国したばかりでちょっと日本語が・・稽古はしておりましたであります」
「ふーん。何段だ?」
「ナンダン、っですか。わかりませんです」
「わからんって。まあいいや。ちょっと見学してろ。オイッ素振り始めるぞ」
「ザスッ(全員)」
あいつ大丈夫か、と心配しながら列になって蹲踞した。するとバラベも隅っこでチョコンと座っている。正座はできるんだな。
「黙想!・・・・。活目!素振り始め!」「ザスッ(全員)」
エイッエイッエイッエイッエイッエイッ!!!
「切り返ーし」「ザスッ(全員)」
エイッ(パン)エイッ(パン)エイッ(パン)エイッ(パン)エイッ(パン)エイッ(パン)
「打ち込み稽古!」「ザスッ(全員)」
「イデイ、ちょっとこい」「ザスッ」
「せっかく見学に来たんだし経験者ということだからジャージに面・小手付けて地稽古で打ち合ってみたらどうだ」
「ザスッ。おーいバラベ君」
居心地悪そうに座っているバラベに声を掛けた。
「じゃあ体操服になって来いよ。地稽古でもやってみよう」
「あのさ、ボクトゥは使わないの」
「何?ボクトゥって」
「木の刀」
「はあ??そんなもんでやったら骨折するぞ。ほら防具付けて竹刀持って」
「シナイってこれ。ふーん」
コイツ・・・。何をやっていたんだ。
何とかかんとか格好をつけさせて蹲踞も教え向かい合った。
どうも話がかみ合わなくて困ったが竹刀剣道ではなくて型の稽古だけをやっていたらしい。こりゃ打ち合って入部を諦めさせることになるのかと思った。
構えた途端に仰天した。基本がなってない。
剣道で最も戒められるガニ股のような腰の引けた低い構えで、柄を握るポイントを左の脇の方に落とし切っ先は右に流れている。子供のチャンバラごっこのようだ、まさかフランスで父親とやった遊びを剣道だと思い込んでるんじゃないだろうな。
あまりの異様な光景に掛り稽古に移っていたみんなも手を止めてこっちを見始めた。
しかもバラベは全く動かない。しょうがないから小手でも狙ってやるか、とフェイント気味に切っ先を少し上げて見た。それでもうずくまる様にジッとしていた。
「・・・・コテ~ーー!」
と打ち込むと、驚いたことにガバッという感じで後ろに跳んだ。オイオイ、かすりもしない。面でも入れてやるか、上段に変えて間合いをつめた。ところがそれでも同じ構えのままだ。
「オメ~~ン!!」
ワッ、振り下ろすと今度は後ろに飛ぶどころかやや向かってくるようにバシーッと受けられ、そしてそのまままるで下から押し上げるようにググッと迫ってくる。鍔競り合いの格好でジリジリとプレッシャーをかけられた。おいおいおいおい、切っ先が僕の左の面に当たっちまうだろ。
たまらず右側に交わそうとした瞬間、裂帛の気合で左の腕を撃たれた。
「イ~~~ヤ~~~!」
いててて、何なんだこれは。とても一本にならないところを打ち込みやがった。声もやけに抑揚のついたまるで歌舞伎のような変な発声だ。
「それまで!!」
ん?ハナフサ師範が止めたのだ。師範は法学部の教授だが大学体育会剣道部の監督でもある。
「ザッス」
「君、ちょっと」
バラベを呼ぶので一緒についていった。
「君、その型どこで覚えたんだ」
「父さんと稽古してました」
「どこでやってたんだい」
「フランスです」
「ほう!二人でやってたのか」
「まあ、そうです。近所のフランス人の子供もいましたが」
「お父さんの出身は」
「群馬県の高崎です」
「わかった。あのねえ、君の覚えたその型は競技剣道ではない」
「そうなんですか!」
「いつからやってたんだ」
「それはフランスに行った頃からですので10年前くらいです」
「それではもう直らないだろう。但し今の君はとても強いよ。だが学生剣道とはルールが違うんだ。残念ながら剣道部に入っても上達はしない。そのまま君の型を続けた方がいいと思う」
「そ・・・うですか」
それから僕達は練習を続けた後に解散した。バラベは正座したまま最後まで付き合って僕と一緒に帰った。
「どうする。あれは体よく断られたみたいだぞ」
「うん。ルジャポンに来たらブシドゥをやるのが夢だったんだけど覚えた型はダメみたい」
何だよ。えらく悲しそうじゃないか。オレこういうの弱いな。
翌日の席替えでは席を選んで、残りのどうでもいい奴等は巨大なアミダくじであっさりと決まった。バラベはどういう理由かは知らないが最前列の左端に、僕は後ろから二番目の右端になった。
離れてしまったので様子は窺えなかったしそれから暫くは挨拶くらいしか話さなくなった。しかしあいつは全く成績が振るわないのは直ぐにわかった。先生に指名されても答えがトンチンカンすぎる。
フランス語がどの程度なのかは知らないが、英語の読み方は全くダメで他の教科も知れたものだろう。
ある日の昼休みにバラベの奴が『イデイ~』と寄って来た。
「剣道部なんだけどサ、あれはやっぱり断られたのかな」
「そうだろうな」
「残念だなァ、別に邪魔するつもりでもないんだけど」
「一人でそのブシドゥ型をやればいいじゃないか。それだって十分『武士道』だと思うけどね」
「一人じゃつまんないよ。ズッと父さんとやってたからみんなと一緒にやりたかったんだ。それでさ、イデイ、僕と一緒にやってくんないか。教えたげるよ」
「えーっ、オレが教わる?そりゃ無理だよ。今だって週3回の稽古出るのがやっとなんだぜ。第一場所がない。剣道場は中学部や大学部が毎日使うんだから。剣道場を使うなら同好会の申請でもしなけりゃ許可が降りないんだぜ」
「ドウコウカイってナンだい」
「正規の学校を代表するのは体育会所属の『部』だけど、そこまでガチじゃない愛好者が組織して学校に承認を受けるシステムで、5人以上のメンバーと活動実体がなければ認可されない」
「難しいんだね」
つづく
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
2015 サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(還暦編 Ⅲ)
2015 JAN 18 14:14:47 pm by 西 牟呂雄

油壺の日曜も暮れる頃、又オレを打ちのめす事態に陥った。またしても彼女の一言だった。
「ご隠居。明日は月曜ですよね。あたしT文大の講義の日じゃないですか。」
「あー?それが?」
「あたし又乗せてってもらえますか?」
「えっ?」
オレは抜けていたので、ボーっとビールを飲んでいた。ふと目を上げると、彼女だけじゃない、英語屋、イベント屋、物理屋の血走った目が邪悪な光をたたえてこっちを見ている。そのゾッとする気配は悪魔のようだった。
オレは小さい声で『みなさん御家庭があるんじゃないですか。』とか『お嬢チャンさんのお部屋のお掃除は。』とか『お仕事が忙しいのでは。』もっとあからさまに『ボクの自由は。』などと言ってみたが、誰一人振り向いてもくれなかった。かわりに、
「おい、酒が残ると困るからお前もう寝ろ。」
という愛情あふれる声がかかったとき、フーッと気が遠くなった。
月曜の朝焼けの中、東名を突っ走るワン・ボックスの中には、ハンドルを握るオレの他、熟睡しているバカじじいどもと美女がいた。
オレは自由と時間の関係について、必死に考えた。
要するに完全な自由になるには、あらゆる誘惑に耐え、完全な孤独に打ち勝つ、鉄のような意思が不可欠なのではないか。そしてそのような意思を持てるのはごく限られた人間だから、そうではないオレのような人間は多少の不自由にならざるを得ないのではないか。
時間が無限にあれば、人間は自由になれると思ったら大間違いなのだ。時間を無駄なく使うことこそ、自由への近道に違いない。現に、最も時間のあるはずのオレが、色々と制約のあるはずのこいつ等にオレの生活を奪われ、奴隷のような扱いをされ、運転手にされているのが、何よりの証拠だろう。
何とか時間通りT文化大にたどりつくと、ヤマトヨシコは『じゃ、後でオウチに行きます。』と跳ぶよう
にキャンパスを走っていった。
「フアー、なかなか洒落た学校だな。」
「散歩でもしようぜ。」
オレも近くではあるが、中まで入るのは初めてなので、4人でフラフラと迷い込んだ。
授業中なのだろう、人影もまばらな静かな佇まいだった。裏手の学食と思われる建物に近づいたとき、明るいギターやバンジョーの音色と屈託のない歌声が聞こえた。
「オッ、やってるのかな。」
「懐かしいなー、フオークソングだな。」
裏手の、もう山のふもとの当たりの雑木林のところで、4人編成のバンドが何とブラザーズ・フオアの”花はどこに行った”をやっていた。随分古い歌だ。実はオレ達4人は今やっている学生と同じ編成でバンドをやっていた。英語屋がギター、イベント屋がバンジョー、物理屋がフラット・マンドリン、オレがベースだった。曲が終わると思わず拍手した。
「君達随分古い歌やってんだね。」
「恥ずかしいです。僕達ヘタですから。」
「他にどんなのやってるの?」
「いや、レパートリーこれしか無いんです、まだ。」
あれこれ話しているうちにオレ達も同じようなことをやっていたことが話題になり、『じゃ、やってみせてくださいよ。』となってしまった。何しろ45年ぶり、四捨五入で半世紀も前のことだ。それぞれの楽器を手にして音を出してみると何やら怪しい感じだ。
「おい、何ができるか?」
「そりゃー、アレだよ。あれ。」
「あー。アレか。ありゃーさすがに忘れないな。」
ギターの軽快なイントロを英語屋が奏でると、何と一発でそろった。都合千回は演った曲、サンフランシスコ・ベイ・ブルースだ。
”オイラを残して あの娘は行っちゃった 富士山の麓まで とってもイカした 娘だったが”
途中の間奏は物理屋のフラット・マンドリンだが、やはり往年の早弾きは無理なものの、無難にこなした。ヤツは天才だ。エンデイングまでやったところで、全員息が切れた。おまけに指がふやけてしまっているので弦を押さえる方と弾くのと両方とも痛いのなんの。皆もそうらしい、マイッタ。
「皆さんお上手ですねー。」
ここで、オレの悪いクセが出た。
「いやなに、昔はプロで鳴らしたもんさ。オレ達はフジヤマ・マウンテン・ボーイズって言うんだ。」
「へー、知らなかった。プロだったんですか。」
ふと気がつくと、他の奴等の視線が痛かった。
そして、しばらくヨタ話をしているうちに、オレの嘘っぱちが止まらなくなり、学生達は純情なのかバカなのか益々それを信じ込み、オレの山荘に遊びに来ることになり楽器ごと車に8人も乗り込み、ガサガサと移動した。
着いたら着いたで、驚いた顔の学生を尻目に早速雀卓を囲みだした。ところで、昨日の段階で手持ちの現金がオケラになったオレは一度終了を宣言したのだが、彼等はそれを許さずツケを主張した。
学生の目が点になっていた。しかしこの時点からおれは勝ち出したのだ。もうどうでもよいが。
そしてそこへ、講義の終わったヤマトヨシコが帰ってきた。もはや『訊ねてきた』という表現は当たらないだろう。皆も『おー、早かったな。』『メシ、メシ。』とか言っている。同級生の娘の扱いではない。更に学生達の反応は以外なものだった。
「大和先輩!どうしたんですか?」「お知り合いですか?」
「君達こそなにしてるの。ここはあたしのシマよ。」
オレのウチなんだけど。聞くところでは、彼女が師事している大学院の先生の学部ゼミ生のようだ。すなわち彼女が姉貴分らしい。呆気にとられた学生を尻目に『2抜けでしょー。』と麻雀にも加わりポン・チーやり出す。
この日またもやオレは続け、自由を奪われ続けた。
今何曜日なのか分らない。部屋はきれいに片付いている。
「クソッ。」
思わず呟いた。一体何なんだ。やっとの思いでメールチェックをした。バカジジイどもからほぼ同じ内容のメール。読んでみると、とんでもないことがわかった。学生達がやる、チャリテイーのミニ・コンサートのゲストに既に在りもしないフジヤマ・マウンテン・ボーイズが出ることになっていて、いくらなんでも少し練習でもしよう、と勝手な日程がそれぞれ書いてあり、レパートリーに入れたい曲がこれまた勝手に列挙してあり、最後にこう締めくくられていた。
『お前は暇で自由でいいなあ。調整をたのむ。』
ヤマトヨシコは、
『とっても楽しかったです。皆さんとの話を母にしたら、懐かしがって、次ぎの麻雀デスマッチは筑波のうちに来て欲しいそうです。自分もやりたいみたい。ご隠居一番自由なんで日程のこと、幹事お願いします。』
オレは頭に来た。ある、強い怒りとも何ともいいようのない言葉が胸に湧いてきた。それは半世紀前にあいつ等と会ったころオレに芽生えた言葉だった。そうだハッキリ思い出した。あいつ等と会ってオレは自我に目覚め、こう呟いたことがあったのだ。
「こうなったら、もうグレてやる!」
ーおしまいー
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
2015 サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(還暦編 Ⅱ)
2015 JAN 16 20:20:21 pm by 西 牟呂雄

このあたりは、梅雨時は実にきれいだ。セーターを着込む程肌寒くなる。特に朝方、川霧がもやっているところなんかは、思わず一杯やりたくなるくらい幻想的だ。
メールチェックをすると、朝の早い木更津の物理屋から、メールがあった。
『いよう、ご隠居。久しぶりに会おうといっても、皆寄る年波で腰が重い。こっちに来ないか?』
とあった。それもいいな、と仲間に転送した。
2日ほど、スッタモンダしたが、結局次の木曜日に行くことになった。木曜はゴルフの日だが、先日前代未聞のスコアが出てしまってくさっていたので別に惜しくない。例によって、黄昏プレイと称して午後2時頃に行くと、その日1.5ラウンド目という主婦3人組みと回らされた。この人達がうまいのなんの。そして、年は40台だろうがオレのことをオジイサン等と呼ぶのだ。すっかり調子が狂ってショット・パット全てダメだった。聞けば東京から来たそうだ。子供がいいかげん大きくなると、自分より年上はみんなオジイサンかね。
さて、木曜になって、翌日金曜の仕事、洗濯と畑仕事(キュウリ、トマト、枝豆)をチョイチョイとや
って、それじゃ一人旅とばかりに車を出そうとしたら、
「ごめんくださーい。又来ましたー。」
の明るい声。なにい!またあの娘か。
「いい天気だから、チョット寄ったんですけど。」
「えっと、スマン。実は今出かけるところなんだよ。」
「あら残念です。お昼作ろうと思ったんですけど。」
「いやー、そいつは残念だったな。又今度頼むよ。」
「どこまで行くんですか?」
「うん。ちょっと千葉まで。」
「わあー、いいなー。あたしもサボッて一緒に行きたい!いいですかー?今日は講義じゃないんですよ。」
「はあー。・・・・。」
結局一緒にドライブになってしまった。目的地まで、首都圏の渋滞も含め3時間のロングトリップ
だ。そして、ここがバカバカしさの極みだが、その道中の殆どを、ヤマトヨシコは後部座席に転がって寝ていたのだった。
暖かな潮風が吹いている。良く晴れてアクアラインからの東京湾が眩しい。山から下りて来た身にはもう充分夏が感じられる。
奴、木更津の物理屋こと出井の住むトレーラー・ハウスの前に着いた。
家は横浜だが、ここの分譲地にそんなものをドデーンと置いて、一人暮らしをしている。周りは洒落た造りの家が点在し、近所はさぞ迷惑だろうと思うが独特の個性とやわらかな物腰で仲良くやっているそうだ。お祭りなんかには積極的に参加していると言っていた。ナニ、大概の人はあいつの殺気に気がついていないだけで、ここ一番の切羽詰った壊れ方はなかなか見破れるもんじゃない。現代の忍者とでも言うべきだろう。
フト気がつくと、芝生のチェアーには、先に着いたのか、蒲田の英語屋、英が何かを読む手を休めてコッチを見ていた。
「いよー。久しぶり。」
例によって、笑っていないがどうも機嫌は良いらしい。喜怒哀楽が通常と逆なので困る。もう40年以上のつきあいだが、こいつが人から強く影響を受けたり何かに衝撃を受けたのを見たことがない。悪く言えば、頑固、偏屈、凝りすぎ、よく言えば・・・・わからない。現代の隠者か。
「おう。もういたのか。物理屋は?」
「居るよ。バーベキューの下こしらえしている。イベント屋は買出しにいって、アッ帰ってきた。」
振り返ると紙袋を両手に持ったイベント屋、椎野が歩いてきた。いつものレイバン・サングラスにヒゲの笑顔が近づいてくるところだ。今までにオレには想像もつかない、大事故、大借金、大病、それからどう言えばいいのか大女難、大博打を潜り抜け、辛くも生き延びたタフな野郎だ。どれが原因か知らないが、あまりの凄まじさにしばらく日本に居られなくなって上海・香港にトンヅラしていた。現代の大陸浪人というところか。狭い日本にゃ住み飽きた、という台詞が似合いそうだ。
こいつらは何故かそれぞれ忙しくしている。オレだけが真面目にサラリーマンを勤め上げて引退した途端、誰よりも隠居になってしまったのは、一体どうしたことか。
と、その時、後部座席で熟睡していたヤマトヨシコが起きたらしい。
「起きた?着いたよ。」
車を降りて、軽く伸びをすると、若い女と一緒なのに気がついた二人がさすがに驚いた表情を浮かべた。出井もトレーラー・ハウスから出てきた。よし、『実はこれがオレの今の女だ。』とでもハッタリをかけてやろう。
「紹介しとくぜ。オレの一番新しい彼女・・・・」
「おう、これが氷川さんの娘さんか。」「なんだそっくりじゃないか。」「ホントだ。高校時代を思い出すなー。」
「・・・・。」
「初めまして。氷川智子の娘です。」
目が覚めた。寝返りがうてず、息苦しくて目を開けると何と寝袋にくるまっているではないか。目を凝らすとテントの中だ。えーと、バーベキューをしてたんじゃなかったか?全く最近本当にボケが進行しているんじゃなかろうか。随分昔話で盛り上がったはずだが。
それにしても、我ながら驚いたが、高校時代にオレは詩人を気取っていたのだった。忙しいサラリーマン暮らしですっかり忘れていたが、ある時期一人でいくつかのペン・ネームを使い分け、小説やら詩やら評論を手書きで書きチラシた雑誌を出していた。雑誌の名前まで思い出して、あまりの恥ずかしさにもだえ苦しんだまで、覚えている。その段階で気を失ったのだろう。
みんなはどうしたのだろう。ヤマトヨシコは帰っただろうか。ゴソゴソ寝袋から這いだして外に出ると、曇り空の夜明け、今にも降りそうだった。 さてはオレをおいて帰ったな。物理屋も横浜にもどったか。だがこのテントと寝袋をどうすりゃいいいのか。しばらくタバコを吸っていた。きょうは金曜日のはずだが、畑はやってしまったから山に帰る必要もない。のんびりともう一つの隠れ家、油壺にでも行くか。オレは油壺にヨットを隠していて、夏はそこにも行っている。隠れ家といっても家族や仲間は承知の上であるが。
「オーイ。起きたか?」
「全く世話焼かせやがって。」
「水掛けても起きねーんだから。」
「おはようございまーす。」
何だ、こいつら。結局みんな泊まったのか。そうか、わかったぞ。トレーラー・ハウスにスペースがないから、自分たちの寝場所を確保するためにオレを体よく外に追っ払ったんだな。奴等が親切にオレをテントに寝かしてくれたのか、などと思いそうになった自分がバカだった。オレをほったらかして、近所のクアに朝風呂を使いに行ったのだそうだ。
雨が降りそうだったので、早々にメシを食べた。昨日のバーベキューの残りに物理屋がサッと炒めたチャーハンを皆で食べて帰り支度を始めたが、オレはこのまま山には帰らないことにした。
「おいご隠居、車乗せてくれ。」
「ああ、特に急ぐわけじゃないから、オレは海に行く。」
「ここも海は近いが?」
「うん。でも海岸じゃなくて入江だな。油壺の隠れ家に行く。」
「オッ、それもいいな。」
まず反応したのは英語屋だった。そして以外なことに、ヤマトヨシコも
「あー、アタシも行きます。」
「おい、学校はどうするんだ。」
「あたしは週2回だし、問題ないです。」
「いや、あの家の方に言わなくていいの。」
「やだなー、もう説明するの3回目ですよ。親は筑波にいてあたしは一人で住んでるんです。」
「昨日も何回も聞いてたぞ。このアル中め。」
「じゃあ僕も行く。ここのハウスなんか鍵1個で戸締りOKだし。」
ぶっ物理屋まで。結局イベント屋も乗ってしまい全員そのまま移動することになった。
そして、車はワン・ボックスだから5人でゆったりだが、イベント屋は隣に座ってアクアラインのトンネル以外ズーッと携帯を握り締め、『あの件はどうなった?』とか『それじゃ見積もりにならん』とか時には『冗談じゃねえ』のような迫力も交えてシゴトしっぱなし。英語屋は昨日から持っていた何やらの原書を読みながら、ノートパソコンンにカタカタと原稿を書いていて、少し静かだと思うと目を閉じていた。そしてヤマトヨシコは最後列にいて、来た時同様出発してすぐに寝てつく頃は横になっていた。物理屋はやはりネット関連を熱心に。オレは運転手か!
ハーバーは雨に降り込められ、人もまばらな梅雨時。何故ヨットもセーリングさせずにもいるのかというと、麻雀をしていたからだ。最初から間違っていた。
しばらくはしっとりと煙る港をみながら、船のキャビンで話をしていたが、備品に雀牌があるのをヤマトヨシコがみつけて言った。
「あらー、こんなところに雀牌がある。懐かしいなー。ウチはよく家族麻雀やったんですよ。」
我々は顔を見合わせた。今から半世紀近く前のはるか昔の都内のある高校で、日々雀荘でとぐろをまいて麻雀白虎隊を名乗っていたのは他ならぬオレ達なのだ。イベント屋は局長英語屋は副長、物理屋は参謀、そしてオレは監察として一部に(某高校内に)その名を轟かせたものだった。異存のあるはずもない、2抜けのデス・マッチが開始された。
ところが最近は麻雀なんか何年もやっていないので、みんなカンが鈍っていた。どういう訳かどいつもこいつもヤマトヨシコに振り込むのだ。
彼女がトップを走り続けているあいだ、オレは3-4位を低迷し、バカどもは2抜けのたびにカップ
ラーメンを買出したりビールを注いだりしていた。しまいに頭に来たオレはビールを買い置きのウイスキィに変えてガブ飲みし、最後の審判を聞いて失神したらしい。
「キャーッ。ご隠居それ大三元当たりー!」
そして次に目が覚めると、オレ以外はキャビンでそれぞれ勝手に携帯やらパソコンで仕事にいそしんでいるではないか。二日酔いで朦朧としている。どこにいるんだっけ、ああそうかハーバーだ。
「アッ、やっと起きたな。」
「いや、まだ眠い。」
「だめだ。早くシャワーでも何でも浴びろ。時間がない。」
すぐに又始まってしまった。もう午後じゃないか。一体何なんだ。何十年も前に似たようなことをした記憶はあるが、まさかこの年でこんなことをするとは・・・・。
しばらくしてヤマトヨシコがいないのに気がついた。やっぱり帰ったのだろうな。
と思っていたら、『ただいまー、です。もうトンボ帰りですよー。』の明るい声。見るとすっかりラフないでたちに着替えた彼女が、両手一杯の紙袋を下げてキャビンに入ってきた。皆、口々に『おかえり。』とか『ごくろーさん。』とか言ってる。
「これで2日は大丈夫な分を仕込んで来ました。」
と言いながら、早速大きなフランス・パンに包丁を入れだした。
「ふつかって何のこと。」
オレは恐る恐る聞いた。オレがつぶれた後どうやら夜明けごろまで続いていた麻雀が一段落し、彼女は着替えと買出しに東京へ行き、皆は仮眠してオレが目覚めるのを待っていたようだった。
やがて、『お待たせしました。』の声とともに、具をたっぷり載せたオシャレなパンが出され、ご丁寧にもオレには缶ビール付きで出された。
その状態がズーッと続いた3日目の朝に、オレは一人で起きたのだ。皆寝静まっているが、今日は何曜日なんだろう。ああ、日曜だ。土曜の勉強と日曜の買出しがパーじゃないか。
他の奴等はオレが寝てしまった時や自分の2抜けの時に勝手それぞれに過ごし事が足りているようなのだ。この通信の発達は、何もこんな連中のボヘミアン生活のために進歩した訳でもないだろうに。そして隠居のオレが自分の立てたスケジュールがこなせないで悶えるとは、少しおかしいんじゃないのか。
そうこうしていると、誰かが目を覚ましたらしく、キャビンから声がする。オレは一人で自問した。
自由とは何か、引退とは何だったのか。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
2015 サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(還暦編 Ⅰ)
2015 JAN 15 20:20:10 pm by 西 牟呂雄

Y県T市は渓谷と清流が売りであるものの、さして観光資源がある訳でもない。深く浸食されたK川の崖の上の山荘は川風が冷たく、遅咲きの桜がチラチラした後も冬支度のままだった。
メールチェックをすませ又ろくなニュースが配信されていないのを確認した後、今日は掃除の予定だったことをカレンダーで見て遅い朝食をとった。
この山荘はオレから2代前のじいさんが往事羽振りが良かった時に、普請道楽と暇に任せて立てた凝った造りのウチだ。
オレはB・B(仮名)通称は『山のご隠居』。長年勤めた会社を2年程前に退職してしまい目下のところプータローではある。東京は下町の生まれだが(現在還暦)一足早いスロー・ライフに対応するため、普段はこの山荘で暮らす。典型的な1週間の予定はこうだ。
月曜、家の掃除及び庭手入れ。夜、酒抜き。 火曜、身辺整理(振込み、引き落とし等)夜、日本酒。水曜、二日酔いのリハビリ。夜、ビール。 木曜、ゴルフ(午後のハーフのみ)。夜、ウイスキイ。 金曜、洗濯。畑仕事(キュウリ、トマト、枝豆)。夜、焼酎。 土曜、勉強(漢字書き取り、物理、英語ボケ防止)。夜、酒抜き。 日曜、買出し(車)後、昼前から1週間の残った酒をみんなやる。
暇といえばヒマだが、やっていると結構忙しい。夏は海に船遊びにいくし、冬は今でも現役スノー・ボーダーだからジットしてここにいるわけでもない。各種会合で月に2-3回は東京に出ているのでしばしば予定も狂う。不思議なもので、この程度の予定がこなせないと頭に来て翌日ガンバルから腹が立つ。ところで今日は、そういうわけでまず掃除だ。
「ごめんくださーい。」
わりと明るい女性の声がした。一体なんだ。このごろ変な勧誘が来ることがあるが、又それか。玄関に出てみると二十歳くらいの若い、それもとびきりの美少女、と言うか美人が立っていた。
「はい、なんでしょう。」
「あのー、初めまして。B・B(本名を言った)さんですか?」
「はあー。なんでしょう?」
「わたしはヤマトヨシコと申します。」
「はあー。」
「あのー、氷川智子(ヒカワサトコ)を覚えていらっしゃいますか?」
「エッと、誰ですかね。」
「B・BさんとE高校で同期と聞いてますが。」
「あー。はい、わたしはE高出身ですが。なにしろ1学年300人だからねえ。」
「実は、母はここのT文化大学の研究室にいたことがあって、私もこの街にいたんです。」
「えーと、マッまあお茶でも入れるから上がんなさい。何もないけど。」
かいつまんで聞いたところによると、その『ヒカワサトコ』なる人は結婚して『ヤマトサトコ』になり、出産後しばらくここの地元のT文化大学で研究をしており、今目の前にいる『ヤマトヨシコ』が小学校就学前まで住んでいた。その後一家は引越し現在は筑波住まい、まあ学者一家なんだろう。そして『ヤマトヨシコ』は親の後を継いだわけでもないのだろうが、T文化大学の大学院に籍をおいて週に2日程やってくるそうだ。そして、偶然オレの現住所に気がついた母親が教えたらしい。
ヤマトヨシコはかいつまんで以上の説明をしながら、オレがやりかけていた掃除機やダスキン・マットに目を留めた。
「あのー、お掃除してたんですか?」
「そうだよ。」
「あら、じゃお手伝いしますよ。」
というが早いか、長い髪をパパッと留めて掃除機をかけだした。何じゃこれは。オレはあっけにとられたがしょうがなくてダスキン・マットを持ってそこらを拭いた。本当は風呂に入ろうと思ったのだが。
「ああ、そこはそんな拭き方じゃだめです。ここの掃除機をかけていて下さい。ちょっと貸していただけますか?」
それからオレは掃除機を掛け続けたのだが彼女は吹き掃除をした後台所に移動して水周りをやっている。しばらくしてなんだか不安になったオレは声を掛けた。
「お嬢さん、お嬢さん。」
「こっちはすぐ済みますから。」
「はい。でも、あの、学校の方・・・・。」
「キャーッ、こんな長居しちゃった。すみません途中で。あの、大学までは・・・」
「歩いて30分くらいだな。」
結局オレが車で送っていった。こりゃ一体何なんだ?ヒカワサトコは良く覚えてないし、そもそも住所を聞いただけで訊ねてくるのもいい度胸だ。ところがこれだけでは済まなかった。
夕方、オレがメシを食おうと野菜を切って、どれ一息とばかりに風呂に漬かった。ここの風呂は西日が見事に入る造りになっていて、こんなところにもジイさんの凝った趣向がこらされている。
窓を一杯に開けて、ぼんやりしていると、カタカタと足音がして、「ごめんくださーい。」という明るい声がした。と思ったとたん、朝方の笑顔が、目の前に飛び出した。
「あらー、お風呂ですかー。いいなー。」
「アッ、そっそうか。」
「今、授業が終わって又おじゃましよーかと。」
「ほう。オレこれからメシだけど。」
「じゃっアタシ作ります。」
「ナニ?そりゃーまあ助かるんだが、あのー、ウチに入っててくれないか。おれ出らんないよ。」
「アハハー。そうですねー。」
何か妙だなと思わないでもなかったが、急いで風呂から上がり普段はすぐパジャマになるところを、まあGパンをはいて出て行った。すると、えーと、ヤマトヨシコは楽しそうに鍋の下拵えを造っていた。何か高倉健の映画で娘役のヒロスエがやっていたシーンに似てる、と思った。
「あのー、オレはビール飲むんだけど。」
「アッはいはい。えーと。」
といいながら冷蔵庫から手際よくビールを出して、グラスもどうしてどこにあるのか分るのか知らないがパッという感じで2つ並べた。
「はーい、どうぞ。乾杯ですね。」
しまった。今日は飲まない日程だったんだが。
食事をしながらヤマトヨシコは母親から聞いたE高の同級生の名前を何人か出して、どんな昔話をしていたかを喋った。驚いたことに、誰一人知ってる名前がなかった。焦ったオレは、逆に今でも付き合いのある、名前を3人出してみたが、これは向こうが聞いたことがないそうだ。本当に同じE高なのか、同じ学年なのか不安になる。
ヤマトヨシコは結構酒に強く、オレと同じペースでビールを飲んでいる。中途で冷酒に変えたがこれも平気で付き合う、オレは酔っ払ってしまった。
でもって目が覚めると、オレはふとんで安らかに寝てしまったようで、テーブルの上はきれいさっぱり片付いている。もう朝じゃないか。きのうはナントカいう女の子と散々喋っていたような気がするが、ハテ誰だっけ。E高校の・・・・。
オレはパソコンに向かいメールを開いた。オレの引退後は会ってなかったが連絡は取れる仲間、木更津の物理屋、蒲田の英語屋、大井のイベント屋にメールしてみた。彼等は別に勤め人でも何でもなく好き勝手にやっているので、そもそも引退の概念がない。先生・社長などと呼ばれるハッキリ言って胡散臭い人々ではある。従って今でも忙しく、またある時はオレ以上にヒマな暮らしをしている。
『えー、お久しぶりですが。昨日突然ヤマトヨシコ、なる美人がオレを訊ねてきて、母親がE高校でワシ等の同期生だそうなんだが、お前ら知ってる?ヒカワサトコさんが母親だそうです。聞くところによると、そのヒカワサトコさんはワシに恋をしていたそうで、いまだにワシを思い出しては泣いて懐かしんでいるそうです。』と嘘っぱちを書いて送った。
さて今日は諸手続きの日なので、通帳を持って市役所と郵便局に出かけた。しかしオレは完全に自由になったはずなのだが、自分でアホなルールを作っては、かえってそれに縛られることになって、昨日のように予定外の酒を飲むと、思わずしまったとなる。すると、オレは完全な自由になるのが怖いのか、と自問しては苦笑せざるを得ない。
帰ってみると、早速奴らから返信が来ていた。『その人は私と同じクラスだったが、お前に恋をしたなんて嘘にしてもシャレにならない。ところで元気なのか?久しぶりに一杯やるか。』これは、木更津の物理屋こと出井から。こいつは木更津にトレーラー・ハウスを持っていてそこで暮らしている変人。ウルトラ級の方向音痴だ。『忙しいんだバカヤロウ。氷川は中学で一緒だった。良く知ってる。』こいつは大井のイベント屋、椎野。社長と言っているがハッキリ言って悪人。『その人はお前があこがれて手紙を出そうとしたのをオレがやめさせたじゃないか、バカ。』ナニ!英(ハナブサ)通称、蒲田の英語屋。偏屈なる奇人でそれはどうでもよいが、てがみ、だと!だけどこいつは滅多なことではウソなんかつかない。オレは慌てた。卒業アルバムは東京の自宅に置いてある。こりゃ急げだ。車を飛ばして東京に向かった。また大幅に予定が狂った。
いた!氷川智子さんだ。いや娘はあんまり似ていないのはオヤジ似か。わかったぞ。
オレは翌日改めて奴等にメールした。
『いや忘れてた。確かにこの人にあこがれていたが、ワシャ忘れてた。娘も美人だぜ。今度紹介してやる。』と強がったのはいいが、連絡先も何も聞いてないし、まあ当分訊ねても来ないだろう。
東京は桜が満開だった。そのままブラブラして3日程してから山に戻った。
車を停めようとした時、ウチの木戸が開いているのに気がついた。しまった、慌てて閉めるのを忘れていたのか。最近ボケが来たのか、こういうことがしょっちゅう起こって困る。
入っていくと、アレ、人の気配がする。
庭に廻って『アッ。』と驚いた。氷川じゃなかった、えーとっヤマトヨシコだ。彼女は何と毛氈を芝生の上に敷いてお弁当を食べているのだ。
「オイオイ。何してるんだ。」
「あらー。あんまりいいお天気だったからお弁当こしらえたんですー。一緒にいかがですかー。」
「うん。まあ、昼時ではあるな。」
「ほら、鍵鍵!お茶ですか?それともビールかしら。」
「ええと、ア、アノッ、ビール下さい。」
まずい、今日は洗濯じゃなかったか。と思う間もなく彼女はテキパキと鍵をあけて家に上がり冷蔵庫からビールを出してハイドウゾ、とグラスまで持ってきてくれた。が、ここはオレのウチじゃなかったっけ。
翌日、正確には夜中の3時に目が覚めた。夕方まで一緒に花見をしてあの娘は授業に行った。一体全体これは夢じゃなかろうか。それとも本当はボケが進行しているのか?
つづく
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる 月光の誓い (196X年 小学校編)
2015 JAN 12 16:16:17 pm by 西 牟呂雄

年末は何かと気ぜわしい、というのはオトナの言うことで、僕達小学生には何の関係もない。
ある日、元彦があわてて寄ってきた。
「ちょっとこい。」
「何だよ。」
「ここじゃマズイ。いいから来い。」
やけに深刻な顔をした元彦は、僕を屋上に引っ張ってきた。
「連絡に使っていた場所が撤去されるらしい。」
「エーッ、どうしたんだ。」
「きょう集会やろうと思って連絡の紙をはさもうと行ったら入れないんだ。」
「エーッ、なんかの工事が始まるのかな。」
「わかんない。。」
「でさー。ともかく今日集会するからさ。オレは何とかCに伝えるからお前Dに言っといて。」
「わかった。」
教室に帰って授業中に、ノートの端っこに『秘密の場所に入れないらしい。今日集会がある。』と書いて、見えるように机の真ん中に押し出した。出井さんは特に反応をしなかったが、例によってニコニコしていた。
授業が終わって帰りに電車に乗って次ぎの駅に行った。ところで国電で一駅行くのも小学生にとっては大冒険だから新しい隠れ家に集会場所が変わってから前のように毎日というわけにもいかなくなった。おかげで伊賀の影丸がどうなったか筋は分らなくなるし困ったもんだ。
例のビルの屋上に行くと声がする。もうみんな来ていたみたいだ。『よう。』と声をかけながら扉をあけた。すると、元彦がウクレレを弾いて見せていた。
「どうしたんだ。買ったのか?」
「兄貴の友達がくれたんだよ。兄貴にギター教えてくれって頼んだら、お前は手が小さいから、小学生のうちはウクレレで練習しろって友達からもらってきてくれたんだ。」
「へー。それでお前弾けるのかよ。」
「できるわけないだろ。だから練習してんだ。」
奴はギターの教本を持っていて、『コード』なるものを練習しているらしかった。
「それってなんだ?」
ポローンと弾いて見せて、「コードって言って、伴奏するときに鳴らす和音だな。」
「あの、牧真二がやってるやつか。『あーーああやんなっちゃった』ってやつ。」
「バカ、そんなんじゃない!」
僕の悪ふざけに元幸は機嫌が悪くなってしまった。そしておもむろにズンチャカズンチャカとリズムを刻みながら歌いだした。英語だ!なにを言ってるのかさっぱり分らないが、明るく軽快な歌に思わず体が反応する。何だか知らないが最後の繰り返しのところで、『サンフラン・シスコ・ベイ』と言っているのが分った。
「お前すげーなー。英語歌えるのか。」
「兄貴に教えてもらったんだ。レコードの歌詞カードにふり仮名ふってもらって覚えた。」
「ヘー。お前のにいちゃん英語喋れんの?」
「お前はどうしてそう世間ばなれしてるんだ。聞いてて覚えたんだよ。」
「ところでA。なんていう歌なの?」
「うん。アメリカでヒットした『サンフランシスコ・ベイ・ブルース』ッていうんだ。」
「ふーん。何かかっこいいな。」
「オレにも教えてくれよ。そのサンスランシスコなんとか。」
「ウクレレもやらせろよ。」
「ところで連絡場所はもう入れない。どうも人が入り込んでいたのが分かって立ち入り禁止になったようだ。」
「これからどうする?」
「しょうがないな。BとDは隣同士だからそこを司令塔にして前みたいにメモを渡すことになるな。」
「バレるなよ。よし、誓いの言葉だ。」
僕達は奴の言うフオーク・ソングなるものにすっかり夢中になった。
帰ったあとから、僕はものすごくウクレレが欲しくてほしくて堪らなくなった。
翌日も、その又次の日も欲しくて堪らず、とうとう母さんにねだった。勿論『ダメ』だの『すぐ飽きるくせに』だの散々言われたが、何が何でも引き下がらなかった。そしてついに日曜になって父さんに自分で言って、ヨシとなったら買っていいまでにこぎつけた。父さんに言うと『まぁいいだろう。大事にしろよ。』といい一緒に買いに来てくれた。バンザーイ!
買ったらこんどは見せびらかしたくてどうしようもなくなった。早速集会をしようと思って、ハタと気がついた。どうやって連絡しよう。この前に決めておけば良いものを何にも決めてない。どうしよう。とりあえず出井さんに、前やったみたいにノートの端っこに『今日集会やろうと思うけど』と書いて机のあいだに置いてみた。出井さんは相変わらずマイペース。見たのか見ないのかわかんない。
突如ヤマダンの大声!
「コラー、原部ー。何ノートもとらずにキョロキョロしてる!」
「・・・・。」
あわててノートをたぐりよせた。まずい。
イライラしながら3時間目が終わってしまった。あーあ、どうしよう、と思いながら給食を食べて、昼休みに3角ベースで遊んで、5時間目の理科の時間になった。教科書を広げると、何かが挟まってる。紙だ。そっと拡げると、丁寧な字で、『私はピアノ。Cもダメだって。Aと直接話して。』と書いてあった。いったいいつ連絡して、いつこの紙を入れたのだろう。全く得体の知れない人だ。
ともあれ、僕はウクレレを誰かに見て欲しくてしょうがないので、元彦を放課後つかまえた。
「オイオイ、今日行こうぜ。秘密基地に。」
「エーッ、皆ダメだって言う話じゃないか。」
「二人で行こうよ。」
「だってまだマガジン、サンデー発売してないじゃないか。」
「オレ見せたいものがあるんだよ。」
「知ってるよ。ウクレレ買ったんだろ。」
「エッ!何で知ってるの?」
「お前もう、見れば分るよ。ニカニカして。最初に気がついたのCだぞ。」
「へー。分るのか。」
「ああ。それで見せて脅かそうと思ったろ?」
「うん。」
「バレてるのにわざわざ集会やってもしょうがないだろう。それで皆のらなかったんだよ。」
「なーンダ。つまんねーの。」
二人で寒い道を歩きながらしゃべった。今度弾き方を教えてくれ、と頼んで分かれた。
一人になって、つくづく残念な気持ちと、一体どうしてバレたのか不思議だった。そういえば茂はこのごろ、オトナっぽくなった、と言うより子供っぽくなくなってきていた。まあ、立派になったとかしっかりした、というわけではないが僕達とバカらしいことでギャアギャア騒ぐことをしなくなってきていた。元彦にしたって、時々小難しいことを言ったりしている。この前ビックリしたのは、例のフオークソングを英語の歌詞を、かたっぱしから覚えているのだ。意味も少しづつ分るらしいくて『自由』とか『平和』とか口走る。世間ではやる歌謡曲をバカにしているようなのだ。そして二人とも半ズボンははかないで、ジーンズなるデニムの生地の長ズボンを愛用し出した。僕も欲しくなったのは言うまでもないが、まだ買ってもらってない。出井さんはもう僕達より背が高くなっていて、タダでさえ落ち着いているのに最近は、ニコニコはしてるが益々透き通ってくるみたいで忍法「木の葉隠れ」を使う女影丸、といった風情だ。
冬の日は暮れるのが早い。ウチにつくころには夕日が落ち掛けていた。寒い。
晩御飯を食べて、大好きなウルトラマンに夢中になって宿題をしたら、フト寂しくなった。今年が終わって三学期になって、その後は卒業しちゃうじゃないか。そうだ、僕達は来年になったら詰襟の制服を着て中学に通うのだ。皆少しオトナに近づく。それなのに僕ときた日には、相変わらずウルトラマンに夢中になって怪獣の名前を暗記していていいのだろうか。
翌日、授業中に気がつくと国語の教科書に又、紙が挟まっていた。『きょうはみんな都合がいいので久しぶりに集会をします。』と書いてあった。きょうは大丈夫なのか、とOKと書いて出井さんにそっとわたした。しかし本当に女影丸だ。
授業が終わると、、一目散に家に帰り、買っていた二週分の少年サンデーとウクレレを持って飛びだした。早くマガジンが読みたい。隣町の駅を降りて歩き出してハッとした。茂だ。見たこともない女の子と話をしている。僕は思わず身を隠してしまった。こっそり見ていると、何やら手渡しされている。茂は僕達に見せたこともないような優しい顔で、少し話して歩き出した。僕は後ろから追いすがって、声をかけた。
「茂!みーたーぞー。」
てっきりうろたえるものと思っていたら拍子抜けの反応だった。
「ああ、Bか。見たってあの子のことか?」
時々この駅で茂を見ていたF小の女の子が手紙をくれたのだそうだ。
「まあ、あんまりかわいくもないからテキトーに話してやってるんだけどな。
何なんだこの落ち着きは。そして隠れ家に着くと、隠し場所に鍵がない。屋上の扉をあけるとAとDがもういた。そしたらCはいきなり切り出した。
「実は叔父さんの事務所がここを立ち退くんだ。だからここを使えるのは今年一杯だ。」
「へー。」「ふーん。」「やっぱりね。」
「それでもってトシが明けリャ3学期で、直ぐ卒業だろ。その後はG中学の新入生ってわけだ。中学に行きゃークラブ活動もするだろうし1年坊主は色々忙しい。だからこういった集まりもできなくなるだろ。この際『ランブル団』の集まりはひとまず解散ってことにしないか。」
「それがね、この前分ったんだけどあたしの住所は学区が違っててG中じゃないらしいのよ。さっきAと話したんだけど山手側の林君とか飯田くんやあたしはJ中なのよ。」
「あっそうか。オレ達浜側がG中か。別々になるんだな。」
「Dはクラブに入るのか?」
「新聞部があれば入りたいけど、ほんとはテニス部に入りたいな。」
「そうなりゃ敵同士になるな。オレはサッカーやろうと思ってんだ。」
僕は何も口が挟めなかった。皆オトナみたいな話ぶりじゃないか。『中学にいってバラバラになっても又集まろうよ。』と言いたかったんだけど、どうもそういうことを言う雰囲気じゃなさそうなのだ。クラブに入るなんて何も考えたことがなかった。運動部でしごかれるのもやだし、文化部で何かの研究なんかするガラじゃない。ランブル団は無くなってしまうとすることもないし、やっぱり地味な文化部にでもいれてもらうのかなー。
「B,なにボーっとしてんだ。やるだろ?」
「ヘッ?なに?」
「やあね。聞いてなかったの?せっかくBもウクレレ買ったんだからフオークソング・グループつくって卒業式のあとの謝恩会で歌おうって言ったのよ。あたしアコーデオン弾くし、Cもウクレレ買うって。」
「ああ。いいよ。・・・・うん、やろうよ。で、なにやるの。」
「もちろん、サンフランシスコ・ベイ・ブルース!」
もう秘密のランブル団ではなく、フオーク・グループ『アルフアベッツ』になった僕達は、誰にもはばからずに一緒に電車に乗って話しながら帰った。ヤマダンに頼んで音楽室で練習させてもらうことも決まった。
そして、2学期が終わった。終業式があって教室にもどって、あしたから冬休みだ。ウチに持って帰らないとならない体操服とか、机に入れっぱなしの定規とか雑記帳をガサガサしまっているとランドセルが重くなった。
「ねえ、B。練習行こうよ。今年最後だよ。」
「アッ。今行く。・・・・そうか、来年は席替えだからとなりじゃなくなるね。」
「そうね。Bの隣はおもしろかったな。」
気がつくと教室に二人だった。ランブル団の秘密を守るためにロクにしゃべったこともなかったことにフと気がついて、思い切って聞いてみた。
「そうだ。前から聞こうと思ってたけど、Dってどんな人が好きなの?」
「アハハハ、なによいきなり。あたしはそういうの良くわかんないのよ。皆好きだよ。」
「そうか。将来はどんなことになるんだろうな。」
「分るわけないでしょ。Bこそ何になりたいのよ。」
「エッ。考えたことないよ。海がすきだから、船に乗って外国にでもいきたいかなー。」
「アハハハ、Bらしいね。じゃ、あたしは月にでも行くか。」
「宇宙飛行士にでもなるの?」
「何いってんの、そんなんじゃない。かぐや姫かな。」
こいつ一体何者なんだ。
「月に行って人から見えないところで人を観察して。人にも干渉しない。・・・・満月見たらあたしを思い出して。」
ウーム。何を言ってるのか良くわからない。その時声がかかった、だ。
「おーい。早くしろ。きょうは最終日だから音楽室使えるのあと30分だぞ。」
エピローグ 40年後のクラス会
「それにしてもあの演奏はヒドかったなー。」
「ワハハ。演奏より歌だろ。何たって英語なんかわかんないんだからな。カタカナで覚えたんだぞ。」
「意味も何にもわかんなくて良く歌ったぜ。実際。」
「あんときゃお前、ウクレレなんか買うのいやだって言って音楽室のウッド・ベースをやったんだよな。」
「結局まともな音を出したのは出井のアコーデオンだけだもん。」
「どうせならハワイアンバンドでもやりゃよかったんだな。業界でいうワイアンだな。」
「でもねえ。楽しかったわよ。先生も喜んでくれたし。」
「ヤマダンが死んでもう10年か。」
「オレ達も50を超えるはずだよ。」
「全くなあ。よくも死なないでここまで来たよ。」
「ロクなガキじゃなかったのになあ。ヤマダンも苦労してたよ。」
「そう言えば、今思い出した。出井は月にいくみたいなこと言ってたな。」
「オレも何か聞いた覚えがある。狼女みたいに満月に甦るって言ったぞ。」
「オレにはかぐや姫って言ったぞ。」
「オホホホホホ。全部あたり。でその通りになった。」
「エッ。」「エッ。」「エッ。」
「今日は久ぶりに下界に来たの。又すぐ帰ろうか、と。」
「また訳わからんことを・・・・。」
「アハハ、女の正体はなかなか分らないのよ。皆奥様がどこの住人だと思ってるの?」
「・・・・。」「・・・・。」「・・・・。」
こっこいつ、何者なんだ。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる 僕らの秘密基地 (196X年 小学校編)
2015 JAN 10 8:08:58 am by 西 牟呂雄

秘密集会でマンガの廻し読みをし終わった頃、茂が聞いてきた。
「おい、B。出井が好きなのは誰だか分かったのか。」
「分るわけないだろ。聞きようがネー。」
「だから教えたろ。名前出して顔色を伺うんだよ。」
「ああ。やってみたけどだめだった。」
「赤くなったりしなかったのか。一体誰を出した。」
「AとC。お前ら。」「バカ!」「バカ!」
「少しは物を考えろ。現実味ないじゃないか。野球の上手い佐藤とか、勉強のできる鈴木とか。」
「だけど、違うと思うぜ。あいつ変わってるんだ。」
「変わってる?クソ真面目じゃないの。」
「あれはワザとやってんだよ。目立つことが大嫌いみたいだよ。」
「オレわかる。だってこないだの国語の試験、何にも書いてないんだぜ。あんなにできるのに。」
「できるけど逆を行った?不思議な人だな。」
「それで職員室行きか。Bは何でだ?一緒に呼ばれてたじゃん。」
「オレは出井さんをよく監視するようにヤマダンに頼まれたんだ。」
「バカ!」「バカ!」
それから誓いの言葉を3人で唱和して、帰ろうと講堂の裏手を回った。
驚いたことに、下校する出井さんにバッタリ会ってしまった。
「アラ、A、B、C、お揃いで集会の帰り?」
僕達は引きつった。特に僕はあわてた。とたんに他の二人はくってかかった。
「お前喋ったのか。」「この裏切り者。」「ちっちがう!オレは喋ってない。」
「アハハ、原部君じゃないわよ。大体君達『これ、秘密文書』とか『今日集会』とか大声で喋ってもうバレバレよ。Aだってその文書とか落としてたし、Cだって『僕らは少年ランブル団』とか口ずさんでるし、アタシもうおかしくて。誓いの言葉だって気をつけないと講堂のなかで聞こえるよ。」
「あのー、他の人にもバレてんの?。」
茂が小さい声で言った。
「大丈夫。今のところ、誰も知らないよ。」
「あのー、今日の集会で何を喋ってたか、は知ってる?」
元彦も消えるような声で聞いた。
「知らないわよ。今日は生徒会だもの。」
アー良かった。誰が好きなのか、なんて喋ってたのがバレたらコトだった。
「あのー、秘密にしといてくれないかなー。」
僕はかすれる声で聞いた。
「あたしは誰にも言わないわよ。但し、条件がある。」
「なんでしょう。条件とは。」
出井さんはニコニコしながら、少し考えるように、小首を傾げていたが、悪戯っぽい目で言った。
「そうね。あたしも入れて頂戴。」「エッ。」「エッ。」「エッ。」
「そうしたらあたしは出井だから、D だね。」
こっこいつ、一体何者なんだ。
僕達はそのままゾロゾロと秘密の場所に出井さんを案内した。
「ここかー。まあ、一般には分らないだろうけど、用務員のおじさんは知ってるだろうね。」
「エッ。」「エッ。」「エッ。」
何だか僕達はさっきから「エッ。」しか言っていないような気がするが。
「そのうちこの漫画は根こそぎやられるから、持って帰ったほうがいいよ。それで、この場所は連絡の秘密文書を隠して置く場所に使うんだね。ほら、そこの隅っこに挟んでおくとかさ。そうすれば君達みたいに人前で『ほら、これ。』とか言いながら渡すようなことをしないですむわよ。それで集会をする場所は学校の外に又作るのよ。毎回変えるとかね。」
ウーム。いちいちもっともなことだ。
「ところで、ランブル団ってどういう意味なの?」
「うん、それはだな。」
やっと、出番が来たっ、といった感じで元彦が始めた。僕には何だかよく分らんが、彼女は『フーン。なるほどね。』等と相槌を打っていた。
「それじゃ、オレ達がいつもやってる『誓いのことば』も覚えてもらおうか。」
多少ペースを取り戻した茂も胸をそらせた。ところが、
「ああ、それなら知ってるわよ。『ひとつ、ランブル団のことは、』ってやつでしょ。」
「エッ。」「エッ。」「エッ。」また振り出しだ。
「言ったじゃない。あんな大声でやってるんだもん。講堂できこえたわよ。」
「・・・・他に誰か聞いたの?」
「下級生がいて、『あれは何ですか?』って聞かれたから、ボーイ・スカウトだって言っといた。」
どうにも僕達より上手のようだ。
「いいこと。これからは秘密結社なんだから、普段はそう仲良く話さないの。秘密の場所にも一緒に来たりしない。連絡を取りたい人が、1時間目の休み時間に秘密文書をそこに挟んでおくの。で2時間目がA、3時間目がB、昼休みがC、5時間目が私。帰りがけに挟んだ人が持ってかえるのよ。それぞれ秘密の集会所を探してきて。それで完璧よ。」
さあ大変だ。学校以外に秘密に集まれる場所なんて見当もつかない。つかないが、1週間以内に探してみることになってしまった。
そして1週間後が来た。この1週間というもの、何しろ普段は仲良く話さないことにしたので休み時間に遊ぶ相手に困った。場所探しはもっと困った。同じ町の中にそんなに秘密の場所があるわけがないじゃないか。シケた公園も、パッとしない神社の境内も、地元の奴にとっては秘密でも何でもない。一度は川の土手をウロウロして、同じようにチョロチョロしていた元彦と会ってしまいお互い、困ってんだろうなー、という顔をしながら、『よう。』と言ってすれ違った。
更に、僕の場合は出井さんが隣だ。まあ、仲良く話すこともないのだが、話さないようにするというのも実に難しいもんだ。いきおい、敬語調になって変なことおびただしい。『それを見せて頂けませんか。』『今、ヤマダンは何と言ったのですか。』と言った具合だ。
ところで3時間目の休み時間が僕の番だったので、例の場所に行ってみた。すると秘密文書が挟んであった。開いてみると、『Cより全員に告ぐ。集会所の候補地が見つかった。本日4時半に駅改札口に集合。』とあった。なにやらワクワクするじゃないか。
教室に帰ると、何食わぬ顔で出井さんの隣に座った。相変わらずニコニコしている。彼女は5時間目の休み時間に行くのだからまだ知らない。しかし言う訳にもいかず。
そして、5時間目の休み時間から帰ってきたが、表情一つ変えずにすましていた。唯者じゃない。
4時半きっかりに改札に行った。一度家に帰ると出にくいので、図書室で時間をつぶしたのだが、他の3人は一度ウチかえったみたいで、ランドセルを背負っているのは僕だけだった。
もったいをつけた茂が黙ったままそっと元彦に紙を渡した。元彦は真剣な表情でそれを見ると僕にアゴをしゃくって渡した。『CからA、B、Dへ。切符を買って次のXX駅で降りろ。Aは3両目、Bは4両目、Dは5両目に乗れ。Dはこの秘密文書を捨てろ。』と書いてあった。僕も無言で出井さんに渡すと、彼女は小さく頷いて切符売り場に行った。僕達も無言のまま、買いに行き、無言のまま改札で切符を切ってもらい、無言のままホームに上がり、バラバラになって電車を待ち、そして別々の車両にのって、次ぎの駅で降りた。その後も無言のまま1列になって茂の後をついていった。何か大真面目でこんなことをやっているのがバカバカしいとは一瞬思ったが、誰かが一言でも言ったら笑い出してブチこわしになるに決まっているから黙っていた。
とある、くすんだビルの中に入っていくではないか。あやしい!3階建ての屋上まで上ると、何と鍵を出して鉄の扉を開けた。屋上は日当たりの悪いビルの谷間で、シケた鉢植えがぞんざいにあって雨よけのシートが掛けてある一角があった。
「どうだ。ここなら絶対に分らないだろう。」
茂が胸をそらせて言った。本当にそうだ。よくこんな所を。さすがだが一体どうやって。
「ここはこの下の事務所をおじさんが借りているんだけど、何かもうすぐ立ち退きなんだってよ。だから暫くこの屋上は勝手に使っていいらしいんだ。だから鍵もオレが持ってる。どこかに隠しておけば皆自由に使えるってわけだ。アッ、それから知ってると思うけどこの学区はF小の地域だ。あそこはやばいからくれぐれもウロウロしたりしてもめごとには気をつけろよ。特にD、お前目立つからな。F小は女子が凶暴なんで有名だから。」
実際に暮らして見なければ分らないだろうが、下町ではよそ者を入れない。山の手のように駅のまわりの商店街を抜けると家ばかりならば人の集まる場所は限られるが、下町の方は人の住んでる所と人が働く所と変なおっさんやアンチャンがウロウロする所が一緒だ。とにかくゴチャゴチャしているし、その変なおっさんやアンチャンの中には見るからにヤバイのもたくさんいる。そういうのがよく他所から遊びに来ているのにインネンをつけて子供はそれをしょっちゅう見ているから小学生でも縄張り意識が強く仲も悪い。茂はそれを注意しているのだ。
ともあれいつまであるのか分らないが秘密の隠れ家ができた。この日の誓いの言葉は一段と声がそろっていた。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる 人呼んで「少年ランブル団」 (196X年 小学校編)
2015 JAN 9 20:20:02 pm by 西 牟呂雄

『AからB,Cへ。本日の集会は例の場所で行う。Bはサンデーを、Cはマガジンを持参。』
授業中に紙が回ってきた。なにやら怪しげだが、僕達は秘密組織「ミッドナイト・ランブラーズ」略して、少年ランブル団、を結成していてA,B,Cはそのコード・ネームだ。
Aこと英(はなぶさ)元彦。Bは僕、原部譲(バラベゆずる)。Cが椎野茂(しいのしげる)の3人だ。
名前は物知りの元彦がつけた。ウエスト・サイド・ストーリーとか言う映画に、アメリカのチンピラがグループにナントカズと名前をつけていて、それを字幕ではナントカ団、とかいてあるのだそうだ。元幸や茂にはアニキがいて、流行の音楽やら映画のことを良く知っていて教えてくれる。自分は見てなさそうだけど。
ミッドナイト・ランブラーズ、少年ランブル団、どういう意味かは忘れた。そして何を今日するのか、というと3人で集まって僕達の間では欠かせない、少年サンデーと少年マガジンに少年キングを回し読みするのだ。ランブル団が結成されてから、それまでそれぞれ別に買っていたのがいかにももったいないので順番を決めて買い、回し読みをすることにしていた。教室は漫画禁止なのでどこかに隠しておく必要があり、それが ”例の場所” である。校内だが言うわけにはいかない、秘密の場所だ。6時間目が終わって集まった。
「誰にも見られてないな。」
「もちろんだ。」「抜かりない。」
「よし。」
『伊賀の影丸』『おそ松くん』。暫く皆で読んでウチに帰る。帰り際に大将格のCが、
「それじゃあ、誓いの言葉だ。(間を取って)ひとつ、ランブル団のことは決して口外しない。他人の前でコード・ネームで呼ばない。」
「(僕)ふたつ。ランブル団は仲間を決して見捨てない。敵に当たるときは全員力をあわせる。」
「(A)ランブル団は秘密をつくらない。互いにウソはつかない。」
「(全員で)裏切ったら除名する。生涯裏切り者として地獄に堕ちよ。」
「よし。」「よし。」「よし。」
何がよし、だか分からないが、僕達は大変満足した。
6年2組は、うるさいクラスだ。授業中もザワザワしていてよく先生が怒る。そして、一番うるさいのは実は僕だ。とにかくなぜか授業が退屈で退屈で窓の外を見たり、いたずら書きをしたり、それでもダメで隣をつついておしゃべりしてしまう。なにしろ二人机でくっついているんだから、初めはいやがっていてもしまいにひきずり込まれているうちに、どんな真面目な奴も僕の隣に座るとみんな成績がガタ落ちになってしまうらしい。一度は母さんがPTAの会合でこっぴどくやられたらしく、その分僕はこっぴどくが10個つくくらい怒られた。
それはどうでもよいのだが、ある日突然席替えがあった。そして結果からいうととんでもないことに、クラスで一番美人でかつ秀才の女の子の隣にさせられてしまった。そしてランブル団は、元彦(A)は小柄なので前の方、茂(C)は左の後ろの方。僕は大好きな窓側から遠く離された廊下際の後ろ、と三角形のようにバラバラにされてしまった。もう授業中に秘密指令を廻すことができなくなった。何しろそれまではA・B・Cの順番で縦に並んでいて(それでコード・ネームを決めた)だからこそ誰にも知られずにランブル団のメモをやり取りできたのだ。
その隣になった子、出井聡子さんは学級委員で先生の信頼厚く、運動神経抜群でかつクラスで一番かわいい。全く僕とは正反対のやつなのだ。今まであまりしゃべったこともない。まいったなあ。
新しい席では僕は警戒していたのだが、出井さんの方は少しも変わらずニコニコしてくれたので安心した。『しゃべりかけないで。』なんて言われたらどうしよう、と思っていたのだ。それどころか、随分親切なので驚いた。僕は宿題を忘れるのもしょっちゅうだが、そんなもんじゃなくて定規やコンパスとか、もっとひどいときは教科書とか筆箱とか致命的な忘れ物もする。翌日に早速算数の教科書をやっちまった。しかも授業が始まってから気がついたので、どうにもならない。するとうろたえていたのに気がついた出井さんが、教科書をスッと机の真ん中に押し出してくれた。えっといった感じで目があったが、相変わらずニコニコしていて、僕はドキッとして、お礼も言わなかった。
席が離れたので、秘密文書は授業中には廻せない。休み時間に3人で喋っている時に『おいこれ秘密文書。』といって渡すのだが、3人で喋りながら渡してその場で見るのはあんまり秘密っぽくない。口で言っても同じじゃないだろうか。
秘密の場所で漫画を交換した後、突然元彦が
「おい、B,新しいおとなりさんはどんなだ。」
と切り出した。
「どうって、出井のこと?」
「そうだよ。」
「よくわかんない。真面目な子だよ。」
「そんなこと見りゃわかる。何か他にないのか。趣味のこととか。」
「分かるわけないだろ。口きいてもらえないんだから。話なら、C、お前時々話してるじゃん。」
「そりゃ話すけど、オレあいつ苦手だ。」
「そうだろうな。相手は学級委員だもんな。」
「オレ達のことなんかバカにしてるだろうな。」
「だってされてもしょうがないよ。バカなことばかりしてるんだもん。お呼びでない。」
「これまった失礼いたしました。」
「そうだ!出井が誰のことが好きか、B、お前調べろよ。」
「シエーッ。無理だよそんなこと。口もきいてないのに。」
「だーかーらー、そこは頭を使え。何となく名前をだして表情を見るとか。」
「オレ無理だよ。お前等のほうがいいよ。」
「だーめ。」「だーめ。」
結局調べるってことになったみたいだが、最後に3っつの誓いを斉唱して帰った。
さて、頭を使えといわれてもどうすりゃいいのか分からない。わからないまま1週間が過ぎた。その間多少わかったことは、まず出井さんはピアノを習っていてものすごく上手い。実は僕も習っていたのだけれど、バイエル、ハノンを終えた時にやめた。出井さんはその上を更に行っていて、レッスンのあるらしい日にピースを広げたりしていた。曲名は知らないが音符の数のベラボーに多い曲だった。女子の間でも人気者というか、輪の中心的存在なのだけれど、あまり喋るわけじゃない。周りがケラケラしているときに、フッとニコニコ顔が消えていく時があって、何か本人が消えていってしまうような感じがした。
ここ東京南部は区はでかいが、大きく分けて『浜』側と『山』側と言っている。高級住宅街と下町が隣合っていて、我等がE小学校はちょうどその真ん中だ。生徒は両方から来ていて、だからごった煮みたいに色んな奴がいる。僕達は言うまでもないが。
ある日、抜き打ちの小テストがあった。ウチの担任の山田先生は自分で問題をつくって時々突然テストをする。この日は国語だった。漢字の書き取り、読み、その後文章題があった。教科書に出ていた物語が載っていて、主人公がどうしたこうした、を20字以内で書け、とか『それは』はなにを指すのか、といった問題があった。僕は鉛筆の持ち方が変なので、もちろん字はめちゃくちゃヘタだが、左手をこめかみに当てて肘をつき、かぶさるように字を書くクセがある。そうしているうちにその物語の続きがどんなもんか、が頭に浮かんできた。なにやら、面白いストーリーが浮かんでニタニタしているうち、フッと眠くなった、というか一瞬眠ってしまったか。
「はい。お終い。鉛筆を置いて。後ろから前に出して。」
同時に、キーンコーンーカーンコーン、とチャイムがなった。しまった!何にも書いてない!あー、全く!そしてテストが後ろから集められてきたので、ヤレヤレと自分の分を出した。その時、隣の出井さんの答案が見えた。さぞよくできてるんだろうな、と思ってチラと目をやると、何と!何にも書いてないじゃないか。息を飲んで目を上げると、ニコニコしている出井さんと目が合った。
「よく寝てたみたいじゃない。」
こっ、こいつ。一体何者なんだ。
早速山田先生が、『原部と出井、放課後ちょっと職員室に。』とお達しがあった。事情を知らないみんなが囃し立てた。違うんだってば。六時間目が終わって、ノコノコ職員室に行った。いや、正確に言えば、出井さんについていった。山田先生、通称ヤマダンは怒っていた。
「お前達、二人そろってどうしたんだ。何か理由があるなら言ってみろ。」
先生がこっちを見るので、僕が口火を切らざるを得ない。
「あのー、ですね。えー、文章を読んでいるうちに、フト、フトですよ、この主人公が5年後にどうな
るのかを考えたらですね、そのー、止まんなくなっちゃって、あのー時間がなくなりまして、」
「バカモン!時間がない、じゃなくて寝てたじゃないか。」
「エッ、先生見てたんですか。じゃどうして起こしてくれなかったんですか。」
「バカ。試験だぞ、全く。集中しろ!出井はどうした。」
「わたしはこの作家、ナントカカントカは認めてないんです。」
「ホオー。どういうところがだい。」
こっ、こいつ。一体何者なんだ。先生と出井さんは訳のわからない話をして、最後は先生が折れ『まあとにかく試験は真面目にやるもんだぞ。』といって終わった。出井さんは僕を見て、
「原部君、おもしろいね。」
とニコニコして言った。訳わかんないのはそっちの方だよ、と僕は心のなかでつぶやいた。
つづく
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」