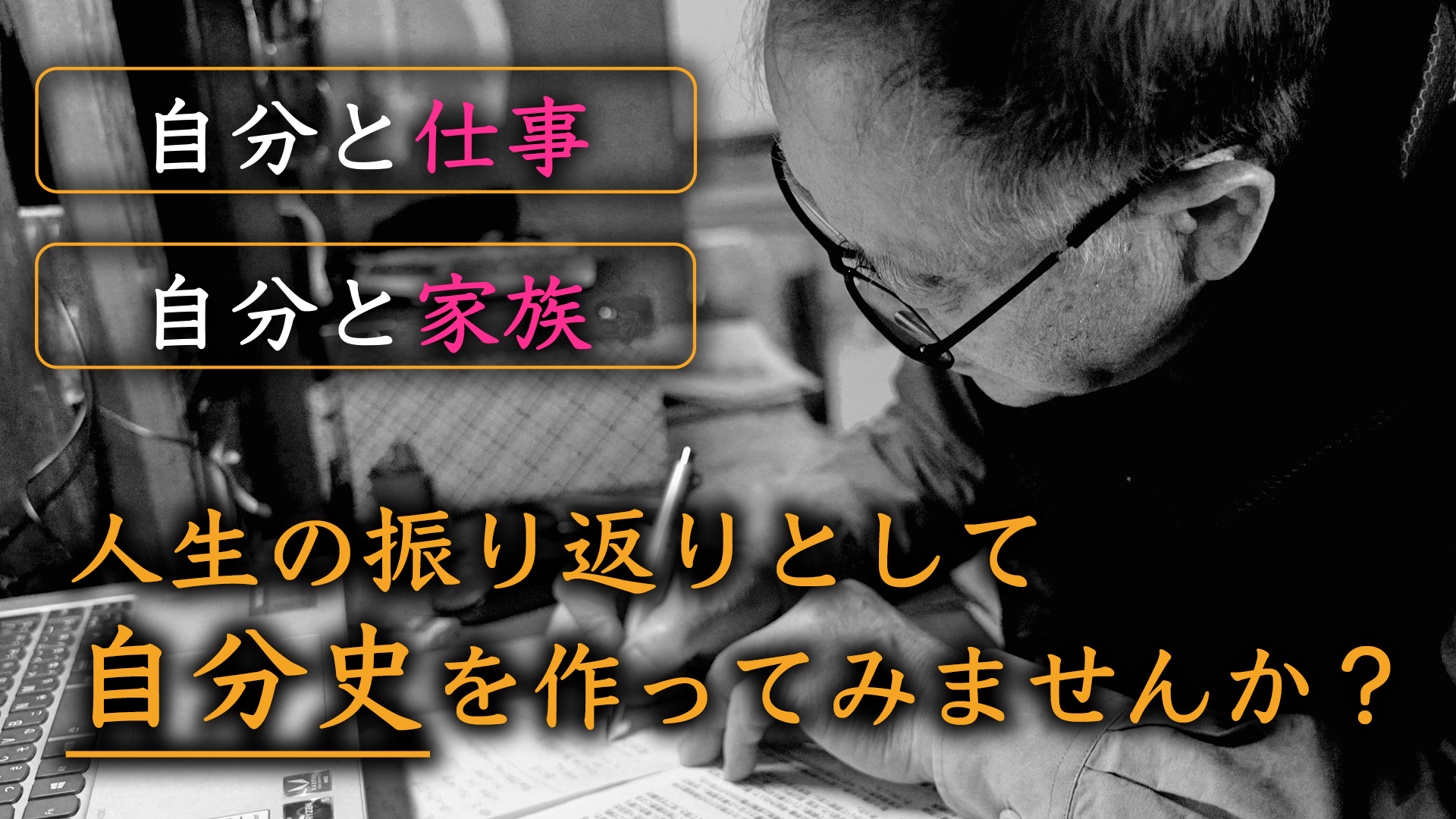サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(1998流浪望郷編 最終回)
2015 MAY 22 22:22:09 pm by 西 牟呂雄

少し前から僕の講義に聴講生として昔の同級生が来るようになった。息子さんが別の学科の学生だったので僕の講座を知ったそうだ。旧姓出井さん、女性である。かつては大変な秀才だったが、卒業後すぐ結婚・出産して今は一段落ということで、勉学の虫が騒いだようだった。
そして例のB・Bがメールの返事を寄越してきた。来月日本に帰ってくるのだそうだ。早速椎野と相談して歓迎会と称し会食することにした。
実は出井さんは高校時代B・Bがあこがれていた人なのだ。もうあれから四半世紀も経っている。多少リスクはあるが、B・Bにはナイショで出井さんを招待してみると『アラッ懐かしいわね。』と参加してくれることになった。アイツどんな顔をするのだろう。さすがに椎野は『そんなことして大丈夫か?』と心配そうだったが・・。
当日、皆忙しいらしく午後8時と遅めのスタートとなった。驚いたのは出井さんは和服でお出ましだった。
ところがB・Bお店に来たのは30分も過ぎてからで、しかも既にデキアガっているようだ。
「よー、よー、よー、よー。グッデイ・フォア・オール。椎野マニラ以来。英(はなぶさ)もうスゲー暫く。アッ初めまして、どっちのカミさん?」
どうも忙しくなかったらしく、どこかで引っかけて来たようだった。それにしてもコイツ、スーツを着た異形のサラリーマンだ。アジアで流行っているのか趣味なのか、襟足を長くタテガミみたいに伸ばしている。しかしこっちも人の事は言えないが。僕は長髪だし椎野もラフな格好で、出井さんは正装ではあるがどうしても浮く。昔懐かしいと気を利かせたつもりで70年代の曲ばかり有線で流しているカフェ・バーを選んでしまったのが悪かった。
「おい、こちら出井さん。同学年だっただろ。」
「あっそうですか。ヨロシクゥ。」
何の反応もないので拍子抜けした。出井さんはポーカーフェイス、僕と椎野は顔を見合わせた。
それからお互いに先も見えずに流離らっていた頃の話を披露した。B・Bは僕たちの話を聞いて、
「何だ!卒業後すぐに上にへつらい下に媚びる就職をしたのはオレだけか。」と開き直り、サラリーマンがいかに大変かをしきりに自慢するのだが、僕たちはバカみたいなことに夢中になっていたあいつの高校時代の延長にしか聞こえなかった。
繰り返し語ったのは、シンガポールやマニラでマガイモンの日本食を食べ飽きた、ホテルの朝飯にお茶漬けのふりかけを持ち込んで食べた、そういう時『日本に帰りたい』と強烈に思った、という情けない話だったが。
そういえば昔一度見たことがあったが、B・Bは酒癖は悪かった。絡んだりケンカするわけじゃないのだが、物凄い早口になって何の話か分からなくなってしまう。だんだんそうなってきた。ちなみに椎野は酒はあまり飲まないが女癖は悪い。
ずっと聞き役だった出井さんが口を開いた。
「ところで原部(ばらべ)君、相変わらず詩は書いてるの。」
「へっ、『し』って何。」
「昔詩集を造ったり雑誌みたいなのを書いて見せてくれたじゃない。」
「ん?何のこと。」
「おお、オレも覚えてるぞ。あれとってあるのか。」
「僕も読んだな。」
「オレそんなことやってたか?」
ポカンとしている、不思議な奴だ。
するとBGMがキングストン・トリオの昔懐かしい『サンフランシスコ・ベイ・ブルース』が聞こえてきた。これ、僕たちが組んでいたフォーク・グループのフジヤマ・マウンテン・ボーイズがレパートリーにしていた。一斉に『懐かしいな』などと言いつつ歌詞を口ずさんでいると、突然B・Bが叫んだ。
「あなたはイデイ・サトコさんなのか!」
深夜2時過ぎのカウンター。出井さんはとっくに帰って僕たちは3人並んで飲んでいた。
B・Bは酔い潰れていたが、最後に『初恋の人を忘れ、初恋をしたことまで忘れ、思い出すのはお前等とのバカ話ばかり。オレの青春はどこ行った。青春を返せ!』と喚き散らし、椎野に『返せったって誰に返してもらうんだバカ。』と怒鳴られて突っ伏した。
椎野は言う。
「結局流れ者をやってても、オレやお前がアテもないのにウロウロするんじゃなくてサラリーマンの尻尾を引きずったままだとそれこそ倭寇じゃないけど日本が恋しくなってかえってきちゃうんだな。」
「ふーん。それじゃお前またどっかに流れるか。」
「うーん、流れ次第だな。当面食えるからねぇ。」
「僕はもう少ししたら今度はアメリカに行く予定があるよ。」
「へぇ、行ったら帰ってこないかも知れんな。」
「どうかな。また10年後にでも会うかな。」
昔の仲間と会って、この四半世紀を振り返り感慨深いものがあるかと思ったが、全くない。むしろこれからはどうなるのか、不安の方が強い。今は結局個性というものは変化も進化もしないものだと良く分かっただけだった。
潰れたB・Bは、もちろん捨てて帰った。
おしまい
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(1998流浪望郷編Ⅲ)
2015 MAY 21 6:06:41 am by 西 牟呂雄

「よう、久しぶり。」
「うん、だけどびっくりしたなー。お前が中国に行ったりしてるのは知ってたけど。あいつがマニラでバンド屋になってるとはねー。いくらなんでも弾け過ぎだろ。」
「それがなぁ。B・Bも一応サラリーマンは続けてるんだそうだ。」
「しかし、歌ってたんだろ。」
「いや、メンバーじゃないんだ。オレがよく行く店にあいつも行ってたんだって。そこのバンドと仲良くなったみたいで時々遊んでたみたいだな。で、あいつが来るとバンドの方もサービスでレパートリを演奏すんだって。それってアレだぞ、ワイルド・チェリーの歌だぜ。」
「へぇ、フィリピン・バンドもよくそんなの知ってたな。サラリーマンってスーツ着てたの?」
「まさか。マルコス大統領みたいなシャツ着てた。まあ、一応正装なんだがな、現地では。あの手のバカはどこにでもいるってこった。ホラあいつの名詞。」
「おお、だけど何だこれ。住所も電話番号もないじゃないか。これ電子メールのアドレスだろ。」
「あいつの説明も良く分かんないんだよ。事務所はシンガポールなんだって。フィリピンにはどうも工場があるらしいんだ。でお客さんが台湾・マレーシア・シンガポールあたりで、そのあたりをウロウロしてるらしいよ。一か所に長くいることはないらしいから電話はあんまり意味がないんだって。」
「それで住んでるところはどこなんだ。」
「ホテルを転々としてるらしい。えらい安宿に泊まってた。」
「この会社知ってるけどそんなところで事業してるなんて聞いたことないな。なんで潜り込んだんだろう。」
「どうも今度こそ真面目にやろうとしたみたいだな。どうせバレるのは時間の問題だよ。」
「日本には帰ってこないのか。」
「だからきっと会社も持て余して鉄砲玉の島流しにしてるんだろ。出張で帰ってはいるそうだが。だけどなぁ、ベロベロに酔っぱらって『帰りたいよ。』なんて涙ぐんでたぜ。」
「あいつが?」
「そうなんだよ、びっくりした。変な話し方になってて日本語のうまいフィリピン人みたいだったな。」
「だけど帰ってくると何かいいことがあるのかよ。どうせ独身だろ。」
「それも焦りのウチさ。おれもお前も結婚してるって教えたらドッと酒が廻って話し言葉がひどくなって何言ってるか分かんなかった。シンガポールのいんちき訛をシングリッシュってんだが、それとアメちゃんの兵隊が使うガター・イングリッシュが日本語に混じりこんでるんだ。」
「僕はロンドンにいたときは一度もホームシックにならなかったがな。」
「オレも3年間は全然帰りたくなかった。」
「それが最も順応性があると思われるB・Bが泣いて帰りたいだって。椎野は何で日本に帰ってきたの。」
「家族のこともあるしね。だけどもうオレみたいのがやれる場所じゃないんだとも思った。」
「どういうこと。」
「バブル弾けてヤレ低賃金だ土地が安いだで中国詣でが盛んになっただろ。初めは上の方とパイプがある奴等が行くわけだ。外資の投資が欲しいから至れり尽くせりで大企業が工場造ったりさ。するとそれにつられて中小や怪しげなのがついてくる。そのドサクサにオレなんかが刺さりこめる所ができるんだよな。だれそれ知ってるとか金渡すとか。で、いいかげん時間が経っていい具合になるともうお呼びが掛からなくなる。もっともその後大体うまくいかなくなるけどね。」
「騙されるのか。」
「面従腹背だと思ってちょうどいいんじゃない。昔、倭寇っていたろ。あれ半分以上中国人なんだってさ。実態は武装商人でうまくいかなくなると暴れたんだな。それで街を占領したこともあったんだけど、漢人の方は倭寇がいる間はヘコヘコしてたんだって。『倭人はしばらくすると国が恋しくなって勝手に帰って行く。』と伝わってたらしいよ。」
「B・Bもそろそろってことか。だけどちゃらんぽらんの天才だったからな。あんな真似は僕達だってできなかった。」
「それにしても、『帰りたい』とは意外だよな。あんなゴキブリみたいなヤツがねぇ。どうせ飽きたんだろうけど。あいつ飽きっぽかったよ、そういえば。」
「そうだよ。詩人になったりシンガー・ソング・ライターになったりしてたよ。」
「哲学者だって言い出した時もあった。確かその後ロックンローラだろ。あと時々発狂してた。」
「それでもクビになってないんだから会社の役には立ってるのかね。とにかくいっぺん3人で会おうぜ。オレも電子メールのアドレス作ったからパソコンで連絡してみる。」
「会社に勤めたことないからあいつが役に立つかどうか知らんけど、僕だってそんなに世の中の役には立ってないと思うけど・・。」
「ウッ・・それはだな、オレは・・・社会の迷惑かもしれない。」
「もう30代になって久しいからな。」
「・・・・そうだったな。」
つづく (最終回へ)
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(1998流浪望郷編Ⅱ)
2015 MAY 17 21:21:31 pm by 西 牟呂雄

うっかりして、香港行の最終が出港してしまった。リスボア・ホテルのカジノでこのまま朝までいるしかない。バカラでこの時間から負けが込んだらえらいことになるので、しょうがないルーレットでもチビチビやるか。
席についてまずは色に張る、素人っぽく4枚・8枚・16枚と掛けて当たればまた4枚から張る。ディーラーが一番いやがるかけ方だ。どうせ勝たなくてもいいんだから、などと気を抜くと全部やられるから一応盤面からは目が離せない、酒のガブ飲みなんぞ以ての外だ。ポツポツとチップが溜まり出す。
するとやっぱり寄って来た、ヤバそうな若い女だ。やたらと露出の多いチャイナ・ドレスを纏ったのが隣が空いた途端に滑り込むように座った。
『ハイ、ニッポンジン?』
顔を見た途端にギョッとした。目の焦点が合ってない、こいつはさっき一本キメてきてラリったかハイになった典型的なジャンキーだろう。
『エニィシング トゥ ドリンク?』
うるさいな。オッと体を摺り寄せてきた。
『シャチョサン、ルームナンバー、100ドルオーケー。』
冗談じゃねぇ。無視プラス白目を剥いてやったらヘンッという顔をしてどこかに行った。
オレ(椎野 茂)は日本を離れて3年8ヶ月。巨額の借金を半ば強引に踏み倒して来た。もっとも金利は十分に払ったつもりだし、相手はまともな銀行だから融資担当の方も消えられるのが一番困るから適当な整理機構に移された時に自己破産してケツをまくった。いわゆるバブルの崩壊というやつだ。活動拠点は上海・香港・マニラでそれぞれ別の仕事をしている(ことになっている)。女房と娘にはいくばくかの金を送りつつ、まぁテキトーにしのいでいる。
上海ではレストラン、香港では雑誌の発行、マニラでは日本人専門の不動産をさばく(ことになっている)。あんまり羽振りが良くなるとこれらの場所では危ないから目立たないように稼いでいた。もうそろそろほとぼりも冷めた頃だろう、日本に帰りたいのだが。
今日はマニラに泊まる、久しぶりにマニラ湾沿いにあるいかがわしさ十分の飲み屋に来た。まさかいきなり女を買うわけじゃないが、飲み食いの時に一緒に座る女の子を選ぶシステムだ。食事は吹き抜けになっている2階部分で取り、一階はバンドが入って女の子と踊ったり、最近はカラオケもできる。日本人観光客はヤバすぎて滅多に来ないがそれでも駐在員のような多少スレた連中は来ることがある。
特徴のあるギター・イントロが聞こえてきた。ワイルド・チェリーの『Play that Funky Music』ではないか。身を乗り出して見入ってみるとヴォーカルはどうも日本人のようだ。『ヘーイ・ドゥ・イ!』の出だしがミョーにカタカナっぽい。こんな所で変なやつがいるなと思ったのだが、良く見ると見覚えのある顔なのだ。目が合った。
あいつ・・・B・Bだ。
奴は一曲だけ歌い終わると二階のオレの席まで来た。
「ユー、椎野だろ。」
「お前原部(バラベ)か、B・Bなのか。」
「ロング・タイム・ミス・ユー。15年ぶり?」
「こんなところで何歌ってんだよ。」
「おまえこそ、よくこんな店に来れたな。ここデンジャラスよ。」
「前にも来てたんだ。」
「ウワーオ。」
話していると馴染みなんだろうか、店のオネーチャンが『ハーイ、B・B』等とあいさつしてくる。
「マニラに住んでるのか?」
「ノー、ノー。出張だよ。あしたはタイペイだし。ユーは遊び来たの。」
「いや、仕事だ。月に一回は来てるよ。次連絡するよ。」
「うん、僕もしょっちゅういるから。ゴルフしようよ、チープよ。でもね、もう日本帰りたい。」
「オレも3年以上帰ってないな。そろそろ帰ろうかと思ってる。」
「そうなの。もう泣きくらい帰りたいよ。結婚した?」
「そりゃしてるよ。娘もいるしな。お前は。」
「こんな暮らししてたらとてもとても。いいなあ、帰りたい。」
いったい何をしているんだ、こいつは。
つづく
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(1998流浪望郷編Ⅰ)
2015 MAY 16 10:10:27 am by 西 牟呂雄

僕(英・はなぶさ・元彦)は学生時代にアメリカではなくヨーロッパを放浪した。なぜヨーロッパかというとまずイギリス、ビートルズの誕生したリバプールを見たかったからだが。僕達の世代はフラワー・チルドレンから少し遅れてきているのでヒッピー趣味はあまりない。それにどちらかというとガンガン鳴るハード・ロックよりもキンクスとかホリーズといった趣味だったこともあってロンドンを中心に動いたのだ。
ヤバい奴らは沢山いたがヨーロッパはどちらかというとヒッチ・ハイクの事故なんかは少なく、日本人自体がまだ珍しがられたせいもあって結構親切にもされた。僕が小柄だったことも相手に危険を感じさせなかったのだろう。
しかし冬場は寒かったのでとても移動する気になれず、アルバイトに精を出した。定住してみるとロンドンは安定感も感じる。何というか基本的な都市インフラは世界大戦前に終わっており(それも19世紀中に)古い物を長く手入れを重ねて使うこと自体が美徳だと思っているかの様だった。
僕は彼の地で行きがかり上(専門は英文学)ジョージ・オーウェルに凝った。
そして言うまでもないが、全く色恋沙汰には縁がなかった。
適当に見切りを付けるはずが1年半も滞在してホームシックも関係なく帰国することにした。日本の情報というか様子は、たまにめぐり合うバック・パッカーのような怪しい日本人から仕入れていたのでロクな話は入ってこなかったが、遂に金融・商社の駐在員といったエリートとは付き合うことはなかった。そういう人達には家族もいるだろうし、政治・経済関係に疎かったのでその辺のいきさつを長々と説明されるのが面倒だったのだ。流れ者は直ぐにどこかへ行ってしまいその後も付き合うことは無かったからその点気楽だ。すっかりそういう人間関係に慣れてしまい、滞在中はズッとそうしていたかった。日本に帰りたいとはあまり思わなかった。
それは英語の語感というか使い回しというか、日本語より遥かに硬質な表現に浸かっていたので、たまに日本人と話しているとピリオドの無いようなズーッと繋がっている会話・文章との際立った違いにうんざりさせられたりしていたこともある。
カズオ・イシグロは世界的に評価が高いベストセラー作家だ。彼は家庭内では日本語で両親と話しているそうだが、作品は完璧な英語である。これを翻訳するとわずかにニュアンスがズレる。
ハッと気が付いた。これは英語で身を立てられそうだ、と。
イシグロは偶然だが1954年生まれで僕と同い年でもある。
日本に帰ってから復学して大学院に進み、翻訳と教師をやりながら、僕は自分の道を見つけられたようだった。
ある日長年音信の途絶えていた高校時代の友人、椎野茂から電話をもらった。暫く東南アジアだか中国だかに行っていたことまでは知っていたが、こちらからは連絡できなかったのだ。
会話はのっけから衝撃的だった。
「オレな、マニラでB・Bと会っちゃった。」
「エッB・Bってあの原部(ばらべ)?」
「そうなんだよ。ビックリしたなー。」
「マニラでなにやってたんだ。」
「それがなぁ。フィリピン・バンドでヴォーカルやってた。」
「なにー!あいつ確かマトモに就職したんじゃなかったか。」
つづく
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(200X年 男子中学編Ⅲ)
2014 JUN 18 20:20:53 pm by 西 牟呂雄

E中学は私立男子一貫校で、中学受験をするため、みんな小学校の5・6年生の時は塾通いをしてくる。そのせいかどうか、何だか話しをしてても面白くも何ともない。初めサッカー部に入ったが同学年の奴等となじめず、すぐ辞めてしまった。そんな訳で、仲間と言えば席が近かったというだけの安直な理由で、同じクラスの4人仲間という具合になった。そして不思議なことに2年も4人が同じクラスとなり、まあ腐れ縁なんだろう。
英(はなぶさ)と出井、もう一人B・B(原部バラベと読む)というのがいる。
E中・高は自由闊達がウリになっているが、僕に言わせれば、生徒と先生が馴れ合っているようなもんで、もともと好き勝手にやっている僕としてはこの1年何とも居心地の悪い思いだった。マア仲間が4人もいれば良しとするところか。こいつらはある意味話していて楽しい。
しかしまぁその4人だって面白いことは面白いが、中身はバラバラだ。僕は自分で言うのはナンだが、みっともない服装が嫌いで中学生にしては凝るが、比較的おしゃれなのは出井くらい。英(はなぶさ)は全く気取らないで一年中ジーパンだし、B・Bに至っては支離滅裂だ。特に色の選び方がひどい。2年になってから、毎月髪の色を変えだしたのを見た時は、狂ったかと思った。
ところで僕は、どういうわけか真面目な兄貴の影響で芥川・三島・春樹くらいは読むが、先日の現代文の授業で太宰の『走れメロス』の感想文を提出しろ、と来た。小学生じゃあるまいし、よりにもよって。それで登場人物のステレオ・タイプぶりをおちょくり倒し、太宰のテーマへのアプローチのあざとさを批判するような文章を提出したところ、何と放課後に来い教官室に来い、を食ってしまった。多少予想された説教であったが『こうひねくれた感想は奇をてらったつもりでも結局陳腐なものにしかならない。もっと中学生らしくあるべき友情の・・・・。』と説教されてマイッた。友情と言われても頭に浮かんだのはあの四人だし。と思いながら教室に帰ると、あいつ等が心配して待っていたので、念のためどんなことを書いたのか聞いた。
英「まァオレは『この王こそが最もメロスの帰りを待ち侘びていたに違いない。』とまとめた。」なかなかやるじゃないか。英は小説を好むけれど洋物中心で、不思議なことに1960年代のことにやたらと詳しい。黒人公民権運動の指導者マーチン・ルーサー・キング牧師がやったという有名(らしい)な長い演説を暗記していて、『アイ・ハヴ・ア・ドリーム』と抑揚たっぷりにスラスラ喋ったのでビックリした。ギターを弾きながら『花はどこへ行った』とか『サンフランシスコ・ベイ・ブルース』といったフォーク・ソングを歌って見せたりもする多才な奴だ。ビーチ・ボーイズという聞いたこともないバンドもこいつから教えてもらった、結構イケてる。
出井「オレとしては途中メロスが襲われるところが切ないが、体力の回復と共に気力が漲ってくるところが『命』の躍動だ、としておいた。」出井は古典趣味で、また熱中すると深読みのしすぎといった趣があってついていけなくなる。この前の日本史の授業中、平安時代の院政の発表をしたが『政治をすると言っても官位の人事をするだけで、この時代に民衆の幸福を考える皇族も貴族もいるわけないから、おべんちゃらか女や稚児さんの取りっこぐらいしか評価の基準はありません。そのスキをついて武士がですね・・・。』とやって教師を激怒させていた。
B・B「僕は『あんなに一日中走れないから、どうせならセリヌンチウスの方になる。』って書いたな。」バカ。マンガの読みすぎで人格の浅さが丸出しだ。
男子校だから女の子に興味深々のやつらばかりのはずだが、あいつ等は口では『女日照りだ。』とか『彼女ほしい。』とか言うくせに、僕に言わせれば女に免疫がないとしか見えない。要はちょっとしたセンスの問題で、そういうことであればあるほどそのセンスの有る・無しは致命傷だ。奴らは永久にだめだろう。
まあ、この手の遊び話は学園内では大したことにはならないし、いきおい外の世界で遊ぶとなるのだが、しかし残念ながらE中学のブランドネームが効いてしまって、そこでは僕がガキ扱いされてしまう。お坊ちゃん学校ということで、ドスが効かないことおびただしい。
おまけにチーマーのアンちゃんになればなったで、これが又ケンカばかりしている本当のバカとか、恐ろしく話しが下品な奴とかは願い下げだから、何でも仲良くなりゃいいってもんじゃない。結局クラス仲間の4人組となってしまう。
2004年恐ろしく暑かった夏が終わり、秋空の下運動会の準備が始まった。
これが又煩わしいことこの上ない。とにかく男ばかりだ。華やかなアトラクションなんか全く無し。競技は高等部が棒倒しで中等部が騎馬戦だけ。そして、その合間にばかばかしかったり、卑猥極まりない応援合戦。それを中高一緒なもんだから、朝から夕方まで延々とやる。
いっそさぼってやろうかと思っていた矢先にクラスの委員選考があった。応援とか何だかんだでクラスの半分くらいは委員をやることになるが、多少の例外を除いて自分で手を挙げる奴はいないから、やれアミダだジャンケンだとやっていたら僕が競技委員になってしまった。これは、いわばクラスの競技のマトメ役で、練習の段取りからチーム編成までやらなければならない、極めてウザイ。
一月前から、体育は全部運動会の練習だ。といっても当日サボリを決めるつもりの奴から、まるっきりオマカセの奴、やたら張り切る奴、まとまりの悪いこと甚だしい。とにかくこんなガキの遊びみたいなもんに付き合うだけでもアホらしいのに、冗談じゃない。
一回めの騎馬の組み合わせからしてモメた。僕達はちょうど4人で組んだが、一人足りないだのあいつとは組みたくないでスッタモンダ。やっと全てが編成されいよいよ立ち上がる時、我が騎馬は崩れた。僕が上に乗ったのだが、英が小柄なためバランスを崩し、走り出した途端に僕はもんどりうって落ちた。何たることだ!
「もうイヤんなった。」
「とにかくウチの騎馬だけでも何とかしよう。」
「うん。おれも思うんだけど上に乗せるのは英の方がいいと思う。」
「だけど、オレが上じゃあ組討になった時は戦力にならんぞ。」
「いや、まあ聞け。」
出井が言うには、実際に組討になった時は見たところ掴み合いになって、ほとんどが両方とも潰れている。それよりも機動力を出して、体当たりで相手の馬を倒した方が確立は高く、剣道でも体当たりは有効な技とされているそうだ。剣道部の出井が言うのだからそうなのかもしれない。急遽僕が前、右出井、左B・B、騎乗英に変えて御丁寧にも昼休みにまで練習した。
ある日B・Bがノートを広げて真剣な声で言った。
「僕は艦隊運動の研究をしているけど、こんなこと考えたらどうかな。」
作戦要務令と書かれたノートには、『五輪陣形』とか、『錐揉陣形』という複雑な陣形にあいつが考えた空母機動部隊が配置されていた。それにしても空母『天狗』とかイージス『高天原』、潜水艦『酒呑童子』とはどういうセンスか。何のためにこんなことをしたのかは知らんが。
「こんなことできる訳ないだろ。」
「いや、使える。」
発案者のB・Bは無視して、英、出井と検討した。
結果、僕達の騎馬が先頭になって、全騎馬が楔形で突進するものと、二つの固まりになってび両側からV字型に挟み撃ちにするものが有効だということになった。
体育の練習の時に、まず教室に集めて説明をすることにした。説明は出井。
「皆ちょっと聞いてくれ。」
こんな時ガキみたいな奴らは単純に乗ってくるから扱いやすい。ヒネた小僧なんかがツベコベ言うと面倒だが、出井は他の3人より信頼が厚いのでこういう時うってつけだ。各騎馬の配置まで決めて、黒板に書き出した。この際楔形は『くさび』、V字型は『鶴翼』と命名された。早速練習するとこれがまた絶望的に動きが鈍い。ダメだ。紅白戦にもなりゃしない。もっぱらワーワー言いながら言ってみれば蛇行行進の稽古をしているようなもんだ。
ところが面白いもんで、1週間もするとアラ不思議。慣れるに従ってみんなキビキビとかなり機動力がついてきた。しまいには上から英の号令の下、楔ー鶴翼ー楔といった複雑な動きまでこなせるようになった。ひょっとしたら。
当日は良く晴れた運動会日和というやつだ。騎馬戦は中学学年ごとの5クラス総当り。なんとなく皆も張り切っている。いよいよ2年の出番だ。円陣を組んで僕がエールをかけた。
「いいかー。」「うおー!」「ぜーってーまけねー!」「ウオーッツ!」段々声もでかくなる。よーし。
騎乗して、合図が鳴ると同時に英の号令がかかる。「くさびー!楔だ!」
結果は正に鎧袖一触というやつだ。びっくりした相手をまるで踏み潰すみたいに追い散らして圧勝した。次ぎもその次ぎも圧勝。こうなりゃ全勝優勝だ。
「みんなー。彼女いるかー!」「いねー!」「彼女ほしいかー!」「ほしー!」「全勝して合コンだー!」「ウーオー!!」最後の声はとりわけでかかった。
合図が鳴って得意の『くさび』にかかったところ、何と驚いたことに相手も同じような形をとるではないか!あわてた英が大声で号令している。
「くさびじゃなーい!カクヨクー、両側広がれー!両翼上がれー!。」
相手も研究したのだろうか、それどころかこちらが体制を変えている間も「ウオーッ」の歓声とともに突っ込んでくる。先頭の馬はサッカー部の頃から僕と何かとソリの合わない飯田ではないか。
「オイ、椎野!飯田の狙いは初めからお前だけだ。潰されたらこっちは総崩れだぞ!」
「上等だ。前進するぞ!」
中心の僕達が突撃したので、きれいに両翼に分かれかけた鶴翼がW字のようになったまま激突した。そのまま揉みあっていたが、向こうも引かない。足まで踏んできた。このやろーと反射的に首を振りながら、左目の上で飯田の鼻のあたりにバチーッと頭突きした。セコいケンカの時にやる手だ。
『ゴッツ!』と音がして「ウーッ。」と呻きながら飯田が膝を屈した。ざまーみろ。
ところが、全体がメチャクチャな潰しあいになった時に、飯田が復活してきて鼻血で胸と顔を真っ赤にしながら、掴みかかってきた。
「椎野ー、やりやがったな!」「やめろ!オレは両手塞がってんだ!」「知るか!きたないことしやがって。」飯田は僕に飛び掛ってきた。
その時左側のB・Bが間に割り込むように入ってきて、飯田のわき腹をドスーと蹴り上げた。おかげで英は頭から落ちた。飯田も再び「ウーッ。」とうつぶせになってしまった。B・Bはそのままサッカーボールを蹴るようにキックしている。押し寄せてくる奴らを制して振り向いた。
「出井!B・Bを張り倒せ、飯田にケガさせるぞ!」
出井は豹が飛び掛るみたいに素早くB・Bに飛びついて2人は転がった。
ガキのケンカは双方の犠牲が同じになれば終わりだ。転がってるのが飯田とB・Bになって双方の睨み合いになった頃、やっと高等部の審判部員がフォイッスルを吹きながらやってきた。結果は没収試合。ヤレヤレ。
ところがそれでは済まなかった。実行委員会審判部は聞き込みの結果、倒れてからのB・Bの蹴りを暴力行為として重く見て、休み明けのクラス討議にかける旨決定した。
そして休み明けのホーム・ルームに高校生の応援団長、審判部長、競技委員長がやって来た。
曰く、審判部としては、競技中のケガについては正々堂々としたものであれば不問に付すが、今回は、詳細に検討した結果見過ごす訳にはいかない、E学園の自治と自由を守るためにも、諸君の真剣な討議を踏まえ、我々は学生を処分することはできないので、職員会議にあげて検討してもらう、その際の処分には停学、退学もあり得る、云々、クドクドと喋った。何が自治と自由だ、たかが中学生のケンカぐらい裁けないで笑わせると思った。
それがどうしたことか、クラスの反応が違う。坊ちゃん育ちの子供達は『処分』にビビッたか。椎野の頭突きはやりすぎだ、B・Bは協調性がない、せっかくの運動会がぶち壊しになった、どーした・こーした意見が出て、全体がB・B非難の論調に収斂していく。なんてこった。こういう奴らがそのうちエリートにでもなって、E学園の校風は素晴らしかった、などとぬかすのかと思うと、胸糞が更に悪くなった。スケープ・ゴートを見つけて後は知らん、の根性が見えるようだ。全くガキは始末に負えない。
と、僕の後ろでガタッと音がしてB・Bが立ち上がった。不貞腐れている。
「オレもういいッス。皆で決めてくれ。」
と言うと、クラスを飛び出してしまった。イカン。英と目が会った。格別のニヤニヤ笑いだ。英は機嫌の悪い時にニヤノヤする癖があった。出井は怒りで真っ青というか、緑っぽくなってしまっている。まずい!
「ちょっと待てよ。オイ少し違うだろ。アクシデントとケンカだろ。先輩達も処分だ何だ言わんで下さい。この程度で処分にされるなら騎馬戦なんかやらずにカケッコでもやってて下さいよ。オイ、皆クラスで処分だなんて結論出すのやめろよ。」
同時に英と出井が席を立った。ヨーシ、こんな坊ちゃん学校でたかが小競り合いに一遍に4人も処分なんかできるもんか。そう思って胸を張って外に出た。
「B・Bはどこだ?」
「カバン持ってないから帰ってないよ。多分あそこだ。」
出井が連れて来た所は、体育館の裏側だった。秋の日が眩しく差している塀の隅に黄色く染めた髪を鮮やかに反射させてB・Bがうずくまっていた。
ハッとしたが、運動会のクラス・カラーは黄色だ。あいつまさか運動会の黄色に合わせるために春先から毎月髪を染め出していたのか?いや、そんな計画性の有る奴じゃない。
「あいつなんであんなとこにいるの?」
「さあ、前にアリの行列で遊んでた。」
「何だ、そりゃ。」
それはともかく声をかけようとした矢先、「待て。」と英が止めた。
「今声かけるとアイツ引っ込みがつかなくなって口が滑るかもしれん。ありゃ悔し泣きだよ。」
「エッ。」
全くガキは手がかかるが、まあいいか。
「夕刻のセリヌンチウスだな。」
「メロスは声をかけないのも情のウチ。」
「じゃ行くか。」「ああ。」「うん。」
振り返って歩き出すと、真っ赤な秋の夕日で僕達3人のデコボコな長い影が伸びていた。
おしまい
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(200X年男子中学編Ⅱ)
2014 JUN 12 20:20:34 pm by 西 牟呂雄

B・Bは不思議な奴だ。
育ちの良いお坊ちゃんなんだが、何を考えているのかさっぱり分からない。一年生の時に席が隣だったので仲良くなったのだが、一年付き合って益々訳が分からなくなった。計画性といったものがまるで無くて、思いつきだけで生きているようだ。発想が自由なのは中学生らしくて構わないが、余程甘やかされたせいか常識に欠けている。まさか犯罪を犯すとは思えないが、突拍子もないことをしては本人は気付かずに周りが慌てることが何度かあった。
二年生になった途端、髪をピンクに染めてきた。茶髪は何人もいるがさすがにピンクはあいつだけだ。更に連休明けには真っ赤になった。狂ったのかと思ったら六月には草色にした。どうしたことかと聞いてみると、一年間で十二色を達成するのだそうだ。
「7月からは夏休みだから黒くしてるけど、虹の七色とピンク、草色、後どうしたらいい?」
一体何のためにそんなことをしているのか分からない。
そう言えば、去年は自分で仮想連合艦隊を仕立てて喜んでいた。こっそりノートを覗いたらB・Bが名付けたイージスやら空母の絵が書いてあって、イージス艦は『高天原』とか『岩戸』、空母は『天狗』『夜叉』だった。どういうセンスなんだ。
僕らの通うE中学は男子中高一貫校だからクラブ活動は高校生と練習しているので、中学大会では結構強い。団体競技が苦手なので剣道部に入った。そこでもそこそこ仲間ができたが、たまたま二年でも又同じクラスになったので、友達といえばちょっと変だがB・Bと、やたら英語が好きな英(はなぶさ)、ちょっとヒネてる椎野の四人組か。
ある日剣道部の練習を終えて、体育館から出て裏のほうに行ったらすみっこに奴がうずくまっている。こんな時間まで何をしているのか、と声をかけた。すると『アッ』とか言って慌てて立ち上がった。
「お前こんな所で何やってんだよ。」
「何でもない、何でもない。」
楊枝が地面にいっぱい刺してある。
「ナンだそれは。」
「何でもない、何でもない。」
地面を覗いて見ると、蟻の引越しの行列があって、それに沿ったように楊枝が何本も刺してある。それが幾筋もの線になって、奇妙な幾何学模様のようになっていた。どうもB・Bが蟻の邪魔をしてルートを変えさせるように楊枝を刺しているのだ。
「お前。いつからこんなことやってんだ?」
「いつって、うーんちょうど三日目かな。」
「・・・・。」
又別の日。放課後、一人体育館で『突き』の練習をしていた。何故か両手を一杯に伸ばしてカウンター気味に決まる突きが好きで、中学剣道では禁じ手だから稽古の後に型の練習をしていたのだが、そこにひょっこりB・Bが顔を出した。
「出井。こういう型やってみてくれよ。」
竹刀を手に取ると、半身でライフルで狙いをつけるような恰好で、竹刀の刃を外側に寝かせ右肘が高く上がるように構えた。やってみると微妙に窮屈だ。
「それで突いてみてくれ。」
というので、えいっ、と突いたが半身の分だけ剣先が伸びきらず、やはり両手を伸ばした方がいい。
「そんなのじゃだめだ。左足を踏み込んでヤッと突いたらすぐ引く。続けてヤッ、ヤッ、と3回踏み込まなきゃだめなんだ。」
「ヤッ、ヤッ、ヤッ!」「遅い!それにもっと踏み込む!」「ヤッヤッヤッ!」「遅い!もっとヤヤヤっと!」
「ちょっと待て。なんでオレがお前なんかに指導されなきゃなんないんだ。」
「ねえ、どんな感じ?人が切れそうかな。」
「・・・・鋸引いてるみたいで窮屈だな。」
「ふーん。そうか。だめかな。」
何を考えているんだ。さっぱり解らない。ところが僕は凝り性なので、さっぱり解らないまま、時々思い出してはやってみた。
合宿で師範の道場に泊まっていた時、朝練の素振りの後に思わず『ヤッヤッッヤッ』をやったら師範が目を丸くした。
「出井。今の型はどうした。」
「いや。何でもありません(B・Bみたいな喋り方だ)。」
「それは実践剣術だ。そんな練習をしても現代剣道では使い物にならん。試合では使えないから。第一君はまだ中学生だろう。型を崩すと太刀筋が悪くなる。誰に教えられた。」
「何でもありません、何でもありません。」
「フム。天然理心流だよ。」
「てんねんりしんりゅう、何ですかそれ。」
「新撰組の剣法だ。今のは沖田総司が得意にしていた、天然理心流の『突き』だ。」
周りがみんな驚いた。
だが何でB・Bがそんなことを知っていたのだろう。それよりその後剣道部では『総司』と言われるようになってしまった。いい気分だ。
夏の都大会が始まった。ウチの剣道部はOBの面倒見が異常に良く、試合にも大げさな応援が来て盛り上がる。部員も多いので、A、B2チームがエントリーしていて、僕はBチームの中堅だった。
2回戦までは順調だったが、3回戦となるとBチームはかなり苦しい。先鋒、次鋒があっさり抜かれた。相手は僕よりでかい。3年生じゃないだろうか。蹲踞から竹刀を合わせると『チエーイ!』と物凄い気合を発している。この暑いのにうるさい、と思った瞬間『メーンン!』と飛び込んできて体当たりしてきた。この野郎、これが得意か。またやるぞ、来た!『メーン!』突っ込んでくるデカゴリラを竹刀も合わせず、右半身を開いてかわしたところ、僕の肩越しに首一つでかいそいつの面が振り向いた。僕も気合を発した。
「ヤッヤヤ!」
しまった。例の突きがカウンターで3発きれいに入っちまった。
「反則!」
師範が鬼のような形相で僕を睨んでいた。E中Bチームの夏が終わった。
夏休み明けに早速B・Bを捕まえた。
「おい、おまえが何で新撰組の剣法を知ってるんだ。」
「ん?何の話だ。」
「お前が教えたあの『突き』だよ。沖田総司の得意技だそうじゃないか。」
「そんな人知らないよ。あれはオレが考えた『飛龍剣』って言うワザだ。あれ役に立ったか?あともう一つは『蛟竜剣』って言うのも有るんだけど今度教えてやる。」
「・・・・。もういいよ。・・・・。」
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(200X年男子中学編)
2014 JUN 6 17:17:25 pm by 西 牟呂雄

僕の苗字は「バラベ」というのだが、読みにくいのでみんなは「B・B」と呼ぶ。都内の中二だ。
毎日遊ぶのが忙しい。ゲームの進化が早くて、ちょっと気を緩めると流行から遅れる。メールはひっきりなしに来る。パソコンもいじる、たまに勉強もする、クラブ活動もしている。夏はキャンプにも行ったし、冬はボードだなんだで一年中飛び回っている。一体僕は何なんだろうか。周りの同級生は天才からアホまで一通りいて、僕自身は天才でもアホでもなく、真面目でもないが、ドスの利いた不良じゃないあたりだろうと思っている。
夢がないのかと言われれば無いようで、将来不安は無いのかと言われれば、あるような気もする。大体何か欲しいとか、何をどうしたいといった気分が沸いてこない。こんなチャランポランでいてはロクなもんにならんことくらいは分かっている。僕の身近に恰好の反面教師がいるからだ。
それはウチのオヤジだ。
僕は一人息子なので、チビの頃は大層甘やかされて育ったと聞いている。母さんがナントカいう難病とアレルギーで入退院を繰り返すので(今もだが)オヤジ本人の言によれば”必死”に可愛がったのだそうだ。実態は病身の母さんの手前一人でほっつき歩くのが具合が悪かったので、僕を連れてヨットだスキーだと繰り出し、色んなワルサを口止めするためビールを飲ませたりした。これを可愛がったと言うのだろうか。
オヤジが一体何の仕事をしているのか未だに僕には良く分からない。朝は僕より遅く起きるし、月給をもらって来るので会社勤めなのは確かだ。スーツを着てると普通のサラリーマンに見えなくは無い。時々びっくりするような有名な会社の話しをしている。年中海外に行くが、行き先は決まってなくて『今は中国にいる』とか『ここはカナダだよーん』といったメールが来るだけ。この前は真夜中に電話があって、慌てた母さんが一緒に来いと言うからタクシーで最寄の駅まで行くと作業服を着て道端で寝転がっていた。その時はつくづくこうはなりたくない、と思ったもんだ。向こうも薄々そう思われていると知ってるらしい。一度あまりに勉強しない僕に真顔でした説教にあきれた。
「お前その調子だとオレみたいになるぞ。」
2004年の7月は目が眩むほど晴れが続き、先が思いやられる夏だった。期末試験が終わり、あしたから休みの日、クラブ活動をして遅く帰ると、オヤジがヨットに乗りに行くところだった。何も予定が無いから、僕もついていくことにした。油壺に停泊する愛艇エスパーランサーに泊まる。
ところでこのヨットも不思議な船で、いったい誰の持ち物なのかわからない。オヤジは『おれのもんだ』と言うのだが、いつも一緒に乗っているオッサン達もゲストを連れて来ると『オーナーは私で他の連中は皆クルーです。』と自慢しているのを何回も聞いた。オッサン達が何者なのかも良く知らない。しょっちゅう長い航海に出ていて、以前はこの人達のことを漁師だと思っていた。
朝、キャビンで目が覚めると、寝る時はいなかった二人のオッサンが転がっていた。外に出るとデッキにはウイスキイの空瓶や空缶が散らばっていて、夜遅く来てから飲んだくれたのだろう。そうなると当分起きて来ないから、ヤレヤレと湾内を散歩した。油壺はフイヨルドのように曲がっていて、どんな時化の時もうねり一つ入らない良港だ。差し込んでくる朝日に山の緑がきらきらしている。入り江の水面は、外洋みたいにブルーじゃなく、周りの森を映してグリーンだが、目を凝らして一点を見ていると、ヒタヒタ満ちてくる潮の中に小さな魚影が分かる。ひと時もジッとすることなく動き回る。ボラだろうか、大き目の魚が泳ぎかかると、一斉に群れが弧を描いてさざ波が立つ。オッチョコチョイはジャンプする。汗ばむ程の夏の光の中、僕は何時間見ていても飽きないだろう。ボラ、カニ、小魚の群。アーア、こいつ等もヒマなんだろうなあ、と歩いていたらガサガサと小さい音がする。そっと林の中に入ると、何とセミがひっくり返って死にかけている。孵化に失敗したのか、羽がクチャクチャになって飛べないのだ。だけど何年も真っ暗な土の中にいたんだろう。やっと地上に出てきたのにうまく飛べずに死んでいくセミがかわいそうだと思った。暫く見ていたが、まだ足が動いている。死ぬところを見たくなくて、走って逃げた。
「オーイ、メシ食いに行くぞ。」
やっと声がかかった。ボチボチ起きて来たんだ。メシといってもビールをガブ飲みするんだろうけど、湾内の定食屋に行った。
出港してセールを上げる。風を一杯に孕んだ帆は生命の躍動感を感じさせる。波をかき分け、乗り上げながら進むワイルドな感覚は実に爽快だ。今日はやや凪の薄曇り。遮るものも無い風に、強い紫外線を浴びながらヒールした右舷から足をブラブラさせて三浦の陸地を見ていた。だけど僕は死んだ(だろう)セミのことが頭を離れなかった。あの森の中に一体、何億何兆の命があることなんだろう。
「よーし、タックしようか」
オッサンのうち舵を取っていた通称『キャプテン』から声がかかった。僕はジブセールのロープをほどいて合図を待つ。『セーノ』の声でリリースすると、大きく傾ぐ船の反対側に移動し、もう一本のロープを手繰りウインチを巻く。一番下っ端は忙しい。
江ノ島までセーリングしてマリーナに入れた。このあたりは古いリゾート地だから、垢抜けない『おみやげ』やら『射的』だの『スマートボール』といった看板が並んでいる。
ところが上陸したオヤジ達は『久しぶりだなー』と感動し、スマートボール屋に大挙してなだれ込んだ。これは白いビー玉をピンボールみたいに遊ぶ子供用のパチンコみたいなもんだ。何人もが並んで『ギャー』だの『やったー』だの言いながらはしゃいでいるのは不気味だが、ふと気が付くと一緒になって大騒ぎしている自分が情けない。何しろ子供は僕だけだから『いい年してみっともないだろ』くらいは言わないとならないんじゃなかろうか。散々騒いで又船に乗った。
帰りの航海は珍しいほど静かで、鏡のような海をセールも上げずに帰港した。風も波もないヨットは渡し舟みたいなもんで、オヤジ達はすっかりやる気を失くし、舵を僕に任せて買い込んだビールを飲みだした。
「B・B、何だか元気ないな。」
実は死んだセミのことをまだ考えていた。何年も土の中にいて、やっと羽ばたく段になったのに、運悪くグロい姿で死んでいった哀れなセミ。言うかどうか迷ったが、行き交う船も見当たらない退屈さから『実はねー』とその話をした。
「いや、そりゃそんな惨めなもんじゃない。何しろ生まれた時から土の中だから自分が惨めだなんて気付いてないんだ。」
「そうそう。結構蟻の巣を掘ったりミミズに出くわしたりして遊んでるわけよ。B・Bがゲーセンに行く感じだな。うん。」
「それがいい加減年寄りになって、ああ疲れた、とか言って出てくるんだろ。一週間で死んじゃうんだっけ。」
「しかも日が昇ると急にサカリがつくわけだ。生まれて初めて明るくなって『やりたい、やりたい』ってなるんだな、これが。」
「で、やったらオシマイ。ナンマンダー。」
「してみるとB・Bの見たやつは光にビックリしたギリギリのところで死んだんだ。」
「かえって良かったんじゃないか。雑念で頭が一杯になる前だからな。」
「うーん、うらやましい死に方だ。ワシ等はもう手遅れだからな。」
これが分別のあるオトナが中学生にする話だろうか。哀れなセミの話がいつのまにかうらやましい死に方になってしまった。オッサン達に口を滑らせた僕がバカだった。今後この手の話をするのは金輪際やめだ。
油壺に帰港すると、今日はこのハーバーのお祭りなので、知らないゲストの人達が一杯来ていた。バンドが入って飲むは踊るはでドンチャン騒ぎだ。オヤジ達がいつも演っている『サンフランシスコ・ベイ・ブルース』をみんなで歌っている。うるさくてキャビンでは寝られず、オヤジと二人、テントで寝た。といってもキャンプ場でも何でもない近所の公園だ。テント暮らしも嫌いではないが公園だとホームレスに思われるかな、と思いながら寝た。
翌朝カッとする日の光で目が覚めて、モソモソしてたら珍しく先に起きていたオヤジが外から声をかけた。
「起きたか、これ見てみろ」
這い出してみると、テントの端っこをジーッと見ている。視線の先をたどるとたくさんのセミの抜け殻がくっついていた。そうか、こいつら命を散らしに行ったんだな。
二人で黙ったまま暫く抜け殻を見ていた。
つづく
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(198X年女子高編Ⅲ)
2014 MAY 9 19:19:48 pm by 西 牟呂雄

「ごきげんよう。」
E女子高独特の挨拶をしながら、鮨屋ののれんをくぐると、そこには異様なオヤジが4人いて、既に飲んでいた。それも4人とも違うものだった。ビールと焼酎と日本酒にウィスキィだった。
今回は相手が相手なのでファッションは各々勝手にしたところ、B・Bは例のスーツ、英元子はトックリのセーターにジャケット、椎野ミチルは例によってハマトラ、出井聡子はワン・ピースとそれなり。だが、オヤジ達は見事に予想を裏切って、業界風ジャケット、ジーンズ上下、濃紺のスーツ、そして遊び人風着流し!事前に椎野ミチルが『何か相当壊れたオッサン達らしい。』と言っていたのもうなずけた。
その中の業界風が、時々椎野ミチルを映画に連れて行ったり、食事をご馳走してくれる、彼女に言わせると『アニイ』なのだそうだ。
「ごきげんよう。アニイ。」
「オウ、何かもめてるっつー話しだからこっちもあらゆるバリエーションに対応できる面子を揃えたよ。まあスシ食いねー。」
豪華な鮨桶が運ばれ、早速パクつきだした。
「(アニイ・ウィスキィ)じゃ一応自己紹介と行くか。合コンの礼儀だからな。広告代理店をやってるイベント屋だよ。趣味バクチ。別にヤクザじゃないから、そこんとこヨロシクウ。」
「(着流し・ビール)僕は物理屋、この着物シブいだろ。ネット関連やってて今は受験産業で食ってます。」
「(スーツ・焼酎)オレはアジア屋。オレ一人マンサラだ。サラリーマンね。趣味ヤ・ザ・ワ、よろしくゥ。」
「(ジーンズ・日本酒)オレは英語屋。ブスっとしてても機嫌悪い訳じゃないんでご心配なく。大学で教えてます。趣味翻訳。」
「あのー。どういうお仲間なんですか?」
「ミチルちゃん達と同じさ。高校の同期だ。それじゃそっちもやってよ。」
「はあい。私は椎野ミチルです。アニイの会社でキャンギャルやったんで知り合って、時々映画みたりご飯ゴチになってます。」
英元子と出井聡子はなんというカマトト喋りか、とあきれた。
「私は出井聡子と申します。テニス部やってて、あとお料理が好きです。ずーっと女子校なんで男の方の考え方に興味あります。」
「私は英元子です。英語のエイと書いてハナブサです。フオークソングが好きでギターやってます。」
「へー。オレ達フオークバンド仲間だったんだよ。」
「ウソー。どんなのやってたんですか?」
「サンフランシスコ・ベイ・ブルース。」
4人が一斉に答えた。
「ナンですか?それ。」
「ぎゃはは。」「オレ達のテーマ・ソングだよ。」「現存する唯一のレパートリー。」
「あのーわたくしは・・・・。」
「どういうバンド編成なんですか?」
「あのーわたくしは・・・・。」
出井聡子が気がついて、英元子に目配せした。出鼻をくじかれたB・Bがすっかり上がっていた。緊張のあまりウルウル状態だ。
「原部玲と申します。バラベなんて読みにくい名前なんで皆様B・Bとお呼びになります。クラブはバスケットをやっております。趣味は読書です。それから・・えーとー・・・。」
「お嬢さん、お嬢さん。」
すかさず合いの手がはいる。こういうときはオヤジは役にたつ。
「はい。」
「オレ等はみんな妻帯者でヘタすりゃあなたくらいの娘がいてもおかしくない。だからそんなに硬くなんなくてもダイジョーブ。こう喋れって誰かに言われたのかい?」
「はい。わたくしの母に今日の会食の話を致しましたところ、」
「チョット待った。コレ一口のんでごらん。」
英語屋がニコリともしないでグラスを差し出すと、自分の日本酒を1/3ほど注いでやった。B・Bは両手でグラスを持って香りを味わっていたが、クッと一息で飲んでしまった。
「あー!おいしー。」
やがてボナールの話になったが、オヤジ軍の絶妙の捌きで、いままでのような大騒ぎにはならずにすんだ。熱くなりそうになると、軽くチャチャが入り、突っ込みをいれ、笑いに持ち込む。正にオヤジ恐るべし!である。こんな具合だ。
「しかし、そもそも男女の前に男同士、女同士で厳密な友情がそこらじゅうにあるもんかね。オレ等は一番ヤバイ悩み事をこいつ等に相談するように見える?」
「恋愛っていうけど僕達の仲間で熱烈恋愛をして彼女の自慢までしてたマヌケはもうバツ2で、この暮れに性懲りもなく3回目の結婚だよ。又呼ばれてんだけど祝辞のネタがない!」
「そんな厳しいことを言われると、オレ達があと50年くらいして、女を見ても何にもときめかなくなってからじゃないと、友達になってもらえないじゃないか。」
「大体君達の倍以上人間をやってるけど、愛だ恋だなんて未だに分らんよ。煮詰まって切羽詰ってもうニッチもサッチも行かなくなった時思わず『結婚してくれ』って言っちゃったんだもんなー。」
「そういやーこの前同窓会に行った時、隣に座った美人に『旧姓はなんですか。』って聞いたら、『昔、愛してるって手紙をもらったヒカワトモコです』とか言われたが、おりゃーそんな手紙を書いたことも忘れててもう面目まるつぶれ、よ。オレのセイシュンを返せ!」
「だけどさ。友情・友情っていってテンパってたら、そのうち男道、すなわち衆道に走ることになりゃせんか?」
そして、オヤジ軍はギャハハと笑いながらのみ続けた。彼等はお互いに名乗った名前では呼び合わず、『イベント屋』『物理屋』『アジア屋』『英語屋』と語りかけるので、結局本名は最後まで分らなかった。
しばらくたって、椎野ミチルは、B・Bに呼び止められた。みると、見違えるようにキレイになって、キチンと髪をウエーブさせている。
「ごきげんよう。ねえ、ミチル。」
「ごきげんよう。玲、どうしたの?」
「聞いて欲しいの。アタシあのおじさん達に又会いたいの。」
「はあー?どうしたの、急にしおらしくなって。」
「あたし、あの人達の言ってることが良くわからないの。」
「そんなこと心配することないよ。アニイたちは嘘ばかり話してんのよ。」
「違うの!この前分ったの。あたしが一番バカだって。」
「頭が悪いとは思わないけど、まあ、時々変にはなってる。」
「皆がB・Bっていうのは、バカでブスっていう意味なのよ。」
「はあー?・・・・。」
「ねえ聡子。」
「アラごきげんよう、ミチル。あたしも話あるの。」
「それがさ、B・Bが変なの。まあ元から普通じゃないんだけど。何か壊れてきてるみたい。いきなり又アニイ達に会いたい、だって。」
「アラ、あたしもお願いしようと思ってたのよ。」
「エッ!・・・・」
「結局この秋3回合コンやったけど、一番気楽だったじゃない。」
「気楽と言えば、それはそうだけど。」
「ミチルだって後でスッタモンダしなかったじゃない?」
「それはそうだけど・・・・。」
「今度はあたし振袖にしようかな。お正月以外に着たことないから。フフフ。」
「・・・・・あの、・・・・。」
「元子、元子、チョッ、ちょっと来て。」
「なあに。」
「アナタは正常よね?」
「何言ってんの?当たり前じゃん。」
「もう元子だけが頼りよ。ねえ、聡子と同じクラスにいて何か変だと思わない?」
「別に、変じゃない。」
「そうお?お願いだから元子だけは普通でいてよ。」
「何よ。ミチルこそどうしたのよ。何焦ってるの?」
「だから、変なのよ。B・Bは壊れかけているし、聡子は変だし。あのオッサン・コンパ又やりたいって言い出したのよ。」
「っていうかー、B・Bは元々少し変わってるしー、聡子だって、ねえ。そういえばB・Bキレイになった気がする。普段だらしなさすぎるからだろうけど、少しかまってるよね。だけど面白いじゃん。あたしサンフランシスコ・ベイ・ブルースって曲調べたのよ。」
「・・・・。」
「オリジナルはアメリカの古いフオーク・バンドで、それを日本の武蔵野何とかっていうマイナーなバンドがリメイクしてるのよ。」
「・・・・・一体どうなっちゃうのかしら。・・・・。」
「何が?」
かくして、椎野ミチルの絶望感にも関わらず、2回目がセットされた。おりしも巷にジングル・ベルが奏でられるクリスマス・シーズンになっていた。場所は例の『物理屋』が別荘を持っているという富士山麓でのパーテイーと決まった。午前中から始めて、日没とともに帰京する、という趣向なのだそうだ。
4人は冬休みである。25日当日、駅に集合した時、椎野ミチルは度胸を決めざるを得なかった。出井聡子は本当に振袖だった。B・Bはどうせ『お母さん』がろくでもないアドバイスの上に、これ貸してあげる、とでもなったのか、ショッキング・ピンクの洋装に毛皮のコートを羽織っている。英元子はジーンズの上下で、ギター・ケースを持っている。これで中央本線の特急4人掛けに座っているところは、まるでコミック・トリオ漫才とマネージャーだと思った。
とはいえ、楽しくお喋りしながら、駅について、駅からすぐというその別荘を探した。その住所は鎮守の森の様な佇まいで、近くまで行くと人の声が聞こえた。男の声ではない。何やらはしゃいだ声がキャアキャア言っているのだ。4人は顔を見合わせた。意を決した椎野ミチルがドアをノックすると中から「ハーイ。」と声がして中からバアサンが顔を出した。
「アーラー、お嬢ちゃん達、もう見えたの。さあさあ。」
と中に招かれた。中には大年増がいて、後片付けをしていた。呆気にとられた4人にお茶が出され、お菓子が出され、バアサマたちはその間騒ぎちらしながら、片付けをすると「オニーチャン達は、今近所に黒湯に漬かっていて、すぐ帰るから。」と言って帰ってしまった。
「チョット何あれ。」
「分んないよ。でも夕べからいるみたいね。」
と話しているうち、オッサン達が帰ってきた。手に洗面器を持ち、タオルを持っていたが、恰好が予想を上回っている、と言うより下回っていた。『イベント屋』はまあ前回のような業界風、『アジア屋』は会社帰りに来たのか、それにしても工事用の作業服のようなものを着ている。英語屋は無粋なスーツにネクタイ。物理屋はライダー・フアッションのような皮の上下。この人達に比べれば、トリオ・漫才+マネジャーの方がまだマシかも知れない。
「よお、もう来たのか。早いじゃないか。」
「ごきげんよう、アニイ。ところで何よ、あのオバーチャン達。」
「お前等のおかげでミョーなもんが流行ってんだよ。まあ始めよう。」
要するに『男と女の友情論』の応用編なのだそうだ。実態はたかだか合コンのことらしいが、条件として酒が好きでないと困る、ヒマでないと困る、ワイ談が好きでないと失言した時に立つ瀬が無い、といった下らない条件が追加されたため、物理屋がこの別荘近くの知り合いのバーサマに声をかけたら、すぐに集まったらしい。
一応はクリスマス・パーテイーである。プレゼントなぞ準備したりして、シャンパンが抜かれ、かの女達も多少嗜み、オッサン達は自分達の酒を別々に飲み出し、ケーキなども用意された。
「それでアニイ。合コンはどうだったの?」
「オウッ、それが大盛り上がりでな。アジア屋は潰れるし大変だったよ。」
「しっかしバーサンってのも元気だよなー。」
「ありゃもうストレスがないんだよ。」
「歌も出ちゃったよな、あれは昔の唱歌かね。」
「こっちも歌ったから人のことは言えんよ。」
「何を歌うんですか?」
「(全員で)サンフランシスコ・ベイ・ブルース!ギャハハ。」
「キャー、あたし覚えてきたんですよー。」
話しは弾み、アチコチに飛び、午後には朝帰っていったバーサマ達が暇になったらしく又乱入してきた。そして『男と女の友情』。アジア屋が総括した。
「そもそも、恋愛と友情が両立しないという話しなんだ。どちらがいい、の問題じゃない。実験してみて分かったが、ある意思をもっていれば男女の友情は成立する。但し、そこはある程度の修行が必要で、それによって味のある友情がマナーと信頼の上に成り立つ、ということだろう。そこでだ、君達のような子供は(4人はムッとしたが)まず恋をしてしてしまくってから、ゆっくり男女の友情を楽しめばよろしい。」
「じゃあロクに恋をしなかったら友情も味わえないんですかー。アタシなんか恋とは縁遠いのに。」
「時間にとらわれることなんかナイ!先は長いし君達は自由だ!年なんか関係ない!」
「(酔っ払ったバーサン)そうだよーオジョーちゃん、この人は昨日アタシに惚れたって言ってた。」
「言ってねー!ぜーったい嘘だー。」
おしまい
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(198X年女子高編 Ⅱ)
2014 MAY 5 20:20:29 pm by 西 牟呂雄

椎野ミチルが声をかけたのは、ナンパで知られるK大生だった。おりしも秋の野球リーグの最終試合の対抗戦を皆で観戦する、という筋書きだった。
ミチルは当日集合した時点で、もう少し打ち合わせをしておけば、と後悔した。英 元子は制服であるセーラー服を着ており、出井 聡子はGパンにトレーナー、自分はこの頃謂うところのハマトラだった。そしてB・Bがやって来ると、皆息を飲んだ。髪をセットした上に、薄化粧を施し、真っ赤なスーツにハイ・ヒールである。
「ちょっとB・B、何、その恰好。」
「うーん、お母さんがちゃんとして行きなさいって買ってくれたのー。」
「・・・・・・・・・」「・・・・」「・・・・」
案の定、合流したK大の4人も目が点になった。
「ごきげんよー。」「ごきげんよう。」「こんにちは。」
挨拶の後、椎野 ミチルの彼氏である、市川がソッと聞いた。
「オイ。あのミズっぽいのは何だ。」
野球そのものは、伝統にのっとった応援合戦あり、アトラクションあり、試合も逆転ホームランが出る、といった具合で大いに盛り上がった。
男女交互にすわったのだがこの際、B・Bが真ん中。左右を、青いジャケットに縁無し眼鏡とサーファー風にはさまれて、体を硬くしていた。二人がしきりに気を使って話しかけるのだが、反応は鈍い。ときおり聞こえてくる会話では、何と彼女は野球を知らないのだった。
「あの人は何で走れるのですか?」
「あれは盗塁。モーションを盗んで走るんだよ。」
「それは、反則をしてるのですか?」
「はああ?・・・・あのー。」
一番隅にいた出井聡子は、時折聞こえてくる会話から、B・Bの極度の緊張感がビリビリ伝わって来るので、気になって野球どころでなくなってしまった。
試合の結果はK大がサヨナラで勝利し、スタンドは興奮のルツボと化した。そして全員総立ちとなって校歌の合唱となるため、応援部の指導のもとに肩を組んだ時、異変が起こった。左右から肩に手を回されたB・Bが貧血を起こしたのだ。
「マジ失敗もいいところね。」
「あれからこっちも大変よ。市川君が『オレの面子をどうしてくれる。』とか逆ギレするし、アタシも頭にきて大喧嘩よ。」
「ウソ。何その面子って。」
「あの後皆で中華でも食べることにしてたらしいのよ。だからって怒り出されてもねえ。おまけにB・Bのこと散々悪く言うし。もう願い下げだな。もともと軽い奴だったし。そう言えば、聡子の電話番号(この頃携帯はまだない)知りたがってるのがいたらしいよ。」
「趣味じゃない。アッB・B来た。」
「ごきげんよー。昨日は楽しかったねー。」
「・・・・。」「・・・・。」「・・・・。」
「男の人ってやさしいねー。だけどあの人達ってちょっと軽くない?やっぱり真面目な高校生がいいなー。」
「チョット玲!そん時はあのカッコはやめてよ。」
椎野ミチルが堪らず言った。
次の機会はすぐにやって来た。G大付属高校の同じ学年である。今度は秋の文化祭で、場所柄前回の失敗もあったので、E女子高のセーラー服の制服で行くことも決めた。
椎野 ミチルの彼氏は仁村といった。他の3人も皆真面目そうで、全員眼鏡を掛けていた。彼等は歴史クラブに属していて、今年のテーマは「決戦!関が原」と称して凝ったジオラマを展示していた。早速案内されていくと、嬉々として説明をしてくれた。出井 聡子は改めて、椎野 ミチルのジャンルの広さに舌を巻く思いだった。
昼食をとりに校外に出て、ピザを食べに行った。4人のポジションも前回の失敗を踏まえ、中心に椎野 ミチルとお相手の仁村君、聞き上手の出井 聡子が脇を固めるシフトを敷いた。
「4人は何の仲間ですか?クラブ?」
「全然関係ないのよ。聡子はテニスで元子は軽音楽。ギターが上手いのよ。玲はバスケ。」
「こんな綺麗な娘が4人仲間って珍しくね?」
一瞬光が走ったような緊張が生まれ、一同黙った。何というセンスの無い会話か。
「そんなこと無いです。この前も誰が一番ブスか、でもめました。」
これもどうかと思われる、B・Bの不規則発言である。
「へー、それで誰になったの?」
出井 聡子は目の前に座っている、この無神経男を殺してやりたいと思った。椎野 ミチルは彼氏の手前あせった。
「やあね、玲。違うのよ、事の発端は『友情論』なんですよ。」
「オツ、ボナールだね。それはオレも読んだな。」
「うん、キザなオヤジだよね。」
「でしょー。男と女のところなんか、なに、あれ。」
「だーかーらー・・・。ボナールはそれが有るって考えなのよ。」
「違うわよ。無い、と思ってるから、あっちでもこっちでも、友情はこう、愛情はこう、って書くのよ。」
一般にこの年頃の男女がこの手の話しを四つに組んで話すには、余程ませた場合を除き、男の方が幼すぎるケースが多い。この時がそうだ。
更に、男子側に、彼女達の気を引こうとする意思が働いており、論点が絞りきれず、『僕もそう思うなー。』だの『僕はその逆だなー。』といった、ふやけた相槌しか打てなかったため、彼女達は例によって、かってに熱くなりだした。男側である仁村君はこの場を取り繕おうと、頭をフル回転させた。結果が地獄とも知らずに。
「それで、玲さんはどういう考えをとっているんですか?」
「あたしは、男女の友情はある。だけどあたしは友情をもって接してあげない、って立場です。」
「すると今僕達とこうして話してますよね。僕はミチルと付き合ってますけど、僕と玲さんの間はある種の友情めいたものがあってもいいじゃないですか。それも否定されると、もし玲さんが何かを感じるとすると、それは愛情になる、ということですか?」
「なんですって!」
本人に何の悪気があろうか。一種の知的会話をしているつもりだった仁村君は思わぬB・Bの剣幕にたじろいだ。椎野ミチルも続く。
「ちょっと。何それ。何の下心があってB・Bに絡むのよ。」
「いいいやっ、違う。例えばの話しだよ。カンベンしてよ。B・Bって誰?」
「玲のことよ。原部(ばらべ)玲。通称B・B。」
「アッ珍しい苗字ですね。」
テーブルの反対側の4人は冷静さを取り戻していたが、既に会話に参加する気力を失っていた。
「こうして見てるだけだったら結構おもしろいね。」
「あのー、あの玲さんって人、いつもああなんですか?」
「あんなもんじゃないですよ。まだ泣きが入ってないですし。蹴りも出てませんから。」
「エッ。」
「元子。およしよ。」
翌日、英 元子がボソボソと出井 聡子に言った。
「ねーえー。いつまでこんなことやってるのー?あたしゃ降りたいよー。」
「それがねー。ミチルがあれから逆ギレして仁村君振っちゃったらしいよ。」
「ウソー。何それー。」
「夕べ連絡が入ったんだけど、夜にあやまりの電話が入ったんだそうよ。で、話してるうちに頭にきたらしくて、怒鳴りつけたんだって。そしたら仁村君も怒っちゃって、もう別れようってなったらしいんだ。」
「まったくー。愛も友情もないもんね。」
「ところがそっから大変なのよ。」
「何が。」
「っていうかー、こうなったら今度こそB・Bに一泡拭かせてやる、って言うのよ。」
「ミチルもバカねー。こんなことしてたらいくらあの娘モテてもカレシいなくなるよー。」
「それも破れかぶれになったらしくて、今度はオヤジだ、だって。」
「キャー、あたしゃヤダよ。エンコーなんて。」
「バカ、バカ。元子、何てこと言うの。でも何かあんまりフツーじゃないみたいなんだな、これが。今度の日曜にお鮨おごってくれるって言ってた。」
「どっちにしてもあたしゃ今度で打ち止めにさせてもらうは。」
「あたしだってそうよ。」
「着てくもんどうすんのよー。B・B又あの恰好だよー。」 続く
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(198X年女子高編)
2014 MAY 2 22:22:11 pm by 西 牟呂雄

「ごきげんよう。」「ごきげんよう。」E女子高特有の挨拶をしながら、校門から桜並木を抜けて教室に生徒が登校してくる。明るい笑い声が飛び交うその中に四人、目を真っ赤にした暗い表情の美少女たちがいた。四人は夕べから一睡もせずに話し続けたのだが、しまいには何を言い争っていたのか分からなくなっても終わらず、朝時点では全員が泣き出してしまったのでそこまでにして、登校してきたところなのだ。仲良しの四人はそれぞれの教室に別れて行った。
「B・Bごきげんよう。」
「うん。ごきげんよー。」
「ちょっと玲、すごい顔になってるよ。どうしたの。」
「うーん、、寝てないの~。」
原部(ばらべ)玲(れい)、通称B・Bは切れ長の目と化粧もしないのにやけに唇が赤く華やかで、その名前からも真紅の薔薇を思わせた。ただムラ気な性格が災いして、しばしば髪型や服装がとんでもなく乱れていることがあり、そんな時はまるで別人のようにむさ苦しい表情にみえた。今日がそうである。更にそのムラ気が言動に出ると、時に人を傷付け自分も取り乱すスパイラルに落ち、周りを巻き込むことがあった。薔薇には棘があったのだ。
「原部さん。原部玲さん。起きなさい。」
「・・・・。」
「玲さん今の先生が読んだところを音読して和訳なさい。」
「・・・・。」 「玲さん気が入っていませんね。集中しなさい。放課後にフランス語教員室にいらっしゃい。お話があります。」
「あの。今日はだめです。」
教室にピンと張り詰めた空気が流れた。
E女子高は1学年4クラス。2年北組で起きたささやかな事件は10分の休み時間に瞬く間に全クラスに伝わり、隣りの南組では『B・Bがフランス語のマダム・ヤマトに啖呵を切って教室を放り出された』だったが、その向こうの西組では『B・Bがキレてマダム・ヤマトを突き飛ばして出て行った』になっていた。
英(はなぶさ)元子と出井聡子は東組のクラスメイトだった。
「あの娘はもう。どうしてるの。」
「北組確か体育だよ。」
英(はなぶさ)元子は小柄だが細面の美少女で、ひきしまった顔立ちが意志の強さを感じさせるものの、どことなく儚げな趣が桜の花を思わせた。出井聡子はスレンダーな長身に長めのボブ・カットが彫の深い表情に良く似合っていた。黒目がちの瞳が何故か可憐なコスモスのようだった。
「どれが本当の話なのよ。」
椎野ミチルが西組から出てきて聞いた。椎野ミチルは浅黒い肌にボーイッシュな短髪、高校生離れしたプロポーションが華やかさを醸し出し、真夏のひまわりに見えた。
「B・Bがやっちゃったみたい。」
「朝方ひどかったもんね。」
「今日はどうするの。」
「どうするって?」
「このままじゃ収まらないでしょ。決着つけなきゃ。」
6時間目が終わるチャイムを合図に3人は北組を目指す。帰り支度で騒がしい教室に入って行くと人垣が割れB・Bの所まで開けた。この四人は仲良しなことは皆知っており、どうも今日のフランス語のモメ事の遠因ではないかと疑っていた。それでなくても個性的美少女が連れ立っていることで、見る側と見られる側の間に思慕・羨望・嫉妬といった様々な感情が一瞬の内に交錯した。
「B・Bあなたどうしたの。」
「うーん、ねむーい。」
「玲、マダム・ヤマトをカンカンにさせたってホント?」
「うーん、もうヤダー。」
「じゃあ、きょうは無理?聡子はテニス部休むって言ってるけど。」
B・Bはバネ仕掛けのように立ち上がった。
「ジョーダンじゃないわ!アタシャ引き下がらんよ。」
クラスが一斉に振り向いて、いったい何事かと固唾を飲んでいるのが分かった。出井聡子が引き取って、穏やかな微笑とともに囁いた。
「サッ行くわよ。B・B。」
事の発端は出井聡子が持ち込んだ、アベル・ボナールの『友情論』だった。回し読みをしてはその難解な言い回しや小洒落たセリフに相槌を打ったり文句をつけたりしてして楽しんでいた。
『真の友は共に孤独な人である。』『恋愛に於いて、我々は世間を捨て、友情に於いては世間を見下ろす。』『恋愛には、人が絶えず口にする向上の欲求と、それ程口にされないが、劣らず強い堕落の欲求がある。』
これらの台詞は、まだ人生経験が少ないが故に、より美しく啓示的に彼女達の心を打った。そこまでは良かったのだ。
第5章『男と女の友情』で激しくモメた。彼女達が未経験であるため、未知の感情を語ることは、時に過激で出口の無い議論になってしまった。
「こんな奴(作中のボナールの対話者)がいるから、それでそいつが言うような女が本当にいるから女がなめられる。こんな男なんかに誰が友情を持って接してやるものか!」
普段から男嫌いの言動が極端なB・Bの発言である。恋愛経験が全く無いがゆえの憤りだろう。
「向こうがそう来るなら、逆手にとって、のぼせ男の頭を冷やしてやんなさいよ。」
真夏のひまわり、椎野ミチルの意見だった。彼女は複数のボーイフレンドがいたが、天性の捌きで、自由を満喫していた。
「だけど玲、居もしない男のことアーダコーダ言ってもしょうがないじゃない。」
これは男嫌いというより、無関心と言ったほうが正しい、英元子である。この発言が引き金を引い
た。『いもしない男』という言い方に、B・Bはカチンときたらしい。そして出井聡子が追い討ちをかけた恰好になる。
「だから玲、『ワタシを男だと思って付き合って下さい』って言えばいいじゃない。」
これは本気の一言だった。彼女なりに、自分だったらそう言おうと思ったのだ。
そしてB・Bが爆発した。
「アナタ達!バカにしてるんでしょう!」
学校の帰りに喫茶店に寄った。校則では禁止されているが、何しろ夕べは椎野ミチルの家に泊まりである。いくらなんでも今日もというわけにはいかない。学校の近所はマズイので、わざわざ地下鉄で一駅移動した。
「ちょっとB・B、何があったの?フランス語は。」
「うーん、寝てたらマダム・ヤマトが後で来い、とか言うからヤダって言ったノー。」
「どうするつもり?赤点貰うわよ。」
「かまやしないわよ。」
「えーっと、それでどうなったんだっけ。」
「いっぱい喋って、訳わかんなくなっちゃった。」
「だーかーらー、男と女の友情よ。」
「ああ、そうね。それでB・Bがキレたのよ。」
「違うわよ。ボナールはいいの。相手が気に入らないのよ。」「相方って言ってもあれがボナールの本音でしょう。」「ウソッ、マジで。」「バカね、小説の手法でしょう?」「違うわよ。」「そうだってば。」「どのみち、大昔のフランスオヤジが言ったことよ。」「小説の手法ってなにさ。」「アラ、ほんの5-60年前よ。芥川より新しいはずよ。」「あなた言ったわよね。男と思って付き合ってくれ、て言えって。」「そんな昔なの、ウチの親の生まれる前じゃない。」「言ったわよ。あたしはきっと本気で言うわよ。」「そんなこと言ったら源氏物語なんかどうするのよ。千年前よ。」「聡子、本気なの?じゃ相手がアホで僕はゲイですから一緒にホモになろう、って言われたらどうするのよ。」 「ストーップ!ヤメナサイ!(声を落として)人がこっちを見てるでしょ。一人づつ。ほら、玲。」
たまりかねて英元子が声を励ました。B・Bを見れば、もう涙目である。
昨日はそのまま帰り、4人の緊張関係は続いていた。普段は校庭の芝生でお弁当を一緒に食べるのだが、お互いに声もかけない。さすがに周りが気にし出していた。もっとも北組ではフランス語の一件以来、誰もB・Bに話しかけなくなっていて、B・Bはだらしなさが一層ひどくなり、髪にブラシもかけていないようだった。
英元子と出井聡子は同じクラスなので、帰りには会話が復活していた。
「どうする?」
「あれじゃ救われないわな。」
「みんなも変だと思っているみたいよ。」
「そうねえ、落しどころは奥の手かなー。」
「何、それ。チョット、変なことに巻き込まないでよ。」
「B・Bは異性恐怖症なんじゃない?」
「アタシもあんまり興味ないけどアレはそれどころじゃない。ありゃタチが悪い。聡子は?」
「アタシは平気。敵に後ろを見せてなるものか。でも女子高だからなー。」
「ボナールも空しいね。」
ズバリ、合コンである。各方面に顔の利く、椎野ミチルに頼んで4対4のセットをする。案の定B・Bは激しく反応したが、聡子はソッと囁いた。
「だけど玲、手打ちをするにもちょうどいいでしょ。他に事情を知らない人がいた方が自然にやれるわよ。あなた、最近誰とも口も利いてないじゃない。」
後に、どういってB・Bを説得したのか、不思議そうに聞いてきた元子に、いきさつを説明するとため息まじりにつぶやいた。
「あのね、あたし前から思っていたけど、あなたほんっとにワルね。」
「なんのなんの。」
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。