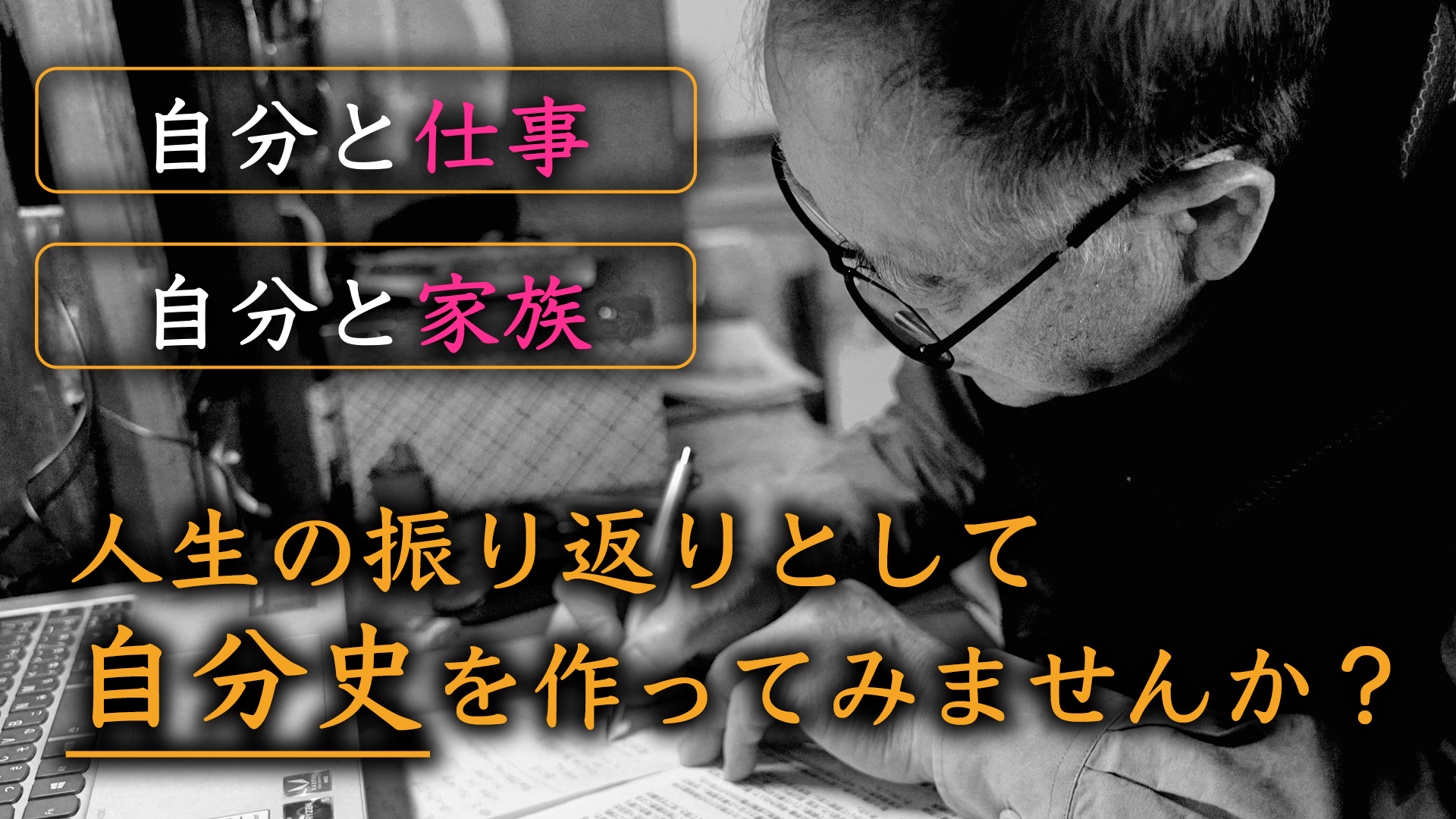南蛮倭国盛衰記 シャム湾海戦から鎖国へ
2026 FEB 15 0:00:16 am by 西 牟呂雄

1630年、和暦では寛永七年、メナム川河口にある南蛮倭国の長老会トップであったヤーマ・ナーマサが死去した。壮大な葬儀にはタイのアユタヤ王朝・ベトナムのフエ王国・バタビアのオランダ東インド会社総督といった近隣の国家から弔問の特使が参列した。式典は神道式で神官の短い祝詞が日本語であげられた。
南蛮倭国は人口約1万人、誠に奇妙な都市国家である。成人男子は全て武士で構成され、ごく少数の両替商と大工がおり、両替商は日本からの銀の交易を手掛け、大工は船大工だった。要するに傭兵集団が独立した海洋国家で、かつては倭寇と呼ばれた日本人達なのである。それでも長老会という議決機関を頂き大将を選任しそれなりの国家の体裁を整えてはいた。
世界史に類似例を求めると、ヴェネツイアやマルタ共和国が近い。ただ、この集団の場合は領土的野心も通商概念もほとんどない不思議な国家だった。
これ以外にも同じような日本人軍事国家がヴェトナム北部の河内倭国(河内は現地語でハノイ。はのいわこく)とフィリピンの切支丹呂宋倭国(きりしたんるそんやまとこく)の二つがあった。
このうち前者は公用語である漢文(当時のヴェトナム王朝は漢文を公文書とした)との親和性が高く、また僧兵崩れが多かったせいで兵士全員は僧衣を纏った仏教国の体裁だ。
一方後者は大阪夏の陣で敗れた浪人達を吸収して成立したキリスト教国で、成立当初の中心人物がキリシタン大名の高山右近だったからである。そして当時の現地を支配していたのはカソリックのスペインだったので、キリシタンであることは都合のよい隠れ蓑となったのだった。
三国は巨大ガレオン式帆船である大安宅船を数隻所有し周辺の制海権を握っていた。そういえば聞こえはいいが、普段日常的にやっていることは海賊である。
時は大航海時代。やや遅れて東洋に進出したオランダ東インド会社は、ジャワ島を拠点に先行したポルトガル・スペインを追うように勢力拡張を図っていた。当初は香辛料の交易のみだったが、バタビア(ジャカルタ)に要塞を築き現地勢力を懐柔するなどして次第に植民地経営を強化していた。
タイ・およびマラッカの諸国はこれを警戒し、南蛮倭国に海上防御を要請。ヤーマ・ナーマサの後に長老会の評議により大将に選出されたニシーム・ローザエモンはこれを受け、シャム湾を往来するオランダの帆船を片っ端から襲いだした。要するに本性をむき出しにして暴れまわったのだ。
これに怒ったオランダは大砲を積載した艦隊に正規兵千人と現地兵千人を乗せてシャム湾を威嚇封鎖した、一触即発の艦隊行動だった。
ニシーム大将は長老会を招集して言った。
「ジャガタラの紅毛人ども、ついに我らがシャムを脅かさんとす、我等はアユタヤのプラサートトン様の要請によりこれを撃滅せん」
おおっぴらに思う存分暴れられるのだ、戦士達は奮い立つ。既にヴェトナムの河内国とフィリピンの呂宋国の日系二国に応援を要請してある。二国といってもやっていることもその生業も同じで、総称としては南蛮倭国と言って差し支えないだろう。
河内(ハノイ)の最高指導者の僧侶である建僧都室西(たけるそうずしっさい)、通称室西僧正(しっさいそうじょう)は謎めいた人物で滅多に人前に姿を現さない。年に数回大きな会葬に出てきては良く通る声で一喝していた。
呂宋では現在アントニオ・オエステと名乗る日本人がリーダーとなっていた。アントニオは日本語を話すが、自分はキリストの生まれ変わり、などと胡散臭いことを言い募る怪しげなことこの上ない人物なのだが、用兵は巧で個別海戦には滅法強かった。
シャム湾に大型帆船のオランダ艦隊が姿を現した。潰すべきは南蛮倭国の本拠地で現在のバンコクだ。浅瀬の湾口を包囲するような布陣から自慢の大砲を撃ち始めた。陸上をかき乱した後上陸する作戦である。
ローザエモンは不敵に笑った。
「紅毛人ども、わざわざ波頭を超えて鮫のエサになりに来おって。望み通り切り刻んでやれ」
その頃艦隊後方から大安宅船の艦隊が北上してくるのが見えた。戦闘前に沖合で待機していた南蛮倭国の船である。
するとこのまま割って入られ陸との挟み撃ちにされるのを避けるため、オランダ艦隊はいったん上陸を諦め回避行動を取った。そして現在のカンボジア方面を目指しパッタヤー半島を回ったところに停泊した。何故か追って来るはずの南蛮倭国の艦隊は半島の反対側あたりで追撃をやめていたのだった。
真っ赤な夕日が落ち闇に覆われると、その漆黒の夜半に大安宅船から手漕ぎ小型舟が十数隻ほどヒタヒタと半島を回って行く。得意の夜襲である。
ヨーロッパでの戦闘は通常ヌーンデイ・タイムに行われるものだったのだが南蛮倭国は知ったこっちゃない。大安宅船による追撃は申し訳程度で、日没後を待っていたのだ。
音もなく寄せると直上に向けて火矢を放ち、手鉤縄を船側に絡ませては次々と乗りこみ全員無言のまま抜刀する。撃ち込まれた火矢に気づいたオランダ兵の当直が大声をだそうとするのを一瞬で切り捨てた。帆にも放火する。
騒ぎが大きくなり甲板に兵士が上がって来て白兵戦になった。倭国兵は全員夜目が利く上に日本刀はこういった乱戦では無類の殺傷能力を持っている。縦横無尽に暴れまわると各々衣服を脱ぎ捨て褌に大刀をぶち込んで次々と海面に飛び込んだ。
見ればオランダ船は数隻に火の手が上がりパニックに陥っていた。
結局、消火できなかった3隻を放棄し、他のオランダ軍は艦隊行動をとることなくバタビアに引き上げていった。南蛮倭国の完勝である。
これよりオランダ東インド会社は倭国と友好条約を結ぶ。オランダ船の安全航行を保証するために金をふんだくるという一方的な条約で、同時に南蛮、河内、呂宋の日系3国家に適用された。とりあえずオランダは南シナ海を北上する航路を確保し台湾・日本のルートを抑えることとなった。
激震が走る。寛永十年(1633年)、江戸幕府はポルトガルとの断交とキリスト教禁教のために鎖国令を出した。海外からは自由に帰国することが叶わなくなったのだ。さすがに動揺が走った。今のうちに何とか故郷に帰りたいと言いだす者、故郷のメシが食いたいと言う者、こんな暑いところはもういやだと泣き出す者までいた。
しかし今更日本に帰ってもすることないから構わない、と開き直る者の方が多かった。なんとなればこの荒くれ者たちはほぼ全員が土地も家族も持っていなかったのである。
ローザエモンは長老会を招集した。
「海禁令が出て何やら騒がしいが、お江戸の将軍様も今や三代目じゃ。余程キリシタンとポルト(ポルトガルをこう呼びならわしていた。オランダはホランド)がお嫌いと見える。ホランドの奴らめ丸儲けじゃの」
「我らは今後いかようになりましょうや」
「まあ、しばらくは様子見よ。帰ったところで誰が迎えてくれる。ホランドは長崎で交易が認められる。ということは裏で舌なめずりしている大名がウヨウヨしているに相違ない」
「ローザエモン様、それはいづこの国や」
「まあ待て。関が原で裏目に出たやつらに決まっておろう。交易の旨味を知り尽くしているところよ。ワシは河内(ハノイ)の室西僧正と呂宋のアントニオに話しに行く」
「よろしくお頼み申し上げまする」
僧形の一行が密かに薩摩の坊津に上陸した。一人だけ頭を丸めているが、他の者は僧形ではあるが全員背中まで伸ばした髪を結ぶこともなく風になびかせている異形だった。
浜で待ち構えていた薩摩藩の役人達に向かいこう告げた。
「河内(はのい)の建僧都室西(たけるそうずしっさい)である。薩摩の太守、島津家久公にお目通り願いたい」
「こころえて候。まずは長旅の疲れ癒されたく」
「あいわかった」
扱いは大名並みの待遇だった。だが、薩摩側の心づくしの接待にも室西以外のものは終始無言。また室西の受け答えも型通りに終始し、宴席は盛り上がらない。だがこの連中、酒は一人一升以上飲んだ。
翌日、薩摩側は駕籠を用意していたが室西はこれを丁寧に断り徒歩で鹿児島に向かった。仕方なく駕籠には土産物を載せて移動したのはご愛敬であるが、南国由来の色鮮やかな珊瑚、めずらしい象牙の装飾品などとかなりの重量で、駕籠かきは苦労していた。
表立っての訪問ではないためか、鹿児島に到着した後しばらくは城下に留め置かれ数日を過ごした。鶴丸城は関ケ原後の築城だが、全く防御を想定していない不思議な構造で、天守のような建築物はない。誠に薩摩らしいといえば薩摩振りの武骨な城である。
数日後、島津家久との会見が成った。面を上げよ、の声とともに端座した室西の眼光に家久はいささか違和感を感じた。やや赤みがかっている。
「お目通りかない恐悦至極に拝し奉りまする。ご機嫌麗しゅう」
「苦しゅうない。此度の来薩、誠に喜ばしい。南方の暮らし向きつつがなきや」
「常夏にて、至極」
「して、件の話に相違はござらぬな」
海禁政策により幕府直轄領である長崎の出島でのみオランダが交易できる新体制になったのだが、倭国勢も島津家もオランダに一人儲けさせるつもりなどサラサラなかった。南蛮倭国は自慢のガレオン船も新たに進水させ自ら密貿易に乗り出し、相手として狙いを定めたのは薩摩と東北の伊達藩だった。オランダ船から荷物を強制的に抜いては売り捌き、代わりに物資・銀を調達、更には人材をスカウトする目論見である。
薩摩側も琉球を勢力下に置くことで密貿易の味は知っていたし、伊達藩も遠く支倉をローマに派遣したりと海外展開をすすめていたので、両藩とも渡りに船だったのだ。
その頃の東南アジアでは、フィリピンを支配していたスペインは国王フェリペ二世の死去による混乱の中にあり、徐々に勢いを増した英国がインドから虎視眈々と中国大陸を狙うという状況で、海上の勢力が変わりつつあった。ところが日系の三倭国の評判があまりに悪く、日本人とは下手にちょっかいを出して暴れられると面倒な奴ら、との認識が広まったお陰で矛先は日本に向かなかったのであった。
話は終わり、御酒くだされ、の宴席となった。家久は上機嫌で一献下げ渡すと言った。
「室西殿、我が薩摩は勇武をもって聞こえた国柄。河内(はのい)の武芸者も腕が立つであろう。軽く手合わせはどうじゃ」
「我らの得物は鉄砲にて」
「ふはは、供の者たちの金剛杖は仕込みであろう」
「これは。座興でござりましょうや」
「そうよ。座興も座興。狂乃介、これへ」
一座の末席に端坐していた屈強そうな若者が呼ばれた。室西はその若者を見据えると傍らの小柄な僧侶を即した。二人は庭先にて名乗りを上げた。
「示現流、立花狂乃介」
ごつく太い樫の木刀を持っている。
「大悟坊峻海」
右手で金剛杖を地に突き立てた。
両者は後ずさりした。狂乃介は「チェース」と猿叫の気合を発して切先を天高くつきだすトンボの構えに入るや「きゃー!」と突進した。俊海は自然体。次の刹那、大地を割らんばかりに振り下ろされた木刀が地面にめり込んだ。俊海の体は毬のように転がり狂乃介の背後にスッと立ち上がる。体制を立て直した狂乃介の眼前に金剛杖が突き付けられていた。
「そこまで!」
声を発したのは室西であった。
「さすがはお留流。われらの杖では受けること敵わず。太刀筋をかわすしかできませなんだ。更に戦えば大悟坊は真っ二つ必定、呵々」
「薬丸示顕流、飛田隼人!」
コケにされたかといきり立つ次の若者が名乗りを上げる。だが今度は家久が言った。
「下がれ、隼人!盛んなるかな薩摩武士。こいは戦場ではなか。座興でごわ」
薩摩弁が飛び出したので一同静まった。
以後、坊津は密貿易の港としてオランダ船や明船、更には朝鮮の交易も含めて大いに賑わうのであった。
然しながら流石に大っぴらにやりすぎて、享保八年幕府による手入れが強行され、薩摩藩は大いに面目を失った。俗に言う『唐物崩れ』である。
だが、元々アウトローの寄せ集めの倭国側は痛くもかゆくもないとばかりに、枕崎にその拠点を移し幕末まで密貿易に励み続けるのである。
余談ながら伊達藩に密貿易を持ち掛けたのは呂宋のアントニオ・オエステ率いる船団で、伊達藩士である支倉常長が洗礼を受けたことを知っていたからであった(禁教令によって失意のうちに仙台で没した)。更に伊達政宗の長女で一度は徳川家康の六男・松平忠輝と婚姻した五郎八(いろは)姫がキリシタンであったので、その知己を得られたのである。
現在の石巻港においてしばらくは盛んに密貿易をしたのだが、五郎八姫の没後に幕府の詮索を恐れた伊達藩によりこのルートは廃れた。
更に余談であるが、密貿易船で南蛮倭国に渡ったのは物資や銀だけではない。酌婦・遊女の類も大勢やって来た。 のちの世に言われる「身売り」のような暗い話ではない。この苦しい生活を捨てて新天地に羽ばたくような気概の、多少危ない女達が海を越えてやってきた。一方で南蛮倭国の方も、ただでさえ内部でも無用の小競り合いが絶えない荒くれ者共を慰撫するためにもそれを必要としたが、統制が取れなくならないよう人数は厳しく制限した。
かくて日本人の純血は続いたのである。
つづく
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:伝奇ショートショート