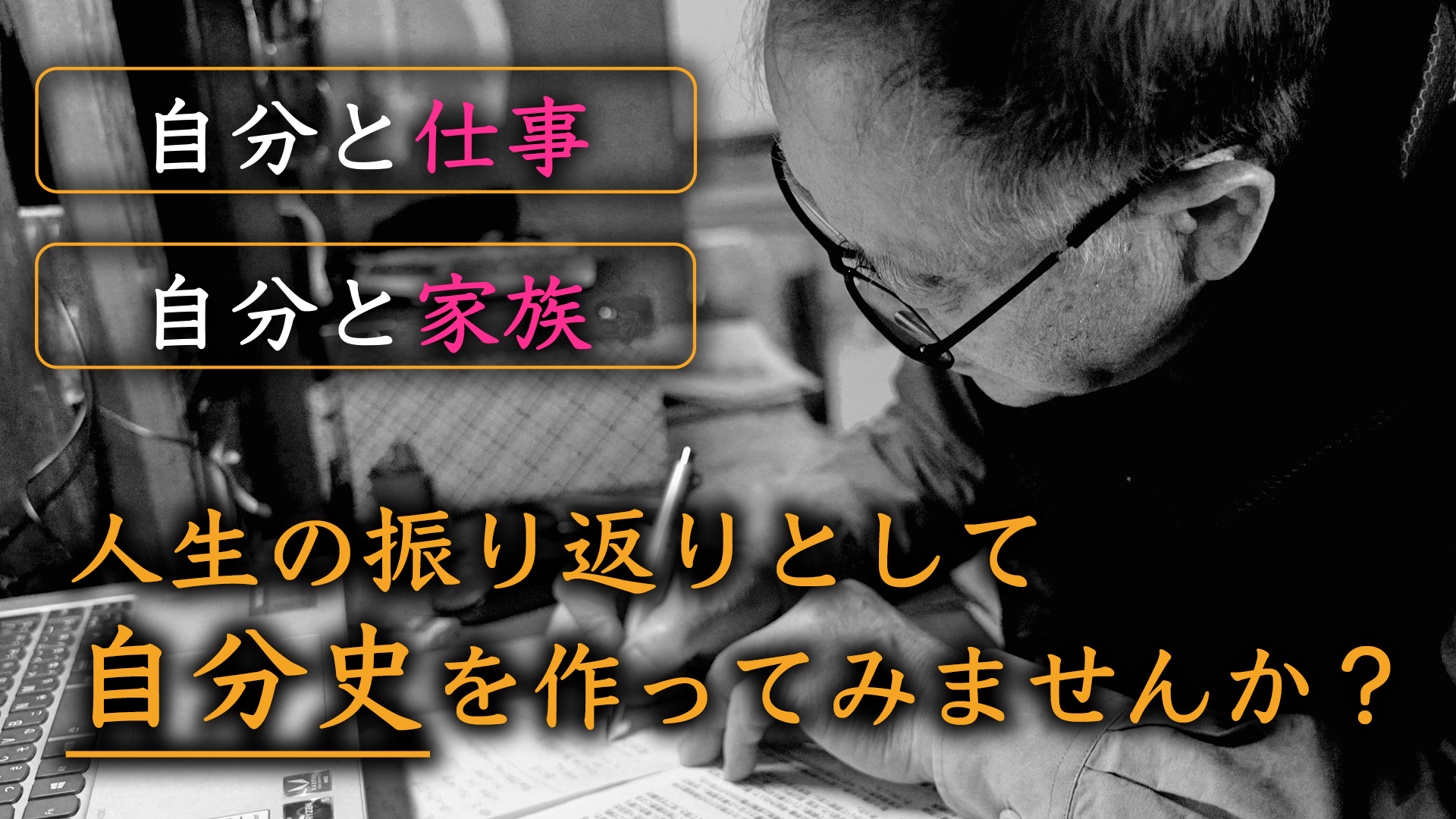南蛮倭国盛衰記 旋風そして維新
2026 FEB 21 0:00:04 am by 西 牟呂雄

少年達が銛を手にして次々に小舟から飛び込む。小舟は現在のアウトリガー・カヌーで、もう岸からは見えないほど遠くに出ている。シャム湾は浅瀬が続くため湾内の潮の流れは早いが、舵取り役を残し数十人の若者は長く・深く潜り、獲物に銛を突き立てる水練をしているところだった。
やがて息が続かなくなった者から海面に飛び出してくる。早いものはやはり手ぶらだ。現在は乾季のため、チャオプラヤー川から流れ込む茶色がかった水は少なく、ここまで沖合に出れば透明度は高い。未だに潜っているのは二人ほどだがその動きは船上からも良く見えた。一人は獲物を突いて上がって来たが、もう一人はまるで魚のように泳ぎ大物を追っていた。その魚はそう早い動きではなかったものの、獲物がより深い方へと逃げて行こうとする刹那、一瞬大きく体をしならせたかと思うと重そうな銛を一閃させて仕留めた。
そのまま一抱えもある大物を手繰りながら海面から頭を突き出し「ファーッ」と息をつくと船に向かって泳ぎだした。
「お春が一番の大物か」
「またかよ。あいつはまるで魚だ」
アジ科と思われる大物を片手で船に放り上げるとザバッと乗り込んできた。
少年たちは15歳くらい、彼等は南蛮倭国の戦士となるべく訓練を受けていた。皆、頭に布を巻き付け上半身は裸で腰は褌姿、良く日に焼けている。だが、ひとり大物を仕留めた者だけは色白の地肌らしくピンク色をしていた。背は頭一つ高く手も足も逞しく太いのだが、胸元はわずかに隆起し少年のそれとは違っている、女なのだ。
名前はお春。肩で息をしながら笑って言い放った。
「お前ら。陸(おか)の上の武術も水の中の潜りもオイに勝てんじゃろう。こんままでは大船(おおぶね)の船長(ふなおさ)にはオイがなるしかなか」
「ないごて。お春なんぞ誰も嫁とりせんから大船に乗るしかなか」
少年たちはもうすぐに元服を迎え艦隊に乗り込むことになる。その際に厳格な能力審査の上、最初から役割を割り振られる。船長、舵取り、射手、帆方、漕方(こぎかた)、賄・荷方、といった具合である。
そして南蛮倭国の艦隊はシャム国王の親衛隊にも序されるため、新人はラーマ一世の閲兵を受けることになっていた。
アユタヤ王朝は既に滅び、紆余曲折を経て現在のチャクリー王朝が成立していた。それに伴い王宮をバンコクに造営し首都と定めた。南蛮倭国は内政不干渉の原則を貫き、艦隊拠点をレムチャバンに移した。ラーマ一世はその潔さにいたく感服し、親衛隊直属で海上防衛の任に当たらせることとした。言ってみればイングランドのサー・ドレイクやのような合法の海賊・傭兵である。
謁見当日、暑い日差しを浴びながら甲冑を付けた40人の新兵が4列縦隊に整列した。両側にシャム軍自慢の像部隊が控え、正面の一段と高いところにしつらえられた黄金の玉座にラーマ一世が座っていた。その前で新兵に向かって起立している親衛隊長シーゲル王子が姿勢を正して「ワイ!(タイ語で合掌の姿勢)」と号令をかけると一同が兜を脱いで脇に置き合掌の姿勢をとった。
王子は閲兵すべく中央を進み、戻ってくるとラーマ一世に向かい再び「ワイ!」の声をかけた。
式典が終わり南蛮倭国の戦士が後退する時、シーゲル王子が指揮官を呼び止めた。その美貌が印象的だったからだろう。
「待て」
指揮官はお春だった。
「ワイ!」
「お前は日本人なのか」
「チャイ・クラップ!(はい・男語)」
「少し話していけ。ついてまいれ」
実はシーゲル王子の男色はつとに知られており直属の親衛隊は大変な美少年を集めていた。ただし、男色は今日の様な捉えられ方ではなく、特に戦乱の続いたシャムにおいては戦場での結束をもたらす絆と考えられ、事実シーゲル王子の親衛隊は無類の強さで知られていた。
王子は衛兵の守る自室に招き入れるとお茶を勧めた。
「お前たちの艦隊は無敵と聞いている。お前たちのおかげで我らは陸の上の戦闘に専念できることを感謝する」
「コープクン・クラップ(そうです・男語)」
「お前の体を見てみたい」
さすがに多少動揺したようだが、次の瞬間鎧を解きだした、薄く笑みを含んでいたようだったが。そして上半身があらわになるとシーゲル王子の方が驚いた。両の胸のたくましさとやわらかいシルエットに目を奪われた。
「待て!お前は女か。なぜ男言葉を使う」
「普段より海に暮らすのに区別なし。特に我が艦隊は全員が戦士ゆえ」
「む・・・。女ともあれば余の後宮にて暮らすことも許されるが」
「おたわむれを。異民族の女戦士など。殿下なら恥辱を受けた日本人の作法はご存じのはず」
と脇差を抜き刀身に布を巻き付けると自分に向けた。王子もさすがに慌てた。
「もうよい!・・・・お前達はラーマ一世の海の親衛隊でもある。任務を果たせ」
「カオジャイレーオ・クラップ!(わかりました・男語)」
そのまま後ろずさりの礼法でさがった。シーゲル王子は興覚めし深いため息をついていた。
往時茫々、10年の歳月が過ぎた。
この時期、イギリス東インド会社は大航海時代を先行していたスペイン・ポルトガル・オランダを凌駕し、数十隻の大砲を装備した武装商船艦隊を擁して、東南アジアから清国へ進出しはじめた。なお、インドから西側はボンベイ・マリーンとして正式な海軍を持っており、まさに七つの海を支配していた時期に当たる。
この武装商船艦隊はいわゆるロイヤル・ネイビーではないものの、組織・階級・並びに士官などはほぼ同じで、強力な戦力である。当然のことながら南蛮倭国と小競り合いが起きることとなるのは時間の問題だった。
マレー半島で出会い頭での接触だったのだが、イギリス側は艦隊行動ではなくブリタニア号の単独航海だったことが災いした。南蛮倭国側は早い話が海賊だ。砲撃されるやサッサと逃げ回り、得意の夜襲で襲い掛かると瞬く間に制圧、拿捕してしまった.双方に若干の犠牲者がでた。倭国側の果敢な攻撃の船長は逞しく成長したお春であった。
死傷者が少なかったのは日本側の目的が人質と船の確保だったからである。作戦を立てたのはお春だった。
お春は既に武装商船隊の船影を目撃しており、その戦力の充実から南蛮倭国の3拠点を合わせても艦隊決戦に勝ち目はないと判断、乗っ取りを長老会に進言して了承されていた。
武装解除されたイギリス人とインド人の水夫が甲板に集められた。
以下、カタコトの英語・蘭語のチャンポンで会話が進む。お春が訪ねた。
「指揮官は誰か」
ボンベイ・マリーンの制服を身に着けた細身の士官が一歩進んだ。
「私だ」
「名前は」
「コマンダー・ウィリアム・アダムス(アダムス少佐)。あなたは」
「お春ジェロニマ」
言うなり兜を脱いだ。
アダムス少佐の顔色が変わった。その名前と美貌に驚いたのだ。
「あなたが有名な『Jager of hurdle(困難な豹)』か」
Jager of hurdle とは東インド会社が手を焼いていた南蛮倭国の船長(ふなおさ)の呼称で、鮮やかな操船と果敢な戦闘で恐れられていた。だがイギリス東インド会社もジャワのオランダもまさか女とは誰も知らなかった。
「その通り。コマンダー・アダムス。あなた達は人質となった。手荒な真似はしない。あなたがたと交渉したい」
「何の交渉か」
「あなた方の身代金と命の引き換えにこの船をいただく」
「私に権限はない」
「権限のある者に取り次いで欲しい」
「どうやって取り次ぐのか」
ここでお春はカラカラと笑った。
「この船で行く」
「なに!」
「わたしの指揮の元で我々とあなた方で操船する」
「ボンベイで無事ですむと思うのか」
「私は全権をもって交渉を任されている。われら南蛮倭国はこの船を買い、河内(ハノイ)呂宋(ルソン)と協力し東インド会社の商船を護衛する。ボンベイ・マリーンはその武力をインドおよびその西側に集中させるがよかろう。東インド会社への海賊行為もしない。あなた方はカンパニーだろう。損得を考えるはずだ」
アダムスは言葉を失った。
ボンベイの港に姿を現した武装商船には東インド会社のフラッグとともに南蛮倭国の旭日旗が掲げられている。そして初めて見る兜に甲冑のサムライが甲板に整列している様を見て、イギリス人もインド人も目を見張るのだった。
『Jager of hurdle(ジャガー・オブ・ハードゥㇽ)』即ち、後に『じゃがたらお春』として日本に知られることになる伝説の女海賊が誕生した日である。
彼女が指揮を執る船は右舷に『Jager of hurdle』左舷に『じゃがたらお春』と表記され、旭日旗とユニオンジャックを掲げていた。いつもの癖で舳先で水平線をみるお春の背後には金髪を風になびかせるアダムス少佐の姿があった。
お春が振り返るとアダムスと目が合う。アダムスが聞いた。
「フナオサ(船長)どちらに舵をとるおつもりか」
「我らに行先などない。ただ漂い、打ち壊し、奪うばかり」
「そのあとは」
「生き延びることができたら・・・そうだな、ウィリアム。お前の生まれたエゲレスにでもいってみるか」
「それは・・・、あの暗い天気はフナオサに似合わない」
「ではお前たちバテレンが忌み嫌う”地獄”の入り口まで航海するか」
「滅相もない」
「フハハハハハ、どこでもよい。お前はついてまいれ」
振り向いて言うが早いか、見上げるようなアダムスの首周りにタックルをかけた。アダムスは副長として『Jager of hurdle』に乗り込み、お春の影のように寄り添っていた。二人は笑いながら転げまわり、甲板のファーネスに引っかかると互いを見つめ合っていた。ちょうど水平線に夕日が落ちていった。
慶応元年、神戸海軍操練所が閉鎖され無聊を囲っていた坂本龍馬が西郷隆盛に誘われて鹿児島を訪問した。
西郷家に逗留すると早速西郷が誘った。
「あすは枕崎まで行きもんそ」
「そこはどこぜよ」
「みせたいもんがあいもす」
鹿児島から枕崎まで一日がかりである。粗末な旅籠に宿を取ると先客があった。
「せごドン、お待ち申し上げておりました」
「おお、お久しぶり。こん者が海軍を作ろうち奔走しちょる坂本君ごわす」
「尊王の志高き志士としてご高名は存じ奉り候。海軍伝習所が閉鎖されお困りと聞いておりもす」
「おんしは誰がじゃ。勝先生を知っとるがですか」
「拙者は蛇潟老春(じゃがた・らおはる)。勝なる方は幕臣ゆえに我らは面識はなか。ですが我らは坂本さあのやりたがっちょう海軍を持っちょいもす」
薩摩訛りだった。
「なに!かいぐん!」
西郷が遮った。
「蛇潟ドンはオイが島に流されていた時分に世話にないもうした。シャムを拠点に艦隊を率い、河内(はのい)、呂宋(るそん)にいる日本人の子孫たちと力を合わせて海軍を持っちょいもす。無論戦闘においてメリケン・エゲレスといった国の海軍に一歩も引けはといもはん」
「日本人ならエゲレスが薩摩と戦になった時はなんで助けんかったがじゃ」
蛇潟がゆっくりと言った。
「あいはボンベイ・マリーンの船ごわす。オイたちゃその指揮下ではあいもはん。それにご存じないじゃろが、あいはすべて空砲でごわした。要するに幕府に対する見せかけ」
西郷も続ける。
「おいたちはもうエゲレスには話をつけておりもした。後は幕府が困るように仕向けた芝居」
南蛮倭国はオランダ軍を退けた後、一時的にヨーロッパが革命騒ぎで東洋進出が小康状態になった時点で周辺の制海権を握った。そして幕府が鎖国政策を取ったことを逆手にとって交易を発展させた。なに、交易といえば聞こえはいいが、実態は密貿易と海賊行為である。それによって莫大な富を蓄えたのだが、日系3国は内陸での帝国経営には一向に興味を示さず海洋独立国家であり続け、3拠点の総称である南蛮倭国が定着したのだ。
一つには現地人との宗教観が違いすぎて通婚がほとんど進まず、また日本から受け入れられる女の数も限られるため人口は増えるわけではない。第一、暴れまわるのが生業なので陸の領土を広げて帝国を経営するノウハウも資質もない連中だったからである。
時代は進み、ヨーロッパから産業革命が起こった。
資本はダイナミックに躍動し動力革命・軍事革命を牽引する。勢いのついたヨーロッパは海洋を制覇し、アフリカ・アジアの分捕りあいが時代の趨勢となり、英国がその覇権を握りつつあった。
イギリスはインドを飲み込み、清国を侵食し始める。その際に南蛮倭国と歴史的な接触があった。そして倭国勢は伝説の女海賊お春(じゃがたらお春)に率いられイギリス海洋進出の一翼を担ったのは前述の通り。
その操船能力と戦闘技術の高さは大英帝国をしてもなお魅力的だった上、そもそも領土的野心はない。更に異常ともいえる識字率の高さ、同調圧力、好奇心、義侠心とアジアの国にあっては極めて特殊な連中だったのだ。また周辺国は非常に恐れ、実際に戦闘が起きると無類の強さだったため、英国も薄気味悪がって懐柔しようとしたのだった。
倭国艦隊は英国商船を保護しつつ南シナ海から沖縄・薩摩まで自由自在に(時に)暴れまわった。
おまけに新技術に対するチューン・アップは日本人のお手の物であり、動力を学び大艦に砲を載せ反射炉で製鉄までした。元々日本は鉄砲大国でもあったため武装艦隊は手が付けられない存在になりおおせていたのである。
時は流れ、ペリー艦隊が日本に砲艦外交を展開したことも南蛮倭国は知っていた。しかし幕府の開港後も政治に巻き込まれるつもりはなく、英国の先兵に甘んじていた。ところが密貿易のパートナーである薩摩が急速に政治の表舞台に出たことによりそうも言っていられなくなったのだ。
倭国は長年の友好関係と島役人への多額の賄賂によって沖縄ー枕崎ルートは庭も同然、そこで沖永良部に流されていた西郷を物心両面で支え、その復帰後も影に日向にサポートしていた。西郷が龍馬に蛇潟老春を引き合わせたのはその時と縁のなせる運命だった。尚、南蛮倭国の日本人が交流したのは密貿易相手の薩摩藩のみだったので今では老春たちは京言葉も江戸言葉も喋れず薩摩弁が標準語だった。
「坂本さあは今更海軍などつくらんと、おいたちにまかせておればよか」
「なにい!」
「おいたちは海禁をした幕府とは相いれもはん。しかも幕府はフランスに肩入れしちょいもす。おいたちは一度義を交わせば必ず守る」
「西郷さん、ホントか」
「相違御座らん」
「むむッ・・・。手の込んだ仕掛けは西郷さんの絵図かの。ほいじゃあわしはなんをすればいいがじゃ」
「かんぱにーをつくられればよか」
「かんぱにーじゃと」
西郷が引き取って言った。
「坂本さあ、こん老春どんとおいたち薩摩が金を出す。坂本さあはそいを預かり日本と世界を相手に大あきないをすればよか。海からの援護でごわす」
「海からの。そうか!海援隊じゃあ」
その後の維新回天の歴史は読者のよく知るところである。
維新後の倭国海上勢力は2つに分かれて存続した。簡単に言えば龍馬派と西郷派に分類され、龍馬派は岩崎弥太郎率いる九十九商会の商船グループ、即ち今日の日本郵船の礎である。それに対して西郷派はのちの帝国海軍に吸収されていく。帝国陸軍が長州系なのに対し、薩の海軍と言われたのはこのグループのことを指す。倭国の日本語は全員薩摩弁だった。
現地の日本人ソサエティは戦前まで国家の体裁は取らなかったが存続し、タイ(バンコク)・河内(ハノイ)・呂宋(マニラ)はそれぞれ日本軍に協力していた。ところが負けてしまったためさすがに居心地が悪くなり300年近く住み慣れた土地を離れた。タイからはインドネシアに移住し、戦後の独立戦争に参加した後はジャワ島の山地にいるらしい。ハノイは台湾の花蓮(ファーレン)に住み着き密かに存続し高砂族の一派に溶け込んでいる。この一派は強力な民進党支持者だと言われている。マニラの連中は戦中に山下兵団とともに北上し、バギオに潜伏した。その後、密かに山下財宝とも称される金塊を山中に隠し持ってフィリピンの世論を裏から操っているという噂が絶えない。
上記3か国の親日ぶりの遠因ではないだろうか。
尚、今日の歴史研究では南蛮のニシーム・ローザエモンと河内(ハノイ)の室西僧正、呂宋(ルソン)のアントニオ・オエスタは同一人物と考えられている。蛇潟老春は言うまでもなく英国人アダムス少佐とジャガタラお春の子孫であった。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:伝奇ショートショート