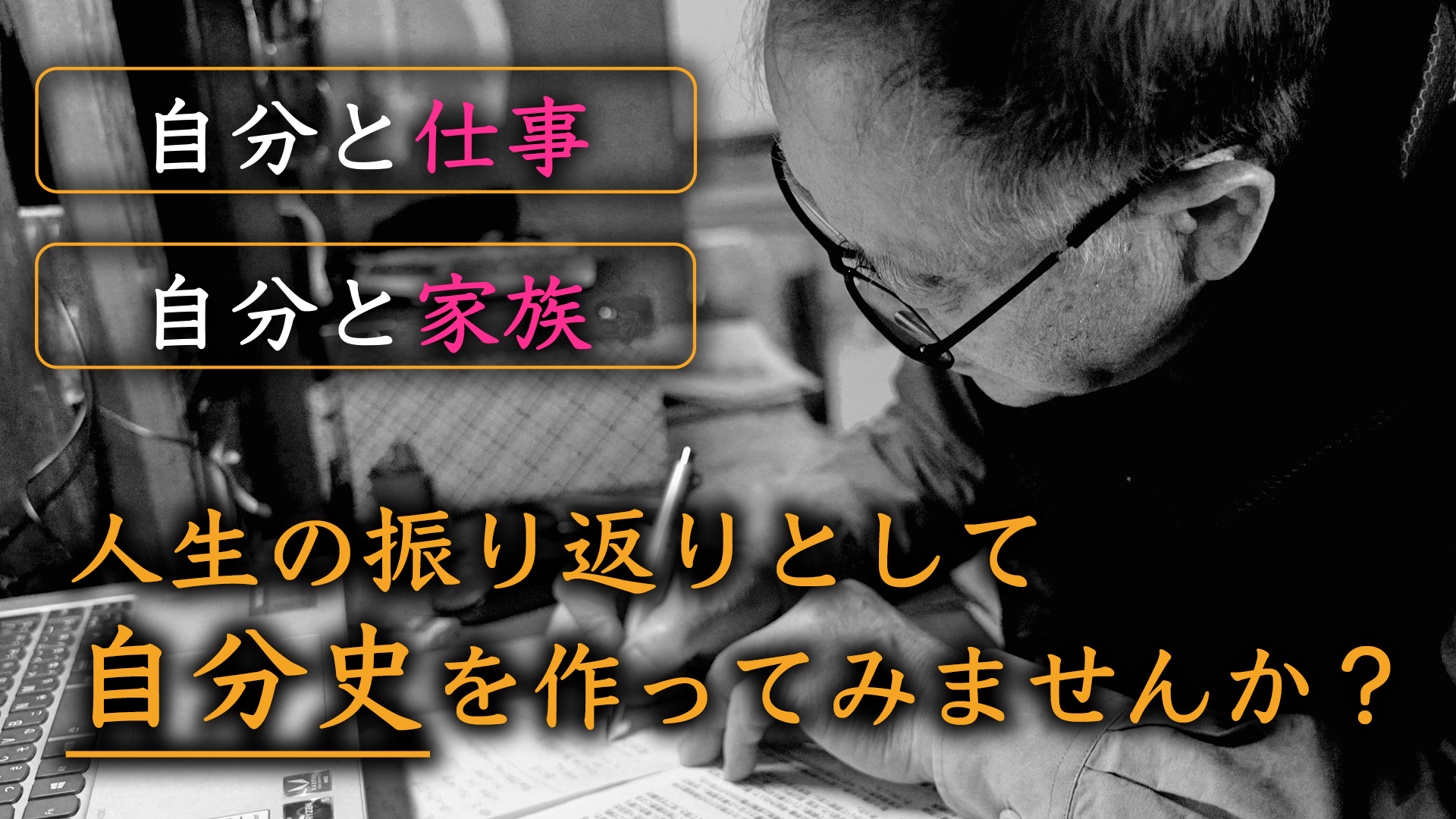新春架空座談会 (文豪編)
2014 JAN 7 12:12:21 pm by 西 牟呂雄

西室「皆様、明けましておめでとう御座います。本年も宜しくお願い致します。さて、皆様が他界されてから長い短い御座いますが、諸先輩から現在の日本の世相を大いに談じて頂きたいとの企画ですが、初めに漱石先生、いかがでしょうか。作品の中で日本はこれから、と問われた人物に『滅びるね。』と語らせておられますが。」
夏目漱石「僕からかね、参るじゃないか(笑)。切り出すのは敗戦後に活躍した三島君の方がいいのじゃないか。」
三島由紀夫「いやいや、先生お願いします。」
漱石「まぁ、ここにいる程度の人ならお分かりだろうが、あれは別に日本人が全滅するとかじゃあない。多少の戦争に勝つには勝って、西欧に追いついたの五大国だのと浮かれるのは少し危ない、と言う意味で警鐘を鳴らしたつもりだ。何しろ僕が『我が輩は猫である』を書き出した時はまだ日露戦争をやっていたんだからね。なあ、司馬君。」
司馬遼太郎「はい。そのあたり私は『坂の上の雲』を書いたことで良く分るつもりです。ただ、私自身はコテンパンにやられた最後の陸軍戦車隊でしたから、正に滅びかけている実感はありましたですね。漱石先生のおっしゃる日本的なるもの、あるいは文化的なものが『滅びる』という意味では、戦前戦後を通じて常に変わりゆくことのアンチ・テーゼとして文学的にも思想的にも現れます。三島さん、そうですよね。」
三島「その通り。僕は戦後の混乱期を肌で感じていたから尚更だ。GHQがいなくなった後の日本を日本人同士がアッチだコッチだとがなりあっているのを見て本当に恐怖した。今となっては単に立ち位置が違うだけと思えるのだが、当時はそれどころじゃない。ああいう終わり方をしたから三島は極右の権化みたいに思われているけど、デヴューの頃は型破りのキワモノ扱いをされもしたんだからね。」
芥川龍之介「今の世の中で言われるような『ネトウヨ』みたいなやつ、あれは三島君の思想的後継者なのかい?」
三島「とんでもない。彼等の心境は分らないでも無いんだが、匿名で騒ぎ立てるのは行動者としての私とは全く違う。まぁ市ヶ谷に至る魂の道程は一言では語り尽くせないのだが、私は思想家でもないし後継者などは残さなかった。」
西室「三島先生の行動に至る前にも、国民としては安保条約とその改定、そしてその後の大学紛争と大変なうねりが起こっていました。」
三島「西室君、それは違うんだ。安保から学生運動への流れには思想的な対立そのものは無いんだ。なにしろ右も左も反対なんだから。あの頃のような凝縮された社会には内輪モメがつきものなんだよ。当時でいえば優れてアメリカに対する反発なんだ。」
西室「それは今日も続いているのではないでしょうか。」
三島「全然違う。まず冷戦構造があってその対立軸の線上に日本が危うく浮かんでいる状態だった。東アジアでは韓国は反日でもなんでもなかったし中国だって大したことはなかったから日本人が感じる外圧はアメリカのみだった。それに迎合しているように見えるものは何でも気に入らない、くらいの話だ。ソヴィエトの工作だってあったがね。」
西室「先生や石原慎太郎さんは一方で時代の最先端の風俗をむしろ広める側としてガンガン走っておられたようにも見えましたが。また『憂国』みたいな映画を撮ったりもされてます。」
三島「不愉快な質問だな。遊ぶときは遊ぶんだ。ついでに言っておくがオレが一言でも『戦争万歳』なんて言ったことがあるか!」
夏目「まぁまぁ、外圧といったって僕がロンドンに行った時なんかに比べれば彼我の距離はずいぶん違うよ。まあ敗けたんだから致し方ないが、僕なんかはロンドンのメシが口に合わなくてビスケットばかり食べて胃を悪くしたくらいだ。しかし三島君が活躍した頃は聞くところの高度経済成長期だったのだろう?司馬君じゃないけど坂の上の雲を目指して必死にセッセとやっていたんじゃないのかね。」
司馬「夏目先生、社会の構造そのものが敗戦で一度崩れています。その後自分で考える間もなく農地解放だ財閥解体だ挙句に憲法はこうしろ、ですからかないまへんですわ。」
芥川「その間に西欧的なるもの、或いは近代的なものへの反動は起こらなかったのですか。」
司馬「もちろんあります。ただ芥川先生の頃とはいわゆる国民の見方そのものが二重も三重も歪められた後ですし、単純には言えませんが左派というものが一種のステータスを持ちましたですからね。」
三島「芥川先生、自虐史観という言葉があります。何でもかんでも日本が悪いと言っているのがメシの種になるくらい論壇の裾野が広がっているんです。今ではその反省期にもさしかかったかと思えます。」
芥川「それは僕のような書生気質には居心地のいい社会とは言えないかい。僕も周りの仲間も、まあ菊池寛は少し違うが、今でいうニートとかオタクみたいな奴ばかりだったよ。」
西室「先生の頃とエリートの有り様が違うんですよ。エリートは何もしなくてもメシが食えたんですよ。」
芥川「何もしないとはなんだ、海軍機関学校の英語教官をやったこともあるんだぞ。」
西室「もっ申し訳ありません。エート本日のテーマに戻りまして、芥川先生の作品の中で『ぼんやりとした不安』と表現されたことの今日的考察なのですが。いかがでしょう。」
芥川「当時の世相と大きく違うのは、今では格差格差と言うそうだが日本全体がこれほど豊じゃなかったからねェ。それこそ当時普通の人がニートなんかやってたらルンペンになって飢え死にするのが関の山だった。」
西室「実はその後の研究で、先生の場合体調を崩され毎日なにもしないでいるうちにご母堂様の死因が精神異常によるものであることを知り、発狂するのじゃないかという『不安』とする説はいかがですか。あッいや、それはともかくぼんやりとしたとは」
芥川「いーかげんにしろ、コノヤロー。もう少し作品読み込んでから来やがれ、このトーヘンボク!」
夏目「芥川君、だけど確か2~3年だったじゃないか、教官やったって言っても。あのねえ、当時は今から考えると原稿料がずっと高かったんだよ。それに新聞社の社員になるという手もあった。僕は朝日、芥川君も大阪毎日だったかな。司馬君は本当に記者だったからプロと言えるな(笑)。僕はそれで帝大の教師を辞められたんだからな。」
西室「夏目先生の一高時代の生徒、藤村操が日光華厳滝で墨痕鮮やかに『巌頭の辞』を残して身を投げたのは、藤村を先生が「君の英文学の考え方は間違っている」と叱りつけた直後だそうですね。」
夏目「ムッ、キミ!いやなことを言うな。そんなこといちいち覚えてないよ。教師が生徒を叱りつけるのは当たりめーだろー。」
西室「失礼しました(長い間白ける)。みなさん江戸っ子なのでお言葉が・・。ところで司馬先生、長く文藝春秋の巻頭随筆で『この国のかたち』を連載されて国家の在り方を論じておられます。その国家を考えてみたいのですが。終戦間際に関東に配置され米軍上陸に備えた際の話ですが。」
司馬「あんたなー、さっきからなんやらケチばかりつけはるけど、座談会の趣旨はどないなっとんねん。」
西室「エッいえ、ちょっと聞いて下さい。先生の部隊に大本営から中佐参謀が来た時の逸話ですが、『敵上陸の際に避難してくる民衆にはどう対処すべきか』の質問に『ひき殺して進め』と答えがあったことになっていて、先生は自国民を犠牲にしてまで守る国というものは何か、と思ったとお書きです。」
司馬「それがどないしたんや。」
西室「しかし、その種の発言をした中佐参謀はいないのですよ。確かに戦車部隊を訪れた参謀は確認できましたが、そんなことを聞いた者は実在しませんが。」
司馬「だからなんやねん。ワレ!えーかげんにさらせ。ワイは歴史家やないで!小説家や。」
三島「一体どういうつもりの司会者だ。なっとらん。僕は帰る。キミ!歴史というのは当事者以外は容易に解釈しちゃいかんよ。」夏目「我が輩も帰る。下らん。」芥川「そうですね、帰りましょう。」司馬「あほクサ。帰るわ。」
西室「・・・・やってしまった・・・・。どうしよう。」
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。
Categories:架空対談