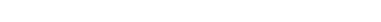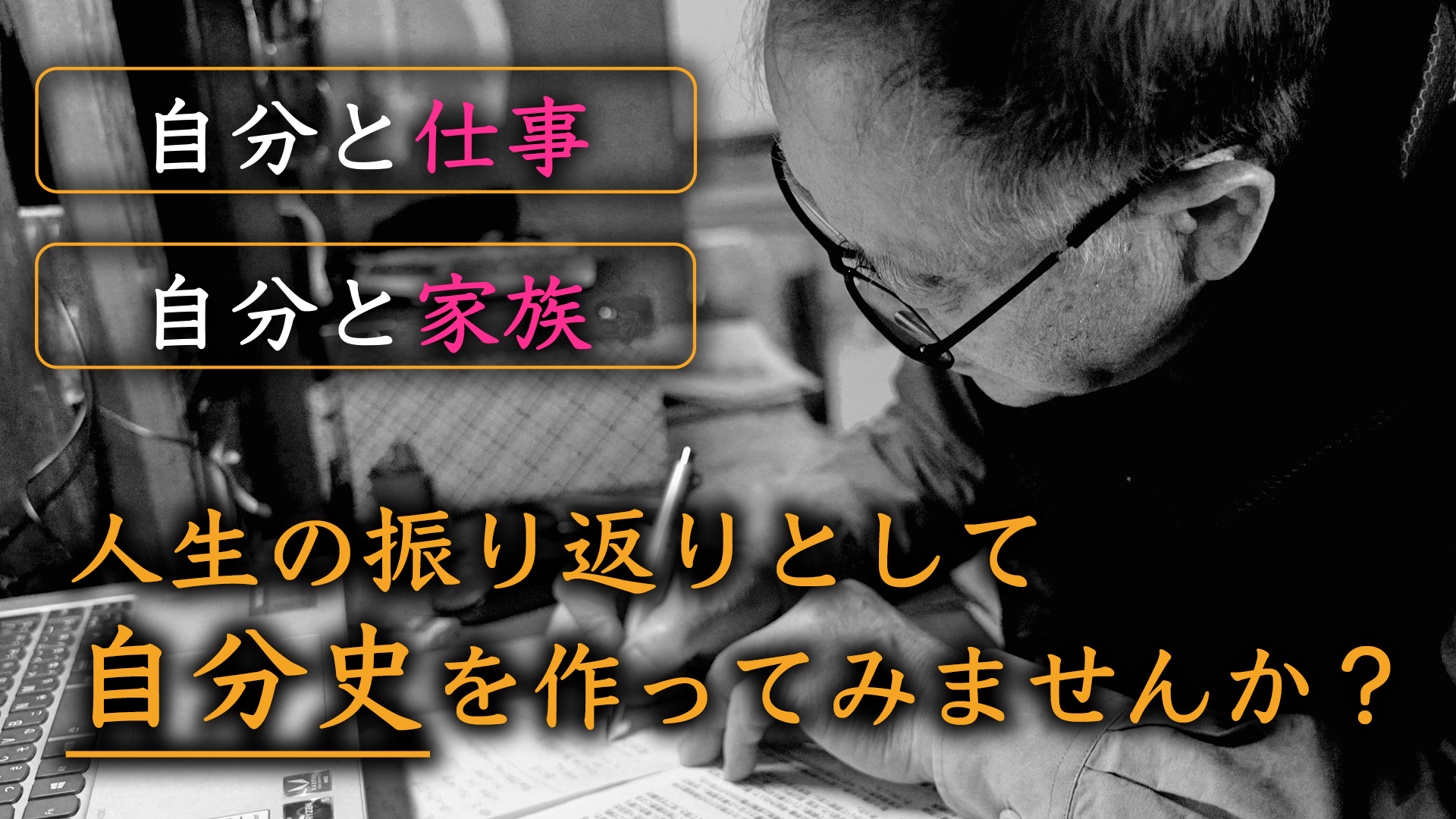タオイズム(道教)は難し
2019 MAR 8 6:06:50 am by 西 牟呂雄

多言(たげんは)数(しばしば)窮(きゅうす)
中(ちゅうを)守(まもるに)如(しかず)
現代訳された『老子』をパラパラ読んで、耳触りのいい片言節句を書き写してみる。ふーん、なかなかいいもんだ、と。『論語』は堅苦しいしね。
生(しょうじて)不有(ゆうせず)為(なして)不恃(たのまず)
長(ちょうじて)不宰(つかさどらず)
是(これを)玄徳(げんとくと)謂(いう)
儒教の体系は朱子学や陽明学に受け継がれて、江戸期にも研究がなされました。
これに比して老荘思想の方は(読まれてはいたが)とかく呪術的要素がミョーな味を添えるせいかすこぶる流行らない、というか道教になるとゲテモノ扱いです。
本場の大陸・香港・台湾でも現世利益的な宗教になってしまって益々怪しい。
故(ゆえに)有(ゆうの)以(もって)利(りを)為(なすは)
無(むの)以(もって)用(ようを)為(なせばなり)
こういった文言を我流に拡大解釈すると、いくらでもなまけていられるのが誠に結構です。それは私の解釈ですが、この系統の学を修めた偉大な先人もそのケがあって困ったものです。
竹林の七賢と言った人材が出ます。魏から西晋の時代に酒を飲んでは清談に興じたことになっていますが、七人とも当時の大変なエリートですから官僚だったり軍人だったりして隠遁しても別に苦労もしない連中なのです。
多少行儀の悪い元サラリーマンのアル中だと思えば腑に落ちます。
王弼・何晏・郭象といった政治家が有名です。
ところがですね、この人達もっといかんのですよ。
王弼(おうひつ)は魏の時代の人。子供の頃から秀才で名高かったのですがチャラチャラしたキャラで、酒ばかり飲んでは音律に通じたりしています。頭のいいことを鼻にかけるところがあって当時の知識人からは嫌われました。
何晏(かあん)も同時代の人ですが、これがまた手鏡に自分の顔を写しては喜んでいるようなナルシストの自信過剰。おまけに大変な女好き。
郭象(かくしょう)は西晋の時代に『荘子』に脚注を入れた学者です。大変に口が達者で『懸河の水があふれるがごとく』喋りまくったらしい。しかし史書には「郭象は軽薄な人間」と書かれてしまう。
これらの人々は”玄学の徒”と称されますが、いくら『無為自然』とはいえこれでは。儒家の言う”徳の無い”こと夥しい。
どうもこういった才人は「ただ内側から光っていればいい」といった境地には至らないもんなんですかねぇ。老荘の学、奥深し。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:遠い光景