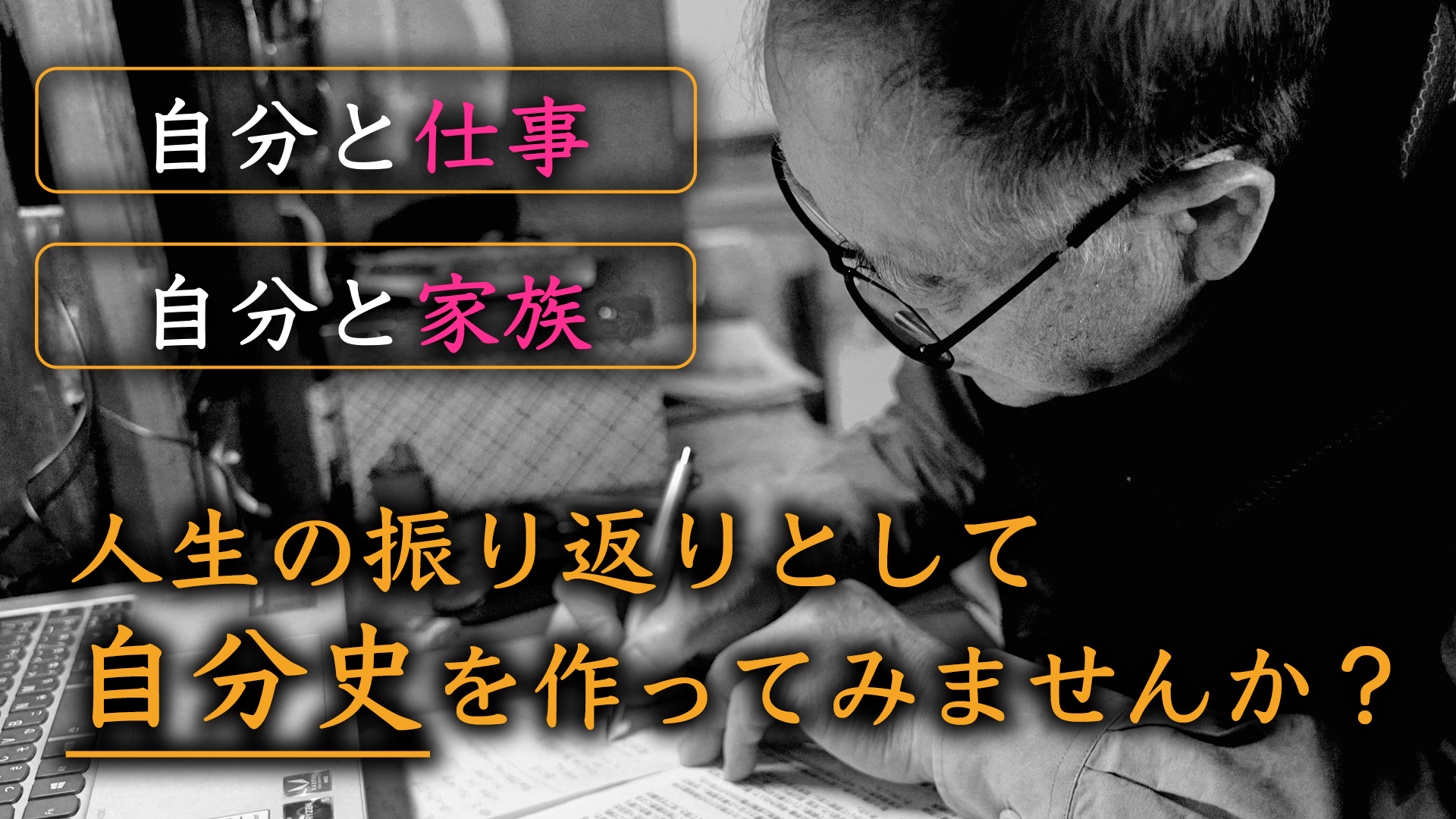天台座主尊雲法親王
2021 MAY 14 1:01:13 am by 西 牟呂雄

「お次!」
今日もやや甲高い声が叡山に響き渡る。太刀・薙刀をしつらえた荒法師が次々になぎ倒され『参り申し候ー!』と打ち据えられる。天台座主自ら僧兵達に武道を手ほどきしていた。
尊雲法親王はわずか6歳で延暦寺に入山すると、その稀に見る英明さでたちまち宗徒の耳目を集め、二十歳になるや天台座主に推される。すると今度は武術の稽古に邁進し、瞬く間にそれを極め、一山の者は舌を巻いた。のちの太平記に『まこと不思議なる御門主』と記される所以である。
顔立ちはやや丸顔に切れ長の鋭い目、小柄ではあるが筋骨たくましく、6尺の塀を軽々と飛び越えた。声はよく通る響きで数千人の山法師はことごとくこれに従った。読経の際の澄んだ声と妖しい眼光からか、軍神・摩利支天の生まれ変わりの神人と称える者もあり、事実しばしば予言めいた偈(げ)を唱え、それは全て当たった。
それもその筈、尊雲法親王の父親こそかの皇統の魔人ともいうべき後醍醐天皇その人であった。
「殿ノ法印、これへ」
尊雲の声が闇を切り裂くと『おん前に』と太い声の返事があり、巨漢の天台僧が現れた。殿ノ法印良忠、関白藤原良実の孫でありながら怪力無双。尊雲の側近中の側近である。
「都の帝に厄災近し」
「・・・っと仰いますと・・」
「帝に大望あり。鎌倉に知れよう」
「そっそれでは」
「帝の御身が危うい。良忠、山を下り都に潜め。八瀬童子を集め備えよ」
「御意。いつもながらの千里眼、恐れ入り候」
「ここも危ない」
「・・・御門主・・・」
「天命と心得よ。いずれ還俗し帝を支えん。ホホホホホホ」
後醍醐天皇は宋学を修め真言に凝り、書を能くし琵琶の名手、茶道の闘茶を主催する全能の帝のような華麗さであるが、同時代の身内の評判は惨憺たるものだった。堂上公卿からも総スカンの有様。要は人の気持ちを斟酌することができない驕りと我儘の塊で周りは全て塵芥にしか見えない。尚且つ執念深く猜疑心の強い性格は魔人としか言いようがない。こちらもまた珍しき天皇であった。
異様な眼光と圧倒的な迫力に、初めはひれ伏さない者はない。しかしながら毒気が強すぎて凡人はその目を見つめ続けることさえできずに委縮し、その後には離反した。
その帝が鎌倉に憎悪を抱かないはずがない。
幕府の方でも警戒し、さっそく中宮(正妻)西園寺禧子への御産祈祷が幕府への呪詛との嫌疑がかけられる。これでおとなしくなるかと思いきや、5年後に討幕計画がチクられて三種の神器を持って逃げ出さざるを得なくなる。尊雲は情報網と独自のカンでそれを察知し先程の会話となったのである。
しかし時がわずかに遅く、良忠が駆けつけた時は比叡山への逃亡に失敗していた。慌てた良忠は八瀬童子の手を借りて帝を笠置山に落ち延びさせた。
同時に叡山の尊雲にも扇動の咎により死罪を申し渡しをすべく六波羅の兵がせまったが、尊雲は僧兵を指揮しこの大軍を坂本にて鮮やかに撃破、姿を晦ませた。山法師達は妖術でも使ったかと噂し、敬愛する天台座主の無事を祈った。
結局、笠置山の後醍醐天皇は圧倒的な兵力に包囲され捕らえられる。その有様を、父帝の花園院から「王家の恥」「一朝の恥辱」と記された等、宮中における不人気を物語っている。そのまま隠岐島に流された。
殿ノ法印良忠も捕縛され六波羅の牢にぶち込まれる。ところがこの荒法師は夜半、その怪力にモノを言わせて錠を捻じ曲げて遁走し、密かに尊雲の後を追った。
以後、尊雲は各地に突如姿を現しては消える神出鬼没の振る舞いで幕府軍を翻弄する。
般若寺では五百騎の兵に囲まれ、本堂の大般若経の経箱に身を潜める所を目撃された。雑兵が経箱をひっくり返すと姿は見えず例の『ホーッホッホッホッホ』という笑い声だけが響く。
吉野では6万の軍勢を相手に、7本の矢を受けるが又しても笑って消える。さすがに幕府方は気味悪くなりだした。次に高野山に現れた時は途中十津川にて還俗しており、大塔宮護良親王の名乗りを上げた。令旨を発するやたちまち参ずる者が後を絶たない。
またその頃、以前より怪僧文観の仲介により後醍醐天皇と通じていた正体不明の悪党、楠木正成が河内より猛烈なゲリラ戦を展開していた。
するといかなる技を使ったか魔人は復活し隠岐の島を脱出した。その霊力は以前にも増して恐ろしく、目は赤光を放ち、舌鋒は火を噴くが如し。ついには西国鎮圧に派遣されてきた足利尊氏を寝返らせ、六波羅を全滅させてしまった。
鎌倉の抑えが効かなくなった時代背景もあり、この動きは連鎖反応を起こす。新田は鎌倉に攻め入り鎌倉幕府は滅亡した。
満を持して上洛した後醍醐天皇は上機嫌で尊氏に『尊』の字を与えた。ところがどうしたことか大塔宮が馳せ参じない。宮は何を考えているのか。
「殿ノ法印、これへ」
「御前に」
「わしの代わりに都に上れ」
「・・・宮様は・・」
「行けば必ずや厄災に巻き込まれるであろう」
「それは、いつもの千里眼にあらしゃいまするか」
「さよう。わしには見えた。帝の周りに蠢く魔性の輩多し。足利、土岐、高、佐々木、それらは皆、帝が引き寄せた者ども」
「帝はお気づきにならしゃいませぬと」
「違う。帝がかの者達を邪悪にしてしまうのだ」
案の定、良忠が上洛してみると、いきなり六波羅を攻略した折に手勢の者が狼藉を働いた、との廉で尊氏の手により配下の十名以上が六条河原に晒されてしまった。仰天した良忠は上洛はやはり厄災である旨を宮に上奏した。
いつまでも上洛しない宮に手を焼いた帝は、遂に大塔宮を征夷大将軍・兵部卿に宣旨した。仕方なしに宮は入京するが、その際には総勢20万騎にもなる私兵を率いていた。さすがの尊氏も、その親衛隊を率いる高師直も驚いたが、だれよりも肝をを潰したのは後醍醐天皇であった。二人の対面は魔人と神人が向き合う異様な雰囲気となった。
帝は御簾の奥からもわかる凄まじいオーラを発していたが、宮もまたそれを跳ね返す眼光で対峙した。居並ぶ公家も尊氏もまるで瑠璃光が漂っている錯覚にとらわれた。しかも二人とも型通りの挨拶の後に一言も発しないのだ。末席にいた尊氏は気分が悪くなったが外す訳にもいかず、ダラダラと冷や汗が背中を伝うのをひたすら堪えた。
尊氏が屋敷に帰って来ると弟直義初め高師直以下幕僚たちが首を長くして待っていたが、真っ青な顔色を見て息を呑んだ。
「殿、いかがでしたか」
「どうもこうもない。恐ろしいものを見た」
「・・・恐ろしい・・・と言いますと」
「帝も一筋縄ではいかないお方だが、宮もまた我等の手に負えるお方ではない。宮が征夷大将軍のままではこっちが危ない」
「どうなされますか。一戦交えると」
高師直が一言漏らすと、尊氏が諫めた。
「馬鹿ぁ!宮は20万騎もの私兵に守られている。負けるに決まってるだろう。しばらく様子見だ。帝も警戒されておられると見た。あのお二人親子とも思えぬ」
尊氏も優れた政治家である。宮中含め都の隅々にまで情報網を巡らせジッと待った。諜報の元締めはかのバサラ大名佐々木道誉である。道誉は武名のみならず連歌・闘茶・香道・立花に深い造詣があり、加えて派手な歌舞伎者ぶりに都の子女から宮中の女房達にまで絶大な人気があった。それをフルに使い、はなはだしきは宮中の噂をことごとく知ることができた。何しろ洛南大原野の勝持寺にあった4本の桜の大木が満開になると、その下に3mもの高さの黄銅の花瓶を置き、遠目には立花に見える仕掛けを施し、都中の白拍子・田楽師を呼んで乱痴気騒ぎに興じた。美酒に山海珍味を山盛りにし、巨大な香炉でむせ返る程の名香を焚き上げるという凝りように、都人は喝采し謡い狂った。婦女子でなびかぬものはない。
すると最近天皇の寵愛を最も受けている側室は新待賢門院という姫君であることがわかった。しかも新待賢門院は恒良親王を産んでおり、その皇子を帝位に着けるため最大の障害が大塔宮をであると思っているらしい。
尊氏は舌なめずりする思いで絹やら香やら惜しげもなく贈り続けた。そして頃合いを見て散々吹き込んだのだ。
「それがし、いかに帝のために骨を折ろうとも厭いは致しませぬが、なぜか大塔宮様の御憎しみを賜り候。毎日身の細る思いで勤めておりまするが、ひょっとして大塔宮様は帝位を望んでおられるやも・・・」
抑揚たっぷりにささやかれるとつい確かめたくなるのは人情、帝との寝物語に繰り返し尋ねる。帝は魔人である。股肱の臣が怯えるのを放っておく訳にはいかない。しかも息子とは言え久方ぶりに会ってみれば恐るべき強者になっている。そして勅命に至った。配下の20万騎を解散させよ、と。勅命とあらば是非もない。手勢の多くを所領に帰し、残ったのは殿ノ法印、光林坊玄尊、赤松則裕律師と僅かなものになった。更に帝は清涼殿の御開宴の時に護良親王を捕縛する挙に出た。二人の間には火花が散り、殿ノ法印は吠えた。
「僭越至極!」
「ホホホホホ、殿ノ法印。慌てずともよい。遠からず帝の心安んじ奉る」
「それはいつもの千里眼にあらしゃいまするか」
「帝に女難の気が立ち上っておる。その後、もののふ共も離反あり」
尊氏はこの機を逃さず、宮の身柄を確保したのちどさくさ紛れに鎌倉にいた弟直義に預けてしまった。
大塔宮は初めから坂東武者の田舎者をことごとく見下し、足利兄弟はいつ裏切るかわからないと警戒していた。しかし帝は鷹揚な尊氏をコンントロールできるのは自分だとの自負が強く、むしろ危険なのは大塔宮として、結局希代の政治家尊氏の思う壺にはまった。魔人も神人も政治家に手玉に取られたのである。
「此頃都ニハヤル物 夜討 強盗 謀(にせ)綸旨
召人 早馬 虚騒動(そらさわぎ)」
二条河原に墨痕鮮やかな落書が高々と掲げられた。
「追従(ついしょう) 讒人(ざんにん) 禅律僧 下克上スル成出者(なりづもの)」
見苦しく蠢く者をあげつらい、禅宗・律宗などにも冷水を浴びせる。
「キツケヌ冠上ノキヌ 持モナラハヌ杓持テ 内裏マシワリ珍シヤ
賢者カホナル伝奏ハ 我モ我モトミユレトモ」
ドサクサと官位にありついた成り上がりを貶し、
「為中美物(いなかびぶつ)ニアキミチテ マナ板烏帽子ユカメツヽ
気色メキタル京侍 タソカレ時ニ成ヌレハ ウカレテアリク色好(いろごのみ)」 その田舎者ぶりをこきおろす。
「ハサラ扇ノ五骨(いつつぼね) ヒロコシヤセ馬薄小袖
日銭ノ質ノ古具足 関東武士ノカコ出仕」
東国侍の風俗を嘲笑う。
後年、庶民の怨嗟の声との解釈もなされたがさにあらず。鎌倉に引かれる直前に大塔宮の命を受けた殿ノ法印が叡山の僧に仕立てさせた最後通牒だったのだ。
鎌倉では尊氏の命を受けた直義が手ぐすね引いて待っていた。この弟は、豪胆無比でともすればあっけらかんとした気前の良さとおおらかなところのある兄尊氏と違い、厳格にして果断。万事筋を通すのだが猜疑心が強く粘着する。尊氏は島流しくらいのつもりだったのだが、宮の扱いは苛烈を極めた。背伸びもできない湿気の多い土牢に閉じ込め、共に落ちて来た殿の法印等の側近達とは顔を合わせることを禁じた。更にむごいことに、愛妾である雛鶴姫のみ月に一度土牢に通わせるという仕打ちである。その日は土牢を見分させる鬼畜の振る舞いまでした。
さしもの宮もげっそりと痩せこけ日に日に神人の面影は薄くなる。
運悪くその半年後、滅ぼされた執権北条高時の一子、時行が残党を率いて一矢報いんと鎌倉に雪崩れ込んだ。中先代の乱である。時行にすれば親の弔い合戦、怨念の塊のような鬼神の攻撃に直義は溜まらず鎌倉から退却する。その混乱の最中に後顧に憂いを絶つとして七人もの刺客を差し向けた。はたして宮は覚悟を決め、開け放たれたにもかかわらず牢から出てこない、いや既に足が萎えて自由歩行ができなくなっていたのだ。暗い土牢に恐る恐る押し入った一人目の刺客は絞殺された。その首に飛びついた淵辺義博が太刀で喉元を刺そうとする、宮は振り向きざまに剣先を噛み折った。こぼれた太刀でなんとか首を取り、這い出して見分しようとした途端、見開いた目が動き淵辺を見据えた。
「ギャーッツ!
思わず放り出し逃げ去った。
大塔の宮の千里眼はその後ことごとく当たり、後醍醐天皇は南朝に君臨するも二度と都に上ること叶わなかった。その魔人天皇に時に従い時に反目しつた足利兄弟も終いには相争い直義は毒殺された。直義の天敵だった親衛隊長たる高師直は観応の擾乱によって戦死。室町幕府を開いた尊氏にしても最期は背中の腫れ物に苦しめられた。廱(よう)即ち黄色ブドウ球菌による毛嚢の化膿の集合体である。拳大に腫れあがった肉腫にはハチの巣のような穴が開き血の混じった膿を脈と共に吹きだすという恐ろしい苦しみの中で死んだ。
帝の女難の相は結局のところ大塔宮の方に降りかかったのだった。この混乱を最後まで生き残ったのはバサラ者の佐々木道誉だけであったが、婆沙羅こそ乱世に会っての華であり、平時には趣味の悪い毒でしかないのである。
ところで、恐怖のあまり投げ捨てられた宮の首はどうなったのか。
大混乱の最中に密かに土牢に駆け付けたのは宮に従って来た愛妾の雛鶴姫と供の者数名。雛鶴姫はそこではっきりとした宮のカン高い声を聴いた『雛鶴、こちらじゃ』。その声に導かれるように藪に分け入ってみると、果たして変わり果てた宮の首が転がっていた。ああ、宮様、と駆け寄って泥と血にまみれた首を取り上げると、宮の瞳ははっきりと雛鶴姫を見つめたのだ、口には噛み切った剣先を咥えたままに。
「おいたわしや」
水で洗い清め薄化粧を施すと、生前の面立ちが蘇り生きているがごとく艶やかであった。
雛鶴姫と供の者の数名は途方に暮れたが、ともあれ鎌倉にいてはどうなるのか分からない。ひとまず都を目指そうと鎌倉街道を北に進んだ。
戦の直後とあっては落ち武者狩りのの野伏りや武装百姓が金品目当てにそこかしこに潜んでいる。そこを僅かな人数での逃避行は危険極まりない。そして、実は雛鶴姫は宮の子供を宿していたのである。
武蔵の国を横切り、相模の津久井を抜けたあたりで案の定野盗の一団に目を付けられた。人数の少ない上に女人の遅い脚、たちまち取り囲まれた。
「クククク。金目の物とその女を差し出せ。命は助けてやる」
頭目とおぼしき大男が笑みを浮かべて凄んだ。
ところが雛鶴姫は少しも動じない。にこやかに供の者を促し、葛籠の中から丸い円筒状の物を取り出すと、捧げ持つようにして中の物を取り出した。
「なんじゃ、それが自慢の宝物か」
うそぶきながら近づいた男はその物を見た途端『ぎゃああああ』と叫んで後ろに倒れた。
何とそれは生首で、しかもその瞳ははっきりと男を見つめると虹色の妖しい光を発した。他の野盗共も『ヒイー』と怯えた声で飛び散るように姿を消した。
一行が甲斐の国に差し掛かかった頃は旧暦の年末、雪のチラ就くほど寒かった。人里離れた渓谷沿いで、間の悪いことに雛鶴姫が産気づいてしまった。
急ごしらえの褥(しとね)で難産の末皇子を出産したのだが、旅の疲れと寒さにより哀れにも母子は亡くなってしまった。
あまりの無常さに残された従者はこの地を無生野(むしょうの)と名付けて雛鶴姫と皇子を手厚く葬った。今日まで伝えられる無生野の大念仏という行事は、護良親王の神霊と雛鶴姫母子を弔うものとして、その地で帰農した従者達によって残された。現存する雛鶴神社は母子を祀っており、石舟神社は大塔宮を祭神としている。尚、真偽のほどは分からないが雛鶴姫が押し抱いていた宮の首も石船神社に残され、年に2度公開されている。現在、無生野の大念仏は国の指定無形文化財でありユネスコ無形文化遺産への登録が提案されている。
この話には続きがある。護良親王の皇子である葛城宮綴連王(つづれのおう)、陸良もしくは興良親王は南北朝の戦乱の中に行方不明となったが、実は雛鶴姫の没後20年ほど経ったこの地に現れ雛鶴姫と兄にあたる皇子の話を聞かされる。そしてこの地を定めの場所として居住し、一子五孫を得て天寿を全うしたという。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:伝奇ショートショート