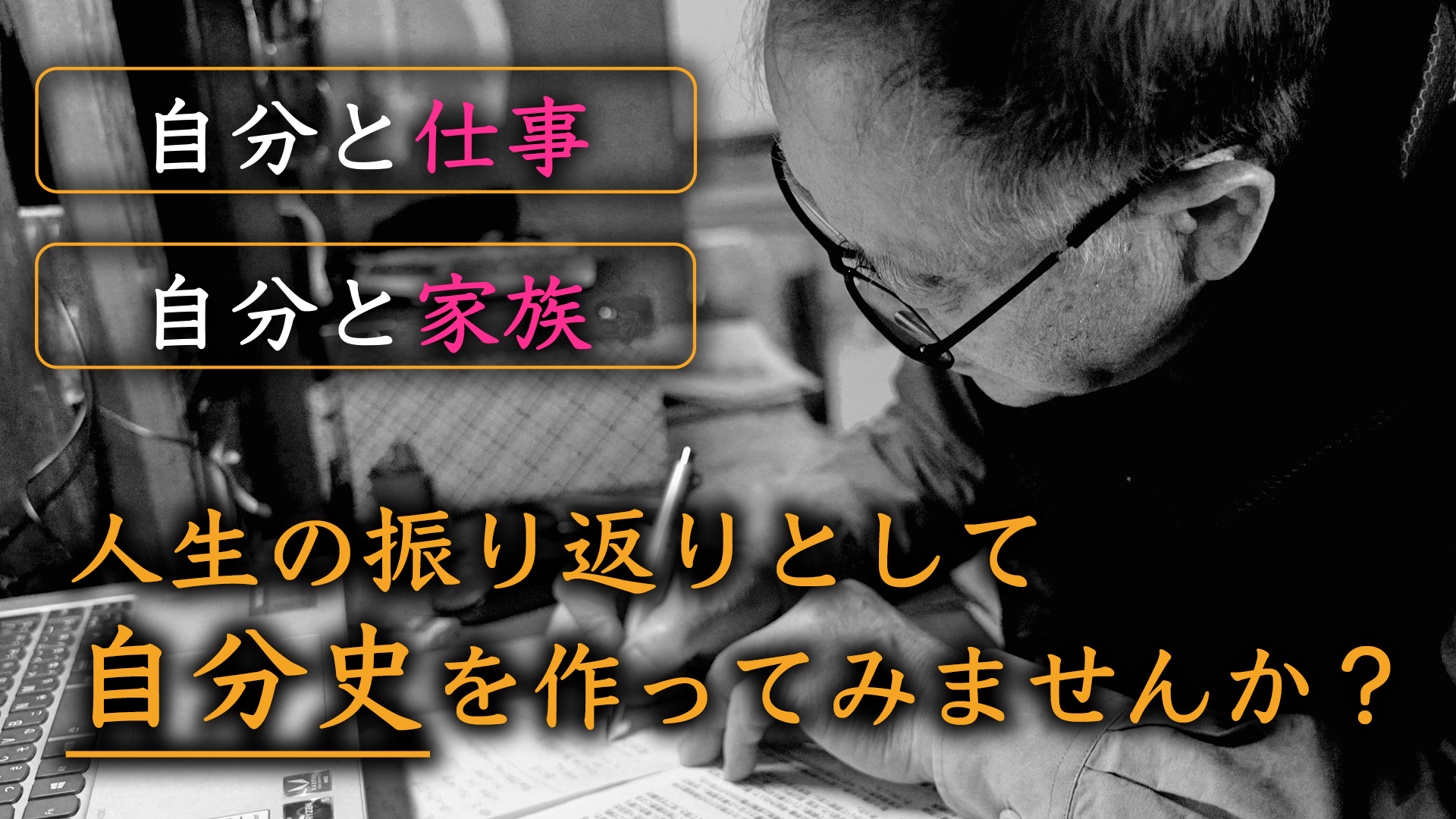サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(198X年女子高編 Ⅱ)
2014 MAY 5 20:20:29 pm by 西 牟呂雄

椎野ミチルが声をかけたのは、ナンパで知られるK大生だった。おりしも秋の野球リーグの最終試合の対抗戦を皆で観戦する、という筋書きだった。
ミチルは当日集合した時点で、もう少し打ち合わせをしておけば、と後悔した。英 元子は制服であるセーラー服を着ており、出井 聡子はGパンにトレーナー、自分はこの頃謂うところのハマトラだった。そしてB・Bがやって来ると、皆息を飲んだ。髪をセットした上に、薄化粧を施し、真っ赤なスーツにハイ・ヒールである。
「ちょっとB・B、何、その恰好。」
「うーん、お母さんがちゃんとして行きなさいって買ってくれたのー。」
「・・・・・・・・・」「・・・・」「・・・・」
案の定、合流したK大の4人も目が点になった。
「ごきげんよー。」「ごきげんよう。」「こんにちは。」
挨拶の後、椎野 ミチルの彼氏である、市川がソッと聞いた。
「オイ。あのミズっぽいのは何だ。」
野球そのものは、伝統にのっとった応援合戦あり、アトラクションあり、試合も逆転ホームランが出る、といった具合で大いに盛り上がった。
男女交互にすわったのだがこの際、B・Bが真ん中。左右を、青いジャケットに縁無し眼鏡とサーファー風にはさまれて、体を硬くしていた。二人がしきりに気を使って話しかけるのだが、反応は鈍い。ときおり聞こえてくる会話では、何と彼女は野球を知らないのだった。
「あの人は何で走れるのですか?」
「あれは盗塁。モーションを盗んで走るんだよ。」
「それは、反則をしてるのですか?」
「はああ?・・・・あのー。」
一番隅にいた出井聡子は、時折聞こえてくる会話から、B・Bの極度の緊張感がビリビリ伝わって来るので、気になって野球どころでなくなってしまった。
試合の結果はK大がサヨナラで勝利し、スタンドは興奮のルツボと化した。そして全員総立ちとなって校歌の合唱となるため、応援部の指導のもとに肩を組んだ時、異変が起こった。左右から肩に手を回されたB・Bが貧血を起こしたのだ。
「マジ失敗もいいところね。」
「あれからこっちも大変よ。市川君が『オレの面子をどうしてくれる。』とか逆ギレするし、アタシも頭にきて大喧嘩よ。」
「ウソ。何その面子って。」
「あの後皆で中華でも食べることにしてたらしいのよ。だからって怒り出されてもねえ。おまけにB・Bのこと散々悪く言うし。もう願い下げだな。もともと軽い奴だったし。そう言えば、聡子の電話番号(この頃携帯はまだない)知りたがってるのがいたらしいよ。」
「趣味じゃない。アッB・B来た。」
「ごきげんよー。昨日は楽しかったねー。」
「・・・・。」「・・・・。」「・・・・。」
「男の人ってやさしいねー。だけどあの人達ってちょっと軽くない?やっぱり真面目な高校生がいいなー。」
「チョット玲!そん時はあのカッコはやめてよ。」
椎野ミチルが堪らず言った。
次の機会はすぐにやって来た。G大付属高校の同じ学年である。今度は秋の文化祭で、場所柄前回の失敗もあったので、E女子高のセーラー服の制服で行くことも決めた。
椎野 ミチルの彼氏は仁村といった。他の3人も皆真面目そうで、全員眼鏡を掛けていた。彼等は歴史クラブに属していて、今年のテーマは「決戦!関が原」と称して凝ったジオラマを展示していた。早速案内されていくと、嬉々として説明をしてくれた。出井 聡子は改めて、椎野 ミチルのジャンルの広さに舌を巻く思いだった。
昼食をとりに校外に出て、ピザを食べに行った。4人のポジションも前回の失敗を踏まえ、中心に椎野 ミチルとお相手の仁村君、聞き上手の出井 聡子が脇を固めるシフトを敷いた。
「4人は何の仲間ですか?クラブ?」
「全然関係ないのよ。聡子はテニスで元子は軽音楽。ギターが上手いのよ。玲はバスケ。」
「こんな綺麗な娘が4人仲間って珍しくね?」
一瞬光が走ったような緊張が生まれ、一同黙った。何というセンスの無い会話か。
「そんなこと無いです。この前も誰が一番ブスか、でもめました。」
これもどうかと思われる、B・Bの不規則発言である。
「へー、それで誰になったの?」
出井 聡子は目の前に座っている、この無神経男を殺してやりたいと思った。椎野 ミチルは彼氏の手前あせった。
「やあね、玲。違うのよ、事の発端は『友情論』なんですよ。」
「オツ、ボナールだね。それはオレも読んだな。」
「うん、キザなオヤジだよね。」
「でしょー。男と女のところなんか、なに、あれ。」
「だーかーらー・・・。ボナールはそれが有るって考えなのよ。」
「違うわよ。無い、と思ってるから、あっちでもこっちでも、友情はこう、愛情はこう、って書くのよ。」
一般にこの年頃の男女がこの手の話しを四つに組んで話すには、余程ませた場合を除き、男の方が幼すぎるケースが多い。この時がそうだ。
更に、男子側に、彼女達の気を引こうとする意思が働いており、論点が絞りきれず、『僕もそう思うなー。』だの『僕はその逆だなー。』といった、ふやけた相槌しか打てなかったため、彼女達は例によって、かってに熱くなりだした。男側である仁村君はこの場を取り繕おうと、頭をフル回転させた。結果が地獄とも知らずに。
「それで、玲さんはどういう考えをとっているんですか?」
「あたしは、男女の友情はある。だけどあたしは友情をもって接してあげない、って立場です。」
「すると今僕達とこうして話してますよね。僕はミチルと付き合ってますけど、僕と玲さんの間はある種の友情めいたものがあってもいいじゃないですか。それも否定されると、もし玲さんが何かを感じるとすると、それは愛情になる、ということですか?」
「なんですって!」
本人に何の悪気があろうか。一種の知的会話をしているつもりだった仁村君は思わぬB・Bの剣幕にたじろいだ。椎野ミチルも続く。
「ちょっと。何それ。何の下心があってB・Bに絡むのよ。」
「いいいやっ、違う。例えばの話しだよ。カンベンしてよ。B・Bって誰?」
「玲のことよ。原部(ばらべ)玲。通称B・B。」
「アッ珍しい苗字ですね。」
テーブルの反対側の4人は冷静さを取り戻していたが、既に会話に参加する気力を失っていた。
「こうして見てるだけだったら結構おもしろいね。」
「あのー、あの玲さんって人、いつもああなんですか?」
「あんなもんじゃないですよ。まだ泣きが入ってないですし。蹴りも出てませんから。」
「エッ。」
「元子。およしよ。」
翌日、英 元子がボソボソと出井 聡子に言った。
「ねーえー。いつまでこんなことやってるのー?あたしゃ降りたいよー。」
「それがねー。ミチルがあれから逆ギレして仁村君振っちゃったらしいよ。」
「ウソー。何それー。」
「夕べ連絡が入ったんだけど、夜にあやまりの電話が入ったんだそうよ。で、話してるうちに頭にきたらしくて、怒鳴りつけたんだって。そしたら仁村君も怒っちゃって、もう別れようってなったらしいんだ。」
「まったくー。愛も友情もないもんね。」
「ところがそっから大変なのよ。」
「何が。」
「っていうかー、こうなったら今度こそB・Bに一泡拭かせてやる、って言うのよ。」
「ミチルもバカねー。こんなことしてたらいくらあの娘モテてもカレシいなくなるよー。」
「それも破れかぶれになったらしくて、今度はオヤジだ、だって。」
「キャー、あたしゃヤダよ。エンコーなんて。」
「バカ、バカ。元子、何てこと言うの。でも何かあんまりフツーじゃないみたいなんだな、これが。今度の日曜にお鮨おごってくれるって言ってた。」
「どっちにしてもあたしゃ今度で打ち止めにさせてもらうは。」
「あたしだってそうよ。」
「着てくもんどうすんのよー。B・B又あの恰好だよー。」 続く
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。
Categories:サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる オリジナル