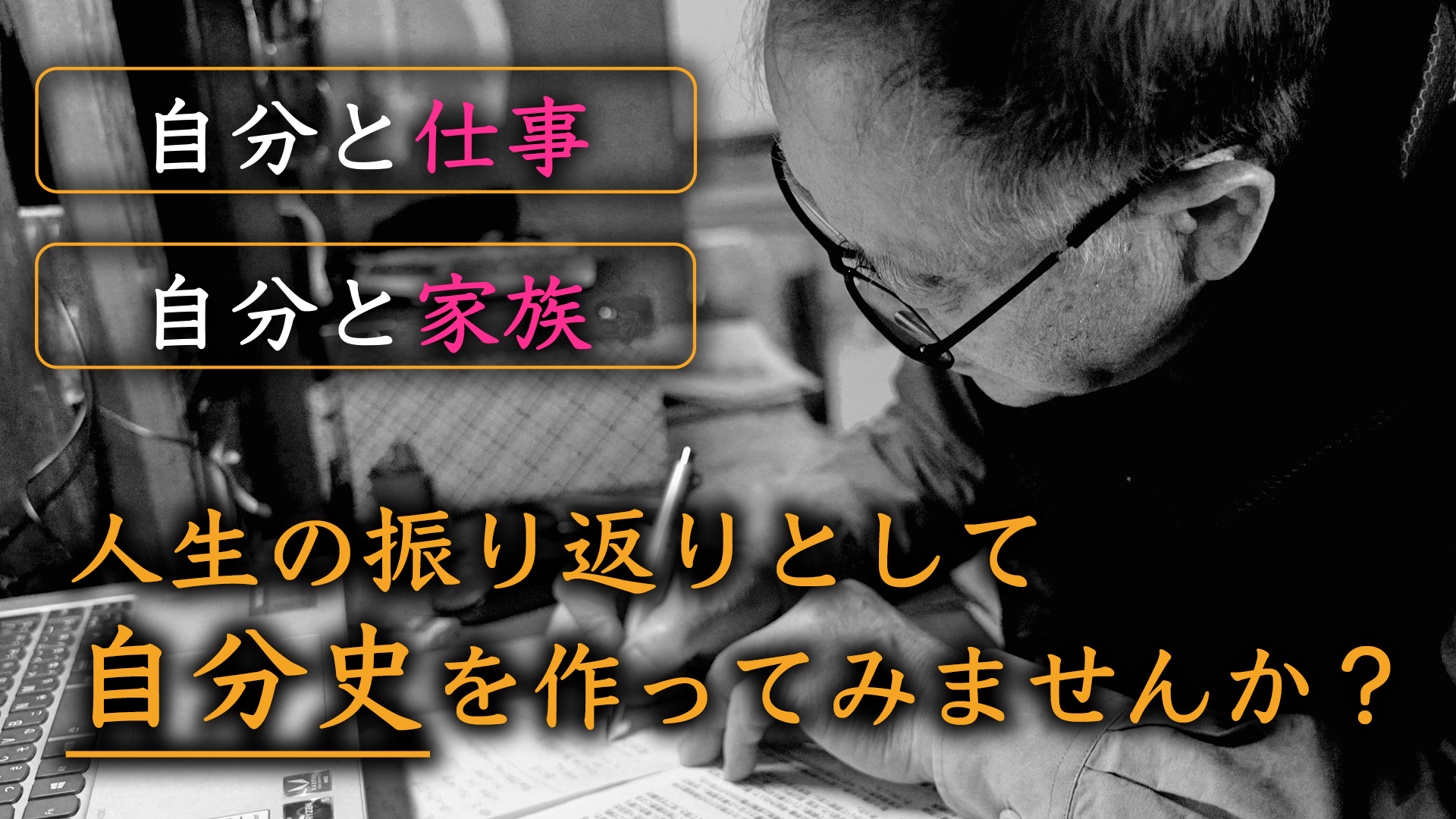サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(198X年女子高編Ⅲ)
2014 MAY 9 19:19:48 pm by 西 牟呂雄

「ごきげんよう。」
E女子高独特の挨拶をしながら、鮨屋ののれんをくぐると、そこには異様なオヤジが4人いて、既に飲んでいた。それも4人とも違うものだった。ビールと焼酎と日本酒にウィスキィだった。
今回は相手が相手なのでファッションは各々勝手にしたところ、B・Bは例のスーツ、英元子はトックリのセーターにジャケット、椎野ミチルは例によってハマトラ、出井聡子はワン・ピースとそれなり。だが、オヤジ達は見事に予想を裏切って、業界風ジャケット、ジーンズ上下、濃紺のスーツ、そして遊び人風着流し!事前に椎野ミチルが『何か相当壊れたオッサン達らしい。』と言っていたのもうなずけた。
その中の業界風が、時々椎野ミチルを映画に連れて行ったり、食事をご馳走してくれる、彼女に言わせると『アニイ』なのだそうだ。
「ごきげんよう。アニイ。」
「オウ、何かもめてるっつー話しだからこっちもあらゆるバリエーションに対応できる面子を揃えたよ。まあスシ食いねー。」
豪華な鮨桶が運ばれ、早速パクつきだした。
「(アニイ・ウィスキィ)じゃ一応自己紹介と行くか。合コンの礼儀だからな。広告代理店をやってるイベント屋だよ。趣味バクチ。別にヤクザじゃないから、そこんとこヨロシクウ。」
「(着流し・ビール)僕は物理屋、この着物シブいだろ。ネット関連やってて今は受験産業で食ってます。」
「(スーツ・焼酎)オレはアジア屋。オレ一人マンサラだ。サラリーマンね。趣味ヤ・ザ・ワ、よろしくゥ。」
「(ジーンズ・日本酒)オレは英語屋。ブスっとしてても機嫌悪い訳じゃないんでご心配なく。大学で教えてます。趣味翻訳。」
「あのー。どういうお仲間なんですか?」
「ミチルちゃん達と同じさ。高校の同期だ。それじゃそっちもやってよ。」
「はあい。私は椎野ミチルです。アニイの会社でキャンギャルやったんで知り合って、時々映画みたりご飯ゴチになってます。」
英元子と出井聡子はなんというカマトト喋りか、とあきれた。
「私は出井聡子と申します。テニス部やってて、あとお料理が好きです。ずーっと女子校なんで男の方の考え方に興味あります。」
「私は英元子です。英語のエイと書いてハナブサです。フオークソングが好きでギターやってます。」
「へー。オレ達フオークバンド仲間だったんだよ。」
「ウソー。どんなのやってたんですか?」
「サンフランシスコ・ベイ・ブルース。」
4人が一斉に答えた。
「ナンですか?それ。」
「ぎゃはは。」「オレ達のテーマ・ソングだよ。」「現存する唯一のレパートリー。」
「あのーわたくしは・・・・。」
「どういうバンド編成なんですか?」
「あのーわたくしは・・・・。」
出井聡子が気がついて、英元子に目配せした。出鼻をくじかれたB・Bがすっかり上がっていた。緊張のあまりウルウル状態だ。
「原部玲と申します。バラベなんて読みにくい名前なんで皆様B・Bとお呼びになります。クラブはバスケットをやっております。趣味は読書です。それから・・えーとー・・・。」
「お嬢さん、お嬢さん。」
すかさず合いの手がはいる。こういうときはオヤジは役にたつ。
「はい。」
「オレ等はみんな妻帯者でヘタすりゃあなたくらいの娘がいてもおかしくない。だからそんなに硬くなんなくてもダイジョーブ。こう喋れって誰かに言われたのかい?」
「はい。わたくしの母に今日の会食の話を致しましたところ、」
「チョット待った。コレ一口のんでごらん。」
英語屋がニコリともしないでグラスを差し出すと、自分の日本酒を1/3ほど注いでやった。B・Bは両手でグラスを持って香りを味わっていたが、クッと一息で飲んでしまった。
「あー!おいしー。」
やがてボナールの話になったが、オヤジ軍の絶妙の捌きで、いままでのような大騒ぎにはならずにすんだ。熱くなりそうになると、軽くチャチャが入り、突っ込みをいれ、笑いに持ち込む。正にオヤジ恐るべし!である。こんな具合だ。
「しかし、そもそも男女の前に男同士、女同士で厳密な友情がそこらじゅうにあるもんかね。オレ等は一番ヤバイ悩み事をこいつ等に相談するように見える?」
「恋愛っていうけど僕達の仲間で熱烈恋愛をして彼女の自慢までしてたマヌケはもうバツ2で、この暮れに性懲りもなく3回目の結婚だよ。又呼ばれてんだけど祝辞のネタがない!」
「そんな厳しいことを言われると、オレ達があと50年くらいして、女を見ても何にもときめかなくなってからじゃないと、友達になってもらえないじゃないか。」
「大体君達の倍以上人間をやってるけど、愛だ恋だなんて未だに分らんよ。煮詰まって切羽詰ってもうニッチもサッチも行かなくなった時思わず『結婚してくれ』って言っちゃったんだもんなー。」
「そういやーこの前同窓会に行った時、隣に座った美人に『旧姓はなんですか。』って聞いたら、『昔、愛してるって手紙をもらったヒカワトモコです』とか言われたが、おりゃーそんな手紙を書いたことも忘れててもう面目まるつぶれ、よ。オレのセイシュンを返せ!」
「だけどさ。友情・友情っていってテンパってたら、そのうち男道、すなわち衆道に走ることになりゃせんか?」
そして、オヤジ軍はギャハハと笑いながらのみ続けた。彼等はお互いに名乗った名前では呼び合わず、『イベント屋』『物理屋』『アジア屋』『英語屋』と語りかけるので、結局本名は最後まで分らなかった。
しばらくたって、椎野ミチルは、B・Bに呼び止められた。みると、見違えるようにキレイになって、キチンと髪をウエーブさせている。
「ごきげんよう。ねえ、ミチル。」
「ごきげんよう。玲、どうしたの?」
「聞いて欲しいの。アタシあのおじさん達に又会いたいの。」
「はあー?どうしたの、急にしおらしくなって。」
「あたし、あの人達の言ってることが良くわからないの。」
「そんなこと心配することないよ。アニイたちは嘘ばかり話してんのよ。」
「違うの!この前分ったの。あたしが一番バカだって。」
「頭が悪いとは思わないけど、まあ、時々変にはなってる。」
「皆がB・Bっていうのは、バカでブスっていう意味なのよ。」
「はあー?・・・・。」
「ねえ聡子。」
「アラごきげんよう、ミチル。あたしも話あるの。」
「それがさ、B・Bが変なの。まあ元から普通じゃないんだけど。何か壊れてきてるみたい。いきなり又アニイ達に会いたい、だって。」
「アラ、あたしもお願いしようと思ってたのよ。」
「エッ!・・・・」
「結局この秋3回合コンやったけど、一番気楽だったじゃない。」
「気楽と言えば、それはそうだけど。」
「ミチルだって後でスッタモンダしなかったじゃない?」
「それはそうだけど・・・・。」
「今度はあたし振袖にしようかな。お正月以外に着たことないから。フフフ。」
「・・・・・あの、・・・・。」
「元子、元子、チョッ、ちょっと来て。」
「なあに。」
「アナタは正常よね?」
「何言ってんの?当たり前じゃん。」
「もう元子だけが頼りよ。ねえ、聡子と同じクラスにいて何か変だと思わない?」
「別に、変じゃない。」
「そうお?お願いだから元子だけは普通でいてよ。」
「何よ。ミチルこそどうしたのよ。何焦ってるの?」
「だから、変なのよ。B・Bは壊れかけているし、聡子は変だし。あのオッサン・コンパ又やりたいって言い出したのよ。」
「っていうかー、B・Bは元々少し変わってるしー、聡子だって、ねえ。そういえばB・Bキレイになった気がする。普段だらしなさすぎるからだろうけど、少しかまってるよね。だけど面白いじゃん。あたしサンフランシスコ・ベイ・ブルースって曲調べたのよ。」
「・・・・。」
「オリジナルはアメリカの古いフオーク・バンドで、それを日本の武蔵野何とかっていうマイナーなバンドがリメイクしてるのよ。」
「・・・・・一体どうなっちゃうのかしら。・・・・。」
「何が?」
かくして、椎野ミチルの絶望感にも関わらず、2回目がセットされた。おりしも巷にジングル・ベルが奏でられるクリスマス・シーズンになっていた。場所は例の『物理屋』が別荘を持っているという富士山麓でのパーテイーと決まった。午前中から始めて、日没とともに帰京する、という趣向なのだそうだ。
4人は冬休みである。25日当日、駅に集合した時、椎野ミチルは度胸を決めざるを得なかった。出井聡子は本当に振袖だった。B・Bはどうせ『お母さん』がろくでもないアドバイスの上に、これ貸してあげる、とでもなったのか、ショッキング・ピンクの洋装に毛皮のコートを羽織っている。英元子はジーンズの上下で、ギター・ケースを持っている。これで中央本線の特急4人掛けに座っているところは、まるでコミック・トリオ漫才とマネージャーだと思った。
とはいえ、楽しくお喋りしながら、駅について、駅からすぐというその別荘を探した。その住所は鎮守の森の様な佇まいで、近くまで行くと人の声が聞こえた。男の声ではない。何やらはしゃいだ声がキャアキャア言っているのだ。4人は顔を見合わせた。意を決した椎野ミチルがドアをノックすると中から「ハーイ。」と声がして中からバアサンが顔を出した。
「アーラー、お嬢ちゃん達、もう見えたの。さあさあ。」
と中に招かれた。中には大年増がいて、後片付けをしていた。呆気にとられた4人にお茶が出され、お菓子が出され、バアサマたちはその間騒ぎちらしながら、片付けをすると「オニーチャン達は、今近所に黒湯に漬かっていて、すぐ帰るから。」と言って帰ってしまった。
「チョット何あれ。」
「分んないよ。でも夕べからいるみたいね。」
と話しているうち、オッサン達が帰ってきた。手に洗面器を持ち、タオルを持っていたが、恰好が予想を上回っている、と言うより下回っていた。『イベント屋』はまあ前回のような業界風、『アジア屋』は会社帰りに来たのか、それにしても工事用の作業服のようなものを着ている。英語屋は無粋なスーツにネクタイ。物理屋はライダー・フアッションのような皮の上下。この人達に比べれば、トリオ・漫才+マネジャーの方がまだマシかも知れない。
「よお、もう来たのか。早いじゃないか。」
「ごきげんよう、アニイ。ところで何よ、あのオバーチャン達。」
「お前等のおかげでミョーなもんが流行ってんだよ。まあ始めよう。」
要するに『男と女の友情論』の応用編なのだそうだ。実態はたかだか合コンのことらしいが、条件として酒が好きでないと困る、ヒマでないと困る、ワイ談が好きでないと失言した時に立つ瀬が無い、といった下らない条件が追加されたため、物理屋がこの別荘近くの知り合いのバーサマに声をかけたら、すぐに集まったらしい。
一応はクリスマス・パーテイーである。プレゼントなぞ準備したりして、シャンパンが抜かれ、かの女達も多少嗜み、オッサン達は自分達の酒を別々に飲み出し、ケーキなども用意された。
「それでアニイ。合コンはどうだったの?」
「オウッ、それが大盛り上がりでな。アジア屋は潰れるし大変だったよ。」
「しっかしバーサンってのも元気だよなー。」
「ありゃもうストレスがないんだよ。」
「歌も出ちゃったよな、あれは昔の唱歌かね。」
「こっちも歌ったから人のことは言えんよ。」
「何を歌うんですか?」
「(全員で)サンフランシスコ・ベイ・ブルース!ギャハハ。」
「キャー、あたし覚えてきたんですよー。」
話しは弾み、アチコチに飛び、午後には朝帰っていったバーサマ達が暇になったらしく又乱入してきた。そして『男と女の友情』。アジア屋が総括した。
「そもそも、恋愛と友情が両立しないという話しなんだ。どちらがいい、の問題じゃない。実験してみて分かったが、ある意思をもっていれば男女の友情は成立する。但し、そこはある程度の修行が必要で、それによって味のある友情がマナーと信頼の上に成り立つ、ということだろう。そこでだ、君達のような子供は(4人はムッとしたが)まず恋をしてしてしまくってから、ゆっくり男女の友情を楽しめばよろしい。」
「じゃあロクに恋をしなかったら友情も味わえないんですかー。アタシなんか恋とは縁遠いのに。」
「時間にとらわれることなんかナイ!先は長いし君達は自由だ!年なんか関係ない!」
「(酔っ払ったバーサン)そうだよーオジョーちゃん、この人は昨日アタシに惚れたって言ってた。」
「言ってねー!ぜーったい嘘だー。」
おしまい
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。
Categories:サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる オリジナル