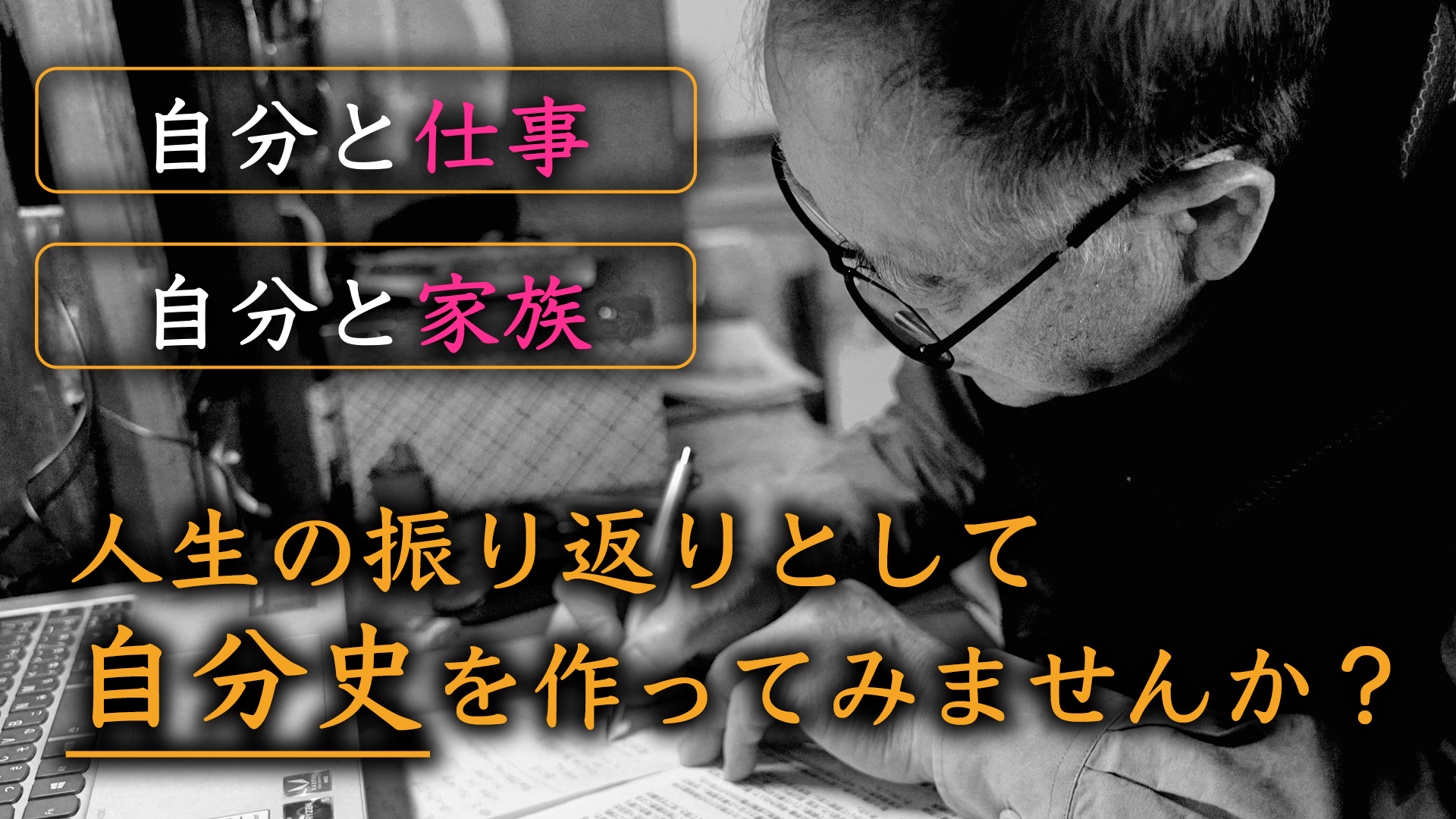藤の人々 (昭和編)
2014 SEP 11 19:19:27 pm by 西 牟呂雄

貴の長男誕生と逸の急死がその前触れとなった。
逸は本当にあっけなく逝ってしまった。大酒飲みで血圧が高く脳溢血だった。この病は当時は倒れてからは早い。遺言も何もない。陽(あきら)が生まれ逸もたまに神田に顔を見せてかわいがっていた。ともあれ貴は三十前に当主になってしまったのだ。当時は旧民法で、貴は順調な家業を一人で相続した。妹節はとうに陸軍将校と家庭を構えていた。
父の死という現実も、こうも唐突だと現実感からは遠い。しかも後世と違い人の死というものが、戦死・病死等日常事であり、従って細々とした葬儀の手続きも事務的に行われるうち、悲しみが引いていく。特に藤家は淡々としていた。
黒紋付きの染抜き技法はいくつかの専売特許に守られほぼ無競争であり、宮内庁にまで納入していた。菊の御紋章は工場総出で水垢離をし、隅々を塩で清めてから全員白装束を付けての仕事であった。無論黒染めであるから一回で汚れてしまい使い捨てだから、大した儲けにはならなかったが貴はお構いなしである。
長男陽はどちらかといえば静に面立ちが似ていて、よく笑う子供だった。二年後長女知(とも)が生まれる。このあたりから貴のタガが外れだした。静と子供達を工場のある地に母ひろと住まわせ、自分は神田・京都・工場をまさに神出鬼没といった風に渡り歩き、住所不定状態になっていた。
神田の店には新たに、お気に入りで帳場を任せていた生真面目な沼田を番頭にし「支配人」と呼ばせた。ある日沼田が算盤を入れていると円タクが停まり、中から大きなバッグを担いで貴が裏口から入ってきた。振り返ると目が合った。
「おかえりなさいまし。何ですかその大きな物は。」
「うん。これはな、ごるふ、というスポーツの道具じゃ。」
「ごるふ。何ですかそれは。野球のようなものですか?」
「そんなアメリカ人がやるような野蛮なもんじゃない。歴とした英国貴族のたしなみじゃよ。」
話しぶりまで貫禄をつけているつもりである。当時は東京も新宿を越えれば十分田舎であり、生活圏は山手線の内側だけで足りる。ゴルフなど、ちょっとした遠足気分でいくらでもやれた。ただ、上達はしなかった。
その点山登りは競技ではないので、一人で満足感に浸れる。こちらの方は生涯の趣味となった。貴の周りには取り巻きのような遊び仲間が始終出入りするようになり、「旦那」とか「大将」などとチヤホヤし出す。思いつくままに突然『よし、山に行くぞ。』となるとたちまち装備一式が用意され、全て貴持ちで出発することも頻繁にあった。
昭和初期は色々と事変も起きているが、いわゆる読書階級は平和なもので、悪いことに静の姉たちが嫁いだ先の大庄屋、造酒屋といった輩は誰も働いている者はいない。それぞれ鉄砲撃ちだの弓だの、挙げ句の果てには自分は何もしないでクルーを集めヨットに乗る者までいた。貴の性格からして、人がやっている面白そうなものには手を出さずにはいられなかった。
次男行(ゆくえ)が生まれた。狂喜した貴は高価な帯を買い与える。実は前年に双子を死産させてしまい、その後の精神的落ち込みに手を焼いていたからだ。こういうときの貴はまるで役に立たず、それは悲しいに違いないのだが掛ける言葉もなくオロオロするだけだった。
大陸での事変は手を変え品を変えとさっぱり終わりが見えない。しかしながら藤家周辺では兵役に行く親族もおらず、さしせまって慌てることはなにもなかった。むしろ昭和八年は好景気に沸いた。ヒマを持て余した貴は現地調査と称して満州旅行に出かけてしまう。
陽は学校帰りにブラブラと大通りを歩いていた。小学校では図抜けた秀才だったが、それもそのはずで、東京のど真ん中ならいざ知らずこのあたりでは百姓の子供は勉強することはまずない。中学受験をすること自体が地域ではエリートと言える立場であり、更に農地解放以前ともなれば小作農が大多数を占めていた。秋風が感じられる涼しい午後だった。遠くの方から大通りをこちらにくる大柄な男を見てギョッとした。一目で貴と分るシルエットが支那服を着てよせばいいのに満州国皇帝のような丸い色眼鏡をしながら歩いていた。この前満州旅行に行った時に新京で仕立てさせたと言っていたが、まさか町中を着て歩くとは思わなかった。あわてて横道にそれて家に帰った。すれ違う人は皆下を向いたりして、とにかく顔を合わせないようにしているのだが、貴はニコニコしながらむしろのぞき込むようにゆっくり歩いていた。暫くして貴が帰ってきた。
「おい静さんや。陽、陽、あきらー、ともー、どこにいる。」
大声で家族を呼んだ。陽は話の内容が容易に想像がついて舌打ちしながら階下に降りていった。
「どうだ、町中で誰もワシだと気が付かなかったぞ。」
「あれまあ、そりゃそうでしょうが、まあおよしなすって。」
かろうじて静が取り持った。しかし既に町で噂になっていることを知っていた。陽が耳にしたところでは、『また藤の大旦那のおふざけが始まった』であった。すれ違った人々も下手に気が付いたことがわかれば、大げさに驚いて見せなければならず、バカバカしくて知らん振りを決め込んでいるのだった。
暫く面白がってその恰好で喜んでいたが、さすがに町の人々もすれ違う際には挨拶をするようになってしまったら貴はもう飽きて以後見向きもしなくなった。
ところが、今度は真っ赤なブレザーに乗馬ブーツに身を固め、拍車の音をチャラチャラさせながらウロつきだした。英国紳士の嗜みとでも思ったのか、手には乗馬鞭を持っている。しかしながら本当に乗馬しているのを見た人間は皆無であった。大体そういった奇抜な恰好をするのは地元に限られていて神田や京都では決してしない。周りは自然に飽きがくるまで放っておくしかなかった。
三男泰(やすし)が生まれる。
この頃から風向きは変わった。まず昭和八年が暮れると不景気が襲った。世情騒然とする内に二・二六事件が起きる。
貴は気質としては、はっきり保守派であり大の共産主義嫌いであったが同時に役人も嫌いであり、今日の言い方を持ってすればノンポリもいいところ。事件のときには折しも神田にいたが、わざわざ野次馬根性まるだしで反乱軍を見にも行っている。そして世間に背を向けるように、今度は普請道楽に凝り出した。
まずは材木の手配から始め、渓谷の崖の上の土地を物色し、庭の設計を始めた。場所については、富士の裾野のちょうど冬場の夕日が遠景の谷間に落ちるポイントを見つけて狂喜した。
「門前の小僧習わぬ経を読む。骨董の目利きはいい物を見て磨かれる。」
と称し出入りの大工の腕利きを二人、京都の支店に半年も神社仏閣を見るように居候させた。二度ほど顔を出しては自ら案内するように「このたたずまいをマネできるか」「庭から見上げたときに同じように日が入ることを考えて見ろ」等と言いながら連れ歩いた。
大石を川から運び上げ、家相に凝り、挙げ句の果てには庭からの景観に気に入らない人家があったのでわざわざ大枚をはたいて樹木を植えさせた。相手にしてみれば酔狂にも金まで払って人の家に庭木を植えてくれるのだから有り難い話である。
更に一角に父逸の業績を記した記念碑を建てることを思いつき、デザインからブロンズのマスクに文案まで自作した。そして母ひろの喜寿を記念して喜寿庵と名付けた。
言ってもどうなるものでもなく、静はほったらかしにしていた。工場は五十人程度の人間が居り、面倒見が良かったので工員の相談事に乗ってやったりしていたが、周りの方も大旦那に言ってもロクに取り合ってもらえないので静の方に行くようになっていまい、そのうち帳簿のやり繰りから経営全般は静がやっているような状態になった。
陽は中学生となり、知と行は小学生、よちよちしていた泰を従えて、夏は沼津の海水浴に冬は赤倉のスキーにと一ヶ月以上も逗留する有様で、その間の切り盛りは全て静だ。静は利口に全てをこなした。
一般人にとっては、寝耳に水の十二月八日、後の運命を暗転させることになる対米英蘭戦争が真珠湾攻撃で始まった。負けるなどとは夢にも思っていない国民は初戦の成果に狂喜した。
貴はというと、喜寿庵の仕上げに水をかけられた恰好になりどちらかといえば不機嫌だったがまさかふて腐れる訳にも行かず無聊を持て余した。
ミッドウェーの大負けを知らされない国民は2年程「勝つぞ勝つぞ」のいさましさに酔いしれていたが様子がおかしくなってきた。
工員にも神田の店にも徴兵が来だして統制色が色濃くなる。さすがの貴も慌てるかと思いきや、工場統制が始まり染め物どころでなくなると、これ幸いとお国のために協力とばかりに工場を閉じた。兵隊に教師がとられた女学校の英語と化学の教師まで買って出て、一方で弓に凝り出す。
しかし成績抜群の陽が海軍兵学校を受験する意思を固めると人ごとではなくなった。海軍兵学校は苛烈な教育を持って知られるが、戦局が厳しくなってくると拍車がかかるように厳しさが増す。実態は下級生を殴ってばかりで些か粗製濫造の感が拭えなくなるが、ともあれ陽は合格し呉の江田島に行った。
ガダルカナルは撤退。サイパン陥落。アッツの玉砕で国民にも敗戦という言葉がちらついたが、口に出す者はいなかった。一方の中国戦線では連戦連勝の記事がまだ新聞紙上に踊るのである。
工場(こうば)のある街に学童疎開がやってきた。首都空襲があったからだ。
この頃、東京の山の手で一人の少女は元気一杯だった。
少女の名は聡子。父親は高級サラリーマンで、家系は御維新でやや傾いたが源氏に連なる名家。戦前のサラリーマンは給料も税金も平成の今日とはケタ違いで、団体役員クラスは特権階級化していた。恐い物なしのやりたい放題だ。普通は単なる我儘お嬢さんとなるところが、何でもトップに立ちたがる性格がいい方に出て、勉強でも体操でもガムシャラにやるのだ。名門女学校に合格してみると、周りの同級生も大体似たようなものでお山の大将だらけだ。世間知らずの女の子同士は俄然意地の張り合いが始まり、聡子は猛烈にがんばる。おかげで一方の旗頭になる頃、戦争が始まった。
この一族は官吏、海軍軍人、裁判官、といった一族でいわゆる平和な時代のアッパー・ミドルを構成していた。それぞれ一家を成していたが叔父・伯父達は例外無く酒好きで、法事等の集まり事があると物凄いことになった。全員愉快に酔っ払い、集まった大勢の従兄弟たちは子供同士で遊んでいる。
「聡子、聡兵衛ー!こっちへ来い。幾つになった。」
「十四です。もう女学校ですよ。」
「オォ、もうそんなか。それじゃ酌の一つもせい。」
「はいはい。おひとつどうぞ。」
「うお、なかなかやるじゃないか。わははははは。」
頭を撫でようとしたが酔い過ぎて手元が狂った次の瞬間、聡子は細身の身体ごと床の間まで吹っ飛んだ。子供達は息を飲んだが、大人は余興とばかり笑う。聡子はこの時のことを後に思い出しては『首がもげるかと思った。』と語る。当の伯父は講道館柔道三段の猛者だった。
兄が海軍兵学校に進んだ頃から戦況はおかしくなってくるが、聡子は逆に闘志を燃やしていた。アメリカ何するものぞ、負けるものか、と。同級生にも同調者が多くエスカレートする。ある日身内を亡くした一人さめざめと泣きだした。
「やさしいお兄様が戦死なさったの・・・。」
悲しみは伝播しその後高揚する。と、一人の優等生がスックと立ち上り。
「いいこと!うちのお兄様は海兵を恩賜で卒業なのに(上位5番以内のこと)戦死されたのよ。そんなに泣くもんじゃありません。」
今では大問題と言うべき発言だが、聡子はもっともだと思った。他の同級生も「さすがね。」という反応だった。
つづく
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:藤の人