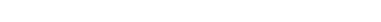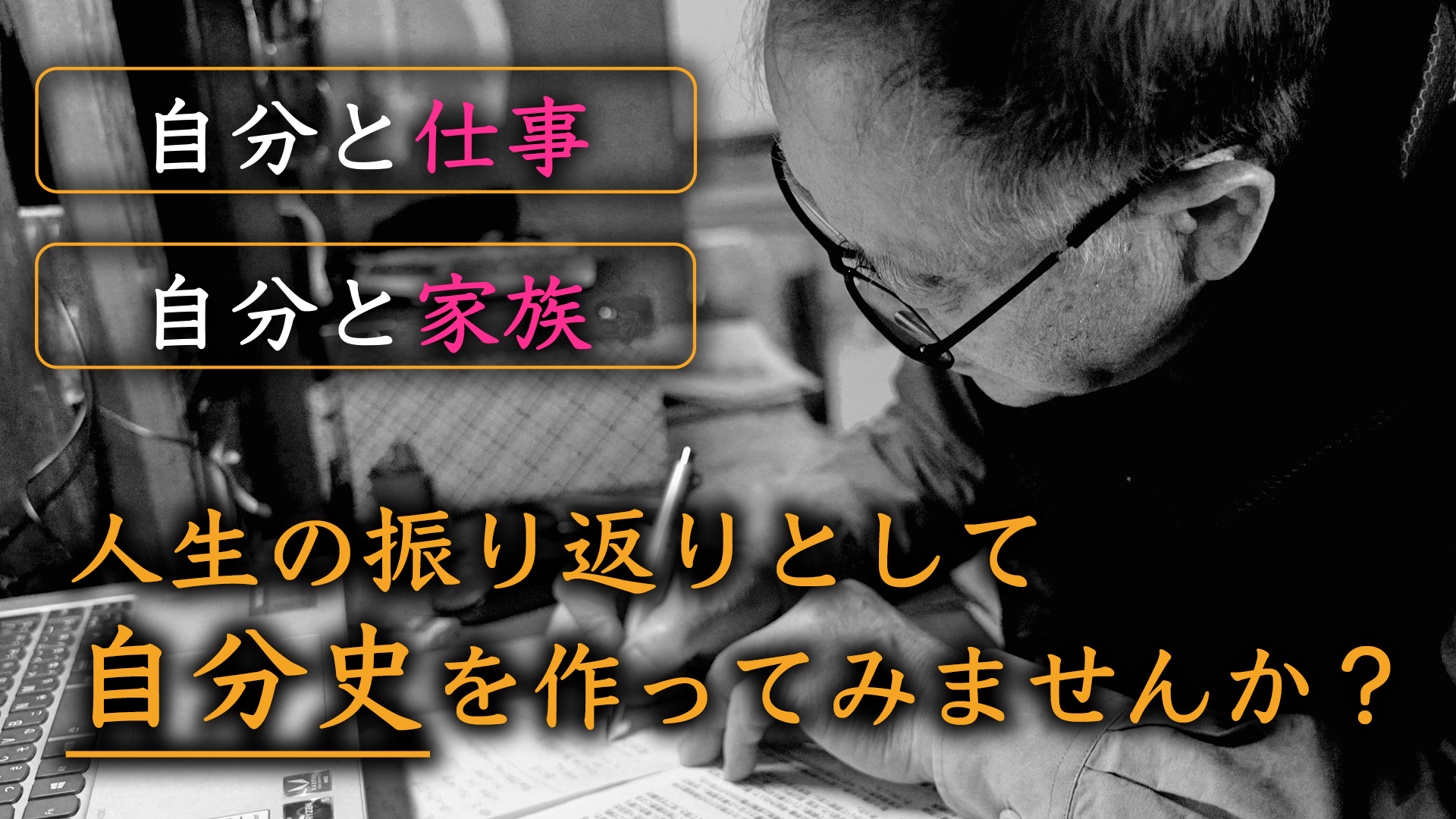犬山城見聞記
2016 JUN 20 5:05:51 am by 西 牟呂雄

先日、チャンスがあったので国宝犬山城を見物に行ってきました。
木曽川沿いにそびえる威容は別名白帝城と呼ばれ、これは荻生徂徠の命名です。由来は、三国志の劉備が呉に敗れて、逃れて没した白帝城から名付けたようです。現在の姿になったのは尾張藩の家老が入城してからです。そして城主成瀬氏が居城とし、驚いた事に明治期をやり過ごして2004年までその成瀬家の個人所有の城でした。さすがに今では維持・管理のため財団法人の所有となっています。
この城は元々織田家の支流の砦だったのですが、小牧長久手の戦いの時に歴史の表舞台に立ちます。本能寺の変の後、城主が変わります。そして豊臣・徳川の対立が鮮明になった頃、かつての犬山城主・池田恒興が突如奇襲をかけ当時の織田信雄方から奪い返すのです。すなわち豊臣側に付く。それに対して家康は小牧山に陣を張り、双方にらみ合いになってしまいます。
その後、豊臣秀次の軍が家康の地元三河に攻撃をかけようとして南尾張の長久手のあたりで激戦が起きますが、戦闘では家康の勝ち。家康は電光石火の読みで長久手の戦場に現れ池田・森の両将を討ち取ってしまう。
しかしながらも双方決め手を欠いている内に半年あまり。二手に分かれた戦乱は関東・加賀・伊勢・四国とあちこちで始まりながらもとうとう大会戦で決着をつけるには至りませんでした。
すなわち、扱いは小さいが後の関が原・大阪の陣に至る萌芽とも言うべきものが小牧長久手の戦いと言えないでしょうか。
そう思って天守閣に登ると、案内板がついていて遥かというよりもすぐ手の届くような感じで小牧山が丘のように見えます。無論当時にこういった城郭はないのですが、恐らくこれくらいの目線で対峙した秀吉は家康の陣を見て何を思ったでしょう。
『ワシは犬のように御屋形様に御仕えしてここまでになった。それどころか猿だの禿鼠とまで言われて。それに比べてあやつは御屋形様と固い絆で結ばれた同志のように振舞っておった。ここまで来て今更上前を撥ねられて堪るものか。』
と闘志を燃やしたのかもしれません。
二人の名将が対峙した訳ですが、濃尾平野はペタンとしていて一鞭を奮って突撃すればさぞ大会戦になったのでは。なにしろ秀吉は十万人を大阪から率いて来ていたのですから。
しかし両者は小競り合いをするばかりで激突には至りません。夜襲も行われなかったようです。どうにも解せないのですが、家康はもっと長期的見地に立っていたのかも知れません。小牧城の防御もガッチリかためています。
この時点では豊臣・徳川の色分けは鮮明ではなく、他地方の状況も不安定。そして関東もまだ小田原に北条が健在でした。急ごしらえの秀吉包囲網ではいかにも心もとない、ここは一つ貸をつくる意味でも講和に持ち込むのが得策、と思案したのでしょう。
今激突するには時期尚早。秀吉の力は今が盛りで月は満ちればいずれは欠ける、こう判断したならば大局観としては正しく、唸らざるを得ません。
一旦は和睦はしたものの、その後二年ほどは本格的な講和には至らなかったのです。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:旅に出る