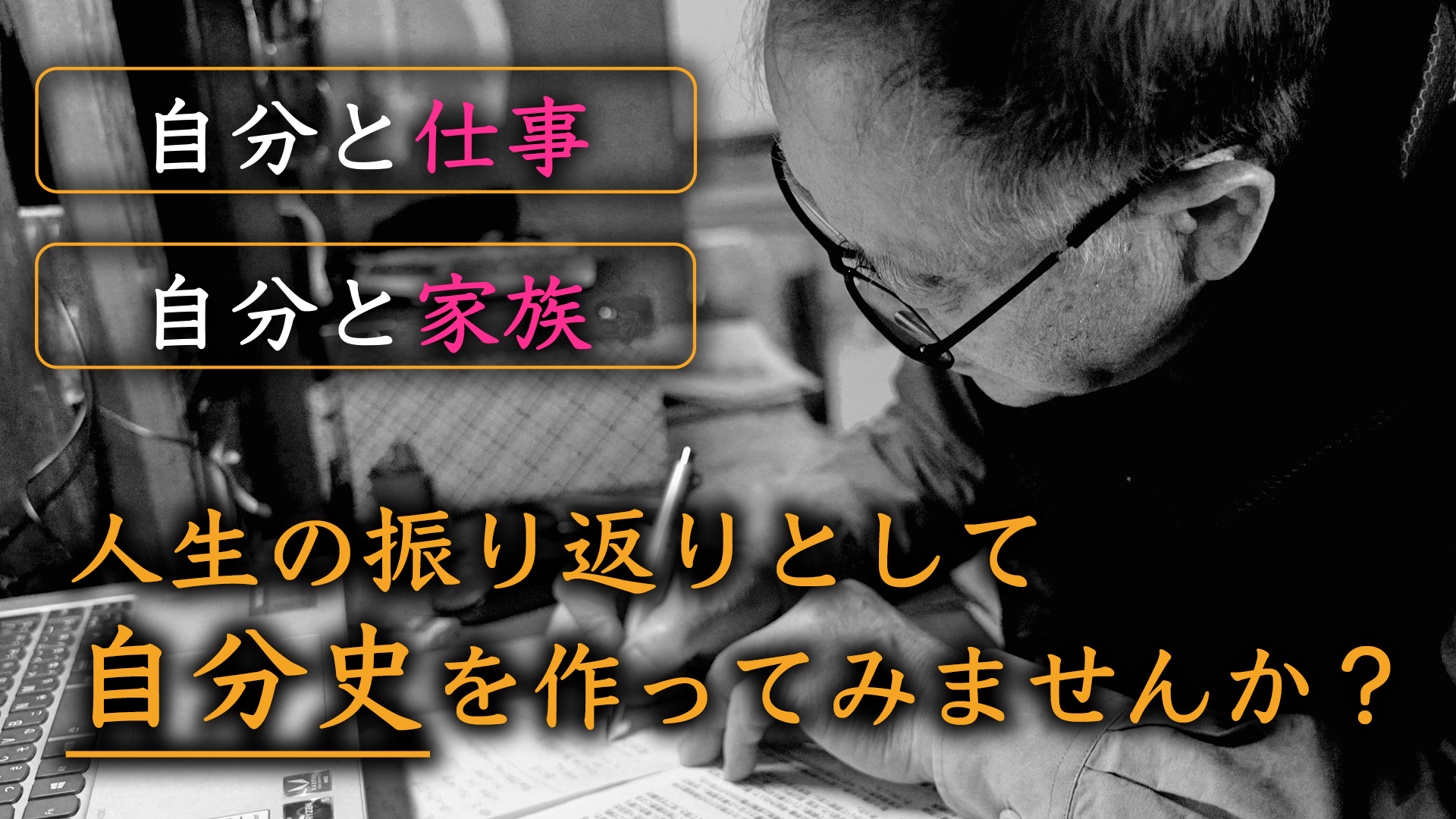喜寿庵紳士録 ピッコロ君
2017 JUN 11 11:11:01 am by 西 牟呂雄

ある日の昼下がり、門の前の道を掃いていたら『やあやあやあ』と声が掛かったので顔を上げるとあのヒョッコリ先生が子供を連れて歩いて来た。
「どうだい。ジャガイモくらいは蒔いたのかい」
「ええ。ピーマンとナスも苗からやってます。その子はお孫さんですか」
「いや、孫じゃないんだけどチョット面倒見ているんだ」
「ボクはお名前は何ていうの」
すると学童前くらいのその男の子は先生の後ろに隠れてしまった。恥ずかしいのか恐いのか。
上目遣いになったその子は小さい声で言った。
「ピッコロ」
「ピッコロ君なの!」
「ハッハッハ。自分で『ピッコロ』って言ってるんだよ」
「へぇー、自分で考えたのか。すごいねピッコロ君」
「あっ調度いいや。僕少し用事があるんでこの子と遊んでてくれないか」
「・・・いいですけどどれくらいですか」
「いやほんの30分くらいだよ。すぐ帰ってくるから頼むよ」
「は・・・・い」
先生はそのままスタスタ行ってしまった。ピッコロ君は不安そうに見送っていた。
「じゃあピッコロ君、お庭に行って見ようか。おいで。お花が一杯咲いてるよ」
しょうがなくて二人で門をくぐって庭に廻った。
芝生を張った前庭に連れて行って『ほーら、これはつつじの花だよ』と教えてやると、いきなり花びらを掴んでちぎってしまい慌てた。
「コラコラ!そうやって取ってしまったらお花が死んじゃうじゃないか。ダメ」
ピッコロ君はムッとした顔になってトコトコ走って行く。
「オイオイ!そっちは崖になって落ちたら大怪我するよ」
今度は鬼ごっこのつもりか『きゃー』などと言ってはしゃいで芝生に転がって見せた。どうも躾けのなってないチビだな。そして腹ばいになってジーッと地面を見ている。丁度いいやとほったらかしておいた。
ところがそれっきり動かない。どうかしたのかと行ってみると、小さい芋虫をたくさんの蟻が運んでいるのを見つめているのだった。そういえば僕も子供の頃に蟻の行列をずっと見ていた記憶がある。
そこで割り箸をたくさん持って来て
「ピッコロ君、オジサンが時間を計ってあげるからこのお箸を蟻さんがいる辺りにこんな風に立ててごらん。するとどういう風にどのくらい運んだか分かりやすいだろう」
と地面に刺してみせた。俄然ピッコロ君の目が輝いている。
それから僕は本を読みながら(ついでにビールも飲んで)10分おきに『はい10分経ったから刺して』と声をかけた。
しかし1時間近くなってもヒョコリ先生が帰ってこない。ピッコロ君が地面に刺している割り箸が5本になった。驚いたことに蟻はこの時点で数メートルも移動しているではないか。一方ピッコロ君の集中力も凄い。冷たいお茶をコップに入れてあげるときに『ずうっとおんなじ蟻さんが運んでるのかい』と聞いても頷きもしない。
と、そこにやっとヒョッコリ先生がきた。
「やあやあやあやあ、お待たせ。チョット込み入っちゃってね。さあ、帰ろう」
するとピッコロ君は困ったような悲しそうな顔になって首を振っている。帰りたくないのか。ここで遊んでいても構わないが、そもそも僕はヒョッコリ先生の家さえわからない。
「この割り箸は残しておいてあげるからまた遊びにおいで。続きはおじさんがやっといてあげる」
と促した。ピッコロ君は名残惜しそうに帰って行った。

ゴルフをやって帰ってくると門の前に小さい子が二人で覗いている。ピッコロ君だ!
「ピッコロ君、どうしたの?おじさんを待ってたの」
ピッコロ君はニコニコしていた。一緒にいるのは同い年くらいの女の子だ。
しまった、『おじさんがやっといてあげる』をコロッと忘れていた!
しょうがない。庭に入れてあげると二人は昨日ピッコロ君が立てた割り箸の列を見に走って行った。子供に向かってはこういう時に嘘をついてはいけない、すぐに見抜くからだ。
「おじさん、きのうピッコロ君が帰った後にビール飲み過ぎて蟻さんの行き先が分かんなくなっちゃったんだよ。ゴメンネ」
ピッコロ君は眉をひそめて割り箸の列の先をジーッと見ている。いたたまれない気分だ。
「お嬢ちゃんはお名前は何ていうの」
「マリリン」
「へー、マリリンっていうんだ」
と、ピッコロ君は僕がほったらかしにした蟻がどこまでいったかを割り箸の列の先まで探そうと地面を見続けた。マリリンちゃんも何にも分からず一緒に見ている。参ったな。どこに行ったか確かめようと奥に行ってしまいそうなので慌てて声を掛けた。
「そうだ。チョコレートあげる。一緒に食べよう」
僕はウィスキー・ロックのつまみに板チョコをかじるのでいつも切らしていない。二人に声を掛けたがキョトンとしている。さあ、おいで、とベランダから家に入ってチョコレートを冷蔵庫から出して来ると不安そうな顔で覗き込んでいた。
「上がっておいで」
と手招きすると、驚いたことに靴のまま入ろうとしたので『あーダメダメ、靴脱いで』と止めた。この子達は一体どういう暮らしをしてるのだ、畳だぞオイ。何考えてんだ、僕の方から外に出てチョコレートを剥いてあげた。
ハッとしたが、この子達は自分の名前(本当かどうか分からないが)以外一言も喋らない。どういうことだろう。可愛らしいのだが、ひょっとするとこの子達は日本語が分からないんじゃないのか。
この前も変態がかわいらしいヴェトナム人の女の子を殺したし、世間の目はオッサンと少年少女の組み合わせに厳しい。しかもああいう事件は何故か田舎でも起きる。ましてや保護者(と思しき)ヒョッコリ先生もいない。だいたいあのオッサンだって何者なのか知らないし、どうしたものか。
そうすると、子供には相手の動揺が直ぐ分かるのか。二人はコッチを見上げてソワソワしだした。そして手を繋いで小走りに出て行こうとするのだ。僕は慌てた。
「おーい、待って」
こういうチビは以外と早い。もう門まで行ってしまってる。必死で声を掛けた。
「又、おいで。友達になろう」
門を出た時にはもう見失っていた。しかし僕はチビちゃん二人の行方よりも大声を上げた自分にビックリしていた。そういえばここにいる限り友達はできない。地元の大学生と付き合いはあるが彼らは彼らの世界があって”友達”にはなれない。せっかくの仲良しを作るチャンスを潰してしまった。
「やあやあやあやあ」
「ウワッ」
ヒョッコリ先生だった。
「なんか”友達がどうした”とか叫んでいたようだが」
「いや、何でもありません。ピッコロ君とマリリンちゃんが遊びに来てたんです」
「誰だい。その変な名前」
「いやっ・・・・この間つれていた子供さんが・・・・」
「ピッコロとマリリンって僕が飼ってる犬の名前だぜ」
先生は笑いながらスタスタ歩いて行ってしまった。
あまりの事に一瞬気が遠くなった。僕は幻視したのだろうか。いや待てよ、もっと聞きたいことがあったのだが飲み込んだ、『あなたはこの世の人なのですか』の質問を。
ヨロヨロと庭に戻れば割り箸はちゃんと立っているではないか。僕は二人と遊んで友達になったのだ。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:藤の人