戦争の終わり方 Ⅱ
2022 JUL 16 22:22:00 pm by 西 牟呂雄

中国史の専門家によれば、今日の習近平が言う漢民族があの広大な大陸を統治した王朝と言うのは、民族の名前になった『漢』『明』『宋』だけで、唐でも元でも清でも北方の遊牧民がガーッと首都を蹂躙して打ち立てたものだとか。
中東でもヨーロッパでも、古代の侵略というものは相手の男を皆殺しにするのがその終結で、民族淘汰的な側面のある残酷なものだった。それが国境という概念が確立するにしたがって、首都制圧・敵王族の殺害・国家体制の変更、といった手順を踏むようになってきた。
近現代の我が国が被った敗戦という事態は、まさにこのパターンで、天皇制が残ったのは奇跡的なことだと言える。それだけ当時の日本人が毅然と『国体護持』を訴え、国民の中に敬う心が根付いていた証とも評価できる。
今回のロシアによるウクライナ侵攻もまた、この手を狙っていたに違いない。当初のキーウ直撃の心理的な効果は大きかったものの、失敗している。実は我が国の敗戦以後、この必勝パターンは大国間では成り立たないのだ。
筆者はその解を核だと考えている。すなわち保有5大国同士は互いに打ち合えば両国民とも全滅することになる。小国は言うに及ばず、G7からG20も含め、いずれかの保有国との同盟もしくは安全保障による共同防衛関係にあるため、20世紀型の(それも日本・ドイツの敗戦が最後の)国家間決戦はありえないはずだった。
ロシアはそこをわきまえず、或いはスキを突いたつもりで侵攻して失敗。その結果核をちらつかせてまで威嚇しているが、そうはさせないと反対勢力の結束がかえって強くなってしまっている。
この事態に、国連など何の役にも立たない、との声が上がる。常任理事国すなわち核保有公認国家5か国という大国の一角が小国に理不尽にも侵略をしたことに打つ手が無いので無用論が取りざたされている訳だ。筆者は国連について、大戦後の平和構築に貢献していると一定の評価をしており、それでは無くせとはならない立ち位置にいる。そもそも国連憲章並びに国際法(慣習法)で他国への侵略を禁止し、それに違反した場合は➀勧告し➁経済制裁をかけ➂武力制裁を取るのがオブリゲーションという、集団安全保障措置になっている。
現在はその集団安全保障措置の➁の段階にいることになるが、国際社会の狡猾さはその建前をとっくに乗り越えて様々な詭弁を弄して止まない。アメリカはゴリ押しするときは多国籍軍・有志連合軍の体裁を取り、ロシアは今回の侵攻を特殊作戦と言い換え戦争ではないと言い張っている.そのせいで契約条項のフォース・マジュールによる損失請求ができない。
更にその『建前』のハードルは続きがあり、この国連集団安全保障措置が取られない場合に限って個別的自衛の権利行使が認められる。それも国家の自衛権は国際法の定めに従い、必要性・均衡性・即時性の原則を満たさなければならない。即ち、敵の侵害手段に釣り合った手段での反撃ということで、1個師団には1個師団を、核には核を・・・。
これらの運用を定めた先人達の平和への思いが滲み出ているが、一体誰がそのことを瞬時に判断し対応できるというのか。本件に関してのもう一歩の踏み込みはもはや筆者の理解を超えてしまうので、プロの見解が欲しい。
もう一つ。ロシアに勝たせるわけにはいかない、とアメリカ中心に西側が結束して対峙している構図になっているが、ロシアが孤立しているわけでは決してない。はっきりと非難し制裁を科したのはG7とオーストラリア・ニュージーランド・韓国ぐらいの話で、インド・中国を含むユーラシアの大半と中近東のイスラム圏、アフリカといった国々は非難にも加わらなければ制裁もしていない。インド・中国といった2大人口大国を含んでいるために、総人口という荒っぽい見方をすればロシア陣営の方が多いかもしれない。
フランスの歴史人口学の泰斗であるエマニュエル・トッドの分析で明らかになったが、これらの地域は父権性が強い外婚制共同体家族 (息子はすべて親元に残り、親は子に対し権威的であり、兄弟は平等)システムの国々である。かつての共産主義国家、中東においてはイスラム過激派を内包する土壌があるということになる。
そしてトッドの考察は、今回の戦争は2014年以前からアメリカのウクライナへのしつこい介入でクリミア問題を引き起こし、頼まれもしないのに米・英そろってウクライナ軍を鍛えて煽り続けた結果ではないかと(断定はしないものの)示唆している。トッドの仮説に従えば、家族形態の最も原始的なものはアングロ=サクソンの完全核家族システムであり、歴史的には次第に父権的なシステムに発展した。その両システムの激突とも言えなくはなく、将に第三次世界大戦の入り口いるという見立ても成り立ち得る。多少解説すると、トッド理論によれば前大戦は核家族システムVS直系家族システムという構図となる。
しかるにこの戦争で得をするのは誰か、と推理小説的に俯瞰すればアメリカと言わざるを得ない。ブッシュ時代は共和党をカヴァーにつかっていたネオ・コンは今や民主党に鞍替えし、当面の主敵である中国に戦争を仕掛ける訳にもいかないからロシアを引きずり込み疲弊させ、中国に面倒を見させて長期戦に持ち込む。及び腰だった独・仏のケツを叩いて緊張感を煽る。NATOを拡大してロシアの緊張感をヨーロッパに向けさせる。コロナ禍により中国を基軸としたサプライチェーンが寸断されたのを立て直す。いいことづくめではないか。するとウクライナで戦っている人々に申し訳ないが、アメリカとしてはロシアでの厭戦気分が蔓延するまでズーッと戦いが続くことが望ましいということになり、外交的な解決は当面ないのだ。
実は、あまり表にでていない話だがあのドンバス・エリアは2014年のドンパチが始まってから当初のウクライナ軍の動きがかなり荒っぽく、その後配置されたアゾフ大隊(あの製鉄所に立てこもった部隊)はもっとひどかったため、地元住民からは蛇蝎のごとく嫌われていた。クリミアに関してはそもそもウクライナ人など殆どいない地域で、ロシアからウクライナに帰属を変えたいとはサラサラ思っていない。元々は強制的に移住させられてしまったがタタール人の地域だった。
するとどちらが力押しで占領してもつらつら述べてきた国連中心の国際秩序が保たれることはなく、シリア化パレスチナ化したテロの温床になる可能性すらある。
そして我が国はどうか。近隣の問題として台湾があり、ウクライナの手詰まり感からバイデンは珍しくはっきりと介入を口にした。対岸の火事どころではない。この問題に早くから警鐘を鳴らしてきた安倍元総理は凶弾に倒れた。筆者としては一瀉千里に世論が傾くことは良しとはしないが、憲法改正・防衛費増額は国際秩序の維持のためにも必要だと考える所以である。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:潮目が変わった


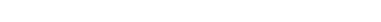
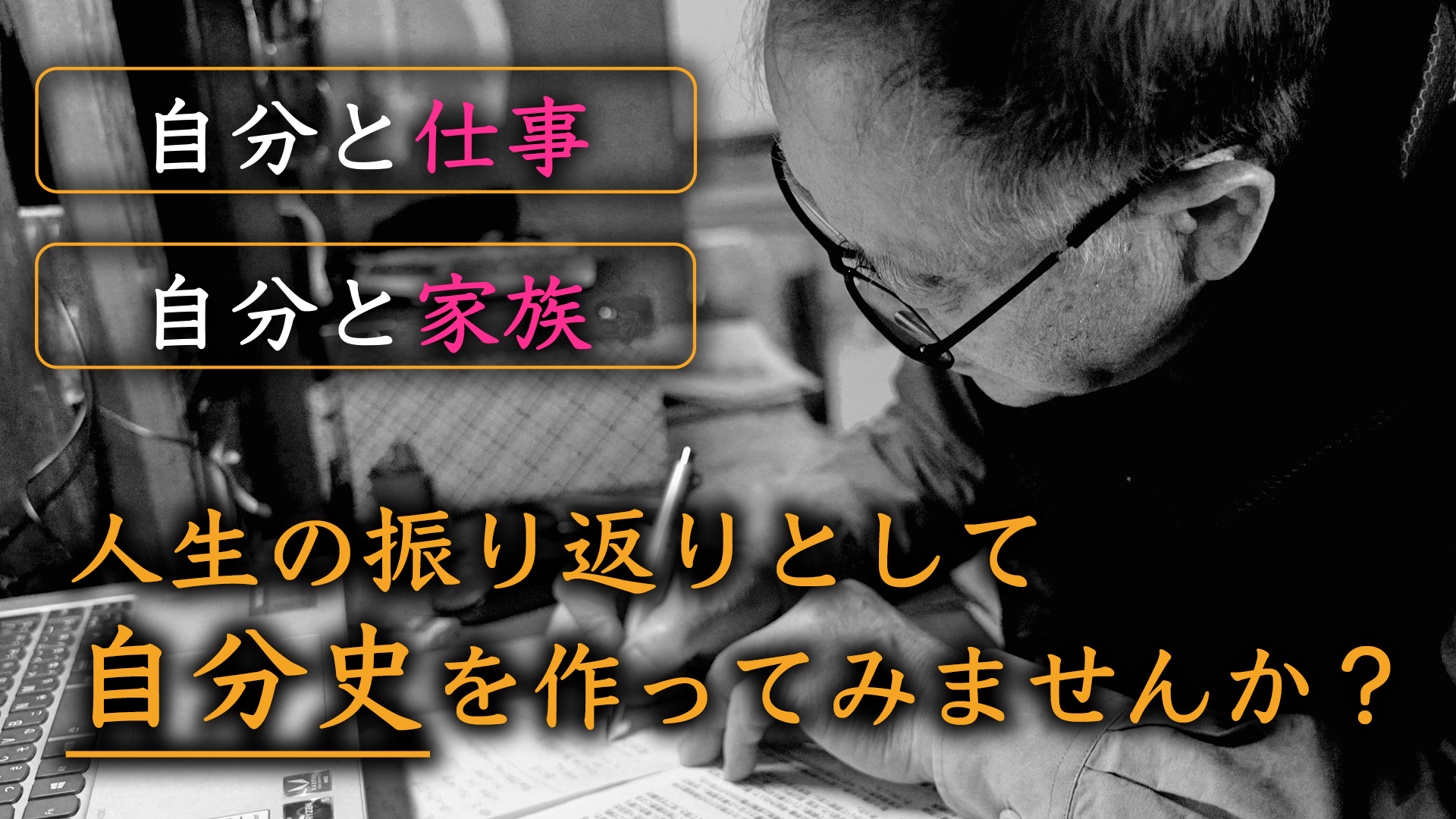


S.T.
7/18/2022 | Permalink
政治経済的な実際の力学についてはわたしはほとんど知らないのですが、キリスト教と人間の法の繋がりについてはざっくり調べました。
カントの「永遠平和のために」にはすでに国連の構想があると読めます。長いこと時間の流れ=普遍史として捉えられていたものの、自然法を含むあらゆる価値観が更新されていった道程で一番大きな変化は「人類が罪を負っている(=救いが必要である)」という見方が回避された点だとおもいます。
「ただし感性界での働きへの神の寄与とか、協力(コンクルスス)という概念を考える学派もあるが、これは捨てなければならない。というのは、これは異なる類のものを組み合わせようとすること、一つの生き物では足りないと考えて他の生き物をかけあわせようとすることであり、みずから世界の変化の完全な原因である神が、世界過程を通じて、予め定められたみずからの摂理を実現するために、別に補足を必要とすると考えることだからだ」
ST
7/18/2022 | Permalink
アングロサクソン同盟については、チャーチルとルーズヴェルトの fraternal association に目をつけています。チャーチルは、この友愛大作戦によって以外に世界の結束はありえないと当時述べています。国連はその前身は主に英国資本、現在のものは米国資本に依ると読みました。国連広場には Isaiah Wall がありますから、わたしがここでお見舞いする言葉はこれになります。
And no wonder, for Satan himself keeps disguising himself as an angel of light. It is therefore nothing extraordinary if his ministers also keep disguising themselves as ministers of righteousness. But their end will be according to their works.
わたしはこれで、チャーチル家と “ルツの息子たち”、PNAC、宇宙軍まで(STAR WARS も!)多少わかったつもりになっていますが果たして。“支配者のムスコ” を “平和の使者” がどうするのかは、桟敷で見ることにします。
西 牟呂雄
7/19/2022 | Permalink
うーん、イザヤ書にルツ記ですか・・・。
チャーチルは超名門貴族マルボロ公爵家の出身ですが、母親がアメリカ人のせいか爵位は継がずに平民でしたね。
娘の一人は確か自殺じゃなかったかな。
ST
7/20/2022 | Permalink
チャーチルの母ジャネットの父はユグノー系投機家、当時のアメリカでかなりの影響力があった人とおもいます。
天に達する塔を建てようとした「神に敵対する狩人ニムロデ」の都市は「混乱」させられました。ヒューマンライツを天より高く打ち立てようとすることは混乱を招くはずです。現にアメリカの分断がそれですが。しかしわたしのおしゃべりが過ぎるとこの場の品位を損ないますので撤退! 西さんは危うき人にも近づいてくださる君子で、良いかたです。
西 牟呂雄
7/20/2022 | Permalink
なんのなんの、撤退には及びません。
ところでニムロデ、ノアの曾孫。ニムロッドあるいはニムロド、西牟呂雄・・・きゃー!
ST
7/29/2022 | Permalink
ニシムロッド様に謹んで申し上げますが、
ロべスピエール氏が像にして拝んだルソーその人は、結果的にFraternitéを(王権やキリスト教の事実上の腐敗に抗って)再興させたとされているようですが、彼個人はごく繊細で傷つきやすく、そして美しい文章をいくつか残しているのをご存知ですか? わたしはこの一文のために仏語を学びたいと感じたくらいです(彼は詩人でもないのに!)。
「静観する者がいっそう感じやすい魂をもっていれば、その人はいっそう深くこの諧調からわきあがってくる恍惚感に浸る。快く深い夢想がそのときかれの官能をとらえ、かれは甘美な陶酔を感じて、その広大な美しい体系のなかに消え失せ、それに同化した自分を感じる。そのとき個別的な対象はすべてかれの視界を去って、かれはすべてを全体のうちにおいてのみ見、また感じる。なにか特殊な状況が観念をひきしめ、想像力に限界をあたえるとき、はじめてかれは包容しようとしていたその宇宙を部分的に観察することができる」
西 牟呂雄
7/30/2022 | Permalink
おっ、『第七の散歩』ですな、手強い。
このころのルソーは精神分裂病、今でいう統合失調症に悩まされていて、妄想・強迫観念に苛まれていたかと。
波が引いた後に紡ぐ言葉の何と見事なことでしょう。
原語で韻が踏んであれば立派な詩になります。
ST
7/30/2022 | Permalink
ご存じでしたか (^^) これ経験ある人はわかるとおもうのですが、ゴッホもきっとこうだったろうと感じます(知覚の淵です)。このかた拝んでも仕方ないですね? ほかの誰にも。わたしとても可笑しなこと言ってるとおもいますが…。
夜歩いていると、そっちに行くと踏みつけられるよ、というほうに、蝉の子が歩いていきます。ひっくり返ってもがいているのも。まるで人間みたいです。こんな現状を受け容れる必要があるのはわたしの感覚的には矛盾しています……うーん、何の話をしているのでしょう??
ST
8/2/2022 | Permalink
舌足らずでした。文庫にルソーの持病は書かれていませんでしたが、当時メンタルが壊れ気味であったのは事実とおもいます。
わたし自身は幼児期、未成熟な脳の機能に発達の凸凹が目立ったようで、色々な体験をしていますので、芸術家たちの言葉にピンとくるものが多いです。そうしたものが残っているのと、消えてしまったのと、どちらがいいかと聞かれれば、ふつうの生活のできる今のほうがよいと答えます。