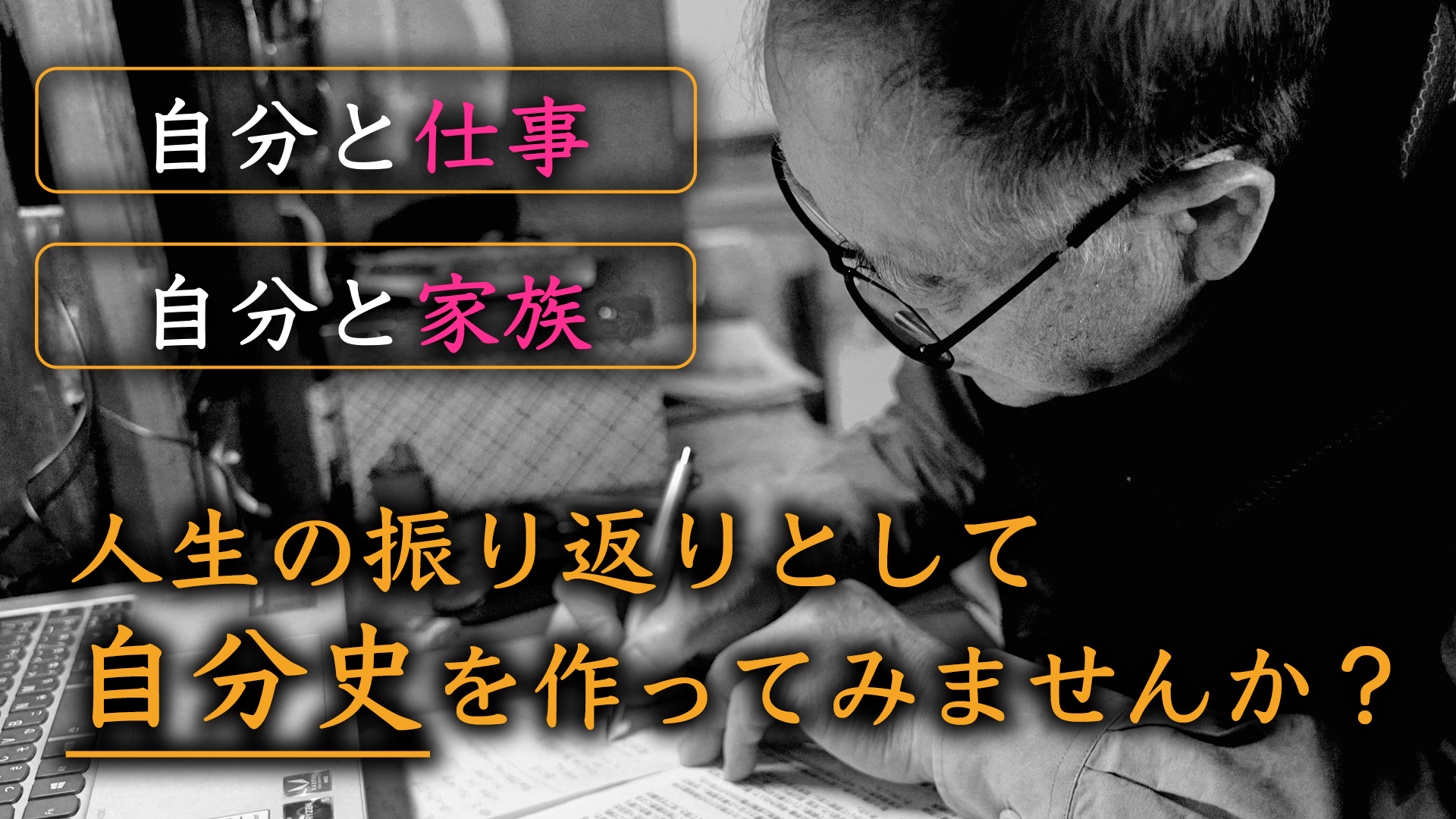小幡篤次郎と語学
2022 SEP 17 20:20:15 pm by 西 牟呂雄

提題の小幡篤次郎に関しては、慶應義塾関係者以外にはあまり知られていないのではないだろうか。福沢と同じ中津藩の出身で年齢は7~8才年下。小幡家は福沢よりも高い家老格の上士であり、幼い頃から四書五経を納め藩校・進脩館(しんしゅうかん) で教頭にまでなった。
その後22才で福沢の強い勧めにより上京し、福沢の英学塾で学ぶと、瞬く間にこれを習熟しここでも塾頭となるなど、とにかく抜群の秀才だった。
同じく俊英だった弟・甚三郎とともに江戸幕府の教育機関である開成所で英学教授も務めたが、この兄弟の語学力と教え方は大変な評判を呼んだらしい。
小幡は福沢の懐刀というか右腕といった存在で、初期の塾長ともなっている。もっともこの当時は現在の大学総長的な塾長ではなく、学生長のような立場ではあった。
そして現代でも名著とされるトクヴィルの『アメリカのデモクラシー』やジョン・スチュアート・ミルの『自由論』の翻訳を成し、言論人としての福沢を支えている。福沢は官軍と彰義隊の上野戦争の最中に、フランシス・ウェーランドの『経済学原論』の講義を続けていたことで知られるが、ウェーランドの原書を購入し福沢に渡したのも小幡だった。何よりも、あの『学問ノススメ』の初版本は小幡と福沢の共著である。
しかし、22才という年齢から(それまでも蘭学とは接点はあったであろうが)英語を習熟して2~3年の内に大著を翻訳し、開成所での講義をするレベルに達する語学教育とはいかなるものなのか、筆者は自身の語学力を顧みて唖然とするばかりだ。
実態は良くわかっていないが、当時の慶應での講義も体系立ってなされたものではないようだ。即ち、アルファベットの読み書きなどすっ飛ばしていきなり原書の講読に入るようなスタイルで、現在の英語教育というよりは、各藩校や学塾で行われていたような漢文の素読に近いものらしい。無論外国人の教師がいたわけではなく、発音などは各人各様のようなメチャクチャだったろう。
ここからは筆者の推測であるが、基礎として漢文の素読を叩き込まれた当時のインテリは、レ点をつけて読むように自然体で文法を理解し、単語については漢語あるいは漢字の持つ意味を置き換えるようにして読み下したのではないだろうか。これを繰り返しているうちに自らの血肉にしてしまった。例えば小幡はRoyaltyを『尊王』としている。
さすれば、国際的に通じる人材育成のために、教えることができる人間もロクにいない小学校での英語教育なぞ全くの無意味。やれ『ゆとり』だ『イノベーション』だ『個性』だ、といじくりまわして明治人にはるかに及ばない無教養を量産してどうなるというのだ。
日本にいて日本の文化を育まなければ日本人にもなれはしない。まさか英語の下手なアメリカ人を造ろうとでも言うのか。
ここで話がグッとくだけるが、先日仲間と例によって騒いだのであるが、席上誰が一番語学のセンスがあるかの話になった。帰国子女上がりが3人もいて他も海外に赴任した経験があるため英語は除いて、第二外国語及び赴任地の言葉がどの程度なのかを比べて遊んだ。はじめは『こんにちわ』あたりからのスタートだったが、伝言ゲームを始めたあたりからめちゃくちゃになった。お店のママからお題を出してもらってカウンターを右から左にやったところ、使う方も聞く方も小声でやっていられなくなり、それこそボディ・ランゲージやジェスチャーの様相を呈し、『ニワトリが金のタマゴを生んだ』が『金のブタがフライドチキンを食べた』となる有様。その間に使用された言語はロシア語・フランス語・ドイツ語・北京語・広東語・韓国語に及んだ。酒も入っていたし、さぞ異様な集団に見えたことだろう。
で、結論としては、会話に限って言えばセンスも才能も関係ない。執念と反復の根性があれば何とかなる。だから子供のうちは国語の読解力と文章力を磨けばよい、というどうでもいいオチでした。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:言葉