本当かよ 承久の乱
2016 AUG 25 1:01:51 am by 西 牟呂雄

後鳥羽上皇は『新古今和歌集』を撰したことで知られるが、武芸も好み自ら刀剣に焼刃を入れるような変わった天皇であった。その異色振りは皇統の魔人、後醍醐天皇にも匹敵すると筆者は考えているが、いかんせん巡り合わせが悪すぎた。
平家が木曽義仲に追っ払われて僅か四歳で三種の神器が無い中に即位。在位中に鎌倉幕府が出来てしまった。
しかし初期鎌倉幕府は畿内を中心に朝廷が一定の勢力を保持する二重政権で、後鳥羽院も広大な荘園を維持していた。西行法師や鴨長明などとチャラチャラ暮らしていればいいのに、一方で北面に加え西面の武士を組織し幕府への対抗心を隠そうともしない。
そこでまた間の悪いことに鎌倉三代目将軍実朝が暗殺されてしまい、新将軍の件でモメる。そしてとうとう北条義時追討の院宣(いんぜん)を出すに至った。
鎌倉では動揺する御家人を前に北条政子が涙ながらの大演説を行ったことは良く知られた話だが、鎌倉武士は団結して京に向かった。
やる気満々の上皇はこれを迎え撃つため、美濃・尾張の国境に布陣するが、実に情けない事に京方は総崩れ。ついに宇治川の決戦となってしまった。後鳥羽上皇は自ら武装したらしい。宇治川は豪雨により増水していたが、鎌倉方は溺死者を出しながらも強行渡河し京へなだれ込んだ。
以上が承久の乱のあらましだが、最近面白い事を知った。
上記北条追討の院宣は当時の公文書、漢文で書かれていた。ところが追討される北条義時をはじめ、鎌倉武士団でそれを読める者がいなかった!慌てて坊主かなんかに読ませてわかったという有様で、都と関東の文化程度はかくも差があったのかと今更ながら驚いた。
どうやらこの時代のサムライとか軍師は、戦国時代の黒田官兵衛のように『孫子』や『六韜』を読みこなしているようなインテリではなく、梶原景時とかは暦と占いで戦争の日を決め、また占いで陣の方角を決め出陣式の段取りをつけるだけ。あとはせいぜい情報を取るぐらいが関の山だから、奈良時代には入っていた『史記』なんぞ読んでないのだ。これらが熱心に読みこなされるのは戦国時代になってかららしい。鎌倉武士団の教養なぞ推して知るべし。
後鳥羽上皇は隠岐の島に流されそこで20年余りを過ごす。することがないので七百首近い和歌をお詠みになった。
我こそは 新島守よ 隠岐の海の 荒き波風 心して吹け
配流後も強い気迫が感じられる。あながち妄想とも言えないのは百年後に流されてきた魔人・後醍醐天皇は脱出に成功している。忠臣楠公ありせば・・。
余談だが、百人一首のパロディーとして「股引や 古き軒端にぶら下がり」と落語のネタに使われる
ももしきや 古き軒端のしのぶにも なほ余りある 昔なりけり
は、後鳥羽院の三男順徳上皇の作品です。オヤジ以上のイケイケで佐渡に流されて詠んだものです。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:伝奇ショートショート


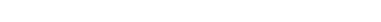
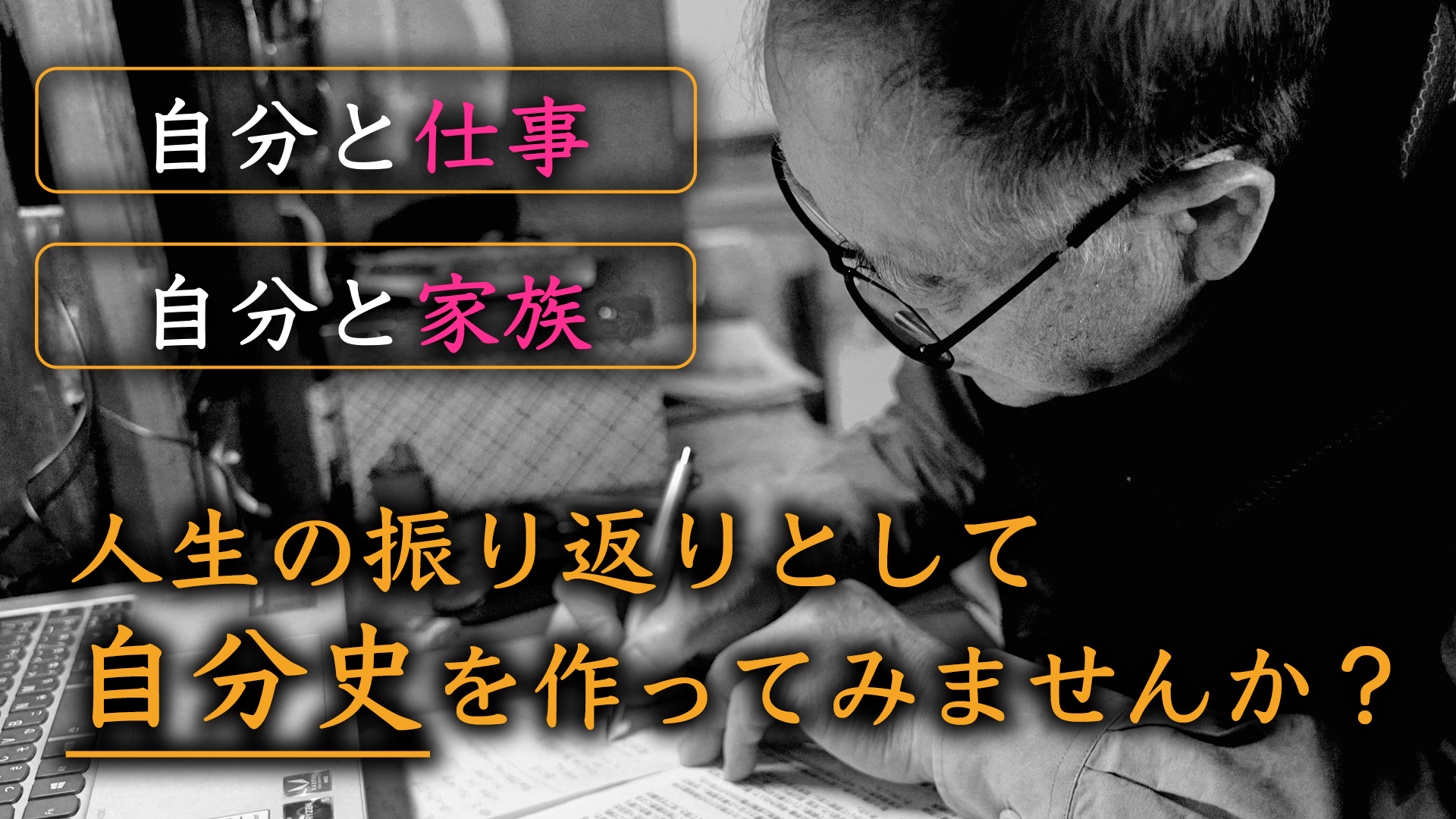


西 牟呂雄
12/19/2022 | Permalink
大河ドラマはこの承久の乱で終了しました。
松也の後鳥羽院は非常に良かった。流される時に発した『いやじゃ~』は誠に歌舞伎調で結構。
後白河法皇・後鳥羽上皇・後醍醐天皇を勝手に 皇統の三魔人 と呼んでるのですがどうでしょう。
何故か順徳上皇は全く描かれなかったのは少し残念。