2015 サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(還暦編 Ⅲ)
2015 JAN 18 14:14:47 pm by 西 牟呂雄

油壺の日曜も暮れる頃、又オレを打ちのめす事態に陥った。またしても彼女の一言だった。
「ご隠居。明日は月曜ですよね。あたしT文大の講義の日じゃないですか。」
「あー?それが?」
「あたし又乗せてってもらえますか?」
「えっ?」
オレは抜けていたので、ボーっとビールを飲んでいた。ふと目を上げると、彼女だけじゃない、英語屋、イベント屋、物理屋の血走った目が邪悪な光をたたえてこっちを見ている。そのゾッとする気配は悪魔のようだった。
オレは小さい声で『みなさん御家庭があるんじゃないですか。』とか『お嬢チャンさんのお部屋のお掃除は。』とか『お仕事が忙しいのでは。』もっとあからさまに『ボクの自由は。』などと言ってみたが、誰一人振り向いてもくれなかった。かわりに、
「おい、酒が残ると困るからお前もう寝ろ。」
という愛情あふれる声がかかったとき、フーッと気が遠くなった。
月曜の朝焼けの中、東名を突っ走るワン・ボックスの中には、ハンドルを握るオレの他、熟睡しているバカじじいどもと美女がいた。
オレは自由と時間の関係について、必死に考えた。
要するに完全な自由になるには、あらゆる誘惑に耐え、完全な孤独に打ち勝つ、鉄のような意思が不可欠なのではないか。そしてそのような意思を持てるのはごく限られた人間だから、そうではないオレのような人間は多少の不自由にならざるを得ないのではないか。
時間が無限にあれば、人間は自由になれると思ったら大間違いなのだ。時間を無駄なく使うことこそ、自由への近道に違いない。現に、最も時間のあるはずのオレが、色々と制約のあるはずのこいつ等にオレの生活を奪われ、奴隷のような扱いをされ、運転手にされているのが、何よりの証拠だろう。
何とか時間通りT文化大にたどりつくと、ヤマトヨシコは『じゃ、後でオウチに行きます。』と跳ぶよう
にキャンパスを走っていった。
「フアー、なかなか洒落た学校だな。」
「散歩でもしようぜ。」
オレも近くではあるが、中まで入るのは初めてなので、4人でフラフラと迷い込んだ。
授業中なのだろう、人影もまばらな静かな佇まいだった。裏手の学食と思われる建物に近づいたとき、明るいギターやバンジョーの音色と屈託のない歌声が聞こえた。
「オッ、やってるのかな。」
「懐かしいなー、フオークソングだな。」
裏手の、もう山のふもとの当たりの雑木林のところで、4人編成のバンドが何とブラザーズ・フオアの”花はどこに行った”をやっていた。随分古い歌だ。実はオレ達4人は今やっている学生と同じ編成でバンドをやっていた。英語屋がギター、イベント屋がバンジョー、物理屋がフラット・マンドリン、オレがベースだった。曲が終わると思わず拍手した。
「君達随分古い歌やってんだね。」
「恥ずかしいです。僕達ヘタですから。」
「他にどんなのやってるの?」
「いや、レパートリーこれしか無いんです、まだ。」
あれこれ話しているうちにオレ達も同じようなことをやっていたことが話題になり、『じゃ、やってみせてくださいよ。』となってしまった。何しろ45年ぶり、四捨五入で半世紀も前のことだ。それぞれの楽器を手にして音を出してみると何やら怪しい感じだ。
「おい、何ができるか?」
「そりゃー、アレだよ。あれ。」
「あー。アレか。ありゃーさすがに忘れないな。」
ギターの軽快なイントロを英語屋が奏でると、何と一発でそろった。都合千回は演った曲、サンフランシスコ・ベイ・ブルースだ。
”オイラを残して あの娘は行っちゃった 富士山の麓まで とってもイカした 娘だったが”
途中の間奏は物理屋のフラット・マンドリンだが、やはり往年の早弾きは無理なものの、無難にこなした。ヤツは天才だ。エンデイングまでやったところで、全員息が切れた。おまけに指がふやけてしまっているので弦を押さえる方と弾くのと両方とも痛いのなんの。皆もそうらしい、マイッタ。
「皆さんお上手ですねー。」
ここで、オレの悪いクセが出た。
「いやなに、昔はプロで鳴らしたもんさ。オレ達はフジヤマ・マウンテン・ボーイズって言うんだ。」
「へー、知らなかった。プロだったんですか。」
ふと気がつくと、他の奴等の視線が痛かった。
そして、しばらくヨタ話をしているうちに、オレの嘘っぱちが止まらなくなり、学生達は純情なのかバカなのか益々それを信じ込み、オレの山荘に遊びに来ることになり楽器ごと車に8人も乗り込み、ガサガサと移動した。
着いたら着いたで、驚いた顔の学生を尻目に早速雀卓を囲みだした。ところで、昨日の段階で手持ちの現金がオケラになったオレは一度終了を宣言したのだが、彼等はそれを許さずツケを主張した。
学生の目が点になっていた。しかしこの時点からおれは勝ち出したのだ。もうどうでもよいが。
そしてそこへ、講義の終わったヤマトヨシコが帰ってきた。もはや『訊ねてきた』という表現は当たらないだろう。皆も『おー、早かったな。』『メシ、メシ。』とか言っている。同級生の娘の扱いではない。更に学生達の反応は以外なものだった。
「大和先輩!どうしたんですか?」「お知り合いですか?」
「君達こそなにしてるの。ここはあたしのシマよ。」
オレのウチなんだけど。聞くところでは、彼女が師事している大学院の先生の学部ゼミ生のようだ。すなわち彼女が姉貴分らしい。呆気にとられた学生を尻目に『2抜けでしょー。』と麻雀にも加わりポン・チーやり出す。
この日またもやオレは続け、自由を奪われ続けた。
今何曜日なのか分らない。部屋はきれいに片付いている。
「クソッ。」
思わず呟いた。一体何なんだ。やっとの思いでメールチェックをした。バカジジイどもからほぼ同じ内容のメール。読んでみると、とんでもないことがわかった。学生達がやる、チャリテイーのミニ・コンサートのゲストに既に在りもしないフジヤマ・マウンテン・ボーイズが出ることになっていて、いくらなんでも少し練習でもしよう、と勝手な日程がそれぞれ書いてあり、レパートリーに入れたい曲がこれまた勝手に列挙してあり、最後にこう締めくくられていた。
『お前は暇で自由でいいなあ。調整をたのむ。』
ヤマトヨシコは、
『とっても楽しかったです。皆さんとの話を母にしたら、懐かしがって、次ぎの麻雀デスマッチは筑波のうちに来て欲しいそうです。自分もやりたいみたい。ご隠居一番自由なんで日程のこと、幹事お願いします。』
オレは頭に来た。ある、強い怒りとも何ともいいようのない言葉が胸に湧いてきた。それは半世紀前にあいつ等と会ったころオレに芽生えた言葉だった。そうだハッキリ思い出した。あいつ等と会ってオレは自我に目覚め、こう呟いたことがあったのだ。
「こうなったら、もうグレてやる!」
ーおしまいー
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる



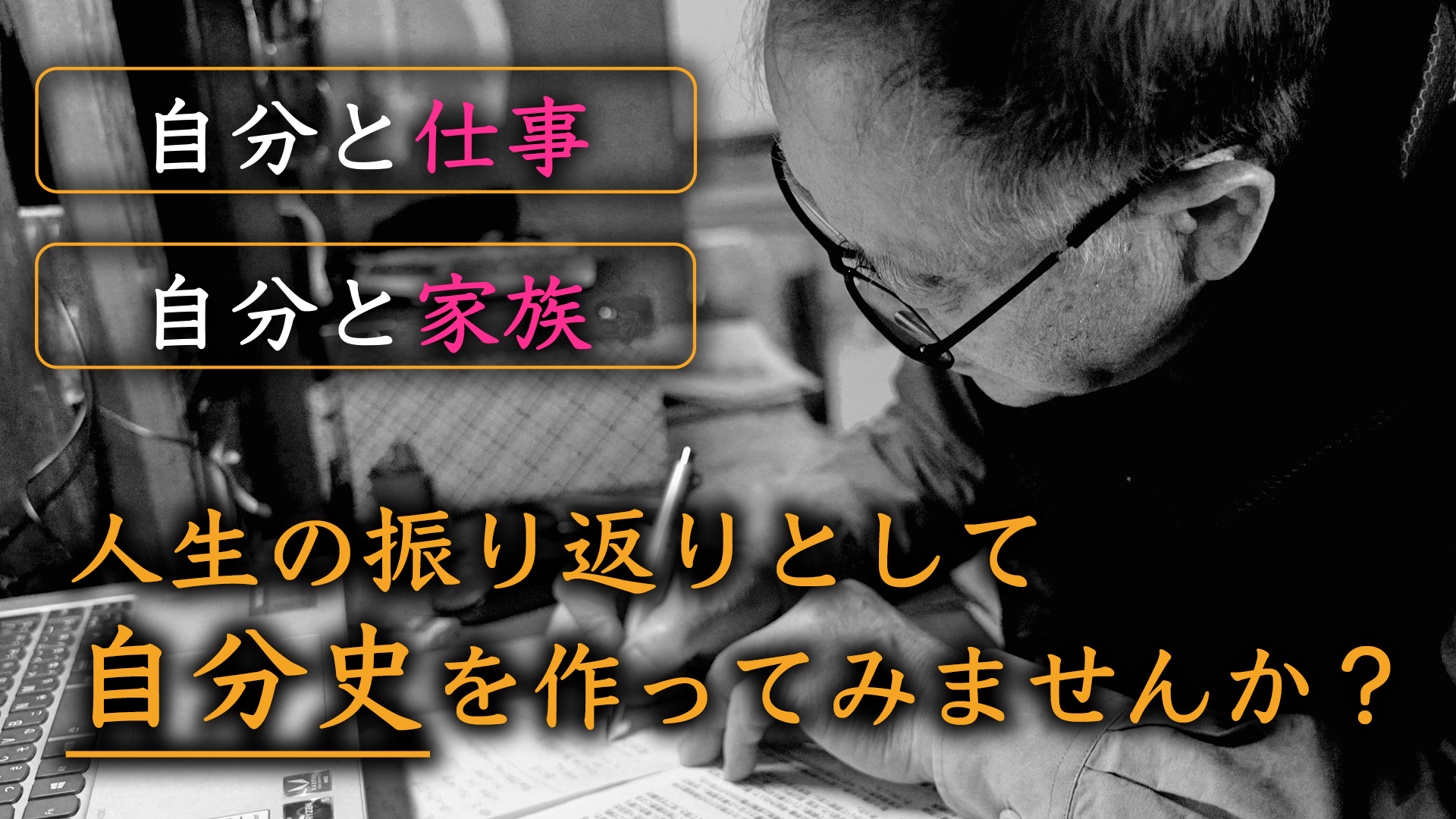


中島 龍之
1/21/2015 | Permalink
バンド再結成まで行ってしまいましたね。青春回顧もの2部作になってますね。面白かったです。
西室 建
1/21/2015 | Permalink
『サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる』はこれでネタ枯れです。次は『流浪望郷編』を構想中です(笑)。
中島 龍之
1/22/2015 | Permalink
テレビでも、シーズン2などと言って続編をやってますから思いついたらまたやってください。「流浪望郷編」期待して待ってます。