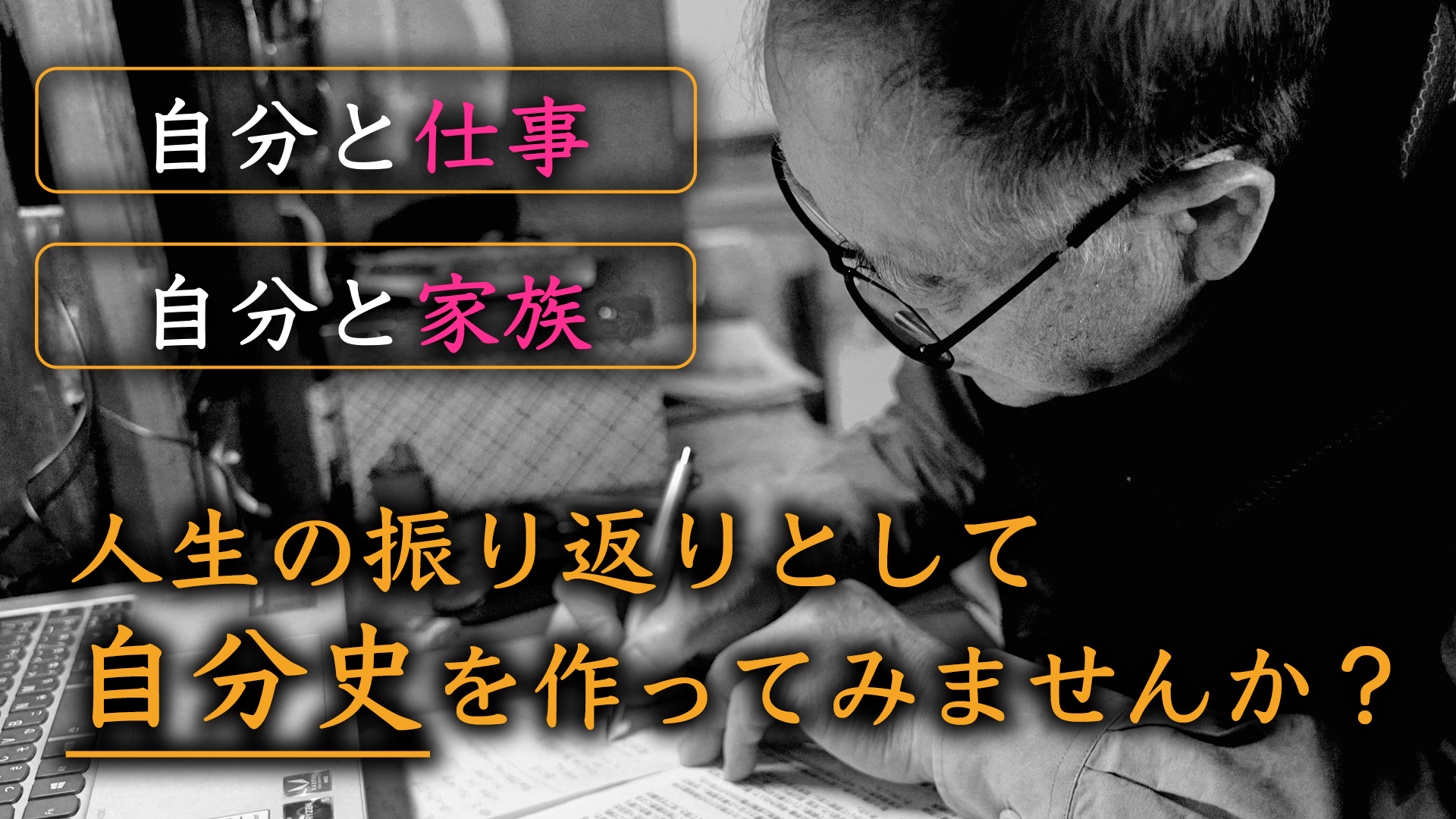サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(197X年共学編 エピローグ)
2014 APR 29 10:10:42 am by 西 牟呂雄

椎野と出井さんと僕にB・B。四人で座った途端に逆上したB・Bはまくし立てた。
「創刊号でも書いたんだけど、中也を見出したのはこの同人誌『山繭』のグループなんだよ。骨董の目利きで白洲正子さんの師匠に当たる青山二郎という人がいて、この人が若き小林秀雄や河上徹太郎を鍛えたんだね。初期のリーダー格は富永太郎っていうんだけど、夭折してしまって作品が少ないから世間的には全く無名なんだ。数少ない散文詩が残ってるけどとっても透明感のあるきれいな文章だよ。そういった猛者の中でも中也は個性的というか特殊な少年だったらしいんだ。それでここが僕の研究してるところなんだけど、中也の恋人で少し年上の長谷川泰子ってとびきりの美人なんだけど、その人に小林秀雄が惚れちまうんだ。僕の仮説では小林秀雄がちょっかい出したと言うより、ガキで生活力のない中也を見切って長谷川泰子の方が乗り換えたんじゃないかと睨んでるんだ。その前後で中也の詩の内容や小林の文章がどう変わったかというと、ほら、」
こいつは出井さんの前で嬉しそうに喋ってるけど、いつの間にこんなことを研究したというのだろうか。こいつの成績は僕の観察によれば、数学以外はほぼ白痴じゃないかと思われる点数を取っているにも関わらず、だ。数学は超変人の数学教官とウマが合って授業中に二人で漫才みたいな受け答えをしていたが、例の日本史に至っては問題外の烙印を押されているにに違いない。何しろバーチャル日本史をまるまる一学期間こしらえていたのだから。そして解説は止まる所を知らないで延々と続いた。B・B恐るべし、しかし。
「ねえ、原辺君。でもあたしどっちかと言うと中也はあんまり好きじゃないんだ。ちょと弱々しくない?萩原朔太郎の方がいいな。こう・・うまく言えないけど。凄味があるっていうの?」
「!」
虚を突かれてB・Bは絶句した。隣りに座っていたので表情は見えない、いや、かわいそうで見られない。しかし、黙っていると噴き出してしまいそうなおかしさがこみ上げてきて実に困ったが、さすがに笑う所じゃない。一瞬の沈黙の後、椎野が助け舟を出す。
「出井さぁ、11月3日にF高の文化祭があってオレら30分ばかりステージに出るけど来ないか。中学で一緒だったのもいるじゃん。飯田とか江藤とか。」
「あら、懐かしい。行く行く。」
帰り際には『また一から萩原朔太郎の研究かぁ。』とため息をついていたが、この驚くべき生命力のゴキブリ高校生は『黄道Vol2 萩原朔太郎研究』までは発行した。尤も力が抜けたようで僕達には見せなかった。
出井さんは、それでもF高校での僕たちのステージに来て楽しんでくれたし、B・Bともコーヒーを飲んだりお付き合いしてくれるようになった。そして後期の中間試験が終わり年が暮れた。
ところが新年から椎野が全く学校に来なくなった。一週間くらい気にも留めなかったが、出井さんが『椎野君はどうしたの。』と聞くのでビックリした。B・Bに聞いても分からない。椎野は僕達の付き合いとは別に地元の仲間がいて、それはヤクザじゃないんだろうが多少危ない連中らしいことは知っていた。B・Bは電話をしてみてこう言った。
「お母さんが出ちゃって繋いでくれなかった。どうも家にいないようなんだけど、オレには、何処にいるか知ってるか、とか聞かないんだよ。今時ヤサグレかねぇ。」
由々しき事態だがどうしようもない。去年は僕たちのグループでいくつかのステージをこなして、人気も少し出たのだがもうバンドは組めないかもしれない。
なすすべも無く高校3年になってしまって、ボソボソと受験勉強に取り掛かることになった。B・Bはというと(3年になるときはクラス替えが行われなかった)、相変わらずチャランポランな暮らしをしているようだが、去年小野田少尉がルバング島で発見されて以来陸軍中野学校の研究に夢中になったらしい。『陸軍中野学校シリーズ』という市川雷蔵の映画があるそうで、深夜5本立てを誘われたが断った。もっとも3年は選択授業ばかりで、文系・理系・その他の選択によってクラスでも滅多に顔を合わせることはない。英語の授業中に『龍3号指令』とか『雲1号指令』というメモが回って来たが、帰りにサテンに行こうぜ、の意味のようだ。そして何を思ったのか背中まで伸ばしていた長髪をバッサリ切って、テカテカのリーゼントに撫で付けていた。
椎野からはがきが来た。何と沖縄にいて、働いていると言うではないか。沖縄は3年前に日本に返還されて、何かと話題になるのだが、まだ観光地としての認知度は高くない。うまいところに逃げ込んだものだと関心するとともに、椎野のタフさ加減に舌を巻いた。暫く隠遁して大検を目指す、と書いてあった。B・Bと出井さんに見せた。
「どうしちゃったのかしら。」
「こりゃ、女だよ。」
「エッ。」「エッ、おんなってB・B知ってるのか。」
「いや、知らないけど。やっぱあいつも色々背負い込んでるもんもあるんだろ。ニッチもサッチも行かなくなったんじゃねーか。」
「お前その頭どうしたんだ。」
「ヘヘッ、おりゃー近頃ロックンロールしかきーてねーんだ。」
「どうしたんだ、その喋り方。」
「ん?最近酒飲み出しちゃってよ。まぁいいじゃない。よろしくゥ。」
秋が過ぎて冬になって、大学も受験し、とうとう卒業の時が来てしまった。この間は交流も薄く、僕にとっては空白期間の様だった。教室に置きっ放しにしていたギターを持って帰らなければ。久しぶりにB・Bと連れ立って学校の裏の神社で話しこんだ。僕は文学部に、奴は経済学部に行くことになった、大学は別だが。B・Bはリーゼントはもうやめていて、また髪を伸ばし出していた。
「お前やっぱりその頭の方が普通だぜ。」
「いやぁ、大変だったよ。オレ目付きが悪いらしくて学校来るのも一苦労だった。あの手の頭の連中は匂いがするのかいつのまにか寄ってきて『なんだお前はよゥ。』がすぐ始まるんだぜ。ボクはロックンローラーです、なんつったって学ラン背負ってちゃ通じないんだもん。」
「なんにせよもう卒業だ。」
「もうここに来なくていい、と思うとホッとする。はみ出しモンはしょーがねーな。」
「出井さんはどこに行くんだ。」
「知らない。なぁ、あれは恋だったんだろーかね。」
「さあー、ちょっと違うんじゃない。相手にされなかったというか・・・。」
「椎野の奴、今も沖縄にいるんだろうか。」
「訪ねようにも住所もわからん。」
「一曲やるか。」
「サンフランシスコ・ベイ・ブルースな。」
演奏を始めると、観光客や遊んでいたガキが寄ってきてちょっとした人垣が出来て拍手をしてくれた。別に嬉しくもなかったが、僕たちは愛想笑いをした。
エピローグ
僕(英)は英文科に進み、イギリスを放浪した後大学に戻りアメリカ文学をやることになった。
B・Bは奇をてらって卒業後、堅気のサラリーマンになる。うまく行くはずはないが。
椎野は沖縄でブラブラした後、香港を拠点にした怪しげなビジネスを始めた。
出井さんは研究者になりかけて、その後結婚した。
四人が再び邂逅するのにそれから四半世紀の時間が掛かることになる。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(197X年共学編Ⅲ)
2014 APR 23 22:22:28 pm by 西 牟呂雄

夏休みが終わり、9月なのだがE高校はすぐ中間テストが始まった。しかし僕たち3人組は試験そのものはどうでもよく、午前中で終わってしまった後まさか麻雀をする訳にもいかずどうやってヒマを潰すのか困っていた。通用門の前を全校生徒がズラズラと下っていく坂道の光景の中で僕達は明らかに浮いていた。すると足早に歩いていく女子生徒と椎野が二言三言会話をした。B・Bはそれを見て僕をつついた。
「おい、あの娘は誰だ。」
「椎野のクラスの娘だよ。確か椎野と同じ中学じゃないか。」
「ちょっとお茶飲んで行こうぜ。」
サテンに入って早速ハイ・ライトに火をつけると、椎野に切り出した。
「おい、さっき話してた中学一緒の娘は何て言うんだ。」
「ん?出井のことか。出井聡子。かわいいよ。」
「フゥーン。イデイさんね。椎野知ってるならオレに紹介してくれよ。」
「ばか!やめとけ。お前の手に負えるわけない。ありゃ真面目だぞ。」
「いいじゃないか。ま、今んところオレは秀才とは言えんが。誰か彼氏がいるのか。」
「そうじゃないんだよ。ありゃ孤独癖とでもいうのかつるまないんだよ。きれいで人気者だけど真ん中にぽつん。お前にはもうちょっとトロそうな愛想のいいのを見繕ってやる。」
「やだぜ、そんなの。」
「だからいきなりチャレンジするのが無理なんだよ。あらゆる物事に手順があるように、アーパーな姉ちゃんに2~3回振られてからじゃないと高みには登れないんだぜ。大体オレ等が喋ってる口調も内容も女にゃ通じないのがオチだ。話をするにも修行がいるんだよ。ナメてもらっちゃ困るな。」
「振られなかったらそのアーパーとくっついちゃうじゃないか。オレの青春が無駄になるだろうが。」
「なるわけないって、所詮お前は麻雀カブレのバンド・ボーイだろ、今はゴキブリ並みの高校生なんだから自分をわきまえろ。」
「何だよ、よしオレひとりでやる。」
「ばーか。」「バーカ。クソして寝ろ。」
しばらくすると、何と驚いたことに出井さんにB・Bが冊子を手渡ししていたのを偶然チラッと目撃した。なんだあいつ、椎野にバカにされて玉砕戦法にでも出たのか。これは早速知らせなけりゃいけない。
「何!あいつそんな無謀なことしてたのか。こりゃどのみちロクなことにゃならん。手を打っておかないと。」
椎野は早速動いて、翌日あきれかえった顔で報告があった。
「どうやらあのバカ、出井に自作の詩集か何かを送って感想を聞かせてくれって言ったらしい。出井は出井でよしゃーいいのに真面目に読んで感想を書いてやったそうだ。『面白い文章です。』みたいなことを返事したと言ってたよ。お前同じクラスだろ。B・Bの様子はどうだ。」
そういえば、夢中になっていたバーチャル日本史のメモは今学期から途絶えていたし、バンドの練習の声もかからない。いや、休み時間や放課後にあいつの顔を見ていない。
昼休みに声を掛けた。
「おい、B・B。」
「ん?なんだよ。」
「練習しようぜ。F高の文化祭からオファーが来てるぜ。30分5曲だって。」
「いつ?」
「11月の3日だよ。椎野もベース・コピーしたからさ。」
「ワシはちょっときょうはダメだ。忙しい。」
「どこ行くんだよ。」
「ん?図書室。」
「はぁ、まさか勉強でもするのか。」
「いや、雑誌造ってるんだ。」
「ざっし?って何の雑誌だよ。」
「あとで教えるよ。まだ一号しか出来てないんだもん。」
「中身なんだよ。手伝ってやろうか。」
「ダメダメダメ。まぁ内容は詩とその評論だけど。」
野郎、ついに気でも狂ったんじゃないか。
3日ほどして椎野と放課後図書室を覗いた。B・Bは受験勉強をしている生徒に交じって隅っこにいるのがすぐ分かった。何やら沢山の本を広げたり積み上げたりした中で一生懸命何かを書いていた。図書室では会話厳禁だから向いの席について「みーつけた」と書いたメモを渡すと、目を剥いてビックリしていた。ビックリしたのはこっちも同じで奴は鉄筆をもってガリ板を切っていた(この時代コピーは無く、ワープロも無い)。積んである本は誰かの全集、高村光太郎、小林秀雄。ノートに草稿を持っているらしく、言葉を確認したりして原稿を書いていたのだ。露骨にいやな顔をして「あと1時間」とメモを返してきた。僕はしょうがないから薄い原書を見繕って読み、椎野は所在無く持っていた推理小説を読んだ。5時前にB・Bが本を片づけ出し、僕たちに目くばせしたので一緒に出た。いつものサテンでハイライト。
「本当に雑誌を造ってるのか。」
「ああ、これが創刊記念号だ。」
表紙には『黄道Vol1』と題名。はやりのサイケデリックなイラスト、花をあしらったつもりのようだ。目次はと言えば、
ー今週の詩 『川の中州の一厘のコスモス』 阿部瀬出男
ー現代詩の創成期 『同人誌 山繭とその時代』 アビイ・ツェーデエ
ー感傷的表現の類似性 『高村光太郎を読む』 恵比寿大師
ー連載俳句 『街の風』 原辺 ユズル
ー季節の連歌 『季題 晩秋』 詠み人知らず
「一体どれくらい掛けてこれ造ってんだ。」
「一週間かかった。次の号は毎日やってまだ原稿が半分だよ。週刊誌にしようと思ったけど企画倒れになりそうだ。」
「この著者ってお前の知り合いなのか、誰も知らないけど。」
「そりゃそうだよ。全部ワシが文体変えて書いてるんだ。」
「じゃみんなおまえのペン・ネームか。それにしてもゴロの悪い。」
「思いつかないからA・B・C・Dをフランス語で読んだりドイツ語で読んだりしながら考えたんだ。」
「で、何だってこんなもん造って、いったい誰が読むんだよ。」
「出井さんにあげるんだよ。」
「お前!出井一人のためにこんなことやってんのか。」
「ワシの詩は個性があって面白いから、連作するといいでしょう、と。類似の作品を探して比較してみるといいでしょう、刺激をうけるのではないでしょうか。って感想書いてくれたんだ。オラオラオラオラこれだ。」
僕は心配になった。B・Bの奴とんでもない勘違いをしたんじゃないだろうか。
椎野は黙って目を通して傍らに置くとドスの効いた声で話し始めた。
「これだからシロートは困る!言わないこっちゃない。初めに聞くけど、お前は出井の何を知ってるんだ。」
「何をって何だ。」
「だから何が趣味か、とかどんなものが好きか、とか得意な物は何かとか。」
「そんなこと知らん。」
「あのなあ。坊や、恋愛は一人でするものじゃないのは知ってるよな。ましてや相手はお前が誰かも知らん。それがいきなりこんな紙屑をワンサカ送り付けられたらどんなに気味が悪いか分かってんのか。何で相談しないんだ。」
「だって、初めに紹介してくれって頼んだらいったらヤメロって言ったじゃないか。」
「当たり前だろ、自分でどう思ってるか知らないがお前立派な変人だぞ。段取りもつけないで何考えてんだ。」
「じゃ、どうしろってんだ。邪魔するな。」
B・Bは例によって不貞腐れた。どうしろって言ってももう遅いんじゃないか、と思っていると百戦錬磨の椎野は言った。
「オレに任せろ。話す機会を作ってやる。」
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(197X年 共学編 Ⅱ)
2014 APR 20 13:13:19 pm by 西 牟呂雄

都内の一軒家で恐ろしくヒマそうな高校生が二人で、ガシャガシャとギターをかき鳴らして歌を歌っている。マイナー・ヒット曲サンフランシスコ・ベイブルースだ。かつてジェシー・フラーがアメリカでヒットさせたフォーク・ソングだが、このころ武蔵野タンポポ団なるバンドが日本語でカヴァーしてコンサートでよく歌っていた。
『オイラを残してあの子は行っちゃったー・富士山の麓までー・とってもイカしたー・娘だーあったがー・さよならと一言言ったきり・あの娘は二度とは帰って来ないだろー・オイラにゃお金も車も無いからー・でも戻っておくれー・機嫌を直してー・そして一緒に歩こうよ吉祥寺の街を』
武蔵野タンポポ団は吉祥寺の伝説のライヴ、ぐゎらん堂という店でよく歌っていた。この二人、原辺(ばらべ)と英(はなぶさ)はバンドを組んで練習していた。もう一人の椎野は夏休みが始まった途端にナンパのメッカと言われた新島に行ったきり、全然連絡もない。
「二人でやってもサイモンとガーファンクルみたいにはいかねーもんだな。」
「そりゃそうだ。本物はギター一本でやってるからな。お前もうちょっと練習しろよ。」
「だからこうしてやってんじゃねーか。椎野は何にも言ってこないのか。」
「まだ島にいるんだろ。金がなくなるまで居るって言ってたな。だけど本当に毎日ナンパして暮らしてるのかな。」
「そんなに成立するとも思えないけど、手当たりしだいに声を掛けて同じ女の子に当たることになったらどうすんだ。」
「何れにせよ華やかなもんだよ。こないだお前と行ったブルース・フェスティバルって気が付いたら客は男ばっかりだったぜ。それも右から左までベル・ボトムのジーンズでガサガサ髪伸ばしてさ。」
「だから女はみんな新島に行ったんだろ。」
「もう夏休み終わっちゃうけどなァ。3人で音あわせしないと秋にステージに上がれないじゃない。」
「だからもう少しレパートリー増やそうぜ。何やる。」
「ビートルズは解散しちゃったから新曲は出ないんだよな。」
「ありゃ映画の時点で終わってんだよ。だってあの心優しきジョージが大天才ポールに苛められてるところ映ってんだぜ。」
「それで時代はフォーク・ソングですかね。」
「お前が試しに造ってくる曲はコード進行がみんな同じだぞ。このけったいな詩が歌に合ってないんだよ。」
「エッそうだったのか。リズム変えるか。」
「シラけた、かったるい、でズーッと行かなきゃなんないのか。大学の方は落ち着いてくれてんのかね。全共闘のオニーさん達もすっかり挫折モードって奴だな。」
「あれはなー、セクトが出てくるとおかしくなるんだよ。一緒にやれなくなって仲間割れしちゃうんだよ。」
「その内セクトに入るのに面接とかが始まったりしてな。」
「試験されたりして。科目は何になる。」
「英(はなぶさ)の得意の英語はないだろう。」
「かえって中国語とかロシア語になったりして。原辺知ってる。あのセクトのフロントってロシア語なんだって。」
「ホントか。知らんかった。」
「毛沢東語録でも覚えるのかな。ML派ってのはマルクス・レーニン派と言われてたけど今は毛・林派って言うそうだ。」
「黒ヘル青ヘル白ヘルとくると野球のチームみたいだな。」
「そんなの言ってるのは広島だけだろ。」
「ゲバ棒振るのにバッティングの練習したりして。」
「オラオラオラオラ腰がはいってないドー。」
「バリの強化のための工学知識。」
「聞かれたら本気で怒られるぞ。ケガ人ガンガン出してるんだから。ハイジャックに総括だもん。」
「それ発音が違う。連合赤軍は関西が主流だからそ’うかつと発音するんだ。」
「安田でやられてから秘密結社みたいになっちゃった。」
「むしろ偉いよな、遊び呆けてるのも一杯いるんだから。」
「うーん、分からん。」
「全共闘のオニーさん達は『網走番外地』が好きなんだって。負けると分かっていても義理を返しに行くってところに痺れるんだそうだ。」
「お前その映画見たことあんのか。」
「いや、ない。」
「三島がハラ切って左右革命決戦でも始まるかと思ったけどな。」
「お前そしたらどっちに付くんだ。」
「・・・・。」
「そう言や新宿のフーテンもいつの間にかいなくなったけど、ありゃどこに行ったんだ。」
「新島じゃない。」
「お前相変わらず中也読んでんのか。」
「それがさ、何しろ早死にして作品数が少ないだろ。暗記しちゃうんだよ。」
「そうか、それで擬態語だらけのけったいな詩になってんだ。こんなモン、特に女の子は読まんぞ。」
「そんなことはない。所詮天才は死んでからしか評価されん。」
「じゃ死にさらせ。」
「ワリャ一人だけ生き残るつもりか。そうはさせんドー。」
「それにしても暑いな。」
「しょうがないだろ。夏なんだから。」
「エーリッヒ・フロム読んだ?」
「お前があんまり煩いから読んだけどつまんなかった。」
「そうだろうな。お前向きじゃないな。」
「オイ、一日中ヒッピってていーんかねワシ等。」
「で何する。」
「映画でも見ようか。」
「あっ駅前の名画座でイージー・ライダーやってたぞ。画面ボロボロらしいけど。」
「あれさ、ピーター・フォンダはラスト・シーンにディランの曲を使いたかったんだってさ。でもディランは発展的なエンドじゃない、という理由で断ったんだって。それじゃ発展的なエンドって何だ、と聞くと二人が一緒に激突して死ぬことだ、と言ったんだそうだ。お前意味分かる?」
「それはだな。一人ずつ撃ち殺されてしまうより、男気を持って敢然と理不尽にブチ当たった段階で・・全ての時間と次元を超越するー・・・・空間的なー、えーと・・・自由が・・・・もたらされてー・・・・。」
「何だ分かんないのか。」
映画館にはヒマな野郎共があたりかまわずタバコを吸っていた。この頃は禁煙も何も関係なく吸っていた。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。
サンフランシスコ・ベイ・ブルースが聞こえる(197X年 共学編 麻雀白虎隊)
2014 APR 6 2:02:58 am by 西 牟呂雄

とある東京のど真ん中の繁華街、学ラン姿の高校生が卓を囲んでポン・チイやっている。午前10時の話だ。こんな時間からやっている雀荘も雀荘だが、高校生もロクなもんじゃない。四人が卓を囲み二人が立ち会っており、一回ごとに二人が入れ替わる。どうやら二人はイカサマをやっていないかをチェックするらしい。何やら緊迫した雰囲気の中「ロン!」の声が掛かった。「やった、メンタンピンだ。トップが来たぞ。」「アチャーッ。」「やられたっ。」「ざまーみやがれ。白虎隊の連勝だ。」
この日は麻雀白虎隊と麻雀奇兵隊の決戦だったのだ。少し解説がいる。この時代の東京のガキで、不良ごっこに勤しむ輩(本当のワルではなく生意気盛りの者を指す)に支持されたのは、深沢七郎・野坂昭如といったところだったが、ウチの高校のグループではアナーキーなギャンブラー阿佐田哲也のエッセイが流行った。一連の麻雀小説にもカブれて、作品中の『麻雀新撰組』が劇画になっているのをB・B(本名は原辺・ばらべと読む)が熟読していた。登場人物は三人だったから僕達3人で名乗りを上げないか、と提案してきたので乗った。名づけて麻雀白虎隊の始まりだった。実は3人でイカサマ(簡単なサイン)をやって誰かをカモってやろうとの魂胆だった。確かに覚えたてのシロウトには抜群の効果があって、色んな奴等を引きずり込んで散々小遣いを巻き上げた。ところが一月ほど経つと、妙な噂が立った。「E高校に麻雀白虎隊なる秘密組織があって、物凄い雀ゴロ集団らしい。」というのだ。初めは同じ学年の間で広まり、雀荘から別の高校にも伝わったらしい。
劇画というジャンルは、要するに漫画なのだが、当時はある種のステータスがあって、いわゆる少年漫画とは一線を画していた。B・Bはソレと思われる作品を好んで熟読し、よく僕たちに勧めた。「ソウル・シンガー」という作品は少年マガジンか何かに連載された奇っ怪なモノで、僕なんかは全然面白くなかったが、確か盲目の歌手が能面を着けて歌う、といったモチーフだった。B・Bはそのセリフを真似た喋り方でよく話していた。
「オレ、今日はかったるいからヒッピるぜ。」
どうも、疲れて面倒臭いからサボッて帰る、と言っているらしい。巷でヒッピーがたくさんいた。又、谷岡ヤスジが一世を風靡した「メッタメタガキ道講座」にも影響を受けて、変な関西弁も使う。
「オラオラオラオラ、ワリャ終いにゃ血ィ見るドー!」
と言った調子だ。同じように勧められた「高校生無頼控」も何か変な劇画だと思っただけ。一番ひどいと思ったのは「パチンカー人別帳」という流れのパチプロの話。奇想天外な技を繰り出す美球一心という主人公がカッコいいと言うのだが。世の中のまともな高校生が「巨人の星」や「あしたのジョー」を読んでいた頃である。アイツの趣味にはついていけない。
しかし妙なもので、白虎隊が有名になると『オレも入れてくれよ。』などと言い出すバカが出てきた。椎野が局長と呼ばれていたので仕切り役だった。『お前の腕ではとてもダメだ。』とか『ホンモノの麻雀新撰組だって3人なんだ。』と言って断っていた。ちなみに本物は阿佐田哲也、小島武夫、古川凱章だったか。そうこうしているうちに同じ学年の麻雀天狗だった大和(やまと)が集めた麻雀奇兵隊なるものができてしまい、バカバカしいことに白虎隊に勝負を挑んできた。大和は学年1の秀才だ。奇兵隊も3人なので、2人づつ出して毎回入れ替える変則ルールで勝敗をつけることになった。それで冒頭の下りになるわけだが、帰り際にB・Bの奴が不思議なことを呟いた。『これで白虎隊の三連勝だ。鳥羽伏見まで押し返したな。』何のことだ。
日本史の授業中にB・Bから紙が廻ってきた。こういうペーパーが先生の目を掠めてよく廻って来るが、なんだろうと思ってこっそり見ると新聞の体裁だ。目に飛び込んで来たのは『1885年(明治28年)初代内閣閣僚名簿』という表だった。何じゃこれは。
《内閣総理大臣 徳川慶喜 前15代将軍》 《外務大臣 福沢諭吉 中津藩士 適塾 慶應義塾塾長》 《内務大臣 勝 海舟 幕臣 海軍伝習所》 《大蔵大臣 小栗忠順 上野介 幕臣》 《陸軍大臣 大島圭介 幕臣 適塾 ジョン万次郎門下》 《海軍大臣 榎本武揚 幕臣 昌平黌 ジョン万次郎門下》 《司法大臣 西 周 津和野藩士 藩校養老館》 《文部大臣 新島襄 安中藩士 米アーマスト大》 《農商務大臣 松平容保 元会津藩主》 《逓信大臣 原 市之進 元水戸藩士 昌平黌》
休み時間にB・Bに聞くと『いや、白虎隊が三連勝したから明治維新が起きなかったんだよ。だけど歴史の必然性があって藩幕体制はもう持たないから、徳川が改革しちゃって廃藩置県はやるわけだ。すると責任内閣制を取らざるを得ないんだけど、薩長土肥の人材は使えないからこういう内閣になるんじゃないかって必死に考えたんだ。』バカかこいつ。教科書を見ると、一学期の今は授業はまだ平安京がどうした、とやっているのに、明治維新の前後にビッシリ書き込みがしてあって、いちいち人物が代えられている。そんなことに夢中になるなら暗記でもしたほうがよっぽど楽だろうに。
ところが白虎隊と奇兵隊の決戦はその後1週間も続き、白虎隊は5連勝した。このころ僕はこの麻雀というゲームの奥深さに魅せられるようになって、五味康祐の本やら指南書を読み込みのめり込んでいた。椎野はめっぽう勝負強く、起死回生の手をよく積もり上がって粘る。問題はB・Bで、自分では天衣無縫流亜空間殺法などとうそぶいていたが、場の流れを見ない殿様麻雀で一か八かの賭けに出たがる、はっきりいって下手だった。同じ頃、隣の謂わば兄弟校にあたるF高校の中学の時の同級生から電話が掛かり、白虎隊のことが噂になって、彼らも麻雀鬼面党を名乗ることにしたから勝負しようぜ、と誘いがかかった。面白い、と受けることにした。F校麻雀鬼面党はやはりなかなか強かった。というか勝負に出ることを極力避けて、こちらの転ぶのを待つ戦法だったようで慎重な打ち回しに徹していた。こういう時にはバカみたいにツイた者勝ちになるのだが、ふざけたことにこの日のB・Bが凄かった。リーチをかければ一発でつもる、相手の高そうなときにピンフで上がる、親ではウラドラを乗せる、と怖いものなしだ。F校の連中は『こりゃ参った。』と頭を掻きながら帰っていった。
しかしその後白虎隊はスランプに陥った。不思議なものでB・Bのバカ打ちのせいじゃなく、僕も椎野もよくマヌケな振込みをしてボロボロ負けだした。奇兵隊は研究も熱心でどうやら僕たちがやる程度のサインを出し合っているのが分かった。分かったがこっちもやっているし、配牌が毎回毎回物凄いクソ手でどうにもならない。椎野もうんざりしていたが、B・Bだけは負けが込んで小遣いが無くなっても嬉々として次の(奴の言う)決戦を仕掛けるのだ。僕は不安になって、奴の日本史の教科書を見た。すると案の定まだ先の江戸時代のところが真っ黒になるまで書き換えられていた。徳川家〇のところが全部丁寧に豊臣秀×に書き換えられており、松平ナントカは羽柴カントカ。加藤家・福島家・石田家という(他にもやたらあったが)関ヶ原から江戸初期に無くなっているところが大っぴらに親藩としていいところに配置されている。無論豊臣太政大臣家は大阪にいて、逆に本田家・酒井家・井伊家は消えていた。
「おい、椎野。B・Bはどうした。」
「ん?英(はなぶさ)か。きょうはF高に行くってすぐ帰ったよ。」
「F高鬼面党か?別に誘われなかっただろ。」
「大和が行ってんだよ。ここのところの勝ちの乗じて奇兵隊を連れて鬼面党とやるそうだ。その取材らしいんだが。」
「あいつF高まで巻き込んでるのか。」
「何だか源平合戦がどうこう、て言ってたよ。」
僕はため息をついていきさつを伝えた。椎野はあきれかえってつぶやいた。
「あいつそんなことに夢中だったのか。どうりで負けても上の空だったわけだ。きっと鬼面党と奇兵隊の試合で鎌倉時代の歴史をいじって遊ぶつもりなんだ。」
白虎隊と奇兵隊の再決戦が始まったが、場は一方的に負けていた。僕と椎野がツキが全くないのだ。この日は午後の授業をサボッて昼過ぎには始めたが、午後4時時点でもう取り返しのつかない負けである。親の時はツモられる、リーチは引っかけても流される、白虎隊がたまに上がるのはB・Bの安手、いいところなしだ。そして今回はもう負け終わりというときにB・Bは大和に劇的な国士無双13面待ちに振り込んだ。実は僕も気が付かなかったのだが。そして終わりになった時B・Bの漏らした一言に椎野は切れた。
「しかし豊臣16代は豊臣明治て言うのかな。初代内閣を造り直さなくちゃ。」
サテンに入ってハイライトに火を点けた途端に椎野はまくしたてた。
「いいかげんにしろ!お前ただでさえお荷物なのにこの5~6試合くらい上の空だろう。まじめにやってるオレ達の身になってみろ!」
物凄い剣幕に、さすがにB・Bも不貞腐れていた。しかし店内のBGMが変わった途端にいつものバカ面に戻った。目が輝いている。曲はマイナーながら密かに流行っている”武蔵野タンポポ団(高田渡や山本コータローがやっていたブルー・グラス・バンド)の『サンフラン・シスコ・ベイ・ブルース』だった。
「分かった。白虎隊は解散する。今度はバンドやろうぜ、こういうやつ」
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/
をクリックして下さい。