『ツクバヤマハレ』
2018 MAR 25 16:16:03 pm by 西 牟呂雄

筆者は最近知ったのだが『ツクバヤマハレ』という符牒を御存知だろうか。
かの真珠湾攻撃命令『ニイタカヤマノボレ』とともに用意されていた暗号らしい。
山本長官は日米交渉が上手く行った場合に機動部隊をUターンさせるつもりでいたが、一部の指揮官がそれに異を唱えると
「百年兵を養うは、ただ平和を護るためである。撤退命令を受けて帰れないと思う指揮官があるなら、ただいまから出勤を禁ずる。即刻辞表を出せ」
と切り捨てている。
そのために用意されたのが『ツクバヤマハレ』という訳だ。
異説では真珠湾に向かった空母機動部隊向けは『トネカワクダレ』だったという話もある。その説では同時に行われるマレー半島コタバル作戦にも12月8日に強襲上陸の『ヒノデハヤマガタ』という暗号文が打たれているが、作戦中止の場合に用意されたのが『ツクバヤマハレ』だと言う、どちらが正しいかは分からないが。
ハワイと英領マレーでの同時襲撃は12月8日のハワイでは早朝、マレーでは真夜中である。尚、米国への宣戦布告が遅れたことが問題となるが、マレー作戦は真珠湾攻撃の2時間近く前に開始されており、こちらの方は英国に対してまるっきり宣戦布告などしてはいない。
その後陸軍は驚異的なスピードで進軍しシンガピール陥落まで2ヶ月しかかからず、マレー沖海戦で制海権も握った。おかげで順調にビルマ・ジャワまで進出したのだが、この時点で英連邦軍10万人の捕虜を抱えた。英国は足元のヨーロッパで苦戦しており、支配下のインド兵などの士気はかなり低かったのだろう。後に捕虜の扱いが問題視されるのだが、占領軍の3倍近い捕虜は食わせるだけで大変だったろう。
御承知の通りインパールの悲劇や南方諸島での米海兵隊との死闘で敗戦に至る悲惨な物語が続くのだが、シンガポール・エリアは血みどろのドンパチなどないまま8月15日を迎える。英本国からマウントバッテン卿がやってきて日本軍の降伏を受理した。
やはり英国もくたびれ果てていたのであろう、協定を結び半年ほど治安維持部隊として日本軍兵士を使っていた。米軍はこのあたりや制空権のなくなったラバウル・台湾をほったらかしにし硫黄島・沖縄で戦闘していたから、マレー・エリアでは惨めに退却する日本軍は現地の住民にも英連邦軍にも目撃されなかったようなのだ。こういった事情があって英国は日本を捻じ伏せたという実感がないのだろう。
ところで話は変わるがシンガポール占領後セイロン島に引っ込んだ英東洋艦隊はプリンス・オブ・ウェールズとレパルスを失ったものの、やや旧式な戦艦5、空母3、巡洋艦6、駆逐艦10隻を擁していた。
これを叩きインド洋までの制海権を確保するために南雲機動部隊を差し向けるのは真珠湾の4か月後、例のミッドウェー直前のセイロン沖海戦である。
急襲空爆は成功したが、攻撃隊指揮官である淵田中佐は即座に「第二次攻撃の要あり」と打電し、機動部隊司令部は湾内艦船攻撃のための雷装を爆装に転換しはじめた。淵田中佐とは真珠湾の時に『トラ・トラ・トラ』を発信した飛行隊長だ。
山口多聞少将は「攻撃隊発進の要ありと認む」と打電してくる。
どうも真珠湾での第二次攻撃を躊躇する南雲司令部の様子が被ってくる。
ところがその後、艦隊行動中の艦船発見の報が入ると再び爆装から雷装へとドタバタを演じ、結局は爆装の急降下爆撃隊を飛ばす。
偵察も不調に終わり敵空母接近を見逃し、雷爆換装中に赤城が空襲を受ける。
こうなると今度はミッドウェーそっくりだ。
結果的にかなりのダメージを与えることには成功した勝利ということになっているが、南雲機動部隊は真珠湾・セイロン沖で散見されたミスを(検証したことはしたかもしれないが)ミッドウェーでは教訓とすることなく惨敗した。
この4月時点ですでに連合艦隊司令部においてミッドウェー作戦は黒島参謀を中心に練られており、そうなるともう止まらない。
戦後の海軍関係者の反省会という体裁の音声が活字化されているが、その中に悲痛な発言がある。12月に真珠湾。4月にセイロン沖。その2か月後のミッドウェーだったので南雲機動部隊の損傷もあった。メンテナンスにせめてあと一月欲しかった、というものだった。
しかも途中に珊瑚海海戦という空母同士が四つに組み、双方一隻づつ失うという躓きがあったにもかかわらず、である。
珊瑚海海戦は史上初の機動部隊会戦という興味深い戦闘である。尚、この時点では海軍の暗号は解読されていた。
米空母ヨークタウンを味方と間違えて日本の九九艦爆が着艦しようとして初めて相手が敵と気づいた、という笑えない話もある。米軍は切り込み隊が強襲したのかと思ったことが記録されている。
それまで連戦連勝だったため、第四艦隊司令長官の井上成美中将は海軍内部で散々な言われようだった。出典が分からないが「コーラルシー(珊瑚海)戦機見る明なし。次官望みなし。徳望なし。航本実績上がらず。兵学校長、鎮長官か。大将ダメ」とまで書かれ、実際に兵学校長になる。
ところが敗色濃くなる中、米内海軍大臣を補佐するために最後の海軍次官となり和平工作の奔走することは阿川弘之の作品に詳しい。
嗚呼 『ツクバヤマハレ』 打電されれば・・・
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
Categories:言葉


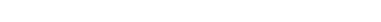
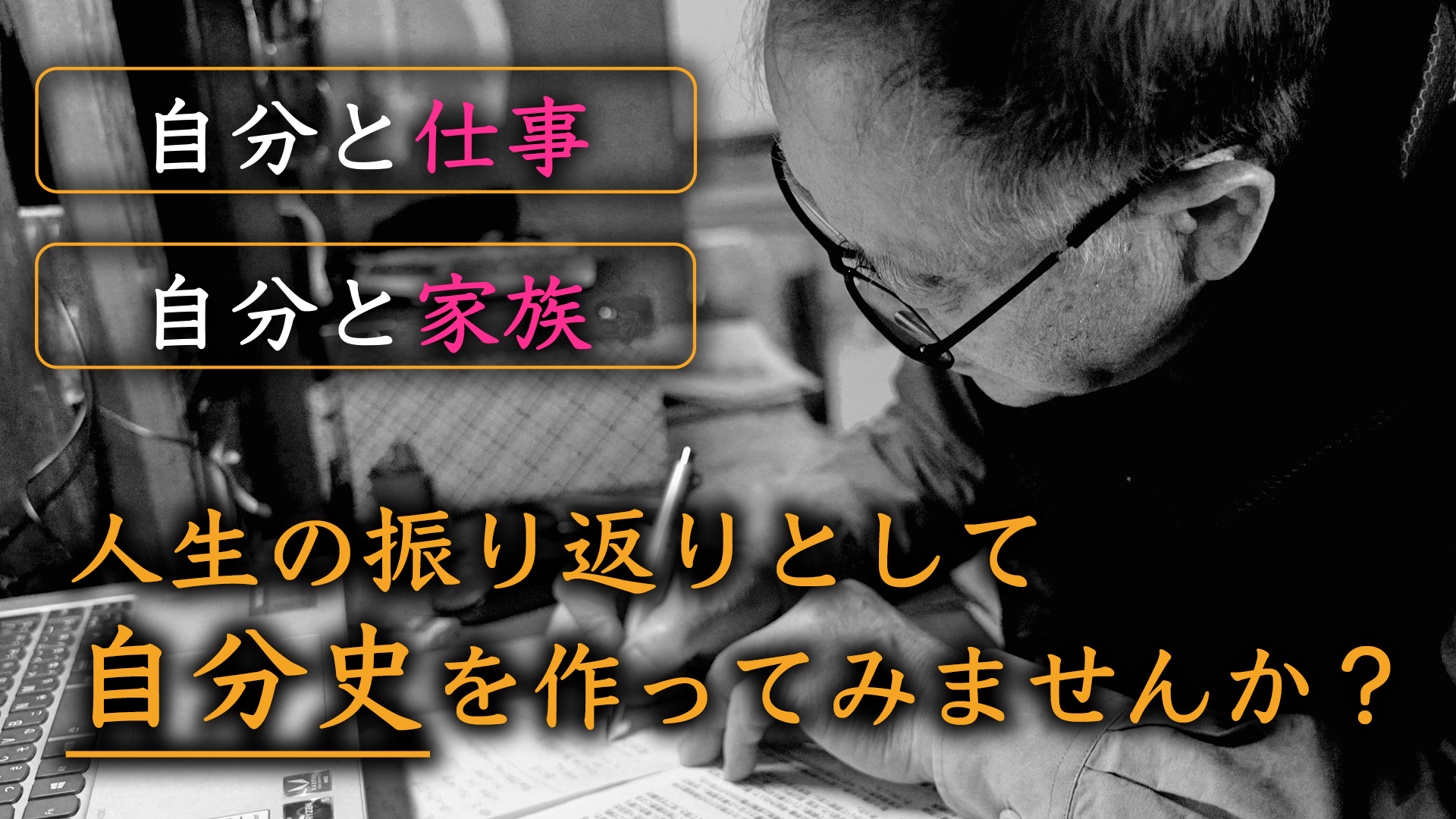


野村 和寿
3/31/2018 | Permalink
符牒「ツクバヤマハレ」情報ありがとうございました。ぼくははじめてこの情報を知ることが出来ました。
同じく符牒「ニシノカゼハレ」はご存じでしょうか? 1941年12月 ヨーロッパの公使館で、在留邦人にかねてから伝えられていた日英開戦の暗号だそうです。日本からのラジオで盛んに伝えられたといいます。(桑木務著『大戦下の欧州留学生活 ある日独交換学生の回想』より)著者はこの日本からの放送をフィンランド・ヘルシンキで聴取。第2次大戦下のドイツ・フライブルク・ベルリンでハイデッカー哲学を学び、フィンランド・ヘルシンキ大学で日本の思想文化教えていました。
西室 建
4/1/2018 | Permalink
「ニシノカゼハレ」
いや、知りませんでした。
これラジオで流されたのですか。在留邦人に伝えられていたとすると当然バレてたでしょうねぇ。
野村 和寿
4/2/2018 | Permalink
12月7日の日曜日は朝から猛烈な吹雪。夕方6時半からフィンランド人の5人の客を招いていた。日本からのラジオが「ニシノカゼハレ」を盛んに繰り返す。かねて公使館でひそかに教えられていた日英開戦の暗号である。客の一人が日本海軍機がハワイを爆撃したという。とくに鈍感になったわけではないが、なんだか眉唾ものという気持ちが先立って平然とパーティを続けていた。
翌日12月8日の新聞は日英米戦争の記事で埋まっている。このままでは地球がパンクするのではないか、そうすると日本は・・・と思うとバンザイ、バンザイと連呼するわけには行かない。とにかく大変なことになった。それが北欧の一角での感想であった。
「大戦下の欧州留学生活 桑木務著 中公新書1981年」より 筆者は1941年12月ヘルシンキで日本学を教える教授でした。
西室 建
4/2/2018 | Permalink
国内には『米英と戦闘状態に入り』と報道し外務省はラジオで邦人用にその「ニシノカゼハレ」を流したのでしょう。
その桑原先生、終戦までどうされていたのですか?
野村 和寿
4/3/2018 | Permalink
桑木氏の経歴は興味深いです。もともと1937年の日独交換留学生にて渡独、ハイデッカー教授のもとで、フライブルク大学で哲学を学び、1941年新設された友好国だったフィンランド・ヘルシンキにて「日本思想史」を教授。1941-44年はドイツとフィンランドを行き来していて、その記述はなかなかに興味深かったです。ところが1944年フィンランドが、対ソ戦で降伏を受け、シベリア鉄道経由にて帰国、1945年4月海軍軍属としてシンガポール着任、ドイツ降伏に伴うドイツ潜水艦の接収業務を行い、1945年8月終戦の詔勅以降、英軍との現地での交渉に携わり1946年7月にやっと帰国しています。前書「大戦下の欧州留学生ある日独交換学生の回想」は1981年の回想のために、あまり緊迫感はないのですが、愛文書林から2001年に刊行された「終戦のあと始末」という本には、シンガポールの対英国交渉のことの詳細がかかれているとのことなんですが、ぼくは、まだ、現物入手できていなくて、上記のヘルシンキ以降の記述は、又聞きを書き記しただけにとどまります。戦後は学究生活に戻られ、ハイデッカー哲学の第一人者だった模様。この人とても人に好まれやすい性格のようで、ドイツ人、英国交渉の英国人もたくさんの友人と戦後も交流があったとのことです。
西室 建
4/3/2018 | Permalink
あの『存在と時間』の翻訳者だったとは!気が付きませんでした。
行く先々で敗戦処理をした人とは。
1945年の4月の時点で良くシンガポールまでたどり着いたものです。
それだけでも随分『徳』のあった人でしょうね。
西室 建
2/18/2019 | Permalink
迂闊なことにやはり連合艦隊への攻撃中止暗号は「トネカワクダレ」が正しいようです。
「ツクバヤマハレ」はマレー上陸作戦中の陸軍へのものらしい。