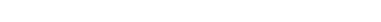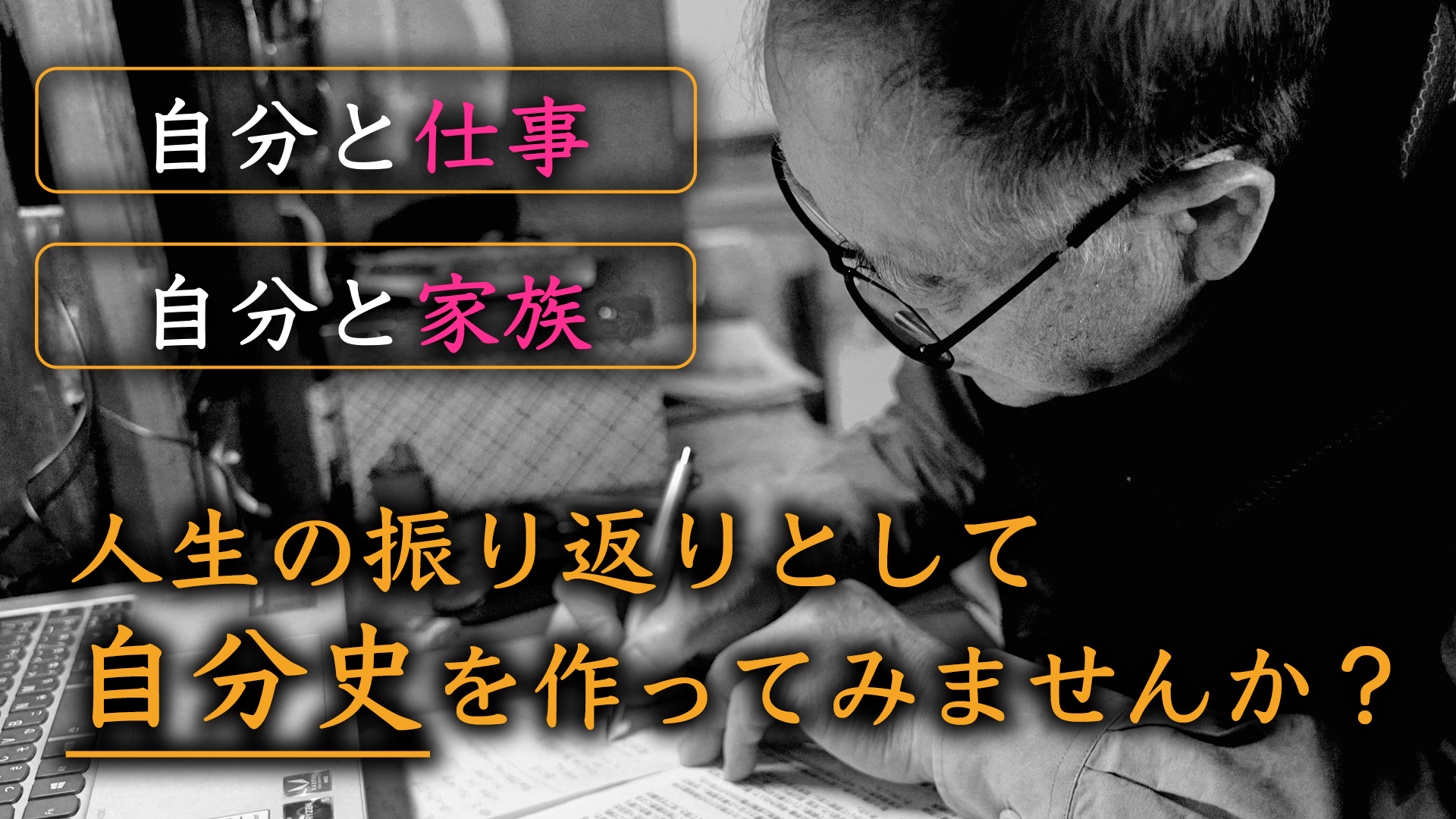異説『死のう団事件』Ⅱ
2023 DEC 3 16:16:25 pm by 西 牟呂雄

一時は千人ほどに膨れ上がった教団だったが、騒ぎのためにその後は50人程にまで減ってしまった。だが、残ったメンバーは桜堂に強く心酔する若い者で、その結束は強くなった。無論丈太郎もその一人である。
そしの丈太郎達から、より強力に布教を推進するにはどうすればいいかという議論が沸き起こって来た。青年が中心になって桜堂の親衛隊ともいえるグループは今後の布教に邁進するというのである。そして例の『死のう!死のう!死のう!』を唱えているうちに頭に血が上り結盟書に血判を押した。
時はテロが横行する不穏な風が一部には流れていた。前年2月、血盟団事件で大蔵大臣井上準之助と三井の團琢磨が暗殺される。5月には海軍将校による5・15事件が起きていた。
血盟団事件の中心人物である井上日召はやはり日蓮宗の信者であった。日蓮宗系では創価学会が立ち上がり、後に不敬罪並びに治安維持法で特高警察から弾圧される。大本教の出口王仁三郎が二度目に投獄されるのもこのころの出来事である。
左派運動に対する締め付けも厳しくなっていたが、同時に宗教系右派への取り締まりも強化されていたのである。
特に労働者の多い京浜工業地帯が広がる神奈川県の特高警察、通称『鬼のカナトク』の取り組みは勇名をはせていた。
桜堂は当初青年党の動きをやや引き気味に見ていたが、丈太郎達に突き上げられるように『殉教千里行』を実行することになった。青年党員28人(内数名は女性)は白い羽織に黒袴、鉢巻きを締めるという異様ないで立ちで、まずは鶴岡八幡宮を目指して旅立つ。家族を捨て仕事も捨て生還も期さない、という覚悟だったが、計画は未熟そのものである。
異様な風袋は丈太郎の発案で、さらに太鼓を叩きながら『我が祖国にために、死のう!』をやるのだから、目立つを通り越して不気味なのだ。警察に通報された。
そして葉山のあたりで野宿をしようとしていたところを一網打尽にされたのだった。更に『カナトク』は過剰反応し、非常呼集をかけて数十か所にガサ入れをかけた。
鶴岡八幡宮で落ち合おうとしていた桜堂は翌日蒲田署に出頭したが、事態が呑み込めておらず、いつもの説法をして帰ってしまった。『カナトク』の思惑を図りかねていた。
カナトクはこの騒ぎを事件とし、読み筋をテロの企てと見立てた。既に起こってしまったテロ、特に血盟団事件のような凶悪なテロを未然に防いだという手柄を立てたい意思が働いたのである。
そして、当然のことながら何も知らない青年部の連中を残虐な拷問にかけた。それは文字にするのもはばかられるすさまじいもので、既に小林多喜二は特高の拷問により死に至っている。中でも数人いた女性信者へは性的嫌がらせも執拗に行われ、ある女子医専に通っていた娘とその妹は精神に異常をきたした。
しかし、本当に何も知らないのであるから白状しようもない。耐えかねた2~3人が、その通りです、と肯定して信仰を捨てただけで、桜堂ほか5人以外は釈放された。ただその5人の中に何故か丈太郎は入っていなかった。
焦ったカナトクはリークを始める。新聞各紙に煽動的な記事が出だす。『西園寺公暗殺を計画』『増上寺を焼き討か』『好色漢の盟主桜堂』このうち、実際に計画になりかけたのは増上寺焼き討ちであるが、事前に桜堂の知るところとなり中止させられていた。この一連のリーク記事で、マスコミは彼らのお題目から教団を『死のう団』と呼ぶようになった。
事件は不思議な方向に進んでいく。人数激減により壊滅されそうになった教団は、何とカナトクの課長以下十数人を人権蹂躙・不法監禁・暴行障害で横浜検事局に告訴したのである。告訴したのは盟主桜堂と精神錯乱に陥った女子医専生徒今井千代の名前もあった。丈太郎の入知恵だった。
丈太郎は相変わらず教団に留まっていたが、なぜかほかの信者のような生々しい拷問の跡がない。例の割腹のパフォーマンスのミミズ腫れが醜く盛り上がり、気味悪がった特高が早めに放り出したと言うのだが。
特高警察を告訴するなど前代未聞、これもまた耳目を集めることとなった。それも今度は新聞の論調が変わって来た。
『裸女に火の拷問 姉は狂い妹も青春空し』
見出しからしておどろおどろしい。
1930年代の世界大恐慌の煽りを食ってダメージを受けた日本経済は、さらにタイミングの悪かった金解禁により落ち込み、巷に失業者の溢れる世相と相まって民衆の怒りがマグマのようにせりあがって来ていた時期である。高橋是清のインフレ政策で多少持ち直してきたとはいえ、格差は今日の比ではない。民衆の怒りがテロの形を採ると、治安当局も苛烈な弾圧をエスカレートさせたのだった。
告訴を受けた横浜検事局の検事正が実態を知り『警察の恥』と言い、それを知った新聞記者も大いに憤慨していった。すると今度は告訴を取り下げろ、と怪しげな男が教団を恫喝する、特高の尾行がつく、会員への嫌がらせが続く。それでも屈しないと、世論におもねったのか、今度は懐柔しようとした。
ついに神奈川県警察部長の相川は、賠償金・慰謝料を負担し、日蓮会を今後は支援する、とまで申し入れてきた。『死のう団は何等国法に触れることなき熱烈なる革新的宗教団体なりと認む』という自筆文書を携えて、である。桜堂はこれに、県警から報道機関へ出された文書に署名・押印することを加えるよう要望した。ところがこの交渉に期間に告訴を受け調査していた地検の検事正は更迭され、告訴は事実上店晒しにされていたのである。
3月24日付けで作成された文書が取り交わされる日に、県警側が用意した席にはビールが持ち込まれいざ手打ち、となるはずだったが、丈太郎の叫び声がブチ壊した。
『筆跡が違ってるじゃないか!』
桜堂は青ざめた。相川部長は作り笑いを浮かべとりなそうとしたものの、座は凍りつきビールは無駄になった。
半年後に衝撃的な事態となる。取り調べに当たったカナトクの主任が鎌倉山中にて割腹自殺を遂げた。遺書には自分の退職金を、拷問を受けた女子医専の学生に渡すようしたためられていた。白い羽織に黒袴、教団が逮捕されたときの装束である。新聞各紙は拷問の責任を執ったものと報じた。実はこの主任はひそかに教団を訪ね、自身が上司からテロリストであるという報告を書かされ梯子を外された、おまけに責任を執って退職を勧告されている、と自白していた。
その頃から示談金は千円から二千円に上がったものの交渉は進まない。相川部長は内務省保安課長に栄転する。そして横浜地検は特高課員の不起訴を決める。桜堂はツテを辿って政友会の久山知之を頼り、帝国議会で特高の拷問につき質問させるに至った。
今度は警察サイドが態度を硬化させ、残ったわずかな信者を徹底した行動監視下に置く。背後に重大事件である2・26の暴発があったためである。治安当局は本気になったともいえる。このような草の根の運動が大きな力を持ってしまえばどうなるのか、計りかねるとともにともすれば血気に同情的な世論を気にしたためであろう。逼塞状況を打破するという大きなうねりが世相を暗くし、その後冷静な判断を失うのは後世の我々だから知りうるのであり、この時点では上も下も右も左も不安にかられたヒステリーだったのである。
ついに警視庁は全信者の動向を監視しはじめ、各自宅にガサ入れを行い会館には警官が常駐するようにエスカレートした。、
教団は壊滅寸前で桜堂の体調も悪化する中、「餓死殉教の行」に突入する。会館に一歩でも外部者が入れば即刻集団自決する、と籠城した。食料もなくわずかな飴玉と塩のみでひたすら『死のう、死のう、死のう』を唱え、万が一に備え8千人の致死量の青酸カリまで調達した異常さである。発案はまたしても丈太郎だった。
結局「餓死殉教の行」は遺体引き取り予定者の死亡により中断せざるを得なかった。
昭和12年2月某日。宮城前広場・国会議事堂正面・外務次官邸玄関脇・警視庁正面玄関ホール・内務省3階にてほぼ同時に『死のう、死のう、死のう』と叫びながらビラをまいた男が短刀で腹を掻き切り血まみれになった。
ただし、短刀には丈太郎が考案した鋏木の細工がしてあったため、全員絶命することはなかった。桜堂が死に至るのを禁じたからである。ところが最側近の丈太郎は日蓮会館には姿を見せなくなって、この割腹騒ぎには加わっていなかった。
その一月後には桜堂が結核をこじらせて死亡するともはや教団は体をなさなくなって消滅する。最後まで残った信者は後追い自殺を始めた。女性信者は一人が青酸カリを飲み、別の二人は猫いらずを飲んで自殺。警視庁で腹を切った男も青酸カリで死に、宮城前広場で切腹した男は東京湾横断の船から「死のう」と叫びながら海に飛び込んだ。
内務省特高課長の手島龍蔵は料亭の一室で一組の男女と対していた。
『原部(ばらべ)君、お疲れであった。首尾よくやってくれた』
『課長、恐れ入ります。ただ奴ら本当に何も企ててはいませんでした。後味は悪いですな』
『ウム。だがああいうのは一旦弾みがつくとどう転ぶかわからん。血盟団の連中だってまじめな帝大生だったし5・15の海軍や2・26の連中だって初めから要人暗殺を考えていた訳ではなかった』
『軍人さん達がやったのはそれを煽ったお偉いさんがいたんでしょう。奴らは民間もいいところでしたよ』
『原部君。だが君の煽りに乗りかかったことも事実だろう』
『それは・・・。私らこれからどうしたらいいのですか』
『心配するな。君には大陸で働いてもらう。満鉄調査部のポストを用意した』
『ほう。いよいよ満州工作ですか』
『狭い日本は飽きたろう。向こうでは甘粕さんの指示を仰げ』
『特高さんの次は憲兵さんですか。まあいいや。今後とも宜しく』
顔を上げると男は丈太郎。女は立花須磨子であった。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
異説『死のう団事件』Ⅰ
2023 NOV 30 23:23:05 pm by 西 牟呂雄

大正末期、蒲田・川崎といった京浜工業地帯の駅頭に一人の青年僧が辻立ちの説法をしていた。
『皆さんが信じているものは何ですか。困った時にはいうでしょう、神様仏様と。ではその神様とは何でしょう』
慌ただしく行きかうのは汚れた服装に身を包んで疲れきった、或いはこれからの夜勤労働に行く、暗い表情のいわゆる職工達で、そんな説法には目もくれずに足早に帰宅、または出勤の歩みを進めるのみだ。
人々の流れが引いた後、夕暮れの中を青年は『不惜身命、不惜身命』と合掌して唱えると長時間の辻立ちにも拘らず満足気にスタスタとどこかへと帰って行った。
青年はまだ20代らしく、どうもこの辻立ちを修行の一環と捉えているようで、飽きもせず来る日も来る日もどこかの駅頭に立ち、感心を示さない労働者の前で説法するのである。
青年の名は江川桜堂。熱心な日蓮宗の信者であった。都下蒲田村の地主の次男坊で極真面目でおとなしい男だ。ただ、少し変わっている、妄想癖があり幾つになっても子供っぽかった。
日蓮宗は時に過激な信仰を促すため、常に内部に分裂の遠心力が働く傾向がある。それは今日でも同じで、いくつもの団体が緊張感を孕んでいる。明治・大正を通じても深刻な対立はあり、教義の研究と宗門統合の布教道場としてその名も『統一閣』という施設を浅草の地に建設した。桜堂はそこで本多日生上人の元で益々研鑽に没頭し、遂には日蓮の経典全てを読破する。
その後、冒頭の辻説法となるのだがしばらくして関東大震災で被災する。幸い生き残ったものの、あまりの惨状を見聞きしているうちに何かが弾けた。
瓦礫の山、夥しい死体、途方に暮れる人々。京浜地区は東京下町のような火災による被害は少なかったものの、桜堂もしばらくは茫然自失に陥り、法華経をひたすら唱えてしのいだ。
ようやく、復興の兆しが見えた頃の蒲田の駅頭に立った時点では、説法は様変わりしていた。
『かの惨状が、ただ自然現象だけだとお思いか。さすれば日頃先祖参りをしていた寺、願をかけて祈った神社、こういったところに祀られていた仏や神は何をしてくれましたか。荒れ狂う大地をいさめることもなく惨状を招き、その後何も手を差し伸べてくれません。それは誠の仏の教えを守らなかったからに他なりません』
こうして説き起こし、日蓮上人はこれを見通していて国難来たると警鐘を鳴らしていたのだ、と訴えた。既成宗派を呪い攻撃し、次第に醸成しつつある国家神道を否定した。
すると、次第に桜堂の辻説法に聞き入り、中にはこの強烈な主張に感化され従うものが出始めた。説法の最後に桜堂が合掌し『不惜身命、不惜身命、不惜しーんーみょーおーー』と唱えると一斉に唱和するのである。そしてそれを珍しそうに遠巻きにする群衆も増えていくのだった。
百人を超える信者が彼を取り巻き『盟主』と慕うようになると、道場のようなところが必要になり、蒲田の糀谷に簡素な家屋をしつらえて、そこを日蓮会館とし自分達は「日蓮会殉教衆青年党」を名乗った。ちなみにその建設費用は桜堂の父親にねだったもので、要するに世間知らずのお坊ちゃんである。
会館でのささやかな勉強会のような集まりに、一人の男が顔を出すようになった。やせ型で色は白く、キリッとした目つきが印象的な若い男で、底辺の労働者ばかりの他の連中とは身なりからして違い小ぎれいである。 教義にさほど熱心にも見えないのだが、呑み込みが早く桜堂も傍に置くようになっていった。男は丈太郎といったが、苗字を知る者はなく、住んでいる所も誰も知らなかった
そしてこの男、なかなかのアイデア・マンで色んなことを桜堂に提案しだした。説法の際にのぼり旗を立てて『不惜身命』と大書する、説法に合わせて笛や太鼓で拍子をとる、
更には『不惜身命』は仏語で難しいのでわかりやすくする、といったことを次々にやり始めた。その分かりやすくしたものが波紋を呼ぶ代物だった。
我が祖国の為めに、死なう
我が主義の為めに、死なう
我が宗教の為めに、死なう
我が盟主の為めに、死なう
我が同志の為めに、死なう
これでは自らカルト教団だと言って歩いているようなものである。
川崎駅頭で桜堂が激を飛ばすと、数百人の信者がのぼり旗をもって囲い、説法が終ると笛や太鼓で伴奏が始まり、独特の民謡調の節をつけて『わがーそこくーのたーめーに』と盟主が謡うと一斉に『しの~~う~』と唱和する様は異様でしかない。
この頃から桜堂の行動もおかしくなってくる。 池上本門寺で『クソ坊主ども』と喚いて暴れた姿が目撃された。
ある日、丈太郎が妙な木細工を持ち込んだ。短刀の鞘のような挟木で、これを使うと担当の刃先が5mm程度しか出ないから腹に突き立てても致命傷にならない。
さすがに桜堂は『死ぬことが目的ではない』とたしなめたが、神妙に手に取ってみる若い信者はいた。そしてある日、丈太郎がやってしまった。
某日、桜堂の説法には信者が20人程、聴衆は10人いるかいないか。説法が熱を帯び信者が興奮して「~~死のう,~~死のう、~~死のう」とやっていると、突如酔漢が前に進んで喚いた。
「じゃ、やって見せろ!そんなに死にたきゃサッサと死ねー」
桜堂は意に介さず『しかるに日蓮上人はこう申された』と続けたが、信者達は蒼白になってその酔っ払いを見つめた。
すると僧衣を纏っていた丈太郎がその男の前に立ちはだかり、スルスルと前を解いて短刀の鞘を払った。桜堂も説教を止めざるを得ない。静まり返ってしまったその刹那。『エーイ!』裂帛の気合とともに一直線に腹を裁いた。『ヒィー』と声を上げたのは絡んできた酔っ払いである。腰を抜かしていた。信者も聴衆の叫び声をあげた。丈太郎の腹から数珠玉のような血が噴き出し、やがて下帯を赤く染めていく。腰を抜かした酔っぱらいはバタバタと駆け寄り、大丈夫ですか大丈夫ですか、と助け起こした後に、次第に増えていく野次馬に向かって叫んだ。
『おーい、みんな。この人たちの話を聞いてくれ。オレが悪かった。この人達は本気だー。頼むから足を止めて話を聞けぇ』
丈太郎は信者に抱えられて行くのだが、勢いでやってしまった驚きと激痛に無様に喚きっぱなしであり、実にみっともなかった。『イテー!イテテテテ』と暴れるが、実のところ深さ数ミリの切り傷であった。例の鋏木の細工のお陰だ。簡単な手当てで傷は落ち着いたが、跡はミミズ腫れになって醜く残った。
ところがこの騒ぎで辻説法の聴衆は膨れ上がり、信者も千人ほどにハネ上がった。日蓮会館には様々な人間が出入りするようになった。
奇妙な女が頻繁にやってくるようになった。美形である。つつましやかな和装であるが、仕草や振る舞いに色気があり自然と信者の目を引いた。名前は立花須磨子といった。ところがこの女、初めのうちは会館の研修会に出てきたが、どうも教義にはあまり興味は無いようだがやたらと盟主である桜堂に近づきたがる。女性信者は数は多くはなかったが、学生・女工・家事見習いの者が年齢に関係なくいた。その中で須磨子はあか抜けた風貌で飛び切り目立った。男達は好奇の目でみたが、女たちはあからさまに白眼視したのだ。それを尻目に辻立ちに現れては帰りに桜堂に寄り添う、会館から外に連れ出そうと声をかける。一部は警戒するようになった。
丈太郎はある日、桜堂と二人になった折に切り出した。
『盟主。あの女マズいですよ。あんまり盟主の話も聞いてないみたいだし、やたらと色目を使いやがる。叩き出しましょうか』
『むっ、それはいかがなものか。確かに目に余る部分もあるのだが、いきなり叩き出すとはなんとも慈悲のない。よし、私から言って聞かせよう』
後日、桜堂は丈太郎を伴って須磨子の家を訪ねた。家は蒲田の近くのしもた屋のたたずまいで、須磨子は一人暮らしだった。
『おや、これは盟主様。わざわざお越しですか。今、お茶を入れます』
と言いながら、傍らの丈太郎を認めると露骨にイヤな顔をした。相対する形で桜堂が須磨子に語り掛けた。
『あなたは何故会館に来ているのですか』
『はぁ、まっ、盟主様の説法をもっと間近にきいてみたり、どなたかにお話を聞いていただくとか』
『私の説法が聞きたいと言うにしてはあまり熱心さがないように思う』
須磨子の目に見る見るうちに涙が浮かんだ。
『盟主様・・・、わたくしは』
と言うと、身の上を語りだした。
話し始めると止まらなかった。
北関東の小作農家の生まれ、子だくさんゆえ小学校卒業後東京に奉公に出たところ、それなりの器量良しを妬まれて壮絶な苛めにあう、一方で家の主人からは強姦まがいに体を奪われ、自分のせいでもないのにおかみさんから半殺しにされて放り出される。
流れ流れてどん底に落ちた遊郭で人入れ稼業の親方に見初められて愛人となる。いかに淋しい身の上なのかを涙ながらに訴えた。刮目して聞き入っていた桜堂は膝頭に何かが当たるのを感じて目を開くと、須磨子が顔を埋めてきたのだ。慌てて振り向くと丈太郎はいない。いつのまにか姿を消していた。
『これ、よく分かった。よーくわかった。これからも会館にきて心静かに南無妙法蓮華経を唱えるがよい』
と諭し、這う這うの体で辞した。
ところがこのことが人知れず噂となりとんでもない事件を引き起こす。
『インチキ坊主出てこい!』
『色狂いの生臭野郎!』
日蓮会館前に屈強の男達がスコップ・ツルハシを担いで大声を上げている。信者達は怯えて雨戸まで締め切ってしまった。一段と人相の悪い小柄だがガッシリした男が会館の引き戸の前に立って声を上げる。
『江川桜堂!人の女に手を出してただですむと思ってんのか!こらァ!』
会館内は物音ひとつ聞こえなかったが、ガラガラと引き戸が開いて青年が出てきた、丈太郎だった。
『何だテメーは』
『大声で話さないでください』
『桜堂を出しやがれ。この落とし前はどうつけてくれるんだ』
『盟主はあなたのかんぐりは見当違いだと申しています』
『だったら顔出しやがれ。この変態坊主共』
『我々はそのような者ではない。ただひたすらに法華経に殉ずる。不惜身命ー!我が祖国の為めに、死なう。我が主義の為めに、死なう、我が宗教の為めに、死なう』
そう言いながら法衣を脱ぎだし、不気味に醜くミミズ腫れの跡が残った腹を曝け出した。対峙していた男は血相を変えて後ずさりする。『我が盟主の為めに、死なう。我が同志の為めに、死なう』と唱えながら例の短刀を持ち出すとサッと腹を一文字に滑らせた。たちまち鮮血が流れ出す。
対峙していた男は『ウwッ』と怯むと後ずさりし、不逞の輩達をうながして『気味の悪いやつらだ』と引いて行った。丈太郎はというと不気味な笑みを浮かべながら会館に戻る。どうやら浅く捌くコツのようなものがあるようで、前回ほど見苦しく暴れなかった。
その場はそれで納まったものの、騒動に嫌気のさした者や盟主の乱淫を信じた女達は教団から離れて行ってしまった。
つづく
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
君は今 駒形あたり 時鳥(ほととぎす)
2023 APR 8 22:22:16 pm by 西 牟呂雄

何といじらしい。尚且つせつないというか可愛らしいというか。
子規によって近代俳句が確立されるおよそ200年も前に発せられた句だが、瑞々しい語感は少しも古びていない。
さぞかし高貴な方の作品かと思いきや、作者は吉原の花魁である。花魁といってもそこらの場末の酌婦・夜鷹とは訳が違う。大江戸ワンダー・ランド吉原の三浦屋に代々伝わる大名跡の二代目高尾太夫の作である。
高尾太夫ともなれば、容姿端麗で教養高く書も良くするスーパー遊女。そこらのチンピラなど相手にもされないまさに高嶺の花と言えよう。かの二代目を寵愛したのは仙台伊達藩主、伊達家十九代綱宗公だった。
花魁は筋のいい情夫(いろ・贔屓筋のこと)には惚れたふり。提題の句は綱宗公に送ったとされる。
ところが、色事は奥が深い。このような美しい句を送っておいても心は違った。隅田川の楼船上にて公の勘気にふれ、吊り斬りに首を刎ねられた。すると後日、その首が日本橋川と隅田川の合流するところに骸が流れ着き。事情を知る人々は大いに同情し、社を建て「高尾大明神」を祀り手厚く葬った。
先日、人込みを避けて葉桜を楽しみながら大川端を散策していて、この高尾稲荷を見つけた。
ビルの一角に嵌め込まれるようにひっそりと佇んでいた。
場所は確かに日本橋川と隅田川の合流する豊海橋のほとりである。
どうやら以前は別のところだったのが、Bー29の無差別爆撃で社殿が燃えてしまいここに再建された。
その際、焼け跡を整地する際に地面を掘ったところ頭蓋骨が出て、これは本物だとご神体として安置した。まずほかに見られないケースである。
恐る恐る、小さな社を覗いたが、おそらく別の場所で大切にされているのだろう。よく見えなかった。
この伊達綱宗は仙台藩主として三代目なのだが、酒色に溺れてどうしようもない殿様とされている。どうやら、親族の政治介入や家臣団の対立で嫌気がさしておかしくなり、「無作法の儀が上聞に達したため、逼塞を命じる」と21才で隠居させられた。おまけに幼い息子が家督を継いだことがのちの伊達騒動の遠因となるなど、ろくでもない殿様だったらしい。
しかしながら隠居後は風流人として和歌、書、蒔絵などを良くし、特に絵は狩野探幽に師事して優れたものを残した。
上記高尾太夫の惨殺も読本や芝居で広まった俗説だとか。実際には旗本の島田利直に身請けされ、死去した後は埼玉県坂戸の永源寺に葬られたというのだ。
すると、祭られている髑髏は一体誰なのか。
まさか何でもない土座衛門の骸骨ではあるまいな、と思いながらお賽銭を投げて鈴を鳴らした。
さて、天気もいいしこのまま浅草橋まで行って神田川の合流を観て行こうか、と歩き出したところこんなのがあった。影がはいってしまい見づらいが旧日銀の跡地の碑である。
かの渋沢栄一が近代資本主義の第一歩を踏み出した所かと、感慨深い。
桜は過ぎたが、新緑の中を散策するのにお勧めのコースです。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
生きすぎたるや二十三 八幡引けは取らるまい
2022 SEP 11 0:00:26 am by 西 牟呂雄

天下分け目の関ヶ原で東軍が勝利した後、大阪の陣までの間は、全国で大地震が起こり世の中は騒然としていた。慶長年間の江戸では、家康の天下普請で町中が埃を巻き上げている中で、ひときわ派手な拵えで闊歩する人足元締がいた。
異装の男伊達を看板に徒党を組んでは暴れまわる傾奇者(かぶきもの)。大鳥逸平、通り名を大鳥居の一兵衛と言った。するとそれに従うバカ共も大風嵐之助、天狗魔右衛門、風吹藪右衛門と調子に乗った名乗りを上げている。
武州下原の刀工に打たせた三尺八寸の厳物造太刀(いかものつくりのたち)には、その銘に「廿五まで生き過ぎたりや一兵衛」と刻んだ。いかにもヒマを持て余した都市の仇花の刹那的な心情が滲み出ている。25年の人生は長生きのし過ぎということか。せっかく手に入れた平和が退屈なのだろう。約半世紀後に現れる六方組と呼ばれる旗本奴の先駆けである。
最もこの時代の死生観は現代の我々とは違っていて当然だ。ましてやついちょっと前まで戦乱が続いていたのだ。平和な時代の今よりも命は遥かに軽い。となれば破れかぶれの潔さが分からんでもない。
大鳥逸平、もともとは幕臣本田信勝の草履取りだった。身持ちが悪く逃げ出したのちはなぜか佐渡の金山奉行かの大久保長安の元、大久保信濃の小者になりおおせたが長続きしない。弓・鉄砲・槍と武芸百般に通じる器用さも持ち合わせていた。まぁ喧嘩には強い。
江戸に出てきて人足元締めを稼業にするころには、今で言うチーマーとか族、半グレの頭として300人を超す配下を束ねていた。
ある時、旗本柴山正次が家僕を成敗した。するとこの奉公人の一味が柴山を切り殺すという事件を起こした。実際の下手人を詮議したところ、裏で糸を引いていたのは大鳥居一兵衛と知れた。ところが当の一兵衛は行方をくらまして見つからない。一計を案じた町奉行・内藤平左衛門は武蔵国多摩郡の高幡不動の春の縁日に合わせて相撲の興行を開く。すると相撲自慢の一兵衛は間抜けにも姿を現し、大捕り物の末に捕縛された。
当時のこと故、厳しい拷問を受けたが口を割らず、本多正信・土屋重成といった大物までが駆り出されたが、自白しないまま一党300人まとめて処刑される。享年25才。銘に彫り込んだ年齢で果てて見せた。
ところで、この『生きすぎたるや』という言い回しは当時の流行り言葉だったようである。
慶長九年、太閤秀吉没後の七回忌に執り行われた豊国臨時大祭礼の喧騒を描いた屏風が名古屋の徳川美術館に所蔵されている。その中に、ヨタ者同士が抜刀して対峙する喧嘩の場面がある。このもろ肌脱ぎの大兵の朱鞘には、金文字で『生きすぎたるや二十三 八幡引けは取らるまい』と書かれている。
先行きの見えない不安。どうにもならない焦燥感。目的も見えずすることもない。ただ人の集まるところでは弾けるように異装に凝っては男伊達を競って暴れる。
この破れかぶれ感、筆者も思い当たらないでもない。しかしながら齢古希に近づかんとする前期高齢者となってみれば、これ等の振る舞いはおろかの極みでありで、何が23だ25だ、どうせならお前達もう5年バカを続けてもいいんじゃないか、と言ってやりたい。
チンピラというのは目標も何もないから、喧嘩沙汰でもなければ退屈でヒマを持て余す。そのうちに相手にされなくなって気が付くともういけない。
まっ今でもそういう輩の種は尽きませんがね。そこから余程才能があればバサラ者になって・・・、もういいや。筆者も危ないところだった。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
逆転 江戸城総攻撃 後編
2021 SEP 27 0:00:26 am by 西 牟呂雄

勝海舟が帰った後、西郷はしばし目を閉じて思料していた。
『夕餉の支度が整いもした』
声がかかっても動かない。心配した側近の村田新八・中村半次郎らが傍らに来て聞いた。
『吉之助さぁ、どげしたとでごわすか』
西郷はその声に即されるよう、カッと目を開き大声を発した。
『夜襲で来もす!勝先生の最期の言葉で分かりもした。戦支度せい。こっちから行きもんそ』
そう言うと、飯椀にお茶をぶちかけ、グーッと一口で飲み込んでしまった。
夜襲は静かに迅速を以て成すべし。しかしながら元々翌日の総攻撃に興奮して酒まで飲んだ官軍は笑う者・歌う者・大声で話す者でごったがえしていた。そこへ各小隊長の「非常呼集ー!」の声がかかると、一瞬静寂が流れた。
大隊長の村田新八が訓示しようと壇上に登って各隊に対面したその刹那、「ドーン!」「ドーン!」「ドーン!」と立て続けに砲撃音の後、地響きとともに官軍本営に猛烈な火の手が上がった。
『しもた!一足おそか』
西郷が叫んだ時には次々と被弾し、全軍が浮足立つ。
西郷は薩摩人の気性を知り抜いている。劣勢に立つと人が変わったように腰砕けになることを。品川沖に停泊していた開陽丸以下、幕府艦隊の一斉砲撃である。開陽丸のクルップ砲の射程は4kmである。
後ろから不意打ちをされた格好で、西郷は直ちに指示した。
『半次郎!先手をとられっした。反撃すっとじゃ』
『心得っごわす。小銃隊!オイに続けー!』
半次郎は抜刀すると配下の小隊長を従え、未だに動きのない幕府側を見据えて進軍(というより切り込み)を開始した。既に戦場となっているのだ。
前衛が幕軍の防衛線に突っ込んでいく。こうなったら静かにも何もない。一斉に鬨の声を上げた。対する幕府歩兵隊のシャスポー銃が火を噴き、半次郎の左右を駆けていた薩摩藩士がなぎ倒された。しかしそれしきのことでは怯まない。
『チェストー!』と独特の声を上げて敵陣に殺到すると手当たり次第に切りつけた。
官軍の先鋒の多くは薩摩兵である。彼らの突進力は凄まじく、潮が引くように幕軍は後退していった。品川沖からの砲撃音は既に止んでいた。
江戸城に構えていた慶喜の元に次々に伝令が来る。
『ご注進ー!申し上げます。敵はいよいよ新橋にまで迫りつつありー!』
それを聞いた慶喜はニヤリと笑った。既に戦闘は3時間を超えている。
『よし。正面から来たな。高橋、遊撃隊を前進させよ。そして浜御殿の新徴組にもかからせよ』
高橋とは幕末三舟(勝海舟・山岡鉄舟・高橋泥舟)と謳われた幕臣で、槍(忍心流)の達人である。いわば将軍の親衛隊ともいえる洋式陸軍の遊撃隊を率いていた。新徴組は清川八郎が集めた浪士隊の分派で、庄内藩預かりの江戸の治安部隊。あの清川八郎が浪士隊上洛後に江戸に下向した際、一緒に帰ってきた連中で、この時に京都に残ったのが新撰組だ。慶喜は勝機と見て虎の子の精鋭部隊を投入し背水の陣を敷いたことになる。
『上様、どちらへ』
『これより桜田門を出て直接指揮を執る。各々覚悟致せ』
江戸城開闢以来、前代未聞の将軍出陣に一斉にほら貝が吹かれた。
官軍にしてみれば、正確な砲撃を撃ちこまれたために敵陣に突撃すると、途端に歩兵部隊の一列横隊一斉射撃を浴びせられ、その侵攻は止まった。と、同時に新徴組に側面を突かれ、不意打ちを喰った。
『こいはまずか、ええい退け、戻るッと。吉之助さぁ守らんな』
半次郎は官軍本営に駆け込んだ。
『吉之助さぁ、思いの外の押されっごわす。逃げったもんせ。オイは殿(しんがり)を務め、捨てがまりやいもす』
『半次郎。背後からも会津と桑名が寄せちょう。武州を西に上って土佐の迅衝隊と合流せい。ステがまりィ?くれぐれも早まんな』
捨てがまり。古くから薩摩に伝わる退却の際の戦法である。十名程の決死隊が全滅するまで追っ手を食い止め、その隙に本隊が進むという十死零生の凄まじい戦法で、有名なのは関ケ原の家康本陣に切り込んだ後の撤退だ。その際は300人が80人に減って薩摩にたどり着く。
半次郎の目の前に背の高い新徴組隊士が突っ込んできた。咄嗟に身を翻らせトンボの構えで対峙すると、敵は正眼に構えた。こんな所で切り合いをしている場合ではないが、ただならぬ殺気に思いきり打ち込んだが手ごたえがない。ヒラリと体を交わされ逆に胸元目がけての電光の突きが飛んできてそれを払った。腕が立つ、半次郎の血が騒いだ。
『おはん、かなりの腕と見た。尋常に勝負したかが今はちょっ手が離せん。あいすまんこつがここは一旦預けったもんせ。大将ば守らんならん。オイは薩摩藩士、中村半次郎ごわす。お名前聞かせたもんせ』
この火急の際に豪胆というかムシがいいというか、あまりの滑稽さに隊士もつい笑ってしまったようだった。
『新徴組、中沢琴』
『かたじけなか。これにてご免』
半次郎は駆けだしながら、今の甲高い声に引っかかるものを感じた。
「あれはおごじょではなかか」
中沢琴は新徴組に実態に在隊した美貌の女剣士だった。史実では新徴組の撤退に同行して庄内まで転戦、維新後は故郷の沼田に隠棲する。
西郷を囲みつつ官軍の大部隊が敗走しているうちに夜が明けつつあった。半次郎は次々に捨てがまりを指名する。
『弥助、隼人、十郎、五郎丸、信吾、小隊連れて捨てがまりじゃ』
『承知ごわす』
すべての薩摩武士はこの時のために胆力を練ったのであろう。嬉々として死地に赴く、笑みさえ浮かべて。
夜が明け切ってしまうと視界が効くようになる。幕軍歩兵部隊は当面の敵が退きつつあるので休みだしたところ、一人の高級指揮官が現れて叱咤激励し始めた。
『一合戦終わったつもりなら心得違いじゃ。朝敵の汚名を着たままですむと思うのか。覇権は関東にありと知らしめい』
各隊の指揮官が訝ってその声の先を見るや、飛び上がって土下座する。
『上様』
各々仰天して身構えるが、声の主である慶喜はサッサと歩を進めつつ言い放った。
『余に続け』
とんでもない事態になって全軍が慌てた。将軍は例のナポレオン三世から送られた洋装に身を固めている。総大将が護衛も付けずに行く後から勝海舟と山岡鉄舟が続く。「上様を先陣に立たすな!」と声を励ますと歩兵部隊は駆けだした。
慶喜がハッと身構えて右半身になり「エイッ」と右手を振り下ろした。グァッ、と断末魔の声がして、黒い影がのけぞって倒れた。慶喜、得意の手裏剣が官軍の残兵のとどめを刺したのだ。
『見よ、未だ戦い成就せず』
勝・山岡は真っ青になって歩兵隊を叱責した。
『馬鹿者!止めを刺さんかァ!』
一方その頃、板橋の中山道で対峙していた官軍と幕府軍の戦闘の火蓋が切られた。夜明けとともに『バタリオーン!アルト!』とフランス語の号令がかかる。
指揮を執るシャノワーヌ大尉に率いられ幕府・伝習隊が前進を開始した。シャノワーヌ大尉は幕府の招聘によりナポレオンⅢ世に派遣された軍事顧問団のリーダーで、後にフランスで陸軍大臣となる名将である。
対する官軍の中心は長州の奇兵隊だ。こちらも士気は高く退くことなどあり得ない。ガチンコの激突となった。だが一つ違う所がある。伝習隊には新設の砲兵隊があったのだ。当時の日本には砲兵戦術はまだなく、固定させてぶっ放すだけだった。それを指導し率いるのはシャノワーヌ大尉の盟友ブリュネ大尉、こちらも後にシャノワーヌ陸軍大臣の元で陸軍参謀総長となるエリートである。
ブリュネの指導は、初めは仰角45度で敵陣中央を砲撃し、次第に下げて前面近くを叩く。更に砲兵部隊を素早く前進させ、機動活用することによりダメージを拡大させるとともに、味方の歩兵の突撃には損傷を与えない、という近代用兵だ。そのためブリュネの部隊は重い青銅製四ポンド砲12門を運用する猛烈な訓練を受けていた。
前進の号令のすぐ後に、そのブリュネ大尉の砲が一斉に火を噴いた。轟音とともに奇兵隊は砕かれ吹っ飛んだ。その後4門3組が仰角を変えて縦横無尽の砲撃で、そこら中を焼き尽くす。
戦闘2時間、シャノワーヌ大尉は総大将の小栗に判断を仰いだ。
『コウヅケノスケサマ。ソウコウゲキデヨロシイデスカ』
『うむ。存分にかかれ』
伝習隊の銃剣突撃が始まった。奇兵隊も必死の防御をするが後方は砲撃により潰されてしまい、とても持ちこたえられるものではない。押されてさらに砲撃の餌食になっていく。幕軍の完勝であった。
江戸城本丸。集まった勝・山岡以下各方面の司令官・親藩大名、榎本海軍総裁等を前に慶喜は更なる命令を下した。依然洋装の軍服のままである。
『皆の者、よくやった。ご苦労であった』
『ははー』
『軍議である。さっさと面を上げよ。敗走した西郷や板垣はどうなった』
『いずれも相模まで下がっており、目下追討の追っ手を差し向けております』
答えたのは勝海舟であった。
『手ぬるい!遊撃隊も向かわせよ。合わせてあの土方に追い詰めさせるのじゃ。必ず二人の首を我が前にならべよ。榎本はおるか』
『釜次郎、御前に』
『官軍主力は関東に出払って居る。艦隊は伝習隊とともに再び大阪湾に移動し、都を制圧する。今度こそにわか官軍の化けの皮を剥いでやる。尚会津中将と桑名定敬、江戸の守りを固めよ』
『上様、下阪の指揮はだれが』
『うつけものー!余が自ら帝に拝謁し、朝敵の汚名を晴らすのじゃ。公家どもめ。こちらも寛永寺におわす輪王寺宮法親王に御動座いただき、菊と葵の旗を掲げて下阪する。錦旗何するものぞ』
官軍本隊はボロボロになり敗走。京都は主力が出払っている。開陽丸が大阪湾に着く頃には「幕軍優勢」の噂と共に日和見だった親藩は寝返って慶喜を先導するだろう。
このまま日本を割った戦を続けるか、はたまた寸止めにして妥協をするのか。
近代日本の夜明けは未だ遠く、行く末はそれぞれの胸先三寸にしか無いのだった。将軍慶喜・勝海舟・西郷隆盛の・・・明日はどっちだ!!!
おしまい
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
逆転 江戸城総攻撃 前編
2021 SEP 24 0:00:06 am by 西 牟呂雄

鳥羽・伏見での動乱の後、急遽江戸に帰ってきた徳川慶喜に、満面の怒りを込めて対峙しているのは勝海舟である、
『上様!何たる不始末!恐れながらこの勝、情けなさに腹も切れませぬ』
『やかましい!』
凄まじい怒声に思わず顔を上げた。
『いいか、ここからが勝負じゃ。そんなに戦がしたければタダではすまぬということを思い知らせてやる。何のために幕府歩兵部隊を無傷で江戸に連れ帰ったと思うのじゃ。小栗上野介を呼べ。そしてそちは榎本の艦隊を品川沖に集結させろ。それからエゲレスのパークスとメリケンのハリスに話をして、今後の商いをエサに中立を約束させよ。覇権は関東に有り』
勝は面食らった。意気消沈しているかと思った将軍慶喜は鬼の形相で言い放ったのだ。
『恐れながら。無傷の歩兵部隊とおっしゃいましたが、なぜ大阪城で籠城なさらなかったのでございましょうや』
『うつけ者!籠城すれば成程戦には負けないであろう。しかしどうする。その後上洛し御所に攻め込むのか。長州風情ではあるまいに、帝の庭先で暴れるつもりか』
『重ねて恐れながら。大阪城が炎上しても最後の一兵まで戦う、と仰せと聞きました』
『時間稼ぎじゃ。この江戸に先回りされたら我が方は後ろ盾を失う。薩長を上方に釘付けにするための方便に過ぎぬ。城受け取りはわが従兄弟、尾張慶勝。意は通じておる』
『恐れ入りましてござります』
『官軍は東海道・甲州街道・中山道を戦闘もなしに意気揚々と来るであろう。江戸府内に入る前に海と陸ですり潰してくれる。おォ、安房守(勝の事)。そこもと敵将西郷と親しかろう』
『ははー』
『山岡でも使って三田の薩摩屋敷までおびき寄せろ』
『といいますと』
『浜御殿(現在の浜離宮公園)から側面攻撃をかける。後ろからは品川沖に停泊させた榎本の幕府艦隊から砲撃する。その間、敵の敗走に備えて海路にて会津・桑名の精兵を移送し挟み撃ちにせよ。ただし外国人の居留する横浜は避ける』
『甲州街道・中山道からも押してきておりますが、いかがいたしましょう』
『甲州の方は街道沿いの諸隊をまとめ上げて甲府にて迎え撃て。官軍本隊はあくまで東海道を来る』
『そちらの指揮は』
『食い止めて膠着状態にしておけばいい。そうだな・・・。多摩か・・・・新選組を使え』
『局長の近藤は負傷しておりますが』
『副長の薄気味悪い男がいるじゃろう。確か多摩出身の』
『土方歳三でしょうや』
『そいつじゃ。そ奴にやらせよ。地の利にも明るかろう』
『中山道方面は』
『伝習歩兵隊四個大隊を小栗に指揮させ板橋にて迎え撃つ』
『すると品川・東海道筋は誰が指揮を執られますか』
ここで将軍慶喜はニヤリと不敵な笑みを浮かべた
『余、自ら成敗してくれる』
勝は内心とんでもないことになったと慌てた。実は京都で王政復古のクーデターまがいが起こって将軍を排除するとは思ってもみなかったのだ。西郷の野郎、本性をむき出しにしやがったな。本音を言えば国を割るような戦はしたくない。そのための大政奉還だったのをブチこわしやがった。上様も気が変わりやすいとは言えあれは本気だ。乗せると手がつけられねえから一戦交えなければ収まらないだろう。それにしても将軍自ら指揮を執るなど二代将軍秀忠公の大阪の陣以来絶えてなかったのだ。
取り合えず小栗と土方を呼んだ。どちらも見るのも嫌な相手である。ただし身分が違い過ぎるので同席させられない。従って同じ話を二度もしなければならないのにうんざりさせられた。ちなみにこの日、勝は幕軍の大参謀という地位を与えられていた。
呼び出された小栗・土方の二人は対照的な対応を見せた。小栗は三河以来の譜代の名門らしく厳かに言った。
『誠に良い死に場所を仰せつかまつり恐悦至極。必ずやその官軍を殲滅し、敵将の首を上様にご覧に入れて見せます』
と、慶喜に拝謁した。
土方の方は
『甲府の城の取り合いじゃ勝っても負けても犠牲が多い。取ったところで知れたもの。攻めて来るのは土佐の乾退助が率いる迅衝隊と聞き及びます。甲州街道は山間をうねるように走って小仏峠を下る。だだっ広い甲府の盆地でやりあうより狭い街道沿いでしつこく襲撃してやれば敵は細る一方で、武蔵の国に入る頃にゃ擦り減っているでしょう。そこを一気に潰します。ついては八王子の千人同心を手前の配下にお加えください。奴等は元はと言えば旧武田の遺臣達ですから今でも行き来があって街道を知り尽くしてます。そうですねえ、まず猿橋で、次は犬目。小仏峠でも仕掛けますかな、ふふふ』
そう言うと笑みを浮かべてさっさと帰った。なるほど上様が薄気味悪いというのも尤もだと気分が悪くなった。
さて西郷をおびき出すと言っても果たして乗ってくるのか。思案した挙句に江戸城大奥にいる天璋院の文と自筆の添え状を持たせて山岡鉄舟を官軍本営に行かせることとした。クソ度胸がなければつとまらない。念のためではあるが、江戸で散々火付け打ち壊しで暴れていた薩摩人、益満休之助を同行させた。自筆の添え状には『江戸開城につき相談の義これあり』とだけしたためている。
官軍は既に駿府に進んで来ていた。
そこへ「朝敵徳川慶喜家来、山岡鉄太郎まかり通る」との大音声を発っして馬上の武士が乗り込んできた。、兵士たちは今にも切りかかりそうであったが、先導する益満休之助を見て踏み止まる。益満は「西郷大参謀にお目通りを」と案内を請い面会が許された。西郷は江戸城引き渡し・将軍慶喜は備前藩に預ける、といった条件を出すとともに勝との面談は飲んだ。策士・勝の術中にはまった。
かくして三田の薩摩藩邸で面談が成ったのである。山岡も同席している。西郷の後ろには村田新八・中村半次郎(のちの桐野利秋、この時点では人切り半次郎である)が控える。
『勝先生、お久しぶりでごわいもす』
『いや西郷さん、わざわざすまねェ』
『さて、いかな御用向きごわすか』
『まぁ、な。例の小御所会議じゃだいぶドスを効かせたらしいですな』
『おいは公家どんの議は好かんごわして』
『煮え切らない連中に「短刀一本でカタがつく」と脅しあげたと聞きましたが。まあいいや。しかしいきなり政りごとをもぎとるのも荒っぽかあねえでんしょうが』
『そいならなして慶喜公は幕府軍を上洛させようとしもした』
『ありゃ呼ばれたんで行っただけですぜ。それをいきなり発砲したのはお前さんの薩摩兵だそうじゃねえですか』
『錦旗に向って進軍されたら守らにゃ仕方あいもはん』
『さてさて、山岡に寄越したあの条件はひどすぎる。飲めなきゃ江戸を焼き払うってんですか』
『そちら次第ごわす』
『なあ、西郷さん。日本の中でいがみあってるご時世じゃねえのはお互い承知でしょう』
『勝先生、先生は油断ならんお人ゆえ、そのまま伺ってはこっちがあぶのうごわす』
『策も何も、あんなに上様を煽っちゃオレもどうしようもねぇ。こうしている間にも開陽丸は目と鼻の先に錨を下ろしてるんですぜ』
『脅すつもりごわすか。帝に弓を引かるっと』
『そんな気はさらさらねえよ。脅すつもりならとっくにこの山岡が抜きますぜ・・・・マッよーく分かった。この足で上様にかけあってくらぁ』
『山岡さあが抜くならば、ここにいる半次郎がだまっておいもはん。いずれんせよ、そいは宣しく頼みもす』
『お互い達者でな』
『勝先生もくれぐれも』
『今年の春は夜がやけに蒸していけねえ、寝冷えしねえように』
互いに暫く無言で見つめ合った。
甲州街道ではしきりに土方のゲリラ戦が展開されていた。何しろ勝沼宿を過ぎると狭い山間の街道のため、総勢千人近くの迅衝隊は長く伸び切ってしまう。編成は15小隊・砲隊・本営・病院・鉄砲隊・輜重隊と近代的な軍である。街道は整備されておらず進軍は平地の倍はかかった。
なお、乾退助は甲斐入国に当たって、先祖である武田の旧臣、板垣信方(武田四天王の一人)の姓に改め、板垣退助となっていた。
土方は配下の小隊を猟師道を使って山中に忍ばせ、しきりにゲリラ攻撃を仕掛けていた。それも鉄砲を打ちかけると一斉に引き上げて深追いしない。初狩(はつかり)では先頭で例の「宮さん宮さん」のメロディーを奏でる隊列を崩し鉄砲隊を粉砕。猿橋では最後尾の兵糧部隊を谷底に葬った。そして犬目(いぬめ)宿で宿営する迅衝隊に夜襲をかける。この時は新選組を率いて自ら切り込み『新選組副長、土方歳三である』と怒鳴り上げて姿を消した。土佐浪人には新選組に切られた者も多い。あからさまな威嚇に隊士は震えあがった。迅衝隊の指揮官は赤熊(しゃぐま。歌舞伎の連獅子のような赤い被り物)を付けていたため遠目にも目立ち、格好の標的になったのだった。
そして、その頃には板垣の耳にも敵が新選組の土方だということは伝わってきていた。当時は龍馬と中岡慎太郎を切ったのは新選組だと思われていたのでその名を聞いて激高する。おのれ、かたきを取ってやる、と。
勝・西郷の会談が行われる7日前。迅衝隊が駒木野(現在の京王線高尾駅のあたり)を過ぎると一気に視界が開け武蔵野が広がるが、板垣は周りを警戒した。土方のことだ、必ず包囲戦の仕掛けをしているに違いない。大砲隊が山肌を下るのを待って、ジリジリと進んだ。時刻は午後の2時頃になった。
すると、八王子宿の街あたりに急ごしらえの幕軍の防衛線が目に入った。左右には敵はいない。板垣はなお慎重に大砲を前面に曳いて据え付けると、轟音とともに前衛を吹っ飛ばした。
幕軍も一斉に射撃を開始して戦場は膠着する。板垣は小軍監(副隊長格)の谷干城(たにたてき)を呼んだ。
『谷。あん中にゃあの土方がおるはずぜよ。何か策を講じてるろう。おまんチクと手勢を連れてあの開けている右へ進んでみい。仕掛けがあるはず』
『心得た』
谷は向かって右側に続く丘陵沿いに侵攻した。不思議なことに敵陣が丸見えなのだが、その防御は扇形に薄く広がっているように見え、橋頭保が築かれていない。妙だな、と思いつつ部隊をその扇の要のあたりに向って進めた。
すると、今までは小銃の射撃のみであった幕軍から、おそらく四ポンド山砲と思われる砲撃音が3発轟いた。その音に反応するかのように一斉に退却が始まった。谷は益々違和感を覚え本営の板垣に『不審の動き也』と伝令を走らせるが、既に官軍は突撃が始まってしまった。板垣が総攻撃命令を下したのだった。
ところが前衛が突っ込んで行くのだが、未だ後方の狭隘地にひしめいている後続部隊がにわかに乱れた。通常は最前線を押し上げるように進むはずが、バラバラになってしまっている。右翼方面に展開していた谷の元にも伝令が転がり込んできた。
『大変ぜよ。突如背後から襲撃されちょるきに』
『なにー!いかん、取って返すぞ。仕掛けは後方じゃった!』
一隊を率いて急遽駆け出し、本体の混乱を目の当たりにした谷は信じられない物を見た。
赤地の段だら模様に『誠』の染め抜き。泣く子も黙る新選組の隊旗である。
『なんじゃとー!どこに潜んじょった。いかんぜよ、しかも前が飛び出して追われる格好の挟み撃ちじゃ』
谷は配下の者達を率いて新選組に突っ込んでいった。既に述べたようにこの時点では龍馬の仇だ。今日では見廻組の暗殺だったことが定説である。谷は突進しながら土方を探した。ところが近づいても誰もあの羽織を着ていない。あの浅葱の段だら模様の羽織だ。土方、どこにいる、と戦闘に駆け寄る、もちろん抜刀した。白兵戦になってしまうと味方を撃ってしまうので銃は使えない。迅衝隊は異変に気がついても前線の鉄砲隊を向けることができないのだ。
混乱の極みになっているところに駆けつけた谷は、真ん中で剛剣をふるっている洋装の士官に目を止めた。あれが土方に違いない。切りかかる迅衝隊士を払いながら「切り飛ばせーい」と声をかけていた。カタキを取るぞ、と力を込めた刹那、今度は前衛の方から鬨の声が上がった。
今までジリジリと後退を続けていた幕軍が突如反撃に転じたのだった。初めから3段構えの塹壕を掘り、3段目に本隊となる八王子千人同心の主力を潜ませていた。地域を知り尽くした土方ならではの『三枚突き通しの陣』である。
前面を持ち堪えられなくなった迅衝隊は敗走を始める。混乱の中、板垣は谷と偶然出会い、取り急ぎ撤退の方針を固め、川に沿って相模方面に落ちることとした。
戦況は逆転した。後を追おうとする新選組隊士や千人同心を止めて土方は言うのだった。
『クククッ、津久井を抜けて東海道筋まで行き、どこかで官軍本隊に追い付こうとしてるぜ。そうはさせるかよ。新選組、一息入れたらオレに付いて来い。ゆっくり行くぞ。ただしやつらは休ませない、眠らせない、食わせない。深追いせずに動きが止まった時だけ撃ちかけ切り込んで少しづつ追い込んでやる。2日もあればバラバラになるさ。千人同心諸君、すまんが多少の人数を割いて2日程の食いものを準備し後を追ってくれ。面白くなるぜー』
隊士も同心も底知れぬ不気味さを感じて引きつった。しかし、この男についていけば負けない、とも強く思った。
つづく
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
維新にさほどの義が有りや
2021 SEP 2 0:00:11 am by 西 牟呂雄

文久三年、薩摩藩は琉球救済の一環として地域通貨のような『琉球通宝』の鋳造を幕府に願い出て、3年間に限って許された。ところがその際に『琉球通宝』だけではなく、幕府が発行する天保通寳も一緒に密鋳していたのだ。その贋金は幕府のものより鉛の含有量を多くしていて、今で言えばあからさまな贋金、立派な犯罪なのだ。尊王討幕の正体見たりと思わざるを得ない。しかもこれを推進したのは名君として名高い斉彬である。
尚武の志高く、武士として胆力を磨きに磨いた薩摩藩にして、藩論分裂によって散々血を流した後に、薩長同盟を結ぶことに筋は通るのか。
大体どこの藩でも『尊王攘夷』一本鎗の派と、討幕までは筋が通らないとする一派で激しい争いが起こり、暗殺・切り合いといった大騒ぎを経験することになる。薩摩・長州はその争いの中の生き残った連中が討幕に舵を切った。結果は良く知るところであるが、歴史的には危ない橋を渡り続けたことになる。どちらも無謀な戦を外国に仕掛けてコテンパンに負けたらさっさと攘夷の旗は降ろす、戦闘こそないものの土佐もまたしかり。
筆者自身、保守派を自称しているので、短絡的に『尊王攘夷』と口走る心情は分からないでもないが、どうも論理体系のゆがんだポピュリズム・ヒステリーに思えてならない。それは幕府・反幕府に関わらず同時発生的に出て来る。
一例は御三家水戸で暴発した天狗党である。水戸は元々同じ御三家の尾張と同様勤皇の志の厚い土地柄だが、理屈ばかり言い立てる藩風とカッとなる気質が災いして藩内に争いごとが絶えなかった。それは藩主の世継ぎ問題だったり、幕府による日米和親条約だったりとキリがない。桜田門外の変にも人材を輩出している。そして水戸学の権威、藤田東湖の息子の小四郎(当時23歳)がたった60人で筑波山で気勢を挙げ武装蜂起してしまう。すると例の気質で頭に血が上った近隣の百姓・浪士が参集して瞬く間に千人を超えた。
その集団が日光東照宮を目指そうとして、一部が暴徒化する。それからは天狗党・保守派が入り乱れ、水戸城や江戸藩邸での勢力争いを引き起こしてのテンヤワンヤ、暴徒により那珂湊反射炉の煙突は爆破されたしまった。
結局目標を失った天狗党は何故か京都を目指す。おそらく一橋慶喜に嘆願にでも行くつもりだったのだろうが、幕府からは追討令が出ており中山道沿いの小藩と小競り合いしながら進む、最後は慶喜に拒絶されてアウト。最初から最後までプロセス無視の計画で、どうしたかったかも不明な混乱だったと言える。
尊王攘夷の天狗党の流れから、対照的な道を進む二人の人物がいる。実際に乱に加わり、途中で逸れ生き残った相良総三と、武田耕雲斎の下で暴れている頃に一度捕縛された芹沢鴨である。芹沢は新選組に行って局長になり、その時点では幕府側ではあるが結局暗殺される。
一方の相良は江戸潜伏中に何と土佐藩の板垣退助の保護を受ける。間の悪いことに丁度そのころ坂本龍馬や中岡慎太郎の斡旋で、薩摩の西郷との間で薩土軍事同盟という討幕の謀りごとが結ばれた。薩長同盟に遅れること1年である。これより西郷の指示で江戸薩摩藩邸にいた益満休之助が幕府の後方攪乱のため放火や、掠奪・暴行と暴れるが、相良はそれに加わった。余談ではあるが益満は勝海舟の親書を山岡鉄舟が西郷隆盛に渡す際の先導役を務めるキーパーソンで、最後は彰義隊討伐の上野戦争で戦死する。
相良の方は、この騒乱を鎮圧しようと庄内藩の新徴組が薩摩藩邸を焼き討ちした際に品川から船で落ち延びる。すると王政復古の大号令が発布されたため、公家の綾小路俊実を盟主とした赤報隊を結成し、官軍の東山道征討として中山道を攻め上ることとなった。しかしこの寄せ集めの赤報隊はかなりいい加減なもので、相良は命令に従わないどころか勝手に『年貢の半減』等を言い触らしては略奪ばかりして顰蹙を買う。何しろ甲州博徒の黒駒勝蔵までが入っているのだ。結局、偽官軍のレッテルを張られて下諏訪で処刑される。因みに命令に恭順した二番隊長を務めたのは元新選組九番隊組長の鈴木幹三郎(分裂して暗殺された伊東甲子太郎の実弟)である。テンヤワンヤぶりが分かろうというものだ。
そもそも何百年も京から出たこともない公家を頭に戴いて圧力をかけることができると思う所がこっけいの極みで、天誅組の騒ぎに至っては目的も何もはっきりしない。
孝明天皇の神武天皇陵参拝、攘夷親征の詔勅が発せられると、その先鋒を勤めようと土佐脱藩浪士の吉村寅太郎が公家の中山忠光をそそのかして浪士を引き連れて大和に出発する。40人位のまぁちょっとした護衛につもりだったのではなかろうか。それが何をトチ狂ったか五条にあった幕府代官所を襲撃して制圧する。しかし例の八月十八日の政変で長州派公卿は追放され、孝明天皇の大和行幸が中止される。こうなるともはやお呼びでない、とばかりに幕府から追討されることになる。すると天誅組は十津川郷士をオルグして千人程の人数を揃えた。
十津川は年貢御赦免の天領だが、言ってみれば古代より尊王専門の傭兵部隊であるから参加した。これが思いつきで頼ったようなものだから、待遇は悪いし戦略もない。中山忠光の無能は如何ともしがたくたちまち四分五裂となって雲散霧消してしまう。これまた何をしたかったのかさっぱり分からない。中山はその後長州潜伏中に暗殺された。
九州の大村湾に面したエリアに2万八千石の大村藩がある。関ケ原で東軍に付いたため準親藩で、代々名君が出たことでも知られる。場所柄長崎から海外の情報も入り易いと思われる。初代藩主はキリシタン大名でもあった。
さて、最後の藩主となった大村純熈(すみひろ)が長崎奉行を命じられた頃、例によって藩内は当然割れた。明治以後に編纂された藩の正史である『台山公事績』は山路愛山が編纂を始めたが、十数年モかけても脱稿せず、愛山死後にやっと完成した代物だ。それによれば、開明派藩主の元、勤皇の旗印を掲げ一丸となって討幕に励んだことになっている。維新後に栄達した者も多い。筆者はさる縁者からそれは嘘っ八であることを知っている。維新に邁進したのは事実であるが、その前に過激派が保守派の家老を暗殺してその罪を保守派の藩士になすりつけたのだ。その狡猾さと残虐さはその後の栄達にふさわしいものでは断じてない。それを塗り込めて正史に落とし込むために愛山は難渋して筆が進まなかったのだ。そのことは、その後を継がされたさる大歴史学者の子孫に確認した。一方暗殺された側にも筆者の知り合いがいて同様の証言を得ている。
最近『歴史のミカタ』という新書を読んでつくづく自分は歴史を生きていない、と感じた。分かりやすく言えば、自分で考えて歴史を体系的に吸収していない、ということだ。ところが老いたりとはいえ未だに息はして物は考えることはできる。なにやらこの先が楽しみになるような気が、今はしてきた。手始めに維新の大義はあるか、と思料した次第である。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
情夫(いろ)に持つなら彰義隊
2021 JUL 4 0:00:00 am by 西 牟呂雄

謹慎していた前将軍、徳川慶喜は水戸に去った。江戸城は主を失ったが、この時点では誰の物なのかははっきりしない。無血開城によって関東各地に散らばった旧幕臣の残存部隊は無傷であり、盛んに抵抗をしており、官軍はその追討に兵力を削かざるを得ない。従って江戸に残っているのはたったの3千程。大参謀西郷隆盛は江戸市中の治安を勝海舟に委ね、勝はその任に上野寛永寺にたむろしていた彰義隊をもって当たらせた。
その彰義隊、無論徳川の正規兵でも何でもない。とにかく江戸に官軍が来て我が物顔に振舞うのが気に入らない不満分子の塊である。頭取からして一橋家の家臣に取り立てられた渋沢成一郎と、与力の養子となって旗本になった天野八郎。彼らが集まっては悲憤慷慨しているうちに出来上がった寄り合い所帯なのだ。
ところが勢いに乗じてその数3千人にまで膨れ上がり、気炎を上げていた。
勢いに乗じて官軍との徳川家処分について交渉していた策士勝海舟は次々に難題を突き付け西郷を翻弄し始めた。西郷は妥協を重ねるが、京都の新政府幹部はそれが気に入らない。西郷も板挟みになっていたのだった。
そのころの江戸の世論は主に廓が発信元だ。花魁達はもちろん幕府びいきで、上京してきた官軍兵士なぞはその田舎者振りや傍若無人な振る舞いで嫌われる。一方彰義隊士は元々江戸っ子ばかりがにわかに景気づいたせいでやたらと金払いはいい。廓の人気はうなぎのぼりで『情夫(いろ)にもつなら彰義隊』と囃される始末。情夫(いろ)とは花魁の贔屓客のことである。当時の記録を読んでみると大人から子供まで、官軍とは異国の進駐軍を見るような感じで、一つには戦闘もなしにのさばっているのが気に入らない。
ところが彰義隊内部では、直情径行の天野に対し元々一橋家の家臣だった渋沢はソリが合わなかった。渋沢にしてみれば主が恭順をしているのに足元で暴れるのはいささかの遠慮があり、戦闘はできれば避けたい。そこを天野から弱腰と罵られ遂に分裂してしまい、一派を率いて江戸市中から多摩の田無村に本陣を移した。
彰義隊のいる寛永寺は、天海僧正が開山し広大な上野の一山が寺領である。歴代皇族の法親王を天台座主に戴いた。幕末の輪王寺宮公現法親王は 伏見宮邦家親王の庶子ながら、新政府からの京都への帰還の勧めを拒否。江戸に進駐してきた東征大総督である有栖川宮の呼び出しにも応ぜず、配下をして彰義隊の面倒を見させる有様はあたかも南北朝を彷彿させる気骨を持っていた。
江戸は不穏な情勢に包まれる。官軍を白眼視する江戸っ子達、情勢次第で勝ち馬に乗りそうな面従腹背の幕臣および関東の親藩、田無から江戸を睨む渋沢成一朗の振武隊。
官軍と彰義隊の小競り合いも多発するにいたり、ついに京都から三条実美が大村益次郎を伴って東上してきた。
「オイ!丈の字!丈太郎!」
「ヘーイ」
「マヌケな返事を寄越すな、このトウヘンボク」
「ヘイヘイ。何でス、親分」
「噂じゃ官軍がいよいよおっぱじめるらしい。寛永寺まで一っ走りして御用の向きを聞いてこい」
「えっ、とうとう始まるんですか戦が」
「おうよ。彰義隊の旦那衆が続々と集結してる。デケー面してやがるイモ侍に一泡吹かせてくんなさるんだ。この新門一家が指咥えて見てる訳にゃいかねー」
「わかりやした」
新門辰五郎、浅草の火消し「を組」の頭でありながら慶喜の知遇を得て、娘を妾に差し出した大の官軍嫌いである。
「親分!でーへんだ。天野様の元にいったら戦はあしただそうです」
「あしたー!」
「へェ、鉄砲の弾除けに畳や俵をあるったけ持って来いっての仰せで」
「若ェ奴等を全員集めろ。そこいらの畳をひっぺがしてお山に登れ」
「合点だ」
「あっそれから「を組」は火消し装束だぞ」
「わっちらも戦すんですか」
「バカヤロー。戦がはじまりゃ火事になるに決まってんだろ。お山を灰にされたら江戸っ子の名折れだ」
「けど親分。親分はここにいなすってくだせいよ」
「何だと。テメー俺を年寄り扱いする気か」
「いやっ、だって古稀ですよ。万が一のことが起きんとも限らねえ」
「やかましい。さっさと纏を持ってきやがれ」
通称「般若の丈太郎」は通り名の般若を背中に彫り込んだテキヤ上がりの道楽者だ。浅草の飾職人の息子だが放蕩が過ぎて勘当され、神農のシノギをしていたところ度胸っぷりを買われて辰五郎の用心棒のような「を組」の代貸し格に納まっていた。喧嘩の時も頼りになる腕利きだが普段は大酒を食らってばかりで何の役にも立たない。
火消しは通常トップを『おかしら』『かしら』と呼ぶが、丈太郎はテキヤ時代の癖が抜けず『親分』と呼びならわしていた。
総勢280人程の『を組』が勢揃いすると辰五郎が激を飛ばす。
「野郎共、明日は上野の山の大火事だぁ。新門一家が束んなって大伽藍を官軍からお守りするんで今夜から籠るぜ」
「おう!」
鳶口(とびぐち)・刺又(さすまた、指俣)・鋸は言うに及ばず、竜吐水(りゅうどすい)・独竜水(どくりゅうすい)・水鉄砲・玄蕃桶(げんばおけ、2人で担ぐ大桶)といったいわゆるポンプの類を担いでの行列はまるで百鬼夜行だが、広小路口からの参道では物見高い江戸っ子から、今までの鬱憤を晴らすように声がかかった。
「かしらー!頑張ってくんねぇー」
「丈の字ー、しゃかりきに行っといでー」
「丈太郎、頼んだぜ」
「般若の兄ィ」
調子にのった丈太郎は手を振って応える。
「任しとけ。官軍なんざ屁の河童だ」
辰五郎はいやな顔をした。
「丈太郎、ただの喧嘩ざたじゃねぇ。黙ってやがれ」
すると同じように黒門を目指してくる武士の集団と出会った。こちらは50人程の小部隊だがやや速足で整然とやってきた。誰も口をきかない。先頭の者が掲げる旗には『會』の文字が見て取れた。
「親分、ありゃお武家さんですね」
「あの旗は会津だ。まだこの辺に残っておられたのか。はて、殿さまと一緒にみんな帰って行ったと聞いていたが」
立場上、先を譲ると軽く目礼して黒門から入っていった。新門一家も後に続く。中腹の寒松院に陣取る頭取、天野八郎に挨拶をすると根本中堂のあたりに固まって朝を待った。
翌朝午前7時。黒門正面の現在松坂屋のあるあたりに兵を進めた薩摩藩の前線指揮官、篠原国幹が「放てーッ」の命令を下した。一斉射撃が響き渡ると彰義隊も撃ち返し戦闘が始まった。丈太郎はつぶやいた。
「いよいよ始まりやがった」
彰義隊は黒門の近くの小高い山王台(西郷隆盛の銅像のあるあたり)に四听(ポンド)山砲を2門据え付け、全面の薩摩藩兵に向けて猛烈な砲撃を加えた。轟音とともに前線が吹っ飛び煙が上がる。
「ざま-みやがれ。こいつぁー景気がいいや」
「丈の字!うるせい、少し黙ってろ」
「へい」
うるさいも何も銃声と砲弾の炸裂音で会話なんぞ聞き取れない状況だ。
薩摩軍の消耗は凄まじく次々に死傷者が運ばれる。すると他藩の動きが鈍った。薩摩軍と共に黒門攻略に当たった熊本藩が誤射してしまい薩軍に負傷者が出る。
当時、脱走歩兵部隊は関東各地で暴れ回り、奥羽や越後の各戦線からもひっきりなしに援軍要請が来る中、官軍の中枢である薩摩兵は江戸に4個中隊(数百人)いたに過ぎない。西郷が事前に薩摩軍の配置を見て「薩摩兵を皆殺しになさるおつもりか」と立案者の大村益次郎を問い詰めると「そうです」と答えたという都市伝説すらある。
また、背後の団子坂から谷中門に向った長州藩は、貸与された新式スペンサー銃の扱いに慣れておらず、すこぶる奮わない。
ドカーンンンと重い大音響と同時に根本中堂が炎上した。
「オイッ、いってーどっから火が降って来たんだ」
「わかりやせんぜ。黒門は破られちゃいねえ」
「グズグズすんな!火消しの出番だ」
そう言っている直後にまた数発が着弾して台地が震える。吉祥閣・文殊楼まで燃え上がった。
「親分、あっちだあっち、池の向こうの前田様のお屋敷からだ」
「バカ言え、あんなとっから届く大筒なんか・・・」
ドカーン、今度はすぐ近くで炸裂した。
「さっさと龍土水をブチかけろ」
「かしらー、永吉がバラバラになっちまったー」
「ナニー」
その時黒門の方を見やった丈太郎は抜刀した一団がこっちに向って来るのを視認した。昨日の会津藩の旗を掲げていた連中だ。その者たちは周りにいる彰義隊士に切りかかっているのだ。
「親分、マズい。寝返りだ寝返り。あいつら会津藩兵じゃねぇ。官軍だったんだ」
「冗談抜かせ」
「火消しどころじゃねえよ。こっちに切り込んできやがった」
黒門の前衛の彰義隊が動揺しているのを見て取った篠原国幹が振り返って西郷に尋ねた。
「もう、よかごあんど」
「うん、もうよか」
西郷は奇しくも後の生涯最後に言った言葉を発した。すると薩軍は一斉に抜刀し、独特の切っ先を高く上げるトンボの構えをすると、各々例の「チェストー」という声を上げて切り込んだ。内部をかく乱されていた彰義隊はもはや持ちこたえられず黒門を破られ、勝負がついた。
「親分、だめだ逃げましょう」「かしらー、もうだめだ」
「バカヤロウ、逃げるな!火を消すんだー」
「親分、分かったからこっちに」
「を組」も四分五裂になり、丈太郎は子分共と喚く辰五郎を引っ担ぐように逃げた。彰義隊は総崩れになり、大村益次郎が作戦立案の際に玉砕覚悟の抵抗を避けるために手薄にしていた東側から根岸の方に落ちて行った。孫子の兵法で言う囲師必闕(いしひっけつ)の構えである。
辰五郎一行がジタバタと走っていると寛永寺の僧侶が二人、やはり落ち延びているのに追いついた。通り過ぎようとして若い方の顔を見た途端、辰五郎は一行を制しひれ伏した。丈太郎以下も何事かと土下座する。辰五郎は絞り出すように言った。
「御前様。あっしらが不甲斐ないばかりに申し訳ございません」
輪王寺宮公現法親王が側近である執当役の覚王院義観を伴って落ちていくところだった。
暫く見送った後で一息入れた辰五郎は呟いた。
「浅草にけえろう(帰ろう)」
「まだ官軍がいますぜ」
「考えてもみろ。おれっちゃー火消しだ。何も逃げ回るこたーねぇ」
「それもそうか」
「お山の火事を消そうとしただけじゃねーか。コソコソしなくていいんだ。第一逃げるってどこ逃げんだよ」
ヨタヨタと歩いていると右手にまだ炎上している大伽藍が見える。
「これでお江戸もお終めーだな・・・・。隠居して上様のおわす水戸にでも行くか」
「親分、それじゃお江戸の火事は誰が仕切るんですかい」
「自分で火ィつけたんだ。あの西郷隆盛とかいうのがやるんじゃねえのか」
「あんなイモに務まるもんか、ベラボーめ」
辰五郎が言った通り、明治とともに江戸という地名は無くなってしまうのである。
辰五郎自身は慶喜の駿府への移封について行きその地で数年を過ごす。慶喜が水戸を出て、江戸から駿府に移動する際には既に旧幕臣の組織だった行動はできなくなっていた。それはあんまりだと辰五郎が音頭を取り江戸中の町火消が装備を纏って数千人の大名行列をしつらえ、出立した。町火消全組の纏が振り投げられたという。辰五郎は最後は東京に戻り明治8年に没。
輪王寺宮公現法親王は、江戸市中を転々とした後、いかなる伝手を頼ったか品川沖に錨を下ろしていた榎本武揚の旧幕府艦隊と共に北上、会津入りする。奥羽列藩同盟の錦の御旗になる可能性があったが、利有らずして投降し京都で謹慎させられる。
維新後には北白川宮能久親王となり、ドイツに留学し陸軍軍人の道を進む。最後は台湾でマラリアにかかり亡くなる。この宮様のお屋敷は赤坂プリンスの旧館で、現在同じ場所で整備され案内版には『朝鮮王族の、李王垠殿下の邸宅』と書かれていたがその前は北白川宮邸だった。筆者はそのまん前の中学に通っていたが、現在よりも道路側にあったことを記憶している。
渋沢成一朗は上野のドンパチが始まったと聞いて参戦しようとしたが、戦闘がたったの一日で終わってしまったため多摩郡田無で地団駄を踏むことになる。その後残存部隊も合流したため、旧一橋領である埼玉の飯能で一戦交えるがあっけなく敗ける。その後、転々とし辛くもこれまた榎本艦隊に乗り込み、こちらは函館まで行く。従って輪王寺宮とも、土方俊三とも会っている。
函館では再結成された彰義隊の隊長だったが、何故か降伏前に離脱して潜伏している所を捕まる。彰義隊の再分裂が原因らしい。その後、従妹の渋沢栄一の勧めで官吏になり財界でも活躍する。今放送中の大河ドラマ『晴天を衝く』の渋沢喜八である。
最後に天野八郎であるが、一度は約百人程の彰義隊士とともに護国寺に集結するが、協議して解散、各々潜伏することにした。一部は渋沢に合流する。天野は隅田川沿いの炭屋に潜んでいる所を捕縛された(先に掴まった彰義隊士から密告されたという説がある)。そして小伝馬町の牢屋敷で獄死する(これも暗殺説がある)。
猪突一本、直情径行の士だったのだが指導力や人望には欠けていたのかもしれない。
彰義隊はその後タブー扱いされ取り上げられることも無くなったが、江戸っ子の口伝には長く残った。明治中期になってから、五世尾上菊五郎が新富座の演目に取り上げると大変な人気を呼び、陸軍少将に昇進していた北白川宮能久親王(輪王寺宮公現法親王)も軍服を脱いでお忍びで観劇している。
筆者は神田淡路町の生まれだが、子供時代のチャンバラごっこのイイモノは彰義隊だった。ただしチビの筆者は「将棋隊」だと思っていた。
そして上述の、前の晩に会津の旗を掲げた一団の武士が裏切った、という話は淡路町から秋葉原・広小路辺りでは都市伝説になっていて、ガキを相手に講釈するヒマなオッサンは実在した。しかし、それを証明する文書にお名に罹ったことはない。上野が燃えると炎がアオい(グリーン)とも伝わっている。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
実録 三方ヶ原の戦い
2021 JUN 20 0:00:08 am by 西 牟呂雄

越後の虎と言われ、生涯敗けなしの猛将・上杉謙信は一向一揆と対峙しながらイライラしていた。武田軍が躑躅ヶ碕の館から出て韮崎・小渕沢に動いたという報告が上がってきたのだ。ここで背後を突かれてはひとたまりもない。
一方、浅井・朝倉連合軍と睨み合っていた織田信長も背中に汗が流れる思いで同じ知らせを聞いた。東美濃で国境を接してから、懐柔しようにも遜ろうにも硬軟自在の信玄には通じない。正直ホトホト手を焼いていた。そこへもってきて盟友の徳川家康が武田と小競り合いを始めてしまったことに気を揉んでいたところだ。
そしてその家康、ここ浜松城は元はと言えば今川領である。謂わば旧敵地にヘリコプターで舞い降りたようなもの。しかも旧今川の本拠であった駿府は武田領となった。浜松と駿府の地侍はツーツーである。もし本気で信玄が攻め上ってきたらばどうなるか分かったものではない。おっとり刀で信長に応援を要請したのだが、信長が援軍として寄越したのはたったの3千人。
追い打ちをかけるように新たな情報がもたらされた。武田の別動隊が甲府を出陣し南下し始めたというのだ。信玄得意の攪乱作戦に違いない。
越後でも謙信が声を荒げていた。
「一体、信玄入道はいずこにある。甲府か!諏訪か!」
無理もない。正面で4回対決した川中島でも陽動作戦には悩まされ続け、終いには単騎突撃するに至ったこともある。おまけに謙信が陣を払った後は、様々な調略によりかの地の国衆を傘下に納めてしまうのだ。
突如、東美濃に武田方の秋山虎繁が2千5百の兵を率いて現れ、猛将・山県昌景が東三河に南下し、破竹の勢いで信長の六男御坊丸のいる岩村城を取り囲んだ。天兵が舞い降りたような早業に、調略を受けた岩村城はあっけなく開城してしまう。
肝を冷やしたのは信長で、上杉謙信は胸を撫で下ろし、家康はパニックになった。信玄の本隊は後発の部隊だと分かったからだ。その本隊は駿河と遠江の境を超えて来る。
浜松城には自分の兵8千と信長の援軍3千人がいる。籠城するか、迎え撃つか。武田軍の騎馬隊の強さは天下に知れ渡っている。当時の平均的編成は足軽7~8人に馬1頭だが、目の前の武田軍は総勢2万5千が1万頭の軍馬を引き連れており、その騎馬武者が独特の長槍を携え、猛烈な勢いで突進してくれば止めるのは不可能だ。
家康は籠城に傾いたのだが、そうも言っていられなくなった。近隣の地侍が先を争って信玄になびき出したのである。我慢できなくなり、3千の兵を連れて威力偵察に出た。
天竜川を渡り、一言坂の下から本多忠勝に5百ほどの兵を付けて先発させた。本多隊が坂を上りきって視界から消えたと思った途端、その忠勝を先頭に息せき切って駆け戻って来る。
「殿!大変です!武田の兵は我等を取り囲んでおります」
「なに!いかほどの数か」
「およそ1万。信玄率いる本隊です」
「そんなバカな。音もなく大軍が降って湧いたとでも申すか」
「とのー、あれを」
指差した先には真っ赤な武者備えの大人数がヒタヒタと駆け下りて来るではないか、ホラ貝も吹かず鬨の声もあげずに、である。
「殿!お下知を」
「ターケ(たわけ)!逃げるんじゃー」
3千人の総退却である。指揮もヘチマもない。灰神楽をひっくり返したように砂塵が舞い怒声が上がる。兎にも角にも馬に乗った家康を先頭に逃げに逃げた。本多忠勝は殿になり駆けに駆けた。見付(現在の磐田市)の集落にたどり着いて一息入れようとすると、なぜかそこには赤備えの騎馬隊がいるではないか。一体いつ先回りしたのか。
「一斉に放てー!」
苦し紛れに家康は鉄砲を撃ちかけ火を放った。自分の領地を焼くのである。もはや作戦もクソもない。3千人はまだ戦もしていないのに敗残兵のように大火事の中を逃げる。天竜川が見えてきたが、一同目を見張った。何とそこにも騎馬隊がズラリと並んでいたのだった。
「もはや、これまでか。信玄恐るべし」
家康は覚悟を決めた。と、その時、殿だった本多忠勝が飛ぶように駆け込んだ。鉄砲隊を連れての決死の突撃だった。本多忠勝は家康の側近中の側近。好んで危険な戦闘に飛び込むのだが、生涯かすり傷一つ負わなかった剛の者である。手には天下の三名槍と後に称えられる二丈余(約6m)の蜻蛉切りを携えていた。穂先に止まったとんぼが真っ二つになったのが名前の由来である。
「とのー!ごめーんん!」
叫びながらの突撃にさすがの騎馬隊も割れ、家康は九死に一生を得たのだった。
しかしこの遭遇は単なる脅し程度のもので、信玄本隊は二俣城に軍を向ける。
浜松城での軍議は寂として誰も声を発しない。かろうじて家康が絞り出すように言った。
「信玄は妖術でも使うのか。あの騎馬武者は音も立てずに我等を追い抜いたとでも言うのか」
「おそらくは我等の動きを読んで先に迂回させていたかと」
「しからばなぜ一言坂に行くことが知れた。裏切り者でもいるのか」
「あれは確か殿とそれがしのみで謀ったことにござる」
「ともかくあんなのとまともに戦ったら勝ち目はない。籠城するぞ」
「敵は我が領地の庭先を悠々と二股に向っており候。遠江の地侍は雪崩を打って武田に馳せ参じております」
「ケッ、腰抜け共め。武田を片付けたら目にモノ見せてくれるわ」
そこへ物見の武者が駆け込んできて庭先に平伏した。
「申し上げます。二股の城が落ちましてござる」
「なにー!あの堅固な城をか」
「いかだを組んで水を切られ候」
「ふうむ・・・・。服部半蔵いずこにある」
家康が突然大声を上げた。
「庭先にて御座候」
「近う」
半蔵が縁側のところまで進むと家康はわざわざ立ち上がって近づいていき、半蔵の耳元で何かをささやいた。諸将は家康が迷っていることを悟った。半蔵を呼ぶのは迷った時のいつもの癖である。それもそのはずで、このまま籠城している間に三河に進軍されれば岡崎の息子信康はひとたまりもない上に信長との同盟が破綻してしまうかもしれないからだ。
旧暦の師走は日暮れも早い。軍装を解かぬまま夕餉を掻き込んでいる所に半蔵が帰ってきた。
「殿、服部半蔵おん前に」
「おう、どうじゃった」
「武田は奥三河に向う、とのこと」
「なんじゃとう」
「放っていた草はみなそう聞き、それがしも確認して候」
「こちらへ向かわず我が庭先に進軍するとは。岡崎の信康を潰して岩村より信長様の背後を突く」
「こうしてはおれぬ。殿、打って出ましょうぞ」
大声で立ち上がったのは鬼のような形相の本多忠勝だった。
三方ヶ原は東西10km南北15kmの広さで標高差は80mもある洪積台地。浜松からは見上げる形で2万8千の武田軍が整然と移動しているのが見えた。家康の手勢は信長の援軍をいれても1万程度。しかも出だしでこっぴどくやられているので、家康は鬨の声が上げられなかった。
しかしついていくように軍を進めている内、まるで敵を追い詰めているような気分が高揚してしまい、先方の部隊が武田の殿に礫を投げ掛け始めた。すると武田側からも印打ち(円盤状の石)を掛けて来る。しかし行軍はそのまま粛々と進むので、家康の先鋒千人ほどがつい深入りした、その瞬間に全軍がピタリと動きを止め向きを変えると鉄砲隊が構えた。
第一撃で前面がやられてもすぐには踏み止まれない。そこへいきなり50騎一組の塊で、次々と突進してきた。しかも例の長槍を携えている。ホラ貝の音も『突っ込め』の声もワーッといった歓声もない無言の突撃だ。家康も仰天するとともに先日の騎馬隊に追われた恐怖がまざまざと蘇った。
叫び声を上げて次々に突かれ騎馬に踏み倒されていくのは家康の兵ばかりである。迎撃戦は破られ総崩れとなりかける。ただ一か所、家康軍左翼で本多忠勝隊のみ奮戦をしていた。あまりの攻撃の苛烈さについにもちこたえられず家康が下知した。
「引け―!浜松まで引くのじゃー」
踵を返して近習と共にひたすら逃げに逃げた。しかしこっちが必死に駆けて居るのに武田菱の馬印の騎馬隊は後ろから迫るかと思いきや、天竜川の時のように向かう先に轡を並べていたり.終いには逃げる家康と成瀬吉右衛門、日下部兵右衛門、小栗忠蔵、島田治兵衛のわずか5人になったすぐ横を並走していた。這う這うの体で浜松に帰り着いた時は切腹まで覚悟した。
家康は破れかぶれになり、全ての城門を開いて篝火を焚き、湯漬けを食べて寝た。猛将山県昌景が浜松に突入してきたが、空城の計(敵をおびき寄せるたのの策略)と勘違いしてそのまま引き上げた。
一方、圧倒的に勝利した武田軍の陣中は勝ちに乗ずるかと思いきやさにあらず。
実は信玄の病は既に手の付けられないほど進行していた。信玄の喋っている言葉が良く聞き取れないのだ。にもかかわらずあの整然とした戦を軍配一つで指揮できるのは武田軍団の日頃の鍛錬の賜物ではある。信玄は歯が全て抜け落ち、口の中にできものができていた。髪は剃髪していたので分からないが、もう無かった。幽鬼のような姿に成り果てて輿に乗るのがやっとだったのを、ここまで押して来たのだ。
いよいよ危なくなってきた。勝頼と側近数名を呼び寄せてかすれる声で告げたのだった。
「我が死を3年秘匿し、ひたすら兵馬を養え」
そして勝頼の名を上げて密かに伝えた。
「越後を頼る事」
信玄は勝って病に伏し、宿命のライバルの名を上げて戦に明け暮れた生涯を終えた。
家康はこの敗北を恥じ、その後の生涯に渡って同じ負けの轍を踏まぬように戦い続けた。負けて生き残り後に天下に覇を唱えることになる。そしてその前に、信長・秀吉の天下統一もまた無かったに違いない。
あまりにも鮮やかな運命の天秤だった。
なお「しかみ像」に関して、家康がこの敗戦の時の姿を模写させたと伝わるが、最近の研究では否定されている。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
高志国(こしのくに)考
2021 JUN 6 0:00:20 am by 西 牟呂雄

筆者は出雲の歴史を研究し、オリジナル出雲族である大国主命が天孫族に攻め滅ぼされ、国譲りという神話を残しその一族はいずこかへ散っていったと考えている。はっきりしているのは大国主命の息子である。建御名方神が糸魚川に沿って南下し諏訪にたどり着いている。また、海岸線を伝って日本海を北上するルートも検証してみると、高志国がキーワードとして浮かび上がってきた。
高志=越国は越前・越中・越後と広いが、このエリアと出雲は古来密接なつながりが有ったはずだ。そもそも須佐之男命が出雲にやってきて八岐大蛇を退治した神話からして、そのオロチは高志の国から毎年やって来ていたのである。
それだけではなく、出雲市には古志町という地名が残っていたり、隣の松江市にも松江市古志町・松江市古志原と言った場所があり、往来の盛んであったことが偲ばれる。
ちなみに新潟では地震の被害が報じられた山古志村がちゃんとある。
時代が下って出雲風土記が編纂された時は国引き神話の記述があるが、八束水臣津野命(やつかみずおみつぬのみこと)が、「志羅紀」「北門佐岐」(きたどのさき)「北門農波」(きたどのぬなみ)「古志」という四つの国の地面を引っ張ってきたとされている。人々が大いに入植したことの例えなのだろう。北門佐岐は佐渡島、北門農波は任那だろう、新羅と越は明らかだ。
古代の航海技術がどれほどのものか詳しくはないが、環日本海の物流・人流があって、時に対立・侵略しながら付き合っていたはずである。アイヌ系はあまり海洋民族のイメージがないが、満州族は後年にいたって刀伊の入寇といった3000人規模の襲撃を仕掛けて来た。
大国主命も高志国まで行って沼河比売(ぬなかわひめ)に妻問いして建御名方神(たけみなかたのかみ)をもうけたりしているが、この場合明らかに侵略だろう。
この高志エリアは古来から豊であったことだろう。大国主命の時代にどの程度稲作が普及していたかは知らないが現在でも米所であり海の幸にも恵まれている。当時は翡翠を産し、GDPも高かったと思う。従って力を持つ者が出て来る。
例えば継体天皇は即位後20年近くこのエリアにいた。越前の朝倉は信長を追い詰める所までに至った。戦国時代は個別戦闘でほぼ無敗の上杉謙信が出る。ただ、あまりに雪深いため、冬季の移動が困難だったので天下に覇を唱えるには至らない。逆に言えば逃げ込むには都合がいい場所だという事だ。
先程、高志の地名をたどってみたが、その逆はないのか。国譲り後に大国主命一族が落ち延びた痕跡が辿れるのではないだろうか。そう思って地名で検索すると、あった。
まず金沢市に出雲町があり、その名も出雲神社なるお宮が5つもある。
隣の富山県小矢部市にもやや小振りながら出雲社が見つかった。
次の新潟に入ると糸魚川市では例の翡翠が採れた地域だから、逃げ込むというよりは沼河比売(ぬなかわひめ)へ妻問いしに遠征したかと思料する。奴奈川神社がある。
新潟は実は結構な数が見つかったのだがもう一つ挙げるとすれば出雲崎だろう。新潟と柏崎の真ん中あたりの出雲崎町は良寛さんの故郷で知られるが、出雲臣の一族が往来したとの伝えが残る石井神社が出雲大神(大国主神)を祭っている。
高志=越の国はここまでだが、ついでにもう少し北上してみる。
山形県では内陸の寒河江市に出雲太神社というのがあって、面白いことに『いずもおおかみしゃ』と読むそうだ。本命かと考えていた酒田市には大国主命を祭っている神社はあるが社名は地味なものだった。
更に秋田まで行くと最南端のにかほ(ひらがな表記)市に大国主命を祭る出雲神社があるが詳しいことは分からない。大国主命がやられた直後の一族・重臣といった第一次出雲難民の脱出先は、どうやらこの辺りが北限と思われる。
筆者としては、松江の宍道湖と同じ汽水湖(海と繋がっている)であった八郎潟あたりがポイントかと想像したが有力な痕跡は見つけられず、『出雲』で検索に引っかかって来るのは出雲大社教(いずもおおやしろきょう)という明治以降に組織化された宗教法人だけであった。出雲大社教とは明治時代に伊勢派が主流を占める国家神道から出雲派が分離した神道系新宗教(教派神道)のことである。
もう一つ出雲教というのがあって、室町時代に千家から分かれた北島家によって創設された教団で、出雲大社に向って右側にある北島国造館が本部である。尚、千家と北島家は今日でも出雲国造を名乗っている。
話がそれたが、出雲神社と言う名称で絞り込むと以上の例が検索できたが、祭神が大国主命(或いは別名であると大穴牟遅神(おおあなむぢ-)・大己貴命(おおなむち-)・大穴持命(おおあなもち)-大物主神(おおものぬし-))である神社はそれこそ数えきれないくらいあった。特に北限と想定した秋田県南部を更に北上した青森県に多い。
筆者の仮説ではこれらは第一次出雲難民の次世代以降の人々が移動した先にゆかりの祭神を祭ったのではないかと考えている。
さて、出雲難民が北上していった先は、その時代が下ると蝦夷(えみし)の国として中央と対立することになる。古くは武内宿禰から、坂上田村麻呂やら八幡太郎義家が散々攻撃して最後は中央に従うのだが、最後の最後まで抵抗した荒蝦夷(あらえみし)が立てこもったのは現在の弘前城のあるあたりである。作家の佐藤愛子や今東光のルーツで、何やらお上に従わない反骨の気質が覗える。蝦夷とはアイヌ系・オロチョン系といった北方民族の別称ともされるが、その構成の中に出雲系もあるのではないだろうか。
筆者の想像は膨らむのである。是非、フィールド・ワークに行ってみたいと思う所以である。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」