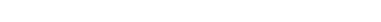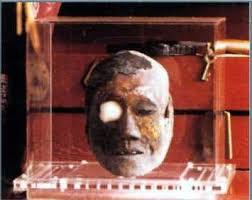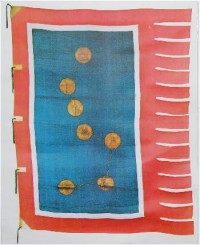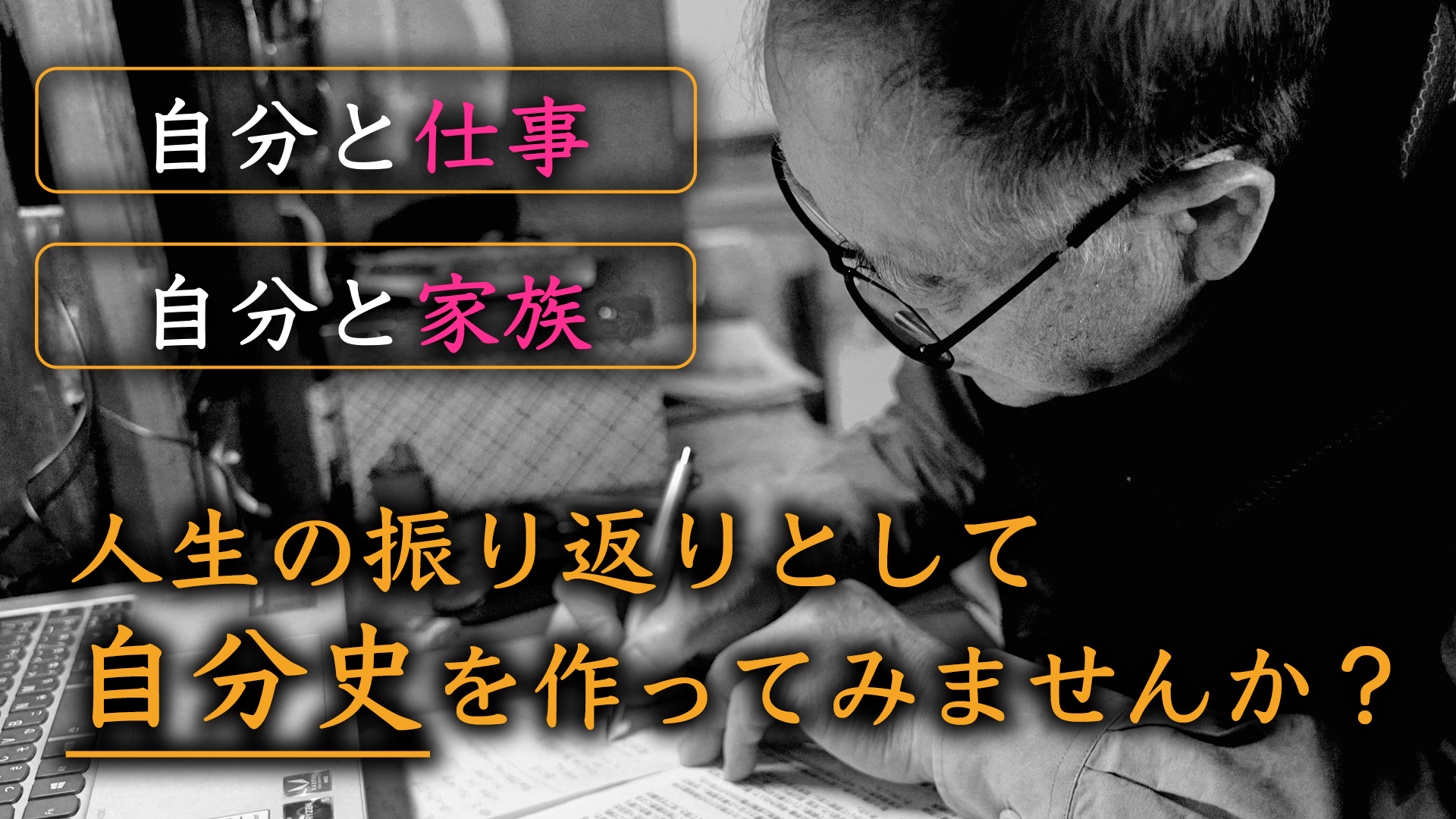婆娑羅競べ
2021 JUN 1 0:00:40 am by 西 牟呂雄

南北朝の相克は、後醍醐天皇亡き後も足利尊氏から二代将軍義詮になってもなお果てしなく続くようであった。後醍醐天皇の魔性、足利尊氏・直義兄弟の争い、北畠顕家の剛直、高師宣・師奏兄弟の狼藉、楠一族の死闘、と筆舌に尽くせぬ人間模様が織りなす奇々怪々が、末法の世にはびこったからである。
京都に押し寄せる軍勢は、元は足利幕府の管領であった細川相模守清氏に率いられた南朝軍であり、先陣として乗り込んできたのは大楠公・楠正成の三男、正儀であった。、四條畷の戦いで、長兄正行・次兄正時が高師直に敗れ討死したため楠軍の総大将となっていた。
追って入京してきた細川清氏は明らかに度を失っていて、室町の幕府屋形に攻め入りもぬけの空であったことに怒り狂い火を放った。略奪する物が何もなかったからである。
清氏の怒りも、元はと言えば政敵となった佐々木道誉に謀反の噂を立てられたせいで幕府における地位を失墜させられたからであり、詮なきものではない。しかしこの時期、転じて北朝南朝のいずれかに宗旨替えすれば、両朝天皇の名の元にいくらでも大義名分がたってしまう。何しろ足利兄弟ですらことあるごとに宗旨替えをしたくらいである。
二代将軍義詮は、後光厳天皇を擁して近江に落ち延びた。
楠正儀は、京極にあった幕府の要人佐々木道誉の屋敷に向った。すると遁世者とおぼしき僧形の姿があり静かに言上するのであった。
「楠左兵衛督(さひょうえふ)様とお見受けいたし候。屋敷の主、道誉禅師申しまするに必ずや楠左兵衛督様おいでの際はこれにて一献さしあげるべしと申しおかれ候。案内(あない)仕りますゆえこちらへ」
正儀も面食らったが、馬を下り従って進むうちに更に仰天した。畳が敷き詰められ(この時代板張りが普通)、花瓶・香炉・盆に至るまで贅を尽くした物が整えられている。寝所には沈香の枕に緞子の寝具が敷いてあった。次に十二間の侍所に行くと山海の珍味が山と準備されており、三石入りの大筒に美酒が満々と蓄えられていた。書院に案内され、書聖・王義之の偈、韓愈の文集が古渡りの硯とともに揃えられるに至っては三嘆せざるを得なかった。
王義之は東晋の書家であるが日本には奈良時代の鑑真和上によりそのコピーが入ったと言われる。コピーとは真筆の上に薄紙を乗せて輪郭を取り、それを丹念に塗り潰したもので、今日日本にはそれすら2点残されるのみである。実際の真筆は世界に一つも伝わってはいない。韓愈は唐代の高級官僚で、詩人の白楽天と並び称された文章家である。
やって来た細川清氏が『佐々木の屋敷など焼き払え』と吠えたが、正儀はそれを制した。さすがの正儀も唸るしかなかったのだ。
時は4日程遡る。前線を破られた幕府軍は都からの離脱を決め、御所でも室町でもそれぞれの御物・宝物・武具を積み込む作業で大童である。ガラガラと荷駄が動き回り埃を巻き上げ、怒号が飛び交っていた。何しろ御所と幕府政所が一緒に引っ越すのだ。女房達の衣装・化粧道具だけでも山のような荷物となる。京極にある佐々木館でも同じような喧噪の中、主である佐々木道誉は一人の遁世者を連れて帰って来た。そしてその様子を見て大音声を発した。
「たわけー!オサマレーッ」
そして振り返ると後ろの遁世者に向って言った。
「まったくあさましいこと夥しく恥じ入る次第で。われらは武装してこれより都落ち候。手筈の通りに宜しく申し上げる」
遁世者は頷くと上述のような常識外れの出迎えの準備にかかったのだ。
京の都は攻めるのに易く守るのに難い。七口の全てを固めるには南朝方の勢いがどうであろうと兵力がたりない。この時期に南朝が攻め入ったこと四たびに及ぶが、体制定まらぬがゆえに敵中に孤立するばかりで兵站が続かない。果たして今次もすぐに撤退することとなった。
正儀は逗留中にこの度肝を抜くような気配りにいたく感じ入り、郎党共に飲み食いは許したが調度品の一切に手を付けさせなかった。
しばし刮目して何かを思案していた。フト目を開けると、自分を出迎えた遁世者が庭先に佇んで自分を見つめている。正儀はニコリともしないでその者を手招きした。
「御坊、ずっとこの屋敷におったのか」
「入道様が行く末しかと見届けよと申されましたゆえ。左兵衛督様のお振るまい、誠に雅であること伝えんがためここに御座候」
「丁度よい。そこもとに願いの義これあり。これより我等は立去るが、道誉入道が揃えし物に倍する馳走を盛り上げてくれぬか」
「あっぱれな武者振り、心得て候」
「奥に設えしは秘蔵の鐙と白幅輪太刀(しろぶくりんのたち)である。去るに当たっての置き土産と伝えてくれ」
「御意のままに」
そう言うと『馬引けー』と号令をかけ馬上の人となった。門前を出た所で振り返りその遁世者に問うた。
「そこもとの法名は」
「さて、徒然なるままに流れる乞食坊主にて」
「されば俗名はなんと」
「卜部と申し候」
「ふむ」
踵を返して去っていった。
元の鞘に納まって舞い戻った佐々木道誉は上機嫌で遁世者を相手に盃を干した。
「それで楠の若造はどんな顔をした」
「初めはあまりのバサラ振りに唖然と驚き入り、深く感じ入った様子にて」
「ほう、やはり大楠公の倅じゃのう」
「なかなかに歯ごたえのあるもののふにて候」
「三十路前であろう、これからか」
「入道様にあしらわれ、鎧に太刀を献上したことにて。この婆沙羅くらべは結局」
「これこれ、兼好法師。人聞きの悪い」
「ふふふふ」「はははは」
かの吉田兼好は太平記に高師直の艶文の代筆者として記述され、歌舞伎の演目にまでなっているが、筆者はこれをかなり怪しんでいる。あの斜めに物をみては悦に入っている兼好法師がそんなことをするだろうか。太平記は誇張された内容が多く、筆写によって伝わるうちに当代一の名文家として後に知られた吉田兼好の名が取ってつけられたのではないかと睨んでいる。この婆沙羅比べに出て来る遁世者の名は太平記には無いが、兼好法師と考えると余程面白いと思うがいかに。実際にはこの時点で大阪近辺の正圓寺のあたりにいたとされるので都までは指呼の距離である。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
天台座主尊雲法親王
2021 MAY 14 1:01:13 am by 西 牟呂雄

「お次!」
今日もやや甲高い声が叡山に響き渡る。太刀・薙刀をしつらえた荒法師が次々になぎ倒され『参り申し候ー!』と打ち据えられる。天台座主自ら僧兵達に武道を手ほどきしていた。
尊雲法親王はわずか6歳で延暦寺に入山すると、その稀に見る英明さでたちまち宗徒の耳目を集め、二十歳になるや天台座主に推される。すると今度は武術の稽古に邁進し、瞬く間にそれを極め、一山の者は舌を巻いた。のちの太平記に『まこと不思議なる御門主』と記される所以である。
顔立ちはやや丸顔に切れ長の鋭い目、小柄ではあるが筋骨たくましく、6尺の塀を軽々と飛び越えた。声はよく通る響きで数千人の山法師はことごとくこれに従った。読経の際の澄んだ声と妖しい眼光からか、軍神・摩利支天の生まれ変わりの神人と称える者もあり、事実しばしば予言めいた偈(げ)を唱え、それは全て当たった。
それもその筈、尊雲法親王の父親こそかの皇統の魔人ともいうべき後醍醐天皇その人であった。
「殿ノ法印、これへ」
尊雲の声が闇を切り裂くと『おん前に』と太い声の返事があり、巨漢の天台僧が現れた。殿ノ法印良忠、関白藤原良実の孫でありながら怪力無双。尊雲の側近中の側近である。
「都の帝に厄災近し」
「・・・っと仰いますと・・」
「帝に大望あり。鎌倉に知れよう」
「そっそれでは」
「帝の御身が危うい。良忠、山を下り都に潜め。八瀬童子を集め備えよ」
「御意。いつもながらの千里眼、恐れ入り候」
「ここも危ない」
「・・・御門主・・・」
「天命と心得よ。いずれ還俗し帝を支えん。ホホホホホホ」
後醍醐天皇は宋学を修め真言に凝り、書を能くし琵琶の名手、茶道の闘茶を主催する全能の帝のような華麗さであるが、同時代の身内の評判は惨憺たるものだった。堂上公卿からも総スカンの有様。要は人の気持ちを斟酌することができない驕りと我儘の塊で周りは全て塵芥にしか見えない。尚且つ執念深く猜疑心の強い性格は魔人としか言いようがない。こちらもまた珍しき天皇であった。
異様な眼光と圧倒的な迫力に、初めはひれ伏さない者はない。しかしながら毒気が強すぎて凡人はその目を見つめ続けることさえできずに委縮し、その後には離反した。
その帝が鎌倉に憎悪を抱かないはずがない。
幕府の方でも警戒し、さっそく中宮(正妻)西園寺禧子への御産祈祷が幕府への呪詛との嫌疑がかけられる。これでおとなしくなるかと思いきや、5年後に討幕計画がチクられて三種の神器を持って逃げ出さざるを得なくなる。尊雲は情報網と独自のカンでそれを察知し先程の会話となったのである。
しかし時がわずかに遅く、良忠が駆けつけた時は比叡山への逃亡に失敗していた。慌てた良忠は八瀬童子の手を借りて帝を笠置山に落ち延びさせた。
同時に叡山の尊雲にも扇動の咎により死罪を申し渡しをすべく六波羅の兵がせまったが、尊雲は僧兵を指揮しこの大軍を坂本にて鮮やかに撃破、姿を晦ませた。山法師達は妖術でも使ったかと噂し、敬愛する天台座主の無事を祈った。
結局、笠置山の後醍醐天皇は圧倒的な兵力に包囲され捕らえられる。その有様を、父帝の花園院から「王家の恥」「一朝の恥辱」と記された等、宮中における不人気を物語っている。そのまま隠岐島に流された。
殿ノ法印良忠も捕縛され六波羅の牢にぶち込まれる。ところがこの荒法師は夜半、その怪力にモノを言わせて錠を捻じ曲げて遁走し、密かに尊雲の後を追った。
以後、尊雲は各地に突如姿を現しては消える神出鬼没の振る舞いで幕府軍を翻弄する。
般若寺では五百騎の兵に囲まれ、本堂の大般若経の経箱に身を潜める所を目撃された。雑兵が経箱をひっくり返すと姿は見えず例の『ホーッホッホッホッホ』という笑い声だけが響く。
吉野では6万の軍勢を相手に、7本の矢を受けるが又しても笑って消える。さすがに幕府方は気味悪くなりだした。次に高野山に現れた時は途中十津川にて還俗しており、大塔宮護良親王の名乗りを上げた。令旨を発するやたちまち参ずる者が後を絶たない。
またその頃、以前より怪僧文観の仲介により後醍醐天皇と通じていた正体不明の悪党、楠木正成が河内より猛烈なゲリラ戦を展開していた。
するといかなる技を使ったか魔人は復活し隠岐の島を脱出した。その霊力は以前にも増して恐ろしく、目は赤光を放ち、舌鋒は火を噴くが如し。ついには西国鎮圧に派遣されてきた足利尊氏を寝返らせ、六波羅を全滅させてしまった。
鎌倉の抑えが効かなくなった時代背景もあり、この動きは連鎖反応を起こす。新田は鎌倉に攻め入り鎌倉幕府は滅亡した。
満を持して上洛した後醍醐天皇は上機嫌で尊氏に『尊』の字を与えた。ところがどうしたことか大塔宮が馳せ参じない。宮は何を考えているのか。
「殿ノ法印、これへ」
「御前に」
「わしの代わりに都に上れ」
「・・・宮様は・・」
「行けば必ずや厄災に巻き込まれるであろう」
「それは、いつもの千里眼にあらしゃいまするか」
「さよう。わしには見えた。帝の周りに蠢く魔性の輩多し。足利、土岐、高、佐々木、それらは皆、帝が引き寄せた者ども」
「帝はお気づきにならしゃいませぬと」
「違う。帝がかの者達を邪悪にしてしまうのだ」
案の定、良忠が上洛してみると、いきなり六波羅を攻略した折に手勢の者が狼藉を働いた、との廉で尊氏の手により配下の十名以上が六条河原に晒されてしまった。仰天した良忠は上洛はやはり厄災である旨を宮に上奏した。
いつまでも上洛しない宮に手を焼いた帝は、遂に大塔宮を征夷大将軍・兵部卿に宣旨した。仕方なしに宮は入京するが、その際には総勢20万騎にもなる私兵を率いていた。さすがの尊氏も、その親衛隊を率いる高師直も驚いたが、だれよりも肝をを潰したのは後醍醐天皇であった。二人の対面は魔人と神人が向き合う異様な雰囲気となった。
帝は御簾の奥からもわかる凄まじいオーラを発していたが、宮もまたそれを跳ね返す眼光で対峙した。居並ぶ公家も尊氏もまるで瑠璃光が漂っている錯覚にとらわれた。しかも二人とも型通りの挨拶の後に一言も発しないのだ。末席にいた尊氏は気分が悪くなったが外す訳にもいかず、ダラダラと冷や汗が背中を伝うのをひたすら堪えた。
尊氏が屋敷に帰って来ると弟直義初め高師直以下幕僚たちが首を長くして待っていたが、真っ青な顔色を見て息を呑んだ。
「殿、いかがでしたか」
「どうもこうもない。恐ろしいものを見た」
「・・・恐ろしい・・・と言いますと」
「帝も一筋縄ではいかないお方だが、宮もまた我等の手に負えるお方ではない。宮が征夷大将軍のままではこっちが危ない」
「どうなされますか。一戦交えると」
高師直が一言漏らすと、尊氏が諫めた。
「馬鹿ぁ!宮は20万騎もの私兵に守られている。負けるに決まってるだろう。しばらく様子見だ。帝も警戒されておられると見た。あのお二人親子とも思えぬ」
尊氏も優れた政治家である。宮中含め都の隅々にまで情報網を巡らせジッと待った。諜報の元締めはかのバサラ大名佐々木道誉である。道誉は武名のみならず連歌・闘茶・香道・立花に深い造詣があり、加えて派手な歌舞伎者ぶりに都の子女から宮中の女房達にまで絶大な人気があった。それをフルに使い、はなはだしきは宮中の噂をことごとく知ることができた。何しろ洛南大原野の勝持寺にあった4本の桜の大木が満開になると、その下に3mもの高さの黄銅の花瓶を置き、遠目には立花に見える仕掛けを施し、都中の白拍子・田楽師を呼んで乱痴気騒ぎに興じた。美酒に山海珍味を山盛りにし、巨大な香炉でむせ返る程の名香を焚き上げるという凝りように、都人は喝采し謡い狂った。婦女子でなびかぬものはない。
すると最近天皇の寵愛を最も受けている側室は新待賢門院という姫君であることがわかった。しかも新待賢門院は恒良親王を産んでおり、その皇子を帝位に着けるため最大の障害が大塔宮をであると思っているらしい。
尊氏は舌なめずりする思いで絹やら香やら惜しげもなく贈り続けた。そして頃合いを見て散々吹き込んだのだ。
「それがし、いかに帝のために骨を折ろうとも厭いは致しませぬが、なぜか大塔宮様の御憎しみを賜り候。毎日身の細る思いで勤めておりまするが、ひょっとして大塔宮様は帝位を望んでおられるやも・・・」
抑揚たっぷりにささやかれるとつい確かめたくなるのは人情、帝との寝物語に繰り返し尋ねる。帝は魔人である。股肱の臣が怯えるのを放っておく訳にはいかない。しかも息子とは言え久方ぶりに会ってみれば恐るべき強者になっている。そして勅命に至った。配下の20万騎を解散させよ、と。勅命とあらば是非もない。手勢の多くを所領に帰し、残ったのは殿ノ法印、光林坊玄尊、赤松則裕律師と僅かなものになった。更に帝は清涼殿の御開宴の時に護良親王を捕縛する挙に出た。二人の間には火花が散り、殿ノ法印は吠えた。
「僭越至極!」
「ホホホホホ、殿ノ法印。慌てずともよい。遠からず帝の心安んじ奉る」
「それはいつもの千里眼にあらしゃいまするか」
「帝に女難の気が立ち上っておる。その後、もののふ共も離反あり」
尊氏はこの機を逃さず、宮の身柄を確保したのちどさくさ紛れに鎌倉にいた弟直義に預けてしまった。
大塔宮は初めから坂東武者の田舎者をことごとく見下し、足利兄弟はいつ裏切るかわからないと警戒していた。しかし帝は鷹揚な尊氏をコンントロールできるのは自分だとの自負が強く、むしろ危険なのは大塔宮として、結局希代の政治家尊氏の思う壺にはまった。魔人も神人も政治家に手玉に取られたのである。
「此頃都ニハヤル物 夜討 強盗 謀(にせ)綸旨
召人 早馬 虚騒動(そらさわぎ)」
二条河原に墨痕鮮やかな落書が高々と掲げられた。
「追従(ついしょう) 讒人(ざんにん) 禅律僧 下克上スル成出者(なりづもの)」
見苦しく蠢く者をあげつらい、禅宗・律宗などにも冷水を浴びせる。
「キツケヌ冠上ノキヌ 持モナラハヌ杓持テ 内裏マシワリ珍シヤ
賢者カホナル伝奏ハ 我モ我モトミユレトモ」
ドサクサと官位にありついた成り上がりを貶し、
「為中美物(いなかびぶつ)ニアキミチテ マナ板烏帽子ユカメツヽ
気色メキタル京侍 タソカレ時ニ成ヌレハ ウカレテアリク色好(いろごのみ)」 その田舎者ぶりをこきおろす。
「ハサラ扇ノ五骨(いつつぼね) ヒロコシヤセ馬薄小袖
日銭ノ質ノ古具足 関東武士ノカコ出仕」
東国侍の風俗を嘲笑う。
後年、庶民の怨嗟の声との解釈もなされたがさにあらず。鎌倉に引かれる直前に大塔宮の命を受けた殿ノ法印が叡山の僧に仕立てさせた最後通牒だったのだ。
鎌倉では尊氏の命を受けた直義が手ぐすね引いて待っていた。この弟は、豪胆無比でともすればあっけらかんとした気前の良さとおおらかなところのある兄尊氏と違い、厳格にして果断。万事筋を通すのだが猜疑心が強く粘着する。尊氏は島流しくらいのつもりだったのだが、宮の扱いは苛烈を極めた。背伸びもできない湿気の多い土牢に閉じ込め、共に落ちて来た殿の法印等の側近達とは顔を合わせることを禁じた。更にむごいことに、愛妾である雛鶴姫のみ月に一度土牢に通わせるという仕打ちである。その日は土牢を見分させる鬼畜の振る舞いまでした。
さしもの宮もげっそりと痩せこけ日に日に神人の面影は薄くなる。
運悪くその半年後、滅ぼされた執権北条高時の一子、時行が残党を率いて一矢報いんと鎌倉に雪崩れ込んだ。中先代の乱である。時行にすれば親の弔い合戦、怨念の塊のような鬼神の攻撃に直義は溜まらず鎌倉から退却する。その混乱の最中に後顧に憂いを絶つとして七人もの刺客を差し向けた。はたして宮は覚悟を決め、開け放たれたにもかかわらず牢から出てこない、いや既に足が萎えて自由歩行ができなくなっていたのだ。暗い土牢に恐る恐る押し入った一人目の刺客は絞殺された。その首に飛びついた淵辺義博が太刀で喉元を刺そうとする、宮は振り向きざまに剣先を噛み折った。こぼれた太刀でなんとか首を取り、這い出して見分しようとした途端、見開いた目が動き淵辺を見据えた。
「ギャーッツ!
思わず放り出し逃げ去った。
大塔の宮の千里眼はその後ことごとく当たり、後醍醐天皇は南朝に君臨するも二度と都に上ること叶わなかった。その魔人天皇に時に従い時に反目しつた足利兄弟も終いには相争い直義は毒殺された。直義の天敵だった親衛隊長たる高師直は観応の擾乱によって戦死。室町幕府を開いた尊氏にしても最期は背中の腫れ物に苦しめられた。廱(よう)即ち黄色ブドウ球菌による毛嚢の化膿の集合体である。拳大に腫れあがった肉腫にはハチの巣のような穴が開き血の混じった膿を脈と共に吹きだすという恐ろしい苦しみの中で死んだ。
帝の女難の相は結局のところ大塔宮の方に降りかかったのだった。この混乱を最後まで生き残ったのはバサラ者の佐々木道誉だけであったが、婆沙羅こそ乱世に会っての華であり、平時には趣味の悪い毒でしかないのである。
ところで、恐怖のあまり投げ捨てられた宮の首はどうなったのか。
大混乱の最中に密かに土牢に駆け付けたのは宮に従って来た愛妾の雛鶴姫と供の者数名。雛鶴姫はそこではっきりとした宮のカン高い声を聴いた『雛鶴、こちらじゃ』。その声に導かれるように藪に分け入ってみると、果たして変わり果てた宮の首が転がっていた。ああ、宮様、と駆け寄って泥と血にまみれた首を取り上げると、宮の瞳ははっきりと雛鶴姫を見つめたのだ、口には噛み切った剣先を咥えたままに。
「おいたわしや」
水で洗い清め薄化粧を施すと、生前の面立ちが蘇り生きているがごとく艶やかであった。
雛鶴姫と供の者の数名は途方に暮れたが、ともあれ鎌倉にいてはどうなるのか分からない。ひとまず都を目指そうと鎌倉街道を北に進んだ。
戦の直後とあっては落ち武者狩りのの野伏りや武装百姓が金品目当てにそこかしこに潜んでいる。そこを僅かな人数での逃避行は危険極まりない。そして、実は雛鶴姫は宮の子供を宿していたのである。
武蔵の国を横切り、相模の津久井を抜けたあたりで案の定野盗の一団に目を付けられた。人数の少ない上に女人の遅い脚、たちまち取り囲まれた。
「クククク。金目の物とその女を差し出せ。命は助けてやる」
頭目とおぼしき大男が笑みを浮かべて凄んだ。
ところが雛鶴姫は少しも動じない。にこやかに供の者を促し、葛籠の中から丸い円筒状の物を取り出すと、捧げ持つようにして中の物を取り出した。
「なんじゃ、それが自慢の宝物か」
うそぶきながら近づいた男はその物を見た途端『ぎゃああああ』と叫んで後ろに倒れた。
何とそれは生首で、しかもその瞳ははっきりと男を見つめると虹色の妖しい光を発した。他の野盗共も『ヒイー』と怯えた声で飛び散るように姿を消した。
一行が甲斐の国に差し掛かかった頃は旧暦の年末、雪のチラ就くほど寒かった。人里離れた渓谷沿いで、間の悪いことに雛鶴姫が産気づいてしまった。
急ごしらえの褥(しとね)で難産の末皇子を出産したのだが、旅の疲れと寒さにより哀れにも母子は亡くなってしまった。
あまりの無常さに残された従者はこの地を無生野(むしょうの)と名付けて雛鶴姫と皇子を手厚く葬った。今日まで伝えられる無生野の大念仏という行事は、護良親王の神霊と雛鶴姫母子を弔うものとして、その地で帰農した従者達によって残された。現存する雛鶴神社は母子を祀っており、石舟神社は大塔宮を祭神としている。尚、真偽のほどは分からないが雛鶴姫が押し抱いていた宮の首も石船神社に残され、年に2度公開されている。現在、無生野の大念仏は国の指定無形文化財でありユネスコ無形文化遺産への登録が提案されている。
この話には続きがある。護良親王の皇子である葛城宮綴連王(つづれのおう)、陸良もしくは興良親王は南北朝の戦乱の中に行方不明となったが、実は雛鶴姫の没後20年ほど経ったこの地に現れ雛鶴姫と兄にあたる皇子の話を聞かされる。そしてこの地を定めの場所として居住し、一子五孫を得て天寿を全うしたという。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
新撰組外伝 十津川の刺客
2019 AUG 10 6:06:12 am by 西 牟呂雄

大和の国、十津川は神武東征の際、長髄彦に一旦敗れ紀伊半島の南に廻り、熊野・吉野を経て大和に北上したルートと言われている。その時に八咫烏が道案内に現れた伝説があり、土地の人々は未だにそれを信じ誇りに思っている。秘境と言っていいほどの山岳地帯なのだが、日本史にはしばしば登場する。
天武天皇が吉野に隠棲した後に壬申の乱を起こすが、その際に十津川から兵が出ている。保元の乱でも崇徳上皇について戦い、南北朝の騒乱では無論後醍醐天皇につく。時代が下るとなぜか家康に従って大坂夏の陣にも参戦。いずれも千人程度の壮丁が山を下りてはせ参じている。
徳川時代を通じて天領なのだが、幕末に至っては尊王の志を抱いた輩が御所の門の守りを固める。言わば尊王専門の傭兵部隊である。京より弾け飛んできた天誅組の騒乱の際には初めはこれに従い、後に離反した。
そして壬申の乱の昔より年貢御赦免、無税なのだ。もともと水田開拓が不可能なせいもあり、普段は狩猟生活でもしていたのだろう。剽悍な戦士であったに違いない。
幕末の御所警護に際しては、”菱に十字”の紋を掲げた“藩邸”のような家屋を京に構えていた。文久3年(1863年)、中井庄五郎が御所警衛にあたるため二度目の上京をする。床五郎は十津川で見よう見まねの居合を身に着けていた。
十津川は藩でもないただの山間の地名に過ぎないエリアだが、その人となりは大小を挿した武士モドキの郷士である。そして自分たちは都の帝と直結していると思い込んでおり、底抜けに明るかった。
時に、幕府が横浜他を開港し、大方の世論は公武合体だった。しかしながら京には、攘夷派・倒幕派・その他がうじゃうじゃしており、とりわけ御所周辺では有象無象の脱藩浪人が多い。ちなみにこの年は薩英戦争が起きている。
ある晩、床五郎は那須盛馬と酒を飲み、したたかに酔った。那須盛馬というのは脱藩した土佐の郷士で、大坂において焼き討ち事件を起こしかけ、十津川で身を隠していた旧知の人物だ。
「那須さん。ほら、肩を貸しますよ。そんなに酔って大丈夫ですか」
「おまんの方がかえってワシによりかかってるがじゃ」
四条を笑いながらヨタヨタ歩いていると、向こうからも大声が聞こえ、同じように泥酔している三人組がやって来る。体格のいい男が肩をそびやかして歩いているのだが、高瀬川の橋上ですれ違いざまに床五郎達がよろけて肩が触れた。那須が勢いよく喚いた。
「無礼者!ぶつかっておいて挨拶ないがか」
「なにー、どこの田舎者だ」
関東言葉である。那須は那須でお尋ね者の分際で酒の勢いが止まらない。
「そっちこそどこのもんじゃ」
まずい展開に床五郎が思わず割って入った。
「御免、別に悪気はありません」
言った途端に相対した男の凄まじい殺気を感じ、床五郎も思わず身を正した。度胸は座っている、実は1年程前にさる事情から人を切ったことがあった。しかし目の前の男はその時に感じた雰囲気とは比べ物にならない気配が漂っていた。
「テメーは猿(ましら)か」
床五郎は体毛の多い体質で、もみ上げから顎にかけて髭が密集していた。そのことをなじられたかと顔色を変え、腰を落として居合いの構えを取った。
まずいことに血の気の多い那須は既に刀を抜いている。すると残り二人のうちの一人がスラリと抜くと下段に刀を落とし、一歩踏み出るとアッという間に那須の刀を跳ね上げ小手先を切った。更に踏み込んで上腕、脛と明らかに急所を外して遊んでいるように捌いた。
一方、その様を横目にしながら抜刀の機会を計っていた床五郎は、相手に気圧されながらジリジリと後退し、堪らず抜いた。瞬時に払われ、後ろに後ずさりしたところ、もんどりうって川原に転がり落ちた。まるで腕が違う。庄五郎は生まれて初めて恐怖した。
「斉藤さん。その辺でいいでしょう。止めを刺すとただの喧嘩じゃすまなくなって、下手するとまた歳さんの『切腹しろー』が始まりますよ、ハハ」
一番若い男のバカみたいに明るい声が聞こえた。斎藤と呼ばれた男は、
「まったく、沖田君にかかっちゃ副長も『歳さん』か」
と薄気味悪くつぶやいて刀をパチリと納め、もう一人に呼びかけた。
「永倉さん、酔いが醒めた。飲み直しましょう」
三人は庄五郎達をほったらかしにして、何事もなかったように闇に消えて行った。
「那須さん・・・那須さん!大丈夫ですか」
庄五郎は泥だらけになりながら這い上がって、倒れている那須を助け起こした。
「やられた。・・・・ウッ、なんじゃあいつ等。そろいの羽織りで」
「凄い出血ですよ。きつく縛らなきゃ」
やっとの思いで知り合いの家にもぐりこんで手当を受けた。
急を聞いて十津川屋敷の者が飛んでくる。
「一体誰にやられた」
「そろいの羽織りを纏った三人組です。それが強いの強くないのって、那須さんも歯が立たない。拙者ははねとばされました」
「そろいの羽織りとは」
「浅葱色(あさぎいろ 薄い藍色)で袖の先が白抜きのだんだら模様でした」
「なにい・・・・それは新撰組だ!まずいぞ那須、お前は大坂の焼き討ち未遂で手配されているんだぞ。庄五郎、新選組の誰だったかわかるか」
「私に向かって来たのは斎藤と呼ばれていたと思います。そいつが那須さんを切った男を永倉さんと呼んでいました。もう一人の若いのは、確か・・・沖田かと」
「アホ!そいつ等は特に腕の立つ人切りだ。今度出くわしたら命はないぞ。那須、お主は薩摩にでも匿ってもらえ、名前も変えろ」
「イテー、イテテ焼酎がしみるー」
結局那須は薩摩藩士に紛れ込み片岡という変名を使った。
暫くは新撰組の目をかいくぐる様にしていたものの、床五郎は天性の明るさと朴訥な性格から他藩の連中に愛された。とりわけ土佐弁丸出しで熱心に語りかける青年が可愛がり、床五郎も彼の話には惹かれた。
大ボラだか本当か良く分からない話をしては人を驚かせていたが、内容は幕臣の勝海舟からの受け売りで、海軍伝習所で聞いた話である。
「おまんら十津川郷士ゆうちょるのは土佐の郷士とはちくとちごうとるぜよ。土佐にゃその上に上士ちゅうのがおってえばっとるがじゃ。十津川っちゅーのは殿様もおらんとええとこじゃの」
分かりやすい例え話を引き、諸藩の事情から世界の様子を聞くと、床五郎は目を輝かせた。青年とは坂本龍馬のことである。
「坂本先生、それでは日本はどうしていけばいいのでしょうか」
「幕府も攘夷もないがぜよ。みーんなでワシら日本人じゃっちゅーて世界に繰り出すきに」
「わたしのような山猿も連れて行っていただけますか!」
「何も関係ないがじゃ。十津川は藩でもないからかえって自由気儘に行けるかわからん。ただ船酔いには慣れてもらわんとの、ワハハハハハ」
不思議なことに十津川には関西のイントネーションがなく(それぐらい隔絶されていたということなのだが)イデオロギーは尊王以外に攘夷も倒幕もない。砂が水を吸うように吸収し、龍馬の率いる陸援隊に傾倒していった。
「何でもやります。何卒ご教授下さい」
龍馬は目を輝かせて言うこの青年を気に入り、所蔵の佩刀を一振り譲っている。
ところがその龍馬が何者かによって暗殺された(近江屋事件)。11月15日だった。
龍馬の暗殺を聞いた海援隊の陸奥陽之助(後の外務大臣。宗光)は怒り狂った。
「やったのは新撰組だろう。この日本の大転換を台無しにするのかぁ」
陸奥は紀州西条の脱藩で、神戸海軍操練所以来の龍馬の盟友である。
「手引きをしたのは伊呂波丸事件で賠償金をブン取られた紀州藩公用人の三浦休太郎に間違いあるまい」
「陸奥さん、下手人は十津川郷士を名乗って坂本先生を訪ねたという噂は本当ですか」
「本当だ。中岡慎太郎が今際の際にそう言って死んだそうだ。十津川を名乗ったのは坂本さんを安心させる為だろう」
床五郎は怒りに震えた。名誉ある十津川の名をかたった卑怯な振る舞いに吐き気がする。
後にカミソリ大臣とまで言われた怜悧な陸奥も、この時ばかりは自分を見失い、海援隊・陸援隊を率いて三浦を討つ決心を固めた。床五郎はすがるように志願した。
三浦の居場所は直ぐに知れた。七条油小路の旅宿天満屋である。
12月7日、十数名の襲撃部隊が天満屋に寄せると、驚いたことにそこでは酒宴が開かれており、笑い声が2階から聞こえる。
有無を言わせずに乗り込んだ床五郎はそのまま階上に駆け上がり襖を開け放った。宴席の騒がしさが一瞬消えると三浦と思しき武士に、腰を落として『三浦氏は其許か』と言うなり斬りつけた。「グワッ」と叫んで三浦が横倒しになると、後から陸援隊・海援隊の有志が雪崩れ込んで来て大混乱となった。
その中で素早く配膳を蹴飛ばして抜刀した男の顔を見て、床五郎は目を見張った。あの四条の橋上で見た新撰組隊士、斉藤と呼ばれた男が不敵な笑みを浮かべている。宴会をしていたのは三浦の護衛に当たっていた新撰組だったのだ。遮二無二切りかかって手ごたえを感じた。と思った刹那に複数の太刀が振り下ろされ、床五郎は瞬時に絶命、世に雄飛する夢も又、都の漆黒の空に溶けた。
庄五郎の一撃は新撰組最強の斎藤一をかすめはしたが、斎藤はビクともしない。喧騒の中で剛剣を奮ったが、背中から切り付けられる。斎藤が声も出さずに振り返ると隊士の梅戸勝之進が傷を負いながらその男を仕留めていた。
格闘小半時、知らせを聞いた紀州藩士等が駆け付けた時には陸奥以下は庄五郎を含め4人の死体を残して逃げおおせた後だった。新撰組にも二人の死亡者が出ている。斉藤は用心深く宴席にも鎖帷子を着込んでいたため、かすり傷も負わなかった。
陸奥の維新後の栄達は良くご案内の通りだが、三浦もまた貴族院議員を務め、第13代東京府知事にまで出世した。ただし疑獄事件により失脚する。
片岡源馬と名を変えた那須盛馬は明治天皇の侍従となり、その命により千島列島を探検、北端の占守島に日本人として初めて上陸した。
斎藤一は会津藩と合流し斗南移封まで共に行動後、西南戦争に抜刀隊で参加し大正四年に死んだ。
中井庄五郎が21才で命を落とさなかったらどれ程の人材になったのか、それは分からない。そして時代に踏み潰された佐幕派にもまた確かな人材はいたはずである。
十津川郷士は維新後全住民が士族に遇される栄誉に浴する。
後に有名な明治22年の大水害で壊滅的な被害を被り、約3千人が北海道に移住した。空知地方の新十津川村であるが、中井家は北海道には行かず今もその血筋は十津川に脈々と続いている。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
令和亜空間戦争
2019 JUL 28 1:01:04 am by 西 牟呂雄

御世変わりには必ず時空が歪み、不穏な怨霊が跋扈する。この目出度い令和の日本のパラレル・ワールドでは宿命の対決が始まろうとしていた。
怨霊とは不思議なもので、その地位を脅かすような次の挑戦者が亜空間に来なければおとなしいものなのだが、新規の参入があると時空の歪みによって亜空間から現世の人物に憑依して霊界戦争を引き起こしてしまう。そして久しぶりに強力な怨霊が出現したのだ。
俗名は内田裕也。言わずと知れたロック界のドンが成仏したのち、あの世で先に逝っていた妻、樹木希林と霊界戦争を起こして負けかけていた。その時に御世代わりが起こったため、亜空間から現世に怨霊として復活し、現副総理兼財務大臣の麻生太郎に憑依してしまった。
無論、お江戸の昔から日本一の怨霊である平将門は黙っていない。自ら時空の歪みを通り抜け、麻生太郎に内田裕也が憑依した事を知り、小沢一朗に姿を変えたののだった。
おりしも選挙が始まる。麻生裕也は吼えた。
「年金がどうしたってぇんだ。例えば家族が力を合わせてやりゃ~どうってことねえだろう。年金はそもそも兵隊さんが戦死した後に家族が苦労しないように設計されたのが最初だよ。それが戦争がなくなってみんな長生きするようになったから制度をかえたり福祉を厚くしたりしてるんであって、90も過ぎたお年寄りが年金以上の贅沢をするはずがねえだろ」
自民党幹部は慌てたがもう遅い。
麻生裕也はここまではやりたい放題で、将門が現世に復帰して小沢一朗に憑依していることに気付いていなかったのだ。
従って麻生裕也は、まずその破戒本能を身内に向けた。まず安倍総理の『今後10年程度は増税する必要がない』との発言に、「『私』という一人称で言っている」といやがらせを言い、選挙の足を引っ張りながら配下の財務官僚の機嫌をとった。ここで安倍政権に頭を抑えられ続けた財務省の反安倍感情を煽ったのだ。
ただ、この時点でヤバいと思った自民党執行部は麻生裕也の応援を封じ込める作戦に出た。
一方、国民民主党をたぶらかしていた小沢一朗は将門に憑依されてからはかつての『剛腕』と称された図々しさを蘇らせ、選挙に対する最終秘策をめぐらせた。
ただ、衆参同時選挙が見送られてしまい、争点があいまいになって自分のお膝元の岩手で自民党に負けかけたため、暫くは地元対策に追われた。そして地下に潜行しながら秘策を練っていた。
それは恐ろしいことに共産党との合流であった。
野党協力の名の元に一人区に統一候補を立てたが、秘かに志井委員長と手を握り共産党の候補者を擁立することに暗躍した。そしてあわよくば風前の灯の国民民主党と共産党を合流させ、新たな党名を『国民党』と変更し看板を掛けかえる奸計を巡らせる。
しかし、いかに霊力が強力でも全国の生身の人間の投票行動に影響は与えられない。小沢将門が姿を消して暗躍したものの、全体としては与党である自民・公明及び改憲勢力の維新が過半数を超える結果となった。
麻生裕也は次の内閣改造に備えてヒートアップし、暴言が飛び出す始末。
『消費税の増税なんか誰も気にしてなかったのが今度の選挙でよく分かっただろコノヨロウ。憲法改正だってやりたがってる野党のやつらを10人も引っこ抜きゃオチャノコサイサイだぁ。韓国にはまだ通過スワップ拒否という奥の手があんだぜ、ロケンロール、よろしくゥ』と喚く。
すると、小沢将門は選挙後に直ぐに動く。不遇を囲って爆発寸前だった石破茂や岸田に禁じ手を使った。『このままでは安倍が四選してしまってあなたの出番は無くなる。安倍は次に必ず小泉進次郎か野田聖子を選ぶ。総理のメは完全になくなるどころか、もう一生入閣すらできないだろう』と吹き込んだのだ。
怨霊同士は現世においては猛烈なマイナス・エネルギーの放射で強く反発する。即ち周りの邪気を吸い込んで肥大化し、互いに相手を打ち消そうとする。
この時点で麻生裕也も小沢将門の正体に気が付いて、これこそ本当の敵であると悪意をつのらせるのだった。
次の決戦のタイミングは両者で一致している。それは本年10月に世界各国の代表を招く「即位礼正殿の儀」と11月の神事である大嘗祭が終わった年末で、その際にまた大きく時空が歪むタイミングだ。
そこで互いの息の根(怨霊だから息はしていないが)を止めるべく、麻生裕也は安倍総理に解散を迫っており、それまでに小沢将門は新生国民党をまとめるべく策を練って、玉木雄一郎と大塚耕平に吹き込んでいる。年末衆議院解散が悪霊の総決算。知らぬは国民ばかりである。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」。
敗れざるを以って徳となす 庄内の鬼と夜叉
2019 JUL 1 5:05:23 am by 西 牟呂雄

庄内藩は徳川四天王の酒井忠次を藩祖と仰ぐ名門で、江戸中期の藩主酒井忠寄が老中として幕閣に参じている。
北越出征軍は既に仙台を出立し山形盆地の天童に達した。藩論は沸騰する。将軍は恭順しているが、このまま軍門に下って果たして筋は通るのか。幕命だったとはいえ、江戸の薩摩藩邸を焼き討ちしたのは庄内藩預かりの新徴組であり、残党は藩内の鶴岡にきている。
新政府軍(出兵させられた天童・山形・その他の各藩と薩摩・長州の連合軍。この時点で奥羽列藩同盟はまだない)に対し庄内藩兵は最上川を挟んで対峙した。もはや戦闘は避けられそうになかった。
驚くべきことに庄内藩には長州における奇兵隊のように、民兵とも言うべき部隊まで編成されるほど士気が高い。更にはかの本間家の財政支援を受け、最新のスペンサー銃まで装備していた。
精鋭二番大隊を指揮する酒井玄蕃(本名、了恒のりつね)は、はやる幹部を前に落ち着いた声で告げた。家老職である。
「上様は大政を奉還され恭順された。新政府とやら、何故大軍勢を仕向けるや。道理が通らねば正すのみ。世に知らしめよ、北斗の姿如何に映るや」
傍らの小姓が満身の力を込めて高々と旗を掲げた。
一同から「おぉ~」と低いかすかな声が広がった。
「これなるは道理を正す『破軍星旗』なるぞ。この旗の下、庄内健児の意気地あり」
北国の兵は歓声などは上げない。むしろ押し黙って頷くのみである。
ところが、この儀はチト効き過ぎた。玄蕃が制したにもかかわらず、一部が川を迂回して渡り猛烈な切り込みにより新政府軍の前衛を蹴散らしてしまった。
新政府軍といっても実際の戦闘を経験しているのは京都や鳥羽・伏見での実績がある薩摩・長州くらいで新政府に無理矢理出兵させられた東北諸藩の軍勢は突撃を受けると一目散に敗走を始める始末。天童藩主はかの織田信長の末裔だが、城を捨てざるを得なかった
慌てた玄蕃は部隊に撤収を命じ即座に領内に引き揚げたが、あまりにあっけない勝利に意気が上がるばかりである。
新政府軍は後に首相となる長州の桂太郎、薩摩の猛将黒田清隆等がいきり立ち、本腰を入れて庄内攻撃を開始した。
しかし巧みに地形を利用した玄蕃の用兵と一斉射撃の前に出ては負け、敗走を繰り返す。
いつしか新政府軍は敵将を『鬼玄蕃』と呼びならわし、戦場に破軍星旗が揚がると恐れた。
酒井玄蕃、二十歳を幾つか過ぎた若者は、漢詩を詠み、書を嗜む教養人だが一旦戦場に立つと決して怯まない。ただ肺が悪かった。
戦闘は続き、新庄・久保田・秋田・米沢と各藩が次々に脱落していく中、床内だけは全く敵を寄せ付けない。新政府側は20回挑んで全て跳ね返された。
現有戦力では敵わないと見た新政府軍は、首都の守りを固める佐賀藩を秋田にまで呼び寄せた。指揮を執るは鍋島茂昌。佐賀鍋島支流の武雄藩主で、彰義隊を殲滅させたアームストロング砲を引っ下げて乗り込んできた。幕末最強の火力部隊である。
雄物川付近の刈和野・椿台を戦場に死闘が始まった。双方全く引かない。鍋島茂昌は砲兵隊を指揮しつつ『鬼玄蕃とやら、いかほどの者。目に物みせてやれ』と激を飛ばしていた。
折り悪く玄蕃は風邪による高熱に伏していたが、止める家臣を叱咤して『輿に乗せよ』と出陣し、劣性に立たされた体制をかろうじて持ち直した。
宿営に戻る際も輿の上で端坐していたが、周りには最前線で負傷した兵達が引き揚げて行く。その中に飛び抜けて背の高い(五尺六寸約170cm)総髪の若侍が左足を引き摺っていた。
「そこもと。ケガは大丈夫か」
との声にその者が振り向いた表情を見て玄蕃はその美貌に少し驚いた。若侍は声の主が二番大隊を率いる玄蕃であることに気付きサッと伏した。普段は話などできるはずもないが、高名な司令官の顔くらいはわかった。
「よい。面を上げよ」
「ハッ。拙者のこの足であらば心配御無用。先の江戸薩摩藩邸を焼き討ちした際の浅手ゆえ。何の支障もございませぬ」
高く澄んだ声に色白で顎の線も柔らかい。光る目、そして喉仏がない。
「名は何と申す」
「新徴組。中沢琴と申します」
「おっおなごか・・・・」
「恐れ入りまする。それよりお熱があると伺っております。早う」
「なんの、もうひと合戦じゃ」
その凛とした佇まいに琴は思わずひれ伏した。
一旦休んで一息入れている際に、玄蕃は思い出したように側近に尋ねた。
「新徴組に中沢というおなごの隊士がおるのか」
「ハッ。物凄く腕が立つそうで、先の合戦では逃げ遅れて数十人に取り囲まれた中を血路を開いて突破してきたようです」
「まことか。おなごの身でなにゆえに剣を使う」
「あれの兄が隊士で、その縁のようです。天狗剣法と言われる上野(こうづけ)法神流の達人と聞きました。それにあの背丈では嫁入り先も・・・。むしろ色男と勘違いした娘共が勝手に熱を上げる始末とか」
「ハハハハ、それは愉快じゃ」
久しぶりに笑顔を見せた。側近たちは風邪をこじらせている玄蕃の気を少しでも和らげたかったのでホッとした気持ちになり、つい言った。
「お側に呼びましょうか」
「合戦の最中に痴れたことを!大馬鹿者!」
一方の琴はしばらく動くことも出来なかった。
同僚の隊士達は、さすがに疲れたのだろうとそっとしていたが、兄である貞祇 (さだまさ)は肩を貸そうとしてギョッとした。琴の顔から血の気が引いていた。
「お琴、何事か」
「兄上・・・・」
「何とした」
「あのお方のために、琴は夜叉になりまする」
貞祇は尋常でない目の色に怯んだ。
それ以降、琴は鬼神の働きをする。徴組組隊士であるため、いわゆる正規軍ではない。従ってもっぱらゲリラ戦に投入された。
膠着状態の前線を迂回し側面から突く、撤退と見せかける際には草に埋もれ泥に臥せってやりすごし背面を襲う。切り込むこと三度にもかかわらず、かすり傷一つ負わなかった。
領内には一兵も入れなかった庄内藩も、会津までもが降伏・開城したことを知り、ただ一藩で抵抗はしかねる。藩主酒井忠篤の元、評定は一瞬にして決まった。
「玄蕃。この難局を如何にせん」
「殿の御下命あらばこそ。われら弱卒雑兵ことごとく城を枕に総討ち死にが最もたやすき道。しかるに庄内健児未だ怯まず」
すると忠篤は静かに口を開いた。
「玄蕃よ。敗れざるをもって徳となせ」
庄内武士は議論などしない。
組織力とはトップの判断が末端までいかに早く伝わるかで分かる。新徴組に伝わったのはその直後だった。
城明け渡しに際して、新政府軍は作法に則り粛々とやってきた。その隊列を城下の辻にて燃える瞳で見つめる目があった。琴である。
勝ちを収めてもいないくせに鶴岡に乗り込んで来るとは、一体どんな者が率いているのか。その姿を見ておきたいと目を凝らすが、一向にそれらしき者は現れない。
北越出征軍の総指揮官として庄内入りした西郷隆盛は、黒田清隆に「政府軍に勝ちに乗じた醜行があってはないもはん」とのみ告げただけで、鶴岡城受領には姿を現さなかったのだ。
琴は納得がいかず、そう広くもない城下の街道筋へ歩いて行った。
涙が頬を伝っている、何故だ、何故私はこんなに泣けるのか。
すると数名の新政府軍と思われる兵士と坊主頭で着流しの大男がいた。琴は帯刀している。時節柄、兵士は警戒して刀に手をかけたのだが、琴の美貌と滂沱の涙の跡に気が付き声をかけた。
「おやっとさーでごわいもした、よかにせどん。わいどんなまごちつよか」
薩摩の兵だった。薩摩人は敗者に憐憫の情をかけるのが常である。庄内藩士の激闘を称えたつもりの一言なのだが、琴はその薩摩訛りが分からず、危険を感じた。すると着流しの巨漢が
「おはんら、よさんな。こいはおごじょでごわそ」
と笑顔で言った。これも分かりかねたが、全く敵意のないことは分かった。
「おごじょ、とは」
「こいはあいすまんこつ。かごまんことばで『おなご』のこつごわ」
一同は一様に驚き興味深げに琴を見た。
琴は琴で坊主頭の大入道の巨眼を見つめた。するとその男ゆっくりと言う。
「おはん、うではたつじゃろ。じゃっどん、もう人は切らんでもよか。また切るこつもなか。そゆ世ん中にないもした」
実は思いつめていた。女の身ゆえ切腹能わず。喉かき切るくらいなら敵将に一太刀浴びせての後に果てよう、と刺し違える覚悟だったのだが、男の一言で風に飛ばされたように体が軽くなる気がした。
「おいたちもこいで帰りもす。気をひろうもちやんせ。ごめん」
そう言うと、小隊は徒歩で隊列を組んで去って行った。
薩摩の小隊はずいぶんと進んで小休止を取った。
「いや、せご先生。めずらしかおごじょで」
「ふむ。鍋島どんの前衛を切り崩したんがおごじょじゃっち聞いちょった」
「あんおごじょごわすか」
「間違いなか。人でも切ろうとしちょったろ」
「誰をな」
「おそらく総大将をば討ち取ろうち。じゃっどんあん目では人は切れん」
「なして」
「おはんらもうとか。あいは恋ばしちょる目ぞ」
「恋!」
「わっはっはっは」
中沢琴は実在の人物で、記録で確認できる新徴組の女性隊士である。新徴組にはあの沖田総司の義兄である林太郎も在籍した。
以下は世に知られた話。維新後庄内は西郷の徳を称えること甚だしく、かの「南洲翁遺訓」は下野した西郷を訪ねた庄内藩士達によって残された。玄蕃自身も鹿児島に行っている。その後、私学校に在籍した二人の庄内藩士、伴兼之と榊原政治は西南戦争で戦死している。
更には明治22年の憲法発布に際して西南の役の西郷の名誉が回復すると、旧藩主酒井忠篤は発起人に名を連ね、上野の西郷の銅像を建てた。
また、薩摩藩士大山格之助(西南戦争時の鹿児島県令)は玄蕃に東京で会い『あの鬼玄蕃の勇名をほしいままにした足下が、容貌のかくも温和で婦人にも見まほしい美少年(よかちご)であろうとは」と慨嘆したそうである。
琴は、兄とともに群馬県沼田に帰郷した。大柄なうえに年も20代後半。当時で言えば大年増ではあったが、その美貌ゆえに縁談もあった。しかしながら終生独身を貫いた。
玄蕃に惚れ、戦に負け(敗北ではないが勝てなかった)、鬱屈した心を薩摩の肥大漢に吹き飛ばされたためである。しかしその薩摩人の大男が、敵将西郷隆盛だったとは生涯知る由もなかった。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
ジェネラル・ザ・ライジング・サン 朝日将軍木曽義仲
2019 APR 5 6:06:16 am by 西 牟呂雄

義仲が三年程暴れ回って見せているうちに、いよいよ平家は十万人もの大軍で討伐に乗り出し北陸に押し寄せて来た。
以仁王の令旨に応えて平家討伐の挙兵をしてみれば、戦の何と簡単な事か。やれば勝つのだから止められない。勝てば年貢の取り立てに苦しんでいた連中がお追従を言いに寄って来はするが、義仲にはうっとうしい限りでしかない。
源氏の再興等と言われても、そもそも義仲の父義賢は兄の義朝と一族でモメた挙句に義仲にとっては従兄弟に当たる悪源太義平に殺されている。鎌倉の頼朝に加勢する義理もヘチマもない。
この時代、武士といっても江戸期に形而上発達した武士道など無く、言ってみれば傭兵集団だから筋目もお題目もない。平家がまとまっているのも清盛以降の話である。義仲にとっては単に戦が面白いだけだったのだ。
だが平家討伐の令旨を出した当の以仁王は計画がバレて忙殺されてしまい、その遺児である北陸宮が越前に落ち延びてこられたのを庇護したため、一種の正当性が生まれた。
側近の義仲四天王、今井兼平、樋口兼光、根井行親、楯親忠と愛妾の巴御前を呼んで言った。
「大軍を率いているのは平重盛の嫡男、維盛だそうズラ」
「ホホッ。都ズレした平家の公達なぞ恐るるに足らず」
「これ、巴。手勢は少ねぇラ。そうなめんじゃねぇ」
「殿こそ目が輝いてござ候。して、いかなる陣立てで」
「倶利伽羅峠に誘い込む。オミャー等は身を潜めていろ。ワシが立ちはだかって名乗りを挙げたら後ろに廻りこんで追い立てる側、と山側から射掛ける二隊に分かれて派手にやれ。地獄谷に放り込んでやるラ、おもしれーぞ」
「承って候。さてどう陣割りをするか」
「そんなのは任す。四天王は下がって良い」
「ハハーッ」「ハハーッ」「ハハーッ」「ハハーッ」
「巴、これへ」
巴御前は年の頃二十歳は過ぎた当時で言えば大年増ではあるが、広い額、切れ長の大きな瞳が異様に光る美貌。大力強弓を引く強者のため、やや肩が広く二の腕などは盛り上がるがごとくであったが、義仲はそこにまで色香を感ずるほどの惚れ込みようだった。情を交わすたびに互いの霊力が憑いたように力が沸き上がり、二人でいれば実際に負けなしであった。
事実、翌日の倶利伽羅峠では迎え撃つ義仲に平家の矢は当たらず、傍らで弓を引き絞る巴の矢は一本で二人の兵を射抜いた。そこへ四天王のゲリラ部隊が切り込むと、狭い峠道から平家軍は次々と谷底に落ちて行き、たちまち総崩れとなった。
義仲は更にこれを追いまわそうと単騎突進したところ逃げ遅れた平家の兵が槍をしごいて後ろから突きかかろうとした。
「殿!危ない!」
振り向くと、巴が両脇に首を抱えるように二人の雑兵を締め付けており、そのままもがき苦しんでいる声はしばらくして『ゴキッ』という音がすると消えた。
「おうっ、あっぱれなる怪力」
「後ろにも気を配りなされ。オーホッホッホ」
美貌と舞いの姿の見事さから桜梅少将とよばれた平維盛は、あっという間に蹴散らされ、後に平家が都落ちした際に謎の自殺を遂げる。
越中の宮崎に御所を構える北陸宮から即座にお召しがあり、上洛せよとのことであった。
「都へ行けとの仰せズラ」
「易きこと」
「平家を追っ払うのですな。痛快至極」
「それどころじゃねえ。宮様は帝になるラ」
「何と!」
「だがのう、戦さはおもしれーけど都に行ってワシ等が政治(まつりごと)なんざできるわけねーラ」
「しかし都のオナゴは美しいと評判がたけー」
「ワシは巴がおりゃええ」
「オーッホッホッホ」
結局のところ大した目算もないままに勢いで京に進軍した。
すると不穏な気配を察した平家は三種の神器ごと安徳天皇を擁して西国に逃げ出すのである。ところが後白河法皇は京に留まり義仲を受け入れる。
入京するとすかさず法皇が座す蓮華王院に参上した。
法皇は側近の摂政九条兼実を従え謁見に応じるが、この時点で義仲は官位がないため地下人扱いだった。
「義仲。ようやってくれた。待ち焦がれておったのや。おう、おぅ、懐かしい源氏の白旗や。どんなに懐かしかったか。あの憎い平家の止めを刺してたもれ。源氏同士、鎌倉の頼朝と力を合わせてのう」
そして従五位下に叙された。
四天王や巴は『おめでとうございます』とお世辞を言ったが、義仲は顔をしかめていた。
「何だあの化け物は。噂通りの大天狗そのものズラ。おまけに鎌倉と力を合わせろったって奴は全然動かねー。出だしも負けてばかりのくせにツベコベ言うだけラ」
頼朝が源氏の頭領として旗揚げし、大義名分をとやかく言い立てるのにうんざりした義仲は、嫡男の清水冠者・源義高を頼朝の娘である大姫と婚礼させ、言わば人質として鎌倉に送っている。
シブシブながらも平家に討伐の戦を仕掛けることになった。しかし義仲の得意な戦法はドロ臭い山岳ゲリラなのだ。一方で平家軍本体はむしろ海軍とでもいうべき構えで、慣れない海戦では平家に歯が立たない。
あわせて悪化する京の街を取り締まれ、とも言われたがこっちはもっとマズい。
そもそも義仲の勝ちに乗じて参集した得体の知れない雑兵なぞにモラルなどない。義仲の直隷の数など知れたもので、おまけに山賊に毛が生えた程度だ。京に帰るたびにいくら言っても略奪が止まらない。
頼みの綱の北陸宮は後からノコノコついてきたが、法皇はこれを相手にもしないでシレッと後鳥羽天皇を即位させてしまう。
そうこうしているうちに大天狗・後白河法皇は秘かに鎌倉に通じ、言葉巧みに上洛を促し宣旨を下した。
「殿。九郎義経殿は不破関(ふわのせき)まで進みおり候。裏で糸を引いているのは後白河院様でございますぞ」
「ナニ!」
四天王の一人、諜報担当の楯親忠が知らせると義仲は激高した。
頼朝めは自分は動かず弟を差し向けたのか。九郎と言えば奥州で育った田舎者ではないか。ワシも木曽の山猿だから分相応とでも思ったか。そしてあの大天狗はそれを裏から画策したのか。
不破の関は古代の壬申の乱の決戦場であり、また天下分け目の関が原の戦いもあった要害である。戦の天才である義仲は瞬時に危機を悟った。
「ふざけやがって。こうなったら法皇も何もあるか。引きずり出して目に物みせてくれらぁ!」
事も有ろうに法皇のいる法住寺殿を取り囲んだ。
不穏な気配を察して後鳥羽天皇を守るべく御所を固めた円恵法親王、僧兵を率いて延暦寺を降りて来た明雲たちが急を知って加勢に参じたものの、猛り狂った義仲の手勢に打ち取られる。後白河法皇は捕らえられた。
五条東洞院に幽閉された法皇に、義仲は立ったまま言い放った。
「まさかお上に切りかかるわけにも参らず、代わりに坊主首一つ、置き土産に五条河原に投げ捨て候。御免」
左手に掲げたのは天台座主にある高僧、明雲の首だった。不敵に笑うと踵を返した。
それにしても大天狗だけあって、後白河法皇は表情一つ変えなかったが、義仲に担ぎ上げられていた北陸宮などはどこかに逃げ去ってしまった。
ガラガラと蹄の音を立てて進むのはたったの六騎、供の者、雑兵は付いていない。
「殿。この後はいかに」
「巴よ。そちゃおなごじゃ。いずこへ落ちてもその器量で安んじて暮らせるラ。もう戦に明け暮れる事もねえズラ」
「ホッホッホ、お戯れを」
「それよりこの街道は不破の関に通づるゆえ、九朗殿の陣に切り込むおつもりで」
「さにあらず。四天王これへ」
義仲は馬を止めた。
四天王は木曽で共に育った今井兼平・樋口兼光の兄弟、佐久の豪族である根井行親・楯親忠の親子(親忠は行親の六男)。いずれも歴戦の勇者であり分かつ事のできない固い主従のつながりである。
「ワシはこれから淡海(おうみ)を北上して越前に出る。その後越中から信濃・甲斐を抜けて武蔵の国まで長躯する」
「武蔵まで」
「何とされる」
「兼平と兼光よ。おみゃーらは武蔵七党とは縁戚ズラ」
「いかにも」
武蔵七党とは関東に割拠する血族的武士団で、樋口兼光と秩父・大里・入間を根城とする児玉党との間には姻戚関係があった。
「早駆けして武蔵にたどり着き、我が一子、義高と鎌倉で一暴れじゃ」
「おォ!」
清水冠者源義高と頼朝の長女・大姫は政略結婚ではあるが、細やかな愛情で結ばれている。側近として鎌倉に同行している海野幸氏と望月重隆は共に流鏑馬の名手として名高い。
「鎌倉の軍勢は京に入った後、どうせあの大天狗にけしかけられて平家と闘うズラ。その間に手薄になった関東はワシ等の切り取り次第ラ。二人は先回りして武蔵へ行け。児玉党と合流せい。その後義高と密議せよ」
「殿、鎌倉殿はいとこにあたるお方。よろしいのですか」
「知れたこと。もともと源氏も平家も親・兄弟で殺しあってきた」
「心得て候」
「行親と親忠は奥州へ行け。奥州藤原をそそのかせて兵を鎌倉に向けさせるラ。頼朝が藤原を磨り潰すらしいと吹き込め。事が成る頃にワシと巴が兵を募って鎌倉に攻め込んでくれるワ」
「ホーッホッホッホ、頼もしい事。してその後は幕府をお開きに」
「わはは!そんなことがワシにできるわけがニャーズラ。よいか、ワシ等にとってはこの戦がズーっと続くことこそが生きることラ。鎌倉を潰した後は、平家を滅ぼした九郎が大天狗の手先となって向かってくる。その軍勢とワシ等とどちらが戦上手かを決めることになる。奴等は西から来るから、それを旭日の輝きを背にうけて迎え撃つ。我は朝日将軍なり」
残念ながら、無論史実はこのようにはならなかった。
埼玉県狭山市入間川に義高を祭神とする清水八幡宮が今もあり義高が討たれた地とされていて、筆者はお参りしたことがある。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
婆娑羅将軍 足利義満
2019 JAN 22 7:07:55 am by 西 牟呂雄

サンスクリットのバージラ(バジャラ)が転じて婆娑羅。「バ」も「サ」も女が入っている当て字を持ってきたところに情念を感じると言ったら女性に失礼かな。
派手な格好で好き勝手に振舞う傍若無人のならず者、お江戸の歌舞伎者に通じる一連の系譜だ。時代を遡れば平家一門、藤原氏の貴公子達、とどの時代にも必ず目立つ連中はいるが、婆娑羅はそれにもまして”強さ”が強調されている。その後戦国時代の集大成のように信長・秀吉のキンキラ文化として花開く。
『婆娑羅』は太平記にしきりに記述されたが、その後の戦国時代の文献からはなくなる。おそらく戦国時代になって日本中が下克上に明け暮れたから珍しくもなんともなくなったからだろう。
婆娑羅大名として必ず名前が挙がるのが太平記の準主役である佐々木道誉・土岐頼遠、高師直・師宣兄弟の不良根性たるや見事ですらある。彼らはそんなに物事を考えていたとも思えないが、個別の戦闘にはやたら強い。権威が何だ、しきたりクソくらえ、とてんやわんやの有様。
そしてその連中の上に天下一大バサラに当たるのが室町幕府三代将軍の足利義満だと思う。日明貿易で大儲けして絶大な権力を振るう。
明の使節と会うときは唐人の装束を着て喜び、世阿弥を可愛がったが飽きがくればポイ捨て。
相国寺に八角七重塔を建てるがその高さは100m以上と言われている。これに金閣寺を加えると誇大妄想気味の気概と悪趣味は物凄いエネルギーを感じさせる。
子供の頃は南朝との抗争や観応の擾乱でドタバタして京から近江や播磨まで逃げ出したりする苦労があったが、その時に立ち寄った摂津の景色が気に入り、景色ごと担いで京都に行け、というわがままな命令を下すようなガキだったらしい。
9才で足利将軍となると、細川・斯波・土岐・山内といった守護大名を巧みに離反させて権力を握り、三種の神器を北朝に返すやり方で南北朝問題をかたずけた。これは日明勘合貿易に大変役に立った。どういう経緯か明の窓口は南朝懐良親王であり、その際の呼称は「日本国王良懐」だった。その後釜のような者として日本国王を名乗ったのだ。
藤原氏出身ではないのに従一位太政大臣になったのは平清盛に次いで史上二人目で、その後は徳川家斉と伊藤博文だけ(藤原氏はたくさんいる)。
太平記はいくら丹念に読んでも因果関係が分かるはずがない。やっている本人達も分からないのだろう。だがこの時代のやりたい放題は維新後・敗戦後に匹敵する歴史の転換点とも考えられる。その時点で権力の頂点にいた者こそ義満であり、この時代から鎖国されるまで今で言えばグローバル時代の荒波を被り続ける時代を切り開いたことになる。
翻って近代では田中角栄が近いところだろうか。娘はゴーツク・ババァだが家族以外は皆敵、というのは孤独な婆娑羅の血を引いている痕跡がある。角栄がいくら贅沢をしても中国高官の汚職に比べればカワイイもんだし、そのついでに教育基金を作ったりしていれば今太閤の上を行った今婆娑羅の偉人になっただろうに惜しい事だ。そういう意味では孫正義さんあたりに期待したい。
日本人よ孤独を恐れるな。ひとりぼっちで死んでいく。その日が来るまでただ狂え。
しかし、ゴジラやモスラはいたが『バサラ』というのはいない。あれだけ毎週新怪獣がテレビに出ていたのに誰も名付けなかった。唯一『怪獣ブースカ』とかいう着ぐるみのコメディがあって、主人公のブースカの笑い声が「ばらさ、ばらさ」だったが、関係ないか。
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
闇に潜む烏 新撰組外伝 下
2019 JAN 2 9:09:14 am by 西 牟呂雄

そもそも『蝦夷共和国』は正式名称でも何でもなく、税金の体系すらない。伝習隊(陸軍)・彰義隊・新撰組の敗残兵と江戸湾から脱出した榎本武揚の幕府海軍(但しこちらは無傷)の連合で、一応の選挙(入れ札)をやり榎本を総裁とはした。
近藤や沖田をはじめ新撰組として戦い続けた仲間はもうほとんどいない。
新撰組は函館でも一応1分隊から4分隊まで百人弱の人数がいて、部隊編成上は陸軍第一列士満(レジマン)配下にあった。レジマンとはフランス語の連隊の呼称をそのまま使った外来語で、幕府陸軍伝習隊の顧問だったブリュネ大尉他四名が伝習隊の北上に従って来ていてそのまま函館で指導を続けていた為に使われた。『大隊、進め』は『バタリオン、アルト』である。
京都以来の生き残りは島田魁、相馬主計(とのも、最後の隊長)以下数名である。陸軍部行並みとはなったが、土方は孤独だった。
ある晩、寝付かれずに五稜郭の堀端まで月を見に出た。漆黒の闇に満天の星。
あれから、甲州・宇都宮・会津と戦い続けてこの函館に来るまで何人が死んでいったか。特に盟友近藤の斬首と沖田の病死が悼まれてならなかった。
函館の冬は厳しい。と、風が吹いて人の気配を感じた。
「ここまでよう来た。土方歳三」
振り向くと伝習隊のユニフォームを着た人影が既に抜刀しており、その顔を見た土方は直ぐに思い出した。あの札をバラ撒いていた顔、ええじゃないかの輪の中にいた顔だった。
「貴様、沖田が切った片割れだな。なにしに来やがった」
すると、後ろからまた声がかかる。
「沖田は我らが始末した。千駄ヶ谷の植木屋で臥せっておったところを切って捨てた」
振り向くと今度は薄汚れた夜鷹のような女がだらしなく胸をはだけさせて抜刀していた。同じ顔である。
「沖田を殺っただと」
土方は後ずさるようにして二人を視界にとらえつつゆっくりと刀を抜いた。
「我等の同胞(はらから)の仇をとったまで。次はお主や」
また後ろから声がした。
さすがに顔色を変えて体を入れ代えると、もう一人。やはり同じ顔が。こちらは町人姿だった。
「ほう。まだいるのか。全部で何人だ」
「ふふふ。冥土の土産に教えたる。我が一族は男も女も双子しか生まれへん。男の双子が十七になると連枝で十五の双子の娘と契りを交互に交わし、再び双子を生むのや。その四人の従兄弟を一束(ひとつか)と呼ぶ。沖田が切ったのは我等が束の一人、夜叉姫や」
「ケッ、薄気味悪い。その束がなんで ”ええじゃないか” のお札を撒いた」
「我等は帝(みかど)に危機迫る時だけ世に出る烏童子。公方(くぼう)慶喜公あまりに目障り、長州を引き込むための騒乱や」
「やはりな。大政奉還でピタリとおさまった。で、今度は官軍のつもりで敵討ちにわざわざ函館までオレを切りに来たのか」
「死ね、土方」
伝習隊の制服姿が切り掛かった。
バン!振り向きざまに懐から引き抜いた土方のリボルバーが火を噴いて、制服は後ろにのけ反った。
「てめえらに切られなくともオレはすぐに死ぬ。京都に帰れ」
「そうはいかんのや。束は一人欠けると全員死ぬのが掟。逆に京都におったら消されてまうわ。ウチらもオマエと同じなんや」
「だったらオレともうひと暴れ一緒にやるのはどうだ」
「今ここで不浄丸を撃っておいてなんや」
「ケッ、だったら名乗りを上げろ」
「北面の烏童子。ワシは浄行丸や」「ウチは吉祥姫」
「土方先生ー。今の銃声はどうしましたー」
衛兵が駆け寄って来たが、死体が一つ転がっており土方が佇んでいるだけであった。
「先生。こいつは何者ですか。このナリはわが軍の・・」
「オレに恨みのある奴が紛れ込んだのだろう。女か」
「男ですね」
「そうか、男か」
「何か」
「いや、いい。この顔を良く覚えて人相書をつくっておけ。同じ顔があと二人いて隊内にまぎれるかもしれない」
烏童子はくノ一だと思っていたが、男もいた。この時代は男女の双子は心中者の生まれ変わりという迷信があって、間引きされてしまうことも多かったため珍しかった。
政府軍は五稜郭を潰そうと続々と北上してきた。五稜郭側は財政的にも苦しくなり、貨幣を発行したり店のショバ代を取り立てたり、勝手に通行税まで取り出して急速に民衆の求心力を失った。五稜郭政権とは初めから砂上の楼閣だったのである。そしてついに江差に上陸した。
土方は烏童子を撃ち殺して以来、尋常な目つきでなくなった。
二股口の戦いが始まると、常に先頭に行くようになった。元々指揮を取るのは最前線だったが、弾丸飛び交う中を進み最初に突進するのである。右手のリボルバーを3発撃つ間に敵陣にたどり着くように間合いを取って懐に納め、剣を左手で振り上げて切り込む。政府軍の弾はかすりもしない、ましてや官軍は刃を合わせることもなく骸と化すのみ。鬼神の突撃で敵を蹴散らした。
ある晩、自室に土方附きの市村鉄之助を呼んだ。遺品を故郷に届けさせる為である。市村が入ると土方の両眼が碧く光ったように見えて驚いた。刀に手を掛け今にも抜刀しそうな殺気に慄きながら座ると、遠くを見据えるような普通の目付きになってこう呟く。
「鉄之助か。よかった」
「副長。どうかされましたか」
「いや。別の顔に見えたんだ」
市村が土方に呼びかけるのはどうしても京都以来の『副長』である。
「別の・・・」
「この前に一人撃ち殺したろう。あれと同じ顔の人間が後二人いて、この五稜郭に忍び込んでいるはずだ」
「・・・ところで副長。なんの御用ですか」
「オウ。戦闘が激しくなる前にお前はここを出て多摩に帰れ」
「何をおっしゃってるんですか!」
その後は多くの読者の知るところである。土方には榎本・大鳥の幹部が降伏の説得を受けかねないことを肌で感じていたのだった。
江差から上陸した新政府軍は箱館市街を制圧した、更に一本木関門を抜こうと迫った。このままでは弁天台場が孤立する。そしてそこを固めているのは新撰組なのだ。
土方は現場に急行する。すると既に押された兵士は敗走して来るではないか。馬上から号令をかけた。
「止まれ、とどまれー。逃げる奴ァぶったぎるぞ!」
一瞬、敗残兵の顔がみな同じ顔に見え、烏童子が押し寄せて来る幻覚に襲われた。馬上より一閃、先頭の男を切った。その瞬間に我に返ったところ、確かに烏童子の一人である。他の兵は土方には目もくれずに逃げて行く。
直後『ガン!』と銃声がして土方は馬から落ちた。背中から撃たれた。地上に転がった土方が辛くも振り返ると伝習隊姿の烏童子が銃を構えていた。
「・・・来やがったな。本懐成就か・・。てめえらも終わりだ」
「我が束の最後。吉祥姫なり」
敗走する兵を追ってきた新政府軍が土方の遺体を踏み越え、一人立ちはだかる吉祥姫に殺到した。
一陣の風が吹いた後、おびただしい遺骸が重なり異臭が漂う。誰なのかもわからない死体はかたずけられ、蝦夷共和国側は降伏した。
時は経ち平成の御世代わりが近くある。
平成の御代。皇居前広場では平日にもかかわらず、多くのランナーがジョギングに勤しんでいる。反時計回りに走る人々を見れば、10分ほどすると先程通り過ぎていった美しい女性と又同じ顔の女性が走っている。また10分後にはそっくりな青年が走り去って行った。
皇居は一周5km、ジョギングペースの1km8分で40分かかる。
同じ顔が10分ごとに現れることは一般ランナーには不可能、即ち同じ顔の四人が正確な間隔で走っていることになる。女・女・男・男の順番で。
御代変わりの皇室は現在も烏童子に守られているのだった。
そして、この同じ顔をした人々は渋谷ハローウィンで騒動が起きた際にも目撃されていた。平成の『ええじゃないか』だったと言われる所以である。
おしまい
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
闇に潜む烏 新撰組外伝 中
2018 DEC 31 17:17:52 pm by 西 牟呂雄

土方が一番隊を連れて駆け付けた時はもうドンチャン騒ぎが始まっていた。
「ええじゃないかええじゃないかえーじゃないか」
「ええじゃないかええじゃないかえーじゃないか」
周りの店(たな)から振る舞い酒が出され民衆が踊り狂っている。まだ昼前だというのに、だ。
「総司、一番隊で遠巻きにしろ。お前が切ったくノ一の片割れがいるかもしれん」
沖田に下知して土方は民衆に目を据えた。
「ええじゃないかええじゃないかえーじゃないか」
男女が入り混じっての大集団が、札降りのあったという家にあがりこんでまで騒いでいる。同じ節のなかで替え歌のようなものも混じっており全体が反響するようなうるささなのだ。その中で気になる一節が聞こえた。
「これは新たな世直りや えじゃないかえじゃないかえじゃないか」
土方は耳を疑いその声のする方を目で追った。だが人数が人数だけに良く分からない。
「おい、総司。今『世直り』と言ってなかったか」
「聞こえました、はっきりと。ほら、また」
明らかに男装している風情の女が中心で踊っている数人の内の一人がこちらに顔を向けた。「あいつだ!あいつがいやがる」
土方が傍らの沖田をうながした。
「どこですか」
「こっちだ。来い」
踊り狂う輪に割って入ったが、興奮している群集は泣く子も黙る新撰組を気にもしなかった。
「ええい、どけ。新撰組だ」
「ええじゃないかええじゃないかえーじゃないか」
踊りの人数が多すぎる。全く統制の取れていない集団は巨大な生き物の様でどっちへ向かっているのかもわからない。土方はついに視線の先に捉えていた者を見失った。
「歳さん、そっちじゃない。逆ですよ、あっちにいる」
沖田が認めた姿は先程の反対側にいて、はっきりとこちらを見据えていた。
「待て。‥‥総司、こっちにもいやがる」
「えっ・・・同じ顔の奴が」
「まだいるのか」
いつの間にか集団に埋没した土方と沖田は必死に捜し求めたが、そのだらしない男装の風情の踊り手は次第に数が四人・五人と増えていく。気色の悪い事におかめ・ひょっとこ・きつねの面を付けていた。その内の一人、ひょっとこの面が近くに来た。土方は乱暴にも『オイッ!』と面に手をかけた。
「これは新撰組はん。ナニをしますんや。一緒におどりまひょ」
いつかの顔とは似ても似つかない正真正銘の男である。
「なに!ふざけんな」
「歳さん。副長。まずいですよ」
「これは・・・、退け」
京都に来て初めて後ずさりした。踊りの中からほうほうの体で抜け出した時には、二人は白昼夢を見たかのようにその怪しげな連中はいなくなっていた。周りを固めていた隊士達に”男装の風情の踊り手”が逃げ出していないか確認しても、誰一人その姿を見た者はいなかったのだ。
禁門の変の時、京都に”鉄砲焼け”と言われる大火を引き起こした長州藩だったが、何故か不思議な事に恨む声よりも同情する声が多かった。京の町衆は時勢に敏感で情報も早い。
10月14日を過ぎると噂が直ぐに広まった。『将軍様が大政奉還なさった』と言うのである。
「歳。どういうことだ」
「見当もつかねえよ。将軍が政(まつりごと)を投げ出したんだろうよ」
「すると幕府はどうなる」
「さあな。今度は帝(みかど)が差配なさるんだろう」
「新撰組は元々尊王攘夷の志だ」
「それはそうだが。それより伊東の一派を何とかする方が先じゃねえか。長州藩に対し寛大な処分を、と建白していたそうだぞ」
「何!」
時代の展開は拍車がかかる。
翌月15日には坂本龍馬が見回組に暗殺された。
そして新撰組伊東一派を磨り潰したのは3日後の11月18日だった。
そして不思議な事にその頃には ええじゃないか のバカ騒ぎはおさまってしまったのだった。
つづく
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」
闇に潜む烏 新撰組外伝 上
2018 DEC 30 9:09:38 am by 西 牟呂雄

「ええじゃないかええじゃないかえーじゃないか」
「ええじゃないかええじゃないかえーじゃないか」
老若男女がデタラメに踊り狂っている。四条烏丸通りの辻に突如伊勢神宮のお札が舞った。どこから降ったのか分からないがヒラヒラと落ちて来るお札を拾った町衆が『天から御札が降ってきた。これは慶事の前触れや』と節をつけて歌うと数人の男女が一斉に踊り出した。幕末の世情を騒がせた『ええじゃないか』の始まりであった。
瞬く間に大勢が寄って来て、どこが始まりでどこが終いなのか分からないほどの群集になりいつ果てるとも分からない騒乱が続いた。慶應三年の八月末、むせかえるような京都の夏の昼過ぎである。
報告を受けた土方歳三はすぐさま非番だった井上源三郎の六番隊を率いて洛中に巡察に出た。
「一体何の騒ぎだ、ありゃあ」
土方達が着いた時はもう手が付けられない状態で、町屋や商家は成るに任せるしかない。酒までが振舞われたようだ。髪をほどいた女、化粧した女形姿、酔っ払った老女などが入り乱れ踊り狂っている。
どうやら伊勢神宮のお札が降って、これはめでたいと踊りだしたと分かった。
「副長。単なる酔っ払いの憂さ晴らしでしょう。御用改めにはなりませんや」
「待て。その降ったというお札はどんなもんだ。持って来い」
誰も泣く子も黙る新撰組には目もくれずに騒いでいた。しばらくして隊士が戻って来た。
「それが、実際に持ってる奴は一向に見当たりません」
「なんだと。降ってもないのに騒いでるのか」
「いや、札振りだって騒いで始まったらしいんですが縁起物だって持ってっちまったみたいで。後はこの騒ぎです」
土方は一瞬表情を曇らせたが気を取り直して言った。
「まったくこいつ等。ようやく長州を追っ払ってやったのに浮かれやがって。ほっとけ」
実際のところ土方にとって踊り狂う町方なぞどうでもいい。頭の中を占めているのは不逞浪士ですらない。
一つ目は、伊東甲子太郎一派が新撰組から御陵衛士として分離してしまったことである。伊東は新撰組の参謀兼文学師範だったが尊王家で、会津藩預りの新撰組主流とは微妙に温度差があった。
次にどうも薩摩の様子がおかしい。特に土佐浪人の坂本龍馬が藩邸に出入りしている、という報告が入る。坂本は要注意人物で、去年伏見奉行所が寺田屋で捕縛しようとして逃げられている。又、禁門の変で追い払ったにもかかわらず、洛中・洛外で長州人を見かけたという話が頻発するようになった。報告によれば薩摩藩邸あたりの目撃情報が多いのだ。
そこで薩摩藩の動向探索と御陵警備任務の名目で伊東が分離を申し入れたときには、これを受け入れざるを得なかった。
付け加えると途中入隊してきた唯一人の薩摩人、富山弥兵衛は伊東に付いて行った。
新撰組はとっくに時流に取り残されていた。薩長秘密同盟は一年以上前に結ばれていたのだ。
例のエエジャナイカは秋になって更に頻発する。踊りもやかましいが、騒ぎは大きくなる一方で、2~3日は商売も何も街の機能が停止する。
しかも洛中洛外だけでなく、大坂・播磨・尾張などでも散見されるようになるにおよんで土方のカンが反応した。
「近藤さん。あの ええじゃないか は何やら臭い」
「そんなこたーねえだろ。浮かれてるだけさ」
局長の近藤の頭にあるのは新撰組の統率だけで時流には疎い。土方は監察方の山﨑丞を呼んだ。
「最近騒がしいあのエエジャナイカだがな。そう年中お札が降るのも尋常じゃない。誰かが糸を引いていると見た」
「わかりました。任せとくれやす」
山崎は大阪人で飲みこみの早い切れ者だ。暫くしてお札を持って来た。
「副長、お見立て通りです。明け方に蒔いてましたわ。これは拾ったもんですが、撒いている所も見てます。忍び装束が4人でした」
「やっぱりな。こりゃひどい捏造品だぜ。どこの野朗だろうと一網打尽にしてやる」
「へぇ」
土方は秘かに夜半になると隊士を巡察に回した。ただし大勢でウロウロはしない、三条から四条にかけて、室町通りと烏丸通りのあたりに潜ませておいて何かが動くのを待つ。
張り込んでしばらく無駄に終わったが4日目、監察からの知らせが入る。錦小路付近で不審者を見た、と言うのである。現場に急行するとこの日の出番は十番隊だ。土方はそっと聞いた。
「原田か(十番隊長は原田左之助)。その賊はどこにいやがるんだ」
「オッ副長。屋根に登っているのを見たんで四辻ガッチリ固めたんやけど。降りてけえへん」
「いきなり火もかけられねえな。よし、梯子を用意しろ。それで御用改めでかたっぱしから町屋に踏み込め。京の町屋は奥までつながっているからそこから梯子をかけて上がってみろ」
「歳さん」
「何だ、総司まで来たのか」
「どうせ人手は足りないんでしょ。調子も良かったもんでチョイと」
「じゃさっさと裏を固めろ」
周辺でドンドンと戸を叩き『新撰組だ。御用改めである』の声が響いて家の中がバタバタする喧騒が広がった。中庭に押し入り梯子を架けて隊士が屋根に上がって行くが誰もいない。だがお札の束が残されていたのを見つけた。
「副長。これが」
「やはりな。どこのどいつだ、こんなものをバラ撒いてるのは。長州の手の者か」
「どうやらズラかった後のようですな」
「逃げ足の速い奴だ・・・・、退け」
隊士は足早に屯所に引き上げて行き喧騒は収まった。
するといずこかの屋根から一つの影法師が音もなく舞い降りた。忍び装束である。そしてスススーっと闇に消えていこうとした時、声がかかった。
「待て」
影はピタリと動きを止めた。
「役にも立たないお札のバラ撒きはおぬしの仕業だな」
それには何も答えず背中の刀をスッと抜いて構えた。物陰から姿を現したのは既に抜刀している土方、待っていたのである。
「そのナリは忍びか」
「シャァッ」
いきなり切りかかってきたのを土方が払いのけ、正眼に構えて対峙した。するとその影法師は覆っている忍び頭巾を解いて顔を晒す。
「素顔を見せるとは覚悟を決めたな。どこの廻し者だ」
「クックッ土方やろ。後ろを見てみい」
「なに」
振り向くと何と音もなく影法師が一つ。いつの間にか挟み撃ちにされていた。しかもその影法師は忍び頭巾をしておらず、その顔を見た土方は息を飲んだ。同じ顔、同じ構えだ。まるで鏡に写したような姿で両方からジリジリと間合いを詰めて来る。しかし百戦錬磨の土方は、元の方に向いて言い放った。
「怪しげなまマヤカシをしやがって」
「グアッ」
怪鳥の叫びが後ろから飛んできた。
「歳さん。危なかったですよ。こいつはマヤカシなんかじゃありませんよ」
新たな影を、その後ろから気配を消して忍び寄った沖田が必殺の突きで葬ったのだった。
土方が振り返ると元の影は姿を消した。
「総司。余計な事しやがって、逃がしちまったじゃねえか」
「ハイハイ。ところでこいつ何でお札を撒いたんですかね」
「そいつの顔を良く覚えておけ。逃げた野郎と瓜二つだった」
「ほう、双子なんですかね。あれ、この仏、女じゃないですか」
「何だと。くノ一ってのはこれか、気色悪い。女の骸(むくろ)なんざいたぶる趣味はねえ。隊士を呼べ」
土方はこの「ええじゃないか」は仕組まれた騒乱だと睨んだ。
15代将軍となった徳川慶喜は二条城におり威を放ってはいたが、既に土方達の知らない内に薩長秘密同盟は成立し、洛中には倒幕の気配が漂う。不逞浪士の姿が目立ってきたのだ。
10日程は何も起こらなかったが秋風を感じた日。
「副長、例の札が撒かれてました」
「どこだ。直ぐに行くぞ」
「四条烏丸通りですわ」
「ど真ん中じゃねえか、なめてんのか。当番は」
「へぇ、一番隊です」
「沖田ー!」
つづく
「ソナー・メンバーズ・クラブのHPは ソナー・メンバーズ・クラブ
をクリックして下さい。」