E・C・ベントリー 「トレント最後の事件」
2019 OCT 16 23:23:35 pm by 東 賢太郎

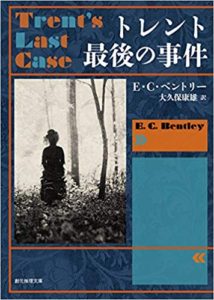
ベントリー(1875-1956)の「トレント最後の事件」(Trent’s Last Case)は1913年、「春の祭典」がパリで初演された年の作品である。
先日、池袋の書店でたまたま手に取って「最初の事件」はなかったことを知り、愚を悟った。「レーン最後の事件」と同様に X、Y、Z (の悲劇)にあたる物があると思い込んでおり、順番通りでないと嫌な性格なので読まずに死ぬところだった。
面白い。久々に、ほんとうに何十年ぶりに、古式ゆかしい本格っぽい香りのする滑りだしでわくわくさせられた。中盤でトレントが新聞社への報告書の中で謎解きを開陳するが、ロジックの要所で文字に点々がふってある。これはエラリー・クイーンの同様の個所でおなじみの景色であり、それを見ただけで興奮するパブロフの犬になる。
しかし、とても恥ずかしいことだが、僕はそれをクイーンのパクリと思って読んでいた。しかも、「推理小説に恋愛を取り入れたのが新しい」との世評にだまされており、本作を「本格物に恋愛でひねりを入れた新機軸の色モノ」と勘違いして読んでいたのだ。
とんでもなかった。英国でアガサ・クリスティが現れるのが1920年、米国ではヴァン・ダインが1926年、エラリー・クイーンが1929年、ディクスン・カーが1930年(以上、処女作刊行年)である。トレント(1913年)はまだコナン・ドイルが『シャーロック・ホームズ最後の挨拶』を執筆中に書かれたのであって、こっちが先なのだ。
推理小説が普通小説と明確に分化する初期の試みとして人間に焦点を当てる恋愛が有機的にプロットに組み込まれ、英国人イーデン・フィルポッツの「赤毛のレドメイン家」(1922)を懐かしく思い出したが、この試みは米国の作家たちには遠ざけられたから新機軸ではあったが不発に終わっていた。
真の新機軸はそこではない。探偵が「観た」殺人現場の不可解さ、どうしてそんな妙な死にざまになってしまったか?が魅力的であることだ。これは成功作の必要条件だが、そうであればあるほど整合的解決に導いて読者を納得させるのは容易でないトレードオフがある。ネタバレにならないように書くが、不測の因果関係で魅力を最大化しつつそれをクリアしたのが実に素晴らしい。
エラリー・クイーンは「点々」だけでなく、「妙な死にざま」もトレントを継いでいると思う(レーン最後の・・・も題名からしてそう)。「Yの悲劇」、「スペイン岬」、「エジプト十字架」はもとより、国名シリーズでは駄作に属する「チャイナ・オレンジ」などフレデリック・ダネイが「妙」だけに賭けた観すらあるが、謎の組成に謎解きが依存する構造において「Y」が近似する。クイーンはロジックの範囲でそれを解いて見せたが、トレントはそこは断念し告白に依存した点が未だ形式の萌芽であり、恋愛をからませた要因と思わせる点だろう。ヴァン・ダイン、クイーンが恋愛を排除したのはロジックの解決のキレを希薄化させないためだったと思う。
E・C・ベントリーはチェスタートンのセント・ポールズ・スクールの1年後輩、無二の親友で、マートン、オックスフォード大学を経て新聞記者となった人物である。原文で読んだわけではないが、文章、描写、ロジック、非常にシャープで文学性もあり、まぎれもないインテリだ。上掲版の訳文も日本語としてすばらしい。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
Categories:______ミステリー





