フォーレ ピアノ五重奏曲第2番ハ短調作品115
2019 NOV 5 1:01:29 am by 東 賢太郎

今年は少々落ち着いた気持ちで秋を迎えられるのは、自然体でのスタンスで仕事が板についてきたからだ。これまでは日本シリーズが終わってしまうと「野球ロス」で空しかったがそれもない。
5年前の10月にこういう物を書いた。
いまはこう思う。秋にふさわしいって、まさにフォーレじゃないか。
 ガブリエル・フォーレ(1845-1924)はその真価が最も高位にある少数の作曲家に属し、かつ、そのことが最も知られていないひとりに属し、母国を除くなら、彼があるべき評価を得ている国はイギリスのみである。僕はロンドン滞在時代に頻繁に演奏会に同行した、顧客であり友人でもあった紳士にそう教わった。
ガブリエル・フォーレ(1845-1924)はその真価が最も高位にある少数の作曲家に属し、かつ、そのことが最も知られていないひとりに属し、母国を除くなら、彼があるべき評価を得ている国はイギリスのみである。僕はロンドン滞在時代に頻繁に演奏会に同行した、顧客であり友人でもあった紳士にそう教わった。
プライド高い英国人の身贔屓を割り引いても、今でもそうかもしれないと思う。ドイツ系の演奏家がベルリオーズ、サン・サーンス、フランク、ドビッシー、ラヴェルを手掛けることはあってもフォーレは少ない。それは彼に交響曲や大規模な管弦楽作品がなく、劇場向きの音楽よりも歌曲、室内楽、ピアノ曲に多作であることと関係があり、ともするとサロン音楽家のイメージに矮小化される愚に陥ってしまう。さらにオルガニストとして出発した彼の作曲法は、ショパン、モーツァルト、ワーグナー、シューマンの影響を経て初期にはシシリエンヌやパヴァーヌなどロマンティックで滋味あふれる旋律を持つ小品を生み出しているものの、中期以降はモノクロの音調で多様な転調を見せる内省的な作品が増える。
我々はドビッシー、ラヴェルによってフランス近代音楽の幕が開いたという認識を持っており、それに「印象派」という本質とずれのある絵画史の概念を “誤って” 援用し、「印象派以前、以後」というステレオタイプな区分けをしているのである。それゆえに、”ドビッシー以前” と認識されているフォーレは19世紀フランスの古典的なロマン派の残滓を残した時代遅れの保守派というあいまいで確固としない場所に置かれることとなり、”誤りの 印象派に eclipse される” 結果となっていることが過小評価の原因の一つだ。
印象派絵画が光と色彩の芸術であるとするなら、フォーレの後期の作品は印象派と呼ばれて不思議でない。ただし、ここで特記すべきことは、フォーレは楽器の音色による効果を音楽の重要な要素と考えていなかったことだ。ケクランらに自作のオーケストレーションを任せたことでわかる。楽器法は単なる自己満足か、作品に創造性のないことを隠すためのものと考えていたフォーレは、パリ音楽院の生徒にグロッケンシュピール、チェレスタ、木琴、鐘、電子楽器の使用を控えるよう指導していた。我々が印象派とイメージするドビッシー、ラヴェルの色彩(colour) を感じさせる管弦楽とは遠い感性の人であり、これが“誤りの 印象派に eclipse される” 原因となっている。
ではフォーレは「光と色彩の芸術」を何によって表現したのだろうか?それは和声だ。彼は師であったグスタフ・ルフェーブルの著書「和声法」(1889)に則って、従来は不協和音とされていた和音や解決しない非和声音による光と影の彩色法を使うことで、誰とも異なる音楽語法を開拓したのである。初期の曲は主調が明確だが後期に至ると頻出する転調によって複数の主調があるかのようになる。ただそれは多くがエンハーモニック(同名異音)を基点としたような内声部からの転調で、延々と続くメロディの起承転結をぼかしてしまう意外さはあるが他の作曲家が用いるように劇的ではなく、屋外での陽光の移ろいのような朧なものだ。それをフォーレは音色より重視した。
「高級な」という日本語はあいまいだが、英語ならhigh-grade、sophisticatedとなる形容詞を音楽につけるとすると、僕にとってフォーレの後期の曲はそれだ。高級であるにはいくつか要件があって、美しいのは当然として、犯し難い気品、そして何より、難攻不落な謎が背後に感じられなくてはいけない。すぐお里が知れるのはチープなビューティーであってすぐ飽きる。高級な宝石は組成の理由も知れぬ不可解な色と光彩の美を発散するし、高級な料理や菓子はレシピや製法がネットで知れ回るようではいけない。そこに理屈は存在しないが、人はそういうものにgrade、sophisticationを感じるようにできている。そして、そのことは僕においては音楽の謎がスコアを見て解決してしまう程度ではいけないということになる。
そう考えると、楽器法が謎かけをする体(てい)の音楽を下に見て、音楽の本質に深く関わる和声で色と光彩を思考していたフォーレのスタンスはもっともである。アーロン・コープランドがフォーレをフランスのブラームスと評したのは、その高級感のあり方が和声に根ざす点では同意だが、フォーレはより比重が大きい。ピアノ五重奏曲第2番ハ短調作品115の第3楽章(以下、Mov3)の、秋の夕暮れの陽光が森の木々の陰影を織りなしながら時々刻々と移ろってゆくような玄妙な和声の揺らぎは他の音楽から聴いたことのない驚くべきものだ。楽器5つのスコアはいたってシンプルに見えるが、すぐ現れる転調、というか、調性が変わったという事なのかそれが本来のメロディーであったのかわからないような揺らぎという物に幻惑され、夢の中のような蠱惑的な謎の迷路をたどり、長いコラール風主題による宗教的な安息に到達する。
Mov2は目にもとまらぬアレグロ・ヴィヴォで、主調は変ホ長調であるがのっけからラが♮に変位して調性がわからないまま謎の疾走となる。ショパンのソナタ2番の終楽章を想起するが、2番目の楽章に不意にこれが襲って来る謎のインパクトは計り知れない。Mov3に比肩する和声の迷宮がMov1である。この楽章の素晴らしさは和声だけではなく、構造面にもある。3つある素晴らしい主題のどれが第2主題かという詮索は些末でソナタ形式の3主題構造はモーツァルトにもいくつも例があるのでどうでもよく、ポイントは各主題が順次現れ展開する様で、フーガ風になり、音型が伸縮して小節線を越えて組み合わさり、再現してコーダに至る前に再度複雑に展開する重層構造を持っていることだ。その効果は圧倒的である。Mov4はピアノが前面に出て全曲をまとめる。この楽章だけは先行する3つの楽章の高級感にやや達しない観があるが、それでも立派なピアノ五重奏曲の締めくくりとして完璧な充足感をもたらしてはくれるものだ。
もうひとつ特徴を付け加えると、Mov3が四分の四拍子である以外は四分の三拍子で書かれている。拍節感は概して希薄で譜面を見ずにそう気がつくことは困難だが、フォーレはそれを変拍子で記譜することはない。この保守性と革新性の混在は、調性音楽の外観を 保持しながらストラヴィンスキーやミヨーが試みたような複調ではない方法のまま既存の調性概念を超えたこととパラレルに感じられる。この驚くべき音楽はドビッシーが没した翌1919年に着手され21年に完成しており、マーラーの交響曲第10番(1910-11)の10年後に現れた。「月に憑かれたピエロ」(1912)、「春の祭典」(1913)、「中国の不思議な役人」(1919)、「ヴォツェック」(1921)と同期する空気の中で書かれ、和声音楽がトリスタンと異なる路程で行きつくことのできる別の惑星が存在することをドビッシー以外の人間が示したという意味で真に革新的なものだ。ショパンが作曲していた頃に生を受けた人間が書いた音楽として、それが20世紀の音楽への連続性を覗かせることを示す最後の作品であり、彼をドビッシーにeclipse される存在とする思い込みは誤りであることがわかる。これ自体が信じ難い音楽だが、難聴で、しかも高い音がより高く低い音がより低く聞こえるという病の中でこれを書いたフォーレの量り難い天才に最高の敬意を表して稿を閉じたい。
保持しながらストラヴィンスキーやミヨーが試みたような複調ではない方法のまま既存の調性概念を超えたこととパラレルに感じられる。この驚くべき音楽はドビッシーが没した翌1919年に着手され21年に完成しており、マーラーの交響曲第10番(1910-11)の10年後に現れた。「月に憑かれたピエロ」(1912)、「春の祭典」(1913)、「中国の不思議な役人」(1919)、「ヴォツェック」(1921)と同期する空気の中で書かれ、和声音楽がトリスタンと異なる路程で行きつくことのできる別の惑星が存在することをドビッシー以外の人間が示したという意味で真に革新的なものだ。ショパンが作曲していた頃に生を受けた人間が書いた音楽として、それが20世紀の音楽への連続性を覗かせることを示す最後の作品であり、彼をドビッシーにeclipse される存在とする思い込みは誤りであることがわかる。これ自体が信じ難い音楽だが、難聴で、しかも高い音がより高く低い音がより低く聞こえるという病の中でこれを書いたフォーレの量り難い天才に最高の敬意を表して稿を閉じたい。
ギャビー・カサドシュ(pf)/ ギレ弦楽四重奏団
素晴らしい演奏。何がといって、5人の奏者が和声を完璧に “理解” して見事な音程で弾いていることがだ。フォーレが書きこんだMov1,3の音符の凄さをストレートに知覚させてくれる意味で他の演奏を圧倒しており、僕のような聞き手は耳に入ってくる音のいちいちに興奮をそそられる。プロだから当然?いえいえ、それがいかに困難かはyoutubeでご確認できる。Mov2におけるロベール・カサドシュ夫人のピアノも目覚ましく、もっと録音を残してほしかったとつくづく思う。録音が古くさく楽器音がヴィヴィッドに前面に出てくるのは好き好きだが、僕は表面的な美しさよりも音楽の本質的な美を味わいたい。
ジャン・フィリップ・コラール(pf)/ パレナン四重奏団
僕はこれで覚えた。決して悪くないが弦楽四重奏がやや後退したように聞こえるアコースティックで、非常に精妙に書かれたMov1、3の和声の味がギレ盤ほど聞こえない。ピアノ五重奏のバランスの難しさで実演はこっちに近いが、あまりこだわらずに平面的に楽器を並べたギレ盤が2Vn、Vaのうまさで引き立っているのは皮肉だ。コラールのピアノは上品、パレナンQはロマンティック寄りであり今となるとホールトーンの中で融け合うように綺麗に丸めた和声はMov3は少々ムード音楽に近い感じがしてしまい、フォーレが求めたのはこれではないだろうという気もする。全曲のまとまりは良い。
ローマ・フォーレ四重奏団
元イ・ムジチのコンサート・ミストレスだったピーナ・カルミレッリ率いる五重奏団。フランス系の演奏だと往々にしてわかりにくいメロディーラインが遅めのテンポでポルタメントがかかるほど切々と歌われるのが愛情の吐露だろうかとてもいい。いっぽうで和声の知的な理解も深く、近接した音程の内声の活かし方はそうでないとこうはならない。技術的に弱い部分もあるが、なぜかまた聴こうという気になる謎を含んだ演奏だ。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
フォーレ「マスクとベルガマスク」作品112
2018 FEB 3 13:13:01 pm by 東 賢太郎

僕は料理と音楽は本来がローカルなものと思っている。ブイヤベースはマルセイユで、チョリソはマドリッドで、ボッタルガはサルジニア島で、麻婆豆腐は重慶で、天九翅・腸粉は廣州で、ビャンビャン麵は陝西省で、カルボナーラはローマで、グラーシュはブダペストで、鮒鮨は湖東で、真正に美味なものをいただいてしまうともういけない。腸粉とはワンタンの春巻きみたいな飲茶の一品で下世話な食だから東京の広東料理店で出てこないが非常にうまい。
チャイニーズは地球上最上級の美味の一部と確信するが、中華料理などというものはない。地球儀の目線で大まかに括ればユーラシア大陸の北東部の料理という程度のもので、同じ目線でヨーロッパ料理と括っても何の意味も持たない。少し狭めて北京料理はどうかというと、内陸だから良好な食材はない。ダックは南京からサソリは砂漠からくる。貴族がいるから美味が集まった宮廷料理であって、我が国の京料理と称されるものの類似品だ。
中華といわれるのは八大菜系(八大中華料理)の総称で、八大をたぐっていけば各地のローカル料理に行きつく。それを一次加工品とするなら京料理や北京料理は二次加工品であって、大雑把に言うならヨーロッパ料理のなかでルイ王朝の宮廷料理として確立したフランス料理はイタリア料理を一次加工品とする二次加工品だ。少なくとも僕の知るイタリア人はそう思っているし歴史的にはそれが真相だが、パリジャンは麺をフォークに巻いて食うなど未開人と思っている。畢竟、始祖と文明とどっちが偉いかという不毛の戦いになるが、イタリア料理と僕らが呼ぶものが実は中華料理と同様のものだとなった時点でその議論も枝葉末節だねの一声をあげた人に軍配が上がってしまうのだ。
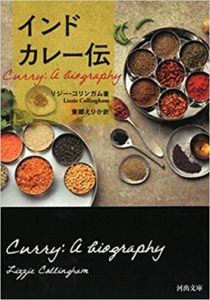 インドカレー伝(リジー・コリンガム著、河出文庫)を読むと、インドにカレーなどという料理はなく、それは英国(正確にはロンドン)のインド風(起源)料理(二次加工品)の総称であり「400年にわたる異文化の衝突が生んだ(同書)」ものとわかる。食文化というものはローカルな味の集大成であって、その進化は富と権力の集まる都市でおこるとは言えるのだろう。しかし、世界有数の都市である東京に洗練された食文化はきっとあるのだろうがそこで育った僕が山形の酒田で漁師料理を食ってみて、長年にわたって刺身だと思ってきたあれはなんだったんだと軽い衝撃を覚えるわけだ。
インドカレー伝(リジー・コリンガム著、河出文庫)を読むと、インドにカレーなどという料理はなく、それは英国(正確にはロンドン)のインド風(起源)料理(二次加工品)の総称であり「400年にわたる異文化の衝突が生んだ(同書)」ものとわかる。食文化というものはローカルな味の集大成であって、その進化は富と権力の集まる都市でおこるとは言えるのだろう。しかし、世界有数の都市である東京に洗練された食文化はきっとあるのだろうがそこで育った僕が山形の酒田で漁師料理を食ってみて、長年にわたって刺身だと思ってきたあれはなんだったんだと軽い衝撃を覚えるわけだ。
海外で16年暮らしていろんなものを食べ歩き、食を通じて経験的に思うことは、文化というものはなんであれローカルな根っこがあってそこまで因数分解して微視的に見たほうが面白いということだ。美しいとまでいうべきかどうかは自信がないが、素数が美しい、つまり同じ数字だけど「100,000」より「3」が好きだと感じる人はそれもわかってくださるかもしれない。素数が 1 と自分自身でしか割れないように、刺身は割れない。一次加工されていても大きな素数、23、109、587の感じがする鰹昆布ダシ、魚醤のようなものがある。割れないものは犯しがたい美と威厳を感じる。
咸臨丸で来たちょんまげに刀の侍一行の隊列を初めて目にした当時のサンフランシスコの新聞がparade with dignityと賞賛しているのはそれ、割れない美と威厳だったろう。いつの間にかそれがカメラと眼鏡がトレードマークのあの姿に貶められてしまうのは相手のせいばかりではない、敗戦を経て我々日本人が信託統治の屈辱の中、割れてしまった。アメリカに尻尾を振ってちゃらちゃらした米語を振り回して仲間に入れてもらって格上の日本人になったと思っている、そういうのは米国人でなくても猿の一種としか見ないのであって、dignityなる語感とは最遠に位置するものでしかない。
音文化である音楽というものにもそれがある。ガムランにドビッシーが見たものは「割れない美と威厳」だと僕は思っている。ワーグナーがトリスタンでしたことは「富と権力の集まる都市でのローカルな味の集大成と進化」であって、ドビッシーはそこで起きた和声の化学変化に強く反応し、やがて否定した。彼は素数でない領域で肥大した巨大数を汚いと感じたに違いない。だからガムランに影響されたのだ。音彩を真似たのではない、本質的影響を受けた。ワーグナーやブラームスやシェーンベルクにあり得ないことで、この議論は食文化の話と深く通じている。
先週行ったサンフランシスコのサウサリート ( Sausalito、写真 )がどこかコート・ダ・ジュールを思わせた。モナコ、カンヌ、ニースの都会の華やぎはなくずっと素朴で質素なものだけれど、なにせ暫くああいう洒落た海辺の街にご無沙汰している。
どこからかこの音楽がおりてきた。ガブリエル・フォーレの『マスクとベルガマスク』(Masques et Bergamasques)作品112。74才と晩年のフォーレは旧作を大部分に用いたが、後に作品番号を持つ旧作を除いた「序曲」「メヌエット」「ガヴォット」および「パストラール」の4曲を抜き出して管弦楽組曲に編曲している。
第3曲「ガヴォット」および第4曲「パストラール」はその昔、学生時分に、何だったかは忘れたがFM放送番組のオープニングかエンディングに使われていて、僕の世代ならああ聞いたことあると懐かしい方も多いのでは。当時、憧れていたのはどういうわけかローマであり地中海だった。クラシック音楽を西欧の窓口として聴いていたのだから、そういう回路で番組テーマ曲が思慕するコート・ダ・ジュールに結びついて、記憶の番地がそこになってしまったのだと思うが、しかし、ずっとあとで知ったことだが、この作品はモナコ大公アルベール1世の依頼で1919年に作曲され、モンテカルロで初演された生粋のコート・ダ・ジュール産なのだ。
 地中海、コート・ダ・ジュールにはマルセイユ、ニース、モンテカルロにオーケストラがあるが、カンヌのクロード・ドビッシー劇場を本拠地とするL’Orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte d’Azur(レジョン・ド・カンヌ・プロヴァンス・アルプ・コートダジュール管弦楽団 )のCD(右)をロンドンで見つけた時、僕の脳内では音文化は食文化と合体してガチャンという音を発してごしゃごしゃになり、微視的かつマニアックな喜びに満ちあふれた。
地中海、コート・ダ・ジュールにはマルセイユ、ニース、モンテカルロにオーケストラがあるが、カンヌのクロード・ドビッシー劇場を本拠地とするL’Orchestre régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte d’Azur(レジョン・ド・カンヌ・プロヴァンス・アルプ・コートダジュール管弦楽団 )のCD(右)をロンドンで見つけた時、僕の脳内では音文化は食文化と合体してガチャンという音を発してごしゃごしゃになり、微視的かつマニアックな喜びに満ちあふれた。
ここに聴くフィリップ・ベンダーという指揮者は2013年に引退したそうだがカンヌのコート・ダ・ジュール管弦楽団(なんてローカルだ!)を率いていい味を出している腕の良い職人ではないか。田舎のオケだと馬鹿にするなかれ、僕はこのCDに勝るこの曲の演奏を聴いたことがない。第4曲「パストラール」は74才のフォーレが書いた最高級の傑作でこの曲集で唯一のオリジナル曲だ。パステル画のように淡い色彩、うつろう和声はどきりとするほど遠くに行くが、ふらふらする心のひだに寄り添いながら古雅の域をはみださない。クラシックが精神の漢方薬とするならこれは鎮静剤の最右翼だ。この節度がフォーレの素数美なのであって、ここに踏みとどまることを許されない時代に生まれたドビッシーとラヴェルは違う方向に旅立っていったのである。
こう言っては身もふたもないが、こういう曲をシカゴ響やN響がやって何の意味があろう。ロックは英語じゃなきゃサマにならないがクラシック音楽まで英語世界のリベラリズムで席巻するのは勘弁してほしい。食文化でそれが起きないのは英米の食い物がまずいからだと思っていたが、音楽だって英米産はマイナーなのだから不思議なことだ。これは差別ではないし帝国主義でも卑屈な西洋礼賛とも程遠い、逆に民族主義愛好論であって、文在寅政権が危ないと思っているからといってソウルの土俗村のサムゲタンが嫌いになるわけでもない。なんでもできると過信した薩摩藩主・島津斉彬が昆布の養殖だけはできなかったぐらい自然に根差したことだと僕は思っている。
じゃあN響はどうすればいいんだといわれようが、それは聴衆の嗜好が決めること。僕のそれが変わるとは思えないが多数の人がそれでいいと思うならフランスから名人指揮者を呼んできて振ってもらえばいい。相撲はガチンコでなくていい、場所数が多いのだからそれでは力士の体がもたないだろう。だから少々八百長があっても喜んで観ようじゃないかというファンが多ければ日本相撲協会は現状のままで生きていけるが、オーケストラも相撲と同じ興業なんだとなれば僕は退散するしかない。音楽は民衆のものだが、お高く留まる気はないがクラシックと呼ばれるに至っているもののお味を民衆が楽しめるかどうかとなると否定的だ。相撲が大衆芸能であるなら一線が画されてしまう。「割れない美と威厳」を感じるのは無理だからだ。
余談だがシャルル・デュトワがMee tooでやられてしまったときいて少なからずショックを受けている。訴えが事実なら現代の社会正義上同情の余地はないが、日本で聴いた空前絶後のペレアスを振った人という事実がそれで消えることもない。日本のオケでああいうことのできる現存人類の中で数人もいない人だ、日馬富士が消えるのとマグニチュードが違うといいたいがそう思う人は少数なんだろう。エンガチョ切ったの呼び屋のMee tooが始まればクラシック界を撃沈するムーヴメントになるだろう。いいシェフといい楽士は貴族が囲っていた、やっぱり歴史には一理あるのかもしれない。
上掲のフィリップ・ベンダー指揮レジョン・ド・カンヌ・プロヴァンス・アルプ・コートダジュール管弦楽団のCDからフォーレ「マスクとベルガマスク」作品112を、ご当地カンヌの写真といっしょにお楽しみください。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
クラシック徒然草-秋に聴きたいクラシック-
2014 OCT 5 12:12:43 pm by 東 賢太郎

以前、春はラヴェル、秋にはブラームスと書きました。音楽のイメージというのは人により様々ですから一概には言えませんが、清少納言の「春はあけぼの」流独断で行くなら僕の場合やっぱり 「秋はブラームス」 となるのです。
ブラームスが本格的に好きになったのは6年住んだロンドン時代です。留学以前、日本にいた頃、本当にわかっていたのは交響曲の1番とピアノ協奏曲の2番ぐらいで、あとはそこまでつかめていませんでした。ところが英国に行って、一日一日どんどん暗くなってくるあの秋を知ると、とにかくぴたっと合うんですね、ブラームスが・・・。それからもう一気でした。
いちばん聴いていたのが交響曲の4番で毎日のようにかけており、2歳の長女が覚えてしまって第1楽章をピアノで弾くときゃっきゃいって喜んでくれました。当時は休日の午後は「4番+ボルドーの赤+ブルースティルトン」というのが定番でありました。加えてパイプ、葉巻もありました。男の至福の時が約束されます、この組み合わせ。今はちなみに新潟県立大学の青木先生に送っていただいた「呼友」大吟醸になっていますが、これも合いますね、最高です。ブラームスは室内楽が名曲ぞろいで、どれも秋の夜長にぴったりです。これからぼちぼちご紹介して参ります。
英国の大作曲家エドワード・エルガーを忘れるわけにはいきません。「威風堂々」や「愛の挨拶」しかご存じない方はチェロ協奏曲ホ短調作品85をぜひ聴いてみて下さい。ブラームスが書いてくれなかった溜飲を下げる名曲中の名曲です。エニグマ変奏曲、2曲の交響曲、ヴァイオリン協奏曲、ちょっと渋いですがこれも大人の男の音楽ですね。秋の昼下がり、こっちはハイランドのスコッチが合うんです。英国音楽はマイナーですが、それはそれで実に奥の深い広がりがあります。気候の近い北欧、それもシベリウスの世界に接近した辛口のものもあり、スコッチならブローラを思わせます。ブラームスに近いエルガーが最も渋くない方です。
シューマンにもチェロ協奏曲イ短調作品129があります。最晩年で精神を病んだ1850年の作曲であり生前に演奏されなかったと思われるため不完全な作品の印象を持たれますが、第3番のライン交響曲だって同じ50年の作なのです。僕はこれが大好きで、やっぱり10-11月になるとどうしても取り出す曲ですね。これはラインヘッセンのトロッケン・ベーレンアウスレーゼがぴったりです。
リヒャルト・ワーグナーにはジークフリート牧歌があります。これは妻コジマへのクリスマスプレゼントとして作曲され、ルツェルンのトリープシェンの自宅の階段で演奏されました。滋味あふれる名曲であります。スイス駐在時代にルツェルンは仕事や休暇で何回も訪れ、ワーグナーの家も行きましたし教会で後輩の結婚式の仲人をしたりもしました。秋の頃は湖に映える紅葉が絶景でこの曲を聴くとそれが目に浮かびます。これはスイスの名ワインであるデザレーでいきたいですね。
フランスではガブリエル・フォーレのピアノ五重奏曲第2番ハ短調作品115でしょう。晩秋の午後の陽だまりの空気を思わせる第1楽章、枯葉が舞い散るような第2楽章、夢のなかで人生の秋を想うようなアンダンテ、北風が夢をさまし覚醒がおとずれる終楽章、何とも素晴らしい音楽です。これは辛口のバーガンディの白しかないですね。ドビッシーのフルートとビオラとハープのためのソナタ、この幻想的な音楽にも僕は晩秋の夕暮れやおぼろ月夜を想います。これはきりっと冷えたシェリーなんか実によろしいですねえ。
どうしてなかなかヴィヴァルディの四季が出てこないの?忘れているわけではありませんが、あの「秋」は穀物を収穫する喜びの秋なんですね、だから春夏秋冬のなかでも音楽が飛び切り明るくてリズミックで元気が良い。僕の秋のイメージとは違うんです。いやいや、日本でも目黒のサンマや松茸狩りのニュースは元気でますし寿司ネタも充実しますしね、おかしくはないんですが、音楽が食べ物中心になってしまうというのがバラエティ番組みたいで・・・。
そう、こういうのが秋には望ましいというのが僕の感覚なんですね。ロシア人チャイコフスキーの「四季」から「10月」です。
しかし同じロシア人でもこういう人もいます。アレクサンダー・グラズノフの「四季」から「秋」です。これはヴィヴァルディ派ですね。この部分は有名なので聴いたことのある方も多いのでは。
けっきょく、人間にはいろいろあって、「いよいよ秋」と思うか「もう秋」と思うかですね。グラズノフをのぞけばやっぱり北緯の高い方の作曲家は「もう秋」派が多いように思うのです。
シューマンのライン、地中海音楽めぐりなどの稿にて音楽は気候風土を反映していると書きましたがここでもそれを感じます。ですから演奏する方もそれを感じながらやらなくてはいけない、これは絶対ですね。夏のノリでばりばり弾いたブラームスの弦楽五重奏曲なんて、どんなにうまかろうが聴く気にもなりません。
ドビッシーがフランス人しか弾けないかというと、そんなことはありません。国籍や育ちが問題なのではなく、演奏家の人となりがその曲のもっている「気質」(テンペラメント)に合うかどうかということ、それに尽きます。人間同士の相性が4大元素の配合具合によっているというあの感覚がまさにそれです。
フランス音楽が持っている気質に合うドイツ人演奏家が多いことは独仏文化圏を別個にイメージしている日本人にはわかりにくいのですが、気候風土のそう変わらないお隣の国ですから不思議でないというのはそこに住めばわかります。しかし白夜圏まで北上して英国や北欧の音楽となるとちょっと勝手が違う。シベリウスの音楽はまず英国ですんなりと評価されましたがドイツやイタリアでは時間がかかりました。
日本では札幌のオケがシベリウスを好んでやっている、あれは自然なことです。北欧と北海道は気候が共通するものがあるでしょうから理にかなってます。言語を介しない音楽では西洋人、東洋人のちがいよりその方が大きいですから、僕はシベリウスならナポリのサンタ・チェチーリア国立管弦楽団よりは札幌交響楽団で聴きたいですね。
九州のオケに出来ないということではありません。南の人でも北のテンペラメントの人はいます。合うか合わないかという「理」はあっても、どこの誰がそうかという理屈はありません。たとえば中井正子さんのラヴェルを聴いてみましたが、そんじょそこらのフランス人よりいいですね。クラシック音楽を聴く楽しみというのは実に奥が深いものです。
Yahoo、Googleからお入りの皆様。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。






