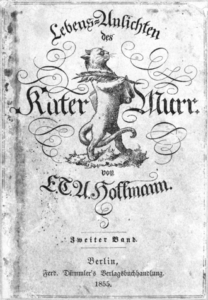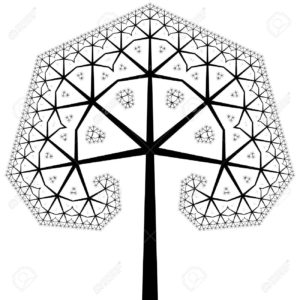E.T.Aホフマン「牡猫ムルの人生観」
2020 FEB 29 0:00:47 am by 東 賢太郎

序論
世の中は新型コロナで騒然としてきた。僕はウィルスのメカを医師に教わったり本やネットで調べたり、大昔からそういうことが好きであり、その結果で腑に落ちた世界観に忠実に2月から行動してきたのがコロナの一連のブログだ。世間がいまさらになって何を騒いでるかなんてことにはからっきし興味がない。唯一あるとすると、KOVID-19が特異だということだ。ウィルスはこわいし徹底して忌避しているが、それはそれとして、ぎょしゃ座エプシロンの伴星ぐらい知的好奇心を喚起されるものがある。この星に子どもの時からずっと興味があるが行ってみたいとは思わないのと一緒である。
人も物事も、齢65にもなると大事なのは興味あるかどうかだけだ。それは、僕の場合は「特異かどうか」なのだ(特異点さがしこそ僕の本質)。「特異」の意味を定義しておくが、「普通でない」ということだ。ではまず普通とは何か。ここでそれを表す日本語が少ないことに気づく(古語だと「つね」)。英語はcommon、usual、normal、average、ordinaryなど盛りだくさんだが、それらの否定語がすべて、ニュアンスの異なる「普通でない」になる。僕の言う「特異」はそのどれでもないからそもそも特異なのである。では何かというと、ある一点をもって偏差値80以上ほどのスペックが明確にあり、そのことが奇異だという、なにか秘境を見つけたようなワンダフルな特別のエモーションを喚起するものであって、英語はそれに対し、普通の否定形でない独立の形容詞を用意している。それはeccentricだ。
言葉は民族の感性と思考が生む。日本人は普通に重きを置かず西洋人は置く(だから分別する語彙が豊富)が、それはそもそも人間に同じ人はいないというギリシャ的視点からは同質の集団が珍しく、名前を付けて区別する動機があったからで、逆に日本人は人間は(庶民は)同質で、いわば羊が不加算名詞であるに似て、区別する動機がなかったから語彙が少ないのだと思う。西洋はその反作用として「普通でない」ものの普通でなさを細かく認識する語彙も豊富になったという気がするのだ。日本ではそれは「変な」「妙な」「けったいな」で感情的に否定して思考停止で終わってしまい、主知的な観察は放棄してしまう。つまり、根っから異質を嫌うそういう民族だということが語彙で分かる。
eccentric(エキセントリック)を多くの日本人は否定的な形容詞と思っているだろうが、むしろとんがった所を肯定するニュアンスだってある。ところがそれをうまく表す日本語がない、だからそういうことになるのである。僕においてはクラシック音楽は、常人が書けるものではないeccentricな音楽であり、したがって、そう定義した非常にピンポイントな意味において「特異」である。そう書きながら自分で馬鹿だと思うのは、特異な曲しかクラシックとして残らないトートロジーではないかと感じるゆえだ。つまりそれは長い時を経て西洋人が、それもとんがりを「なにか秘境を見つけたようなワンダフルな特別なエモーションを喚起するもの」として愛でることのできる美的素養、教養のある人たちが愛好してきたものだけのクラスターだ。だから「クラシック音楽」というジャンルは一曲一曲、特異を生むわくわくするような秘密があるのあり、僕のような習性の人間には楽譜を解剖してそれを解き明かす無上の喜びの宝庫である。
そのことは音楽だけでなく人間にも当てはまる。クラシックにまつわるすべての人物の内でもとりわけ特異な男がいる。eccentricだがもちろんその言葉のポジティブ・サイドの極だ。作曲家はみなとんでもない男ばかりだが、格別に特異であるのが本稿の掲題ホフマンである。能力というもの泣いても笑ってもアウトプットしたものでしか他人にわかりようも認められようもがないが、この男のそれは質も量も巨大だ。量だけならワーグナーに軍配が上がるが、それは音楽いち教科のこと。ホフマンは三教科で全部80越えだから異質の異能、二刀流どころか三刀流の達人であり、僕にとってあらゆる角度から興味を引く人間の最右翼である。いま邦訳で手に入る彼の小説を片っ端から読んでいるところだ。
(1)法律を学んだ音楽家たち(才能の二面性について)
 E.T.A.ホフマン(1776 -1822)は法律家の家に生まれた。彼がどういう人であったはわかりずらい。ケーニヒスベルクの陪席判事、プロイセンのワルシャワ市首席行政官、バンベルグの劇場支配人、ライプツィヒの音楽新聞の評論家、プロイセン大審院判事というところが給金を得るための公の職業であったが、後世は彼をまず幻想文学の小説家として、次にくるみ割り人形、コッペリア、ホフマン物語の原作者として、そして、作曲家ロベルト・シューマンに文学的影響を与えたマイナーな作曲家として記憶している。僕はというと、オペラ、宗教曲、交響曲、室内楽、ピアノ・ソナタが200年後にCDになっている人類史上唯一の裁判官として評価している。大酒飲みでパラノイアであり、反政府の自由主義者としてメッテルニヒに処分されそうになったが、うまく逃れてベルリンで梅毒で死んだ破天荒の男だ。
E.T.A.ホフマン(1776 -1822)は法律家の家に生まれた。彼がどういう人であったはわかりずらい。ケーニヒスベルクの陪席判事、プロイセンのワルシャワ市首席行政官、バンベルグの劇場支配人、ライプツィヒの音楽新聞の評論家、プロイセン大審院判事というところが給金を得るための公の職業であったが、後世は彼をまず幻想文学の小説家として、次にくるみ割り人形、コッペリア、ホフマン物語の原作者として、そして、作曲家ロベルト・シューマンに文学的影響を与えたマイナーな作曲家として記憶している。僕はというと、オペラ、宗教曲、交響曲、室内楽、ピアノ・ソナタが200年後にCDになっている人類史上唯一の裁判官として評価している。大酒飲みでパラノイアであり、反政府の自由主義者としてメッテルニヒに処分されそうになったが、うまく逃れてベルリンで梅毒で死んだ破天荒の男だ。
彼の「公の職業」はパンのためで、ライフワークは文学、なかんずく音楽であった。著名な音楽評論家でもあって、Allgemeine musikalische Zeitung(総合音楽新聞)の執筆陣に名を連ねている。この新聞は最古の楽譜出版社で今に至るブライトコプフ・ウント・ヘルテル社(https://mag.mysound.jp/post/491)のオーナー、ヘルテルらがドイツを中心とした音楽界の事情を発信するメディアとして立ち上げたものだ。19世紀になると作曲家は楽譜を印刷して収入を得ることで自立の道が開けた。そのため彼らは出版社と運命共同体であり、出版社は新聞に識者による評論を掲載して彼らの新作をプロモートし円滑に売ることができる。その良好な関係がワークするには執筆陣の質的な優位性はもちろんだが、同時に中立性が求められた。同紙が「御用新聞」でないことは、例えば、後に金の卵となる若きベートーベンが1799年の同紙で「モーツァルトの『魔笛』主題による変奏曲」を始めとする初期の変奏曲の変奏技術を同紙の複数の論者に酷評されていることで証明されている。
ところが同じ年のピアノ・ソナタ作品10(第5-7番)のレヴューで評が好転し、彼の作曲スタイルが初めて認知された。その後数年で、彼の初期作品の複雑さが同紙で重ねて議論されるようになり、それなら再演して確認しようという声が上がりだした。その例として1804年に同紙の発起人で主筆のヨハン・フリードリヒ・ロホリッツ(ゲーテ、シラー、E.T.Aホフマン、ウエーバー、シュポーアの友人)が交響曲第2番ニ長調(1803)の再演を求めていることが挙げられる。2番が難しいと思う人は現代にはいないだろうが、当時、初演だけでは専門家にも理解が充分でない “現代音楽” だったことが伺える。かように出版と評論が表裏一体を成して新作の理解と普及に能動的に関与していた。ロマン派に向けて準備していた時代のダイナミズムを感じられないだろうか。
その最も著名な例だが、E.T.Aホフマンは評論家として今日あるベートーベンの評価に貢献している。それは1808年(上掲写真の年)に同紙に発表した交響曲第5番、コリオラン序曲、ピアノ・トリオ作品70(第5,6番)、ミサ曲 ハ長調 作品86、エグモント序曲の論考であった。それが大きな影響力があったことはベートーベン自身が謝辞を述べたことでわかる。これぞホフマンの審美眼と文筆力のあかしだ。ちなみに本稿掲題の「牡猫ムルの人生観」に登場する楽長クライスラーのポートレートはその際に同紙に初めて登場している。ベートーベンもこの絵を眺めたのだろう。なおクライスラーという空想の人物はホフマン自身の分身、カリカチュアであることは後述する。
ホフマンの音楽はyoutubeで聴ける。廣津留すみれさんに教えていただいたクララ・シューマンのピアノ・トリオも良かったが、もっと前(1809年)に書かれたE.T.A.ホフマンのトリオもこの出来である。
お気づきと思うが、第4楽章はジュピター音型(ドレファミ)を主題としている。ペンネームのE.T.A.を使用しだしたのがやはり1809年であり、その “A” の由来を「Amadeusから」と述べている彼が音楽でモーツァルトへの敬意を示したのがこれだろう。
更に素晴らしいのは「ミゼレーレ、変ロ短調」である。
1809年の作品であるが、ここにもモーツァルトのレクイエムの和声や書法を想起させるものが聴こえる。
これだけの作曲ができる人がプロイセン大審院判事として判決文を書いていたという事実は一応の驚きではあるが、論理的な作業に人一倍すぐれた能力があるという理解でくくれないことはない。しかし、一転して、感性の領域である「砂男」などオカルト文学、幻想文学の作家でもあるという二面性の保持者となると、そのどちらもが人類史に作品が残る水準にあったという一点において非常に異例だ。ワーグナーは楽劇の台本も自分で書いたが、音楽のない指輪物語でどこまで彼の名が残ったかは疑問に思う。
ホフマンに限らず、音楽と法学をやった人は意外に多い。テレマン 、ヘンデル 、L・モーツァルト、チャイコフスキー 、ストラヴィンスキー 、シベリウス 、シャブリエ、ショーソン、ハンス・フォン・ビューロー、ハンスリック、カール・ベームなどが挙げられるが、このことをもって僕は「二面性」と言うのではない。比喩的に極めて大雑把に丸めればどちらも論理思考を要する点で理系的であり、この名簿にロベルト・シューマンも加わるわけだが、同時に、文学者、詩人というすぐれて文系的な資質も開花させる才能を併せ持つのは異例だという意味で二面的なのである。そして、以下に述べるが、名簿の内でもシューマンだけはE.T.A.ホフマンに匹敵する才能の二面性の保持者であった。それが本稿の底流に流れるもうひとつのテーマである。
シューマンがハイデルベルグ大学で法学を学んだアントン・ティボー教授も上記名簿のひとりだろう。同大学は1386年創立。ヘーゲルやマックス・ウェーバーが教授を勤め33人のノーベル賞受賞者を出したドイツで1,2を争う名門大学だ。ティボーはパレストリーナをはじめとする教会音楽の研究家でハイデルベルクを代表する楽団 “Singverein” を創設、運営していた音楽家でもあるが、ドイツの法典を「ナポレオン法典」に依拠させるか否かの「法典論争」の主役を張った法学界の大家である。ローマ法を基盤とする汎ドイツ的な民事法を「一種の法律的数学」とした主張は、キリスト教徒がルネッサンス以来懐いてきたアポロ的理性で諸侯が群立する神聖ローマ帝国に啓蒙の光を投じようという啓蒙思想的、自由主義的なものだ。中産階級市民の子であったシューマンが共鳴しそうな議論だが、しかし、教授は教え子に関しては「神は彼に法律家としての運命を与えていない」と審判を下し、シューマンは20才でライプツィヒに戻ってフリードリヒ・ヴィークに弟子入りする運命になるのである。
(2)フリーランスの音楽家
外科医の娘であったシューマンの母親が息子に法律を学ばせたのは、絶対王政末期から国民国家の揺籃期の当時、ガバナンスのツールである法典の専門家に権力側の需要があったからだ。法学は中産階級が確実に食える実学だったのである。かたや音楽家はミサを書いたりオルガンを弾く教会付きの職人でしかなく、宮廷に職を得てもモーツァルトですら料理人なみの待遇だった。「フリーランスの音楽家」などというものはベートーベンが出現するまで存在しなかったのである。19世紀に大学に通う子弟の家庭は地位も財力も教養もアッパーである。好んで息子を音楽家にする選択肢はなく、息子の方も教会と貴族によるアンシャンレジームに取り入る方が人生は楽だった。かような時代背景の中、神童ではなかったシューマンはピアノ演奏を覚えはしたが、20才まで作曲家になるレベルの訓練を受けていない。
日本語のシューマン本はほとんど読んだと思うが、その彼の思春期について音楽家か詩人かで迷う文学青年のごとく描くのが馬鹿馬鹿しいほどステレオタイプと化している。独語の種本のせいなのか日本人特有のセンチメンタルなパーセプションなのかは知らないがどっちでも構わない。本稿で本当にそうだろうかという反問を呈したい。僕は独語の原書が語学力不足で充分に読めないしその時間もないが、日本語になった充分な根拠があると思われるピースを推論という論理の力を借りて組み合わせるだけでもその反問は成立する。天才的作曲家であったという結果論から推論を逆行するのは学問的にナンセンスで「天才」という思考停止を強いる言葉は危険ですらある。音楽家の道を推してくれた父を16才で失い、20才で法学に挫折して国に帰ってきた青年である。本当に音楽、文学で食っていける自信があったの?というのが自然な疑問であろう。
その証拠に、なかったからピアノに人生を賭け、同い年のショパンにコンプレックスと焦りを覚え(それは評論家の仮面で巧みに隠している)、だからこそ自ら大リーグ養成ギブスばりの機械を作って星飛雄馬みたいに特訓し、ついに指を故障してその道すら断たれてしまったのである。夢見る詩人のシューマンはそんな悩みと無縁だったという類の仮定は否定する論拠はないが、現実性がないという反論を否定する論拠もない。最も身近にいた母は亭主が残したそこそこの遺産を相続したが、息子がそれを食い潰して終わる懸念を強く持ち、だから名門大学に進ませ、彼もそれにこたえるだけのギムナジウムでの優等な成績をあげていた。音楽の道と別の何かとを迷ったとすれば、それは法律家だったに違いない。彼のその道での生まれ持った能力が、その時点での意思に現実性を与えていたかどうかは別としてだが。
そう考える根拠は2つある。まず、彼が作品を愛読して強い思想的影響を受けたアイドルであるE.T.A.ホフマンが、まさにお手本のようにそれに成功した人だったからである。そしてもうひとつは、指の故障でピアニストを断念したおり「一時はチェロに転向することや音楽をあきらめて神学の道に進むことも考えた」(wikipedia)ことだ。彼はハイデルベルグ大学に進む前にまず父の母校であるライプツィヒ大学の法科に入ったが、彼が心酔したもうひとりのアイドル、ジャン・パウルは同大学神学部に在籍して1年で文壇に転身して成功した。法学の道もすでに断たれ自信も指針も喪失したシューマンが作曲でなく神学の道に向きかけたことは、彼にとって何が「現実的」だったかを雄弁に証明してくれる。
 現実性がない、という主張は歴史の大局を眺めない人にはピンとこない。時はナポレオン戦争後のウィーン体制下だ。そこで再びパリで革命の狼煙が上がる。靴屋だろうと音楽家だろうと法学者だろうと、シャルル10世がギロチンで斬首かという隣国の暴動に無縁、無関心でいられた人はいない。音楽史というのは戦争、政治力学、貨幣経済によほど鈍感、無知な人が書いているのか、とてもナイーブな、宝塚のベルばらのノリの説が堂々と真面目に信じられている。ウィーン体制が全面的に崩壊するのは1848年だが、その端緒となった七月革命は遠くポーランドにまで飛び火して、蜂起した祖国がロシアに蹂躙され悲嘆したショパンは『革命のエチュード』を書く、それほどの重大事件なのだ。20才のシューマンの精神状態はそのパラダイムに規定されていたという世界的常識に基づいて思考するというインテリジェンスなくして語れないものである。
現実性がない、という主張は歴史の大局を眺めない人にはピンとこない。時はナポレオン戦争後のウィーン体制下だ。そこで再びパリで革命の狼煙が上がる。靴屋だろうと音楽家だろうと法学者だろうと、シャルル10世がギロチンで斬首かという隣国の暴動に無縁、無関心でいられた人はいない。音楽史というのは戦争、政治力学、貨幣経済によほど鈍感、無知な人が書いているのか、とてもナイーブな、宝塚のベルばらのノリの説が堂々と真面目に信じられている。ウィーン体制が全面的に崩壊するのは1848年だが、その端緒となった七月革命は遠くポーランドにまで飛び火して、蜂起した祖国がロシアに蹂躙され悲嘆したショパンは『革命のエチュード』を書く、それほどの重大事件なのだ。20才のシューマンの精神状態はそのパラダイムに規定されていたという世界的常識に基づいて思考するというインテリジェンスなくして語れないものである。
音大の学生で七月革命とは何だったか正確に知ってそれを弾いている人がどれだけいるか?知らなくても音符は弾けるが、ショパン・コンクールのような舞台で満場を唸らせる演奏をしようというなら、カール・ベームが指揮者の条件とはと問われて「音楽の常識です」と答えたその事を心したほうが良い。その年にショパンと同じ20才だったシューマンが無縁であったはずはない。彼はビーダーマイヤー期の旧態依然たる人々を「ペリシテ人」と名づけて揶揄し、それに対抗する「ダヴィッド同盟」なる彼の革命のための脳内結社を作るが、フリーランスの音楽家に挑むも指を怪我してしまった不安な彼にとって心の要塞のようなものだったろう。『ダヴィッド同盟舞曲集』はもちろんのこと、『謝肉祭』や『クライスレリアーナ』を弾こうという人がそうした常識を身に備えていないというなら、僕には少々信じ難いことである。
(3)ベートーベンの後継者
その時代においてベートーベンこそ貴族にも教会にもひれ伏さず、群れを嫌い、権威を嫌い、束縛を嫌う叩き上げのスキルの持ち主だった。難聴だったことで彼の音楽に価値を認めた音楽家はいない。それは楽譜の読めない後世の信者が神殿に奉納した「天才伝説」という聖者の冠であり、モーツァルトの借金伝説と同様のものである。音楽家はまずピアノの即興演奏と変奏の技量で、そして何より名刺代わりの交響曲の作曲で、彼を人生の目標とした。新時代にフリーランスの音楽家として食っていくためにはベートーベンの正統な後継者だというレピュテーションを得ることが出世のパスポートだったからである。20才で法律を捨てて音楽で身を立てる決意をしたシューマンは、名誉もさることながら、それを得るコミットメントを自らに課したのである。
神童でありティーンエイジャー期に職業音楽家としての特訓を受けたモーツァルト、ベートーベン、ショパン、クララ、リスト、メンデルスゾーンらに比べ、作曲家としてのシューマンの心のありようには別種の立ち位置があるように思えてならない。私事で誠に恐縮だが、都立高校出で受験技術の訓練を積んでいなかった僕は大学で出会った有名難関校出に根本的に違う資質を見たが、ああいうものが20才まで作曲素人だったシューマンにあるように感じてしまう。10代の思考訓練は一生の痕跡を残すが、20を過ぎてからのは必ずしもそうならない。彼が根っからのロマンチストであるなら若くして十分に達者であったピアノでショパンのように詩人になり、交響曲やカルテットは書かなかったろう。しかし、彼はそういう人ではなかったのだ。町名(ASCH)を音化したり、ABEGGの文字を変奏したり、クララの文字や主題をミステリー作家のようにアナグラムとして仕掛けを施す論理趣味があり、バッハの平均律への執着、ベートーベンのピアノソナタ、交響曲のテキスト研究は文学青年の作曲修行などではなく、10代の思考訓練の賜物としての内面からの欲求であろう。その精神が青年ブラームスにも伝わり、ハンス・フォン・ビューローの「バッハは旧約、ベートーベンは新約」の言葉に受け継がれていったのではないだろうか。
ここでもう一つ、背景を俯瞰しておく。興味深いことだが、神学と哲学と法学と音楽はテキスト研究、解釈の方法論の厳格さにおいて科学に比肩する。神学についてあまり知識はないが、科学と神学は中世では同義であり、聖書の厳格なテキスト研究がマルティン・ルターのプロテスタンティズムを生んだと理解してる。音楽と法学は、明白に人間の書いたものなのに、あたかも神の法である科学の如く扱うという姿勢を、少なくともドイツ語圏ではとっていた。それはア・プリオリの法則ではなく、かくあるべしという「心理的態度」に過ぎないのだが、アントン・ティボー教授の「民事法は法律的数学」という比喩に見事に表象されている。後に音楽を数学的に扱う作曲家が現れるのもこの観察に整合的だろう。
音楽先進国イタリアには左様な心理的態度が芽生えなかった。「歌」に理屈はいらないだろうが、さらに本質的な理由として、カソリックが宗教改革と無縁であり続けたことと軌を一にするように思える。それは真にドイツ的な、ドイツ語世界での現象である。シューマンがとった態度を見ると、北イタリアを旅はしたが、ロッシーニを酷評し、オペラ等の歌は器楽の下に見る地点からスタートしている根っからのドイツ人である。アリアのように感じたまま気の向くままに心をこめて音楽すればいいという姿勢は程遠い。彼は評論家としてベルリオーズの幻想交響曲を医学の検体のような眼で眺め、第1楽章の自らによる子細な分析スタンスを「解剖」という言葉で端的に述べている。
(4)シューマンのファンタジーの深淵
一方で彼には、二面性の他方である、先達にはない非常にオリジナルな側面があった。文学からのインスピレーションである。文学者を志しライプツィヒ大学に学んだ父アウグスト、詩作を嗜んだ母ヨハンナから受け継いだ資質だろうが、彼の楽曲が生き残ったのは解剖、解析による堅固で論理的な要素の貢献よりも、その資質による詩的な要素の魅力によるところが多いというのは衆目の一致する所だろう。彼自身も、名人芸を浅薄としイタリア風を否定したが、同時に、規則にがんじがらめの対位法家を糞食らえとしている。「根本的に勉強したあとでなければ規範を軽蔑しないように。これ以上危険な反則はない」と述べている(「音楽と音楽家」38ページ)のに、「わたしはナイティンゲールのように、歌がつぎつぎとあふれてくる。わたしは歌って、歌って、歌い死にしそうだ」(同248ページ)とも書いているのが二面性の裏面だ。理性と情緒。その両方がバランスを時々に変化させながら、後にも先にも類型のないシューマンの音楽というものを形作っている。
彼は評論においても、ホフマンに負けず劣らず理性と情緒を駆使して美文調だが本質を鋭利に見抜く眼で音楽を語っている。シューマンの音楽評論はそのほとんどが、冒頭の「総合音楽新聞」(1798年創立)と同じライプツィヒでシューマン自身が発起人として1834年に創立した「新音楽時報」(Die Neue Zeitschrift für Musik)にて展開されることになる。「総合音楽新聞」の確立したベートーベン崇拝の伝統を受け継ぎ、シューベルトを発見し、ショパンの天才、ベルリオーズの新しさ、メンデルスゾーンの新古典主義を讃えるなど、ロマン派幕開け期の作曲家と作品の評価を高める貢献があったと評されているが、読んでみた僕の感想は、主情的、感覚的な人間と思われているシューマンが公平で客観的な眼を持っていることだ。ここにも二面性が現れている。
同年生まれのライバルでもあるショパンの持ち上げ方は理性を超えているように見えるが、彼の理性は科学のように客観性を内包した性質のものなのだ。シューマンにベルリオーズを称賛すべき何があるのか?「最高の力を持っているのは女王(旋律)だが、勝敗は常に王(和声)によって決まる」と述べている事実がある。そこで彼の幻想交響曲の第1楽章の子細な「解剖」を調べてみると、ブログで僕が「展開部ではさらに凄いことが起こる。練習番号16からオーボエが主導する数ページの面妖な和声はまったく驚嘆すべきものだ。」と書いた第1楽章のその部分に何の反応もコメントもしておらず期待外れだ。彼の称賛は和声も標題も形式も包含した新しい音楽(ノイエ・ムジーク)への情熱からベルリオーズをダヴィッド同盟の同志と見たものだと解するのが説得力があろう。マーラーが「私はシェーンベルクの音楽が分からない。しかし彼は若い。彼のほうが正しいのだろう」と評価したのと似たスタンスかもしれない。
「新音楽時報」は一時の中断を経て現在も刊行されているが、19世紀初頭から脈々と続く「ドイツ語世界」での批評家精神は畏敬に値する。批評、評論というものは主観に照らしたその物の形であるが、評者の思考プロセスに一定の普遍性、客観性が備わっていなくては説得力がない。評論にフロレスタンとオイゼビウスという ”二面性キャラ” を登場させ、知的に戯画化した文学的創作(ドビッシーが ”クロッシュ氏” によってそれを模倣しているが)がシューマンの評論を乾ききった理屈の干物にしないばかりでなく、自己の心のうちに潜む対立する2本のナイフによってその物の形をクリアに彫琢する。この手法は敬愛した文学者であるジャン・パウル、E.T.Aホフマンから継承したものであった。
バッハ、ベートーベンに習った「一定の普遍性、客観性」という入れ物のなかに、持ち前の詩情、ファンタジーの泉がこんこんと湧き出ているという様相が僕にとってのシューマンの楽曲の特性だ。
(5)「牡猫ムルの人生観」
E.T.A.ホフマンの長編小説「牡猫ムルの人生観」は学識のある猫による自伝である。ムルは上述した楽長クライスラー(ホフマン自身だ)の自伝のページをちぎって下書きやインクの吸取り紙として使用したが、製本ミスでそれが挿入されたまま両者が交互に現れる形で印刷されてしまったという誠にトリッキーで実験的な構造を持っている。当然ながら、章ごとに場面も人物もガラッと変わるが、その様はミステリーのカットバック手法かと思う程だ。何か深い意図があるか?と思ってとりあえず身構えて読むと、実は単なる印刷の失敗でしたというタネは落語的でもある(それでも捨て猫のムルが引き取られるのがクライスラー自伝の始めに来ているので時間的連続性は担保)。
シューマンは自己の精神の内奥に潜む二面性を知り、まったく同じものをE.T.A.ホフマンに見た。ホフマンはこの小説で自己を楽長クライスラーに投影し猫ムルとの裏表の二面性を描いたが、クライスラーという自分のカリカチュアは、ジャン・パウルが自作に登場させたドッペルゲンガー(Doppelgänger、自己像幻視)である。10代のころジャン・パウル(マーラーの「巨人」の作者)を精読し、その世界に浸りきっていたシューマンは自己像をひとつ提示するのでなく、アポロ的人物(フロレスタン)とディオニソス的人物(オイゼビウス)に分割した。ふたりの対話で評論は書かれるが、実は彼らはそれを記述しているシューマンに対するドッペルゲンガーであり、シューマンは文面に出ないがシャーロック・ホームズに対する記述者ワトソンとして存在している。
同書は「そもそも猫が執筆なんて」というところからホフマンの術中にハマれない頭の固い御仁はお断りでございという軽妙洒脱とハイブロウな粋(いき)がスマートで格好良く、愛猫家の必読書である(ただし岩波の日本語版は絶版だ。独語、英語は入手できる)。そこはソフトバンクのお父さん犬と同様だ、それってアリだよねと楽しんでしまう姿勢がいいねという暗黙知が世間にあるからそのキャラが成り立つのであって、見た者は死ぬと伝わるドッペルゲンガーの不気味さはないが、何せ未完だから本当はどういう構想だったかは謎だ。
シューマンはこれを読んだインスピレーションで「クライスレリアーナ」を書いた。本作は漱石の「吾輩は・・」と歴史的名作をふたつも生んだ偉大な作品ということになる。E.T.A.ホフマンは生涯の業績をマクロ的に見てもお化けのように巨大だが、こうして細部をミクロで見てもやっぱりお化けであるというフラクタル型巨人である。漱石は作中で本作に軽く言及している。知ってるけどパクリでないよというスタンスだが、どう考えてもパクリだろう。それでも上質のパロディではあるから不名誉どころかお見事と称賛したい。ただ、漱石は猫に自分の言いたいことを語らせただけであり、ドッペルゲンガーの闇はない。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
Categories:______シューマン, ______ロッシーニ, 読書録