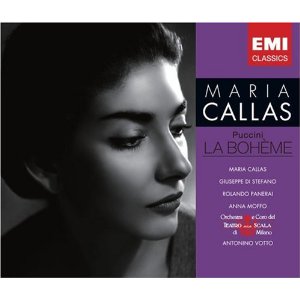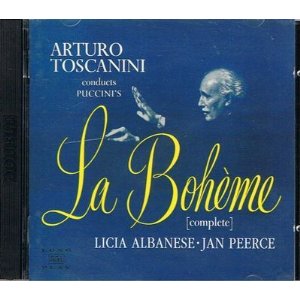僕が聴いた名演奏家たち(ヘルベルト・フォン・カラヤン)
2019 DEC 20 22:22:03 pm by 東 賢太郎

 昭和のころ、「巨人・大鵬・卵焼き」というミーハーを揶揄する言葉があった。そのクラシック版は?というなら「巨人・カラヤン・卵焼き」だろう。「外車はベンツ、第九はカラヤン」でもいい。クラシック通を自認していた御仁たちはそんな初心者と俺はちがう、ミーハーと一緒にするなと「カラヤン嫌い派」を形成していたように思う。もっと上級者の領域では様相はやや違う。カラヤンはたしかにベルリン・フィルを率いるだけの腕達者であって、新譜が出てくれば悔しいけど聴かずにはいられない。聴きたい。それは否定し難い。しかし、それでも私はイケメンで才能があって富豪で権力者などというのは許し難く認め難いのだ、要は、そういう奴は無条件に嫌いなのだという層もあった。識者であるその連中は「欠点はあるぞ、彼の華美な作り物の音楽だ、あんなものは低級な俗物だ」という方向に攻撃材料を作った。ある評論家は、あれは年増の厚化粧と書いた。なかなかうまい表現だが、要は、男の寂しい嫉妬である。
昭和のころ、「巨人・大鵬・卵焼き」というミーハーを揶揄する言葉があった。そのクラシック版は?というなら「巨人・カラヤン・卵焼き」だろう。「外車はベンツ、第九はカラヤン」でもいい。クラシック通を自認していた御仁たちはそんな初心者と俺はちがう、ミーハーと一緒にするなと「カラヤン嫌い派」を形成していたように思う。もっと上級者の領域では様相はやや違う。カラヤンはたしかにベルリン・フィルを率いるだけの腕達者であって、新譜が出てくれば悔しいけど聴かずにはいられない。聴きたい。それは否定し難い。しかし、それでも私はイケメンで才能があって富豪で権力者などというのは許し難く認め難いのだ、要は、そういう奴は無条件に嫌いなのだという層もあった。識者であるその連中は「欠点はあるぞ、彼の華美な作り物の音楽だ、あんなものは低級な俗物だ」という方向に攻撃材料を作った。ある評論家は、あれは年増の厚化粧と書いた。なかなかうまい表現だが、要は、男の寂しい嫉妬である。
しかし、日本人よりもっとカラヤンを嫉妬した人がいた。ウィルヘルム・フルトヴェングラーである。どこにもある、強力な若手の台頭にじいさんがビビる話だ。あいつは優秀だ、イケメンだ、正妻のベルリン・フィルを寝取られると怯え、そのとおり取られた。浮気相手のウィーン・フィルも取られた。もう彼は死んでいたけれど、それは非常に正鵠を得た予見であったといえる。カラヤンが権謀術数としてそうしたかどうか知らないが、ライバルのトスカニーニを範としたスタイルでフルトヴェングラーの盤石の牙城に切り込んだのは正解だった。速めの爽快なテンポや流麗なレガートだけではない、レパートリーからしてそうだ。ロッシーニのウィリアム・テル序曲をトスカニーニほど痛快にカッコよく指揮した指揮者はいないが、唯一肉薄したのはカラヤンだ。
我々はフルトヴェングラーはおろかクナッパーツブッシュ、カイルベルト、ベームというドイツの保守本流がスカラ座で蝶々夫人なんかを振る姿を想像もできない。そっちが本家だったイタリアのマエストロ、トスカニーニはベートーベンもワーグナーもブラームスも得意としたが、オーストリア人のカラヤンはその路線を逆輸入して踏襲したと思えばわかりやすいだろう。ドイツ音楽の保守本流ど真ん中に鎮座しながらイタリアオペラでも名をあげた指揮者は彼しかいない。
僕はチャレンジャー時代のカラヤンを聴けた世代ではないが、レコードは彼の才能を雄弁に語ってくれている。中でも最も好きなのが、1963年ウィーン国立歌劇場でのラ・ボエームのライブ録音だ。これはこの名オペラの数ある録音の中でも白眉としての地位を占める特筆すべき記録である。全曲を、ぜひ聴いていただきたい。
このビデオにいただいたコメントにこう返信した。
カラヤンはこの公演直前にスカラ座で新人フレーニをミミに起用して当たり、自信満々でそのプロダクションごとウィーンに持ってきたのです。彼はイタリア語上演にこだわりスカラ座のプロンプターを連れてきたことが発火点になってウィーン国立歌劇場の組合のボイコットにあい、プレミエはストライキで中止になります。数日後にプロンプターなしで合意してやっと幕が開いた初日がこの録音です。労働問題としての理解はできますが、我々日本人はたかがオペラ、たかが娯楽と思ってしまう部分もあります。歌手は外人OKでもそれ以外は国家公務員だし、スイトナーがフィガロをドイツ語で録音したのはこの翌年で、イタリア語上演がそうすんなりいく雰囲気でなかった時代背景も読み取れますね。
モーツァルトがイタリア語で書いたダ・ポンテ・オペラだけではなく、イタオペをドイツの諸都市でドイツ語版で演奏したドイツの指揮者はいる。カール・ベームのオテロ(1944年)、シュミット・イッセルシュテットは運命の力(1952)、ホルスト・シュタインやクルト・マズアもヴェルディを録音したし、フランス語のカルメンのドイツ語版はヘルベルト・ケーゲル盤(1960)やオイゲン・ヨッフム盤(1960)がある。ドイツ語圏で需要があったからだ。上記コメントで「スイトナーがフィガロをドイツ語で録音したのはこの翌年で」と書いたのは、1963年はそれがちっとも不思議でなかった時代だということをお示ししようとしている。
そんな時代に、「スカラ座イタリア語上演」で天下のウィーン・シュターツ・オーパーに乗り込んだのがヘルベルト・フォン・カラヤンだったのである。その歴史的記録こそが上掲ビデオのラ・ボエームなのだ。その試みが伊達や酔狂ではないことは、いまどき、ボエームをどうしてもドイツ人のプロダクションでドイツ語で聴きたい人がドイツにだっているだろうかと問うてみればわかる。しかし、1960年代当時は、まだたくさんいたのだ。だからウィーン国立歌劇場にその専門のプロンプター(歌手が歌詞や出だしを忘れたり間違ったりしないようキューを出す係)がおり、カラヤンが本場スカラ座のプロンプターを連れてきたら俺たちは失業するじゃないか、ふざけんな!と組合に提訴して大騒動となり、なんとオープニング公演がストライキで飛んでしまったのである。
このストライキ事件は元々火種があった歌劇場と裏方従業員の労働時間問題に油を注ぎ、翌1964年に行政裁判所に提訴される。カラヤンのイタリア人プロンプターの起用が与えたオーストリア人プロンプターの経済的損失が争点となったが、ウィーン国立歌劇場はミラノ・スカラ座と互いの最高の制作を交換し合う契約があったのだからおかしいだろうというカラヤンの主張が認められた。理屈からして当たり前であるが、サラリーマン時代に国際派だった僕は「理念だけのグローバル」が純ドメ派のナショナリズムでいともたやすく曲げられるこんな場面に何度も遭遇したのでカラヤンに同情してしまう。そこで宗教裁判に陥らなかった1964年のオーストリアの裁判所は少なくとも現在の隣国のそれより立派である。しかし、その法の裁きが6月出る前の5月、カラヤンはウィーン国立歌劇場の運営ポリシーに愛想をつかし音楽監督を辞めてしまう。
ちなみに、プロンプターが大事ということは上掲ビデオの第2幕で子供の合唱が大きく乱れる部分でわかる。スキャンダルの数日を経てやっとこさで初日を迎えたこのライブ録音は喧嘩両成敗の妥協策としてプロンプターなしで強行されていたのだ。子供はかわいそうだったが、パネライ、タッデイ、ライモンディ、フレーにら大人たちだって我々素人にはわからない数々の難所を迎えていたろう。このビデオにコメントをくださった指揮者の方は「ボエームは指揮するのが最も難しいオペラ」とされている。この演奏で聴けるイタリア人たちの歌はまさにホンモノだ。まだ28才だったミレラ・フレー二はこれに先立つ同曲スカラ座公演デビューで大成功し、彼女の代名詞となったミミはここからスタートしたのである。
イタオペは嫌いだと何度も書いた。ヴェルディの曲はかけらも興味ないし、プッチーニもほとんどはどうでもいい僕が、唯一、ラ・ボエームだけ例外というのは不可思議だ。なぜなら、スコアを見ずに頭の中で全曲リプレイできるオペラといったら魔笛とカルメンとこれしかない。ということは客観的ファクトとして「座右の3大オペラ」に99%以上の曲が嫌いなイタオペが堂々と入っているのだ。なぜそういうことになるのかは「楽譜に即物的根拠があるはずだ」というのが僕の合理主義者としての譲れぬ態度だが、未だに自分の内面を解明できていないというのは少なくない認知的不協和を発生させることになる。不可思議という語をここに置くしかない。
ともあれボエームの全音符が好きであり、全部を一緒に歌いたい。そうすると、若返った気がする。これを振った55才のカラヤンは若くはないが、気概は若かった。わが身と重ねて恐縮だがそれは僕が独立した年齢であり、ギリシャ系の血がそうさせたのだろうか彼はドイツ純ドメ派ではなく国際派だった。「カラヤンは低級な俗物」、「年増の厚化粧」と断じてしまう一派とは高校時代からどうも肌が合わないと感じていたのは血なんだろうか。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
音楽の偏食はあたりまえである
2019 JUL 15 17:17:34 pm by 東 賢太郎

演奏家にはレパートリー(repertoire)がある。何でも初見で弾けるピアニストはいても、それが即レパートリーというわけにはいかない。演奏家は自分の何らかのステートメント(statement、声明、自己証明)を他人の書いた楽曲に乗せて発信する人という認識が19世紀後半に主流になり、聞き手はそれを愛でに会場に来るというのが現代に至ってオペラやコンサートの定型的な図式となった。つまり演奏家とはステートメントによって自らを世にアピールする存在であって、その一点において「弾ける曲」と「レパートリー」とは決定的に違う。
自分で音を紡ぎだす肉体的制約のない指揮者はレパートリー選択の自由度は高いと書いてそれほど間違いではないように思う。カラヤン、オーマンディー、ネーメ・ヤルヴィは何でもござれのイメージがある。実はカラヤンはそうでもないが、守備範囲は前任フルトヴェングラーよりずっと広かった。かたやジュリーニやカルロス・クライバーは狭かったが、だからふたりがカラヤンに劣ると思う人は少ないだろう。ステートメントの品質は物量で決まるわけではない。
このことは演奏する側ばかりでない、聴く側にもあると思うがいかがだろう。僕は幼少時に偏食だったので「なんでも食べなさい」と言われて育ったが結局そうはならなかった。おそらく多くの方がちょっと苦手なもの、嫌ではなくて出てくればいただくが、自らレストランではあまり注文しないものがあるのではないだろうか。食物と違って音楽は生命維持に必要なわけではないから好き嫌いで選んで文句を言う人はいないし、一切聞かないという選択肢だってある。
つまり音楽は偏食があたりまえなのであり、僕のようにベンチャーズもモーツァルトもメシアンも半端なく日常的に好きだという雑食はむしろマイノリティである。好きの根っこは古典派にありそうな気がするが今は音楽室に入るとラフマニノフPC3Mov2冒頭とブルックナー7番Mov2冒頭を弾くのが日課であり、どうしてもその欲求に負ける。それがどこから湧き出てくるのかわからない。その5人の音楽家の作品に僕に響く何らかの共通因子があるということだけは確実だが解明したところで誰の役にもたたないし日本のGDPにも世界平和にもならないからしない。響く器のほうが僕なのだと定義すれば足りる。畢竟、それがステートメントの本質である。
僕のレパートリーは学生時代にできて、そこからは忙しくてあまり進化していない。浪人して若さとヒマが両立しており、当時だと3回で暗記OKだから図書館でかたっぱしから聞き、それはできた。万事興味ないことは覚えないから花や木の名前は数個しか言えないが、好きな曲はオペラでも室内楽でもバスを暗譜で歌えるまで記憶しており、そうなったものを僕は自分の鑑賞レパートリーとして認識している。ブログで曲名タイトルで書いた楽曲はすべてそれに属している。ブログもステートメント発信だからそれが自分であるという表明であり、レパートリーでない音楽への意見表明は僕の価値基準からは不適格だからそれに自分を代表させようということはあり得ない。
お気づきかもしれないがイタリアオペラはボエーム1曲しかない。プッチーニは多少好きということでスカラ座、コヴェントガーデン、メットなどで代表作はぜんぶ聞いているがそれでも記憶には至っていない(つまり続けて3回聞いてない)。「ボエーム」と「その他全部」でボエームのほうが重い。ボエームの音源は17種類もっていて魔笛の18種に次ぐから全オペラの堂々第2位なのであって、どうしてそれがイタオペという鬼門のジャンルに鎮座しているのか不思議でならない。10余年ヨーロッパに住んでいてヴェルディを歌劇場できいたのは数回で、そんなに少ないのに回数すら覚えてないしアイーダは白馬が舞台に出たのしか覚えてない。レコード、CDを家で全曲通したことはない。
ちなみにイタリア国や文化が嫌いなのではない。イタメシもブルネッロ・ディ・モンタルチーノもローマ史も半端なく好きだし、カエサルは尊敬してるし、スキー場もゴルフ場もグッドだし、クルーズは2回したし観光で一番たくさん訪れた国だし、アマルフィの油絵を居間に掛けて毎日眺めている。しかもミラノではイタオペ大権現トスカニーニの墓参りまでしたのだ。なんで「オペラ好き親父」でないの?わからない。出てくればいただくが自分からは食べないというのは英語で indifferent (どっちでもいい)であるが、無関心なもののために4時間を空費することは耐えられないという理由から僕はヴェルディはマーラーと同じく嫌い(dislike)だといって差し支えない。
それでヴェルディ、マーラーの音楽に身勝手な優劣を論じているつもりはまったくない。記憶してもいない曲を論じる資格はないというのが僕の絶対の哲学である。単に、二人の音楽の効能、一般には予期される化学反応が僕にはいささかも発揮されないということだ。「効きますよ」という薬を何度飲んでも効かないだけのことで、だから何百万人が「効きます」と声高に言っても僕には関係ないのである。正確に繰り返せば、薬は indifferent な存在なのだが、飲む時間の空費が dislike なのだ。イタリアはいつでも行きたいが、行って音楽を聴かないでOKな欧州唯一の国だ。ベニスでもフィレンツェでもナポリでもボローニャでもジェノバでも聴いてないし、ミラノではスカラ座には3回入ったが2回はワーグナーとグルックであり、一番時間を費やしたのはモーツァルトの足跡巡りだった。
石井宏著「反音楽史」(新潮文庫)は僕が教育の過程でドイツ人学者たちの洗脳の餌食になっていた可能性を示唆してくれた。そうかもしれないしそれではイタリア音楽にとって不遇でアンフェアとも思うが、仮にそうだとしてその洗脳がなければ僕がヴェルディ好きになったかといえば全くそうは思わない。学者がいくら頑張ってもモーツァルトやベートーベンの音楽が優れていなければこういう世の中にはなっていないし、逆に、「反音楽史」でなるほどとなってもイタリア音楽の魅力がそのことで倍加するわけでもない。似たことで、近隣国が我が国に対してそれ同様の歴史評価逆転劇を狙っていろいろの仕掛けを考案されご苦労様なことだが、ドイツ音楽と同じことで、古より和をもって貴しとなしサムライの精神で研ぎ澄まされた我が国の精神文化の優位性が揺らぐはずもないのである。
クラシックと一口に言ってもバロック前、バロック、ロココ、古典、ロマン、後期ロマン、近代、現代に分科し、演奏形態で教会音楽、オペラ、声楽、協奏曲、管弦楽、室内楽、器楽、電子音楽に分科して両者がマトリックスを成す。その個々に硬派な演奏家とファンがおり、通常はあまりまたがらない。僕の記憶ストックは時代として古典前後が多いがそれはユニバースがそうなためで、ユニバース比でマトリックスのセグメントでは近代・管弦楽のシェアが高い。そこに位置する著名作曲家がレスピーギしかおらず、ロマン・オペラしかないイタリアは国ごと視野になく、後期ロマン/近代・オペラであるプッチーニだけが残ったということだと思われる。
近代・管弦楽の硬派なファンとしては僕は分科またぎができる方で、クラシックの中においても雑食派だと思う。ヒマにあかせて受験勉強の要領でレパートリーを一気に作ったから20代から進化してないし、逆にそこから脱落する曲もあってむしろ減ってるのではないだろうか。クラシックは飽きが来ない、だからクラシックになるんだと思っていたがそんな特別なものではない。ちゃんと飽きる。というより、原理原則でいうと、既述の「無関心なもののために*時間を空費することは耐えられない」ということであって、飽きる=無関心(indifferent)となり、しかも人生の残り時間が逓減するにつれ単位時間あたりの限界効用価値の期待値はバーが高くなり、ダブルの逓減効果で飽きる=嫌い(dislike)と進行していくのである。
しかし、何百回きいても飽きない曲があるのも事実だ。ビートルズのSgt. Pepper’sとAbbey Road、ベンチャーズやカーペンターズやユーミンの一部はそれに属する。そしてモーツァルトやベートーベンの大半の曲もそこに属する、そういう形で僕の「音楽ユニバース」はできているからそこにクラシックというレッテルは貼らないし、いわゆるクラシックファンの一員ではないし、いわゆるオーディオファイルの一員でもない。レッテルをどうしても貼るなら枕草子で清少納言が400回以上使っている「をかし」しかない。僕は「をかしき音楽」ファンであってクラシックにそうでない “名曲” はいくつもある。僕のユニバースがユニバーサル(普遍的)と思ったことは一度もないし、あれを貴族社会で決然と書いて残した清少納言もそんなことは気にもかけてなかったろう。枕草子は随筆(essay)とされるが、僕流にはあれこそが保守本流のステートメントだ。
(この稿のご参考に)
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
プッチーニ 「ラ・ボエーム」
2012 NOV 18 18:18:47 pm by 東 賢太郎

僕の世代の男性、このオペラが琴線にふれない人がいるのだろうか?
これが始まると1分のうちに僕は20代にもどっている! なんという素晴らしい音楽!!歌、歌、歌!!! 青春をうたいあげたオペラでこれをしのぐものはない。
プッチーニは自分のオペラのヒロインのなかでミミが好きだったらしい。だからだろう、愛情に満ちた渾身のアリアをミミに書いてあげている。蝶々さんにもトスカにもない。ミミの死の場面は感動のあまり泣きながら書き終えたと言われている。
クリスマスイヴ。ろうそくが風で消えてしまい、鍵を手さぐりで探したミミとロドルフォの手が触れる。我々の世代はまだロドルフォになれた。LED照明時代の今なら3 メートル先から「そこに落ちてますよ」で終わりだろう。今の若者がかわいそうな気がしてくる。
この曲、何回実演を聴いたか覚えてもいない。メット、フランクフルト、ヴィースバーデン、チューリヒ、香港、東京などで。そして聴くたびに、舞台を見ても音だけでも、どうしても第4幕で涙が止まらなくなる。はずかしいのでオペラハウスにはあまり行かないことにしている。プッチーニがこの音楽に封じ込めた力はすさまじい。
原作のアンリ・ミュルジュの小説は題名が『ボヘミアンの生活情景』。時は19世紀の半ば、パリのクリスマス・イヴである。第1幕。文無しの芸術家の卵たち、詩人ロドルフォ、画家マルチェッロ、音楽家ショナール、哲学者コッリーネがカルチェ・ラタンに近いアパートの屋根裏部屋で暮らしている。原稿を薪がわりに暖をとるほど貧しい。しかし彼らは人生を謳歌している。若さと未来がたっぷりとある。家賃を取りたてにきた大家を追い出してしまうと、カフェ・モミュスでイヴを祝おうぜと出ていく。
あとで行くよと一人残ったロドルフォ。そこに階下に住むというお針子のミミがノックして入ってくる。ここで二人が出会うことになるのだが、それが鍵の場面になる。そこで歌われるロドルフォのアリア「冷たい手」、ミミのアリア「私の名はミミ」など有名だが、このオペラはアリアだけでもっているわけではない。最初の1音から終わりの1音にいたるまで途切れることのない素晴らしい音楽の連続で、アリア集など作ってもナンセンスなオペラなのである。
暗い舞台設定の第1幕が閉じて第2幕のカーテンが上がったときに目にする華やいだカフェ・モミュスのクリスマスを祝う群衆のざわめき!(左は2011年メットのポスター、下の方の写真が第2幕の舞台である)。誰もがオペラの贅沢さに息をのむ瞬間であり、そこに目くるめくばかりの奔流のような音楽が息つく間もなく流れていく。子供の歌がアクセントになり、マルチェッロの彼女である(あった)ムゼッタの歌う「私が街をあるけば」の魅力的なこと!天才の仕事であるとしか言いようがない。
第3幕は翌年2月。舞台は夜明けのパリ郊外、ダンフェール門の徴税所に雪が降る寒々とした場面。悲劇の影がさしてくる。「ミミを愛しているが、彼女は結核を患っており、貧乏の自分といても助からない。別れなくては」とロドルフォが言う事態になってくる。「以前買ってもらったあの帽子だけは、良かったら私の思い出にとって置いて欲しい」と言い残してミミは去る。咳こむミミ。アリア「さようなら、恨みっこなしにね」 。このあたりの音楽はもうすでにとても悲しい。
しばらく時がたって第4幕の舞台は再びアパートの部屋に戻り、第1幕と同じ音楽で幕を開ける。ロドルフォとマルチェッロは昔の愛を語りあい、孤独を嘆く。そこへコッリーネとショナールがささやかな食事を運んで来る。4人は踊り始め、決闘のまねごとをしたりして戯れている。そこへムゼッタが瀕死のミミを連れて駆け込んでくる。ミミは愛するロドルフォの元で最期を迎えたいと望んでいる。仲間たちはアクセサリーを売ったり外套を質に入れたりして薬を手に入れようと奔走するが甲斐なく、ミミは息をひきとる。
こう書いてしまうと味気ないがプッチーニはワーグナーのライトモティーフという手法を用いて、死に瀕したミミがロドルフォに語りかける場面では出会いの幸せだった場面(第1幕)の旋律をひっそりと回想などする。これがかわいそうで、この辺からはもう泣かずに抵抗などできるものではない。演奏している人たちはそういうわけにもいかないからそれもかわいそうだといつも思う。ミミが亡くなったことはホルンの長い和音が知らせる。永遠の青春譜である。
トゥリオ・セラフィン/ 聖チェチーリア音楽院管弦楽団・合唱団
1959年8月、ローマでの録音。DECCA原盤。
ミミ(レナータ・テバルディ)、ロドルフォ(カルロ・ベルゴンツィ)、ムゼッタ(ジャンナ・ダンジェロ)、マルチェッロ(エットーレ・バスティアニーニ)、コルリーネ(チェザーレ・シエピ)、ショナール(レナート・チェザーリ)
僕はこれでボエームを覚えた。キャストも指揮もオケも最高であり、録音も素晴らしい。ベルゴンツィのロドルフォ、バスティアニーニのマルチェッロが実に立派であり、テバルディのミミも若々しくはないが音楽的に充実しきっている。ローマのオケもいい。そして何より名指揮者セラフィンが見事につわもの達をコントロールしている。これを凌駕するボエームが現れるとは当面考えられない。僕はチューリヒ歌劇場とNHKホールでネロ・サンティが振るのを計3回聴いたが、現役で対抗できるのは彼ぐらいだろう。このオケパートは簡単ではない。ベルリンフィルやウィーンフィルならいいという単純なものではない。第1幕である。
まず、プッチーニの和声法は三和音の伝統的和声法をぜんぜん外れていないので気がつきにくいが、実はドビッシーを感じさせる、いや凌駕さえしている非伝統的な感性に彩られている。ちょっとした場面転換や登場人物の気持ちのうつろいにつく素晴らしい転調や万華鏡のように自在な和声の揺らぎ!台本が若者たちの未熟さ、うぶな恋のかけひき、友情など、食べて恋して歌ってオンリーのイタオペらしからぬリアリズムと繊細さを秘めており、プッチーニの語法がぴったりと寄り添うことで空前絶後の効果をあげていることがボエームの成功の一因であることは間違いないだろう。
オケは3管編成でバス・クラリネット、バス・トロンボーンまであり、打楽器は木琴、カリヨン、鐘、チェレスタ、ハープまでありと、それだけ聞けば現代音楽かなと錯覚する。ズンチャッチャとお歌の伴奏をするオケとは程遠いシロモノである。作曲家の意図通りにこのオケを駆使しないとボエームは演奏できないのである。あたりまえのイタオペ指揮者ではだめだ。耳と力量が非常に問われる。余談だが、チューリヒでは指揮者のすぐ後ろの席だった。ロドルフォが不調で、第1幕が終わると同時につい「こりゃあひどいな」と(日本語で)思わず言ってしまったら振り向いたサンティに睨まれてしまった。そのためかどうか、第2幕開始前に「テノール(誰か忘れたが)は今日はのどの調子が悪い、あしからず」と(ドイツ語で)場内アナウンスがあった。だから仕方なくその日は目の前のオケばかり聴いていたのだが、忘れられない名演奏であった。
トーマス・シッパース / ローマ歌劇場管弦楽団・合唱団 ミミ(ミレッラ・フレー二)、ロドルフォ(ニコライ・ゲッダ)、ムゼッタ(マリエッラ・アダーニ)、マルチェッロ(マリオ・セレーニ)、コッリーネ(フェルッチョ・マッゾーリ)、ショナール(マリオ・バジオラJr.)
フレーニといえばミミ、ミミといえばフレーニである。後にカラヤン盤などに起用されるが64年録音の当盤ではまだ28歳!そして夭折したシッパースも、美声のロドルフォであるゲッダもまだ30代!この大スターたちの若さの記録であるこの録音は永遠の価値がある。ローマのこの歌劇場、92年に聴いたジョコンダは熱かったが、いいオケを使ったとも思う。ムゼッタが固いなどセラフィン盤の完成度は求めるべくもないが、ボエームらしいボエームはこちらなのかもしれない。
アントニノ・ヴォットー / ミラノ・スカラ座管弦楽団&合唱団
ミミ(マリア・カラス)、ロドルフォ(セッペ・ディ・ステファノ)、ムゼッタ(アンナ・モッフォ)、マルチェッロ(ローランド・パネライ)、コッリーネ(ニコラ・ザッカーリア)、ショナール(マヌエル・スパタフォーラ)
録音:1956年8月3,4日、9月12日ミラノ・スカラ座劇場
マリア・カラスの声質はミミに向いているとは思えない。しかし、うまい。ミミらしく繕うのではなく「私の名はミミ」などカラスの地声なのだが、演技力と独特の間でなるほどと思わされてしまう。ディ・ステファノのロドルフォは甘い声ではまり役であり、アンナ・モッフォのムゼッタもとてもいい。ヴォット―とスカラ座のオケは最高。こうでなくっちゃという歌心あふれる音を出している。ときどき聴きたくなる個性と魅力にあふれた演奏である。
アルトゥーロ・トスカニーニ / NBC交響楽団・合唱団、少年合唱団
ミミ(リチア・アルバネーゼ)、ロドルフォ(ジャン・ピアース)、ムゼッタ(アン・マックナイト)、マルチェッロ(フランチェスコ・ヴァレンティーノ)、コッリーネ(ニコラ・モスコーナ)、シュナール(ジョージ・チェハノフスキー) 録音:1946年2月(モノーラル)
1896年2月1日にトリノ王立劇場でボエームを初演したのが29歳だったこのトスカニーニ(1867-1957)である。当時38歳のプッチーニが全幅の信頼を寄せる指揮者だった。初演50年記念としてニューヨークで最初のオペラ録音にボエームを選んでくれたことを音楽の神様に感謝するのみである。歌手とオケの緊密なアンサンブルの中心に指揮者があり全部をコントロールしている。この曲はこうでなくてはいけない。アルバネーゼはかわいい系のミミでこれが作曲者の意図に近かったのだろう。カラスが嫉妬したといわれる美声である。ピアースのロドルフォも(ハイCは回避しているが)きっちりとした発声でカンタービレで燃えるところは熱く燃え上がる。とてもいい。
しかし、この演奏で何より僕が感動するのは、歌が盛り上がる部分やホルンのテーマなどでトスカニーニがオケを引っぱりながら感きわまって一緒にメロディーを歌ってしまっていることである。それがはっきりと録音されている。ボエームは彼の血であり肉であり、他人事で指揮棒を振るだけというわけになはいかなかったのだ! 彼の歌が聞こえる部分、実は僕も家でセラフィン盤を聴きながら同じメロディーを大声で歌っていた。この曲は僕にとっても他人事ではない。
この録音でロドルフォ役を歌ったジャン・ピアースが 「指揮するトスカニーニの頬を涙が伝っているのが見えました」 と証言している。このとき79歳だったトスカニーニも、きっと指揮台で20代の青年に戻っていたにちがいない。