ルーセル バレエ音楽「蜘蛛の饗宴」作品17
2022 AUG 25 9:09:30 am by 東 賢太郎

英国からもドイツからも、列車や車でフランスへ入るといつも感じた。キラキラ輝く畑の光彩に感じた胸のときめき。あれは同じフランスでも飛行機でド・ゴール空港に着いてパリの雑踏に紛れては味わえない不思議なものだ。外国はほんとうにいろいろな処に行かせてもらったが、車で真っ暗な砂漠の丘を越えると忽然と現れた巨大な光りの玉みたいなラスヴェガス、車で長い長い橋を何本も渡り、やはり丘を越えてぽっかりと視界に浮かんだキーウエストの不思議な期待に満ちた遠望と同様に、フランス入りの欣喜雀躍は僕の記憶の中では特別なものになっている。
ニース近郊のサン・ポールの丘の上から眺めた地中海、カプリ島の断崖の頂上で昼食をとりながら虜になった紺碧のティレニア海、ドゥブロヴニクの高い城壁からため息をつきながら眼下に見とれたアドリア海と、できれば生きてるうちにもう一度味わいたい風景はいわば「静物画」だ。フランス入りは少々別物で「動画」であり、動きの中から不意に現れた驚き(aventure、アヴォンチュール)の作用というものである。不意であるから恋人との出会いのように一度きりで、流れ星を見たら消える前に祈れというものだ。そう、あれは思いもかけず心地良く頬をなでる風なのだ。
そんな希望をもたらす風のことをフランス語でvent d’éspoir (ヴァン・デスプワール)という。生きていれば誰しも何かのBeau(ボー、美しい)、movement(ムヴマン、動き)を見ているだろう。夕暮れの太陽、流れる雲、小川のせせらぎ、正確に時を刻む時計、競走馬の駆ける姿、みな美しいが、やはり人間の整った肢体が見せる統制された動きは格別だ。それはバレエやスケートはもちろんあらゆる一流のアスリートの競技姿に見て取れる。訓練した舞台人による動きもそうであり、そうした演技を抽象化、象徴化したパントマイム(無言劇、大衆的な笑劇)は古典ギリシア語 pantomimos に発する古代ギリシアの仮面舞踏であるが、初期イタリアのコンメディア・デッラルテが大道芸になり、そこから生まれたものだ。
笑劇、残酷、妖艶。これが融けあった「美(beauté ボテ)」というものは動画でしか表せない特別なものだ。それになるには人が蠢いて生み出すエロスが必要で小川や時計や馬ではいけない。仏語を書き連ねたが、その語感はゲルマンにもアングロ・サクソンにもなくラテン起源のもので、ラテン語は知らないのでフランス語の “感じ” で表したくなる。ニューヨークで全裸ミュージカル『オー!カルカッタ』を観た。初めから終わりまで登場人物は全員が全裸でダンスやパフォーマンスをくり広げる。それはそれで美しい場面がたくさんあったが、あの健康なエロスはからっと乾いたアメリカンなものだ。笑劇、妖艶はあっても残酷を欠くのである。ローマ皇帝を描いた映画にある残酷さ。死と向き合った快楽、その裏にある人間というはかなく愚かな生き物の露わな生きざま。これをへたに理性で隠し立てしないのがラテン文化であることは多くのイタリア・オペラの筋書きを見ればわかるだろう。
ラテン民族である「フランス人」という言葉は多義的で民族的ではなく、植民地をすべからくフランス文化圏にしようとした汎フランス主義の産物とでもいうものだ。スペインもそうで、南米でインカ帝国を殲滅した残虐さは目に余る。現地文化を同化することなく認め生かした英国の植民地政策とは対極にあり、大陸において日本軍が参考にしたのは仏国式だったといわれるが大きな誤りだった。欧州におけるフランス文化圏の東側はライン川だが、その西岸にいたゲルマン系にそれが被さって混血が進んだ地域がベルギー、オランダ、ルクセンブルグのベネルクス三国である。言語も宗教もしかりだ。ベルギーの首都ブリュッセルは当初はオランダ語を話すゲルマン民族のフラマン人が多かったが今はフランス語話者が多数であり、私見だがブリュッセルのフレンチ・レストランはパリに劣らぬクオリティだ。
そういう複雑な文化、宗教の混合がアマルガム状となった結末という意味でのフランス音楽というと、僕の脳裏にまず浮かぶものにアルベール・ルーセル(Albert Roussel、1869 – 1937)のバレエ-パントマイム「蜘蛛の饗宴」がある。蜘蛛が嫌いなためジャケットもを見るのもおぞましかった当初、この曲がこんなに好きになろうとは想像もしなかった。ドビュッシーが7つ年上、ラヴェルが6つ年下のルーセルはベルギー国境の街トゥールワコン出身、フラマン系のフランス人である。海を愛し、18才で海軍兵学校に進んだ経歴の持ち主で、中尉に任命されて戦艦スティクスに配属され当時はフランス領インドシナだった地域(現在のベトナム)に赴き、そこに数年滞在した。海軍の軍人だった作曲家はリムスキー・コルサコフもいるが、軍人の志と音楽愛は別物というのは僕もわかる。第一次世界大戦が始まると敢然と戦地に出て運転手を努めるのだから軍人の志も半端なものではなく、いわば二刀流であったのだろう。
しかし同時就業は無理である。音楽愛が勝った25才で退役し音楽の道に進むことになる。そしてもう中年である44才の1913年4月3日にパリのテアトル・デ・ザールで初演されたこの曲は成功し、堂々パリ・オペラ座のレパートリー入りを果たした。この道は王道なのだ。シャンゼリゼ劇場でいかがわしい興行師ディアギレフがやってる際物のロシアの踊りとは違う。そういう中で5月29日に「春の祭典」が初演されたが、両曲のたたずまいを比べるならそっちの騒動は納得がいくというものだ。1918年にドビッシーが亡くなるとルーセルはラヴェルと共にフランス楽団を率いる存在になるが、ラヴェルとは対照的に交響曲(4曲)および室内楽のソナタ形式の楽曲が多いのはゲルマンにも近い北フランスの血なのだろう。彼の音楽の色彩を考えるに、大戦後はノルマンディーに居を構えたことは示唆を与える。この地というと僕はロンドン時代の夏休みにドーヴィルのホテルに泊まってモン・サン・ミッシェルへ行ったときのことが忘れられないが、海は地中海のようには青くなく灰色で、波もなければきらめいてもいない。それでも、海がもっと青くない英国人は競ってここに避暑に行くのだ。彼の管弦楽はラヴェルと比べるとそういう色だと思う。
この曲の冒頭、d-aの五度に弦がたゆとうBm-Amの和声。これにふんわり浮かんで歌う、ふるいつきたくなるようにセクシーなフルートのソロはこの楽器の吹き手なら誰もが憧れるものではないか。
ここの効果たるや音というよりも色彩と香りが際立つ。これぞフランスに入った時に感じるあのときめきを思い起こさせてくれる。何度だって行きたい。だから蜘蛛がこわい僕がこの曲を愛好するのは仕方ないのである。しかしこのフルートは庭で昆虫が女郎蜘蛛の巣に誘い込まれる「いらっしゃいませ」の様子を描いているのだから恐ろしくもある。音楽は庭の昆虫の生活を描いており、昆虫が蜘蛛の巣に捕らえられ、宴会を始める準備をした蜘蛛が今度はカマキリによって殺され、カゲロウの葬列が続いて「いらっしゃいませ」の回想から平穏で静かなト長調のコーダになり、チェレスタとフルートのほろ苦い弔いのようなa♭が4回響いて曲を閉じる。何度きいても蠱惑的だ。フランスの昆虫学者ジャン=アンリ・ファーブルの昆虫記にインスピレーションを得て書かれたバレエ-パントマイムは笑劇、残酷、妖艶の大人のミックスという所である。
無声劇の痕跡として音楽が昆虫の動きを追って素晴らしく animé(生き生きと快活)であり、デュカの「魔法使いの弟子」を連想させる。このままディズニーのアニメに使えそうな部分がたくさんある。また、誰も書いていないが、オーケストレーションはリムスキー・コルサコフ直伝というほど僕の耳には影響を感じる(シェラザードと比べられたい)。もうひとつ、非常に耳にクリアな相似はペトルーシュカ(1911年、パリ初演)である。ルーセルは当然聴いているだろう。彼の楽曲の真髄は表面的な管弦楽法にはないが、パリに出てきた北フランス人として興隆し始めていたバレエ・ルッスのロシアの空気は無視できるものでなかったろうし、別な形ではあるがバスクの血をひくラヴェルもリムスキー・コルサコフの管弦楽法およびダフニスの終曲にボロディンの影がある。
全曲版と抜粋版(交響的断章)がある。
全曲版
第1部
前奏曲 Prélude
アリの入場 Entrée des fourmis
カブトムシの入場 Entrée des Bousiers
蝶の踊り Danse du Papillon
くもの踊り 第1番 Danse de l’araignée
アリのロンド Ronde des fourmis
2匹の戦闘的なカマキリ Combat des mantes
くもの踊り 第2番 Danse de l’araignée
第2部
カゲロウの羽化 Eclosion et danse de l’Éphémère
カゲロウの踊り Danse de l’Éphémère
カゲロウが止まる Mort de l’Éphémère
カゲロウの死 Agonie de l’araignée
カゲロウの葬送 Funérailles de Éphémère
交響的断章
アリの入場 Entrée des fourmis
蝶の踊り Danse du papillon
カゲロウの羽化 Eclosion de l’éphémère
カゲロウの踊り Danse de l’éphémère
カゲロウの葬送 Funérailles de l’éphémère
寂れた庭に夜の闇は降りる La nuit tombe sur le jardin solitaire
ルーセルは虫眼鏡で観察するほどの虫好きだった。アリ、カブトムシ、蝶を食いながら生きる蜘蛛、そしてカマキリ。これは人間界の生態に擬せられる。懸命に羽化して踊って生を楽しみ、すぐ命が尽きるカゲロウ、これもはかない人間の姿の象徴だ。そしてカブトムシが蜘蛛の巣にいったん捕獲されていたカマキリを逃がし、饗宴の準備をしていた蜘蛛を食ってしまう。これが世だ。こうして笑劇、残酷、妖艶はひとつになるのである。
演奏時間は全曲だと約30分、断章はその半分ほどだ。火の鳥、マ・メール・ロワと同様だ、これだけの素晴らしい音楽はまず全曲版を聴かないともったいない。
デービッド・ソリアーノ / ユース オーケストラ ・ フランス
全曲版だ。とても美しい。フルートの彼女、とっても素敵だ。これぞフランスの音。若い奏者たちが母国の美を守ってることに感動する。アンサンブルの水準も高い。指揮のソリアーノにブラヴォー。
アンドレ・クリュイタンス / パリ音楽院管弦楽団
交響的断章なのが残念過ぎるが、僕はこの演奏で曲の真髄に触れた。冒頭フルートの官能的なけだるさ!あっという間に魅惑の虜である。オーボエ、ホルンのおフランスのおしゃれ、チェレスタの目くるめく光彩に耳を澄ませてほしい。木管はもちろんハープの倍音まで効いていて夢のような17分が過ぎてゆく。西脇順三郎の「(覆された宝石)のやうな朝」はこんなではないか?なんということか、モーツァルトのコシ・ファン・トゥッテの6重唱のように木管があれこれ別なことをしゃべっている。アンサンブルが雑然となるが節目でピシッと合う。パントマイムの面目躍如。こういうのはフランスのオケでないと無理だが、フランスだって今時はこうはしないよ。ドイツ風に縦線を合わたアンサンブルでは綺麗にまとまるが毒にも薬にもならない。それでおしまい。この毒にあたるともう抜け出せない。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
クラシック徒然草ーフランス好きにおすすめー
2016 SEP 3 2:02:01 am by 東 賢太郎

ジャズやポップスはアルバムが唯一無二の「作品」ですが、クラシックはそうではなくて、作品が富士山ならアルバムはその写真集のような関係です。
しかし、中にはちがうのがあって、ほんのたまにですが、これは「作品」だという盤石の風格を感じる録音があります。風格というより唯一無二性と書くか、音の刻まれ方から録音のフォーカスの具合まで、総合的なイメージとしてそのアルバムが一個の個性を普遍性まで高めた感じのするものがございます。
演奏家と録音のプロデューサー、ミキサーといった技師のコラボが作品となっている印象でブーレーズのCBS盤がそれなのですが、DG盤もレベルは高いがその感じに欠けるのは不思議です。何が要因かは僕もわかりません。
名演奏、名録音では足らず、演奏家のオーラと技師のポリシー・録音機材の具合がお互い求め合ったかのような天与のマッチングを見せるときにのみ、そういう作品ができるのでしょうか。例えばブーレーズCBSのドビッシーの「遊戯」は両者のエッセンスの絶妙な配合が感じられる例です。
いかがでしょう?
冒頭は高弦(シ)にハープとホルンのド、ド#が順次乗っかりますが、ハープの倍音を強めに録ってホルンは隠し味として(聞こえるかどうかぐらい弱く)ブレンドして不協和音のうねりまで絶妙のバランスで聴かせます。聴いた瞬間に耳が吸いよせられてしまいます。
ここから数分は楽想もストラヴィンスキーの火の鳥そっくりでその録音でも同様の効果を上げていますが、いくらブーレーズでもコンサートホールでこれをするのは難しいと思われます。エンジニアの感性と技法が楽想、指揮者の狙いに完璧にマッチしている例です。
録音の品位、品格というものは厳然とあって、ただ原音に忠実(Hi-Fi)であればいいというものではありません。忠実であるべきは物理特性に対してではなく「音楽」に対してです。こういうCDはパソコンではなくちゃんとしたオーディオ装置で再生されるべき音が詰まっています。
僕がハイファイマニアでないことは書きましたが、そういう名録音がもしあれば細心の注意を払って一個の芸術作品として耳を傾けたいという気持ちは大いにあります。それをクラウドではなくCDというモノとして所有していたいという気持ちもです。
ライブ録音に「作品」を感じるものはあまり思い当たりません。演奏の偶然性、感情表現の偶発性などライブの良さは認めつつも、演奏会場の空気感や熱気までを録音するのは困難です。C・クライバ―、カラヤンなど会場で聴いたものがCDになっていますが、仮にそれだけ聞いてそれを選ぶかと言われればNOです。
「音の響き」「そのとらえ方」はその日のお客の入りや温度、湿度によって変わるでしょう。CDとして「作品」までなるにはエンジニアの意志、個性、こだわりの完璧な発揮が重要な要素と思われますが、彼らは条件が定常的であるスタジオでこそ本来の力が発揮されるという事情があると思います。
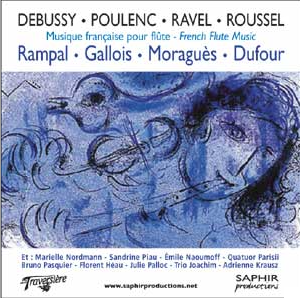 このことを僕に感じさせたのはしかしブーレーズではありません。右のCDです。これはSaphirというフランスのレーベルのオムニバスですが、同国の誇る名人フルーティストのオンパレードで演奏はどれもふるいつきたくなるほどの一級品。以下、曲ごとに印象を書きます。
このことを僕に感じさせたのはしかしブーレーズではありません。右のCDです。これはSaphirというフランスのレーベルのオムニバスですが、同国の誇る名人フルーティストのオンパレードで演奏はどれもふるいつきたくなるほどの一級品。以下、曲ごとに印象を書きます。
ルーセルの「ロンサールの2つの詩」のミシェル・モラゲス(フルート)とサンドリーヌ・ピオ(ソプラノ)の完璧なピッチ、ホールトーン、倍音までバランスの取れた調和の美しさは絶品!これで一個の芸術品である。
ラヴェルの「 序奏とアレグロ」はフランスの香気に満ち、ハープ、フルート、クラリネット、弦4部がクラリティの高い透明な響きでまるでオーケストラの如き音彩を放つさまは夢を見るよう。パリ弦楽四重奏団のチェロが素晴らしい。この演奏は数多ある同曲盤でベストクラス。
ミシェル・モラゲス(フルート)、エミール・ナウモフ(ピアノ)によるプーランクのフルート・ソナタはフルートの千変万化の音色、10才でブーランジェの弟子だったナウモフのプーランク解釈に出会えるが、色彩感と活力、素晴らしいとしか書きようがなく、しかも音が「フランスしてる」のは驚くばかり。エンジニアの卓越したセンスを聴く。同曲ベストレベルにある。
マテュー・デュフール(フルート)、ジュリー・パロック(ハープ)、ジョアシン弦楽三重奏団によるルーセルの「 セレナード 」、これまた「おフランス」に浸りきれる逸品。この音楽、ドイツ人やウィーン人に書けと言ってもどう考えても無理だ。録音エンジニアもフランス、ラテンの透明な感性、最高に良い味を出しておりフルートの涼やかな音色に耳を奪われる。最高!
ドビュッシーの「 フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ」は(同曲の本編に書きませんでしたが)、これまた演奏、録音ともベスト級のクオリティ。序奏とアレグロでもルーセルでもここでもフルートとハープの相性は抜群で、その創案者モーツァルトの音色センスがうかがえるが、そこにヴィオラが絡む渋い味はどこか繊細な京料理の感性を思いおこさせる。
以上、残念ながらyoutubeに見当たらず音はお聴きいただけません。選曲は中上級者向きですがフランス音楽がお好きな方はi-tunesでお買いになって後悔することはないでしょう(musique francaise pour fluteと入力すると上のジャケットが出てきます)。CDは探しましたがなく、僕も仕方なくi-tunesで買いました。間違ってもこんな一級品のディスクを廃盤に追いこんでほしくないものですね。
Yahoo、Googleからお入りの皆様
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
プロコフィエフ 交響曲第2番ニ短調作品40
2016 MAY 4 18:18:05 pm by 東 賢太郎

米国の鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの墓碑銘に「Here lies one who knew how to get around him men who were cleverer than himself.(自分より賢き者を近づける術知りたる者、ここに眠る。)」とあるそうだ。以前ここにバレエ・リュス(ロシアバレエ団)のセルゲイ・ディアギレフについて書いた( ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」)が、実業家としては彼は天賦の才ある成功者だったが、当初志した音楽家としてはカーネギーの言葉があてはまるのではないか。
 ところが、自身も音楽家(指揮者)として名を残しながら自分より賢き者を近づける術を知った者がいた。こちらもロシア人のセルゲイ・クーセヴィツキー(1874-1951、左)である。音楽家の息子でコントラバスの名手であり、ボリショイ劇場で弾いていた。彼がラッキーだったのは2番目の奥さんが富豪(茶の貿易商)の娘だったことだ。彼女は結婚記念として「カレにオーケストラを買ってあげて」と父にせがんだ。
ところが、自身も音楽家(指揮者)として名を残しながら自分より賢き者を近づける術を知った者がいた。こちらもロシア人のセルゲイ・クーセヴィツキー(1874-1951、左)である。音楽家の息子でコントラバスの名手であり、ボリショイ劇場で弾いていた。彼がラッキーだったのは2番目の奥さんが富豪(茶の貿易商)の娘だったことだ。彼女は結婚記念として「カレにオーケストラを買ってあげて」と父にせがんだ。
「逆タマ」の財力で彼は巨匠指揮者アルトゥール・二キシュの博打の負けを払ってやって指揮を教わり、なんとベルリン・フィルを雇って(!)演奏会を指揮し(ラフマニノフの第2協奏曲のソリストは作曲者だった)、祖国へ帰って出版社を創ってオーナーとなりラフマニノフ、スクリャービン、プロコフィエフ、ストラヴィンスキーの版権を得て楽譜を売った。
ロシア革命後は新政府を嫌って1920年に亡命し、パリで自身が主催する演奏会「コンセール・クーセヴィツキー」を立ち上げる。これは1929年まで続いたが、その間に初演されたれた曲がストラヴィンスキーの「管楽器のための交響曲」(1921)、ムソルグスキー「展覧会の絵」のラヴェル編曲版(1922)、オネゲル「パシフィック231」(1924)、プロコフィエフ交響曲第2番(1925)、コープランド「ピアノ協奏曲」(1927)であった。
クーセヴィツキーは1924年にボストン交響楽団(BSO)常任指揮者となる(パリには夏だけ行った)。バルトーク「管弦楽のための協奏曲」、ブリテン「ピーター・グライムズ」、コープランド交響曲第3番、メシアン「トゥーランガリラ交響曲」はクーセヴィツキー財団が委嘱して書かせ、BSOの50周年記念として委嘱したのはストラヴィンスキー詩編交響曲、オネゲル交響曲第1番、プロコフィエフ交響曲第4番、ルーセル交響曲第3番、ハンソン交響曲第2番だ。クーセヴィツキーはこれだけの名曲の「父親」である。
自分より賢き者を近づける術はカネだったのか?そうかもしれない。BSOの前任者ピエール・モントゥーも弟子のレナード・バーンスタインも、名曲の世界初演をしたり自分で名曲を書いたりはしたが他人に書かせることはなかったからだ。しかし、彼が財力にあかせて「管弦楽のための協奏曲」や「トゥーランガリラ交響曲」を書かせたといって批判する人はいない。
 もう一つ、僕として聴けなければ困っていた曲が表題だ。パリにでてきたプロコフィエフ(左)だが、当時は6人組が新しいモードを創って人気であり、彼の作品は理解されなかった。よ~しそれなら見ておれよ、奴らより前衛的な「鉄と鋼でできた」交響曲を書いてやろうとリベンジ精神で書いたのが交響曲第2番だ。パリジャンを驚嘆させた「春の祭典」騒動はその10年ほど前だ、もちろん念頭にあっただろう。
もう一つ、僕として聴けなければ困っていた曲が表題だ。パリにでてきたプロコフィエフ(左)だが、当時は6人組が新しいモードを創って人気であり、彼の作品は理解されなかった。よ~しそれなら見ておれよ、奴らより前衛的な「鉄と鋼でできた」交響曲を書いてやろうとリベンジ精神で書いたのが交響曲第2番だ。パリジャンを驚嘆させた「春の祭典」騒動はその10年ほど前だ、もちろん念頭にあっただろう。
芸術はパトロンが必要だが、モチベーションも命だ。天から音符が降ってきて・・・などという神話はうそだ。それで曲を書いたと吐露した作曲家などいない。バッハもヘンデルもハイドンもモーツァルトもベートーベンも、みな現世的で人間くさい「何か」のために曲を書いたのだ。お勤め、命令、売名、就職活動、生活費、女などだ、そしてそこに何らかの形而上学的、精神的付加価値があったとするなら、ことさらにお追従の必要性が高い場合においては曲がさらに輝きを増したというぐらいのことはいえそうだ。
クーセヴィツキーはカネがあったが、その使い方がうまかった。BSOの50周年なる口実で名誉という18,19世紀にはなかったエサも撒くなど、作曲家のモチベーターとして天賦の営業センスがあったといえる。そういう天才は99%のケースではカネを作ることに浪費されるが、冒頭のカーネギーは寄付をしたりカーネギー・ホールを造るなど使うことにも意を尽くした1%側の人だった。そしてクーセヴィツキーは嫁と一緒にカネも得て、それを使うだけに天才を使った稀有の人になった。
しかしその彼にとっても、刺激してやるモチベーションが「リベンジ精神」というのは稀有のケースだったのではあるまいか。プロコフィエフは速筆でピアノの達人でもあり、ピアノなしでも頭の中で交響曲が書けたという点でモーツァルトを思わせる。どちらも後世に明確な後継者が残らない、技法に依存度の高くないような個性で音楽をさらさらと書いた。しかしこの第2交響曲は力瘤が入っている。異国の地で勝負に燃えた33才。モーツァルトがフィガロにこめた力瘤のようなオーラを僕は感じる。
攻撃的な響きに満ちた2番の初演はパリの聴衆の冷たい反応しか引き起こさなかった。暴動すらなく、専門家の評判も悪く、ほめたのはプーランクだけだった。ここがディアギレフとクーセヴィツキーのモノの差だったかもしれないが、曲がそこまで不出来ということはない。力瘤の仮面の下で非常に独創的な和声、リズム、対位法が予想外の展開をくり広げる。これが当たらなかったから、あの第3交響曲という2番の美質をさらに研ぎ澄ました名曲が生まれた。しかしその萌芽のほうだって、春の木々の新芽のように強い生命力があり、不可思議な響きの宝庫だ。
プロコフィエフはロシア革命のときに27才だった。アメリカに逃げようと思った。モスクワからシベリア鉄道で大陸を横断し、海を渡って敦賀港に上陸した。日本に来た最初の大作曲家はプロコフィエフだ。サンフランシスコへ渡航する船を待つ約2か月の間、日本各地を見物して着想した楽想が交響曲の2,3番、ピアノ協奏曲の3番に使われたとされる。2番は第2楽章の静かな主題がそれだ。クラリネットと弦のゆったりした波にのってオーボエが切々と歌う。シベリウスの6番の寂寞とした世界を思い浮かべるが、これが6回変奏されて不協和音を叩きつけ、最後に回帰するのが実に美しい。
僕は3番の次に2番をよく聴く。秀才がワルになろうと暴走族のまねごとをしたみたいな部分がかえっていい答案だなあ秀才だなあと感嘆させてしまうあたりが面白い。第1楽章は全編がほぼそれだが、これでも喰らえとわざとぶつけた感じのする2度、9度の陰でぞくぞくするコード進行が耳をとらえて離さない。こんな音楽は他にない。これがたまらないのだ。小澤/ベルリンPOだと見事に浮き彫りになっている。何という格好よさ!!
これを何度聴いたことか、これはラテン的音楽ではないがこの小澤さんの演奏のクリアネスは凄い純度である。そのたびに僕は本質的にロマン派のテンペラメントではない、恋に恋するみたいな人間とは180°かけ離れていて、100km先まで透視できるヴィジョンを愛するラテン気質に親和性があるのかなと思う。小澤さんはロマン派もとてもうまいが、この2番の合い方は半端でなくラテン親和性をお持ちでないかと察する。
小澤征爾 / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
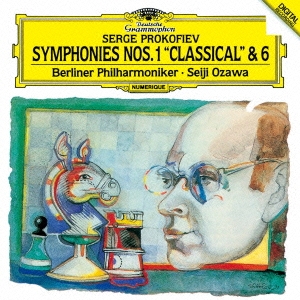 この全集は小澤さんがBPOを振って打ち立てた金字塔である。上述に加えて第2楽章の透明感と細部のしなやかな生命力も素晴らしく、2番の挑戦的な暴力性がここまで整理され純化されていいのかというのが唯一ありえる批判と思う。それは若かりし頃にシカゴSOを振った春の祭典に同じことが言えるが、僕はあれが好きであり、したがってこれも好きだ。BPOの機能性あってのことだが、このピッチの良さ、見通しの良さ、バランス感は指揮者の耳と才能なくしてあり得ない。日本人で他の誰がこんなことができるだろう。
この全集は小澤さんがBPOを振って打ち立てた金字塔である。上述に加えて第2楽章の透明感と細部のしなやかな生命力も素晴らしく、2番の挑戦的な暴力性がここまで整理され純化されていいのかというのが唯一ありえる批判と思う。それは若かりし頃にシカゴSOを振った春の祭典に同じことが言えるが、僕はあれが好きであり、したがってこれも好きだ。BPOの機能性あってのことだが、このピッチの良さ、見通しの良さ、バランス感は指揮者の耳と才能なくしてあり得ない。日本人で他の誰がこんなことができるだろう。
ジャン・マルティノン / フランス国立管弦楽団
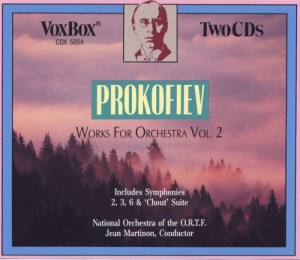 これぞラテン感覚の2番である。マルティノンはラヴェルもドビッシーもロシア音楽も明晰だ。不協和音も濁らない。印象派というと、春はあけぼの、やうやう白くなり行く・・・の世界と思いがちだがぜんぜん違うということがこの2番のアプローチでわかる。第2楽章テーマはその感性だからこその蠱惑的なポエジーがたまらない。管楽器は機能的に磨かれフランス色はあまり強くないが、弦も含めて音程と軽やかなフレージングが見事で、きわめてハイレベルな演奏が良い音で聴ける。
これぞラテン感覚の2番である。マルティノンはラヴェルもドビッシーもロシア音楽も明晰だ。不協和音も濁らない。印象派というと、春はあけぼの、やうやう白くなり行く・・・の世界と思いがちだがぜんぜん違うということがこの2番のアプローチでわかる。第2楽章テーマはその感性だからこその蠱惑的なポエジーがたまらない。管楽器は機能的に磨かれフランス色はあまり強くないが、弦も含めて音程と軽やかなフレージングが見事で、きわめてハイレベルな演奏が良い音で聴ける。
ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー / モスクワ放送交響楽団
 ごりごりした低弦と派手な金管、打楽器が鳴り響くロシア軍の行軍みたいな第1楽章はまことに威圧的で、2番の趣旨にはかなっている。そういうのは好みでないが、救いはロジェストヴェンスキーの縦線重視の譜読みだ。和音を叩きつけまるでストラヴィンスキーだがこの強靭なタッチはフランス系では絶対に出ない味である。第2楽章のデリカシーはいまひとつだが変奏の激烈さがあってこそテーマの回帰の静けさは心にしみる。
ごりごりした低弦と派手な金管、打楽器が鳴り響くロシア軍の行軍みたいな第1楽章はまことに威圧的で、2番の趣旨にはかなっている。そういうのは好みでないが、救いはロジェストヴェンスキーの縦線重視の譜読みだ。和音を叩きつけまるでストラヴィンスキーだがこの強靭なタッチはフランス系では絶対に出ない味である。第2楽章のデリカシーはいまひとつだが変奏の激烈さがあってこそテーマの回帰の静けさは心にしみる。
Yahoo、Googleからお入りの皆様
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。







