モーツァルト 「 キリエ ハ長調 K.323」
2017 AUG 24 22:22:58 pm by 東 賢太郎

モーツァルトの最高傑作のジャンルが何かという問いはあまり意味がないだろう。彼が手を付けたが傑作は残さなかったというジャンルはないからだ。彼も人の子であり、創作のモチベーションが高い所に傑作が生まれるという法則から完全に自由だったわけではないが、やっつけ仕事ではあっても駄作を生んで済ますことのできる性格ではなかったとも思う。
我が国において宗教曲というジャンルは難儀だ。J.S.バッハのマタイ受難曲やロ短調ミサ曲が名曲であることは何人たりとも認めるしかないが、ではその根拠はと問われると説明に窮する。それらがキリスト教の葬儀や典礼の音楽だからだ。逆にキリスト教徒が仏教の典礼に参列して読経を聴き感動したと言って、我々がどこまでその人の言葉にシリアスに向き合うかということを考えればわかる。文化に国境はないだろうが、宗教が介在すると別な境界が出てくるのである。
その境界は西洋音楽の歴史にも内在している。音楽そのものが宗教とは別個に人間に与える生理的な快感として認知され、教会という宗教スペースから外界に出て独立し世俗化していく起点をかなり遅めのJ.S.バッハ(バロック期)としても、音楽が民衆のものとなる起点であるベートーベンの時代に至るまでは100余年を要しているからだ。
古来より民衆の間に娯楽として存在した歌、俗謡、シャンソンなどが権威づけを補完する道具として宗教に取り込まれ、当初は単旋律であった(例えばグレゴリオ聖歌)が教会という空間に放り込まれると物理現象としての和声、ポリフォニーが知覚され、理論化されていったのである。和声、ポリフォニーの喜びが民衆(といってもまずは貴族だが)に認知されて外界へ出たところに我々が呼ぶクラシック音楽というものが形成された、というのが我々の教わる音楽史である。
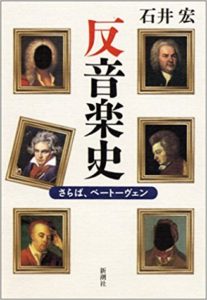 この考えが誤りであることは石井宏氏が著書「反音楽史(さらばベートーヴェン)」で鋭く看破されている。音楽後進国であったドイツはオペラ、声楽などでイタリア音楽を受容したが、イタリア音楽はギリシャ悲劇を再現して音楽を付けた劇(オペラ)とともに発展し、イタリアの教会音楽の音楽家はイタリア人でなく多くがフランドル、ブルゴーニュの出身者だった。バロック時代に教会が音楽理論化への「培養器」として機能したのはドイツであったが、それが音楽史の起点であるかのようにバッハを「音楽の父」と讃えてしまうのはルネッサンス以降のイタリアの歌の興隆を歴史から消そうと試みるものだ。バッハはプロテスタントの一派であるルター派の信者だが、あたかも音楽においてもプロテスタントがカソリックを否定しに行ったとさえ感じられる。
この考えが誤りであることは石井宏氏が著書「反音楽史(さらばベートーヴェン)」で鋭く看破されている。音楽後進国であったドイツはオペラ、声楽などでイタリア音楽を受容したが、イタリア音楽はギリシャ悲劇を再現して音楽を付けた劇(オペラ)とともに発展し、イタリアの教会音楽の音楽家はイタリア人でなく多くがフランドル、ブルゴーニュの出身者だった。バロック時代に教会が音楽理論化への「培養器」として機能したのはドイツであったが、それが音楽史の起点であるかのようにバッハを「音楽の父」と讃えてしまうのはルネッサンス以降のイタリアの歌の興隆を歴史から消そうと試みるものだ。バッハはプロテスタントの一派であるルター派の信者だが、あたかも音楽においてもプロテスタントがカソリックを否定しに行ったとさえ感じられる。
カソリックであったモーツァルトがバッハを知ったのはウィーンに出てからだったのはそんな時代背景があるからだ。ウィーンもザルツブルグもカソリック、イコール、イタリア音楽であり、モーツァルトが初めてウィーン訪問した時の宮廷楽長ジュゼッペ・ボンノの本名はヨーゼフ・ボンだった(上掲書)。オーストリア人のボンはイタリアに留学した。うだつのあがらないドイツ人を捨てるために名前をイタリア風にして「イタリア男」として戻ってきてポストを得ることに成功したのだ。そんなウィーンでオーストリア人のモーツァルトに地位を脅かされるとは考えてもいなかったろうサリエリがリスクを冒して暗殺を試みるというプロットは小説としても奇なり過ぎる。
ザルツブルグのモーツァルトの宗教音楽がいまひとつ評価の高くない地位にあるのは、田舎者のモーツァルトが大司教(地方都市のカソリック教会権威の代表)のサラリーマンとして不承不承に書かされたというイメージが定着しているせいもあるだろう。それが嫌でウィーンに飛びだしたのだからモチベーションが低かったのは事実だろうが、実はモーツァルトにおける宗教音楽は僕の最も好きなジャンルの一つなのだ。それもウィーン時代に書かれたハ短調ミサ、レクイエムといった有名曲だけでないザルツブルグ時代の10-20代の作品においてもだ。
声楽アンサンブルは無上の喜びであってオペラもアリアより合唱、重唱の部分が好きだ。もちろんJ.S.バッハやヘンデルのポリフォニックな声楽曲は何でも聴くが、モーツァルトのそれは対位法の精度は高くないものの後年の作品群に投影、結実されていく語法の萌芽が明確にあって興味が尽きない。むしろモーツァルト好きがこれを聴いて喜ばないならモグリだろうという音楽がぎっしり詰まっているのである。
私事だがこの趣味は、ビートルズから来たものだと思っている。若いころあれだけ聴いたものが残ってないはずはない。声楽(3声、4声)で生み出す純正調のハーモニーの快感は忘れがたく、カーペンターズを経て和製ポップス(荒井由実、ハイ・ファイ・セットetc)まで同じものを見出した。その好みがモーツァルトのミサ曲で「共鳴」したと書いたら奇異だろうか。自然にそう思えるのは、ロンドンやチューリッヒやウィーンで教会に入り浸ってみて、そこに生まれてれば讃美歌で入門してたと感じた、そのかわりがレノン・マッカートニーのハモリだったというだけだからだ。
宗教曲は少なくとも西洋音楽のドイツにおける進化のルーツとは言えるのであって、ドイツ音楽を楽しむ人間がここを鑑賞の本丸とすることはまったくもって正道である。仏教徒が聴いてわかるのかという疑念は、キリスト様の血と肉であるワインとパンを毎日おいしくいただいている我々には不要だろう。ましてロックから近寄ってしまった僕にとって、教会とは最高の残響とアコースティックを提供してくれるコンサートホールに思えないでもない。
余談だが西洋音楽のドイツにおける進化のルーツをJ.S.バッハの教会音楽に置いたのがシューマンとブラームスだ。だから彼らは保守本流意識があり、ワーグナー、ブルックナーと対立したのだ。ブラームスは4番のパッサカリアにバッハを引用した。
シューマンの3番は第4楽章が「教会の中」、第5楽章が「そこを出た喜び」という構図で解釈でき、その証拠に第4楽章にバッハの平均律第一巻ロ短調の引用がある。「ライン交響曲はルソーの自然回帰への賛歌という側面があり」と書いたが
本稿のコンテクストから述べるなら、「教会という培養器を出た音楽が人間の喜びを表す様を主題とした音楽」「ロマン派の開花に至る来歴を刻印した音楽」がライン交響曲だということもできよう。
モーツァルトの宗教曲には超ド級が多くあるが、まず衝撃を受けたのはこれだった。キリエ ハ長調 K.323である。レネ・レイボヴィッツがウィーン国立歌劇場のオケと合唱を指揮した演奏に脳天を直撃され、何度聴いても耳がダンボ状態のまま釘づけになってしまう。そのCDを自分でアップしたので、ぜひ皆さんも味わっていただきたい。4曲入ってるが、第1曲がそのK.323だ。
この曲は出自が不明でスコアは未完であるためにK.Anh.15/323 とされ、死後に友人の音楽家マクシミリアン・シュタードラーが完成させている。このCDではRegina Coeli K.Ahn118 と誤ってクレジットされているがそんな曲はなく、1879年の Breitkopf & Härtelのスコアを見れば同一の曲であるのは明白である(ご興味ある方はPetrucciにあるのでご自身で確認していただきたい)。
ついでに第3曲 テ・デウム K.141 の終結部の素晴らしいフーガもお聞きいただきたい。ジュピターのそれが素晴らしいだの奇跡だのと騒ぐのが的外れに思えてきて白けてしまう13歳の少年のこの腕前は何なのだろう?K.141はミヒャエル・ハイドンの作品をモデルに書いた譜面を父レオポルドが添削したと言われるが、そうではあってもこれが習作に聞こえることは一切ない。
キリエ ハ長調 K.323は母を亡くしたパリ旅行からザルツブルグに戻ったころ(1779年)の作品と信じられてきた。そこには同じほど完成度の高い戴冠式ミサがあるのだから不思議ではないが、楽譜のX線による年代測定をしたA・タイソンの研究によるとK.323は1787年に使われた五線紙に書かれており、86年12月から89年にかけて書かれたことになる。となると、これをお読みいただいた方は「あの頃」の音楽であることがお分かりになると思う。
父に断られて念願のロンドン行きを断念し、持っていくつもりだった交響曲は「プラハ」になってしまったあのころだ。父が亡くなり、ドン・ジョバンニを書いた。そして翌88年に戦争となってオペラ需要は激減し、忽然と「三大交響曲」が出現するのである。そのあたりでモーツァルトの脳に降ってきたK.323が凡俗の脳天を直撃したとしても宜(むべ)なる哉だ。
彼がグルックの死で空席となったウィーン宮廷作曲家の職を得たのは1787年12月のことであるが、報酬はきわめて低く、そのうえ仕事は毎年冬期間の舞踏会用のつまらないダンス音楽の作曲だった。タイソン説が現れると「87年以降に教会での定職を得ようとして宗教音楽の作曲を試みていた」と考えられるようになったのはごく自然なことと思われるが、それにしてもウィーン宮廷はイタリアかぶればかりだったのか、彼をいじめたかったのか、嫉妬するなど人品骨柄レベルが低かったのか。
こういう細かい事実の検証が常にモーツァルトの人生は不幸であったというベクトルに収束してまう。彼に対するぞんざい極まる扱いと、音楽のクオリティの異常な高さのギャップは人間というものの不条理を後世が学ぶ良い題材だが、そこに数々の都市伝説が生まれてしまうのは別の意味でまた不条理を教えてくれる。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
Categories:______モーツァルト, ______音楽書





