チャイコフスキー交響曲第6番「悲愴」の聴き比べ(2)
2018 DEC 29 1:01:19 am by 東 賢太郎

オットー・クレンペラー / フィルハーモニア管弦楽団
 非常に興味深い。知的だ。mov1アレグロは遅いがTrの三連符など細部を聴くと馬なりの操縦でないことがわかる。提示部は静的だが緊張が支配し、第2主題が甘いロマンなどでなく怖いものを含む。展開部は暴れさせずHr信号が伴奏する第1主題再現の熱病の不安定な感じはmov4のHr信号部分(第2主題)に呼応するがクレンペラーはそれを見抜いているだろう。mov2は滑らかつややかな美を目指しておらず5拍子がぎこちない。中間部はインテンポ。mov3はとても遅くAllegro molto vivaceとは程遠い。スケルツォの細部(付点音符のリズムとフレージング)も神経が通うのはほとんどの人が無難な通過であるのと思想が根本から違うとしか言いようがない。マーチへのブリッジ部分は加速せず書かれた楽譜だけで興奮を高めるがマーチ主題はほぼインテンポながら微妙に遅いという類例のない解釈である。2度目もほぼ同じ道をたどる。ティンパニと使い分けたバスドラムの運命の鉄槌のごとき強打もユニークで一切の加速なく苛烈に終る。終楽章の対抗配置により第1,第2Vnに振り分けられた旋律の分断が衝撃だ。これぞチャイコフスキーの意図であり現代においてはストコフスキー配置(スコア改変に相当)がスタンダードになった理由は僕には全く解せない。コーダはことさらに泣きはしない静かな人生の終結だが悲しい。ここに至るまでの道のりがずっしり重かったからだ。これがチャイコフスキーかという声は昔からあったが、彼は最期にそうではない音楽を意図して書き残したのであって、これがダイイングメッセージであるという僕の仮説からはクレンペラーの表現は一理ある。昨今多い綺麗にまとまったお涙頂戴のショーピースなどとは比べ物にならない大人の音楽である(総合点:5)。
非常に興味深い。知的だ。mov1アレグロは遅いがTrの三連符など細部を聴くと馬なりの操縦でないことがわかる。提示部は静的だが緊張が支配し、第2主題が甘いロマンなどでなく怖いものを含む。展開部は暴れさせずHr信号が伴奏する第1主題再現の熱病の不安定な感じはmov4のHr信号部分(第2主題)に呼応するがクレンペラーはそれを見抜いているだろう。mov2は滑らかつややかな美を目指しておらず5拍子がぎこちない。中間部はインテンポ。mov3はとても遅くAllegro molto vivaceとは程遠い。スケルツォの細部(付点音符のリズムとフレージング)も神経が通うのはほとんどの人が無難な通過であるのと思想が根本から違うとしか言いようがない。マーチへのブリッジ部分は加速せず書かれた楽譜だけで興奮を高めるがマーチ主題はほぼインテンポながら微妙に遅いという類例のない解釈である。2度目もほぼ同じ道をたどる。ティンパニと使い分けたバスドラムの運命の鉄槌のごとき強打もユニークで一切の加速なく苛烈に終る。終楽章の対抗配置により第1,第2Vnに振り分けられた旋律の分断が衝撃だ。これぞチャイコフスキーの意図であり現代においてはストコフスキー配置(スコア改変に相当)がスタンダードになった理由は僕には全く解せない。コーダはことさらに泣きはしない静かな人生の終結だが悲しい。ここに至るまでの道のりがずっしり重かったからだ。これがチャイコフスキーかという声は昔からあったが、彼は最期にそうではない音楽を意図して書き残したのであって、これがダイイングメッセージであるという僕の仮説からはクレンペラーの表現は一理ある。昨今多い綺麗にまとまったお涙頂戴のショーピースなどとは比べ物にならない大人の音楽である(総合点:5)。
エルネスト・アンセルメ / スイス・ロマンド管弦楽団
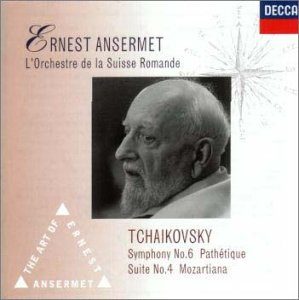 冒頭のバソンの低音がフランスだ。弦は心もとないアンサンブルだが管が入ってくると何となくまとまる。第2主題の品の作り方はうまいが木管のユニゾンの音程はオーボエが合わない。展開部はアマオケ並みに危ない感じでこの遅さが必然と思える。終結のロ長調の木管合奏の音程は不気味なほどひどい、ティンパニのシも低い。指揮者が何とかできないのか?僕はこういうのは耐え難い。mov2は良いテンポだ。中間部はインテンポで淡々と行く。mov3の弦はかなりましだ。マーチは1度目はインテンポで進行、2度目はやや減速するがティンパニの鳴らし方が僕の好みだから相殺だがシンバルがどうも安っぽい。コーダへ向けて加速するのはまあ良しとする。mov4はまたclの音程が邪魔で集中力をそぐ。こういうのが気にならない人は聞けるだろうが僕には困難。感傷がどろどろしない良さがあるが、そもそもこのレベルのオケ演奏が商品になるのも不思議であり、アンセルメの解釈には敬意を表するにしても彼のクレジットになるような演奏なのだろうかは疑問だ(総合点:2)。
冒頭のバソンの低音がフランスだ。弦は心もとないアンサンブルだが管が入ってくると何となくまとまる。第2主題の品の作り方はうまいが木管のユニゾンの音程はオーボエが合わない。展開部はアマオケ並みに危ない感じでこの遅さが必然と思える。終結のロ長調の木管合奏の音程は不気味なほどひどい、ティンパニのシも低い。指揮者が何とかできないのか?僕はこういうのは耐え難い。mov2は良いテンポだ。中間部はインテンポで淡々と行く。mov3の弦はかなりましだ。マーチは1度目はインテンポで進行、2度目はやや減速するがティンパニの鳴らし方が僕の好みだから相殺だがシンバルがどうも安っぽい。コーダへ向けて加速するのはまあ良しとする。mov4はまたclの音程が邪魔で集中力をそぐ。こういうのが気にならない人は聞けるだろうが僕には困難。感傷がどろどろしない良さがあるが、そもそもこのレベルのオケ演奏が商品になるのも不思議であり、アンセルメの解釈には敬意を表するにしても彼のクレジットになるような演奏なのだろうかは疑問だ(総合点:2)。
・・・・
悲愴をこうして聴いているとどうしても「死」というものを思ってしまいます。昨年に母を見送って、どうしても。人は死ぬと何処へ行くんだろう?これの第4楽章をピアノで弾いていてコーダで泣けたことが何度もあります。こんな音楽は、眼前に「死」がない人には書けないだろうと思います。
・・・・
ジャン・マルティノン / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
 上掲盤を聴いた後でVPOが機能的にも優れていることを思い知る。マルティノンの指揮は強いメリハリがあり強弱もテンポも伸縮自在で、VPOが承服してついて行っていることそれ自体が価値ありだ。mov1第2主題の弦の艶っぽさは「ならでは」であり展開部の金管の鳴りっぷりも圧倒的。マルティノンのオケのドライブは圧巻でアクセルの一気の踏み込みも自在である。mov2主題のブレーキはその逆。中間部の息をひそめた p は実にいい、これでこそmov4コーダと繋がるというもの。mov3の弦アンサンブルは素晴らしいの一言だが僕がこの演奏を初聴で気に入らなかったのは2回目のマーチの常套的な減速のせいだった(今でもそうだ)。mov4もテンポは流動的でほぼ一定に収まることなく水性(liquid)であり、それに同化してしまえばいいのだろうが僕のイデアとしての悲愴はそうではなくどうもひっかる。ひとつの管弦楽のプレイとしてはユニークな一級品であり、まさにonly oneを誇れるものだ。VPOという猫をのせたマルティノンの才能に頭を垂れつつも、それは若き日のケルテスやシャイーが成し遂げた流星の輝きを思わせる業績に近く、マルティノンとしてボロディンやプロコフィエフの路線に近接したロシア物の一環であって、作曲者がロシア人かどうかは置いて一個の人間が死を迎える間際のメッセージとしての悲愴交響曲の演奏としてはチェリビダッケの作り出した感動とは質が異なるという感想を払拭するのは困難だった(総合点:4)。
上掲盤を聴いた後でVPOが機能的にも優れていることを思い知る。マルティノンの指揮は強いメリハリがあり強弱もテンポも伸縮自在で、VPOが承服してついて行っていることそれ自体が価値ありだ。mov1第2主題の弦の艶っぽさは「ならでは」であり展開部の金管の鳴りっぷりも圧倒的。マルティノンのオケのドライブは圧巻でアクセルの一気の踏み込みも自在である。mov2主題のブレーキはその逆。中間部の息をひそめた p は実にいい、これでこそmov4コーダと繋がるというもの。mov3の弦アンサンブルは素晴らしいの一言だが僕がこの演奏を初聴で気に入らなかったのは2回目のマーチの常套的な減速のせいだった(今でもそうだ)。mov4もテンポは流動的でほぼ一定に収まることなく水性(liquid)であり、それに同化してしまえばいいのだろうが僕のイデアとしての悲愴はそうではなくどうもひっかる。ひとつの管弦楽のプレイとしてはユニークな一級品であり、まさにonly oneを誇れるものだ。VPOという猫をのせたマルティノンの才能に頭を垂れつつも、それは若き日のケルテスやシャイーが成し遂げた流星の輝きを思わせる業績に近く、マルティノンとしてボロディンやプロコフィエフの路線に近接したロシア物の一環であって、作曲者がロシア人かどうかは置いて一個の人間が死を迎える間際のメッセージとしての悲愴交響曲の演奏としてはチェリビダッケの作り出した感動とは質が異なるという感想を払拭するのは困難だった(総合点:4)。
キリル・コンドラシン / モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団
youtubeにて聴く(1967年、東京ライブとのこと)。コンドラシンは聴けなかったがそれを痛恨に思う指揮者の一人だ。この悲愴の各所にみる旋律の熟達のフレージングは名優のセリフのようで、一朝一夕の指示でオーケストラに教え込める質のものと思えない。テンポは絶え間なく変転しているが、こういうものなのだという絶対の説得力を感じ、スケルツォの2度目のマーチの減速はこの演奏でなるほどと初めて思わされた。管弦楽はライブの傷はあるものの、本当にうまい。素晴らしい演奏、そして、なんていい曲なんだろう。これを会場で体験された方は幸せだ。
ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。
Categories:______チャイコフスキー





